この広告は30日以上更新がないブログに表示されております。
新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。
広告
posted by fanblog
2021年01月14日
映画「死刑執行人もまた死す」‐ ナチス副総督ラインハルト・ハイドリヒ暗殺事件を背景にした傑作サスペンス
「死刑執行人もまた死す」
(Hangmen Also Die!)
1943年 アメリカ
監督フリッツ・ラング
原案フリッツ・ラング
ベルトルト・ブレヒト
脚本ジョン・ウェクスリー
撮影ジェームズ・ウォン・ハウ
音楽ハンス・アイスラー
〈キャスト〉
ブライアン・ドンレヴィ ウォルター・ブレナン
アンナ・リー ジーン・ロックハート
ヴェネツィア国際映画祭特別賞
ナチス占領下のプラハで実際に起きたナチス副総督、ラインハルト・ハイドリヒ暗殺事件を背景に、ナチスに抑圧されたチェコの民衆、そして反ナチの活動家たちの暗躍と悲劇を、重厚でリアリティーあふれる中に娯楽性を織り交ぜた傑作。

第二次世界大戦下のヨーロッパ、ナチス・ドイツのベーメン・メーレン保護領(チェコ)で、統治者であるラインハルト・ハイドリヒが何者かに狙撃されます。
ゲシュタポ(国家秘密警察)は犯人捜索を開始。
そんな中、マーシャ・ノヴォトニー(アンナ・リー)は、立ち寄った八百屋の店先で不審な男を目撃しますが、ゲシュタポから男の行方を尋ねられたマーシャは、男の逃げた道とは反対の方角を教えます。
しかし、その男との偶然の出会いが、マーシャとその家族にとっては波乱の要因となるものでした。
夜の8時以降の外出が禁止されているその日、マーシャの家にひとりの男が現れます。
ヴァニヤックと名乗るその男(ブライアン・ドンレヴィ)は、ゲシュタポを欺いて自分を助けてくれたマーシャにお礼を言いに来たのですが、マーシャの父、ステファン・ノヴォトニー教授(ウォルター・ブレナン)とも親しくなる中、その夜は遅くなったので帰宅することのできなくなったヴァニヤックはマーシャの家で一夜を過ごすことになります。
犯人追求のゲシュタポの手は、嘘をつかれたマーシャの身辺に及び、怪しい男ヴァニヤックをかくまっていたマーシャ一家へと疑惑が移り、やがてノヴォトニー教授はゲシュタポに連れ去られ、プラハの市民たちも人質のために連行されることになります。

父が連れ去られ、処刑されることを恐れたマーシャは、ヴァニヤックのために事件に巻き込まれたことを憤り、ヴァニヤックの居所を突き止め、自首をすすめますが、ヴァニヤックに断られたマーシャはゲシュタポ本部へ通報しようとします。
しかし、プラハ市民やレジスタンスは巧妙にそれを察知し、マーシャの通報を阻みます。
一連の騒動を不審に思ったゲシュタポは、犯人が名乗り上げるまで、連行した市民たちを次々と処刑する方策へと非情性を表していきます。
レジスタンス内部でも動揺が広がる中、ヴァニヤックは自分が自首することもなく、市民たちの処刑を止められる一計を考えつきます。
それは、レジスタンスの中に紛れ込んでいるゲシュタポのスパイ、ビール工場の持ち主、チャカ(ジーン・ロックハート)を犯人に仕立て上げることでした。
レジスタンスの仕組んだ罠の中に入り込みそうになったチャカでしたが、彼には絶対ともいえるアリバイが切り札として残っており、それを証明してくれる警察主任クリューバーの存在が鍵となったのですが、そのクリューバーは行方不明となっていて、クリューバーは後に死体となって発見されます。

ヒロイン、マーシャや、その父で教授のステファン・ノヴォトニー、謎めいたヴァニヤックなど、個性的な人物たちが登場する中で、悪賢く立ち回ろうとするチャカの存在が映画に面白いドラマ性を添えています。
ビール工場主で秘密警察とも内通してレジスタンスの分裂を図ろうとするチャカ。
しかしチャカの悪だくみは自分自身へと跳ね返り、レジスタンスの仕掛けた罠にはまり込んで、ハイドリヒ暗殺事件の犯人として射殺されてしまいます。
このチャカの存在はイソップ物語の寓話を連想させて面白いし、自らの保身のために選んだ策略に自らがはまり込む人間的な哀れさが、なんとなく同情を起こさせてしまう滑稽さも含んでいて印象的でした。
製作が戦時中の1943年で、監督のフリッツ・ラングや原案を担当したベルトルト・ブレヒト、音楽のハンス・アイスラーなど、ドイツからの亡命者によって作られているので、映画としてはナチスに対するプロパガンダの要素を持っていることは確かなのですが、にも関わらず、スリリングな展開や巧妙なストーリーなど、一瞬も目を離せない面白さを持った娯楽要素をタップリと含んでいて、映画史に残る傑作といえます。
映画の背景となっているのは、チェコのイギリス亡命政府などが計画した“エンスポライド作戦”と呼ばれるラインハルト・ハイドリヒ暗殺計画で、当時、秘密警察をも束ねた国家保安本部の長官で、ユダヤ人や他の人種問題を扱っていたハイドリヒは、その冷酷さから“金髪の野獣”“絞首刑人”の異名をもって恐れられていた人物。
映画「死刑執行人もまた死す」は、ハイドリヒ暗殺事件そのものを扱うのではなく、ナチスによる抑圧から解放されたいと願うプラハの市民、そして地下に潜って活動を続けるレジスタンスたちの活動を、暗殺事件を背景に力強く描いたものです。

監督は、「メトロポリス」(1927年)、「月世界の女」(1928年)、「M」(1931年)などの巨匠フリッツ・ラング。
原案には、詩や戯曲などで世界的な影響を与えたベルトルト・ブレヒト。
ヒロイン、マーシャに「わが谷は緑なりき」(1941年)、「アパッチ砦」(1948年)、「馬上の二人」(1961年)など、巨匠ジョン・フォードとも縁の深い美人女優アンナ・リー。
マーシャの父親で大学教授のステファンに、「西部の男」(1940年)でアカデミー賞助演男優賞を受賞。その後「ヨーク軍曹」(1941年)、「荒野の決闘」(1946年)などで、善人や悪役など幅広い演技力を持つウォルター・ブレナン。
特に、「リオ・ブラボー」(1959年)では飄々とした味わいを残しました。
事件の犯人ヴァニヤック(フランツ・スヴォボダ医師)に「大平原」(1939年)、「砂塵」(1939年)、「死の接吻」(1947年)のブライアン・ドンレヴィ。
ゲシュタポに内通するビール工場主チャカに、「群衆」(1941年)、「壮烈第七騎兵隊」(1941年)、「三十四丁目の奇蹟」(1947年)のジーン・ロックハート。
アルフレッド・ヒッチコックばりのとても面白いサスペンス映画であるため、映画が製作された1943年という時代を忘れそうになるほどなのですが、ラストに使われた「NOT THE END」(終わりではない)は、現在もまだ続いているナチスの蛮行と、それと戦い、自由をつかもうとする民衆蜂起を訴えるようなラストの余韻は、映画の世界から一気に現実の狂気の時代へと引き戻され、その時代に苦難をなめた人々の悲痛な思いが伝わってきます。

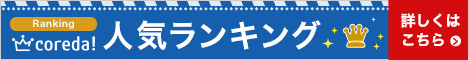

1943年 アメリカ
監督フリッツ・ラング
原案フリッツ・ラング
ベルトルト・ブレヒト
脚本ジョン・ウェクスリー
撮影ジェームズ・ウォン・ハウ
音楽ハンス・アイスラー
〈キャスト〉
ブライアン・ドンレヴィ ウォルター・ブレナン
アンナ・リー ジーン・ロックハート
ヴェネツィア国際映画祭特別賞
ナチス占領下のプラハで実際に起きたナチス副総督、ラインハルト・ハイドリヒ暗殺事件を背景に、ナチスに抑圧されたチェコの民衆、そして反ナチの活動家たちの暗躍と悲劇を、重厚でリアリティーあふれる中に娯楽性を織り交ぜた傑作。

第二次世界大戦下のヨーロッパ、ナチス・ドイツのベーメン・メーレン保護領(チェコ)で、統治者であるラインハルト・ハイドリヒが何者かに狙撃されます。
ゲシュタポ(国家秘密警察)は犯人捜索を開始。
そんな中、マーシャ・ノヴォトニー(アンナ・リー)は、立ち寄った八百屋の店先で不審な男を目撃しますが、ゲシュタポから男の行方を尋ねられたマーシャは、男の逃げた道とは反対の方角を教えます。
しかし、その男との偶然の出会いが、マーシャとその家族にとっては波乱の要因となるものでした。
夜の8時以降の外出が禁止されているその日、マーシャの家にひとりの男が現れます。
ヴァニヤックと名乗るその男(ブライアン・ドンレヴィ)は、ゲシュタポを欺いて自分を助けてくれたマーシャにお礼を言いに来たのですが、マーシャの父、ステファン・ノヴォトニー教授(ウォルター・ブレナン)とも親しくなる中、その夜は遅くなったので帰宅することのできなくなったヴァニヤックはマーシャの家で一夜を過ごすことになります。
犯人追求のゲシュタポの手は、嘘をつかれたマーシャの身辺に及び、怪しい男ヴァニヤックをかくまっていたマーシャ一家へと疑惑が移り、やがてノヴォトニー教授はゲシュタポに連れ去られ、プラハの市民たちも人質のために連行されることになります。

父が連れ去られ、処刑されることを恐れたマーシャは、ヴァニヤックのために事件に巻き込まれたことを憤り、ヴァニヤックの居所を突き止め、自首をすすめますが、ヴァニヤックに断られたマーシャはゲシュタポ本部へ通報しようとします。
しかし、プラハ市民やレジスタンスは巧妙にそれを察知し、マーシャの通報を阻みます。
一連の騒動を不審に思ったゲシュタポは、犯人が名乗り上げるまで、連行した市民たちを次々と処刑する方策へと非情性を表していきます。
レジスタンス内部でも動揺が広がる中、ヴァニヤックは自分が自首することもなく、市民たちの処刑を止められる一計を考えつきます。
それは、レジスタンスの中に紛れ込んでいるゲシュタポのスパイ、ビール工場の持ち主、チャカ(ジーン・ロックハート)を犯人に仕立て上げることでした。
レジスタンスの仕組んだ罠の中に入り込みそうになったチャカでしたが、彼には絶対ともいえるアリバイが切り札として残っており、それを証明してくれる警察主任クリューバーの存在が鍵となったのですが、そのクリューバーは行方不明となっていて、クリューバーは後に死体となって発見されます。
ヒロイン、マーシャや、その父で教授のステファン・ノヴォトニー、謎めいたヴァニヤックなど、個性的な人物たちが登場する中で、悪賢く立ち回ろうとするチャカの存在が映画に面白いドラマ性を添えています。
ビール工場主で秘密警察とも内通してレジスタンスの分裂を図ろうとするチャカ。
しかしチャカの悪だくみは自分自身へと跳ね返り、レジスタンスの仕掛けた罠にはまり込んで、ハイドリヒ暗殺事件の犯人として射殺されてしまいます。
このチャカの存在はイソップ物語の寓話を連想させて面白いし、自らの保身のために選んだ策略に自らがはまり込む人間的な哀れさが、なんとなく同情を起こさせてしまう滑稽さも含んでいて印象的でした。
製作が戦時中の1943年で、監督のフリッツ・ラングや原案を担当したベルトルト・ブレヒト、音楽のハンス・アイスラーなど、ドイツからの亡命者によって作られているので、映画としてはナチスに対するプロパガンダの要素を持っていることは確かなのですが、にも関わらず、スリリングな展開や巧妙なストーリーなど、一瞬も目を離せない面白さを持った娯楽要素をタップリと含んでいて、映画史に残る傑作といえます。
映画の背景となっているのは、チェコのイギリス亡命政府などが計画した“エンスポライド作戦”と呼ばれるラインハルト・ハイドリヒ暗殺計画で、当時、秘密警察をも束ねた国家保安本部の長官で、ユダヤ人や他の人種問題を扱っていたハイドリヒは、その冷酷さから“金髪の野獣”“絞首刑人”の異名をもって恐れられていた人物。
映画「死刑執行人もまた死す」は、ハイドリヒ暗殺事件そのものを扱うのではなく、ナチスによる抑圧から解放されたいと願うプラハの市民、そして地下に潜って活動を続けるレジスタンスたちの活動を、暗殺事件を背景に力強く描いたものです。

監督は、「メトロポリス」(1927年)、「月世界の女」(1928年)、「M」(1931年)などの巨匠フリッツ・ラング。
原案には、詩や戯曲などで世界的な影響を与えたベルトルト・ブレヒト。
ヒロイン、マーシャに「わが谷は緑なりき」(1941年)、「アパッチ砦」(1948年)、「馬上の二人」(1961年)など、巨匠ジョン・フォードとも縁の深い美人女優アンナ・リー。
マーシャの父親で大学教授のステファンに、「西部の男」(1940年)でアカデミー賞助演男優賞を受賞。その後「ヨーク軍曹」(1941年)、「荒野の決闘」(1946年)などで、善人や悪役など幅広い演技力を持つウォルター・ブレナン。
特に、「リオ・ブラボー」(1959年)では飄々とした味わいを残しました。
事件の犯人ヴァニヤック(フランツ・スヴォボダ医師)に「大平原」(1939年)、「砂塵」(1939年)、「死の接吻」(1947年)のブライアン・ドンレヴィ。
ゲシュタポに内通するビール工場主チャカに、「群衆」(1941年)、「壮烈第七騎兵隊」(1941年)、「三十四丁目の奇蹟」(1947年)のジーン・ロックハート。
アルフレッド・ヒッチコックばりのとても面白いサスペンス映画であるため、映画が製作された1943年という時代を忘れそうになるほどなのですが、ラストに使われた「NOT THE END」(終わりではない)は、現在もまだ続いているナチスの蛮行と、それと戦い、自由をつかもうとする民衆蜂起を訴えるようなラストの余韻は、映画の世界から一気に現実の狂気の時代へと引き戻され、その時代に苦難をなめた人々の悲痛な思いが伝わってきます。

2021年01月07日
映画「ブレイブ ワン」‐ ニューヨークの夜に浮かび上がるもう一人の自分, そして衝撃のラストへ
「ブレイブ ワン」
(The Brave One ) 2007年
アメリカ / オーストラリア
監督ニール・ジョーダン
脚本ロドリック・テイラー
ブルース・A・テイラー
シンシア・モート
音楽ダリオ・マリアネッリ
撮影フィリップ・ルースロ
〈キャスト〉
ジョディ・フォスター テレンス・ハワード
メアリー・スティーンバージェン
結論から言ってしまえば、女性版「狼よさらば」。
1972年にマイケル・ウィナー監督、チャールズ・ブロンソン主演で作られた「狼よさらば」は、街のチンピラグループに妻を殺され、娘をレイプされた男が、かつてアメリカに根付いていた自警の精神に目覚め、銃を手に入れて犯罪者を処刑(射殺)していくという話でした。
あきらかに「狼よさらば」を下敷きにしたと思われる「ブレイブ ワン」なのですが、違うところは、主人公が男性ではなく若い女性(多少無理はありますが)であるということと、「狼よさらば」が妻子を凌辱した犯人に対する復讐劇ではなく、社会の悪そのものに目を向けられていたのに対し、「ブレイブ ワン」では犯人への復讐に主眼が置かれていること。

エリカ・ベイン(ジョディ・フォスター)はニューヨークでラジオパーソナリティーを務め、恋人デイビッド(ナヴィーン・アンドリュース)との結婚を目前に控えて幸せな日々を送っています。
そんな二人は夜、デイビッドの愛犬を連れて散歩の途中、三人の暴漢にからまれ、袋叩きにされてデイビッドは死亡、エリカは一命をとりとめますが、事件の衝撃から立ち直ることができず、心に傷を負ったまま外出もできない状態が続きます。
警察は事件の捜査をつづけますが、警察署の対応に嫌気がさしたエリカは護身のための銃を買おうと銃器店に入りますが、ライセンス取得のために日数を要すると言われ、銃の購入をあきらめかけた直後、アジア系の男に声をかけられ、闇でオートマチックの拳銃を手に入れます。

ある夜、買い物のために立ち寄ったコンビニエンスストアでエリカは強盗事件に遭遇。店主の女性を射殺した犯人に追い詰められながらも、エリカは強盗を射殺してしまいます。
コンビニ事件を担当したショーン・マーサー刑事(テレンス・ハワード)とも親しくなる中、エリカの中でもう一人の自分が目覚め、地下鉄の暴漢を平然と射殺する、歯止めのきかない自分に気づきます。
事件を捜査するマーサー刑事は、犯人が男性ではなく女性であることに気づき、親しくなったエリカの言動に不審を抱くようになります。
やがて、エリカを襲った暴漢グループの所在が明るみに出始め、破滅を覚悟したエリカはマーサーに別れのメッセージを残し、ひとり、復讐の死地へと向かいます。
「狼よさらば」でもそうでしたが、法の裁きを経ずに犯罪者を処刑してゆく人間に対して、世論からは賛否両論の声が上がります。そして、それはそのまま、映画を見ている私たち観客に対してへの問いかけでもあります。エリカ・ベインのやっていることは正しいのか?
私たちは無法地帯に暮らしているわけではなく、法治国家に住んでいる以上、どんな犯罪者であろうとも法の裁きを経て審判が下されなければいけない。
だから、エリカは間違っている。
しかし、そう単純に決められないところに人間社会の、モヤモヤとした複雑さがあります。

「ブレイブ ワン」でエリカ・ベインの犯す殺人の設定には同じパターンはなくて、コンビニ強盗であったり、地下鉄の暴漢であったり、セックスにからんだ娼婦への暴行、さらに、マーサー刑事たちが追いかけながらも捕まえることできなかった犯罪組織の極悪なボスなどが登場しますが、これは社会悪の暴力の象徴として考えることができます。
それらを抹殺する中でエリカは煩悶します。殺さなくても、銃で脅すだけでよかったのではないか。
しかしまた、人間には自分で気づかないもう一人の自分がいることに気づくことがあります。
「アラビアのロレンス」(1962年)の中で、重傷を負って、とても助かる見込みがないと分かったロレンスの従者の少年を、楽にしてあげようとロレンスが銃で撃ち殺してしまう場面があります。
しかしロレンスは一発で仕留めるのではなく、二発三発と少年の体に銃弾を撃ち込みます。
そのときの邪悪な自分を振り返ってロレンスはこう言います。
「私は彼を殺すことを楽しんでいた」
「ブレイブ ワン」のラストでは、エリカの復讐が遂げられようとしている場面を私たちは目撃するのですが、そこへ現れたマーサー刑事の視点に立って、自分ならどうするだろうという問いかけが突きつけられます。
エリカの殺人をやめさせ、法に従うようエリカを説得するのか、それとも…。
マーサー刑事は「合法的な銃を使え」とエリカに自分の銃を渡し、復讐を遂げさせます。
このラストを、間違っている、と感じるのが正常な感覚であるかとも思います。法の番人たる警察官が殺人に手を貸したのですから。
「目には目を 歯には歯を」は、やられたらやり返せという意味ではありませんが、人の命を奪った者に対しては、その人の命で償うのが本当だと思いますから(明確に犯人が特定された場合に限ります)、映画としての、このラストはいささか衝撃的でしたが、個人的には納得してしまいました。

監督は、「クライング・ゲーム」(1992年)、「インタビュー・ウィズ・ヴァンパイア」(1994年)のニール・ジョーダン。
ヒロイン、エリカ・ベインに、「ダウンタウン物語」、「タクシードライバー」(1976年)で天才子役と騒がれながらも映画界を離れ、後に「告発の行方」(1988年)、「羊たちの沈黙」(1991年)で二度オスカーを受賞したジョディ・フォスター。
エリカの心のよりどころとなるマーサー刑事に、「クラッシュ」、「Ray/レイ」(2004年)などのテレンス・ハワード。
ラジオ局のディレクター、キャロルに「バック・トゥ・ザ・フューチャーPART3」(1990年)、「ギルバート・ブレイク」(1993年)、「ニクソン」(1995年)などの実力派で、1980年の「メルビンとハワード」ではアカデミー賞、ゴールデングローブ賞の助演女優賞を受賞しているメアリー・スティーンバージェン。
暴力という社会的で普遍的なテーマとエンターテインメントをうまく一つにまとめ上げた見応えのある映画。
ただ、欲を言えば、ジョディ・フォスターもいいのですが、さすがに40代半ばに達していて、これから結婚しようという女性を演じるにはちょっと無理があったかなあ。
一度結婚に失敗して、新たな幸せをつかめると思った矢先に暴力事件に巻き込まれるとか、そんなほうが良かったような気もしました。
「羊たちの沈黙」のころだと良かったのですがね。



アメリカ / オーストラリア
監督ニール・ジョーダン
脚本ロドリック・テイラー
ブルース・A・テイラー
シンシア・モート
音楽ダリオ・マリアネッリ
撮影フィリップ・ルースロ
〈キャスト〉
ジョディ・フォスター テレンス・ハワード
メアリー・スティーンバージェン
結論から言ってしまえば、女性版「狼よさらば」。
1972年にマイケル・ウィナー監督、チャールズ・ブロンソン主演で作られた「狼よさらば」は、街のチンピラグループに妻を殺され、娘をレイプされた男が、かつてアメリカに根付いていた自警の精神に目覚め、銃を手に入れて犯罪者を処刑(射殺)していくという話でした。
あきらかに「狼よさらば」を下敷きにしたと思われる「ブレイブ ワン」なのですが、違うところは、主人公が男性ではなく若い女性(多少無理はありますが)であるということと、「狼よさらば」が妻子を凌辱した犯人に対する復讐劇ではなく、社会の悪そのものに目を向けられていたのに対し、「ブレイブ ワン」では犯人への復讐に主眼が置かれていること。

エリカ・ベイン(ジョディ・フォスター)はニューヨークでラジオパーソナリティーを務め、恋人デイビッド(ナヴィーン・アンドリュース)との結婚を目前に控えて幸せな日々を送っています。
そんな二人は夜、デイビッドの愛犬を連れて散歩の途中、三人の暴漢にからまれ、袋叩きにされてデイビッドは死亡、エリカは一命をとりとめますが、事件の衝撃から立ち直ることができず、心に傷を負ったまま外出もできない状態が続きます。
警察は事件の捜査をつづけますが、警察署の対応に嫌気がさしたエリカは護身のための銃を買おうと銃器店に入りますが、ライセンス取得のために日数を要すると言われ、銃の購入をあきらめかけた直後、アジア系の男に声をかけられ、闇でオートマチックの拳銃を手に入れます。

ある夜、買い物のために立ち寄ったコンビニエンスストアでエリカは強盗事件に遭遇。店主の女性を射殺した犯人に追い詰められながらも、エリカは強盗を射殺してしまいます。
コンビニ事件を担当したショーン・マーサー刑事(テレンス・ハワード)とも親しくなる中、エリカの中でもう一人の自分が目覚め、地下鉄の暴漢を平然と射殺する、歯止めのきかない自分に気づきます。
事件を捜査するマーサー刑事は、犯人が男性ではなく女性であることに気づき、親しくなったエリカの言動に不審を抱くようになります。
やがて、エリカを襲った暴漢グループの所在が明るみに出始め、破滅を覚悟したエリカはマーサーに別れのメッセージを残し、ひとり、復讐の死地へと向かいます。
「狼よさらば」でもそうでしたが、法の裁きを経ずに犯罪者を処刑してゆく人間に対して、世論からは賛否両論の声が上がります。そして、それはそのまま、映画を見ている私たち観客に対してへの問いかけでもあります。エリカ・ベインのやっていることは正しいのか?
私たちは無法地帯に暮らしているわけではなく、法治国家に住んでいる以上、どんな犯罪者であろうとも法の裁きを経て審判が下されなければいけない。
だから、エリカは間違っている。
しかし、そう単純に決められないところに人間社会の、モヤモヤとした複雑さがあります。
「ブレイブ ワン」でエリカ・ベインの犯す殺人の設定には同じパターンはなくて、コンビニ強盗であったり、地下鉄の暴漢であったり、セックスにからんだ娼婦への暴行、さらに、マーサー刑事たちが追いかけながらも捕まえることできなかった犯罪組織の極悪なボスなどが登場しますが、これは社会悪の暴力の象徴として考えることができます。
それらを抹殺する中でエリカは煩悶します。殺さなくても、銃で脅すだけでよかったのではないか。
しかしまた、人間には自分で気づかないもう一人の自分がいることに気づくことがあります。
「アラビアのロレンス」(1962年)の中で、重傷を負って、とても助かる見込みがないと分かったロレンスの従者の少年を、楽にしてあげようとロレンスが銃で撃ち殺してしまう場面があります。
しかしロレンスは一発で仕留めるのではなく、二発三発と少年の体に銃弾を撃ち込みます。
そのときの邪悪な自分を振り返ってロレンスはこう言います。
「私は彼を殺すことを楽しんでいた」
「ブレイブ ワン」のラストでは、エリカの復讐が遂げられようとしている場面を私たちは目撃するのですが、そこへ現れたマーサー刑事の視点に立って、自分ならどうするだろうという問いかけが突きつけられます。
エリカの殺人をやめさせ、法に従うようエリカを説得するのか、それとも…。
マーサー刑事は「合法的な銃を使え」とエリカに自分の銃を渡し、復讐を遂げさせます。
このラストを、間違っている、と感じるのが正常な感覚であるかとも思います。法の番人たる警察官が殺人に手を貸したのですから。
「目には目を 歯には歯を」は、やられたらやり返せという意味ではありませんが、人の命を奪った者に対しては、その人の命で償うのが本当だと思いますから(明確に犯人が特定された場合に限ります)、映画としての、このラストはいささか衝撃的でしたが、個人的には納得してしまいました。

監督は、「クライング・ゲーム」(1992年)、「インタビュー・ウィズ・ヴァンパイア」(1994年)のニール・ジョーダン。
ヒロイン、エリカ・ベインに、「ダウンタウン物語」、「タクシードライバー」(1976年)で天才子役と騒がれながらも映画界を離れ、後に「告発の行方」(1988年)、「羊たちの沈黙」(1991年)で二度オスカーを受賞したジョディ・フォスター。
エリカの心のよりどころとなるマーサー刑事に、「クラッシュ」、「Ray/レイ」(2004年)などのテレンス・ハワード。
ラジオ局のディレクター、キャロルに「バック・トゥ・ザ・フューチャーPART3」(1990年)、「ギルバート・ブレイク」(1993年)、「ニクソン」(1995年)などの実力派で、1980年の「メルビンとハワード」ではアカデミー賞、ゴールデングローブ賞の助演女優賞を受賞しているメアリー・スティーンバージェン。
暴力という社会的で普遍的なテーマとエンターテインメントをうまく一つにまとめ上げた見応えのある映画。
ただ、欲を言えば、ジョディ・フォスターもいいのですが、さすがに40代半ばに達していて、これから結婚しようという女性を演じるにはちょっと無理があったかなあ。
一度結婚に失敗して、新たな幸せをつかめると思った矢先に暴力事件に巻き込まれるとか、そんなほうが良かったような気もしました。
「羊たちの沈黙」のころだと良かったのですがね。

2021年01月05日
映画「忠臣蔵」- オールスターキャストで挑む熱演の“忠臣蔵”
「忠臣蔵」
昭和33年(1958年) 大映
監督 渡辺邦男
脚本 渡辺邦男
民門敏雄
松村正温
八尋不二
撮影 渡辺孝
音楽 斎藤一郎
〈キャスト〉
長谷川一夫 滝沢修 市川雷蔵 山本富士子
鶴田浩二 京マチ子 淡島千景 若尾文子
日本人に最も親しまれ、現在でも語り継がれる「忠臣蔵」。
大映創立18年の記念として(18年は中途半端な気もしますが)、オールスターを配して挑んだ大作。
時は元禄、五代将軍徳川綱吉の時代。
江戸からの急使が早駕籠で播州(播磨国・現兵庫県南西部)赤穂へと向かって駆けつけます。
急使の報を受けた赤穂城筆頭家老の大石内蔵助(長谷川一夫)以下の赤穂城家臣たちは、城主浅野内匠頭(あさのたくみのかみ)(市川雷蔵)の江戸城における刃傷(にんじょう)事件を知らされ、その後届く内匠頭切腹の顛末(てんまつ)などを知らされることになります。

正式な審議は行われず、喧嘩両成敗が本当であるはずなのに、相手の吉良上野介(滝沢修)には咎めはなく、一方の内匠頭だけが罪人のように腹を切らされたことへの幕府に対する怒りと抗議から、城に籠って討ち死にをしようと言う者、いや、短慮は謹んで裁きに従おうと言う者、二派に分かれて評議が続きますが、最後は家老大石内蔵助の判断を仰ぐことになります。
大石の策として、内匠頭の弟である浅野大学を立てて城主とし、まずはお家再興を幕府に願い出ようとするものでした。
城明け渡しも整い、お家再興の嘆願書も幕府に届きましたが、当時の権力を握っていたのは綱吉の信頼の厚い老中柳沢出羽守吉保(清水将夫)。
上野介の実子、綱憲(船越英二)は上杉家の養子でもあり、出羽守という職掌柄、上杉家とつながりのある柳沢吉保は吉良家の養護にまわり、赤穂事件の処理にあたっていた脇坂淡路守(菅原謙二)から受け取った大石による浅野家再興の嘆願をはねつけてしまいます。
城を明け渡すということは、その日から家臣たちは職を失い、家族共々露頭に迷うことを意味します。
浅野家再興がかなわないと知った大石は、幕府を相手に討ち死にをしようと言う者だけを集めて、かねてから腹案のあった吉良上野介仇討ちへと舵を切ってゆきます。

よく知られた赤穂浪士四十七士による吉良上野介仇討ち物語なのですが、少し分かりにくいのが、事件の発端となった浅野内匠頭と吉良上野介の関係から起こった江戸城松の廊下における一連の流れ。
事件は、元禄14年3月14日(現代の暦でいえば1701年4月21日)、巳の下刻(午前11時40分ごろ)、江戸城本丸大廊下において、吉良上野介義央(よしなか)と留守居番・梶川頼照が儀式の打ち合わせをしているところへ、浅野内匠頭が「この間の遺恨覚えたか!」と叫び、脇差で吉良に切りつけたというもの。
事件をさかのぼること約一カ月前の2月17日、京都の東山天皇から勅使が派遣され、江戸へ向かいます。
柳原資廉、高野保春をはじめとする勅使の一行は3月11日に江戸・品川の伝奏屋敷に到着。
その翌日、3月12日に勅使の江戸城登城。白書院において将軍・徳川綱吉に下賜の儀式が執り行われます。
その京都朝廷の勅使の饗応役、つまり接待役にあたったのが浅野内匠頭で、勅使に対する礼儀・作法を指南していたのが高家(幕府の儀式・典礼を司る役職)の名門吉良家。
ところが、吉良義央は浅野内匠頭に対して何かと嫌がらせをしたり、田舎侍とバカにした態度を示したりと、浅野の饗応役としての役職を貶(おとし)めるような振る舞いに及んだため、とうとう堪忍袋の緒が切れて…。
時間をかけた審議が行われなかったので、浅野内匠頭がどのような遺恨で刃傷に及んだのかは実際にはハッキリとしないのですが、映画にも出てきたように、吉良に対する賄賂の少なさなどが尾を引いて、浅野への嫌がらせ等につながり、それが吉良への悪感情になって暴発したのではないかと考えられますが、実際的な問題としては、なぜ一方的に浅野内匠頭だけが罪人のように屋敷の庭先で腹を切らされたのか。

“生類憐みの令”のような悪政と非難された法を作った五代将軍綱吉は、また一方で尊皇心の篤いことでも知られ、そのため、勅使一行への饗応には細大の気を使い、勅使から下された聖旨・院旨に対する勅答の儀は、幕府の行事の中でも最も格式の高いものとされていました。
その奏答の儀が行われたのが、元禄14年3月14日。
綱吉としては、こともあろうに最も重要な日に刃傷事件を引き起こした浅野内匠頭に対する怒りは生易しいものではなかったのでしょう。一方の吉良家は名門であり、浅野家は五万三千石の大名。
由比正雪の乱(慶安の変)や“伊達騒動”に見られるように、江戸幕府による大名取り潰し政策は幕府初期から行われていたことから、“刃傷事件”は浅野家取り潰しの格好の口実となったのかも分かりません。
それはともかくとして、綱吉の怒りは内匠頭に向けられ、即日切腹、というのはいかにも片手落ち。
まして“仇討ち”は江戸時代にあっては美徳以上の絶対的な義務。幕府の失政に対する反省を促す意味と、主人浅野内匠頭を死に至らしめた相手、吉良上野介を打ち取るため、旧浅野家家臣団は窮乏と貧苦の中で結束を固めてゆくことになります。

現在では考えられないような豪華絢爛たる配役の映画「忠臣蔵」。
大石内蔵助に今や伝説的なスター長谷川一夫。
浅野内匠頭には、歌舞伎から転じ、後に「眠狂四郎」シリーズが当たり役となった二枚目の市川雷蔵。
内匠頭の妻・瑤泉院(ようぜんいん)に第一回ミス日本にも選ばれた美人女優山本富士子。
憎まれ役、吉良上野介に名優滝沢修。
そして、「座頭市」シリーズで人気を博すことになる若き日の勝新太郎、鶴田浩二、京マチ子、若尾文子、淡島千景、木暮実千代、二代目中村鴈治郎、さらに、清水将夫、小沢栄太郎、内蔵助の息子大石主税(ちから)に川口浩など、そうそうたる顔ぶれの中で、個人的に注目したのが大高源吾を演じた品川隆二さん。
テレビシリーズ「素浪人 月影兵庫」や、その続編のような「素浪人 花山大吉」で近衛十四郎との名コンビの相手役、焼津の半次のコミカルでけたたましい三枚目の強い印象があって、品川隆二といえば焼津の半次のイメージがあったから、大高源吾のような二枚目は意外でしたが、考えてみれば、テレビ時代劇「忍びの者」ではかなりシリアスな主人公・石川五右衛門を演じていましたから、やはり正統派の俳優なんですね。
見応えのある映画「忠臣蔵」なんですが、このころの時代劇の特徴として、歌舞伎からの影響が抜けきっていなくて、市川雷蔵のメークアップなどは歌舞伎の隈取りを連想させますし、殺陣(たて)などもヒラリヒラリと体をかわして刀をよける、芝居小屋の引き写しでリアリティーに乏しい(さすがに後半の討ち入りのシーンは違っていますが)。
そんな欠点を物ともせずに魅せるのが、火花を散らすような俳優たちの演技。
内匠頭に寄り添い、切腹の場面では庭先で嗚咽をもらす片岡源五右衛門(香川良介)。
遊郭で遊び呆ける大石に迫り、「腰抜け!」と罵り、切りつける浪人・関根弥次郎(高松英郎)。
吉良上野介の身辺を守り、吉良邸で討ち死にをする腕利きの武士清水一角(田崎潤)。
大工・政五郎(見明凡太朗)、娘婿の勝田新左衛門の不甲斐なさを嘆く大竹重兵衛(志村喬)、大石の東下りに立ちふさがる垣見五郎兵衛(二代目中村鴈治郎)など、その配役とそれぞれの持ち場での熱のこもった演技は見もの。
特にラスト、仇討ちが成って引き上げる大石たち一行を拝むようにぬかずく白装束の遥泉院(山本富士子)の姿は、何度見ても感動を覚えます。
増上寺の畳替えや、山科の別れ、赤穂城明け渡しか討ち死にかで評議が続く場面など、様々なエピソードを織り交ぜて構成された「忠臣蔵」は、上映時間3時間にも満たない映画では中途半端になってしまうのは致し方のないところですが(1982年のNHKの大河ドラマ「峠の群像」では、そのあたりはけっこう詳しく描かれていたように思いました)、映画「忠臣蔵」は、艱難辛苦に耐えて本望を遂げる、浪花節的醍醐味をタップリと楽しめる映画です。



監督 渡辺邦男
脚本 渡辺邦男
民門敏雄
松村正温
八尋不二
撮影 渡辺孝
音楽 斎藤一郎
〈キャスト〉
長谷川一夫 滝沢修 市川雷蔵 山本富士子
鶴田浩二 京マチ子 淡島千景 若尾文子
日本人に最も親しまれ、現在でも語り継がれる「忠臣蔵」。
大映創立18年の記念として(18年は中途半端な気もしますが)、オールスターを配して挑んだ大作。
時は元禄、五代将軍徳川綱吉の時代。
江戸からの急使が早駕籠で播州(播磨国・現兵庫県南西部)赤穂へと向かって駆けつけます。
急使の報を受けた赤穂城筆頭家老の大石内蔵助(長谷川一夫)以下の赤穂城家臣たちは、城主浅野内匠頭(あさのたくみのかみ)(市川雷蔵)の江戸城における刃傷(にんじょう)事件を知らされ、その後届く内匠頭切腹の顛末(てんまつ)などを知らされることになります。

正式な審議は行われず、喧嘩両成敗が本当であるはずなのに、相手の吉良上野介(滝沢修)には咎めはなく、一方の内匠頭だけが罪人のように腹を切らされたことへの幕府に対する怒りと抗議から、城に籠って討ち死にをしようと言う者、いや、短慮は謹んで裁きに従おうと言う者、二派に分かれて評議が続きますが、最後は家老大石内蔵助の判断を仰ぐことになります。
大石の策として、内匠頭の弟である浅野大学を立てて城主とし、まずはお家再興を幕府に願い出ようとするものでした。
城明け渡しも整い、お家再興の嘆願書も幕府に届きましたが、当時の権力を握っていたのは綱吉の信頼の厚い老中柳沢出羽守吉保(清水将夫)。
上野介の実子、綱憲(船越英二)は上杉家の養子でもあり、出羽守という職掌柄、上杉家とつながりのある柳沢吉保は吉良家の養護にまわり、赤穂事件の処理にあたっていた脇坂淡路守(菅原謙二)から受け取った大石による浅野家再興の嘆願をはねつけてしまいます。
城を明け渡すということは、その日から家臣たちは職を失い、家族共々露頭に迷うことを意味します。
浅野家再興がかなわないと知った大石は、幕府を相手に討ち死にをしようと言う者だけを集めて、かねてから腹案のあった吉良上野介仇討ちへと舵を切ってゆきます。
よく知られた赤穂浪士四十七士による吉良上野介仇討ち物語なのですが、少し分かりにくいのが、事件の発端となった浅野内匠頭と吉良上野介の関係から起こった江戸城松の廊下における一連の流れ。
事件は、元禄14年3月14日(現代の暦でいえば1701年4月21日)、巳の下刻(午前11時40分ごろ)、江戸城本丸大廊下において、吉良上野介義央(よしなか)と留守居番・梶川頼照が儀式の打ち合わせをしているところへ、浅野内匠頭が「この間の遺恨覚えたか!」と叫び、脇差で吉良に切りつけたというもの。
事件をさかのぼること約一カ月前の2月17日、京都の東山天皇から勅使が派遣され、江戸へ向かいます。
柳原資廉、高野保春をはじめとする勅使の一行は3月11日に江戸・品川の伝奏屋敷に到着。
その翌日、3月12日に勅使の江戸城登城。白書院において将軍・徳川綱吉に下賜の儀式が執り行われます。
その京都朝廷の勅使の饗応役、つまり接待役にあたったのが浅野内匠頭で、勅使に対する礼儀・作法を指南していたのが高家(幕府の儀式・典礼を司る役職)の名門吉良家。
ところが、吉良義央は浅野内匠頭に対して何かと嫌がらせをしたり、田舎侍とバカにした態度を示したりと、浅野の饗応役としての役職を貶(おとし)めるような振る舞いに及んだため、とうとう堪忍袋の緒が切れて…。
時間をかけた審議が行われなかったので、浅野内匠頭がどのような遺恨で刃傷に及んだのかは実際にはハッキリとしないのですが、映画にも出てきたように、吉良に対する賄賂の少なさなどが尾を引いて、浅野への嫌がらせ等につながり、それが吉良への悪感情になって暴発したのではないかと考えられますが、実際的な問題としては、なぜ一方的に浅野内匠頭だけが罪人のように屋敷の庭先で腹を切らされたのか。

“生類憐みの令”のような悪政と非難された法を作った五代将軍綱吉は、また一方で尊皇心の篤いことでも知られ、そのため、勅使一行への饗応には細大の気を使い、勅使から下された聖旨・院旨に対する勅答の儀は、幕府の行事の中でも最も格式の高いものとされていました。
その奏答の儀が行われたのが、元禄14年3月14日。
綱吉としては、こともあろうに最も重要な日に刃傷事件を引き起こした浅野内匠頭に対する怒りは生易しいものではなかったのでしょう。一方の吉良家は名門であり、浅野家は五万三千石の大名。
由比正雪の乱(慶安の変)や“伊達騒動”に見られるように、江戸幕府による大名取り潰し政策は幕府初期から行われていたことから、“刃傷事件”は浅野家取り潰しの格好の口実となったのかも分かりません。
それはともかくとして、綱吉の怒りは内匠頭に向けられ、即日切腹、というのはいかにも片手落ち。
まして“仇討ち”は江戸時代にあっては美徳以上の絶対的な義務。幕府の失政に対する反省を促す意味と、主人浅野内匠頭を死に至らしめた相手、吉良上野介を打ち取るため、旧浅野家家臣団は窮乏と貧苦の中で結束を固めてゆくことになります。

現在では考えられないような豪華絢爛たる配役の映画「忠臣蔵」。
大石内蔵助に今や伝説的なスター長谷川一夫。
浅野内匠頭には、歌舞伎から転じ、後に「眠狂四郎」シリーズが当たり役となった二枚目の市川雷蔵。
内匠頭の妻・瑤泉院(ようぜんいん)に第一回ミス日本にも選ばれた美人女優山本富士子。
憎まれ役、吉良上野介に名優滝沢修。
そして、「座頭市」シリーズで人気を博すことになる若き日の勝新太郎、鶴田浩二、京マチ子、若尾文子、淡島千景、木暮実千代、二代目中村鴈治郎、さらに、清水将夫、小沢栄太郎、内蔵助の息子大石主税(ちから)に川口浩など、そうそうたる顔ぶれの中で、個人的に注目したのが大高源吾を演じた品川隆二さん。
テレビシリーズ「素浪人 月影兵庫」や、その続編のような「素浪人 花山大吉」で近衛十四郎との名コンビの相手役、焼津の半次のコミカルでけたたましい三枚目の強い印象があって、品川隆二といえば焼津の半次のイメージがあったから、大高源吾のような二枚目は意外でしたが、考えてみれば、テレビ時代劇「忍びの者」ではかなりシリアスな主人公・石川五右衛門を演じていましたから、やはり正統派の俳優なんですね。
見応えのある映画「忠臣蔵」なんですが、このころの時代劇の特徴として、歌舞伎からの影響が抜けきっていなくて、市川雷蔵のメークアップなどは歌舞伎の隈取りを連想させますし、殺陣(たて)などもヒラリヒラリと体をかわして刀をよける、芝居小屋の引き写しでリアリティーに乏しい(さすがに後半の討ち入りのシーンは違っていますが)。
そんな欠点を物ともせずに魅せるのが、火花を散らすような俳優たちの演技。
内匠頭に寄り添い、切腹の場面では庭先で嗚咽をもらす片岡源五右衛門(香川良介)。
遊郭で遊び呆ける大石に迫り、「腰抜け!」と罵り、切りつける浪人・関根弥次郎(高松英郎)。
吉良上野介の身辺を守り、吉良邸で討ち死にをする腕利きの武士清水一角(田崎潤)。
大工・政五郎(見明凡太朗)、娘婿の勝田新左衛門の不甲斐なさを嘆く大竹重兵衛(志村喬)、大石の東下りに立ちふさがる垣見五郎兵衛(二代目中村鴈治郎)など、その配役とそれぞれの持ち場での熱のこもった演技は見もの。
特にラスト、仇討ちが成って引き上げる大石たち一行を拝むようにぬかずく白装束の遥泉院(山本富士子)の姿は、何度見ても感動を覚えます。
増上寺の畳替えや、山科の別れ、赤穂城明け渡しか討ち死にかで評議が続く場面など、様々なエピソードを織り交ぜて構成された「忠臣蔵」は、上映時間3時間にも満たない映画では中途半端になってしまうのは致し方のないところですが(1982年のNHKの大河ドラマ「峠の群像」では、そのあたりはけっこう詳しく描かれていたように思いました)、映画「忠臣蔵」は、艱難辛苦に耐えて本望を遂げる、浪花節的醍醐味をタップリと楽しめる映画です。









