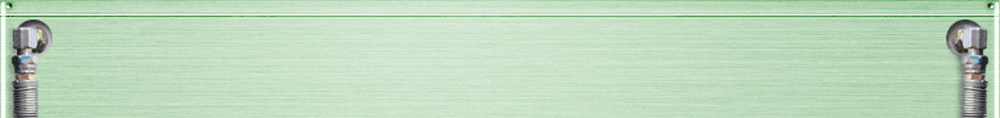全て
| カテゴリ未分類
| プレスリリース
| ドライアイ
| 文献発表
| 厚生労働省通知
| 妄想
| 新聞報道
| お勉強
| 前立腺がん
| 医療費
| 原発
| 制がん剤
| 政治
| 自閉症
| 子宮頸がんワクチン
| 哲学
| 宣伝
| 憲法
| 医療用医薬品
テーマ: 気になったニュース(30373)
カテゴリ: 妄想
2月9日に 免疫チェックポイント阻害薬は大腸炎を引き起こす
というブログを書きました。
化学療法剤では副作用の機序が制癌作用と分離できる場合には、化学療法剤の中止のデメリットを小さくできるために副作用防止剤を使います。この薬剤は保険適応されています;
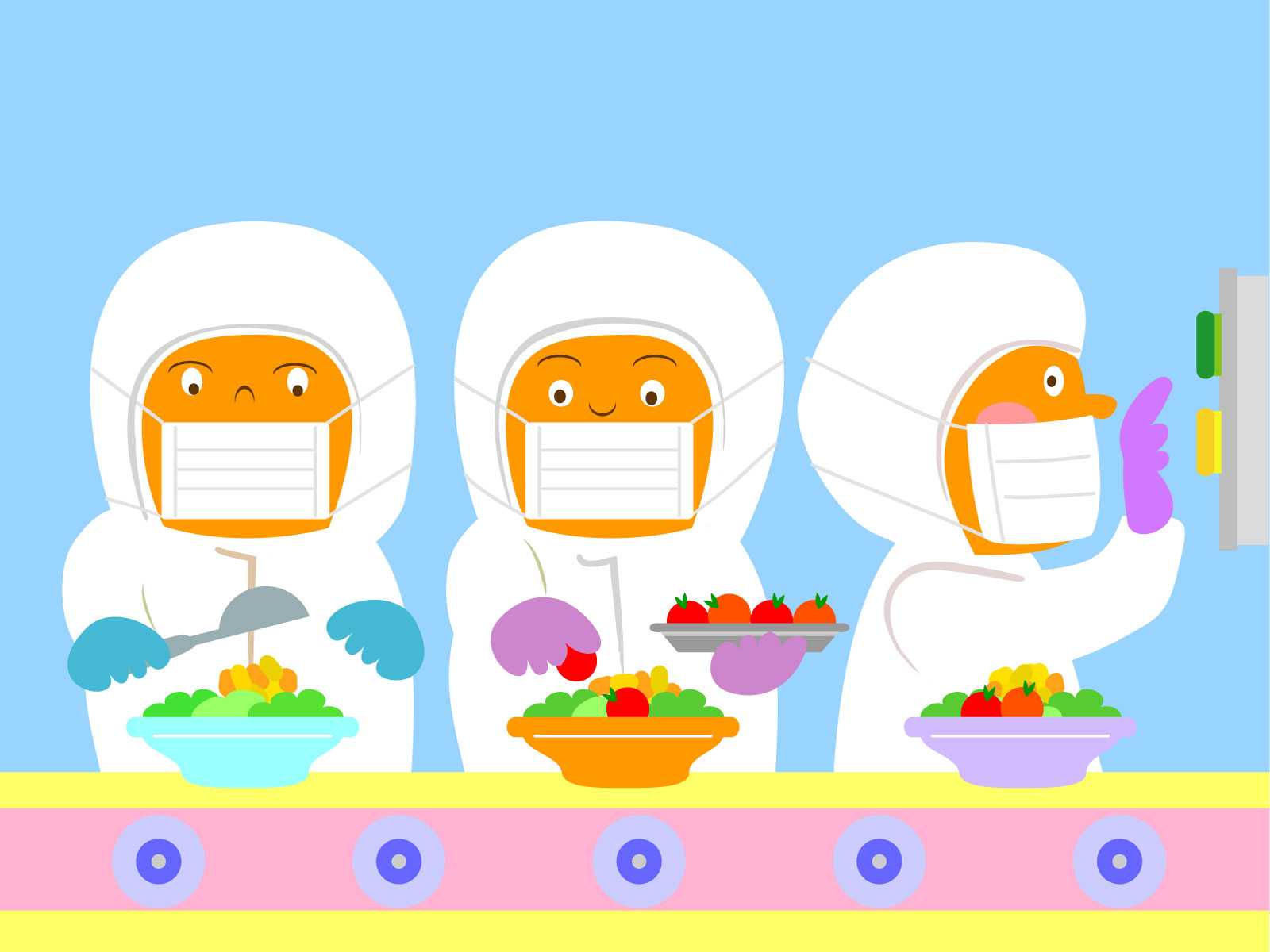
シスプラチンの嘔吐は中枢性なので、5-HT3受容体拮抗薬が使われます。
これは予防的投与はあまり行われませんが白血球減少に対しては顆粒球コロニー刺激因子[G-CSF]が対処療法的に用いられます。
前のブログでも書きましたが、フルオロウラシルの下痢の防止のためにティーエスワンでは、フルオロウラシル分解阻害剤の他に、消化管でのフルオロウラシルの活性化を阻害するオキソン酸が配合されています。
免疫チェックポイント阻害剤で大腸炎が発生したら免疫チェックポイント阻害剤を中止することになります。中止後すぐに大腸炎は回復せず、免疫抑制剤を使わないと大腸炎が治まらない症例もあるとのことです。
がんが縮小しているときに、この副作用が発生した場合には、中止による効果の消失と免疫抑制剤によるがんの再発もあるかもしれません。

従って、化学療法剤のように予防的に副作用改善剤を投与することによって、抗腫瘍効果の増強が想定されます。
PD-1、PD-L1よりもCTLA-4に対する抗体の方が大腸炎を引き起こす可能性が高いようですが、併用すれば相乗(相加?)的に発生率が増えるようです。
抗体を使う限りは、腫瘍あるいは腫瘍認識部位に抗体を運んでやる必要があります。体中にある受容体に対して選択的に分布する抗体が必要であるということです。それを考えるとPD-1Lが腫瘍の受容体を抑える事から推奨されるかもしれません。しかし、実データを見るとそれほど差があるようには思えません。
化学療法と同じように腫瘍と生体を無差別に効果を示している可能性があるということです。
現在は 効果の観点から免疫チェックポイントが発生している腫瘍のみに使うと制限がついている免疫チェックポイント阻害剤があります 。その薬剤が一番使われています。オブジーボはその縛りがついてはいませんが、それが原因と思いますが、オブジーボはナイーブながん(無治療のがん)を対象とした現在の第1選択薬との比較試験で上回る効果を出すことができませんでした。
ひとつには、 腫瘍組織の受容体が発現していることで、抗体がその受容体を阻害することで、大腸にある受容体を阻害する量が相対的に減らすという仮説のもと使用患者を絞ることによって、効果の上昇と副作用の減少を求めることです。 これは、大腸炎の副作用がでている患者の腫瘍の受容体を測定することで確認は可能です。
もう一つは抗体から離れることです。 有機化合物で免疫チェックポイント阻害作用を示すものをさがすことです。 これは副作用防止の観点からでは大きすぎる課題かもしれません。しかし、抗体の場合には細胞特異性を見つけることは難しいと考えています。
有機化合物であれば、可能ではないかと思います。イメージとしては受容体とがっちり結びつく抗体よりも、受容体の一部分に作用して受容体の作用を停めることができれば、別の薬を配合したり、有機化合物の部分改変で細胞特異性が出る可能性があると思っています。

化学療法剤では副作用の機序が制癌作用と分離できる場合には、化学療法剤の中止のデメリットを小さくできるために副作用防止剤を使います。この薬剤は保険適応されています;
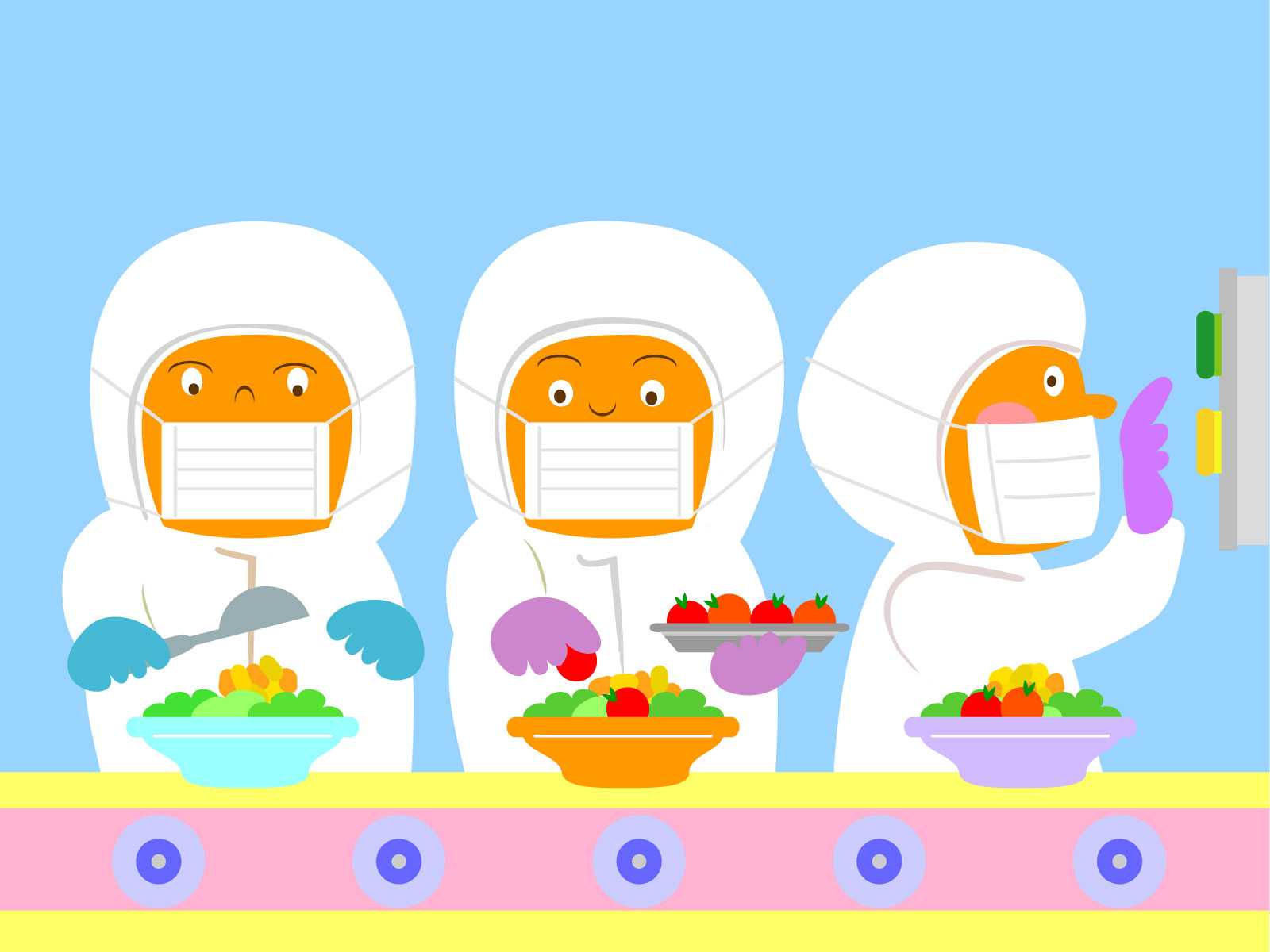
シスプラチンの嘔吐は中枢性なので、5-HT3受容体拮抗薬が使われます。
これは予防的投与はあまり行われませんが白血球減少に対しては顆粒球コロニー刺激因子[G-CSF]が対処療法的に用いられます。
前のブログでも書きましたが、フルオロウラシルの下痢の防止のためにティーエスワンでは、フルオロウラシル分解阻害剤の他に、消化管でのフルオロウラシルの活性化を阻害するオキソン酸が配合されています。
免疫チェックポイント阻害剤で大腸炎が発生したら免疫チェックポイント阻害剤を中止することになります。中止後すぐに大腸炎は回復せず、免疫抑制剤を使わないと大腸炎が治まらない症例もあるとのことです。
がんが縮小しているときに、この副作用が発生した場合には、中止による効果の消失と免疫抑制剤によるがんの再発もあるかもしれません。

従って、化学療法剤のように予防的に副作用改善剤を投与することによって、抗腫瘍効果の増強が想定されます。
PD-1、PD-L1よりもCTLA-4に対する抗体の方が大腸炎を引き起こす可能性が高いようですが、併用すれば相乗(相加?)的に発生率が増えるようです。
抗体を使う限りは、腫瘍あるいは腫瘍認識部位に抗体を運んでやる必要があります。体中にある受容体に対して選択的に分布する抗体が必要であるということです。それを考えるとPD-1Lが腫瘍の受容体を抑える事から推奨されるかもしれません。しかし、実データを見るとそれほど差があるようには思えません。
化学療法と同じように腫瘍と生体を無差別に効果を示している可能性があるということです。
現在は 効果の観点から免疫チェックポイントが発生している腫瘍のみに使うと制限がついている免疫チェックポイント阻害剤があります 。その薬剤が一番使われています。オブジーボはその縛りがついてはいませんが、それが原因と思いますが、オブジーボはナイーブながん(無治療のがん)を対象とした現在の第1選択薬との比較試験で上回る効果を出すことができませんでした。
ひとつには、 腫瘍組織の受容体が発現していることで、抗体がその受容体を阻害することで、大腸にある受容体を阻害する量が相対的に減らすという仮説のもと使用患者を絞ることによって、効果の上昇と副作用の減少を求めることです。 これは、大腸炎の副作用がでている患者の腫瘍の受容体を測定することで確認は可能です。
もう一つは抗体から離れることです。 有機化合物で免疫チェックポイント阻害作用を示すものをさがすことです。 これは副作用防止の観点からでは大きすぎる課題かもしれません。しかし、抗体の場合には細胞特異性を見つけることは難しいと考えています。
有機化合物であれば、可能ではないかと思います。イメージとしては受容体とがっちり結びつく抗体よりも、受容体の一部分に作用して受容体の作用を停めることができれば、別の薬を配合したり、有機化合物の部分改変で細胞特異性が出る可能性があると思っています。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[妄想] カテゴリの最新記事
-
オリンピックはやめてくれ 2021年04月06日
-
完全に妄想:中国オリンピックボイコット… 2021年04月01日
-
ブルーライトはそんなに体に悪いのか? 2021年02月24日
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.