メヒコ
-プロローグ-
小さな時から「鬼の子」と呼ばれていた。
母は誰とも夫婦の契りを交わさないままに僕を産んだ。
母が16歳の時のことだった。
僕の父親がどんな人だったのか、誰だったのかを母は僕に教えてはくれなかった。
だから、僕はいまだに父親を知らない。
物心付いた時には、他人には見えないものが見えていた。
「おかぁちゃん、あの人の後ろになんかいる」
そういうと、必ず母は僕をたしなめた。
だから僕は、僕の見えたものを母以外に言ったことはなかった。
その母はもういない。
5歳になったばかりの春、母は流行り病でこの世を去った。
不思議と悲しくはなかった。
母の身体から、母の形をした幻のようなものが抜け出たのが見えた。
僕の視線に気づくと、幻のような母の影は僕を抱きしめた。
しかし、すぐに霧のように溶け消えてしまった。
それ以来、僕は祖父母の家で暮らしていた。
優しい祖母と、無口な祖父。
普通の両親以上の愛情を僕に与えてくれた。
その祖父母も、相次いでこの世を去った。
母と同じように最後に僕を抱きしめてから・・・。
-露見-
祖父母が亡くなってから、一人だった。
隣の家のおばさんが、食事を運んでくれた。
その家には僕と同い年の「かよちゃん」という女の子がいた。
おかっぱで日本人形みたいな子だった。
僕はおばさんとその子が好きだった。
ある日、遊びに出かけるかよちゃんを見かけた。
日差しの強い夏の日だった。
かよちゃんの肩の上に黒い影が載っていた。
僕は知っていた。
あの影に魅入られた人は必ずその日のうちに死んでしまうことを。
僕は慌てた。
おばさんに知らせようとかよちゃんの家に行った。
「おばさん、かよちゃんが、かよちゃんが・・・」
僕が言えたのはそこまでだった。
それ以上何をどう説明していいのか分らなかった。
おばさんの怪訝な目線に、僕は走って家に帰った。
それからなにをしたか僕は覚えていない。
ただ、はるかに長く感じられた時間の末に、耳にした記憶。
慌しい人の足音。騒然としたざわめき。
そして、おばさんの泣き叫ぶような声だった。
その夜、遅くおばさんはいつものように食事を運んできてくれた。
それまで騒然としていたかよちゃんの家は、しいんと静かになっていた。
おばさんの目は真っ赤だった。
僕は胸が締め付けられた。
かよちゃんとおばさんに謝りたかった。
僕がご飯を食べる間、おばさんは僕の隣にいた。
暗がりの中、おばさんの後ろに何かの気配を感じた。
おばさんの後ろにあの影がいた。
僕は息が止まった。
「おばさんも・・・死んじゃう・・・」
とりあえず今日はここまで・・・。
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- フィギュア好き集まれ~
- 【中古】[FIG]SNK美少女 不知火舞(し…
- (2024-12-02 16:00:45)
-
-
-
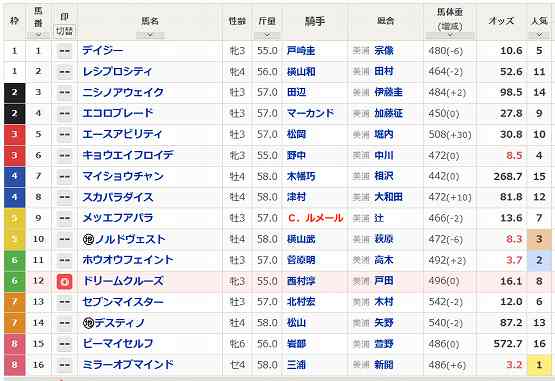
- 競馬全般
- ドリームクルーズ(10)~初ダートでし…
- (2024-12-03 19:57:31)
-
-
-

- 一口馬主について
- ノルマンディー懇親会2024(2):吉…
- (2024-12-03 19:54:55)
-
© Rakuten Group, Inc.



