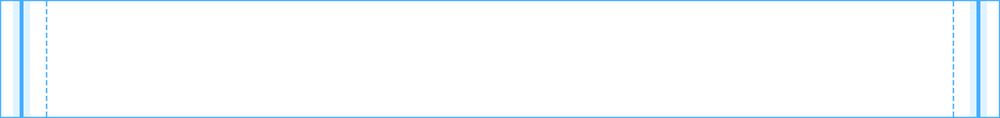車椅子の高さで
多発性硬化症の診断が下ったのはナンシー・メアーズが二九歳の時だった。脳と脊髄の白質に起きる病で、症状は人によって異なるが、末端神経のどこかに影響があらわれる。「幼い子どもと元気はつらつとした夫もいる、知的で詩人としての将来もある」と思っていたメアーズは、三〇歳間際の「最盛期」に病に冒されたというわけだ。その後、病はゆっくりと進行し、移動を助ける道具も二〇年ほどの間に杖から電動車椅子へとかわっていった。
アメリカ社会の中で、それなりの「幸福」が保証される中産階級に属するには実践と賞賛の源ともいえるability(能力)が欠かせない。文学的才能に恵まれたメアーズは人々の敬意の視線に囲まれていた。仕事をこなし、妻として母として生き、政治集会にも参加し、社会のなかでabilityを開花させていった。しかし病を負った彼女はdisability(能力の欠損=障害)の身の上になった。「能力」への信仰と礼賛が強いアメリカにおいて、人々が最も恐れる状況に彼女は堕ちたのだ。病は彼女自身の努力によって獲得したと思っていたabilityを一つ一つ〈諦め〉させていった。悲しみと絶望の淵を歩くメアーズを「励ましてくれる文化的土壌はまったくないにひとし」かった。
ある日、病によって人生がどれだけ歪められてきたかを語るメアーズに、看護士のジョアンが訊ねた。「多発性硬化症にかからなかったら、あなたはどうな人になっていた?」 正解が用意されていたわけではない。「いっしょに考えるための問いかけ」だった。日本語では〈諦め〉の語源には「明らかに見る」という意味が含まれるが、メアーズはこの問いかけ以来、自身をとりまく状況を〈諦め〉ていく。障害一般ではない。あくまでも自分の身体に限った個別的状況を〈諦め〉ていくのだ。「障害者」ではなく、「カタワ」という言葉で自身の状況を語る彼女に見えてきたのは「なにか、人の変なところ、とくに機能障害を暗に示すものは、無視するように教え込まれ、なきものにしてしまう」人々の姿だった。彼女は思う「私たちの社会には魔法のような考え方」が広がっていることだった。ときに怒りに震える差別に直面してメアーズはこう言う「いちばんひどい仕打ちをする人たちは、私のような運命をいちばん恐れている人たちではないか。そしてこの恐れが私とのあいだに心理的な距離をとらせるから、私の人生は彼が思っているほど半分も悲惨ではないということを、いちばん学べない人たちなのだ」。
自分自身を染め上げていた能力への信仰から脱し、「障害者」をつくり出す「健常者」の共同性に対して、「否」を突きつけるに至るまで、彼女の内面では想像を絶する長い葛藤があったろう。私たちは能力や美、永遠などの価値を礼賛することに余りに慣れている。メアーズのまなざしは、私たちが自らを自身たらしめるために用いている価値が何を排除して成り立っているのかを照らし出す。この本を手にしたら、もう以前の自分に戻ることはできない
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- 入浴後の体重
- 2024/11/18(月)・昨夜のおかず/コ…
- (2024-11-18 17:00:00)
-
-
-

- 今日の体調
- 金曜日の夜は穏やかな天気頼む
- (2024-11-17 15:34:36)
-
-
-

- ウォーキングダイエット日記
- 80万アクセスだけど、ボチボチ。
- (2024-11-15 08:20:37)
-
© Rakuten Group, Inc.