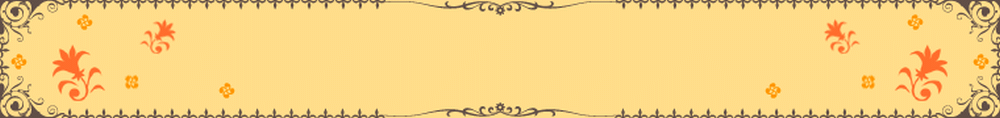干支ガール 前編
俺はその晩、荒れまくっていた。
進めていた仕事はポシャる、企画書は最終段階でボツになる、おまけに元彼女から結婚報告のおめでたいハガキが来る。
これが飲まずにいられるか?
「ちきしょう」
知らず知らずのうちに酒が進み、頭がぼうっとしてくる。
義理で付き合ってくれた同僚に、やたらと絡みたくなる。
すると・・・・。
いつのまにか、周りには、誰もいなくなっていた。
俺は居酒屋に一人、取り残されてしまったのだ。
俺の酒癖が悪いということは、同僚なら誰だって知っていることだ。だからといって、みんなで示し合わせて帰るこたぁねえじゃねえか。
「何だってんだよ、バカにしやがって」
もうやけくそ。
俺は酒の勢いで、居酒屋の中で一人大声をあげてしまった。
すると、店員が厳しい顔つきで近寄ってきやがった。
「何だよてめー」
俺はこれ幸いとその男に悪態をつくことにした。相手は誰だっていい気分だった。けれど、その直後からの記憶が曖昧になってしまった。
かなり酒が回っていたらしい。
そして俺はいつのまに、その店から追い出され、薄汚い路地の片隅に座り込んでいたのだった。
ゲロの匂いがどこからか漂ってくるような、薄汚い路地。
ビルの裏側の、幅1メートルもないような、「建築基準法は一体どうした!」と大声で叫びたくなるような隙間の路地には、誰一人として人はいなかった。
たぶん、ここは路地のように見えるけど、道ではないのだろう。
ビルとビルの間なのだろう。だから通行人がいないのだ。
要するに俺は他人の通行の邪魔にならない場所に放置されたのだ。
見上げたところには外灯もなく、両脇のビルに光を遮られ、都会の夜にしてはやたらと暗く感じる。
コンクリ、コンクリ、コンクリ、目につくのはどこもかしこもボロのコンクリート。
「何だよ、何だよ、何でだよ・・・・」
俺はいつの間にか、自分の目に涙が浮かんでいるのを感じていた。 泣くつもりなど無かったはずなのだけれど、酒のせいで増幅した感情が、うわぁっと波のように押し寄せてきたのだ。
内心、
(俺、もしかしてちょっとバカじゃないの)
という気もしたが、どうせ誰も見てないんだから涙くらい流してもばちは当たらないだろう。
俺は酒を飲みすぎると、泣き上戸も入ってしまうタチなんだ。
(いいんだ、どーせ俺はバカなんだよ)
そう思って、ひと思いに涙を流してやろうとしたその時。
ふと俺の目に、不思議というか、とんでもないものが目に入って来た。
それは、薄汚い路地の、細いビルの間の隙間の奥で、丸く光る二つのものだった。
(なんだ、ありゃあ?う、うわぁっ)
俺は思わず息を呑み、叫ぼうとしたものの、声が出なくなってしまった。
あまりにも驚きすぎたのだ。
(け、ケモノだ!)
俺は心の中で叫んだ。
大都会東京の、ビルの隙間に、なにやら大きな動物がいるのだ。
ありえない話だ。田舎の山の中じゃあるまいし。
(し、渋谷だぜここは!)
俺は硬直したように固まり、動けなくなってしまった。そして自分の意思に反して、足が小刻みに震え始めた。
(企画書がなんだ彼女がなんだ会社がなんだってんだ。そんなことよりも命が大事じゃないか)
俺は生まれてはじめて、本当の「身の危険」をリアルに感じていた。
なぜならば、そのケモノは、あきらかに「でかい」のだ。どう見ても犬や猫の大きさではない。もしも犬だと仮定したとして、大きめの秋田犬くらいは優にあるはずだ。
秋田犬は熊と戦う犬としてマタギに可愛がられていたという。
ということは、もしも秋田犬ぐらいの大きさのケモノ、と考えたとしたって、そいつはきっと、弱い人間の男の一人や二人は、簡単に噛み殺すことができるはずだ。なんたって熊と戦う犬なんだからな。
俺の頭の中では、関係あるような無いような考えがぐるぐる回っていた。人が死ぬ前には頭の中に、走馬灯のようにいろんなことが浮かぶというが、
(だからってなぜマタギが浮かぶんだよ!)
俺は自分で自分にツッコミを入れ、なんとか少しでも落ち着こうと必死になった。
何の自慢にもならないが、俺はバイオレンス方面には全く自信がない。
高校時代、授業でやった柔道では、ひたすら投げられ役だった。 身長は165センチ。そして体重は50キロ。どうだ小さいだろう?小柄だろう?投げてみたくなるだろう?
そんな訳で、まぁ、なんていうんだろう。もしホラー映画だったら俺ってたぶん一番最初に殺される役回りの男だろうと思う。つーか、わけわかんないケモノに襲われたら、間違いなく死んじゃうよ!
俺はとにかく、真っ暗な闇に目を慣らすようにして、必死にその物体を見つめた。
もしかしたらデカいぬいぐるみが捨ててあるだけかもしれないじゃないか?
そして、そう思った俺がやっといくらか冷静になり、耳を澄ますようにすると、なんと、鼻息のような、「ぶすっ、ぶすっ」
という音が聞こえてくるのがわかった・・・。
(ま、まずい・・・こりゃ、本物だ。生きているケモノだ。やっぱりぬいぐるみなんかじゃないんだ)
万事休す。俺の体から、脂汗とも冷や汗ともつかないものが、だらだらと流れ始めた。
(俺、ここで死ぬのか。そんなのイヤだ)
後ずさりして逃げたかったが、俺が動けばその獣も動くかも知れず、大声を出して助けを呼ぶのもためらわれた。その声を聞いてもし誰かが助けに来てくれたとしても、そのときにはもう俺はこの世にいないか、少なくとも大ケガくらいはしているだろう。
(ど、どうすりゃいいんだよ。こんなときは。し、死んだフリか?)
そんなことを自問自答しながら動けずにいると、しだいに俺の目が暗闇に慣れてきた。暗いとはいえ都会なので、どこからか光が漏れて来る。息を詰めて、俺は前方を見つめた。
すると目の前のケモノの形が、次第にはっきりしてきた。
(なんだ、ありゃあ。・・・・ブ、ブタ?・・・でも、ちょっと違うな・・・・、毛が一杯生えてるし・・・茶色いし・・・・まさか、)
「イノシシ?」
俺はは思わず小さな声を出して言ってしまった。
すると。
「そうですよ」
と、返事のようなものが聞こえるではないか。
(は?)
俺の頭は真っ白になった。そして耳を疑った。それこそ、純粋に言葉通りの意味で。俺、耳がどうかしちゃったんじゃないの。
「い、イノシシ・・・・?」
「だから、そうですよ。こんばんは」
俺の目には、どうしても、そこに誰かいるようには見えない。
イノシシしかいないように見えるのだが。
「あのー、誰かいるんですか」
マヌケかとも思ったけれど、俺は恐る恐る尋ねてみた。イノシシの後ろに飼い主が隠れてでもいるのかと思ったのだ。
都会にはいろんな人間がいる。もしかしたら渋谷のマンションの部屋で、イノシシをペットにしているやつだっていないとは限らない。
「はい、目の前にいますよ。見えてるんでしょ?こんばんは」
そんな俺の思いをよそに、そこには人の姿は無かった。イノシシだけが、4本足で立ったまま、俺を見ている。
(お、俺、とうとうどうかしちゃったんじゃないだろうか。それとも、飲みすぎ?つーかこれは夢?)
俺は何度も何度も自分を叩いてみた。
(夢なら醒めてくれ。それとも俺はとうとうアル中になったのか?)
そんな俺の思いも虚しく、目の前でイノシシがじっと俺を見つめながらしゃべっている。
「あのー、びっくりさせてしまって、非常に申し訳ないんですけど、出会ってしまったついでに、お願いがあるんです・・・」
イノシシが、路地の奥からのっしのっしと歩いてきた。見たところ、かなり大きな大人のイノシシのようだった。いや案外、普通のイノシシよりも大きいかもしれない。
そして、そのイノシシが、しゃべっている。
正に、悪い夢のよう。
「は、はい、なんでしょう」
俺はすっかり気圧されて、イノシシに返事をした。
相当に酔っ払っていたはずなのだが、一瞬で水をぶっかけられたように醒めてしまった。
「あの、わたし・・・。早く来すぎちゃったみたいで。それであの・・・。わたし、方向音痴なので、早めに出たら、なんだかまだお呼びじゃなかったみたいなの。で、戻るわけにも行かないし、いる場所も無くて・・・。ずうずうしいみたいなんですけど、ここで出会ったのも何かのご縁と思って、あなたのおうちに居候させてもらえませんか」
(はぁ?)
俺の頭の中はもうめちゃくちゃだった。
そりゃそうだろう。渋谷で飲んで暴れていたら、しゃべるイノシシに出会って、そのイノシシが俺の家に来たいって言う。何がなんだかわかるわけがない。
俺はやっぱり、とうとう頭がおかしくなってしまったのだろうか。
「あのー、でも、俺の家狭いしペット禁止だから」
俺はそんなマヌケな答えしか言えなかった。
「あ、それは大丈夫です。えと、ちょっと待ってくださいね」
「え、大丈夫ってどういう・・・」
「ペット禁止なんでしょ」
イノシシのそのセリフとともに、俺の視界が歪んだ。というよりも、目の前のイノシシが歪み始めたのだ。
ぐにゃりぐにゃり、まるでSF映画みたいだなあと思いながら、俺は現実と上手く同化できなくなっている自分に気がついた。
(へ、ヘンなことが起こってるよ)
逃げたい、今すぐにこの場から逃げたしたい。俺は直感的にそう思い目をつぶった。なぜかわからないが、恐ろしかった。しかし、逃げることはできなかった。びっくりしすぎていて、足が動かないのだ。
そして、俺が必死に目を閉じていると、声がした。
「これなら、大丈夫?」
俺の目の前には、もうイノシシはいなかった。そして、こげ茶色のダッフルコートに、ベージュ色のロングブーツを履いている、ちょっと太目で大して可愛くもない、地味な見た目の背の低い女が立っていた。
「あの・・・えっと」
「本当にごめんなさい。でも、困っているの・・・。12月31日まで、あなたのお部屋にいさせてくださいな。けしてご迷惑はおかけしませんから」
目の前の女は、俺に向かって深々と頭を下げた。俺は、ぐらりと眩暈がした。そして、がくんと尻餅をついてしまった。
そうしたら、女が少し微笑んで、俺に手を伸ばして来た。
それが、12月1日のことだった。
「早瀬さん、今日の合コン、結構かわいい女の子が揃ってるらしいですよ」
昼メシを食べ終わって、社内の喫煙所で一服していると、後輩の畑野が声をかけてきた。
「あー、あの話って今日だったっけ」
「そうですよ。なにぼんやりしてるんですか。クリスマスムードで派手にやるらしいですよ。早瀬さん、けっこう楽しみにしてたじゃないですか。まさか都合でも悪くなったとか?」
「えーと、うん、そうなんだ。ちょっとさぁ」
俺は言葉を濁した。どう説明したらいいのかわからない。
「へっ?マジっすか?早瀬さん、前はあんなに乗り気だったのに。あー、さては新しい彼女が出来たんじゃないですか?そうでしょ」
畑野が訳知り顔で言い出す。こいつは前の彼女と俺が出会った合コンに一緒に参加していたのだ。だから別れたことも知っている。
「そんなんじゃねーよ」
俺は眉を顰めて否定した。
彼女・・・なんかじゃねえよな。あれは・・・、イノシシなんだから。
しかし、合コンに行くはずだった俺の頭の中にあるのは、あのイノシシ女が毎晩丁寧に作っているらしい、やたらと美味いメシを、早く帰って食べたいという、そんな気持ちだけだった。
「まったく、いい年して照れることないじゃないですか。そうかぁ、早瀬さん、良かったじゃないですか。ま、そういうことなら仕方ないっすよね」
畑野はニヤニヤしながら、煙草に火をつけた。
俺は喫煙所の灰皿に吸い殻を放り込み、席を立った。
京王井の頭線の高井戸駅から5分ほど歩くと、俺の住むマンションがある。
まぁ、マンションとは言っても建物も小さいし、部屋も1DKで狭いのだが、単に名前が「高井戸ローズマンション」というのだ。
外壁にバラの花が彫刻してあったらやめようと思って不動産屋と見に来たところ、名前が「ローズマンション」なだけで、見た目はただの地味な普通のマンションだったので、ここに決めたのだ。
家に帰ると、部屋に灯りがついている。・・・なんだかまだ、それは不思議な光景に思える。もしかしたらこういうのをバラ色っていうのかもしれないと俺は思う。
俺は今年で34歳、大学に入るために田舎の町から上京してきて一人暮らしをはじめ、そのまま東京に就職し、もう16年にもなる。 その間、何度か彼女ができたこともあったし、部屋に女が通っていた時期も無いわけじゃないけれど、女と一緒に暮らしたことは皆無だった。どちらかといえば、つき合い出したとたん部屋に来て彼女づらするような女はうっとうしいとさえ思っていた。
そんな俺だったのが。
いきなりやってきたイノシシ女がイヤじゃない、というのは、これは一体どういう心境の変化なのだろう。
俺が玄関のチャイムを鳴らすと、中で、
「はーい」
と、明るい声がして、ぱたぱたとかわいい足音が聞こえ、ドアが開いた。
「和弘さんお帰りなさい!今晩はすき焼きですよー」
「お、今日もいい匂いだなぁ」
腹が減っていた俺は、うきうきしながら靴を脱ぎ、部屋の中に入った。
「さあ、スーツなんか脱いで」
イノシシ女が俺の後ろに回ってジャケットを脱がせ、ハンガーにかけてくれる。
「最初にお風呂にしますか?」
「いや、風呂は後にするよ。っていうか、一緒に入ろうぜ」
「やだもう、和弘さんったら、エッチなんだからぁ」
俺はイノシシ女の尻を撫でる。
これがまた弾力があって柔らかい、いい尻なんだ。
テーブルの上ではおいしそうなすき焼きが、イノシシ女の丸っこい柔らかそうな手で手際よく作られて行く。
「うん、美味い!」
ひとくち食べて、俺がそう言うと、温かな湯気の向こうでイノシシ女が微笑む。
「そう?良かったぁ」
「ところで、イノシシなのにすき焼きってアリなのかよ」
ふと俺は疑問に思った。するとイノシシ女は、
「イノシシというのは雑食なんですよ!それに第一、今は人間に変身してるんですから何でもアリなんです。お肉、大好きです」
と、笑いながら答えた。そういうものらしい。
冷たいビールに、おいしいすき焼き、そして女。
(なんか俺、幸せなんですけど)
なぜか一週間前から、俺の生活に降って湧いて雪崩れ込んできた現実。
俺は狐につままれた気分だった。狐じゃなくてイノシシだけど。
後編へ続く
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- ★ おすすめのビジネス書は何ですか!…
- ウェブ国産力/佐々木俊尚
- (2024-11-29 10:15:36)
-
-
-

- 読書日記
- 書評【 勝間式 超ロジカル選択術 …
- (2024-11-29 00:00:20)
-
-
-

- イラスト付で日記を書こう!
- 一日一枚絵(11月17日分)
- (2024-12-01 00:29:56)
-
© Rakuten Group, Inc.