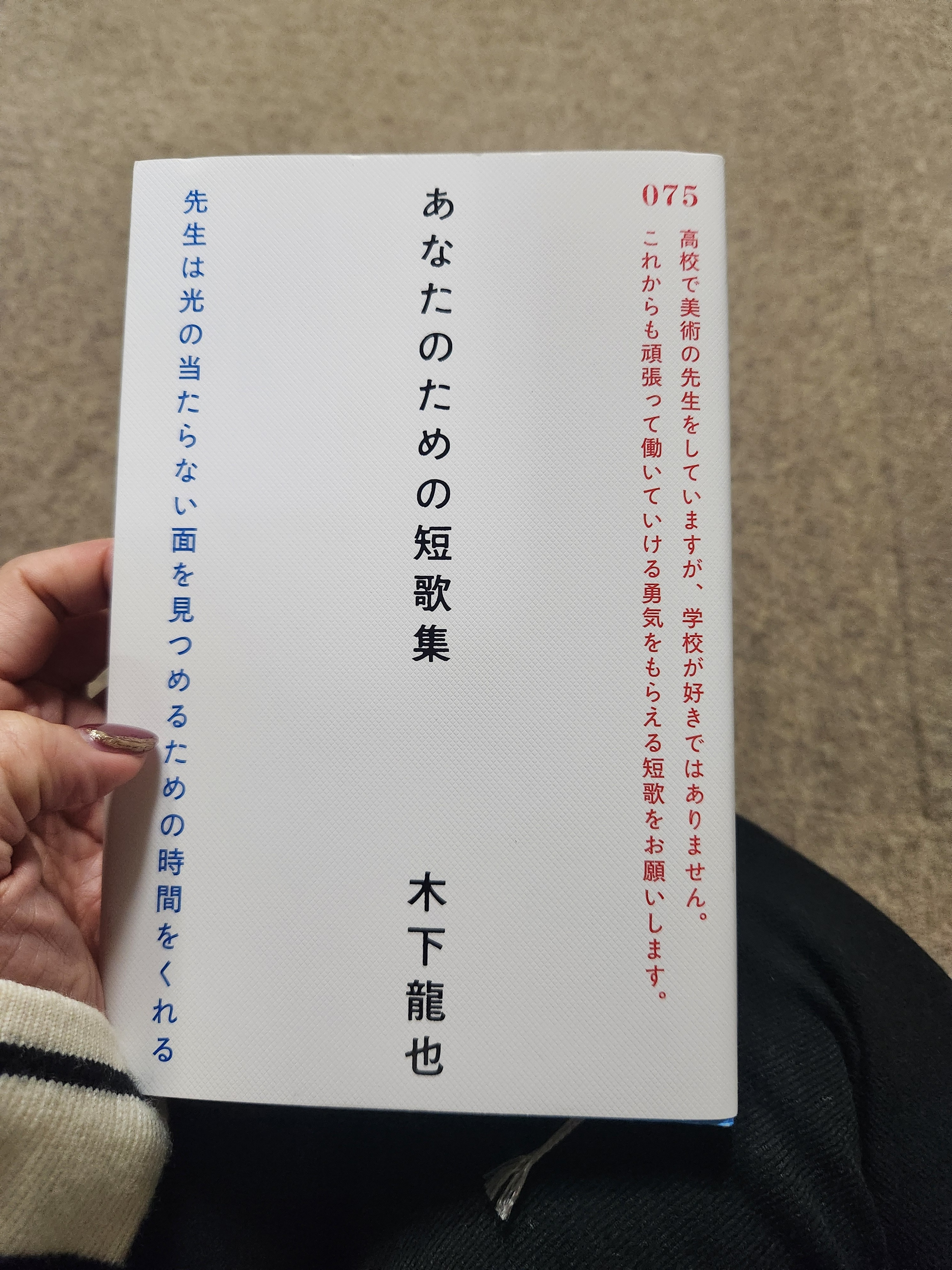第三話 反乱前夜(3)

【 第三話 反乱前夜(3) 】
アパサと一応の話を済ませたトゥパク・アマルは、そのまま商隊を率いてペルー副王領の首府リマに向かった。
反乱準備を進めながらも、彼の中には、まだ判然とせぬ思いがかねてより存在していた。
それは、この国の暴政は、真にスペイン国王の意志なのか、という根本的な疑問であった。
なにしろ、この植民地はスペイン本国から遠く離れており、また、複雑な統治機構によって国王の意志は何段階にも渡る役人たちを介して、やっと民衆のもとに伝わってくる仕組みになっている。
仮に、スペイン国王が、あるいはこの植民地である副王領の副王が、どれほど崇高な理念に基づく統治をこの植民地で行おうとしていたとしても、末端の代官ら強欲なスペインの役人たちが法に暗い民衆を騙し、国王らの本来の大御心の実現を阻んでいるのかもしれぬ、という考えはまだ完全に否定することはできなかった。
真の敵は、末端の代官レベルなのか、あるいは、スペイン国王や副王レベルまで達するのか…――その見極めは、トゥパク・アマルにとって今後の行動を決める上で非常に重要なことであった。
そして、もう一つ、トゥパク・アマルの中で考察を要する問題があった。
それは、宗教の問題だった。
アンデス地帯ではもともと創造主ビラコチャ神への信仰が行われていたが、スペイン侵略以降、キリスト教が侵略者によって強制的に布教され、この200年の間にインカの民の間にもキリスト教信仰はかなり浸透していた。
スペイン人に憎悪を抱く民衆たちの中にも、キリスト教は受け入れ、今や熱心な信者である者が少なくなかった。
もちろん、キリスト教信仰と共に、心の奥深くに本来のビラコチャ信仰を秘めている場合は多かったが、それでも、キリスト教の存在は今や絶大なものだった。
侵略者のもたらした宗教が、時代の変遷によって、いつしかその支配下で苦しむ人々の精神的支えになっているというのも皮肉な話ではあったが、その事実をトゥパク・アマルは冷静に見極めていた。
今や、民衆の心の支柱ともなっているキリスト教までをも否定することは、民衆から精神的支柱を奪うことにもなりかねず、心を一つに合わせ、強い意志をもって侵略者に立ち向かわねばならぬ事態において、決して得策ではないはずだと考えていた。
「トゥパク・アマル様、まもなく首府リマに到着いたします。」
ビルカパサの声に、愛馬に揺られながら考えに耽っていたトゥパク・アマルはゆっくりと顔を上げた。
商隊が進んできた荒野の道も、次第に舗装が進んだ石畳の路面に変わってきている。
道を往く人々の行き交いも、徐々に賑わいを見せてきたようだ。
さすがに、この首府リマの周辺はスペイン人が多く、どこか人々の装いも華やかで町全体の風情も西洋風な趣が濃厚である。
そのようなスペイン的気風の中でも、トゥパク・アマルら商隊の一行は、その格調高い輝きによって、路往く人々の目をひときわ惹きつけた。
荷を積む10台あまりの堅固な貨車には、インカの象徴である太陽の文様が彫り上げられ、風格がありながらも鮮烈な色彩が施されていた。
100頭あまりの荷を運ぶ頑強そうなラバの艶やかな肢体は陽光を照り返して輝き、それらを守るように進む50人ほどの商隊員たちは、正確にはトゥパク・アマルの選りすぐりの護衛官たちだが、毅然と胸を張って悄然と歩み、非常に統制がとれていた。
そして、商隊員たちに堅固に守られるようにして、その中央には愛馬に跨り凛として進むトゥパク・アマルの姿があった。
もちろん、トゥパク・アマルのすぐ横には、側近のビルカパサが、ひときわ逞しいラバの背の上で、いかなる事態にも瞬時に反応できる体勢で身構えていた。
ちなみに、この時代、騎馬を許されていたのは、白人以外ではカシーケ(領主)レベルの者だけだった。
トゥパク・アマルは、これから会おうとしている首府リマのある重要人物のことに再び思いを馳せながら、きっ、と前方を見据えた。
暮れかけてきた朱色の空を背景にして、まるで凱旋さながらに前進する、凛々しくも妖艶なまでの強いオーラを放つその「インディオ」の姿に、往来のスペイン人たちは気圧された眼差しで遠巻きに、あるいは、無意識のうちに道を開けていた。
一方、先程までは、路の端をスペイン人に遠慮がちに身を縮めながら歩んでいたその土地のインカ族の人々は、その壮麗な同族の商隊と、そして、同じインカ族とは思えぬほどに堂々たる態度で前進する馬上のその人を見て、まるで光を与えられたように胸を張って歩み始めた。
永年に渡り社会の底辺に追いやられ、すっかり自信を失っていたインカの人々にとって、トゥパク・アマルが何者かを知らずとも、同じインカ族の一人の人間が放つその輝くような存在感と高潔な雰囲気は、それだけで彼らに再び民族の誇りを呼び覚ます力を秘めていたのだった。

その頃、この首府リマにあるペルー副王領の統治機構の中枢、インディアス枢機会議本部の執務室では、あの植民地巡察官アレッチェがもう一人の別の人物と共に、苦々しい表情で向き合っていた。
アレッチェは、普段はあまりみかけぬ「インディオ」の商隊の一行が町に入って参りました、という報告を部下から受けたところだった。
しかも、何やら居丈高な雰囲気で、どうもインディオらしくない尊大ぶった人物がその中にいる、という観察も言い添えて部下は退室した。
トゥパク・アマルだ、とアレッチェはすぐに分かった。
彼の中に、一瞬、この機に乗じてトゥパク・アマルを始末してしまおうか、という考えがよぎる。
が、「インディオども」に妙に慕われているトゥパク・アマルに安易に手をくだすことは、逆に、それらインディオどもをへたに刺激することにもなりかねない。
ここは状況を見ていくしかあるまいか、とアレッチェは心の中で唾を吐いた。
報告の部下が下がると、アレッチェは憎々しげに言った。
「来たようですな。
モスコーソ様。」
モスコーソと呼ばれた人物は、「うむ。」とおもむろに頷いた。
その人物は、極上の生地で仕立てられた見事な紺色の僧衣を身に纏い、僧衣の中にも同色で統一された格調高い衣を身につけ、手首には幅広の純白の袖飾りをつけていた。
さらに、その胸元には、首からさげた、直径30センチ以上もあろうかと見える見事な十字架が輝いていた。
その十字架には美しい数種類の大粒の宝石がちりばめられ、重厚な黄金の飾りが附されている。
まるで、王家の秘宝と見まがうほどの豪華な十字架である。
その十字架こそ、この殖民地において最も高位の司祭であることの証であった。
実際、このモスコーソは、この植民地におけるカトリック教会の頂点に立つ最高位の司祭であった。
彼は単に宗教的な意味合いで高位に君臨する存在というだけでなく、この時代、司祭という存在は国の統治においても絶大な発言力を有する政治的権力者でもあった。
このモスコーソ司祭は、50代にさしかかった威風堂々たる風貌の持ち主で、年齢のためにやや横幅の広くなったその体格も、かえって彼の貫禄を高めていた。
キリスト者らしい厳かさを漂わせながらも、そのわざわざ慈愛深気に細めた目はかえって不気味な色味を発し、奇態な雰囲気を周囲に放っていた。
この植民地に赴任して既に長い年月の経つアレッチェでさえ、未だにこの最高位の司祭の実像をつかみかねていた。
「わざわざ、あのようなインディオにお会いにならずともよろしいのでは。」
アレッチェは、その真意をうかがうように司祭を見て言った。
モスコーソは不自然なほどに目を細めたまま、唇の両端を軽く吊り上げた。
「子羊が会いたいとわざわざ申しておるのだ。
牧者として、その申し出を断る道理はあるまい。」
そして、一瞬、カッと目を見開いた。
「道理を通しておいた方が、有利よのう。」
その眼光の不気味さに、さすがのアレッチェも背筋に悪寒を覚えた。
その頃、トゥパク・アマルは、モスコーソ司祭との目通りのために丁寧に運んできた衣装の荷をほどき、面会の準備を整えた。
そして、今回の目通りを申し出たその目的を、頭の中で反芻した。
まず、かねてより思案していたこと、つまり、この国で虐げられている民衆にとって、真の敵は誰なのか、それを見極めることだった。
敵は、末端の代官レベルなのか、あるいは、スペイン国王や副王レベルにまで達するのか…――最高位の司祭との面会はその答えを探る手掛かりを与えてくれるだろう。
また、この国の民衆の精神的支柱となっているカトリックの教えを司る頂点に立つ司祭とは、果たしていかなる人物なのか、そのことも見定めておきたかった。
実は、トゥパク・アマルは、今回の面会には一縷の希望を託していた。
キリスト教の教義を知るトゥパク・アマルにとって、その愛と赦しの教えに真の意味で従うならば、司祭の長たる者が、この国の窮状を野放しにしておけるはずはないのだ。
キリスト者としての最高位の立場に選ばれし人物であれば、トゥパク・アマル自身が願ってやまぬ虐げられた人々への人権や人道的配慮について、それ相応の理解と采配を期待できるかもしれない。
モスコーソ司祭との話し合いの展開によっては、流血の事態を見ずにすむかもしれぬ…――トゥパク・アマルの中には、この時、まだそうした思いが残されていた。
トゥパク・アマルは敢えてインカ風の身なりは控え、折り返しの襟がついた白い絹のシャツの上に、深い藍色の上下揃いの西洋風の衣服を身に纏った。
既に日は落ち、リマの中心部にあるインディアス枢機会議本部の広大な建物は、夜闇の中に異様に白くその影を浮かび上がらせていた。
ビルパカサを含む護衛の者は、建物の敷地内に入ることを禁じられた。
非常な不安を滲ませた眼差しで見送る警護の者たちを門前に残し、トゥパク・アマルは一人、モスコーソ司祭と会うべく所定の面会室に向かった。
その日の面会室は建造物の奥まった場所にあった。
スペイン人の役人が、無言でトゥパク・アマルをその場所まで導いた。
その辺りの廊下一帯には赤い絨毯が敷かれ、ただでさえ壮麗豪奢な建造物内の他の場所よりも、いっそう凝った造りになっている。
いかにも、「特等の間」と言わんばかりの場所であった。
やがて、目を見張るような豪奢な彫刻の施されたドアが見えてくる。
案内の役人は、形だけの礼をして、素早く立ち去った。
トゥパク・アマルは周囲の気配に神経を研ぎ澄ませた。
実際、何が起こっても不思議ではない場所だった。
これまで、どれほど多くのインカ側の人間の命が、スペインの役人たちの手で闇に葬られてきたことだろうか。

トゥパク・アマルは辺りに注意しつつも、その豪奢なドアに近づき、ノックをした。
「入りたまえ。」
中から、太く響く声がした。
既に、司祭が中に来ているのだろうか。
時間よりも大分早く到着したはずなのだが、と一瞬トゥパク・アマルはとまどいを覚えた。
司祭を待たせたことは、トゥパク・アマルにとっては礼を欠くことにも思われたのだった。
やや動揺したままドアを開ける。
やはり、中には既にモスコーソ司祭が待っていた。
全体に赤い絨毯が敷き詰められたその部屋は、宮殿内のような華やかな壁紙に飾られ、堂々たる、しかも優美な家具が至るところに配置されていた。
司祭は部屋の中央の臙脂色がかった豪華なソファに座っていたが、トゥパク・アマルが姿を見せると「おお!」と目を細めて立ち上がり、まるで走り寄るかのごとくにトゥパク・アマルの前までやってきた。
「そなたがトゥパク・アマル殿か。
よくお越しくだされた。」
そう言ってキュッと目を細めた。
そうしながら、細めた瞼の向こうから、舐めるようにトゥパク・アマルの全身を覗き見た。
トゥパク・アマルの中に、えもいわれぬおぞましい感覚が瞬間的に走った。
が、彼は丁寧に司祭の前に腰を落として跪(ひざまず)き、深く礼を払った。
「遅くなりまして、申し訳ございませぬ。
ティンタ郡のカシーケ、トゥパク・アマルでございます。
本日は、お目通りをお許しいただき、身に余る光栄に存じます。」
「なにを、なにを。」と、モスコーソは跪いているトゥパク・アマルの腕を取り、抱き起こすように立たせた。
「よく来てくれた。
会いたかったのは余の方じゃ。」
と、いっそう目を細めた。
そして、「そちは、かのインカ皇帝の直系の子孫なのだそうだな。」と、低い声で探るように言う。
トゥパク・アマルは、その司祭の目が急にカッと見開いて、また、キュッと細まるのを見た。
殆ど瞳の見えないその司祭の目は、瞼の奥の方で常に探るように怪しく光っている。
「さあ、さあ。」と、モスコーソはトゥパク・アマルをソファに座るよう促した。
「今日は、余に話があってきたのであろう。」
トゥパク・アマルは「はい。」と応えながらも、その瞬間に、頭の中でこの後の対応をめまぐるしく考えていた。
さすがのトゥパク・アマルも、このモスコーソという司祭の人物を読みかねていた。
不自然なほどに懐柔なその態度の裏側に、どす黒い腹の内があるようにも見えた。
それはトゥパク・アマルの直観だったが、少なくとも、警戒に値する。
トゥパク・アマルが言葉を選んでいる間も、モスコーソは異様なほど唇の端を吊り上げて微笑みながら、その細めた目の奥からこちらをじっと観察している。
トゥパク・アマルは言葉を選びながら、「では、恐れながら、申し上げます。」と目で礼を払い、やや動揺している内面を見せぬよう、慎重に声色をも統制しながら言った。
「この国のインカ族の者たち、混血の者たち、黒人たち、そして、この国生まれのスペイン人たちが置かれている窮状を司祭様はご存知でしょうか。
二重課税の問題、鉱山や織物工場での強制労働や虐待、関税の問題、強制配給など、いずれの面におきましても、恐らく、副王様や司祭様の御意図を超えた尋常ではない過酷な事態が永年続いているのです。」
そう話しつつ、今度はトゥパク・アマルの方が、あからさまにならぬよう、しかし探るように司祭を見た。
こうした非道な暴政の実態を、司祭は知っての上なのか、否なのか。
トゥパク・アマルの視線を受けて、モスコーソは瞬間的にカッと再び目を見開いた。
トゥパク・アマルの背筋に悪寒が走る。
司祭はまた細めた目で、今度は顔全体を歪めながら、すがるような目でトゥパク・アマルの方に身を乗り出した。
「ひどいとは噂に聞いていたが、そこまで酷いのかね!!
おお、そんなにか…。」
一見、あまりにも白々しいと思われたが、トゥパク・アマルは言葉をぐっと呑みこんだ。
そして、感情を抑えながら、応えた。
「はい。
何卒、実態をお調べになってください。
そして、どうぞ副王陛下にお口添えを願いたいのです。
このままでは、インカの民をはじめ、この国の虐げられた民衆は、本当に息絶えてしまいます。」
トゥパク・アマルの前にすがるようにしていたモスコーソは、再び幾度も頷き、「わかった、わかった、そのようにいたそう。」と、あっさり同意した。
そのモスコーソの様子に、かえってトゥパク・アマルは釈然としない思いに憑かれた。
「トゥパク・アマル殿…。」
モスコーソは弱々しい声を出した。
「神の御前の子羊よ、この牧者の手の中から出てはならぬ。」
トゥパク・アマルは、ひれ伏すようにしているその司祭の顔をハッと見た。
「妙なことを考えてはならぬぞ。
例えば、反乱行為など…。」
モスコーソの目が、トゥパク・アマルの目を射抜くように光る。
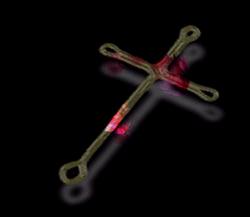
伏せがちだったその体をゆっくりと起こしながら、モスコーソはトゥパク・アマルの表情をあの舐めるような視線で見渡した。
司祭の胸元の巨大すぎる十字架が、ゆらゆらと不気味に揺れている。
そして、今までの不自然に下手に出ていた態度を翻すように、大きく反り返り、トゥパク・アマルを見下ろすようにして言った。
「美しいインカの末裔よ。
そなたが、かつてのインカ皇帝たちのように、あの処刑台に上るさまを見たくはないのだよ。」
その目は完全に見開かれ、ギラギラと奇態な光を放っていた。
トゥパク・アマルはその瞬間に至って、はっきりと悟った。
この司祭も、完全にスペインの権力者側の人間なのだ…――と。

トゥパク・アマルたちが反乱準備を秘密裏に進めはじめてから、はや3年が経っていた。
その間、自分の領地を治めながらも、彼は国中を旅し、息つく暇もないほど忙しく活動してきた。
そんなトゥパク・アマルも、今宵は久しぶりに故郷の地で、心許せる同志たちと共にひとときの穏やかな時間を過ごしていた。
とはいえ、そうした場でも話題といえば、やはりこの国の将来のこと、及び、今後の行動につてであったが。
トゥパク・アマルは、かつてコイユールが彼と出会ったあのアンドレスの館で、あの時と同じように広間の中央に座し、その周りにはアンドレスの叔父ディエゴ、腹心のビルカパサ、やや神経質そうなフランシスコがいた。
ただ、あの時の初老のインカ族の紳士、ブラスの姿はなかった。
ご記憶の通り、3年前、ブラスはスペイン国王へ直訴の海路で、スペイン側の役人の手の者により虐殺されてしまっていたのだった。
そして、今、あのブラスのかわりに、アンドレスがトゥパク・アマルらと同じテーブルについていた。
あのまだ少年だったアンドレスも、今は15歳の青年に成長していた。
この3年間で、彼はすっかり凛々しい若者になっていた。
叔父である大男ディエゴほどではないが、彼に似て長身で、インカ族とスペイン人との混血児である彼はもともと美男子ではあったが、今はまるで神話の中から抜け出してきた若い軍神のごとく精悍で麗しい風貌になっていた。
そして、今、成長した彼は、どこかトゥパク・アマルの雰囲気に似てきていた。
もちろん、血がつながっているのでそれも不思議なことではないのだが、そうした血縁的なものだけでは説明しがたいもの、その身に宿る魂が似ているような…――、言葉で表現するとしたらそのようになるかもしれない。
だが、トゥパク・アマルには深い影があったが、アンドレスには湧き立つような華やかさ、光、のようなものがあった。
同じ魂の結晶のそれぞれの側面が顕れているような、そんな表現が適切だろうか。
もちろん、15歳のアンドレスは、まだ少年のような面影も残してはいたが。
彼はまだ神学校に在学しており、今日も、あの3年前のあの日と同じように、長期休暇のために帰省していたのだった。
そして、今、その館の一隅には、そんなアンドレスを優しい眼差しでみつめる少女、いや、少女から一人の女性へと成長しつつあるコイユールの姿もあった。
アンドレスと同年齢の彼女もまた、この3年間でずいぶん変わっていた。
風貌も、体つきも、女性らしく大人びてきたのは自然のことであるし、その場にいるだけで醸し出されるような柔らかい雰囲気は、その年代の女性たちに特有のものかもしれない。
しかし、それだけではなく、コイユールの以前から変わらぬ涼しげな目元には、包みこむような深い優しさが宿っていた。
それは、表面的なものとはどこか違った。
彼女は、自らがこの国の社会の底辺を生きてきたと共に、その特有な自然療法の施術を求められ、この3年間に、はからずも数多くの底辺にいる人々と出会ってきた。
そして、信じられぬような窮状を、その渦中に身も心も晒しながら、生(なま)の体験として目の当たりにしてきた。
もともと洞察力が鋭く正義感の強かった彼女は、それらの過酷な現実に直面する中で、深い悲しみと絶望を、年齢に似合わぬ深い慈愛と、そして、強さへと変えてきたのだった。
そうすることができたのも、アンドレスとの出会いがあり、トゥパク・アマルとの出会いがあったからこそ、だったかもしれない。
二人の存在は、彼女にとって、暗闇を照らす光り輝く希望そのものだった。
今は闇夜の中を彷徨うこの国の未来を、導きゆく光…――!
コイユールは広間から少し離れた場所から、トゥパク・アマルと同じテーブルを囲むまでに成長したアンドレスを、そして、トゥパク・アマルを眩しそうに見つめた。

「あっ!…つっう…!!」
突然、背後の炊事場の方から悲鳴が聞こえた。
「マルセラ?!」
コイユールは慌ててそちらの方にとって返した。
調理用の鍋の傍で、マルセラが右腕をおさえて半ベソのままうずくまっている。
その辺りをインカ族の召使いたちが数名、心配そうに取り囲んでいた。
恐らく慣れない調理などしようとして、火傷か何かしたのだろう。
コイユールは周りのインカ族の人たちに頭を下げながら、心配なさらずお仕事の続きをなさってくださいと伝え、自分がマルセラの傍に膝をついた。
そして、すらりと引き締った褐色のマルセラの腕を、そっと自分の手に取った。
幸い、手首の少し下あたりに軽い火傷を負った程度である。
コイユールはホッと息をつき、急いで冷水を運んできてマルセラの傷口を浸した。
「たいしたことなくって、良かったわ。
でも、どうしたの?
炊事場になんて立ったりして。」
コイユールは純粋に不思議そうに、首をかしげながらマルセラを見つめた。
貴族の娘のマルセラが調理など縁の無いことは知っていたし、それ以上に、女性的なことには全く無頓着で、むしろ少年のような志向のマルセラには、炊事場に立つなど考えられないことだった。
そんなマルセラは、年頃になった今も、相変わらず短く切った黒髪を無造作にターバンでまとめ、以前にも増してすらりと伸びた手足を、ただ動きやすいという理由のために、露(あらわ)にしたままの格好でいた。
しかし、成長と共に女性らしさが備わり、本人の意思とは無関係に、むしろその中性的な美しさが周囲の目を惹いていた。
コイユールは冷水で浸したマルセラの傷跡に、そっと自分の手を当てて、治療のためにいつものシンボルを心の中で描いた。
マルセラは無言のまま、かすかに頬を赤らめている。
コイユールには平素と様子の異なる今日のマルセラの内心を測りかねたが、いずれにしろ、炊事場で何かをしようと思っていたのは確かだろう。
「何を作ろうと思っていたの?手伝うわ。」と、笑顔でごく普通に声をかけたコイユールに対して、「いい、いい!ほんと何でもないんだから。」と、妙にムキになってマルセラが答える。
「そ、そう…?」と、マルセラの調子に少々とまどいながらも、コイユールはもう一度、彼女の火傷の跡を確かめた。
そして、大分腫れがひいている様子に安堵しながら、「そろそろ、アンドレスたちにお食事を出す時間かしら。」と、何気なく言った。
すると、マルセラが突然つっかかるような調子で、コイユールの方に身を乗り出してきた。
「あたし、前から、すっごく気になってたんだけど、アンドレス様のこと呼び捨てにするのって、それって、すっご~く、まずくない?」
「え?」と、不意をつかれたようにコイユールは目をみはる。
マルセラはコイユールの鼻先まで、にじり寄ってきた。
「ほんと、よく考えてごらんよ!
あんたとアンドレス様じゃ、身分も立場も何もかも、全然、全く、違うんだし!!」
と、そこまで言ってしまってから、マルセラはハッと自分の口を押さえた。
コイユールは固唾を呑んだ。
マルセラは基本的に人を差別しないし、身分がどうのとか言う人間ではないことを知っていた。
そもそも女性特有のあのドロドロした部分を嫌い、竹を割ったような性格のマルセラは、誰に対しても意地悪なことを言ったりすることのないのも知っていた。
そんなマルセラの言葉だけに、妙にコイユールの胸に突き刺さってきた。
そして、実際、マルセラの言う通りのようにも思えてくる。
「それじゃ、なんて呼べばいいのかしら…。」
コイユールは自分の心にも問いかけるように呟いた。
「そんなの、『アンドレス様』でいいに決まってるじゃないさ!」
相変わらず、へんにムキになった口調でマルセラが言い放つ。
「アンドレス…さま…?」
と、小さく言ってみてから、「う~ん…。」と、今度はコイユールが複雑な顔をした。
「やっぱり、なんだか違和感が…。」
コイユールが呟くと、マルセラが怖い顔をして、さらにコイユールに詰め寄ってくる。
「あ、それって、すご~っく失礼じゃないの?!
じゃあ、なにさ、トゥパク・アマル様のことも、あんた、呼び捨てにできるの?」
「ま、まさか!!」
コイユールが目をみはって否定するのを、マルセラは一本取ったとばかりに強気で言った。
「ほうらね!
あんたがアンドレス様を呼び捨てにするのは、トゥパク・アマル様を呼び捨てにするのと殆どおんなじくらい、だいそれたことなんだから!!」
マルセラの剣幕に押されつつも、コイユールは、はたと動きを止めてふと何かを思いついたように上目づかいで天井を見た。
それを言ったら、平民のコイユールの立場からは、貴族のマルセラも本来『マルセラ様』となるのだ。
コイユールはマルセラに視線を戻して、「マルセラ様…?」と、その響きを確かめるように呟いてから、再び複雑な顔をした。
マルセラは耳を赤くして、「あたしのことはいいの!やめてよ~、気持ち悪い!」と、コイユールの呼びかけを振り払うようにぶんぶんと首を振った。
「でも、それだと、なんか矛盾が…。」
「とにかく!
アンドレス様は、アンドレス様なのっ!!」
そのマルセラの剣幕は、トゥパク・アマルらのいる広間の方までしっかりと響いていた。
マルセラの叔父でもあるビルカパサは、苦虫を噛み潰したような顔になった。
トゥパク・アマルらも、まじめな話をふと止めて、あっけにとられた様子で炊事場の方向に顔を向けた。
「なにやら、もめているようだが…。」
トゥパク・アマルの言葉に、「すいません、私の姪っ子が…。」とビルカパサは眉間に皺を寄せて、立ち上がりかけた。
それを制するように、アンドレスが立ち上がった。
「ビルカパサ殿、どうぞそのまま。」
ビルカパサに笑顔を返して、アンドレスは炊事場の方に向かった。
炊事場では、インカ族の護衛官や召使いたちが仕事の手を止めて唖然と見守る中、マルセラがコイユールにいっそう詰め寄りながら、最後の確認をしているところだった。
マルセラはコイユールの目をまっすぐ見た。
「わかった?
今日から、アンドレス様は『アンドレス様』だからね。」
コイユールが改めて見つめ返すと、マルセラの瞳は意外なほど、真剣だった。
コイユールが返答に窮していると、突然、炊事場にいた護衛官や召使いの者たちの間に張り詰めた空気が流れた。
そして、皆、恭しく、炊事場の入り口の方に礼を払った。
そんな様子には全く気づかぬまま、マルセラは最後通告のように、念を押す。
「わかった?!」
「マルセラ、どうしてそんなにムキになるの?」
マルセラの真剣さに気づいたコイユールは、その真意を確かめるように穏やかに言った。
「それは…。」と、マルセラは一瞬頬を染めたが、ハッと我に返ったように「そんなこと、ただ、おかしいから直した方がいいって言ってるだけだってば!」と、内心を悟られまいとするかのように早口で言い返した。
「マルセラ、君も俺のことは、『アンドレス』と呼び捨てでかまわないんだよ。」
ふいに背後からアンドレスの声がした。
コイユールとマルセラは、突然のアンドレスの登場に身を硬くした。
「アンドレス様っっ…!!」
マルセラはギョッと目を見張って、コイユールの影に隠れるように身を寄せた。
全く、普段の勇猛果敢なマルセラからは考えられない行動だった。
「アンドレス…!」
コイユールもふいをつかれて、目を見開いた。
そして、はっと口に手を当てて、(『アンドレス様』だったっけ…。)と、マルセラの方に目配せした。
しかし、マルセラはコイユールに対応する余裕など全くなくしたまま、完全に固まっている。
そんな二人に、あの懐かしい優しい笑顔で、アンドレスは穏やかに言った。
「コイユールは今まで通りでいいし、マルセラも、『アンドレス』でいいんだよ。」
マルセラは首から上を真っ赤にして、言葉を失っていた。
そんなマルセラの様子を見て、コイユールはやっと合点がいった。
マルセラはアンドレスに好意をもっているのかもしれない、多分、特別な感情を…。
それで、あんなにムキになっていたのだわ。
そんなマルセラの様子を何だか微笑ましく感じながら、コイユールはやっと間近で出会えたアンドレスを改めて見上げた。
数年前は殆ど変わらなかった背丈も、今はすっかり差がついている。
コイユールの目から見ても、アンドレスはとても素敵に成長していた。
そして、また、アンドレスも、いつのまにか女性らしくなってきたコイユールを間近にして、一瞬、微かに視線をそらした。
神学校の卒業年度が次第に迫り、いよいよ学業も大詰めになってきたアンドレスは、この1年間、寄宿舎で過ごしたまま、この故郷に戻ってくることができなかった。
ほぼ1年ぶりの再会に、アンドレスもコイユールも、密かに胸を躍らせていた。
「コイユール、マルセラ、二人とも元気そうでよかった。」
「アンドレスも。」
アンドレスとコイユールは、しっかりとその瞳で頷き合った。
本当に、この時代、何が起こってもおかしくなかった。
生きて再び会えたこと、その喜び、そのかけがえのなさ…――、それは決して大袈裟なものではなかったのだ。
それから、コイユールは自分の後ろに身を隠すようにしているマルセラの方を見た。
「アンドレスがいない間、マルセラがとっても良くしてくれたの。
マルセラはいろんなことを教えてくれたわ。
あ!
ほら、アンドレスが以前くれたスペイン語の教科書も、マルセラが解説してくれたし、他にもいろいろ…!
それで、今は、私もスペイン語、少しわかるようになってきたのよ。」
アンドレスとマルセラの方を交互に見ながら夢中で説明するコイユールに、優しい眼差しを向けて、「それは、すごい!」とアンドレスは深く頷いた。
そして、アンドレスは、マルセラにも「どうもありがとう。」と微笑みかけた。
マルセラは火が上がるほど顔を赤らめて、「いえいえ、そんなこと…!」といったようなことを呟きながら、まだ顔を上げられぬまま首を振っていた。
コイユールはそんなマルセラの様子を微笑ましく思いながら、自分の心の奥にも、何か似たような不思議な、どこか切ない感情が存在するのを微かに感じた。
それは、一体、何だろう…。
まだ、この時のコイユールには、それが何かは全くわからなかったのだけれど…。

その数日後、コイユールは、再びアンドレスの館近くの集落の中心部まででかけていた。
その日、コイユールはいつものように自然療法の施療を求められて、この近辺の住人宅まで出向いていたのだった。
教会の傍のアンドレスの館の前を通りかかると、そろそろ暮れかけの夕闇の中に、ニ階のアンドレスの部屋の窓から柔らかな灯りがこぼれている。
まだ休暇中のアンドレスが、自室にいるのだろうか。
(何をしているのかしら…。)
窓を見上げてそんなことを思いながら、しかし、今日はそのまま館の前を通り過ぎ、コイユールは家路を急いだ。
間もなく夜の帳が下りてくる。
彼女の住む貧しい農民たちの住まいは、ここからかなり先の辺鄙な地にある。
ますます年老いた祖母を、長時間一人で残しておくことが心配だった。
コイユールは半ば駆け足で、道を急いだ。
ちょうど露店の並ぶ繁華街も終わりにさしかかった辺りだった。
鮮やかな刺繍の布が並べられた露店の陰から、ふいに小さな男の子が飛び出してきた。
コイユールが駆けてきたのとちょうど鉢合わせになってしまい、男の子はステンと前に転んでしまった。
コイユールが「あっ!」と思った時には、既に子どもは地面に腹ばいに倒れていた。
まだ4~5歳の、とても幼い少年である。
コイユールは慌ててその場に跪いた。
「ごめんね!
私が…。」
コイユールが助け起こそうとすると、少年はゆっくりと自分で身を起こした。
少年は顔を下向き加減にしたまま、口をギュッと結んで、健気にも泣くのをこらえている。
見ると少年の膝のあたりがすりむけて、血が滲んでいる。
相当痛みがあるに違いないのに、その幼い子どもは黙って痛みを我慢していた。
コイユールは息を呑んで、切ない思いと申し訳なさから、改めて謝罪の目で少年を見た。
褐色の肌をしたインカ族のその少年は、あどけないながらも気品ある風貌をしており、身なりもかなり高貴な衣を着せられている。
どこかの貴族の子どもかしら…。
少女のようなサラサラの綺麗な黒髪と澄んだ黒い瞳、そして、年齢に似合わぬ、すっと切れ長の目元が印象的だった。
(この男の子、どこかで見たことがあるような…。)
ふとそんな気がしたが、それよりも、とにかく手当てをしないといけない。
コイユールは急いで懐からハンカチを取り出して、少年に「ちょっとだけ、ね、触ってもいい?」と、少年の目の高さから優しく問いかけた。
少年は泣くのをこらえてはいるものの、涙を潤ませた瞳で、少し驚いたようにコイユールを見た。
が、コイユールの眼差しに安堵したのか、小さくコクンと頷いた。
コイユールは再び少年に微笑みかけて、そっと傷口付近の血を拭きとった。
こういう時は薬草などを持っていると役立つのだが、普段の施術時も薬を使わないコイユールは持ち合わせの薬草など持ってはいなかった。
コイユールは心配そうに少年を見た。
「痛い…よね?」
少年はまだびっくりしたような表情をしたまま、無言で、まっすぐコイユールの方を見ている。
「がまんできて、えらいね。
強いんだね。」
コイユールが笑いかけると、少年の瞳にはかえって涙がふくれあがってきた。
少年が痛みを相当我慢していると見て取ると、コイユールは少年の傷口の血が止まってきたのを確認して、それから、再び少年に笑顔を向けた。
「痛いのがとれる魔法をかけてあげてもいい?」
「まほう?」
少年がはじめて口をきいた。
まだ幼い舌足らずのあどけない話し方だったが、少年の瞳には好奇心の色が浮び上がった。
そして、「うん、やって!」と明るい笑顔を見せた。
コイユールは少年に笑顔が戻ったことに安堵しながら、そして、感心して言った。
「まほうって、でも、それって、ちょっとも怖くないの?」
「僕、怖いものなんて、ないもの!」
少年は輝くような自信のある瞳で、きっぱりと言った。
コイユールはそんな少年の瞳に、やはりどこかで見たような、と感じながらも思い出すことができなかった。
「そっかあ。
よおし、じゃあ、やってみよう。」
そう笑顔を返して、コイユールは人通りの邪魔にならぬように、道の端の柔らかい草の上に少年と腰を下ろした。
「それじゃあ…。」と、コイユールは少年の瞳を優しく覗きこんだ。
「これから私がこの手を君の傷口の近くに置いて、痛いのがなくなる魔法をかけるから、君はただ黙って目をつぶっていてね。」
少年はキラキラと瞳を輝かせて、「うん!」と元気よく返事をした。
少年の物怖じしない様子にまた感心しながら、「じゃ、目を閉じてね。」と促し、コイユールはそっと少年の傷口の近くに手を添えた。
コイユールも静かに瞳を閉じた。
そして、意識を少年の膝のあたりに集中する。
が、その時だった。
「おまえ、何をしている!!」
いきなり、険しい、太い、咎めるような男の声がした。
コイユールはハッと目を開いた。
目の前に、スペイン人の役人とおぼしき男たちが三人ほど、険しい表情で立ちはだかっている。
コイユールは、瞬時には、何が起こったのかわからなかった。
が、彼女はすかさず少年を背後にかくまうようにして、身構えた。
スペイン人の役人風の男たちは、コイユールたちの方にじわじわと近寄ってくる。
きつい酒の臭いがした。
コイユールは本能的に、強い危険を感じた。
彼女は少年をしっかりと背後にかくまいながら、息を殺して相手の出方に備えた。
男の一人が一歩踏み出して、コイユールを上から下まで眺めてから、居丈高な調子で言う。
「話は聞かせてもらった。
おまえだな。
あの、怪しげな治療とやらをやっている娘は。」
コイユールは、息を呑んだ。
まずいところを見られてしまった、と心の中で悔やむ。
この界隈でも、キリスト教以外の教えに由来する土着の思想や自然療法などに対する取り締まりや弾圧は、年々、厳しくなってきていたのだった。
コイユールの噂が、この辺りのスペイン人の役人たちの耳に入っていても不思議はなかった。
スペイン人たちに取り囲まれているコイユールたちを、露店の通りにいるインカ族の者たちは息を詰めて遠巻きにしていたが、スペイン人の役人に物申せる勇気ある者は誰もいなかった。
コイユールは内心動揺しながらも、改めて役人たちを観察した。
役人は3人共かなり酒を飲んでいるようで、目つきがすわり、しかも、酒のためか絡みつくような視線を向けてくる。
へたに刺激をしてはまずい、と思われた。
まずは、少年の身を安全にこの場から解放してあげねばならなかった。
コイユールは動揺を隠しながら、静かに役人たちに言った。
「わかりました。
お話はゆっくり、聞きます。
でも、この子は関係ありませんので、この子だけは帰してあげてください。」
コイユールは不安な面持ちで、背後にかくまっている少年をそっと見た。
なんと、そのまだ幼い少年は、きっ、とした険しい目で、役人たちを睨むようにまっすぐ見据えていたのだった。
役人たちは少年の眼差しに気付くと、鬼のように目を吊り上げて少年の方にズカズカと迫ってきた。
「なんだ、その生意気な目は!!」
役人の一人が、間髪入れずに、その頑強な靴を勢いつけて蹴り上げてきた。
「危ない!!」
瞬間的に、コイユールは少年の前に身を伏せる。
役人の蹴りが、コイユールの顔面にざっくりと当たった。
左目の上あたりの額が切れて、真紅の血が滴り落ちる。
コイユールは少年を胸に抱くようにして、役人たちを見た。
意図せずとも、その目は険しくなっていた。
「何をするのです!
まだ、こんなに幼い子どもではありませんか!」
思わず喰ってかかったコイユールに、役人たちも気色ばんで迫ってきた。
そして、コイユールの左手首を荒々しく掴むと脅すように言った。
「お前、逮捕になっても、いいんだな?」
役人の目が、ギラギラと憎悪と汚濁に満ちた光を放つ。
その時だった。
役人たちの背後から鋭い声が聞こえた。
「おやめなさい!」
それは、凛と響く女性の声だった。
役人たちはコイユールに掴みかかったまま、背後を振り返った。
コイユールも、ハッとして前方を見る。
そこには、一人のインカ族の女性が、役人たちを射竦めるような厳しい眼差しで立っていた。
コイユールは目を見張った。

その険しい表情にもかかわらず、まるで絵の中から抜け出てきたような、本当に、この世のものとは思えぬほどの麗しい女性がそこにいたのだ。
男性を凌ぐほどのすらりとした長身に、ほっそりとした、それでいて、しなやかな手足。
首は見たこともないほど細く、その上には、とうていインカ族とは思えぬ洗練された美しい顔があった。
高貴で繊細な目鼻立ち、しかし、その眼差しには毅然とした強さと、凛々しさが漲っていた。
いかなる悪行も許さない、そんな強い正義と信念に貫かれた瞳の色である。
とても女性的でありながら、一方で、非常に男性的な印象をも与える。
髪は流れるように長い黒髪で、それを背後に垂らし、一つにまとめて結んでいる。
その耳元には、インカ風の華やかな黄金のイヤリングが輝いていた。
そして、質の良い布地で仕立てられた、ただし、決して華美ではない西洋風の上品なロングドレスを纏っている。
年の頃は、20代半ばくらいだろうか。
褐色の肌も青銅色に輝くようで、そのあまりに美しくも凛々しい姿は、まるで戦の女神のブロンズ像がこの世に甦ったかのようだった。
さすがのスペイン人の役人たちも、そのインカ族の女性の気高い美しさに目を奪われて、暫し言葉もなく息を呑んでいた。
その女性は、まるで見下ろすようにして、役人たちに険しく厳しい声音で言った。
「その娘さんをお放しなさい。」
一つ一つの言葉に、力と魂が宿っているように、きっぱりとよく響く。
役人たちは、かなり気圧された様子になっていた。
しかし、簡単に引き下がるわけにはいかぬとばかり、それでも相当頑張って去勢を張っているというのがわかったが、なんとか言い返してきた。
「なんだ、お前は…!!
余計な口出しをすると、お前も一緒にしょっぴくぞ!」
しかし、その声には既に自信のなさが滲みはじめている。
美しい女性は、目を細めながら冷ややかにその役人を一瞥した。
「どのような事情があれ、そのように若い娘を傷つけ、幼い子どもを脅すなど、許されることではない。
ましてや、その娘のことも、何か証拠がおありなのですか?
いい加減なことで逮捕などしようものなら、あなた方の罪も問われますよ。」
彼女は自国語であるケチュア語を愛しむように、毅然と澱みないケチュア語で語ると、コイユールの手首を掴んでいる役人の方に近づいてきた。
何気ない動きの一つ一つさえ、優美である。
そして、「お放しなさい!」と、最後通告を突きつけるかのごとくの気迫で、氷のように役人を睨みつけた。
役人の手が、力を吸い取られたかのように、コイユールの手首からはずれる。
役人は怯えを必死で隠すように、そのインカ族の美女を憎々し気に見やった。
「おまえ、何者だ…。」
女性は、まるでナイフの刃のような冷ややかな眼差しで役人を見下ろしたまま言った。
「私は、ミカエラ・バスティーダス。
この地のカシーケ(領主)、トゥパク・アマルの妻です。」
役人たちは、さっと顔を青くした。
そして、そそくさとその場を離れながら、それでも「次は、これですむと思うなよ!」と捨てゼリフを吐き、急ぎ足で消えていった。
驚いたのはスペイン人の役人だけではなかった。
コイユールもその場に固まっていた。
(トゥパク・アマル様の、奥様…?!)
一方、コイユールの背後から険しい眼差しで事の流れを見守っていた少年は、役人が立ち去るとすぐさま彼女の背後から飛び出し、その美しい女性の方に走り寄った。
「母上!!」
トゥパク・アマルの妻と名乗ったその女性、ミカエラは、少年をしっかりと胸に抱いた。
「フェルナンド、心配しましたよ。
お買い物の途中で勝手に離れてはいけないと、あれほど言っておいたでしょう。」
それは、息子の身を心から案じる優しい母親の声だった。
それから、茫然自失しているコイユールの方に向き、ミカエラは声の調子を和らげて話しかけた。
「大丈夫ですか?」
コイユールは、息を吸い込んでから、やっと頷いた。
「怪我をしていますよ。」
ミカエラは心配そうに、コイユールの額を見た。
コイユールの額からはまだ血が流れ続けており、頬を伝って肩のあたりに血の雫が滴っている。
コイユールは慌ててハンカチで額を押さえた。
そして、深く頭を下げた。
「助けてくださって、どうもありがとうございました。」
本当は、少年の怪我のことなど説明しなければならぬことがいろいろあったが、何かひどく動揺していて、言葉にすることができなかった。
そんなコイユールをミカエラは静かな眼差しで見つめ、それから、涼やかに微笑みながら諭すように言った。
「お気をつけなさい。
どんな無法なこともやりかねない者たちだから。」
そして、その美しい女性は少年の手をしっかりと握り、露店への道を戻っていった。
◆◇◆◇ここまでお読みくださり、誠にありがとうございました。続きは、フリーページ 第三話 反乱前夜(4) をご覧ください。◆◇◆◇
© Rakuten Group, Inc.