2018年11月の記事
全13件 (13件中 1-13件目)
1
-

Daniil Trifonov:Destination Rachmaninov - Departure
トリフォノフの新譜はラフマニノフのピアノ協奏曲全曲録音シリーズの第一弾。2番と4番のピアノ協奏曲とラフマニノフが編曲したバッハのパルティータ第3番からの3曲。共演はネゼーセガン指揮のフィラデルフィア管弦楽団。このコンビとは以前の「パガニーニ狂詩曲」でも共演していた。どの曲も極めて明晰な演奏で、ラフマニノフらしいロシアの憂鬱を感じさせるロマン的な演奏ではない。清冽な叙情とでもいうべき表現だろうか。ところが、随所で思い切ったアコーギクが加えられていて、どきっとさせられる。まあ、いやらしい表現ではないので、印象が悪くなることはないが、突然ですがという感じは否めない。フィラデルフィア管の弦がとても美しい。オーケストレーションのせいかもしれないが、管はごった煮的なサウンドで、いまいちはっきりしない。(特に4番)昔の傾向が未だに残っていて、古臭いと感じられる。4番はライブのためか、カロリーがかなり高い演奏で、最後に盛大な拍手が入っている。バッハは初めて聞いたが、音数が少なく、少し拍子抜けする。ジャケ写は髭ズラのトリフォノフが電車のコンパートメント?の3人掛けくらいのソファーに一人で座って、窓のところについている小さなテーブルで指を動かしているというもの。写真がシンメトリーになっていて窓から外の風景が見える。コンパートメントはシックで内装が豪華。さながら映画の一場面を見ているようだ。ブックレットにも鉄道で旅をしているという設定?のトリフォノフの写真や古ぼけた駅の景色が載っていて、詩的で実にいい感じに仕上がっている。ラフマニノフのアメリカでの演奏旅行の情景を想定したものだろうか。当ブログはブックレットなどまともに読まないのだが、こういう丁寧な仕事を見つけると嬉しくなる。ポピュラー系のアルバムに多く見られる、歌詞や曲目の解説もないような雑なつくりとは大違いだ。なお、トリフォノフはミュージカル・アメリカ(1898-)という音楽の情報誌みたいな雑誌の今年の「アーティスト・オブ・ザ・イヤー」(1960-)に選出されている。日本ではあまり知られていないが、過去にバーンスタイン、カラヤン等大物の音楽家が受賞している。因みに小沢は1998年で、直近ではユジャ・ワン、アンドリス・ネルソンスが受賞している。どういう基準での選考か不明だが、権威のある賞なのだろうから、トリフォノフも超一流の音楽家の一人として認められたのだろう。Daniil Trifonov:Destination Rachmaninov - Departure(DGG 0289 483 5335 4)Sergey Vasil'yevich Rachmaninov (1873 - 1943)1.Piano Concerto No. 2 in C Minor, Op. 18Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)4.Partita for Violin Solo No. 3 in E Major, BWV 1006Arr. Piano by RachmaninovSergey Vasil'yevich Rachmaninov (1873 - 1943)7.Piano Concerto No. 4 in G Minor, Op. 40Daniil TrifonovThe Philadelphia OrchestraYannick Nézet-SéguinRecorded Philadelphia,Kimmel Center,Veriozon Hall,10/2015(Concerto No.4,live),4/2018(Concerto No.2,Partita)
2018年11月29日
コメント(0)
-

北とぴあ国際音楽祭20181 モンテヴェルディ:ウリッセの帰還
数か月前にふとバロックのオペラを見たことがないことに気が付いた。バロック・オペラといえば日本でも恒常的に上演しているところを思い出した。毎年行われている「北とぴあ国際音楽祭」だ。調べてみると今年はモンテヴェルディの「ウリッセの帰還」(1639-1640)を上演するという。モンテヴェルディのオペラは「オルフェオ」を何回か聴いた程度で、あまり馴染みのある音楽とは言えないが、「オルフェオ」の輝かしさには、とても惹きつけられるものがあった。「ウリッセの帰還」は、クリスティーのDVD(旧盤)のリッピング音源は聞いていたものの、DVDを観たことはなかった。それも、いまいち身についていない状態だった。なので、準備としてこの音源を何回も聴いていたのだが、頼りのオペラ対訳プロジェクトでも、まだ取り上げられていなくて、結局自分の理解の状態は、あまり変わらなかった。そういう状態で、観に行ったのだが、対訳が付いていて、とても内容が理解できた。最近のオペラ上映は両袖にセリフや歌詞の訳が表示されるので、とても分かりやすくなっている。昔だったら、プログラムに対訳が付いているのはいいほうで、殆どの上演では歌詞もないような状態で、それを考えるといい時代になったということを感じる。歌詞が付いていても、それを観ながら舞台も観るというのはなかなか難しい。スコアを観ながら演奏を聴くというのも、肝心の演奏を聴くことが、疎かになりがちで、何のためにコンサートに行っているのかわからなくなる。最初から、無駄話になってしまったが、今回の上演は、主要なキャストをイタリア人が歌い、そのほかを日本人が固めるという形。バックは寺神戸亮の指揮振りの北とぴあの座付きオケ「レ・ボレアード」演出は演出家の小野寺修二で、マイムの「動きをベースに取り入れた演出で注目を集めているという。ウリッセの帰還では予算の関係でセミ・オペラ形式。小道具は椅子が数脚、テーブルも2台くらい。あとは、いろいろな用途に使われる衝立と台、それに銀の弓とウリッセが載ってきた船の玩具に、バイクのような玩具の二輪車(実際に二人乗りで走っていた)程度。背景もなしで、ホールの反響版むき出しだったが、ハンデを逆手にとって素晴らしい舞台を見ることが出来た。面白かったのは、パネーロペを賭けて、ウリッセの銀の弓を誰が射ることが出来るかを試す場面。弓に直接擦れるのではなく、舞台にしつらえたスポット照明で後ろの後方の反響版に影絵を写すというもの。この利点は弓を動かしたり伸び縮みが自由にできること。実際に弓を弾くのではなかなか困難なことが、簡単にできてしまうのは、今回がオリジナルかどうかは不明ながら、なかなか秀逸な方法だ。それから、灰色の衝立がゲートになったり、食器棚になったりと、演劇を知らない当ブログとしてはとても興味深く観た。また、この演出の大きな特徴にパフォーマーという物語とは直接関係のない男女2名(辻田暁、遠山悠介)が加わっていること。モダンバレエ的な踊りや黒子のように道具を設営したり、渡したりする役目を担当していて、とても面白い効果を出していた。肝心の演奏だが、歌手はバラツキが少なく、寺神戸の引き締まったテンポと生き生きとした表情で、とても楽しめた。400年も前のオペラが、これほど面白いとは思わなかった。すべてはモンテヴェルディの凄さなのだろう。主人公のウリッセ(ユリシーズ)を歌ったエミリアーノ・ゴンザレス=トロ(tn)はドミンゴを思い出させるような輝かしい声と、劇的な歌唱でとても印象的だった。ミネルヴァと運命を歌ったクリスティーナ・ファネリは顔がチェチーリア・バルトリに似ていて美しい声だった。メラント役のマルチド・エティエンヌは歌もさることながら、清楚な容姿が大変美しかった。ウリッセの子供のテレーマコ(ケヴィン・スケルトン(tn))は若々しい声と、きびきびとしたパフォーマンスを披露していた。大食漢のイーロを演じたのはフルヴィオ・ベッティーニ。寺神戸に食い物を無心するシーンやコミカル演技で会場の笑いを誘っていた。日本人歌手も外国人歌手に遜色ない歌いっぷりだった。ウリッセの妻ペネーロペ役の湯川亜矢子は主役級の役柄だったが、他の主要キャストに伍して大変立派な歌唱だった。最初外国人かと思ったほどの姿や、ペネーロペの頑な心を表す立ち振る舞いが物語にはまっていた。第3幕の後半で、聞かれる4人の男性歌手による海の合唱も素晴らしかった。唯一違和感があったのは、ペネーロペに求婚する3人の王の一人ピザンドロ役の中島俊晴。カウンターテナーなのだが、通常カウンターテナーかテナーがキャスティングされるようなので、彼の責任ではないだろう。オケは珍しい楽器がいくつか並んでいた。寺神戸の解説によると、ハルモニウムのような音を出すのがレガール、リュートのお化けみたいなテオルボ、ツィンク(コルネット)同じ名前だが、現在のコルネットとは別な楽器。金管に分類される(マウスピースで吹く)が木製のようで、複数の穴を開閉することで音高を変える。演奏は大変難しいとのこと。鄙びたようなトランペットの音で、音量は小さい。本番では、まっすぐなものと曲がったものが使われていた。とうことで、生モンテヴェルディ初体験は、予想外の素晴らしい体験だった。来年はヘンデルの「リナルド」を上演する予定なので、また観に来たい。モンテヴェルディ:ウリッセの帰還エミリアーノ・ゴンザレス=トロ(tn)湯川亜矢子(s)ケヴィン・スケルトン(tn)クリスティーナ・ファネリ(tn)マルチド・エティエンヌ(s)ケヴィン・スケルトン(tn)フルヴィオ・ベッティーニ(br)レ・ボレアード(管弦楽)指揮、ヴァイオリン:寺神戸亮演出:小野寺修二2018年11月25日 北とぴあさくらホール 2階D列43番で鑑賞
2018年11月26日
コメント(0)
-

盛岡吹奏楽団 第50回定期演奏会
盛岡吹奏楽団(1968-)が50回目の定期演奏会を迎えたということで、久しぶりに聞きに行った。出来たのが当ブログが中学生のころで、当時一般の吹奏楽団といえば北上吹奏楽団と盛吹しかなかったと思う。以来紆余曲折があったと思うが、50年続けるのは並大抵のことではなかったと思う。熱意だけでは続けられるわけはなく、その間の維持と演奏力の向上には敬意を表したい。最近は一時の低迷を脱して、東北大会の常連になっていることはご承知の通りだ。音楽監督に建部氏を迎えたことが大きかったと思う。他人事ながら建部氏も還暦を過ぎているので、後任をそろそろ考える時期に来ているのではないだろうか。アマチュアの場合には指揮者やトレーナーいかんで大きく変わる。いい例が今年コンクールの全国大会で初の金賞を受賞したの上野中学校だろう。岩手県では抜きんでたレベルの学校だが、どういう経過であれほどまでになったのか、知りたいものだ。閑話休題会場は9分程度の入りで盛況だった。いつもだと2部構成だが、今回は記念の演奏会で1部オリジナル、2部協奏曲、3部ポピュラーという構成。第1部の注目は盛吹が音楽監督の建部氏に委嘱した「Fragments for Wind Orchestra」。てっきりこの曲でコンクールに出場したものと思っていたが、調べたら酒井格の「 半音階的狂詩曲」という曲だった。今回の断章は大曲なので、コンクールの曲と並行してこういう曲を仕上げるのは大変だったと思う。プログラムによると、テーマは東日本大震災で、同じテーマで書いた「故郷へ~その若葉のころ」(2011)が、その時の体験を通して人と人のお互いの気持ちをやさしさで包まれるようにと願った曲であるのに対し、今回の曲は直接的な記憶ではなく「人の力の記憶」として表した作品だそうだ。全体が4楽章に分かれていて、力強い楽章(2,4)、悲しみが漂う抒情的な楽章(1,3)からなる。全体的には深い悲しみが感じられるし、力強いマーチ風の部分にもそれは当てはまる。繰り返し聞いてみたい音楽だ。団内指揮者によるスパークとバーンズは出来は普通だったが、この曲は見違えるような出来だった。オーボエやアルトサックスの美しい音色も印象に残った。第2部は須川展也を迎えてのマッキーの「ソプラノサックスのための協奏曲」初めて聞く曲だったが、曲の面白さと須川氏の超絶技巧がマッチして、大変興味深く聴いた。須川氏による曲目紹介があり、♩=180と急速調の第5楽章フィナーレはソロの休みがなく、8分音符の間にブレスをしなければならないほどで、酸欠状態になる曲のようだ。score曲は5楽章からなり、第2楽章がフェルト、第3楽章がメタル、第4楽章がウッドとサックスの部品の素材を楽章が名前についていた。特殊奏法を交えた演奏が素晴らしく、特に第4楽章「Wood」のエキゾチズムに溢れた音楽が楽しかった。第4楽章のマリンバが一部ずれていたように思えたのは、気のせいだったろうか。事前のアナウンスで三時間のコンサートという話があったので、ひいてしまい、第3部は聞かないで帰宅してしまったが、1,2部だけで十分満足した演奏会だった。盛岡吹奏楽団 第50回定期演奏会第一部1.Sparke:Jublee Overture(1984)2.Burns:Symphonic Overture(1990)3.Takebe:Fragments for Wind Orchestra(2018)第二部John Mackey:Concerto for Soprano Sax and Wind Ensemble(2007)アンコール真島俊夫:アルト・サキソフォーンとバンドの為の協奏曲「バーズ」から第2楽章「シーガル」第3部杜色に染まった大地からの音像スパイラル1.スカイハイ2.酒とバラの日々3.グラナダ4.追憶のテーマ5.アメリカン・グラフィティⅫ須川展也(ss)建部知弘、皆川洋祐(指揮)盛岡吹奏楽団2018年11月23日盛岡市民文化ホール 大ホール2階下手で鑑賞
2018年11月23日
コメント(0)
-

三浦一馬キンテート2018
このコンサートの情報を知ったのは、それほど前のことではなかったが、別の予定が入っていたため、諦めていた。ところが、日時が変更になったことを知り、速攻で予約した。出演者の都合ということだが、珍しいことだ。予想では、日時が変更された影響で入りは悪くなると思っていたが、ほぼ満席だったのは、御同慶の至り。この方は名前は知っていたが、演奏を聴くのは初めて。今回は最新アルバムの「ピアソラ」発売記念のツアーのコンサート。キャラホールの自主事業なので¥3000と低廉な料金で聞けるのもいい。もし、これが¥5000ほどだと、まず聴きに行かないが、聴きに行ってよかったコンサートだった。新しいアルバムはピアソラのみなのだが、コンサートは前半がガーシュイン、後半がピアソラという構成。そのためか、最後の5人目が、前半は石川智のドラムス、後半は大坪純平のエレキギターというメンバーだった。始まってすぐ上手のドラムスの音が小さいことに気がついた。当ブログの座席が下手の前の方で、PAの近くだったこともあるのか、とてもバランスが悪い。アコーディオン以外は、全体的にオフ・マイクの感じで、よくいえばソフト、悪くいえば弱弱しい感じがする。ヴァイオリンを見たら、マイクが結構上のほうにあって、わざわざ近づいて演奏していたのが、何とも気の毒。ピンマイクを使うことは考えなかったのだろうか。まあ、全体のサウンドがクラシックに近いミキシングなので、敢えてそのようにしたのかもしれないが。。。そのため、後半のピアソラは、こちらの期待している攻撃的な演奏が聞けなかった。バンドネオンだけは十分に聞こえていたのに、他の楽器が聞こえなかったのが物足りない。バンドネオン以外の楽器の音がもっと大きかったら印象は全く違っていたものになっていたに違いない。特に、エレキ・ギターの音が小さくて、最も期待していた「五重奏のためのコンチェルト」の最後の速弾きがほとんど聞こえないのはがっかりした。この曲のハイライトなのに台無しになってしまったのは何とも残念。念のため、新しいアルバムでの同曲を聴いたら、普通に聞こえる。CDだと他の曲も普通のバランスで、どうも今回のコンサートのPAのバランスがおかしかったとしか思えない。演奏者はバランスはよくわからないので、関係者が調整しなければならないのだが、そこはどうなっていたんだろうか。とてもいいコンサートだったのに、何とも残念だ。結局、音に関しての不満ばかりになってしまったが、肝心の演奏について一言。前半のガーシュインは「三浦一馬プレイズ・ガーシュウィン」からの選曲。訴える力が弱く、なんとも中途半端な出来に終わってしまった。基本的には作曲された当時の感じに編曲されていたが、PAのために、音楽が薄められていたと思う。良く知られる歌ばかりだが、歌の良さもあまり感じられない。「ラプソディー・イン・ブルー」も全曲ではなく、うまく縮められてはいたが、あまりいいとは思えなかった。最後の「ガール・クレージー」序曲は珍しい選曲で、CDで聴くと洗練されていて面白いのだが、生ではそこまで聴き手には届かなかった。CDで聴くと一種のサロン風音楽で活気のある演奏だったので、今回はPAの失敗が何とも痛い。後半のピアソラは次第に熱を帯びてきて、お目当ての「五重奏のためのコンチェルト」では素晴らしい盛り上がり方だった。コンサートの途中では珍しいことに、かなり長い時間拍手がやまなかった。大曲で技巧的にも難しいため、めったに演奏されることはない曲だが、聴衆がこの曲の良さを認めてくれたのだろう。三浦のバンドネオンはうまいが、時々陳腐なフレーズが出てくるのが気に入らない。また、少しクールで、当ブログとしてはもっと熱のある演奏をしてほしかった。ヴァイオリンの石田泰尚は神奈川フィルのソロ・コンサートマスター。短髪でやくざみたいな風貌や癖のあるステージマナーは良くも悪くも印象に残るキャラクターだ。黒眼鏡にすればジャーナリストの勝谷誠彦にそっくりだ。何故かメンバー紹介で、ただ一人声援があっちこっちから飛んでいた。音は美しいが線が細く、ポピュラー音楽に必要な踏み込みが足りない。ましてやピアソラなので、もっと濃厚なヴァイオリンを聴きたかった。ピアノの中島剛は線が細いが、ダイナミックな演奏でかなり頑張っていた。ベースの高橋洋太は堅実なサポートで、ところどころいい味出していた。ドラムスの石川智は控えめなプレーながら、いろいろな小物を使って面白い音を出していた。残念な結果になってしまったが、ほかの席で聴いた人にはどのように聞こえたのだろうか。ポテンシャルは大きそうなので、出来ればもっといい音で聞きたい。三浦はリーダーとして大変だろうが、できるだけ恒常的なメンバーで活動して、音楽を深めてもらいたい。新作がレコード芸術今月号の特選になっていたことも、彼らの励みになるだろう。ただ、取り上げられたのが器楽曲部門というのは解せない。三浦一馬キンテート20181.ス・ワンダフル2.魅惑のリズム3.誰か私を見守って4.サマータイム5.ラプソディー・イン・ブルー6.「ガール・クレイジー」序曲休憩1.オヴリヴィオン2.デリカシモ3.アディオス・ノニーノ4.ブエノスアイレスの冬5.五重奏のためのコンチェルト6.リベルタンゴ三浦一馬(Bandneon)石田泰尚(vn)高橋洋太(b)大坪順平(e.gt.)中島剛(p)石川智(ds)2018年11月20日盛岡市都南文化会館キャラホール 6列7番にて鑑賞
2018年11月21日
コメント(0)
-

Madeleine Peyroux:Anthem
マデリン・ペルーの新作「Anthem」を聴く。いつぞやのジャズオーディオ・ディスク大賞で「Half the Perfect World」が目にとまり、さかのぼってレンタルで聴いてきたのだが、肝心の「Half the Perfect World」のみレンタルできずにいた。ここまで何枚も聴いていたが、いまいちしっくりこない。彼女は「21世紀のビリー・ホリデイ」といわれているらしいが、舌足らずなところとかフレージング、ビブラートなどが似ていることは確かで、ビリー・ホリデーがあまり好きではない管理人がペルーの歌に入り込めないのも、それが理由かもしれない。ペルーのアルバムはニュー・オーリンズのような田舎っぽい雰囲気が売り?で、いまいち洗練されているとはいいがたい。新作が出たので、今度こそ何得できるかと思って初めてCDを購入。約2年ぶりとなる9作目とのこと。総勢18名という大所帯で、いろいろなタイプの音楽を聞かせてくれるが、総花的なところがいまいち。レナード・コーエン作のタイトル・チューンと最後のラリー・クラインの「Liberté」以外は演奏に参加したペルーを含むメンバー5人の共作。プロデュースはペルーとラリー・クライン。クラインは元妻がジョニ・ミチェル、現在の妻がルシアナ・ソウザだそうだ。何回か聴いているが、最初の数曲は従来の路線であまり気に入らない。ジャズ的に洗練させないことを、逆に売りにしているのかもしれない。ところがグレゴリア・マレのハーモニカをフィーチャーした、「Party Tyme」が始まったら、どうも雰囲気が違う。結構快適なノリで、コール&レスポンスを思い起こさせるバックコーラスも悪くない。同じくハーモニカーをフィーチャーした「On A Sunday Afternoon」もダンサブルでニューオーリンズ的な雰囲気満点の曲。ラテン・ナンバーの「Honey Party」はダンサブルでラテンの暑苦しいムードが濃厚なところに、舌足らずのヴォーカルが妙にはまっている。バックのジョン・スクラッパー・スナイダーのトランペットやアンディー・マーチンのトロンボーンのしつこいフレーズも、むさくるしい曲にぴったり。ジョン・スクラッパー・スナイダーは「The Ghosts Of Tomorrow」でも、ニューオーリンズ・スタイルのトランペットが、いい味出している。「We Might As Well Dance」はアーシーでダンサブルな曲だが、少し重い。最後は何故かフランス語の「Liberté」アコースティック・ギターとストリングスで、他の曲とはだいぶ趣が違うが、フランス語が重ったるい。最後の爽やかなコーラスで幾分救われる。ということで、納得できるナンバーに出会えたのは収穫だったが、違和感は残ったままだ。もう少し辛抱して聞け、ということかもしれない。Madeleine Peyroux:Anthem(Verb B0028679-02)1.On My Own2.Down On Me3.Party Tyme4.Anthem5.All My Heroes6.On A Sunday Afternoon7.The Brand New Deal8.Lullaby9.Honey Party10.The Ghosts Of Tomorrow11.We Might As Well Dance12.LibertéMadeleine Peyroux(vo)Recorded at Sunset Sound in Hollywood CA.
2018年11月18日
コメント(0)
-

Jurowski Berg:Wozzeck
この前ベルクのヴォツェックを取り上げたが、またまたヴォツェックのレビュー。今回は映像作品で、昨年のザルツブルグ音楽祭での上演。指揮はユロフスキーで演出は南アフリカのヨハネスブルグ出身のウイリアム・ケントリッジ(19550-)。彼は「動くドローイング」として有名な手書きアニメの作家で、映像の世界でも活躍しているようだ。日本でもよく知られた存在で個展も開かれているようだ。オペラに関しては魔笛(モーツァルト)、ウリッセの帰還(モンテヴェルディ)、鼻(ショスタコーヴィチ)などを手掛け、メトロポリタン歌劇場ではベルクの「ルル」の演出も行っている(2015)日本でも、先月魔笛の上演が行われたばかりだ。正規の舞台は世紀末のウイーンなのだが、今回の演出では第1次世界大戦後を舞台としている。舞台上に雑然と置かれた椅子や机、木製の階段などの小道具や装置、鉄条網、戦場を思わせる抽象的なモノクロの映像、キャストにはないガスマスクをつけた衛生兵みたいな服装の人たちなどで、なんともまがまがしい世界が描かれている。X線でとられた動く馬とか、何というかグロテスクな趣味がこれでもかと写されて、オペラの筋とどう関係しているのか理解に苦しむ。こういう印象を持たせたということは、このオペラの雰囲気に沿っているということも言えるわけだが、個人的にはあまり見たくない景色だった。また、マリーの子供が木でできた人形で、これまたガス・マスクをつけている。木馬が松葉杖になっているのも理解できない。キャストの動きも少なく、殺人の場面も暗示にとどまっている。酒場の場面でのダンスは、人形が踊っているような、ぎこちない踊りだ。最近はリアリティを重んじる演出も多いが、舞台はあくまでもきれいなものが多い。この演出は舞台のごちゃごちゃとした舞台と薄汚れたようなアニメ、暗い照明で、見ていてあまりいい気分にはなれない。ということで、演出に関しては全く賛同できなかった。音楽はユロフスキーの引き締まったテンポ、歌手陣の優れた歌唱で、とても楽しめた。ただ、間を多くとりすぎて、一部間延びしている場面(第3幕)があった。当初リッピングした音声を聴いていたのだが、映像とともに見るとまた別な感じがする。とにかく、映像のインパクトが強く、音楽がおろそかになる恐れが強いので、音楽だけを楽しみたい時には映像は見ないほうがいい。タイトルロールはなんと、マティアス・ゲルネ。彼がこの役をやるとは思っていなかったので、とても興味深く見た。いつもながらの立派な歌唱だが、声が太すぎるし、弱い人間としてのヴォツェック像の表現が少し不足していたような気がする。それに堂々とした太鼓腹は、とても食事にも事欠く貧しい兵士には見えない。マリーはAsmik Grigorian(1981-)はリトアニア共和国のヴィリニュス出身の歌手。リトアニアの国立歌劇場でデビューし現在はヨーロッパで広く活躍しているようだ。大変うまい歌手で、舞台のイメージも当方がイメージするマリー像に近い。このパッケージはDVDとBDが一緒に入っているという珍しいものだが、管理はしやすいだろう。メディアの製造費は大したことはないので、こちらのほうがいいのだろう。日本語字幕が付いていないのは、残念だった。PVPV インタビュー付きJurowski Berg:Wozzeck(HMD 9809053-54)Matthias Goerne, WozzeckJohn Daszak, TambourmagorMauro Peter, AndresGerhard Siegel, HauptmannJens Larsen, DoktorAsmik Grigorian, MarieVladimir JurowskiKonzertvereinigung Wiener StaatsopernchorSalzburger Festspiele und Theater KinderchorWiener PhilharmonikerRecorded in 1987 at the Vienna State Opera
2018年11月16日
コメント(0)
-
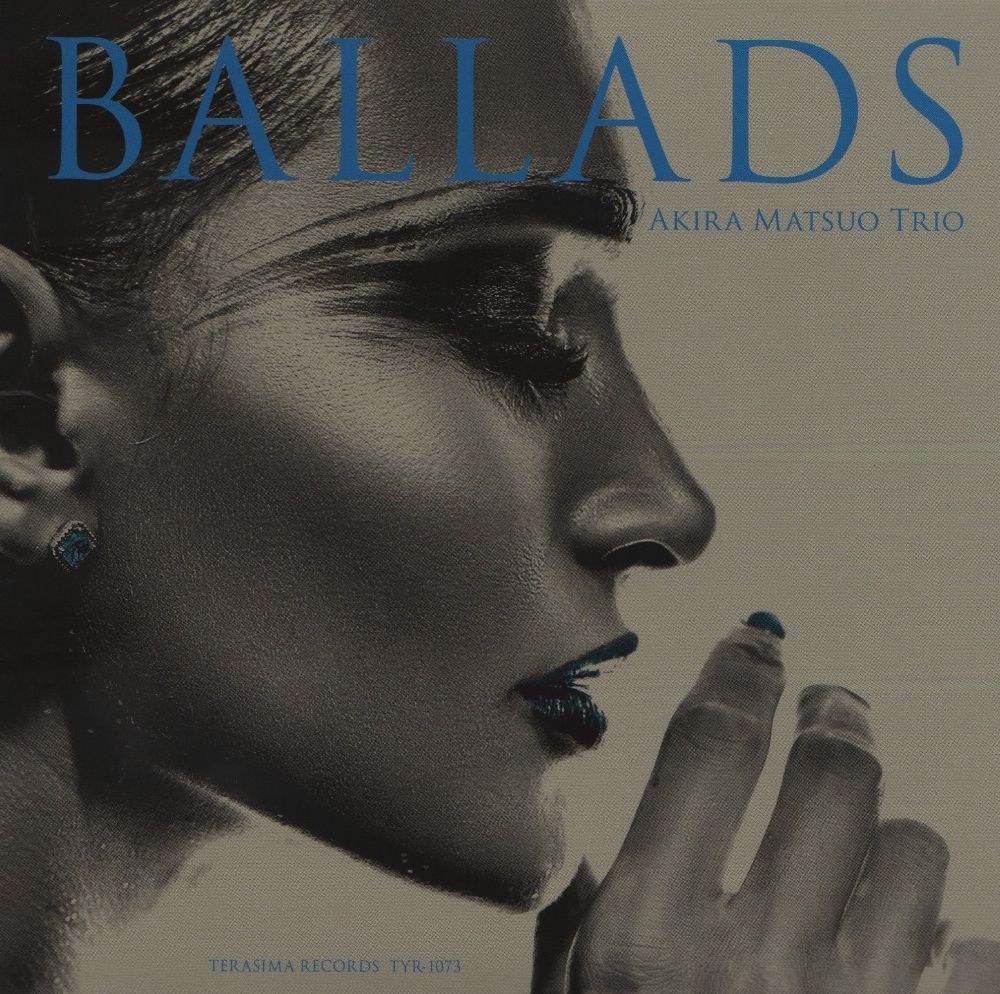
松尾明:Ballds
寺島レコードからイタリアのエンジニアで人気絶頂のステファーノ・アメリオがリマスタリングしたCDが何枚か出たので興味本位で松尾明トリオの「Balads」というCDを購入した。動機は、当盤が今年のジャズ・オーディオ・ディスク大賞インストゥルメンタル部門の銀賞を受賞していて、レンタルで聴けなかったことと、比較用にオリジナルが付いていることだった。因みにメインはオリジナルでリマスター版はボーナスCDという位置づけだった。オリジナルは佐藤宏章(LANDMARK STUDIO)によるレコーディングとマスタリングだった。オリジナルは至近距離で聴くピアノ・トリオよりも音像がでかく、いかに何でもやりすぎではないかと思った。オリジナルを聴いたアメリオは、コンプレッサーの使い過ぎだと話したとか。リマスター盤は奥行きが広がった感じで、押しつけ感も少なくなっている。オリジナルは、クラブで最前列で聴いている感じで、リマスターは小さめのホールの少し離れたところで聴いている感じだろうか。どちらも寺島氏の意向が働いていると思うので、エンジニアの好みだけではなく、寺島氏の音の好みの変化も加味された結果だと思う。厳密に聞いてはいないが、当方としてはリマスター盤のほうが好ましく感じる。ただ、これは聞き方にもより、真剣にジャズを聴く態勢の方はオリジナルのほうが向いている気がする。当方はオーディオマニアではないし、音は良いに越したことはないが、聴き疲れしない音が好ましいのだ。ブックレットによると、寺島氏が新宿のオーディオユニオンで行った聞き比べでは、6:4でオリジナルの評価が高かったそうだ。この時のお客は20人ほどのオーディオマニアで、「オリジナルがバランスがいい」、「ボーナスはオーディオ的」という意見が聞かれたそうだ。オーディオ的とは具体的には、ピアノ・トリオだと、ピアノが前で、ベースとドラムスが後ろに配置されているという構図(が見える)なのだそうだ。試しに、5.6MhzのDSFにアップコンバートして聴いてみた。いつもならSN比が改善されるのに気が付くのだが、この時はあまり違いは感じられなかったが、オリジナルの圧迫感は薄れていた。wav、24bit96kHzflacでも大きな違いは感じられなかった。オリジナルが優秀で、小手先のアップコンバートでは、改善の余地が少ないのかもしれない。このトリオの演奏は、これまたレンタルで聴いたことはあったが、いまいちという感想だった。今回こそはと思ったが、企画自体は興味深いが、何せ演奏がいまいちで面白くなかった。美しいことは美しいのだが、バラード集のためか、あまり覇気が感じられない。松尾明のオリジナル「Lupus Walk 」も美しいが暗い。アドリブが全く面白くないのも問題だ。ここで思い出したのがアレッサンドロ・ガラティのCD。何枚か聴いたが、面白いと思ったことがない。その時と全く同じ感じだ。結局、オーディオ的にいい演奏と音楽がいいというのは別ものだということを、改めて認識させられた。ジャケットは厚手の紙にコーディングが施され、CDも不織布に入れられていて、かなり丁寧なつくり。CDが2枚なのに普通の価格なので、お得なことは確か。セールスが期待できるかは疑問が残るが、実際に夢を実現させた寺島氏と彼を支えたディスクユニオンの方々には敬意を表したい。松尾明:Ballds(Terasima Records TYR-1073)1.Lupus Walk (Akira Matsuo)2.Estate (Bruno Martino)3.I'll Be Seeing You4.Moonlight Becomes You (Jimmy5.How Deep Is The6.Do You Know What7.Sway To Fro (Kenji8.Violet For Your Furs9.Just A Mood (George10.Stairway To The MoonAkirMatsuo(ds)Yoko Teramura(p)Kenji Shimada(b)Recorded March 27 2017 at Landmark Studio
2018年11月14日
コメント(0)
-

ボヘミアン・ラプソディ
久しぶりに映画に行った。殆ど半年ぶりくらいだ。畑とか日常の仕事が多く、どうしても見たい映画も少ないので、億劫になってきたということもあり。大分ご無沙汰してしまった。今回は、評判の良い映画で、トレーラーを観てもわくわくするので、観に行きたいとは思っていた。世の中の評価はとても高いのだが、音楽映画なので、なかなか万人向けとはいかない。そのためか、3日の1回目だったが、半分も入っていなかった気がする。映画はフレディ・マーキュリーの半生を描いたものだ。クイーンの音楽はほとんど知らないし、フレディがエイズで死んだことをかろうじて覚えているくらいだ。映画はクイーンの前身バンドの「スマイル」にフレディーが加わることから始まり、彼らの成功と別れ、クライマックスの再会後のAid Africaの野外コンサートまでが描かれている。その中では、ゲイの話やフレディのエイズへの感染も赤裸々に描かれている。当然音楽の話が多くなるが、レコーディングでのギター・オーケストレーションやコーラスをテープが擦り切れる程オーバーダビングを繰り返した模様や、メンバー間の選曲やクレジットでの揉め事など、実際の出来事が再現されていて大変興味深かった。Live Aidでの演奏曲目は「Crazy Little Thing Called Love 」以外の5曲が収録されている。コレが感動もので、何故か涙が出てきてしまった。圧巻は旧ウエンブリー・スタジアムで行われたlive Aidのシーン。スタジアム上空を俯瞰し、そこから高度を下げてステージに近ずくシーンやピアノの下からメンバーに近ずくシーンなど、映像が実に素晴らしかった。CGかと思ったが、実写のようなリアリティがある。こちらに撮影監督を務めたニュートン・トーマス・サイジェルとのインタビューが載っていて、その時の苦労話が語られている。新しいエンブリー・スタジアムでは、なくなってしまったステージの実寸大のセットやバックステージを作ったというのだから、リアリティがあるのも頷ける。観客は900人で実写とCGを組み合わせたという。また、YouTubeで観られる映像と同じものを作らないようにするため。コンサートの観客からの視点を避けて、映画の観客がバンド・メンバーになったような感覚になる映像にこだわった」というコンセプトも成功している。キャストは万全。特にフレディ・マーキュリーを演じるラミ・マレックの体当たり的な演技は圧倒的だった。ただ、歯が出すぎて、ねずみ男みたいで、髭を生やした頃はラテン系のいい男に見えるので、少し気の毒な気がする。また、フレディの別れた妻メアリー役のルーシー・ボイントンが美しかった。映画はエレキ・ギターによる21世紀FOXのファンファーレから始まり、テンポよく進み、とても分かりやすい。音楽産業の人間臭い側面を見ることができたのも、嬉しかった。ということで、このロックバンドを知っている人も知らない人も、この感動的な映画を是非広いスクリーンと素晴らしい音響の劇場で見て欲しい。公式サイト
2018年11月11日
コメント(0)
-

Kazuki Yamada conducts Roussel、Debussy、Pourenc
山田和樹がスイス・ロマンド管弦楽団を指揮したCDは以前触れたことがある。以来このコンビのCDをおりに触れて聴いてきた。この前いつも使っているeclassicalで、このコンビのハイレゾが出ているのに気づき、2点ばかり購入した。1つはアルルの女などで、もう一つは、ルーセルのバッカスとアリアーヌを含むCD。後者の出来がすごくよかったのでレビューしてみたい。アルルの女のCDはなかなかいいのだがオケの機能に不満があった。ところが、このCDになったらまるで違う楽団かのように活きがいい。収録はアルルの女が2013年2月、今回のCDは2015年10月なのでは、このコンビが円熟した成果なのだろうが、これほど違うというのも珍しい。曲は余りポピュラーとは言えないルーセル、、プーランク、それにドビュッシーのこれまたあまり演奏されない「6つの古代の墓碑銘」という渋めの選曲。まあ、渋いとは言ってもルーセルやプーランクはクリュイタンスやプレートルの演奏で親しんできたので当ブログとしては馴染みの曲目だ。特に、プーランクは大好きな曲の一つだ。3曲ともCDはあまりなく、この演奏は新しいスタンダードになるだろう。ルーセルの「バッカスとアリアーヌ」は第2組曲が有名だが、第1組曲も取り上げられているのは珍しい。現在のカタログにあるのは、ドゥネーヴ指揮のロイヤル・スコティッシュ・ナショナル管の演奏(Naxos)だけのようだ。当ブログは第1組曲を初めて聞いたが、あえて聞きたいとは思わないが、それほど悪くはない。第1組曲が穏やかで第2組曲が華やかという、ラヴェルの「ダフニスとトクロエ」の第1組曲と第2組曲の関係がこの曲でも当てはまりそうだ。冒頭から見通しの良い音楽でサウンドの透明感が目立っている。あくまでもしなやかな表現で、ルーセル特有の強直した表情はあまり感じられない。ドビュッシーの「6つの古代の碑銘」がビリティスの歌からの6曲を選んだピアノ連弾用の編曲であることは、この項を書くまで知らななかった。これを管弦楽に編曲したのがアンセルメで、他にパイヤールによる弦楽合奏版もある。編曲があまり良くないので普及しないという意見もあるようだが、当ブログは楽しめた。静けさの中から浮かんでくるつややかな木管のサウンドがとても魅力的だ。まあ、原曲自体があまり取り上げられないので仕方がないが、もう少し取り上げられてもいいような気がする。「女鹿」は素晴らしい演奏。少し早めのテンポでテンポは殆ど動かさないが、この曲のアプローチとしては妥当だろう。軽やかな表情が魅力的で、金管を強奏させないのもいい。参考までに聴いたプレートルの全曲盤の「ラグーマズルカ」では、リスのようなすばしっこさを感じたが、今回の演奏もかなりいい。このCDがPresto ClassicalのPresto Discs of the Year2016でノミネートされていたのも頷ける。このコンビでの録音を楽しみにしていたものとしては、山田がスイスロマンドでの首席客演指揮者のポストを去ったことを知って、とても残念な気持ちだ。現在のポストであるモンテカルロ・フィルとの録音も始まっているようだが、オケの自主レーベルからのリリースなので、いままでのようにハイレゾを安価に入手できないのは何とも残念。そもそもハイレゾを配信しているかも不明だ。Kazuki Yamada conducts Roussel、Debussy、Pourenc(PENTATONE PTC5186558)24bit 96kHz Flac1.Roussel: Bacchus et Ariane, Op. 43 - Suite No. 12.Roussel: Bacchus et Ariane, Op. 43 - Suite No. 212.Claude Debussy:6 Epigraphes antiques (arr. E. Ansermet for orchestra)18.Francis Poulenc:Les biches Suite, FP 36Orchestre de la Suisse RomandeKazuki YamadaRecorded: October 2015Recording Venue: Victoria Hall, Geneva, Switzerland
2018年11月09日
コメント(0)
-

渡辺貞夫:Love Songs
TSUTAYAで最近リリースされた渡辺貞夫の「リバップ・ザ・ナイト」を探していたら、同時にリリースされたこのCDがレンタルできることを知り、早速レンタルした。当方は既出アルバムのコンピレーションはあまり好きではない。知らないミュージシャンの演奏を知るために聞くのがほとんど。勿論買うことは殆どない。渡辺貞夫貞夫に注目し始めたのが遅かったので、昔の演奏が聞ければと思ってレンタルした。ビクター音源のほか、ユニヴァーサル・ミュージック、ワーナー・ミュージック、ソニー・ミュージックの70枚以上のアルバムから渡辺自身が選曲した、というところがセールスポイントだろう。バラードを集めていて、ボサノヴァを中心に渡辺特有の哀愁に満ちた演奏が楽しめる。曲の良さは、演奏によっていっそう引きたてられていることも感じる。機会があれば、他のミュージシャンの演奏でも聴いてみたいものだ。こうしてバラード系の曲を一度に聞く機会もあまりないと思うが、彼のメロディー・メーカーとしての才能の豊かさがよくわかる。最近の演奏が多いが、当方が狙っていた昔の録音もある。廃盤のCDからもセレクトされているのは嬉しい。録音年代によって演奏スタイルは異なるが、渡辺のプレイは一貫している。甘く切ないフレージングに、またかと思いつつ、惹きつけられてしまうのだ。未聴の演奏で、特に気に入ったのは、ファンハウスから出ていた「イン テンポ」に含まれる、「ポルタス・フェッシャーダス 」ブラジルを代表する女性シンガー、レイラ・ピニェイロの歌がとても美しい。トラック5はチャーリー・マリアーノを迎えてのライブ録音で、マリアーノの痩せて詰まり気味のアルトに違和感がある。出来ればワンホーンでの演奏を入れて欲しかった。手持ちのCDも大半は忘れてしまっているが、改めて聞くと、しみじみと曲の良さを感じる。どの曲も演奏の水準は高く、サイドメンの優れたバッキングも楽しめる。録音はリマスターしたのであろうが、粒がそろっていて、古さを感じさせるトラックはない。というわけで、曲、演奏、価格と3拍子揃ったCDで、とてもお買い得だ。渡辺貞夫の入門としても最適だろう。ポリシーを破って、ハイレゾが出たら、買いたくなる気がする。なお、正確な資料を参照したわけではないので、収録アルバムとリリース年が不正確な曲もあるかもしれない。ご容赦下さい。渡辺貞夫:Love Songs(VICJ-61777)1:イフ・アイ・クッド ~リバップ・ザ・ナイト (2018)2:タイムズ・アゴー ~into tomorrow(2009)3:リトル・ワルツ・フォー M ~ヴィアジャンド(1998)4:アイ・ソート ・オブ・ユー ~リバップ・ザ・ナイト (2018)5:コール・ミー ~ Sadao and Charlie Again (2006)6:ポルタス・フェッシャーダス ~In Tempo(1994)7:ナイトリー・ユアーズ ~ゴ-・ストレ-ト・アヘッド・アンド・メイク・ア・レフト (1997)8:ストレイ・バーズ ~マイシャ(1985)9:アイ・ラヴ・トゥ・セイ・ユア・ネーム ~Good Time for Love(1986)10:ファイアープレイス ~ヴィアジャンド(1998)11:ジュント・コム・ヴォセ ~NATURALLY(2015)12:シンパティコ ~オウトラ・ヴェス~ふたたび~(2013)13:シーズ・ゴーン ~カム・トゥディ(2011)渡辺貞夫(as)
2018年11月07日
コメント(0)
-

Barbara Hannigan:Vienna - Fin de Siècle
以前取り上げたソプラノのバーバラ・ハンニガンの新譜が出ていることを知り、αレーベルのハイレゾを配信しているHIGHRESAUDIOをチェックしたところ、$10.2で売られていたので購入した。珍しく配信が先行して、CDは9月のリリースだったようだ。フォーマットは24bit48kHzFlacで、例によってdbPowerAmpで96kHzにアップコンバートして聴いた。タイトルは「ウイーン:世紀末」(最近リリースされた国内盤CDでは「ウィーン世紀末、六人の作曲家 ~アルマ・マーラーのまわりで~」というタイトルになっている)というもので新ウイーン楽派界隈の人たちと、何故かフーゴ・ヴォルフ(1860 - 1903)の歌曲で構成されている。同じウイーン生まれで、シェーンベルク(1874 - 1951)とヴォルフの晩年と少し重なっていることから取り上げられたのかもしれない。すべて調性音楽なので、アルマやヴォルフの歌曲も違和感なく収まっている。柔らかなロマンが感じられる品のいい演奏で、少しひんやりした気分も悪くない。シェーンベルクなど、馴染めないでいたが、この演奏だとすんなり入ってくる。この中では、アルマ・マーラーの歌曲が当ブログにとっては新鮮だった。アルマの作品は16曲の歌曲のみが知られている。今回の二種の歌曲のほか1924年に残りの2曲が出版されている。最近アルマの歌曲全集の購入を検討していたので、数曲とはいえ入っているのは嬉しい。飛びぬけて優れているとは思はないが、悪くない。ベルクは管理人の好きな歌曲集で良く聴いていた。そのオッターの歌唱よりも滑らかで、優れている。オッターはアバド=ウイーンフィルの管弦楽伴奏だったが、今回のピアノ伴奏もそん色はない。ツェムリンスキーは手持ちのバーバラ・ボニー(DG →Brilliant)の歌を聴いてみた。ハンニガンのほうがくっきりとした表情付けで、ボニーの歌がぼやけて聞こえてしまう。ヴォルフは最近聴いていなかったが、昔シュワルツコップの歌で親しんでいたことを思い出した。特に好きな「君よ知るや、かの国を」はエキセントリックにならず立派な歌唱で嬉しかった。ハンニガンはこの前の「ガールクレイジー」のほか、もう一つくらいしか知らない。当ブログは、少しエキセントリックな歌手だという認識だった。ところが、今回のCDを聴いているとディクションの美しさ、声量の大きさ、高音から低音までムラのない声などの美点を教えられた。特にとろけるような滑らかさは、めったに聞けるものではない。ピアノはラインベルト・デ・レーウ(1938-)。現代音楽の指揮者として有名だが、懐の広い積極的な伴奏で気持ちがいい。今年80歳だそうだが、老いは感じられない。Barbara Hannigan:Vienna - Fin de Siècle(Alpha Record ALPHA393)24bit48kHzFlacArnord Shoenberg:1.四つの歌曲 作品2(1899)Anton Werbern(1906-1908):5.リヒャルト・デーメルの詩による五つの歌曲Alban Berg(1885~1935):10.七つの初期歌曲Alexander von Zemlinsky(1871~1942):17.歌曲集 作品2(1895~1896)より19.歌曲集 作品5(1898~1899)より21.歌曲集 作品7(1898~1899)よりAlma Maria Mahler-Werfel(1879~1964):24.五つの歌曲(1910)より27.四つの歌曲(1915)よりHugo Wolf(1860 - 1903):28.ゲーテ歌曲集(1888)よりBarbara Hannigan (s)Reinbert de Leuuw(p)Recorded Octover,2017
2018年11月05日
コメント(0)
-

Debra Mann:Full Circle
デブラ・マンというアメリカのフォークやジャズを歌う歌手のジョニ・ミッチェルの作品を歌ったアルバム「Full Circle」を聴く。彼女はバークリー音楽院卒のピアニスト兼ヴォーカリスト。メジャーな活躍はされていないようだが、歌唱力はなかなかある。ジャズというよりはフォークやポップス系のスタイルだ。ポートレートを見ると年齢は40代から50代前半のような感じがする。whaling city soundという聞いたことのないレーベルからのリリースホームページを見ると、1999年に設立されたレーベルで、ジャズを含むポピュラー音楽が殆どだが、クラッシックも僅かにある。設立理由はアーティストの支援が目的のようだ。ジャズレーベルでいえばマリア・シュナイダーのArtist Shareのような立ち位置だろう。 CDはデジパックで、コーティングされた厚手の紙を使用していて、ブックレットもカラー写真が多く、かなり贅沢な仕上がりだ。取り上げられた曲は、ミンガスの「Goodbye Pork Pie Hat」と「Dry Cleaner From Des Moines」以外はジョニ・ミッチェルの曲で作詞はすべて彼女が担当している。歌はうまい。いろいろな歌手からの影響があるのだろうが、ナンシー・ウイルソンやカーリン・クローグを思い出させる語り口だ。ジャズを主体に、フォークやロックなどの味わいも感じさえる。本家の歌が少しやせているのに対して、潤いのある声で雰囲気がだいぶ緩いのが、却ってなかなか心地よい。全体的に洗練されていて、ミンガスのアクの強い曲でさえも毒は薄められているようだ。「Dry Cleaner From Des Moines」はジョニ・ミッチェルのアルバム「Mingus」のために作られた曲。ノリのいい演奏で、中間部のベース・ソロもご機嫌だ。「Goodbye Pork Pie Hat」は、最もジャズ的な演奏だ。ただ、仕上がりがゴージャスで、曲が持っていた素朴さが薄れている感じがする。「Both Sides Now」は速めのテンポで軽快に歌っている。中間部のギターやサックス・ソロもノリノリ。代表的なラブ・ソングである「A Cae of You」は僅かにフォーク的な香り感じさせるものの、抒情的な雰囲気が堪らない。デブラ・マンのとても滑らかなヴォーカルが聴きもの。ギター・ソロもいい感じだ。個人的にはもっとも共感できるトラックだった。最後の1969年に行われたウッドストック・フェスティバルについて歌った「Woodstock」では、ワイルドなギターやサックス・ソロのソロが入っている。原曲と同じようにバック・コーラスを入れていて、これがなかなか洒落ている。ところで、このレコーディングは、クラウドファインディングで資金を調達している。データが古いようだが、サイトで見る限り、143人の支援者が$13,550寄付しているが、$16000という諸経費を賄うまでには至っていないようだ。願わくは、多くの人たちがこのプロジェクトに賛同するか、CDを購入してくれることを願う。youtubeに全曲アップされているが、日本では試聴できないのが残念。恐らくプロキシーを変えれば視聴できるかもしれないので、ご興味のある方は試してみてほしい。Debra Mann:Full Circle(whaling city sound WCS 109)1.Black Crow2.Jericho3.Be Cool4.Goodbye Pork Pie Hat5.Both Sides Now6.The Circle Game7.Big Yello Taxi8.Blue9.A Case Of You10.Dry Cleaner From Des Moines11.Urge For Going12.WoodstockDebra Mann(vo,p)Dio Govani(sax,fl)Jay Azzolina(g)Dave Zinno(b)Marty Richards(Ds)Paul Nagel(p track 8,11)Jerry Leake(perc. track 9,11)
2018年11月03日
コメント(0)
-

Gergiev Stravinsky:Petorushka,Jeu de cartes
ゲルギエフが手兵のマリインスキー歌劇場管弦楽団を振った「ペトルーシュカ」(1911)を聴く。ゲルギエフは再録になるが、マリインスキー歌劇場管弦楽団とはこれが初めて。eclassicalのメールでハイレゾが$10.39で配信されていることを知り、速攻でダウンロード。概ね悪くはないが、高音域がきつい。CDのSACD層なら、このきつさもある程度軽減されるだろうが、当方は価格優先なので仕方がない。テンポは適正で、特に違和感のあるフレーズの処理は感じられない。細部でちょっと気になるところがある。第一場の主題がレガート気味なのが違和感あり。また、ソロは奏者に任せているのだろうが、フルート・ソロがところどころアゴーギクが過度で、小節からのずれが目立っている。パーカッションなど普段聞こえてこない声部が聞こえてくるあたりは、なかなか面白い。マリインスキー歌劇場のオケはロシア特有の重量感と粘り気がある。ローカル色がところどころ垣間見られて、ペトルーシュカではいい意味でロシアの香りを感じさせ、他の演奏からは聞こえてこない味わいが感じられる。ただ、低音が重すぎて、鈍重な感じで、この曲の持っている軽妙さが失われている。金管もオーバーブローぎみで疲れる。「かるた遊び」も同じ趣向だ。この曲でも、他の演奏とは違う味わいをどう評価するか、好みの分かれるところだが、個人的には、もう少し軽く、乾いたタッチが好ましい。第3ラウンドのセヴィリアの理髪師ほかの引用は、はっきりわかってなかなか楽しい。同じゲルギエフでも、LSOなどとの共演のほうが、より一層いい演奏になっていた感じがする。Stravinsky:Petorushka,Jeu de cartes(Mariinsky MAR0594)24bit96kHzFlac→DSF 5,6MHzStravinsky:1. Petrushka(1910-1911)2. Jeu de cartes(1936-37)Mariinsky OrchestraValery GergievRecorded at Mariinsky Concert Hall, St Petersburg14 January 2014 (Petrushka) / 26, 29 & 31 December 2009 (Jeu de cartes)
2018年11月01日
コメント(0)
全13件 (13件中 1-13件目)
1
-
-

- 楽器について♪
- 11月1日クリスハープの新色カラー。…
- (2024-11-12 17:06:30)
-
-
-

- 防弾少年団(BTS)のパラダイス
- あさって、ジンのI’ll be there 楽し…
- (2024-10-23 23:53:52)
-
-
-
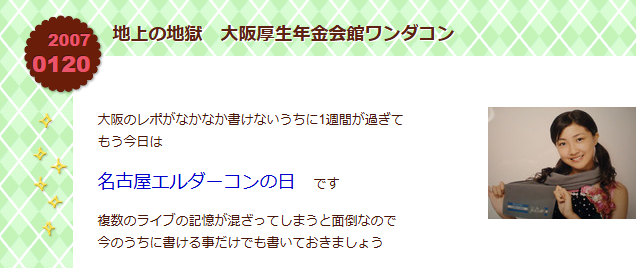
- LIVEに行って来ました♪
- 始原本家 70年史 2007年1月
- (2024-11-24 10:29:27)
-







