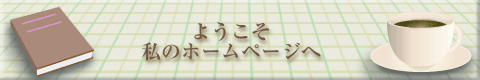・・唐国の波(完)
少し高い所に芝生の緑の帯が長く伸びる。
今まで見たこともない、一抱えもありそうな、いやそれ以上の、
アレカヤシの大株のような樹木が数株、
一定の距離を空けて植えられてあった。
何という樹なのか、ピンポン玉ほどのオレンジ色の実を無数に着け、
白っぽい葉を風にそよがせ、いやでも南国の情緒を醸す。
金印のことを忘れて、リゾート地を訪れたような気分に浸った。
この島にこんな素敵な所があったとは。
私はこの朝ホテルの玄関から乗った、
タクシーの運転手の言葉を思い出した。
「博多埠頭、志賀島行の船乗り場まで・・」
私が告げると、彼はいきなり語気荒く言った。
「お客さん、なんで志賀島へ行くとね。なアンもなかですとよ」
「・・・・・」
「金印かなんか知らんけど、つまらんとこですたい。
そりゃあ行けと言われれば行きますばってん、仕事ですから。
そいでん、街の方がずっとよか。
なんぼでん行くとこあるでっしょ。シーガイヤーとか・・」
まあよく喋る男である。
私は苦笑するばかりで返す言葉もなかった。
運転手は更に続けて言った。
「特別金印に興味があえるという変りもんというか・・
特別な人は別でっしょうが・・
海の中道ならよかですばってん。
あそこんには大きい公園があって、レジャーランドになって・・」
私は変わり者とも思わないが、レジャーランドに興味はなかった。
金印を訪ねようと思い立ち、
仕事を終えて羽田から空路福岡入りをしたのである。
暮れ残る福岡上空から志賀島の全景が眺められた。
当然ながら地図と同じ形の島影を見下ろし、
金印への思いを膨らませていた。
海の中道も、そこに建つホテルも、雁の巣砂丘もはっきりと見えた。
時間があれば、あの砂丘にも行ってみたい。
運転手が何と言おうと、その為に博多へやって来たのだから。
黙っている私に、その心を推し量ってか、
彼はもう行くなとは言わなくなった。
祝日とあって往来の車はさほど多くはない。
タクシーの窓から見る限り、
ビルが林立した街は東京や横浜と大して変わりなかった。
ただ、聳える椰子の樹に、南の国に来た実感を覚えるだけである。
波打際まで出ると風は思いの外強かった。
芝生や砂浜の上で、人々は思い思いに寛いでいる。
私も芝生に足を投げ出した。
秋天は高く澄み渡り、一片の雲すらない。
この分だと素晴らしい夕日を拝めるだろう。
沖合いに浮かぶ玄海島の方を眺めた。
海辺のレストランで、ウエイターが教えてくれた日没の方角である。
日はまだ高い。サンセットショーまで2時間近くあった。
果てしなく広い海は、繰り返し繰り返し波を寄せてくる。
金印を携えた使者達もこの波を越えて帰ってきたのだ。
それにしても、この小さな島に、
どうして金印は埋もれていたのだろうか。
私の疑問は何ひとつ解明されなかったけれども、
金印の眠っていたこの島に入っただけでも満たされた思いはあった。
歴史の解明は研究者に任せよう。
古のロマンを秘めた私の金印物語を創ってみたら、
それもまた楽しいのではあるまいか。
光武帝はなくなる僅か2ヶ月前に、倭国の使者と何を話したのだろうか。
唐国の波に乗ってきた金印は・・そして卑弥呼は・・
規則正しく届く潮騒の音を耳にしながら古代史を思い、沖を眺めた。
この波の果てにかの国はあるのか。
繰り返し繰り返し寄せてくる波の音は、
私をかの国に、金印のふるさと唐国へ誘う調べのように心地よく響いた。
夕暮の風は冷気を帯び、更に強く吹き付けてきた。
私の髪は先ほどからずっと狂ったようにはね続けている。
着てくるべきであった。
身をすくめながら、ジャケットをホテルに残してきたことを悔い、
スカーフを取り出して首に巻きつけた。
いつの間にか黒ずんだ海には、無数の光の胞子が散りばめられ、
弾ける音が聴こえてくるように輝きを放つ。
そして太陽は、
しだいに膨らんできた柔らかな雲に包まれるようにして
水平線の彼方に消え、
やがて錦の帯も黒い海に飲まれていった。
(完)
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- 英語のお勉強日記
- 百万長者になるにはどのくらいのカス…
- (2024-05-17 13:50:40)
-
-
-

- やっぱりハワイが大好き!
- 【ハワイ旅】子連れハワイ1日目の過…
- (2024-05-12 09:00:15)
-
-
-

- ぶらり、歴史の旅、歴史探訪(歴男、…
- 半鐘
- (2024-05-14 14:44:00)
-
© Rakuten Group, Inc.