10月のバラ 【6】

あの夜、私はサンマルコ広場にいた---------。




サンタ・ルチア駅の川向こうに面したホテルの裏にはローマ広場がある。
ラグーンに浮かぶこの島へ渡った者はここで車を乗り捨てることになる。
この島ではエンジンを搭載した車は乗り入れ禁止となっている。
皆、道替わりである運河を異国情緒溢れるゴンドラや水上バスで行き交うのだ。
私もごたぶんにもれず、水上タクシーを利用してベネチアの心臓部サン・マルコ広
場へ向かった。宵も深まり、ワインを果敢に腹に入れて「騎士」となった勢い
で・・。
キリスト教徒の重要な節目の祝いであるカーニバル=謝肉祭は太陽暦とは違う暦で行われるため毎年同じ月日と決まっているわけではない。
毎年2月から3月の間に行われる。
前夜祭に合わせてベネチアの町に足を踏み入れたのはラッキーだった。
乗合での水上タクシーで、サン・マルコ広場近くの停止場で降りたのは数名だっ
た。
昼間あれほど賑やかだった町は眠りについているかのように閑散としていた。
広場裏の商店が並ぶ華やかな通りもひとっこ一人みかけない。
祭りの狭間のもう一つの街の顔と面しながら広場へ歩く。
すると、円柱が続く回廊を抜け、いよいよジオットの塔が暗闇のなかぼんやりと浮かびあがるほどに見えてきた角を曲がった時、楽団のマーチのような音楽が夜空の風に乗って流れ出してきたのだ。
心踊らせながら私は広場へ駈け出した。
そしてこの夜の祭りは終わってないこと、終わらないことを知った。
眠れぬ夜に夜な夜な集まってきた地元民や観光客たちは、数珠繋ぎに飾られた裸電球の下、宮殿に囲まれた広場の片隅で楽団に合わせて中世の騎士や道化師に扮した仮面を被りお互いの素性を隠して酔狂に踊り狂っていた。
やがて私もその輪のなかへ飛び込んだ。私は誰でもなかった。私だけではない、
彼、彼女らも、誰でもなかった。--素晴らしき哉、人生--
ある人はカサノバであり、マルコ・ポーロであり、共和国時代の総督であった。
踊り疲れた頃、楽団は宮殿とサンマルコ寺院に挟まれた路地へ進んだ。楽団に続いて唄を歌う人々の行列が続くのだった。
ベネチアの迷路のような道をさまようように、終わりも知らず・・・・。
しかし私はいつまでもそこに留まっているわけにはいかなかった。
心残りながらも明日は早朝ヴェローナへ向かわなければならない。
おとぎの国のようなこの町でも時間は決して止まってはくれない。
最終がなくなるという心細さが勝り水上バスの波止場へと一人踵を返さなければならなかった。
私の祝祭に浮かぶ夢島の物語もここまでであった。
20分待ってようやく、バスは空のままリアルト橋近くにいた私を拾った。
そのバスは最終ではなく、始発のバスだった-----------。

**********************************************************

「シュワイヤ、シュワイヤ」私も独り言を呟いていた。
「甥の結婚式らしいよ」
回想が遮断され、こちら側に引き戻された。
「えっ、何?」
「モーセスの甥の結婚式だって」と、妻は言う。
「今頃になって、何?」
「だって、そう言うんよ、あれ?言わんやったっけ?」
「最初からそう言ってくれたら胸わずらわして毛穴かきむしるようにして、いらんお酒もようけ飲まんと悩まんでもよかったのに」
「お酒はしょっちゅう、いつでもどこでもの癖に」と冷ややかに返す。
妻は、肝心なことをいつも見過ごして、いつも些細なことの上げ足をとるのが好きだ。
しかしモーセス、おまえはかくもボキャブラリーが少ないのか。
それとも、妻の読解力が未熟なのか。「打てば響かん奴ばっかりや」と嘆く。
それよりなにより、私の誇大妄想気味かつ単細胞な想像力が逞しすぎたのか。
やれやれ、現実のドラマの結末はいつもあっけない。
「だって、最初から『ファミリーのダンスパーティー』って言いよらんかった?」
「・・・・・・・・・ショコラン(ありがとう)」
「アフワン(どういたしまして)」
おっしゃるのはご尤もですがここは異国ですぞ、あまた多くの敵から世界で何より大切な君の生命を守るのが私の課せられた使命なのだ、―――とは心の中でも言わん。そのかわり、
「馬鹿は死んでも分からんわ」
行列にもまれながら、また妻は女の子たちに取り囲まれていった。
その姿は、まさしく現代に蘇ったクレオパトラであったか、はたまた・・・・。
「餌に群がる金魚や、いや糞に群がる金魚やわ」
「正しい毒気」に開放された妻は子供たち、特に女の子に大変な人気で、女王様気取りのシャイマーが一抜けた今、妻の争奪戦で下克上のような歩く戦国時代の様相だった。
妻は妻でモーセスに全般の信用を置いてるのか、離されまいと必死に後を付いて行く。
おかげで私は「不当な毒気」から開放されるとせいせいしてた。
「なんであいつだけなん」
私は置いてきぼりにならぬよう、ビデオのファインダーを通して皆を追いかけていた。
広場にでた。これまでより比較的に広い空間だ。村に入って、やっと夜空を仰げ
た。
楽団の数人が片手にタンバリンを掲げ、腕を組み合い輪をつくり踊りだした。
最前列でその光景を、おそらくちんぷんかんな説明を受け、これまたちんぷんかんぷんな合い打ちをしているモーセスと妻を眺めてながら呟いた。
「置いてけぼりや・・・」
ポツンとしていた私をモーセスは手招きした。
あんたに手招きされる筋合いはないよ、とは裏腹にしっぽを振るようにして私は彼の傍へ駆け寄った。--ワンワン--
「ダンスダンス」と、彼は言う。
--あんたに言われなくってもわかるわい--
億劫そうにフンフンとうなずいた。
どうしても、「ラクダ使い」には馴染めない。
間髪入れずに妻は解説する。
「二人で輪のなかへ入って踊れって言いよるんよ」
--おいおい、あんたはいつからこのラクダ詐欺師と以心伝心できる仲になったのだ--と感心していたら、
「あのおじさんが手招きしよるよ」
と、とてもわかりやすい説明を付け加えてくれる。
「どんちゃん騒ぎはしょうに合わんわ」と言いながら私は彼女の腕をとり、輪のなかへと飛び込んでいった。
--ああ、楽しい楽しい楽しいなー--
「一緒に踊れ」と招いてくれた根のやさしそうな老人は白いジュラバを着ていた。
さぞかし高貴なお方に違いない。ひょっとしてここの村長か、オビワン・ケノービや。
と、おもいきや片目が不自由そうな禿げ鷹のような老人が、
「はやく踊りを中断して、次へ行くぞ。こんなところでちまちましてたら日が暮れちまわー」というニュアンスで叫んだ。とっくに日は暮れてますけど・・・。
禿げ鷹老人は異様な雰囲気をたっぷり滲みだしている風貌だった。
「帝国の逆襲」や。
彼はこの村の訳有りな指南役に違いない、占い師か何かだろうか?
踊りは突然中断され、馬車はゆっくり進みだした。
派手なシャツを着た禿げ上がりデブなオヤジ(ただし、カイロなど都会の中年男の多くは太り気味で髪の毛は薄く、民族衣装を着ない人は皆が派手柄シャツを着ている)が、
「おらー、おまえらもっと気合いれて吹かんかい!太鼓鳴らさんかい!声あげんかい!」
と、怒鳴りつけるように火を吹き出さんばかりの指示をしていた。
かと思えば、火は吹かないけど顔中に華厳の滝状態の汗を吹き出している背の高い男が派手デブおじさんに負けじと、指揮棒を振りかざして楽団をリードしている
(つもり)。
いったい誰がこの祭の宴の先導者なのか、なんなのかさっぱりわからなかった。
ただし、行列の塊はちぎれることなく続いているのが不思議であり、お約束のようでもあった。
カタルシスの絶頂は、それぞれ各人の方向に委ねられている。
そうさ、祭は皆が主役なのさ、たぶん・・・。
そのなかで主役である田舎の結婚披露宴でもみたことない派手なフリルのついたドレスを着たインド映画のプリンセスのような新婦とマイクタイソン新郎は馬車に
次々に祝福のキスと握手を求めてくる村人やら遠い縁戚者たちを相手にしている。
笑顔を絶やさなくてはなくてはならないという過酷な状況とトイレにも行けない不自由さにほとほと疲れ果てていることと勝手に察する。
「新婚さんにはやりたいことがほかにもあるだろうに」10日ほど前にその新婚さんの身になった自分に言い聞かせ、一人赤面していた。
おまけに、呼んでもいない東の果ての国から(彼らにしてみればほとんど宇宙人と同じ存在の)私たちまでいるのだから。私らがではない、彼らが異性人と「コンタクト」だ。
いずれにせよ、ああして真の主役は馬車に乗せられ、さらされるような目にあっているが、きっと退屈であろうこの村での唯一の楽しみを年に何度か与える役柄、いわば出汁に過ぎないのかもしれない。
「ああ、楽しいダンス・パティーだったね」と息をはずませ妻に声かけた。
すると、妻は、
「ダンス・パティーはこれから別の広場の会場かどこかでやるんよ」
と、確信を持った口ぶりで言い切るのだ。
「えっ、今のはちがうの?なんで?なんで?」
もう、すっかり彼女のペースに乗っかった方がお気軽状態の私だった。
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- ちいさな旅~お散歩・日帰り・ちょっ…
- 【都内紅葉散策】Let's 豪徳寺2024
- (2024-11-30 20:07:24)
-
-
-
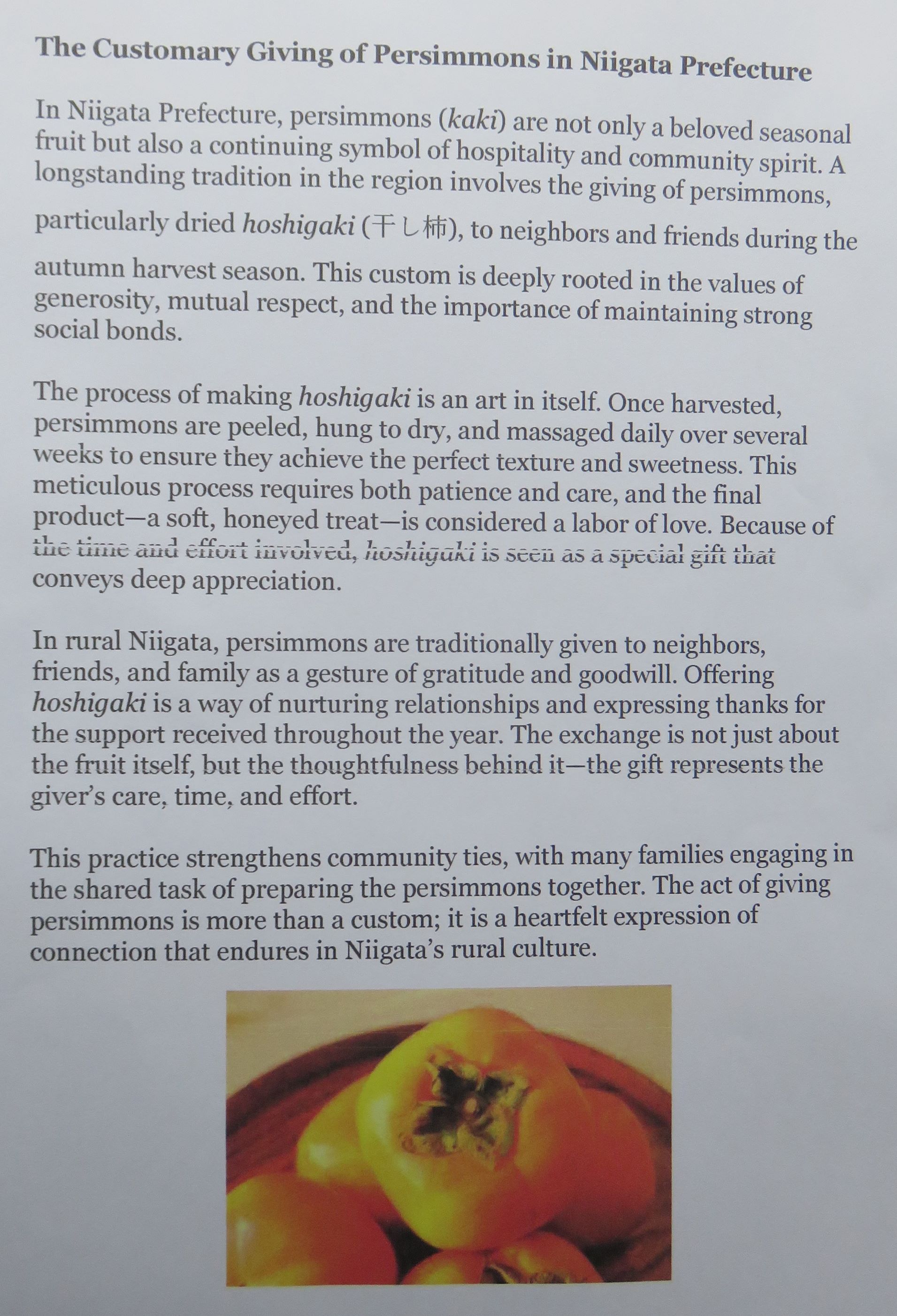
- 英語のお勉強日記
- English speech November 2024 …
- (2024-12-01 00:00:25)
-
-
-

- あなたの旅行記はどんな感じ??
- 伊豆沼と南三陸
- (2024-11-26 21:13:50)
-
© Rakuten Group, Inc.



