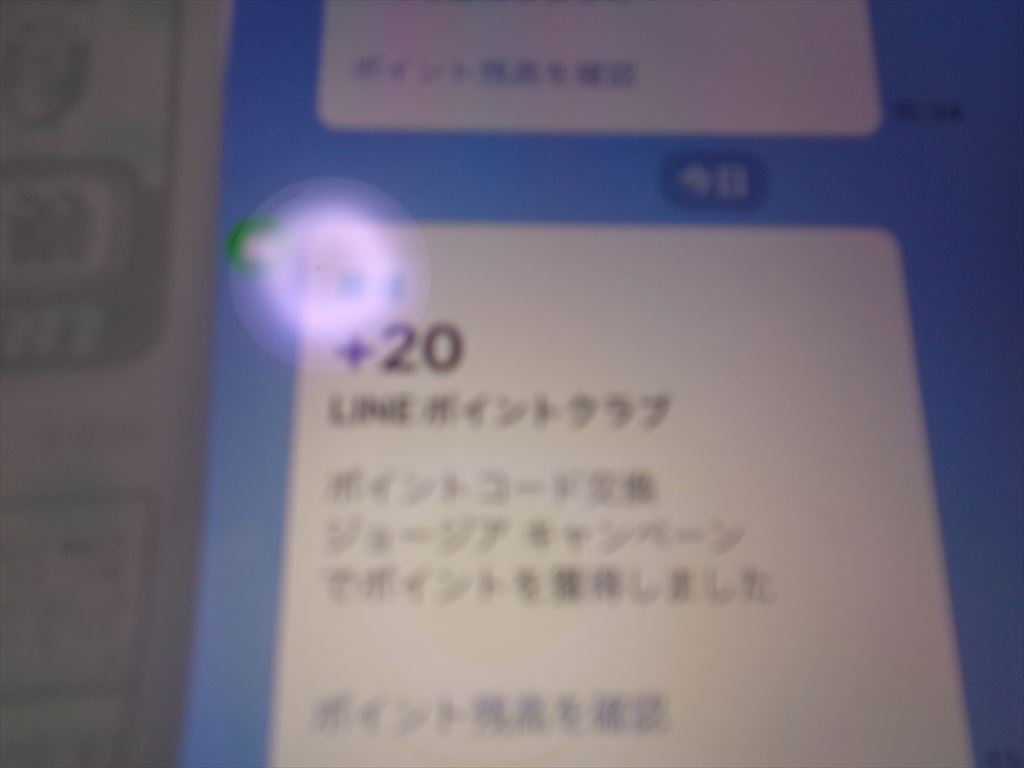E.St.6
-6-
動き出す時間
その日から、芙美の面会は誰も通さない事になった。芙美のそばにはずっと松坂が付き添い、食事を運んだりお茶を入れてやったり、髪を解かして遣ったりもした。
「伊藤さん。今日から僕がそばについているから、ゆっくり養生して元気になるんだよ。」
始めはぎこちなかった松坂も夕方には、細かい世話が出来るようになった。
夕食を終えて、タオルを洗面台に置くと、松坂は芙美のベッドのそばの椅子に座った。
「伊藤さん、もうウイルスは逃げて行ったんだよ。君が僕を刺した事だって、ウイルスの仕業だったんだ。君は誰に咎められることも無い。それに、見ての通り僕はもう元気になっただろ。今度は君が自分を取り戻す番だ。
明日、また来るよ。今日はよく眠って。じゃあ。」
松坂は励ますように芙美の白い手をそっと握って、立ちあがった。
「お休み。」
静かにドアを閉めると、松坂はとぼとぼと席に戻ってきた。めずらしく机に向かって書類を書いている石塚に、松坂が言った。
「なあ、石塚。これは仕事なんだよな。公私混同しているわけじゃないよな。」
石塚は顔を上げると松坂をチラッと見て「お疲れだな。コーヒーでも入れてやるか。」と言って立ちあがった。
「なんだか、恐いんだよ。このまま、自分の感情に歯止めが利かなくなりそうで。」
松坂は席に座りこんで、頭を抱えていた。石塚は2杯分のコーヒーを持ってそばまで来るとぼそっとつぶやいた。
「良いんじゃないか、本当に好きになったんなら。俺達だって人間なんだから。」
松坂は、石塚の言葉に驚いて顔を上げた。
「お前はここが固すぎるんだよ。」
石塚は、そう言って松坂の頭を小突いた。松坂は苦笑いして、石塚のコーヒーを受け取って一口飲んだ。そして、大きく息を吐くと「砂糖が入ったコーヒーもたまにはいいな。」と笑った。
一人になってまた、静かな時間が始まった。今までこんなに静かな時間を過ごした事などあっただろうか。芙美は、そっと窓辺によってカーテンを開いてみた。月の光が静かに満ち足りていた。
芙美は、もう森村が怒鳴りつけた時点で、正気を取り戻していたのだ。それでも、太陽が昇って辺りがざわめき始めると、なぜか自分をうまくコントロールできなくなる。声を発する事が、意志を表す事が、恐いのだ。
芙美は先ほど松坂が握っていった手を月の光に翳してみた。穏やかなぬくもりが今でもそこにあるようだった。
ふと見ると、風に流された雲が月を隠し始めていた。芙美の中で、悲しい過去が浮かび上がってきた。
「あんたなんか、あの人には不釣合いなのよ。何勘違いしてんのよ。」
突然、すぐ後ろで声がしたような気がして、芙美は慌ててベッドに潜り込んだ。
『あの時の呪縛を引き千切らない限り、次の恋には行けないんだわ。』
芙美は松坂のぬくもりを微かに留めた手をグッと胸に押し当てて眠った。
朝になって、松坂がやってきた。
「おはよう、朝食を持ってきたんだ。一緒に食べよう。」
松坂はサイドテーブルを引き寄せて、クロワッサンのサンドウイッチと缶コーヒーを紙袋から出してきた。
「お袋が焼いたクロワッサンなんだ。結構いけるんだよ。食べてみてよ。」
ドアをノックする音が聞えて、森村が入ってきた。
「どうだ。具合は?」
「随分早いね。夜勤明け?」
「ああ、昨日ひき逃げ事件があってな。今調書を書き上げて解放されたところだ。おお、懐かしいな。」
森村は、クロワッサンを見て目を細めた。
「アイツは元気でやってるのか。」
「ああ、元気にしてるよ。時々、父さんの話しもするんだよ、冷え込んだ夜なんかに。また酔いつぶれてコタツの中で寝てるんじゃないかしらってね。母さんも父さんの事心配なんだよ。
大人になって、やっとわかった。父さんと母さんは憎しみあって別れたんじゃないってことがね。もういい加減復縁したら?どうせ痴話げんかの末に、勢い余って離婚届出したんだろ。」
「ふん、世間ずれしやがって。威勢ばっかりいいくせに身体が弱いんだから、アイツは!無理すんなって言っとけよ。」
森村は、芙美に向き直って言った。
「嬢ちゃん、あんた見てると若い頃の女房を思い出すよ。身体をゆっくり休めて、またあの威勢のいい姿、見せてくれよ。哲也、この嬢ちゃんは俺のお気に入りなんだ。大事にしろよ。じゃあな。」
森村が出て行くと、松坂は少し顔を赤らめて言った。
「親父の奴。気を聞かせ過ぎだよ。」
芙美は、なんとか身体を動かそうともがいていた。
『やわらかな焼き立てのパンの香り、松坂さんのお母さんが作ってくれた物なら、なおさら食べてみたい。』
ゆっくりと腕を伸ばして、やっとサンドウイッチにたどり着いた。まだ動きはぎこちないが、なんとかパンを口に運ぶ事ができた。
『香ばしくて、おいしい。なんだか松坂さんの家の暖かい雰囲気が詰まっているみたい。』
「芙美ちゃん、やっと自分の手で食べてくれたね。ありがとう。」
松坂は嬉しそうにそう言うと、缶コーヒーを芙美の手に運んでやった。
「よかった。このまま点滴を続けていたら、筋力が落ちて歩けなくなるところだったんだ。本当によかった。」
松坂は相変わらず表情を変えない芙美に、まるで一人芝居のように浮かれて喜んでいた。しかし、芙美はまた、深い深いラビリンスに陥っていた。
『私は、本当に松坂さんにふさわしいのかしら。』
過去の記憶が、底無し沼のような迷宮へと芙美を引き込もうとしていた。
石塚が3個目のドーナツにかぶりついていると、松坂が鼻歌交じりで遣ってきた。
「おはよう。相変わらずいい食いっぷりだね。」
余りの浮かれように、石塚は最後に残していたお気に入りの生クリーム入りのドーナツを落としそうになった。
「どうしたんだ、松坂。悩み過ぎてとうとう脳みそが沸騰したか。」
石塚が渋い顔をして、松坂に詰め寄った。松坂ははっと我に帰って、ちょっと咳払いをすると、席に戻って書類の整理を始めた。
「あれ、コーヒー飲まないのか?」
変な生き物でも見るように、石塚はドーナツをくわえたまま松坂の動向を見つめた。
「ああ、さっき伊藤さんのとこで朝食を取ったところなんだ。」
そう言うと、ぐっと石塚に顔を寄せて、「伊藤さんな。自分の手で、クロワッサンを食べたんだぞ。」とささやいた。
「ええ!自分の意志でか?やったじゃないか。」
これには石塚も喜んだ。
「だけど、まだ表情が戻らないんだ。」
はあっと肩を落として息を吐くと、さっきとは打って変わって落ちこんだように視線を落とし「早くみたいな、芙美ちゃんの笑顔。」とつぶやいた。
「芙美ちゃ。。。?! まるで恋する少女だな。」
石塚は呆れて言った。
午後になって、今日子と志穂がやって来た。
「こんにちは。芙美の具合、どうですか?」
今日子が声をかけると、石塚が答えた。
「朝は自分でパンを持って食べたらしいんだけど。昼にはまた元に戻っちゃったんだ。今松坂がそばについてるから、部屋の方に行ってやってよ。」
今日子と志穂が芙美の部屋にやってきた。
「あれ、芙美のベッドが空っぽ。」
今日子が驚いていると、奥で声がしていた。
「やあ、ごめんごめん。今、伊藤さんに外の景色を見せてあげようと思って、中庭の見える窓まで来てたんだ。」
簡単な食器棚の向こうから、芙美を抱き上げた松坂がやってきた。
「ベッドに戻ろう。疲れたかい?」
松坂の甲斐甲斐しさに今日子も志穂も驚いていた。今日子は途中で買ってきたワッフルをみんなに振舞った。
「私、ちょっと石塚さんにも届けてきます。」
そう言って席を外すと、急いで石塚の席へ向かった。
「石塚さん。松坂さん、人が代わったみたいに熱心に芙美の世話をしてくださってるけど、無理してないのかなあ。」
今日子は、石塚のワッフルを差し出しながら心配そうに言った。
「奴のことだ。イヤならイヤだってはっきり言うだろう。そう言うところは、クールに割りきる奴だから。
僕に言わせれば、喜んでやってるって感じだけどなあ。伊藤さんが朝食を食べてくれた時だって、小躍りして喜んでたよ。」
「小躍り?松坂さんが?うーん、信じられない...。」
今日子は考え込んでしまった。
「まあ、そんなに気にしなくても良いって事だよ。とりあえず、伊藤さんが松坂を信頼できるようになって、自分自身を認められるようになったら、ハッピーエンドって事だろ。」
「はい。」
今日子は明るく返事をすると、芙美の部屋に戻って行った。石塚は、今日子から受け取った紙袋を開け、砂糖のこげる香ばしい香りに酔いしれていた。
志穂は芙美のベッドのすぐ横に座りこんで、小さい頃からの話をしていた。
「私は、貴方の事を物心ついた頃から知ってるわ。嬉しかった事も悲しかった事も、悔しい思いをした事も、必死でがんばった事も、全部全部貴方自身じゃない。どうして殻から出てこないの。何を怯えているの。貴方は堂々と胸を張っていればいいのよ。」
「しほ.....。」
ふりしぼるように、芙美が声を発した。
「芙美ちゃん。」
部屋に居る誰もがぱっと明るい顔になった。
芙美は必死でもがいていた。仲良しの志穂を傷つけられて、囮にまでなって復讐してやりたいと思っていたのに、その志穂が、逆に自分を励ましてくれているのだ。芙美はなんとか志穂の気持ちに答えたかった。深い深い迷宮から這い出し、現実世界への扉にしがみつこうとしていた。
「芙美、どんな事があっても、私達が付いてて上げる。勇気を出して。」
今日子も芙美の手を取って言った。
「今日子。」
今度はさっきより、一段としっかりした口調になってきた。
「伊藤さん。何も心配要らないんだよ。」
松坂がそっと近づいていった。すると、急に芙美は視線を泳がせ、不安そうな瞳でうつむいてしまった。
「伊藤さん。。。」
松坂は少し気落ちしたような顔で言った。しかし、また顔を上げ、「急がなくて良いさ。ゆっくりやろう。」と自分を奮い立たせていた。
その頃、石塚は医務局からの電話を受けていた。
「あ、はい。分かりました。担当者と相談して早急にお返事致します。」
受話器を置くと、石塚は腕組してうなり出した。
「まいったなあ。この状態で伊藤さんを帰すのは、彼女を元に戻すには逆効果じゃないかなあ。
といって、松坂が伊藤さんを傷害事件で提訴するってものありえないしなあ。」
医務局からは、ウイルスの影響も見受けられず自力で食事が出来るなら、退院してもらうように要請があったのだ。石塚が粘りに粘って、今夜一晩は猶予を貰ったが、明日には帰らないと行けない事に成るだろう。石塚は悩んだ末に、芙美の部屋に松坂を呼びに来た。
「松坂、ちょっと。」
松坂が居なくなると、芙美は心なしかホッとしたような表情になった。
「芙美。貴方がウイルスに侵入される前、私達車の中で大はしゃぎしてたよね。貴方が松坂さんに一目ぼれしちゃって。その事が、引っかかってるんじゃないのかな。私の知ってる芙美はそんなに恐がりじゃ無かったわよ。当たって砕けろって、私にいつも言ってくれてたじゃない。」
今日子の言葉を聞いて、志穂は、はっとした。
「そうだ。私、あなたに言い忘れるところだった。この前貴方がここに入院してから今日子ちゃんに会ったの。その時、抜け殻になってるって聞いたから、居ても立っても居られなくて、あの時の貴方の好きだった男の子を探し出してきたの。松田修二君、でしょ。私、彼に会ってきたわ。あの時の事、聞かせて欲しいって頼んだの。」
芙美は明らかに狼狽して困った様に耳を塞ごうとした。
「芙美、がんばって聞いてみようよ。」
今日子が芙美を励ました。怯えるような瞳で志穂を見ている芙美を、じっと見つめ返して、志穂が言った。
「続けるよ。あの時修二君は、芙美の事凄く好きだったんだって。だから、男の子達にからかわれても、ちっとも恥ずかしくなかったんだって、むしろ誇らしかったんだって言ってたのよ。
それなのに、芙美が突然、私は関係ないなんて言うから、修二君相当ショック受けてたみたいで、しばらく落ちこんでて学校にも来なかったんですって。
私も貴方の事ばかり心配して、修二君の事まで気づかなかったんだけどね。修二君があんまり落ちこんでるから、心配になった例の男の子達が家まで謝りに言ったんだって、女の子達にそそのかされて遣ったんだって。でも、芙美はもう近づくことさえ嫌がっていたから、振られてしまったんだと思って諦めたんだって言ってたわ。
彼も、あの時のショックで女の子と付き合うのが恐くなったんだそうよ。あれから一人も彼女を作ってないって言ってたわ。」
「芙美、勇気を出してね。今、目の前に居る松坂さんは、あなたのことあきらめたりしてないわ。」
芙美の目からぽろりっと涙が一滴流れ落ちた。
「あ、りがとう。」
ドアがノックされて、松坂が帰ってきた。浮かない顔の松坂に今日子が声をかけた。
「どうかしたんですか。」
「実は、さっき医務局から連絡があって、自力で食事を取れるようになってる伊藤さんを、自宅で療養させたらどうかって言ってきたんだ。」
松坂の言葉に今日子と志穂は顔を見合わせた。
「そんな。芙美は今日やっと言葉を発せられるようになったばかりなのに。何とかならないんですか。」
今日子は松坂につかみかからんばかりに頼んだ。しかし、松坂も石塚も、帰宅要請を明日に伸ばすのがやっとの状況だった。
「ごめんね。大分がんばったんだけど、明日が限度だって言われたんだ。」
落ちこみそうな心を隠すように松坂は続けた。
「こればかりはどうしようもない。でも、伊藤さんのお宅にも時々はお見舞いに覗うよ。これっきりじゃないんだ。それより、伊藤さんのご両親にこの事を伝えてもらえるかな。」
「ええ、私達あとで寄る事になってますから。」
「よろしく頼むよ。」
松坂は今日子と志穂を見送った。
芙美の夕食を終えると、松坂は石塚を誘って小料理屋に来ていた。カウンターに座ってあれこれ注文すると、松坂は深い溜息をついてつぶやいた。
「僕は、伊藤さんに本当は嫌われてるんじゃないだろうか。今日だって、小林さんや前田さんが話しかけると、懸命に返事をしようとしているのが、そばに居ても分かるんだ。だけど、僕が話しかけると、下を向いてしまってどんどん気持ちが沈んで行く。」
「松坂、お前本当に女の子の気持ちがわかってないな。好きだから素直になれないって事もあるだろ。」
石塚は小芋の煮転がしを口に運びながら言った。
「んー、うまい。」
「まあ、石塚さんに松坂さん。お久し振りねえ。あら、どうしたの、松坂さん。随分浮かない顔してるじゃない。」
店の女将が声を掛けてきた。
「女将さん。こいつ、この歳になって恋煩いなんだよ。まったく、今まで何をやってきたんだか。」
石塚が呆れたように言うと、「石塚、うるさいよ。」と松坂も返した。女将は石塚と松坂を交互に見比べて、楽しそうに笑った。
「フフフ、石塚さんと松坂さんとじゃキャラクターが違い過ぎるわ。そんなにいじめないで上げてよ。で、もう意中の人には告白したの?」
女将に不意を付かれて、松坂は、しどろもどろになった。
「いや、それはまだ。あの。」
その様子を穏やかに見ていた女将は、さっとビールを二人の間に置いた。
「はい、これは私からの差し入れよ。これ飲んで景気つけたら、思いきってその子に告白してくれば?」
「おおー、さすが女将さん、気が利くねえ。」
石塚は楽しげにガハハハと笑いながら、次々と小皿をからにして行った。
しばらくすると、松坂がすっくと立ちあがった。
「ごちそうさま。石塚、僕はまだ遣り残した書類があるから、研究所に戻るよ。」
「ええ、もう帰るのか?」
口を尖らせて不満げな石塚だったが、芙美の事を思い出したのか途中から表情を変えると、「明日、聞かせろよ。」とだけ言った。
松坂が店を後にして歩き出すと、後ろから誰かが声を掛けてきた。
「ちょっと、松坂さん。」
振り向くと女将が追いかけてきていたのだった。
「きちんと話をするのよ。女の子はね、分かっていても口に出して言って欲しいものなの。貴方の気持ちを素直に言ってあげなさい。そして、その子を安心させてあげなさい。」
「女将さん。」
松坂は心を見透かされたようで、恥ずかしくなった。
「うまく行ったら、うちの店にも連れていらっしゃいね。じゃあ。」
女将はそれだけ言うと、店に帰っていった。松坂はその後姿に頭を下げた。
時間は8時30分を廻っていた。研究所の灯りも全部消え、非常口の灯りだけが妙に明るく辺りを照らしていた。奥の医務局の方は、まだ消灯時間になっていないからか、いくつかの部屋から灯りが漏れていた。松坂は、芙美の部屋の前まで遣ってくると、深呼吸を一つした。幸い部屋の明かりはまだついている、芙美が起きているのだ。
「こんばんは。松坂です。入りますよ。」
松坂が部屋に入ると、芙美は窓辺で外を眺めているところだった。
「伊藤さん、自分で立って歩けたの?」
松坂は目を見開いて驚いた。しかし松坂が近づくと、芙美は力が抜けたようにその場に座りこんでしまった。
「伊藤さん。大丈夫?」
松坂は慌てて芙美を抱き起こすと、ベッドまで運んでやった。そして、暫く芙美を静かに見つめていた。芙美は悲しげな瞳で、視線を反らした。松坂はふと先ほど小料理屋の女将に言われた事を想いだし、決意を新たにした。
「伊藤さん。君は僕が嫌いですか?」
穏やかだが決意を込めた言葉だった。芙美はその事に気がついたのか、松坂をそっと見上げた。
「やっと、僕の方を見てくれましたね。僕は今、松坂刑事としてではなく、松坂哲也として君に話したいことがあってきたんだ。」
芙美は身体がどんどん固くなって行くのを感じていた。それでも、必死で松坂の方を見ていようとがんばっていたのだ。
「僕は…、僕は、伊藤さんが好きです。大好きなんです。どうしても、前の君に戻ってほしい。あの、勝気でちょっと生意気で、それなのに何処かか弱くて危なっかしくて、そんな君の全部が好きなんです。」
芙美の瞳は明らかに動揺し、揺れ動いていた。
「まだ、心配ですか。君のチャットモデル、見せてもらいましたよ。小林さんからも、君がそのモデルの事で、心配しているって事も聞いています。だけど、良いんじゃないですか、きみらしくて。僕は、そう思います。」
「私、らしい…?」
芙美は心の中で氷のように固く凍てついていた部分に日差しが差し込んだような感覚を覚えていた。松坂は静かに深く頷いた。
遠くで、管理人の足音が聞えてきた。
「もう、9時になります。消灯の時間ですね。」
「もう・・・、帰るの?」
芙美はごく自然にそんな言葉を発していた。松坂は返事が出来ずに居た。このまま、そばに居たい。そんな言葉が頭をよぎっていたのだ。
管理人の足音が近くまで来ていた。時折電気の消えていない部屋に声をかけている。
「9時です。電気を消して休んでください。」
そんな声が、すぐそばで聞えた。松坂はとっさに食器棚の向こうに隠れた。その瞬間、管理人がドアをノックして、顔を出した。
「9時です。電気を消しておやすみなさい。」
芙美は、「おやすみなさい。」と小さな声で言った。
「お、お嬢ちゃん。口が利けるようになったんだね。よかったねえ。おやすみ。」
管理人はそう言って、ドアを閉め、奥の部屋へと進んで行った。その足音が遠のくのをまって、芙美は小さな声で呼んでみた。
「松坂さん。もう大丈夫ですよ。」
松坂は恐る恐る出てくると、疲れきったようにはあっと深い息を吐いた。
「ばれたら謹慎ものだな。」
松坂はそう言って小さく笑った。
「ごめんね。君の気持ちも聞かないで。でも、どうしても今夜はそばにいたかったんだ。明日になったら、君は自宅に戻らないと行けないんだ。今までのように簡単には逢えないだろう。」
松坂は芙美のベッドのそばに椅子を引き寄せると、そこに座ってゆっくりと芙美と向き合った。
「今夜、一晩中君のそばに居てもいいですか。」
松坂は芙美の手をそっと握って言った。
「はい。」
芙美は何かを誓うかのように、松坂をまっすぐ見つめてそう言った。
電気を消して、ベッドの脇の小さなスタンドをつけると、ありきたりな病室が何処か違う場所のようになった。
「段々呪縛が解けてきているんだね。」
「うん、もう身体を動かすのになんの抵抗も感じないわ。
松坂さん。ありがとう。貴方が居なければ、私は深い迷宮の中に引きずり込まれるところだった。」
松坂は首を振った。
「僕は、君の気持ちが強かったから助かったんだと思うんだ。いや、ありがとうを言うのは僕の方かもしれない。
両親が離婚した時、僕は中学生だった。言いたい事をずけずけ言い放つおふくろと、人の言うことなんかに耳を貸そうとしない親父。二人は派手なけんかを散々やって、そして離婚した。少なくとも、中学生だった僕の目にはそんな風に映っていたんだ。だから、真剣に人を好きになろう何て、思いもしなかった。
石塚に笑われたよ。いい歳をして恋煩いか。今まで何をしてきたんだってね。でも、本当に僕は何もしてこなかったんだ。ほのかな思いを抱いても、相手の気持ちが分からないと、自分のカードを出さない。そんな生き方しか、して来なかったんだ。だから、君のストレートで素直な感情表現に励まされて、ここまで来れたって言うのが本音なんだ。」
「松坂さん。」
芙美は、少し不安気に言った。
「私。。。 私は本当に貴方にふさわしいのかしら。」
ずっと抱えてきた思いを、芙美はやっと口にすることができた。
「君でないとダメなんだ。ずっとそのままの君で居て欲しい。」
芙美は心の中のわだかまりがすべて消え去ったのが分かった。そして、以前のような元気な自分を取り戻した。
「ねえ、明日退院しても、うちにお見舞いに来てくれる?」
芙美の瞳は、もういつもの勝気な輝きを取り戻していた。
「もちろんさ。」
その言葉に、芙美は満面の笑顔で答えた。松坂は急に胸が苦しくなってきた。
「その笑顔が、ずっと見たかったんだ。抱きしめてもいいですか?」
「ばか!」
芙美はそう言うと自分から松坂に飛びついて行った。松坂がそっと背中に手を回すと、芙美は不意に顔を上げ、キスをした。松坂は成す術もなくされるがままになっていた。すると、芙美がそっと離れて、頬を赤らめたまま憎らしげに言った。
「もう、私にここまでさせておいて、ぼんやりしてちゃだめでしょ。きちんと抱きしめてよ。」
そう言って、再び抱きついた。
「ごめん。こういうのに慣れてなくて。これから色々教えてもらわなくちゃね。」
松坂は照れながらも腕に力をこめた。
「そうそう、その調子。」
2人は顔を見合わせて笑った。
夜更けまで話しこんで、松坂は芙美をベッドに寝かせると、芙美が眠るまでじっと見つめていた。
「おやすみなさい。」
「おやすみ。君が眠るまで、そばに居るよ。」
そして、不覚にも、松坂はそのままベッドサイドの椅子に座って眠ってしまった。
翌朝、退院の準備のため、朝早くやってきた芙美の両親が、手を握り合って眠っている二人を目撃したのは言うまでもない。
辺りのざわめきにふと目が覚めた松坂は、周りを見渡して愕然となった。
『しまった。』
そう思ったが、今更どうすることも出来ない。呆然と見ている芙美の両親に、松坂は急いで床に座りこみ、頭を下げた。
「すみません。昨日、遅くまで芙美さんと話しこんでいて、つい眠ってしまったみたいで。」
松坂の声で芙美も目が覚めたようだった。
「どうしたの?あ、お母さん。来てくれたのね。」
いつもの表情を取り戻した芙美が、状況もわからず嬉しそうに母に言った。
「まあ、芙美。元に戻ったのね。松坂さんが昨日遅くまで掛かって芙美を治してくださったのね。ありがとうございます。」
「そうか、そう言うことだったのか。私はてっきり...」
芙美の父が言い出すのを、母が止めた。
「おとうさん、何無粋な事言ってるの。芙美が元通りになったのよ。こんな嬉しい事はないわ。それじゃあ、父さん、お会計お願いしますね。」
芙美の父は、妻に促されて会計に行った。
それを見送って、芙美の母が嬉しそうに言った。
「松坂さん。遠慮なさらずに、家にも来てやってください。芙美、そういうことなんでしょ。」
芙美の母は、嬉しそうに娘を見た。
「うん。」
芙美は恥ずかしそうに下を向いたまま、そう言った。松坂は、芙美の母が好意的だったので、ほっとして口走った。
「一生、大切にします。」
「おいおい、もうプロポーズか?」
後ろから森村刑事が来ていた。
「父さん!」
「芙美さんのお母さんですか。私はこの事件の担当をしておりました、森村です。そして、この出来そこないの父親です。」
森村は丁寧に頭を下げた。
「いやあ、しっかりしたいいお嬢さんですね。前田さんの件で、しっかり調べろと怒鳴りつけられた時には驚きました。しかし心根の優しい、いいお嬢さんだ。家の出来そこないにはもったいない。」
「いいえ、家の娘は、ご存知の通りの跳ねっかえりですから。どうぞ今後ともよろしくお願い致します。」
芙美の母も丁重にお辞儀をした。芙美の父が帰ってきたのを見て、森村が声をかけた。
「今度、一杯ご一緒しませんか。」
森村は、片手をくいっとあげて見せた。
「いいですねえ。」
状況はわからなくても酒好きの芙美の父は、楽しげに答えた。森村、松坂親子に見送られ、芙美は両親と共に帰っていった。
石塚は、ぼんやり窓の外を見ていた。
「あれ、お前が何も食べずに、考え事なんてめずらしいなあ。」
芙美を見送った松坂が席に戻ってきた。
「伊藤さん、帰ったのか?」
「ああ、帰った。なんだか、寂しいもんだな。」
松坂も石塚と同じように窓の外を眺めていた。そして、昨日あれだけ冷やかしていたのに、芙美との事を聞いてこない石塚の異変に、やっと気づいた。
「石塚。どうしたんだよ、元気無いなあ。」
石塚はふうっと溜息を吐いて、つぶやいた。
「小林さん、もう来ないんだろうな。」
「石塚.....。」
松坂は暫く考えて、石塚がいつも行くドーナツ屋を訪ねた。そして、袋に一杯のドーナツを買うと、足早に石塚の元に急いだ。
「石塚。元気出せよ。」
松坂が大きな袋を石塚の前に置くと、石塚は「おおーっ。」と歓声を上げた。
「お前はいいよ。分かりやすくて。」
松坂は小さな声で言った。
Apurの山本の店に、一人の男がやってきた。
「いらっしゃいませ。あ、佐々木さん。」
店番をしていた今日子は、驚いて声を上げた。
「えっ。佐々木?」
奥に居た山本が店先に現れた。
「おお。久しぶりだな。どうしてたんだ。」
佐々木はちょっと恥ずかしそうに下を向いて物静かな様子で話した。
「病院でちゃんと検査してもらって、もう大丈夫って太鼓判押してもらったから、暫く休養を兼ねてあちこち旅をしようかと思ってるんだ。でも、その前に色々迷惑かけたから、太一と今日子ちゃんには、一言謝りたかったんだ。」
「謝るだなんて、佐々木さんが元気に成ってくれるだけで充分です。」
今日子はやさしい眼差しで佐々木を見た。
「あ、お客さん。いらっしゃいませ。」
今日子は急いで客の方に駆け寄って行った。
「佐々木、ごめんな。ずっと気になってたんだ。僕が抜け駆けしたような気がしてしょうがなかった。」
「そんな事ないさ。今日子ちゃんが、自分で選んだんだ。俺達がどんな風にしてたって、答は一緒だったんだと思うよ。きれいになったな、今日子ちゃん。」
佐々木は明るく客に対応している今日子を目を細めてみていた。
「ああ、うちの看板娘だ。彼女が手伝ってくれるようになってから、お客さんが増えたんだ。」
山本も嬉しそうに今日子を見た。今日子は手際よく、人当たりもよかった。
「結婚式には、呼んでくれよ。じゃあな。」
佐々木はそう言うと、あたふたしている山本を残し、スーツケースを引きずって駅の方に消えて行った。
「帰ってきたら、連絡しろよ。」
山本は、佐々木が消えた方向に大声で言った。
気落ちしていた石塚に一本の電話が入った。
「はい。わかりました。ありがとうございました。」
呑気な石塚が、見たこともない程緊張していた。
「どうしたんだ。」松坂がモニターから目を離さないで聞いた。
「松坂、どうしよう。」
石塚は、よろよろと松坂のところまでふらつきながら歩み寄ると、ワッと抱きついた。
「俺達、警視総監特別賞に選ばれたんだって。」
「そんなことかよ。大袈裟だなあ。....ぬあにいいー!」
松坂は石塚の腕をわしづかみにして叫んだ。
「本当なのか?お前、寝ぼけてるんじゃないだろうな。」
「ほ、本当だよ。さっき、事務局から連絡があったんだ。例のペットウイルスの件で、世界の先進国の警察から、データを譲って欲しいって、希望が殺到しているそうだ。」
「石塚、やったなあ。あのパソコンショップのパソコンを解読したのがよかったんだ。」
「いやあ、松坂のお袋さんと芙美ちゃんが、交代で弁当届けてくれたのがよかったのかもな。」
「そうだ、例の小料理屋で前祝といくか。」
松坂はあの女将を思い出した。
「いいねえ。芙美ちゃんを連れてく約束だったんじゃないのか。電話してみろよ。」
石塚に急かされて、松坂も急いで電話した。
日が暮れて、約束通り芙美が研究所にやってきた。3人はふざけあいながら、小料理屋の暖簾をくぐった。
「いらっしゃい。あら、今日は可愛いお連れさんがいらっしゃるのね。」
女将は嬉しそうに言った。
「女将さん。先日はありがとうございました。お陰様でこうして、彼女を連れてくる事が出来ました。」
「今晩は。芙美です。松坂さんから、とてもよくして頂いてるって伺っています。これからも、よろしくお願いします。」
芙美はぺこっと頭を下げた。
「そう。しっかりしたお嬢さんね。こちらこそよろしく。」
石塚と松坂は、女将に特別賞を獲得した話しを聞かせた。すると、女将はふと手を止めて、寂しげな目をして言った。
「そう。あれは、貴方達が担当していたのね。実はあの時亡くなった男の子は、私の甥なの。生まれた時から遺伝性の病気を持っていて、妹も随分その事では心を痛めていたのよ。それがあの子には反ってよくなかったみたいで、家族にはわがまま放題、友達と言えばモニターを通した人ばかりで、実際に人と逢うって事が出来ない人間になってしまってたのね。
確かあの事件が起こる2、3日前だったかしら。妹から電話を貰ったのよ。息子がウイルスを作ってるみたいだってね。自分の息子がそんな悪い事をしているなんてって随分取り乱していたわ。」
女将は肩を落として溜息をついた。
「それで私、妹に言ってやったの。貴方は母親なんだから、ダメな事はダメだってきちんと言ってあげないと、真っ当な大人にならないわよって。
妹もその気になったみたいで、あの日、甥に注意したらしいわ。そしたら、うるさい、お前の指図は受けないって、自分の母親をひどく殴って飛び出して行ったんですって。それがあのパソコンショップだったのね。そこからは、貴方達のご存知の通りよ。
バチが当たったんだって、妹は言ってるわ。妹には他にも娘が2人居るけど、病気が出たのは甥だけだったから、他の子はいい子に育ってる。
ひょっとしたら、甥自身も亡くなって、ホッとしているのかもしれない。あの子は、ペットウイルスをやっつけるために世の中の役にたてたんですものね。」
女将は気分に区切りをつけるように、3人にビールを振舞った。石塚は、鯖の煮付けを上手そうに口に運びながら、語り出した。
「昔はさ、学力をつけてより優秀な学校に入学させるんだって、大人達が炊きつけて塾だ受験だと騒いだ挙句に、いじめだの学級崩壊だのが起きていたけど、今の子供達は学校にも週2回しか行ってないし、友達と遊ぶのも、個人レッスンで勉強するのも、インターネットを使ってたりするから、自ら実際の人間同士が関わって行こうとしない傾向にあるよね。それが今後どんなふうに社会に影響を及ぼして行くか、僕はそれが心配だな。」
「石塚、どうしたんだ。お前らしくもない。」
「なんだよ。俺だってたまには良い事言うんだよ。松坂ぁ。俺と何年の付き合い? 芙美ちゃん、しっかり教育してやってよ。」
「はい、はい。」
芙美は笑いながら頷いた。女将はそっと目じりを押さえていた。
「あはは、おかしくて涙が出ちゃう。貴方達見てると、なんだかほっとするわ。あの子も、もう少し前の時代に生まれてたらよかったのにね。さ、前祝なんでしょ。しっかり食べてってね。」
店の扉が開いて、客が入ってきた。
「いらっしゃいませ。あら、村田さん。今日は随分遅いんじゃない。お仕事忙しいの?」
女将はカウンターを勧めて、客と話し出した。松坂はその姿をじっと見つめてつぶやいた。
「こんな店がいっぱいあった時代は、よかったんだろうなあ、人情があって。」
「あら、私達の世代だって、友情や人情って、持ってるわ。ただ、それを感じる機会が少なくなってるのよね。私達が伝えて行かないといけないのよね。そういう事を。」
「がんばれよ。それが君達21世紀生まれの世代に託された使命だ。」
石塚は、ブリ大根をほおばりながら言った。
-fin-
© Rakuten Group, Inc.