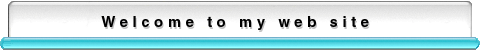遠雷は季節を告げ
人はより良き方向を目指し、それでも世界が悪しき方向に向かう、と嘆く。
それは、避けがたい世の運命だ。
紙を束ねる。これまでの些細なメモだ。
無駄な紙くずとは思わない、思わないが、それをもって外に出る。
幸い、この辺りのモンスターは一時、なりを潜めたようだ。
魔法は一言だけ。
『 炎の舌は貪欲なり 』
杖を用いる必要もなく、紙くずは炎に舐められてゆく。
「あら、思い切って」
背後から、面白がっている声がした。
振り向く気は起きず、私はそのまま炎を眺める。
「良いのかしら?折角の経験なのに」
背後に生じた気配に、足音は伴っていなかった。
だから、律儀に振り向いて答えてやる必要なんかないのだが。
「昔、ある将軍が、前任者の戦場の日記を部下から受けとった」
「ふぅん」
「将軍は、それを全て焼き捨てたそうだ」
「どうして?」
「戦況はその時々で変わるのに、古い記録にこだわれないからだよ」
全てに成功する人間など存在しない。
前任者は老いたのか、戦死したのか、いずれにせよ戦地を去った。
古い言葉を重んじる余りに、新しい目標を腐らせてはなるまい。
勇気ある将軍は、そこでは成功した。
しかし彼もまた、己の策に固執して戦場を去り、不遇に死んだと聞く。
世界は、歩みを止めない。
また歩みを止めたものにも、寛容ではないのだ。
「また、一から作り上げるの?新しい将軍のように?」
「まさか」
一から、というのは余りにも馬鹿げている。
今までに身体に刻んだ戦いの記憶を、活かせないわけではない。
将軍となった男も、その前に兵士として訓練を積み、戦ったのだ。
その経験なくしては、新しいことも始められなかっただろう。
私はただ、気持ちを切り替える儀式をしていただけだ。
様々の理由で戦場を去る戦友たち。新しく入る後生恐るべきものたち。
私はそのどちらでもなく、留まる道を択んだ。
ただ古い記憶を、将軍に差し出すだけの部下に終わりたくない。
勇者でもない、知者でもない。
豪腕でもないし、俊敏でもない。
けれど、考えることはできる。
前に踏み出す足はあり、杖を握る両手がある。
足跡をこの世界に記してゆける。
いつか、何かの形でここを去る日がくるまでは、前に進む。
それが強くなるための基礎だ。
天を仰ぎ、怒号したところで唾が降りかかるだけ。
不利?不遇?
最初から天分の才能を授けられたものでない限り、人は皆同じだ。
努力を投げ出して、菓子をねだる子供ではない。
私たちは、冒険者だ。
独りで立ってはいる。独りで力はつけてゆく。
その道に、肩を並べる戦友がいて、それを誇れればいい。
最期には、笑って去ってゆけるように。
やむを得ずに戦列を離れるものたちに、真っ直ぐな背を見せたい。
失敗を笑い、粗忽を笑われ、それでも目は彼方を見ていたい。
「しかつめらしいこと、考えてるのね」
炎が消え、白い灰だけがそこには残る。
文字は消える、けれど、記したものは紙の上だけではない。
遠雷が聞こえる。
季節の移ろいとやらが起きてから暫くして、雷は威力を落とした。
それでも、まだ、あるいはまた、私にやれることはある筈だ。
それを見つければいい。
「つまらないわ、泣き喚きも怒りもしないなんて」
ふい、と気配が消える。
人ならぬ存在は、喜怒哀楽を見て嘲笑いでもしたかったのだろうか。
或いは憑りついて、暫しそれを味わいたかっただけか。
「焦ることはないさ」
じたばたするのは、まだこれからだ。
爪を立てて崖をよじのぼり、徒手空拳で強大な相手に立ち向かう。
その時こそ、気持ちを昂ぶらせよう。
叫び、笑い、泣き、怒り、全てを世界に叩きつけよう。
言葉だけではない、己の力の放出によって。
灰は、何処からか吹いてきた風に散らされていった。
こうして消えるまでに、どのくらい新しい文字を残せるだろう。
どんな戦い方を確立できるだろう。
誰と出会い、何を得るだろうか?
呪うより、世界を笑い飛ばせるような、そんな強さを持つために。
見知らぬ土地で戦う準備を整えるべく、私はまず倉庫へと向かっていった。
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- ゲーム日記
- PS2 ソフト プレゼントキャンペーン…
- (2024-06-23 04:11:42)
-
-
-

- REDSTONE
- アップデート モンスターの能力値の…
- (2024-06-22 08:03:47)
-
-
-

- 妖怪ウォッチのグッズいろいろ
- 今日もよろしくお願いします。
- (2023-08-09 06:50:06)
-
© Rakuten Group, Inc.