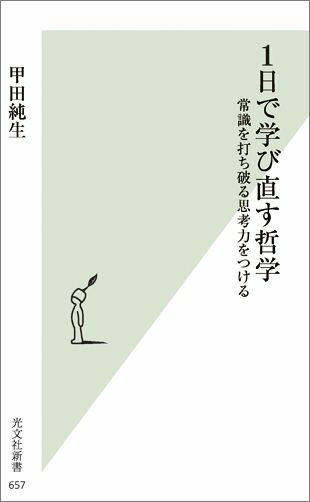PR
キーワードサーチ
フリーページ
ぱふぅ家のお勧めガジェット

フレッシュマンにおすすめ
セキュリティ対策グッズ
自分買い特集
2005年「役に立つ1冊」
2006年「役に立つ1冊」
2007年「役に立つ1冊」
2008年上期「役に立つ1冊」
2008年下期「役に立つ1冊」
2009年上期「役に立つ1冊」
2009年下期「役に立つ1冊」
2010年上期「役に立つ1冊」
2010年下期「役に立つ1冊」
2011年上期「役に立つ1冊」
2011年下期「役に立つ1冊」
2012年「役に立つ1冊」
2013年「役に立つ1冊」
2014年「役に立つ1冊」
2015年「役に立つ1冊」
2016年「役に立つ1冊」
2017年「役に立つ1冊」
2018年「役に立つ1冊」
2019年「役に立つ1冊」
2020年「役に立つ1冊」
2021年「役に立つ1冊」
2022年「役に立つ1冊」
2023年「役に立つ1冊」
2024年「役に立つ一冊」
デジタル一眼レフカメラ
4K特集
ハイレゾ特集
最新プリンタ
自作PC特集
インフルエンザ対策
花粉症対策
癒やし特集
あったかグッズ
最新PC特集
防災特集
| 著者・編者 | 甲田純生=著 |
|---|---|
| 出版情報 | 光文社 |
| 出版年月 | 2013年8月発行 |
ソクラテスの功績として最も重要なことは「ソクラテスの死」だという。キリストの死によってキリスト教が生まれたように、ソクラテスの死によって哲学が生み出されたというのだ。そして、哲学の価値は「不死」から「永遠」へと移行した。「『永遠なるものを観る』行為が、テオーリア」(72 ページ)で、英語の theory(理論)の語源となっている。
プラトンのイデア論では、真の存在は不変なものであるはずとされており、その後の西洋哲学を支配するモチーフとなる。だが、イデア論は「観察や実験によってはとらえられない領域の存在を示している」(84 ページ)という。これは自然科学とは相性が悪い。
プラトンに学んだアリストテレスは自然研究を重視しており、「生命の存在を説明しようとするときに、アリストテレスは『人が物を作る』という行為をモデルにしてしまう」(111 ページ)ため、キリスト教と相性がいい。
「近現代のフランスの哲学」の章ではベルクソンを取り上げ、顔の表情は「精神が物質を造形した」ものという。「年をとった人の顔つきには、その人の人柄、その人の人生がにじみ出ています」(137 ページ)というのはよく言われることだが、これはアリストテレスの生命観を受け継いでいる。さらに、20 世紀初頭の哲学者ジョルジュ・パタイユの著作を引き合いに出し、死への恐怖を知ったことが、人間を猿から分けた能力だと指摘する。さらに、「腐敗物や死体がおぞましいのは、それが、生命の基礎にある物質性に私たちを直面させるから」(144 ページ)と説く。これは認識を新たにさせられた。この視点で、腐敗物や排泄物、死体を扱う小説や映画を見直してみると、あらたな知見が得られそうだ。
甲田さんは「ドイツ観念論以降、哲学警は驚くほど難しくなります」(154 ページ)と断った上で、ドイツ観念論の説明を始める。
まずカントだが、認識というのは、われわれが外界から来る情報をキャッチすることではなく、それを主観で整理し対象として再構成することだという。
つまり、デカルト哲学の第一原理である「私」は、認識を成立させるための根源的条件とされる。ところがヘーゲルは、「『私』の存在というのは、お互いを認め合うという承認関係の糸が絡まり合ってできた結節点のようなもの」(183 ページ)であるため、爆弾を抱えているようなものだという。「私」が必要とされないと、ボケてしまうというのだ。
最後にハイデッカーを紹介する。アリストテレス論から発展した「存在と時間」を提唱するが、ここまで読んでくると、哲学は現代科学から乖離しているのではないかと感じる。認識の捉え方も違うし、時間と空間を分けて考えるのも相対論的ではない。
甲田さんは「おわりに」において、「哲学の醍醐味を示そうとすれば、ある程度は哲学の細部の議論を追うことが必要」(232 ページ)と述べている。
また、「『批判』というのは、『非難』とは違います。真の批判とは、物事をその根底から考え抜くことで、そのものが孕む矛盾を明らかにすることです。それゆえ批判とは、哲学のラデイカリズムがもつ力の形」(193 ページ)だという。
科学的な考え方ですら時間がかかるのに、哲学にはさらに時間をかける必要がありそうだ。仕事に追われる今の生活で哲学の時間を捻出するのは至難の業だが、少なくとも「何かを批判」するときには相応の時間をかかねかればならないと感じた。
-
【生命の多様性を再認識】生命と非生命の… 2024.06.05
-
【警備コンサルタントとしての初仕事】逃… 2024.05.18
-
【最新スペース・オペラ短編集】黄金の人… 2024.05.14