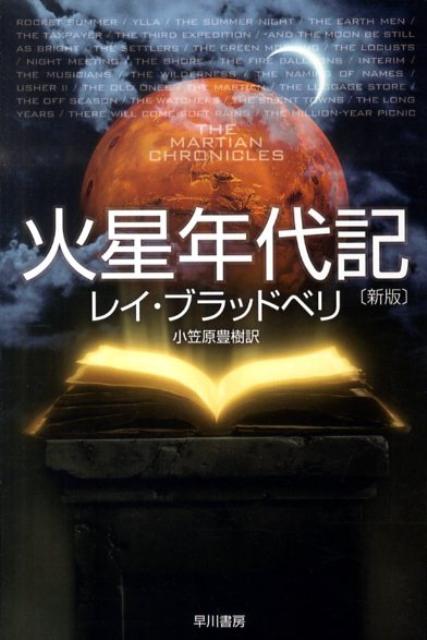PR
キーワードサーチ
フリーページ
ぱふぅ家のお勧めガジェット

フレッシュマンにおすすめ
セキュリティ対策グッズ
自分買い特集
2005年「役に立つ1冊」
2006年「役に立つ1冊」
2007年「役に立つ1冊」
2008年上期「役に立つ1冊」
2008年下期「役に立つ1冊」
2009年上期「役に立つ1冊」
2009年下期「役に立つ1冊」
2010年上期「役に立つ1冊」
2010年下期「役に立つ1冊」
2011年上期「役に立つ1冊」
2011年下期「役に立つ1冊」
2012年「役に立つ1冊」
2013年「役に立つ1冊」
2014年「役に立つ1冊」
2015年「役に立つ1冊」
2016年「役に立つ1冊」
2017年「役に立つ1冊」
2018年「役に立つ1冊」
2019年「役に立つ1冊」
2020年「役に立つ1冊」
2021年「役に立つ1冊」
2022年「役に立つ1冊」
2023年「役に立つ1冊」
2024年「役に立つ一冊」
デジタル一眼レフカメラ
最新プリンタ
自作PC特集
インフルエンザ対策
花粉症対策
癒やし特集
あったかグッズ
最新PC特集
防災特集
火星年代記 新版
| 著者・編者 | レイ・ブラッドベリ=著 |
|---|---|
| 出版情報 | 早川書房 |
| 出版年月 | 2010年7月発行 |
レイ・ブラッドベリの名作 SF『火星年代記』の“新版”である。
何が新版かというと、目次を見れば分かるが、1999 年(平成 11 年)スタートだった年代記が 2030 年(平成 42 年)スタートに変わっている。それだけでなく、いくつかの短編が追加になった。もちろん新訳は読みやすくなり、活字は大きくなり、少年時代にレイ・ブラッドベリに魅せられた我々も老眼で再び名作を楽しむことができるという仕組みだ。21 世紀に入り、レイ・ブラッドベリ自らが改訂した、最新で最後の『火星年代記』である。
最初に『火星年代記』を呼んだのは 35 年前のこと。その直後、アイザック・アシモフ『銀河帝国の興亡』シリーズを読む。『銀河帝国の興亡』が『ローマ帝国衰亡史』をオマージュしているように、火星年代記はアメリカ開拓史を彷彿とさせる。
では、本書は歴史書か。いや、違う。とはいえ、純粋な SF ではない。ファンタジーでもないし、風刺小説でもない。
もう、レイ・ブラッドベリの世界としか言いようがない。
『火星年代記』が名作であるとする私なりの理由は、本書は、読んだ人の年齢や経験に応じて、その感想が千変万化することである。
私が最初に読んだときは、これはスペースオペラだと感じた。ちょうどスター・ウォーズ(エピソード 4)が上映され、スペースオペラが息を吹き返した時期だった。本書には派手な戦闘シーンがあるわけではないが、火星人と地球人の戦いは、幼い頃に読んだ E ・ E ・スミス『レンズマン』シリーズを想起させた。
大学生の時に読み返したとき、本書は風刺小説だと感じた。エドガー・アラン・ポーやラヴクラフトを読み、体制に胡散臭さを感じていた私は、『第二のアッシャー邸』に涙したものである。
そして、わが子が大学生になろうとしている今、再び読み返してみると、これは家族の愛を描いた小説であり、生命の普遍性を謳う人間ドラマであると感じる。『長の年月』で、製造者の家族の生き写しとしてつくられたロボットたちが、にっこり笑って破壊者に対応する。破壊者は思わず、「ああ、あの連中を破壊したら殺人です!」(374 ページ)と逃げ出す。だが本編には、ロボットという言葉も、アンドロイドという言葉も登場しない。これが「レイ・ブラッドベリの世界」なのである。
何度読み返しても面白みが尽きない――これこそ小説の真骨頂ではないか。
というわけで、本書は定本として、本棚のいつでも取り出せる位置に置かれることを、強くお勧めする。ページが手垢で黒くなるまで、何度でも読み返そう。
-
【マルチヴァース宇宙へ】ミネルヴァ計画 2025.02.05
-
【銀河はダイナミック】宮沢賢治『銀河鉄… 2025.02.01
-
【天久鷹央の事件カルテ】猛毒のプリズン 2025.01.15