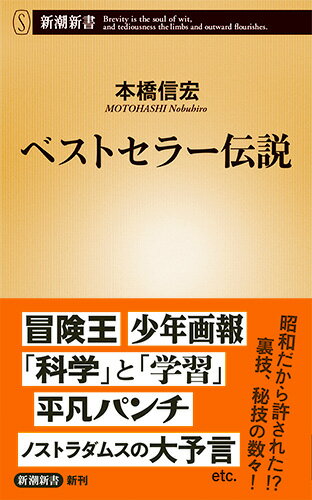PR
キーワードサーチ
フリーページ
ぱふぅ家のお勧めガジェット

フレッシュマンにおすすめ
セキュリティ対策グッズ
自分買い特集
2005年「役に立つ1冊」
2006年「役に立つ1冊」
2007年「役に立つ1冊」
2008年上期「役に立つ1冊」
2008年下期「役に立つ1冊」
2009年上期「役に立つ1冊」
2009年下期「役に立つ1冊」
2010年上期「役に立つ1冊」
2010年下期「役に立つ1冊」
2011年上期「役に立つ1冊」
2011年下期「役に立つ1冊」
2012年「役に立つ1冊」
2013年「役に立つ1冊」
2014年「役に立つ1冊」
2015年「役に立つ1冊」
2016年「役に立つ1冊」
2017年「役に立つ1冊」
2018年「役に立つ1冊」
2019年「役に立つ1冊」
2020年「役に立つ1冊」
2021年「役に立つ1冊」
2022年「役に立つ1冊」
2023年「役に立つ1冊」
2024年「役に立つ一冊」
デジタル一眼レフカメラ
最新プリンタ
自作PC特集
インフルエンザ対策
花粉症対策
癒やし特集
あったかグッズ
最新PC特集
防災特集
ベストセラー伝説
| 著者・編者 | 本橋 信宏=著 |
|---|---|
| 出版情報 | 新潮社 |
| 出版年月 | 2019年6月発行 |
著者はノンフィクション作家の本橋信宏さん。1956 年生まれだ。私より 8 歳年長なのだが、当時のベストセラーが、いかに息が長かったかを思い知らされた。「冒険王」「少年画報」「学研の科学」「平凡パンチ」「でる単」「ノストラダムスの大予言」――これらを一度でも読んだことがある方に、おすすめ。これらベストセラーの裏側は、大人になった今だから理解できる。
「ベストセラーを作るのは、目に見えちゃダメなんだよ。目に見えないけど、無いと困る本こそベストセラーになる。だから空気なんだ。空気は目に見えないけど吸わないと死んじゃう。それが本当のベストセラー」(「試験にでる英単語」著者・森一郎)
「タイトルが一番大事。(タイトル会議は)しつこくやれ、著者だけでなく社内的にも」(伊賀弘三良・祥伝社社長)
「雑誌は格調が必要。床の間が必要、そういうのがあればあとは何をやっても様になるんだな」(島地勝彦・週刊プレイボーイ元編集長)
学研の「学習」「科学」は学校で販売されていた。なぜか――後発出版社だった学研の古岡秀人社長は、公職追放された元校長たちに目を付け、子どもの教育に役立つ本の普及に同志として力を貸して欲しいと協力を求め、彼らに営業を委託したのである。元校長たちの営業力は絶大だった。さらにトラック輸送を活用し、付録の素材は自由に選べるようにした。
「でる単」の著者は、毎年東大へ大量の合格者を出していた都立日比谷高校の現役英語教師・森一郎だった。その職人芸が「でる単」を誕生させた。これに部数を奪われてはなるものかと、旺文社創業者の赤尾好夫が編集した「豆単」は、電算機を使って受験英単語の出題頻度をはじき出した。
1973 年秋、祥伝社から「ノストラダムスの大予言」が発刊された。この年、石油危機が起き、光化学スモッグ、河川汚染が問題になった。1973 年暮れに「日本沈没」が映画化され、翌74 年にはユリ・ゲラーが来日、超能力騒動が起き、スプーン曲げ、こっくりさんが大流行する。高度成長期が終わり、社会の先行きが不安になった時代だった。著者の五島勉は、本書の最後に「たしかに、「恐怖の大王」が降ってきてマルスが支配する、と書かれているけれども、人類全部が滅亡する、と明記されているわけではないからだ」と記している。
本橋さんは、こう思う――「ノストラダムスの大予言」を書いた五島勉は昭和 4 年生まれ、「日本沈没」を書いた小松左京は昭和 6 年生まれ。両者を担当した編集者の伊賀弘三良は昭和 3 年生まれ。いずれも昭和 1 桁世代である。この世代は 10 代の思春期のときに、親や教師が 8 月 5 日を境に 180 度主張を反転させた姿を目撃してきた。国家、体制に対してどこか不信感を持っている。1973 年の 2 冊の大ベストセラーも、いまの泰平を信じるな、という昭和 1 桁世代からのニヒルな警醒の書ではなかったか。(214 ページ)
子どもの頃、本書に登場するほとんどの書籍・雑誌を読んだわけだが、大人になった今、これらの出版物は、編集者たちの汗と涙の結晶ではないか――いや、怨念すら感じた次第。
出版不況と言われて久しいが、雑誌出版点数は 1970 年代の 1.5 倍、書籍出版点数に至っては 4 倍近い。子どもたちの「記憶に残る」ベストセラーは、まだまだ出せる余地はあるのではないか。なにも紙の出版物でなくてもいいだろう。
作家さんと編集者さんが心血を注いだ作品が、これからも世に出ることを願わん――。
-
【SFではなく科学】宇宙はいかに始まった… 2024.10.20
-
【大都会の迷路】Q.E.D.iff -証明終了… 2024.10.06
-
【寝台列車で密室殺人事件?】Q.E.D.if… 2024.10.05