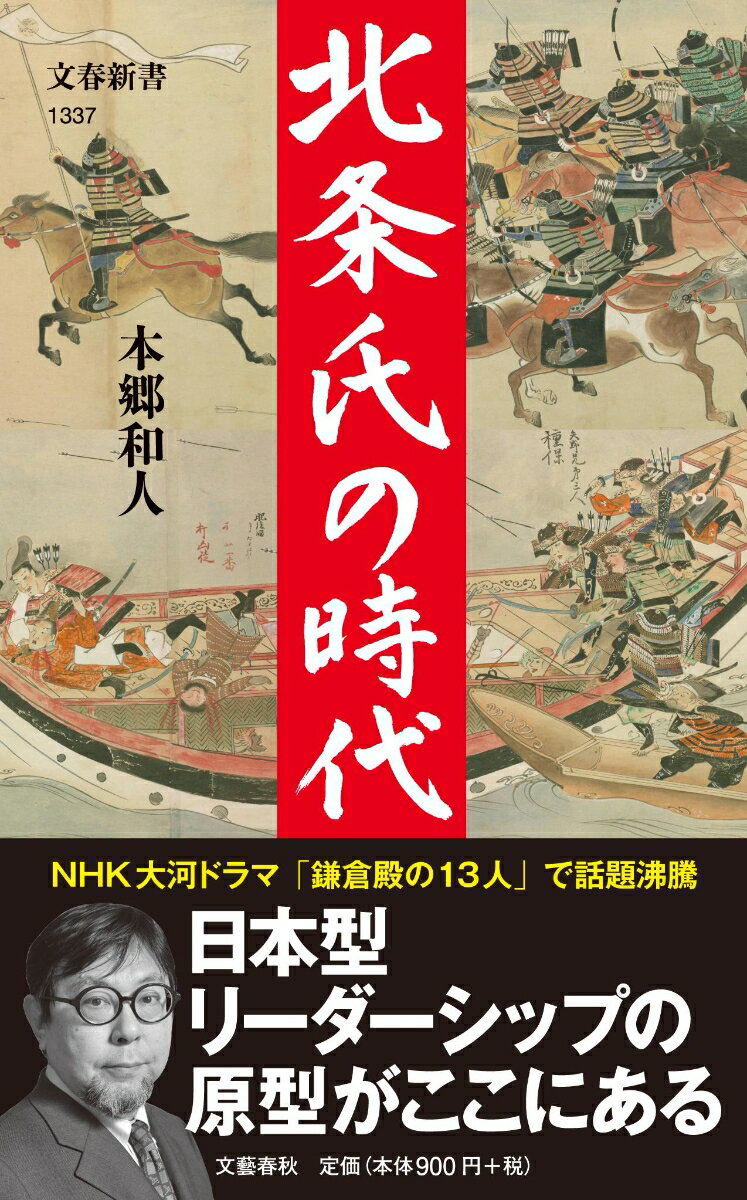PR
キーワードサーチ
フリーページ
ぱふぅ家のお勧めガジェット

フレッシュマンにおすすめ
セキュリティ対策グッズ
自分買い特集
2005年「役に立つ1冊」
2006年「役に立つ1冊」
2007年「役に立つ1冊」
2008年上期「役に立つ1冊」
2008年下期「役に立つ1冊」
2009年上期「役に立つ1冊」
2009年下期「役に立つ1冊」
2010年上期「役に立つ1冊」
2010年下期「役に立つ1冊」
2011年上期「役に立つ1冊」
2011年下期「役に立つ1冊」
2012年「役に立つ1冊」
2013年「役に立つ1冊」
2014年「役に立つ1冊」
2015年「役に立つ1冊」
2016年「役に立つ1冊」
2017年「役に立つ1冊」
2018年「役に立つ1冊」
2019年「役に立つ1冊」
2020年「役に立つ1冊」
2021年「役に立つ1冊」
2022年「役に立つ1冊」
2023年「役に立つ1冊」
2024年「役に立つ一冊」
デジタル一眼レフカメラ
最新プリンタ
自作PC特集
インフルエンザ対策
花粉症対策
癒やし特集
あったかグッズ
最新PC特集
防災特集
北条氏の時代
| 著者・編者 | 本郷和人=著 |
|---|---|
| 出版情報 | 文藝春秋 |
| 出版年月 | 2021年11月発行 |
著者の本郷和人さんは日本中世史が専門の歴史学者で、NHK 大河ドラマ『平清盛』の時代考証を担当したほか、週刊少年ジャンプで連載中の『逃げ上手の若君』(松井優征=著)の監修・記事執筆を行うなど、漫画やアニメの仕事を多くこなしている。2022 年の大河ドラマ『鎌倉殿の 13 人』だ。鎌倉幕府の始まりの「13 人」と、最後の「逃げ上手の若君」を比較してみるのも面白そうだ。承久の乱を境に、武による支配拡大から、法による統治へ移行した鎌倉幕府。朝廷から武力を取り上げ、御成敗式目という、その後の武家を統制するルールを作って、あらたしい政治体制を築いた。それ同時に、幕府の権力の中枢は、源氏の将軍家から北条氏の得宗家へ移行する。しかし、貨幣経済の波にのまれ、元との外交に失敗したことなどから凋落し、
本郷さんは冒頭、「鎌倉時代こそ、日本史の大きな転換点であると同時に、ドラマティックな面白い時代」(2 ページ)という。歴史を動かす原動力が貴族から武士へ移り、拠点は京都から東(鎌倉)へ移動。
そのなかで、天皇家を出自に持たない北条氏は、武力や陰謀力だけでなく、人脈や周到な根回しをしながら、幕府を動かす存在となっていく。
本郷さんは、以仁王の令旨に呼応し、源頼朝が鎌倉を拠点として平氏討伐に立ち上がった 1180 年を鎌倉時代の始まりと考えている。私たちが習った 1192 年
(征夷大将軍に任官)より 12 年も前のことだ。
頼朝は、朝廷に依存せず、関東武士の世界を作ろうとした。そこで、関東武士に対しては土地などの権利保障を行うことで結束を固め、朝廷に対しては東国武士の自立を認める交渉を行った。京都生まれの頼朝は、文字の読み書きすらできなかった関東武士に加え、京都から文官を集め独自の政治体制を築いていった。
ここで、時政の行き過ぎた謀略にストップをかけ、鎌倉武士たちの「世論」を集めることに成功したのが北条義時だった。義時は時政の次男であったが、頼朝の側近として経験を積み、時政の謀略を補佐した。時政を伊豆へ追放し、当主になった義時は、3 代将軍・源実朝の擁立し、侍所別当の和田義盛を追討した。政治と軍事の両方の最高権力を手に入れた義時によって、執権体制が確立される。
将軍・実朝は、京都の持つ高い文化の香りに惹かれ、後鳥羽上皇はそれを見逃さず、実朝との交流を深めた。だが、鎌倉政権は京都からの自主独立を目指したものであったから、実朝の行動は鎌倉武士の不興を買った。こうして鎌倉武士の総意を義時がまとめる形で、実朝は暗殺された。その後、源氏一族は次々に殺害される。京都からの自主独立を守るのは源氏ではなく、北条氏となっていった。
義時は、4 代将軍として、源氏より格上の皇子の下向を画策したが、これは失敗に終わり、代わりに摂関家九条家から九条頼経を迎え入れた。
この頃、幕府と朝廷の対立は決定的となり、承久の乱が起きた。
後鳥羽上皇は優秀ではあったが詰めが甘く、開戦時の幕府軍と朝廷軍の兵力差は 10 対 1 で、あっという間に幕府軍の京都入城を許してしまう。後鳥羽上皇は軍備放棄を宣言し、こうして武士による支配の時代が到来する。
義時は支配を盤石にするため容赦がなかった。戦後処理においては貴族たちを次々に処刑し、後鳥羽上皇を隠岐へ流し、没収した荘園を武士に配分した。また、六波羅探題を設置し、朝廷を監視するだけでなく、その人事権にも介入した。
1232 年、義時の後を継いだ北条泰時は御成敗式目を制定し、法による統治をスタートさせた。本郷さんは、「泰時は北条氏のなかでも、最も優秀なリーダー」(137 ページ)と評価する。御成敗式目を制定し、安定した政治システムを構築し執権制度を確立、鎌倉の都市整備を実行したからだ。御成敗式目18 条は女性への財産分与が認められていたり、8 条では 20 年間の土地占有があると変換しなくてもいいという現代の民放に繋がる条文がある。この頃、九条道家によって朝廷は有能な官人を登用し、道理に基づく公正な裁定を行うようになり、徳政を敷いていた。泰時は、六波羅探題で朝廷を相手にする中で、この徳政を知り、政治に活かしていく。
4 代執権となった北条経時は、頼経を将軍職から引きずり下ろすが、病弱で、4 年間執権を務めると、弟の時頼に後を託した。
時頼は、三浦一族を押さえ込み、極楽寺重時を加えることで朝廷と良好な関係を築いた。また、武士が荘園を管理、経営するようになり、領民に対する姿勢が変化し、時頼は民をいたわるという思想(撫民)を強調し、禅宗を保護した。
だが時頼も病弱で、1256 年に 30 歳で出家。まだ時宗が幼かったために、中継ぎとして、極楽寺重時の子の長時が第6 代執権に、つづいて北条政村が第7 代執権に就いた。
このころ貨幣経済が発展し、モノの売買によって銭を得る手段のない武士は、領地を担保に借金するしかなかった。だが、返済できなくなって領地をとられてしまう御家人が続出したことから、土地売買に関する御成敗式目の追加法が発布された。これが、のちの徳政令に繋がる。
また、元帝国の親書をもった高麗の死者が訪れた。朝廷は返書を作成するが、幕府はそれと止め、棚ざらしにした。一方で、6 代将軍宗尊親王を追放した。『吾妻鏡』の記述はここで終わる。
そうした危機が続く中の 1268 年、北条時宗が第8 代執権に就いた。だが、生まれながらにして執権の座が確約されていた時宗は、「卓越したリーダーではなかった」(206 ページ)と、本郷さんはいう。
しびれを切らした元帝国は、1274 年、博多湾へ遠征する。文永の役である。この遠征は偵察が主な任務だったようで、1 日で撤兵した。その後、元は再び使者を送り冊封体制に加わるよう要求するが、時宗はこれを拒絶し、死者を斬首してしまう。高麗、南宋を滅ぼした元は、1281 年、ふたたび日本へ軍を進め、弘安の役が起きた。
元軍の上陸を阻止した幕府軍だったが、御家人以外も動員していたため、恩賞をめぐって武士たちの間に不満が燻った。
そんななか、1284 年、時宗が 34 歳の若さで死去し、14 歳の嫡男、貞時が第9 代執権となる。
だが、幕府は貨幣経済の波にのまれ、1297 年、永仁の徳政令を発布する。貞時は得宗専制体制を維持しようとしたが、これが富と権力の集中を生み、北条氏同士で殺し合いが始まってしまう。
1301 年、貞時は出家。師時、宗宣、煕時、基時が中継ぎとなり、1316 年、貞時の嫡男、高時が第14 代執権に就く。一方、京都では、1318 年、尊治親王が即位し、後醍醐天皇が誕生した。
このころ、持明院統と大覚寺統が交代で天皇を輩出していたが、後醍醐天皇は自分の子どもに皇統を継がせようと、元弘の乱を起こす。この動きに河内の楠木正成が加勢するが、後醍醐側が敗北し、1332 年、後醍醐天皇は隠岐へ流される。
翌1333 年、隠岐を脱出した後醍醐天皇は、追討のため幕府から派遣された足利尊氏を味方に引き入れ、六波羅探題を攻略。関東で挙兵した新田義貞が鎌倉を陥落させ、ついに北条氏は滅亡する。鎌倉は、一騎打ちの時代は天然の要害だったが、集団戦の時代になり、それが通用しなくなっていた。
本郷さんは、「尊氏の決心を促したのは御家人たちの『世論』」(283 ページ)であるとし、逆に北条氏があっさり滅亡したのも、「自らが拠って立つべき御家人たちに見捨てられ」(294 ページ)たからだという。
高時の次男、北条時行は、1335 年に中先代の乱を起こし、一時的に鎌倉を奪還するが、足利尊氏によって配送させられる。その後も南朝に協力して足利軍を悩ませるが、1352 年、ついに足利軍に捕らえられ処刑された。
-
【SFではなく科学】宇宙はいかに始まった… 2024.10.20
-
【大都会の迷路】Q.E.D.iff -証明終了… 2024.10.06
-
【寝台列車で密室殺人事件?】Q.E.D.if… 2024.10.05