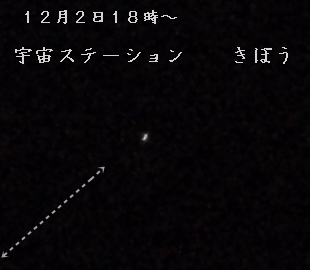いつかは、きっと…
いつかは、きっと…
由紀は、両親のひどい反対を押し切って家出をして良一と一緒になった。
「あんたはね、良一さんの《男》の部分に引っ張られているだけで、そのうちに目が覚めるから」
母が言いにくそうに、それでもそう言った意味は後で充分に分かるようになる。
雌が雄を求めて何が悪い。由紀は狂ったように良一に抱かれた。由紀は自らの淫乱性にとうに気が付いていた。そういう気性をもてあましてもいた。
ニンフォマニア、突き上げる性衝動。
卒業した学校は、世間でいうお嬢様学校だったので、友人に相談も出来ないことだった。
お嬢様とてそれなりに卑猥な情報に興味があって、噂話に興じることはあっても、私たちは上品な家系の子女でございますと仮面をかぶって生きていた。
親に紹介された青年と、コンサートや映画に行き、レストランで食事をして、紳士的に家まで送ってもらって帰る。彼らは申し分なく上品で、由紀にそれ以上のアプローチをしない。もの足りなく思っても、由紀は可憐でつつましい淑女を演じていた。
「レディたるもの、殿方に隙を見せてはいけませんよ」
それが母の口癖だった。
良一は由紀の内に野獣のような欲望が眠っていることを見抜いたのだろうか。
短大の卒業式の日、謝恩会の後で、シルクのシャンパンホワイトのパーティドレスを華奢な身体にまとった由紀は、ひどく浮ついていた。だから学生最後の日を、仲良しの三人でもう少し遊んで帰ろうということになったのだ。
「ちょっとここへ行ってみない?」
友人の一人が名刺のような黒っぽいカードを取り出して言った。
「恐くない?」
「平気、平気。実はね、昔、兄貴に連れてってもらったことがあるの。ちょっと大人びて良い感じのショットバーだったわ。」
短大とはいえ高校の延長のような生活で、少し背伸びがしてみたかっただけだ。
細い急な階段を履きなれないピンヒールで地下に降りる。黒い扉を開けると、黒い空間だった。目が慣れると、手前からずっと奥へ一列のカウンターがあり、ライトが薄ぼんやりとカウンターの上で流れていた。腰掛けた客の表情が見えないような仕組み。
「一番奥が空いている」
「いらっしゃいませ」も言わないカウンターの中の黒ずくめの男が、つぶやくように低い声で言った。
一番奥だけ、一人分のL字形になっていて、由紀はこわごわそこに座った。
「何、飲む?」
初めての経験に、三人ははしゃいだ。
スローなジャズのボーカルが低く流れる店内では、小声で話したつもりでも三人の小娘の声がかん高かったのか、先客にジロリとにらみつけられた。
座っている席のせいで、由紀は自分だけがにらまれているような気がして、戸惑った。
「なるべくアルコールの少ないカクテルをください」
冒険は、一時間程度で終わりにした。居心地がすごく悪かったからだ。
「明日、ここで待っているから」
さっき由紀をにらんだ先客が、その後ろを帰り際に通ろうとした時に、振り返りもせずにそう言った。
「え、私?」
それは不思議な感覚だった。一瞬、金縛りにあったような感覚。動けないでいると、
「由紀、早くぅ」
入り口で、友人が呼ぶ。
「面白かったね」
と、二人の友人が外に出てから肩をすくめて笑うのに、由紀は、
「少し、恐かった・・・・・・」
と青ざめたのだ。青ざめたのに、次の日に由紀は一人で、また来てしまった。
カウンターの真ん中あたりに、昨日の男が座っていた。それが良一だった。
魔法にでもかかったように、由紀は良一の隣に座る。
「由紀、やっぱり来たんだ……」
そう言われて、
「うん」
と答えてしまった。
黒ずくめのバーテンは、黙って良一のボトルで水割りを作り由紀に差し出す。
それが始まりだった。その日の彼が何を着ていたのかさえ覚えていない。覚えているのは、バーテンの黒い服だけ。
由紀の名前をどうして知ったのかと、驚いて聞くと、オトモダチガソウヨンデイタカラと良一は答えた。
良一の話は、親が紹介してくれたボーイフレンドのそれよりも大人びていて、由紀にはちょっとした感動があった。何のことはない。世間知らずの小娘がバツイチ男に翻弄されただけのことだ。数回、そのバーで会って、自宅までタクシーで送ってもらうことを繰り返す。別れ際の良一は、いつも、少し怒ったような顔をしていた。
「明日は店の前で会って、一緒に入ろう。マスターと賭けをしたんだ」
何の賭けだろうと思ったが、良一からの電話に、
「いいわ」と答えてしまった。
約束の時間に店の前に行くと、良一がいない。ドコニイルノと聞こうと思って、バッグから携帯を取り出したそのとき、
「お待たせ!」
と、肩を抱かれた。身体に触られたのは初めてでびっくりしたが、良一は自然な感じで由紀の肩を抱いたまま、急な階段を降りて店のドアを開けた。
「一番奥が空いている」
相変わらずいらっしゃいませを言わない黒ずくめの服のマスターが言った。
出されたのは、コーラと良一のボトルの水割り。最初に、マスターは由紀の前にコーラを置いた。
「逆だろう」
良一が二人のグラスを入れ替えると、マスターが意味深な笑いを返した。
「今日は車で来てるんだよ」
良一がコーラを飲むのはそういう訳かと思いながら、何故マスターがそれを知っていて、そういう行動をとったのか、初めは、由紀も不思議に思った。
「何を賭けたの?」
マスターも良一も、何も答えずに笑うだけ。
いつものように送ってもらって帰る気でいた由紀は、良一の車が別の方向を目指しているのに驚いた。
「ちょっと……」
チガウと言いかけた由紀を制して良一は、
「ラブホにタクシーで行くのは嫌だろ?」
と、たたみかけて言う。
「それが賭けだったの?」
言い終わらないうちに変わった造りの門を良一の車がくぐった。
もう、どうなっても良いと思いながら、由紀は、初めてのキスをラブホの駐車場に止まった車の中で受けたのだった。せまってくる危険に陶酔をして。
恋に狂った由紀の目には、良一は野生的で、親が紹介してくれた誰よりも魅力的な大人にみえた。その彫りが深く濃い顔も。
自分の離婚の原因は、仕事が忙しくて、家庭をかえりみなかったせいだよと良一は言う。
「私ね、仕事に燃える大人の男の人が好きよ。だから、仕事と家庭とどっちが大事?って聞くオクサンの気持ちがわからない。男の人って家族のために働いているわけじゃない?仕事をしてこそオトコじゃないの?仕事がデキル男の人の方が好き」
シゴトガデキルはずの男が、由紀と暮らすようになると、たったひと月で仕事を止めてきてしまった。
独立するんだと言う。友人たちと、起業するのだと。しかし、その友人たちに一度も会わせてもらえないまま、そのシゴトは潰れてしまった。
「チキショウ!」
良一は家の中でゴロゴロしてばかりで、ため息をつくだけだ。直に食い詰める。
「私も仕事を探すから、あなたも何か仕事をみつけて!」
由紀は、良一を励ましながら、新聞の求人広告を探した。
『求む社長秘書。容姿端麗』
行ってみれば、小さい会社の社長の愛人探しであった。
やっと、ブティックのマヌカンの仕事にありつけたが、立ち仕事で足が棒になる。それでも、二年は続いた。金持ちの中年女性向けの店であったが、名指しで呼んで洋服を選ばせる特定の顧客も出来た。
良一には未だに定職がない。
仕事のし過ぎで、家庭を顧みなかった為に離婚までした人だとは、とても思えない。
「由紀ちゃんが仕事をするから、甘えるのよ。あんたが働かなきゃ働くって」
マヌカン仲間にそう言われて由紀は納得をした。
ちょうど妊娠が分かったので良一に告げる。
「本当か?!」
喜んだ良一は、仕事を選ばず働くようになった。まずは収入のある仕事。そう考えて、ゴミ集めのパッカー車にまで乗った。年子で生まれた息子の病院のお迎えはそのパッカー車で、である。生まれたばかりの幼子を抱えて、丈の高い位置にある車の座席によじ登る。そう豊かではなかったが、人間らしい暮らしがあった。ずっと続いていたら良かったのに。
「お母さまが知ったら、嘆くかな?」
そう思っても笑みがこぼれた。由紀にとっては、めずらしいが楽しい、普通の暮らしだ。安くておいしい食事を考える。ご近所さんに子供服のお下がりを貰う。子供の背が伸びて、その服が着られなくなったらお人形の洋服に仕立て直す。ミシンなんて無いから全部が手縫い。
古い借家は雨漏りもした。洗面器やお鍋、子供のおもちゃのバケツまで総動員して、「雨漏りのうた」を歌う。「ギシギシのうた」は、建てつけの悪い玄関戸を開けるときの歌。子供と由紀は、遊びを探す天才になった。高価な玩具がなくても、いや、ないから考え付いたのだと由紀は思う。色鉛筆と裏に印刷のない紙、例えば古いカレンダーなんかをまとめて捨ててあったと良一が持ち帰った物だったが、そんなものがあれば、子供たちと遊べた。お絵かき、折り紙、紙ヒコーキ飛ばし。切り絵も喜んだ。ダンボール遊びも大好きだった。箱から出たり入ったり、人間の子供も子犬のようだ。
息子の健太が歩き出すのが遅くて、一才の誕生日になっても這っている。十三ヶ月でやっと立ったと思ったら、なんのことはない、それから一週間でちょこまか走るまでになった。
その日も、ダンボールでお家を作って遊んでいた時、まだ帰るには早い時間に良一が帰って来た。
「クビになった・・・」
聞けば、ダンボールの横流しをしていたのだという。小遣い稼ぎに。
貧しいが、お弁当を作って持たせていたし、後はタバコ代があれば良いだろう位の考えしかなかった由紀は驚いた。たいして広くない庭先に積まれたダンボールは、子供たちの遊び道具のためには量が多かった。『横流し』の一時保管だったようだ。
ゴミ屋の親方に、「社長さんと呼べ」と言われた、その社長に保証人になってもらっている借家は出ていかねばならないと言う。敷金だって社長から借りていたのだから、出て行くにも夜逃げ同然だ。
「もう、ギシギシのお家には住めないのよ」
「ギシギシ、ギシギシ♪」と、飛び回る結衣と健太に、悲しみに青ざめた由紀が言った。
あれ以来、三日が経っても寝床から出てこようとしない良一に、
「起きてよ」
と言うと、
「起きたら腹が減るだろう」
怒ったような声だ。
「呆れた」
新聞の折込み広告を見て先のことを考えながら、由紀はそう言った。
「面接に行ってくるから、子供たちを見ててね」
そこには、『制服、寮、託児所有り』と明記されていた。
その手の水商売が、ピンクサービス系のものであることを由紀は知らない。
「ピンクじゃありませんよ」
黒服は満面の笑みをたたえてそう言う。コンパニオンさんと呼ばれる女性たちの制服はお尻すれすれの短さだった。由紀は目を丸くする。
「あなたみたいな素人っぽい人が人気がでるんですよ!」
寮は、ワンルームマンションのような洒落たところではなく、六畳一間のアパートで、夜は託児所になる部屋である。ほとんどの荷物を捨ててこなければならない。だが、他に行く所がなかった。実家は飛び出したときに忘れた。大反対をした両親に泣きつくことはできない。
勤めてみれば、ピンクサービスをしないと黒服は言ったのに、周りでそれらしきことをしている。
「手を使ってするサービス、口と本番はしないんだから」
「あんたねえ、子供もいるんだろ?お嬢さんじゃあるまいし!」
由紀は無理にしなくても良いという黒服の言葉を信じていた。ところが、付いた客が強要する。断れば指名にならない。
「ヒロミちゃん、お金に困っているんだろ?ふっきるとね、収入が増えるよ。みんな最初はあんたみたいだったんだよ」
ヒロミとは由紀の源氏名である。
託児所で子供同士が仲良くなったミドリという先輩が、由紀をかばってくれた。
「出来ません・・・」
泣きそうになると、
「お客さん、代わりに私がするから」
ミドリがどこからか現れて、助けてくれた。
「ありがとう」
礼をいうと、ミドリは苦々しく笑った。
「良いけどね、あんた、私の収入の半分もないよ」
それから一月後、由紀はとうとう高熱を出した。夜は託児所に変わる寮の部屋では、寝ているわけにもいかない。良一は仕事を探すと言って出かけたっきり、二週間も帰ってこないままだ。
「ダンナが帰って来るまで、ウチで寝てなよ」
ミドリがなにくれとなく面倒をみてくれる。お互いさまと大きな目を細めて笑いながら。
だが四日経っても、高熱がひかない。
「これ使って、病院へ行ってきなよ」
差し出されたのは、保険証だった。
「ないんだろ?私も持ってない。黒服に借りたさ。奥さんの名前、使うといい」
医者は、神経的なものかな? と言って、点滴をしてくれた。
あくる日、ウソのように熱が下がったが、まだフラフラとする。
「子供は私がみててやるからさ、寝てな」
ミドリに言われ、その好意にすがって由紀は死んだように眠った。夢すらも見なかった。一切の感情を捨てて、眠りにまかせた。
熱が下がっても、由紀は仕事に行く気力がなかった。すでに限界であった。ミドリの好意に甘えて、言われるままに彼女の部屋にいた。一週間後、酔って上機嫌のミドリが笑いながら帰ってきた。
「はーい、面白いもん拾ったよォ。託児所にうちのチビ迎えにいったらさ
ぁ、戸口のとこにかしこまってる奴がいてさぁ」
良一が帰って来たのだった。
それからは、良一が持って帰ったお金でアパートを借りて、品の良い店にも勤め変えることが出来たけれど、落ち着いたら落ち着いたで、良一は仕事を変えては、最後は給料を貰えない辞め方をする。
今度だって、いつまで持つだろう。もう結論を出すことを考えた方が良いのだろうか。「今度こそ、頑張る」は何回聞いたことだろう。
と、玄関のチャイムが鳴った。玄関といっても、たたきがあって、すぐに台所だ。娘の結衣が開けたドアの向こうには、七年ぶりのひどく悲しげな由紀の母の顔があった。
由紀は、両親のひどい反対を押し切って家出をして良一と一緒になった。
「あんたはね、良一さんの《男》の部分に引っ張られているだけで、そのうちに目が覚めるから」
母が言いにくそうに、それでもそう言った意味は後で充分に分かるようになる。
雌が雄を求めて何が悪い。由紀は狂ったように良一に抱かれた。由紀は自らの淫乱性にとうに気が付いていた。そういう気性をもてあましてもいた。
ニンフォマニア、突き上げる性衝動。
卒業した学校は、世間でいうお嬢様学校だったので、友人に相談も出来ないことだった。
お嬢様とてそれなりに卑猥な情報に興味があって、噂話に興じることはあっても、私たちは上品な家系の子女でございますと仮面をかぶって生きていた。
親に紹介された青年と、コンサートや映画に行き、レストランで食事をして、紳士的に家まで送ってもらって帰る。彼らは申し分なく上品で、由紀にそれ以上のアプローチをしない。もの足りなく思っても、由紀は可憐でつつましい淑女を演じていた。
「レディたるもの、殿方に隙を見せてはいけませんよ」
それが母の口癖だった。
良一は由紀の内に野獣のような欲望が眠っていることを見抜いたのだろうか。
短大の卒業式の日、謝恩会の後で、シルクのシャンパンホワイトのパーティドレスを華奢な身体にまとった由紀は、ひどく浮ついていた。だから学生最後の日を、仲良しの三人でもう少し遊んで帰ろうということになったのだ。
「ちょっとここへ行ってみない?」
友人の一人が名刺のような黒っぽいカードを取り出して言った。
「恐くない?」
「平気、平気。実はね、昔、兄貴に連れてってもらったことがあるの。ちょっと大人びて良い感じのショットバーだったわ。」
短大とはいえ高校の延長のような生活で、少し背伸びがしてみたかっただけだ。
細い急な階段を履きなれないピンヒールで地下に降りる。黒い扉を開けると、黒い空間だった。目が慣れると、手前からずっと奥へ一列のカウンターがあり、ライトが薄ぼんやりとカウンターの上で流れていた。腰掛けた客の表情が見えないような仕組み。
「一番奥が空いている」
「いらっしゃいませ」も言わないカウンターの中の黒ずくめの男が、つぶやくように低い声で言った。
一番奥だけ、一人分のL字形になっていて、由紀はこわごわそこに座った。
「何、飲む?」
初めての経験に、三人ははしゃいだ。
スローなジャズのボーカルが低く流れる店内では、小声で話したつもりでも三人の小娘の声がかん高かったのか、先客にジロリとにらみつけられた。
座っている席のせいで、由紀は自分だけがにらまれているような気がして、戸惑った。
「なるべくアルコールの少ないカクテルをください」
冒険は、一時間程度で終わりにした。居心地がすごく悪かったからだ。
「明日、ここで待っているから」
さっき由紀をにらんだ先客が、その後ろを帰り際に通ろうとした時に、振り返りもせずにそう言った。
「え、私?」
それは不思議な感覚だった。一瞬、金縛りにあったような感覚。動けないでいると、
「由紀、早くぅ」
入り口で、友人が呼ぶ。
「面白かったね」
と、二人の友人が外に出てから肩をすくめて笑うのに、由紀は、
「少し、恐かった・・・・・・」
と青ざめたのだ。青ざめたのに、次の日に由紀は一人で、また来てしまった。
カウンターの真ん中あたりに、昨日の男が座っていた。それが良一だった。
魔法にでもかかったように、由紀は良一の隣に座る。
「由紀、やっぱり来たんだ……」
そう言われて、
「うん」
と答えてしまった。
黒ずくめのバーテンは、黙って良一のボトルで水割りを作り由紀に差し出す。
それが始まりだった。その日の彼が何を着ていたのかさえ覚えていない。覚えているのは、バーテンの黒い服だけ。
由紀の名前をどうして知ったのかと、驚いて聞くと、オトモダチガソウヨンデイタカラと良一は答えた。
良一の話は、親が紹介してくれたボーイフレンドのそれよりも大人びていて、由紀にはちょっとした感動があった。何のことはない。世間知らずの小娘がバツイチ男に翻弄されただけのことだ。数回、そのバーで会って、自宅までタクシーで送ってもらうことを繰り返す。別れ際の良一は、いつも、少し怒ったような顔をしていた。
「明日は店の前で会って、一緒に入ろう。マスターと賭けをしたんだ」
何の賭けだろうと思ったが、良一からの電話に、
「いいわ」と答えてしまった。
約束の時間に店の前に行くと、良一がいない。ドコニイルノと聞こうと思って、バッグから携帯を取り出したそのとき、
「お待たせ!」
と、肩を抱かれた。身体に触られたのは初めてでびっくりしたが、良一は自然な感じで由紀の肩を抱いたまま、急な階段を降りて店のドアを開けた。
「一番奥が空いている」
相変わらずいらっしゃいませを言わない黒ずくめの服のマスターが言った。
出されたのは、コーラと良一のボトルの水割り。最初に、マスターは由紀の前にコーラを置いた。
「逆だろう」
良一が二人のグラスを入れ替えると、マスターが意味深な笑いを返した。
「今日は車で来てるんだよ」
良一がコーラを飲むのはそういう訳かと思いながら、何故マスターがそれを知っていて、そういう行動をとったのか、初めは、由紀も不思議に思った。
「何を賭けたの?」
マスターも良一も、何も答えずに笑うだけ。
いつものように送ってもらって帰る気でいた由紀は、良一の車が別の方向を目指しているのに驚いた。
「ちょっと……」
チガウと言いかけた由紀を制して良一は、
「ラブホにタクシーで行くのは嫌だろ?」
と、たたみかけて言う。
「それが賭けだったの?」
言い終わらないうちに変わった造りの門を良一の車がくぐった。
もう、どうなっても良いと思いながら、由紀は、初めてのキスをラブホの駐車場に止まった車の中で受けたのだった。せまってくる危険に陶酔をして。
恋に狂った由紀の目には、良一は野生的で、親が紹介してくれた誰よりも魅力的な大人にみえた。その彫りが深く濃い顔も。
自分の離婚の原因は、仕事が忙しくて、家庭をかえりみなかったせいだよと良一は言う。
「私ね、仕事に燃える大人の男の人が好きよ。だから、仕事と家庭とどっちが大事?って聞くオクサンの気持ちがわからない。男の人って家族のために働いているわけじゃない?仕事をしてこそオトコじゃないの?仕事がデキル男の人の方が好き」
シゴトガデキルはずの男が、由紀と暮らすようになると、たったひと月で仕事を止めてきてしまった。
独立するんだと言う。友人たちと、起業するのだと。しかし、その友人たちに一度も会わせてもらえないまま、そのシゴトは潰れてしまった。
「チキショウ!」
良一は家の中でゴロゴロしてばかりで、ため息をつくだけだ。直に食い詰める。
「私も仕事を探すから、あなたも何か仕事をみつけて!」
由紀は、良一を励ましながら、新聞の求人広告を探した。
『求む社長秘書。容姿端麗』
行ってみれば、小さい会社の社長の愛人探しであった。
やっと、ブティックのマヌカンの仕事にありつけたが、立ち仕事で足が棒になる。それでも、二年は続いた。金持ちの中年女性向けの店であったが、名指しで呼んで洋服を選ばせる特定の顧客も出来た。
良一には未だに定職がない。
仕事のし過ぎで、家庭を顧みなかった為に離婚までした人だとは、とても思えない。
「由紀ちゃんが仕事をするから、甘えるのよ。あんたが働かなきゃ働くって」
マヌカン仲間にそう言われて由紀は納得をした。
ちょうど妊娠が分かったので良一に告げる。
「本当か?!」
喜んだ良一は、仕事を選ばず働くようになった。まずは収入のある仕事。そう考えて、ゴミ集めのパッカー車にまで乗った。年子で生まれた息子の病院のお迎えはそのパッカー車で、である。生まれたばかりの幼子を抱えて、丈の高い位置にある車の座席によじ登る。そう豊かではなかったが、人間らしい暮らしがあった。ずっと続いていたら良かったのに。
「お母さまが知ったら、嘆くかな?」
そう思っても笑みがこぼれた。由紀にとっては、めずらしいが楽しい、普通の暮らしだ。安くておいしい食事を考える。ご近所さんに子供服のお下がりを貰う。子供の背が伸びて、その服が着られなくなったらお人形の洋服に仕立て直す。ミシンなんて無いから全部が手縫い。
古い借家は雨漏りもした。洗面器やお鍋、子供のおもちゃのバケツまで総動員して、「雨漏りのうた」を歌う。「ギシギシのうた」は、建てつけの悪い玄関戸を開けるときの歌。子供と由紀は、遊びを探す天才になった。高価な玩具がなくても、いや、ないから考え付いたのだと由紀は思う。色鉛筆と裏に印刷のない紙、例えば古いカレンダーなんかをまとめて捨ててあったと良一が持ち帰った物だったが、そんなものがあれば、子供たちと遊べた。お絵かき、折り紙、紙ヒコーキ飛ばし。切り絵も喜んだ。ダンボール遊びも大好きだった。箱から出たり入ったり、人間の子供も子犬のようだ。
息子の健太が歩き出すのが遅くて、一才の誕生日になっても這っている。十三ヶ月でやっと立ったと思ったら、なんのことはない、それから一週間でちょこまか走るまでになった。
その日も、ダンボールでお家を作って遊んでいた時、まだ帰るには早い時間に良一が帰って来た。
「クビになった・・・」
聞けば、ダンボールの横流しをしていたのだという。小遣い稼ぎに。
貧しいが、お弁当を作って持たせていたし、後はタバコ代があれば良いだろう位の考えしかなかった由紀は驚いた。たいして広くない庭先に積まれたダンボールは、子供たちの遊び道具のためには量が多かった。『横流し』の一時保管だったようだ。
ゴミ屋の親方に、「社長さんと呼べ」と言われた、その社長に保証人になってもらっている借家は出ていかねばならないと言う。敷金だって社長から借りていたのだから、出て行くにも夜逃げ同然だ。
「もう、ギシギシのお家には住めないのよ」
「ギシギシ、ギシギシ♪」と、飛び回る結衣と健太に、悲しみに青ざめた由紀が言った。
あれ以来、三日が経っても寝床から出てこようとしない良一に、
「起きてよ」
と言うと、
「起きたら腹が減るだろう」
怒ったような声だ。
「呆れた」
新聞の折込み広告を見て先のことを考えながら、由紀はそう言った。
「面接に行ってくるから、子供たちを見ててね」
そこには、『制服、寮、託児所有り』と明記されていた。
その手の水商売が、ピンクサービス系のものであることを由紀は知らない。
「ピンクじゃありませんよ」
黒服は満面の笑みをたたえてそう言う。コンパニオンさんと呼ばれる女性たちの制服はお尻すれすれの短さだった。由紀は目を丸くする。
「あなたみたいな素人っぽい人が人気がでるんですよ!」
寮は、ワンルームマンションのような洒落たところではなく、六畳一間のアパートで、夜は託児所になる部屋である。ほとんどの荷物を捨ててこなければならない。だが、他に行く所がなかった。実家は飛び出したときに忘れた。大反対をした両親に泣きつくことはできない。
勤めてみれば、ピンクサービスをしないと黒服は言ったのに、周りでそれらしきことをしている。
「手を使ってするサービス、口と本番はしないんだから」
「あんたねえ、子供もいるんだろ?お嬢さんじゃあるまいし!」
由紀は無理にしなくても良いという黒服の言葉を信じていた。ところが、付いた客が強要する。断れば指名にならない。
「ヒロミちゃん、お金に困っているんだろ?ふっきるとね、収入が増えるよ。みんな最初はあんたみたいだったんだよ」
ヒロミとは由紀の源氏名である。
託児所で子供同士が仲良くなったミドリという先輩が、由紀をかばってくれた。
「出来ません・・・」
泣きそうになると、
「お客さん、代わりに私がするから」
ミドリがどこからか現れて、助けてくれた。
「ありがとう」
礼をいうと、ミドリは苦々しく笑った。
「良いけどね、あんた、私の収入の半分もないよ」
それから一月後、由紀はとうとう高熱を出した。夜は託児所に変わる寮の部屋では、寝ているわけにもいかない。良一は仕事を探すと言って出かけたっきり、二週間も帰ってこないままだ。
「ダンナが帰って来るまで、ウチで寝てなよ」
ミドリがなにくれとなく面倒をみてくれる。お互いさまと大きな目を細めて笑いながら。
だが四日経っても、高熱がひかない。
「これ使って、病院へ行ってきなよ」
差し出されたのは、保険証だった。
「ないんだろ?私も持ってない。黒服に借りたさ。奥さんの名前、使うといい」
医者は、神経的なものかな? と言って、点滴をしてくれた。
あくる日、ウソのように熱が下がったが、まだフラフラとする。
「子供は私がみててやるからさ、寝てな」
ミドリに言われ、その好意にすがって由紀は死んだように眠った。夢すらも見なかった。一切の感情を捨てて、眠りにまかせた。
熱が下がっても、由紀は仕事に行く気力がなかった。すでに限界であった。ミドリの好意に甘えて、言われるままに彼女の部屋にいた。一週間後、酔って上機嫌のミドリが笑いながら帰ってきた。
「はーい、面白いもん拾ったよォ。託児所にうちのチビ迎えにいったらさ
ぁ、戸口のとこにかしこまってる奴がいてさぁ」
良一が帰って来たのだった。
それからは、良一が持って帰ったお金でアパートを借りて、品の良い店にも勤め変えることが出来たけれど、落ち着いたら落ち着いたで、良一は仕事を変えては、最後は給料を貰えない辞め方をする。
今度だって、いつまで持つだろう。もう結論を出すことを考えた方が良いのだろうか。「今度こそ、頑張る」は何回聞いたことだろう。
と、玄関のチャイムが鳴った。玄関といっても、たたきがあって、すぐに台所だ。娘の結衣が開けたドアの向こうには、七年ぶりのひどく悲しげな由紀の母の顔があった。
© Rakuten Group, Inc.