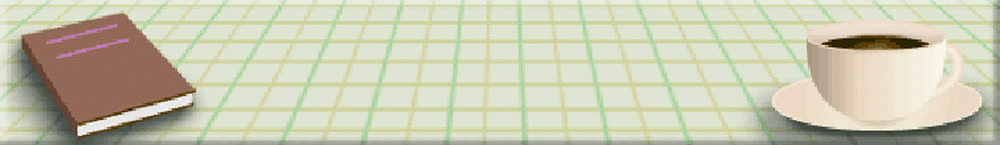企業活性化、再生の本
著者名:遠藤功
出版社:東洋経済新報社
紹介:トヨタ、花王、アスクル、ドン・キホーテなど強い現場を持つ企業の取組みを通して強い現場をつくる7つの条件を説きます。(04年3月読了)
感想:以下の点に共感しました。
・企業をどのような断面で見るかによって、「強い企業」の定義やものさしは変わってくる。しかし、肝心なことは収益性、株価、CS、ブランド価値といったものさしは、あくまで企業活動の「結果」を測る指標であって、その企業の「実体」を表すものではないということだ。
・「強い企業」とは「高い経営品質を誇る企業」と言い換えることができる。目先の業績だけにとらわれることなく、持続的な競争優位性の構築に成功している企業は、経営全体の品質がきわめて高い。
・マイケル・ポーターは、競争優位を生み出すための基本戦略は三つしかないと言い切る。その三つとは、「コスト・リーダーシップ」「差別化」「集中」である。
・とかくカリスマリーダーとしてのゴーン社長に目がいくが、成果を生み出しているのはあくまで日産の現場である。ゴーン社長のリーダーシップと現場の底力があってこそ、日産の奇跡の復活は実現されたのである。
・ヤマト運輸の小倉昌男前会長はこう指摘している。「事業発展の鍵は、あくまで(1)努力、(2)人材、(3)経営戦略の順である」
・ビジョンや戦略自体に実行性は担保されていない。競争戦略を「正しくやりきる」主役はあくまで企業におけるオペレーションを担う現場であり、現場こそが企業価値を生み出す主役である。
・12期連続増収増益を果たしたドン・キホーテには、「主権在現」という言葉がある。「ビジネスの主権は現場にある」という意味であり、現場への権限委譲を徹底させている。
・トヨタ、花王、セブンーイレブン、ヤマト運輸といった「強い企業」が共通してめざしているものを平たく言うと、「正しいことを正しくやりつづける」ことのできる企業である。
・数学のノーベル賞といわれるフィールズ賞を受賞した京都大学名誉教授の広中平祐氏は、人間の持つ可能性についてこう語っている。
「人間は生まれながらにして、湧き出る泉の根源のようなものをもっている。その根源を『湧源』という。機械と違って、人間は総て湧源性をもって生まれる。その湧源性が活性化されているか押しつぶされているかどうかで、能力や生甲斐に差が生まれる」
・現場力とは、放っておくと途切れたり、部分最適になってしまう「業務の鎖」の結束を強め、一連の仕事の流れから生み出される価値を最大化する組織能力と言い換えることができる。
・トヨタには「前工程は神様、後工程はお客様」という言葉がある。前工程では自分ができない仕事をやってくれているから「神様」、後工程は自分の仕事を引き継いでくれるから「お客様」という考え方である。
・同様に、ヤマト運輸の小倉昌男前会長は、「前だけでなく、後ろにも、横にも目をつけろ」と指摘する。「仕事はつながってこそ価値を生む」という業務連鎖の思想がこうした言葉には込められている。
・圧倒的な現場力を誇るトヨタでは、品質vsスピード、機能vsコスト、スタイリングvs実用性といった、一見両立が困難と思われる目標にチャレンジしつづけることが「トヨタらしさ」の本質であると定義している。花王やトヨタにみられる「二律背反克服の精神」こそが、強い現場を根っこで支えている。
・トヨタに「三現主義」という言葉がある。三現とは「現地」「現物」「現実」のことであり、トヨタの社員に染み込んでいるDNAのひとつである。
・頭でああだこうだと考えるよりも、まず現地に飛び、現物を確認し、現実を認識することが何よりも重要であり、それがすべての思考、行動の出発点となるべきだという考え方である。
・あらゆるデータや情報が苦もなく入手できるようになると、経営者、管理職、そして現場従事者までもがそれらを見るだけで今現場で何が起きているのかを分かった「気」になってしまう。これが怖い。
・46歳の若さでP&Gの最高マーケティング責任者(CMO)に就任したジェームズ・ステンジェル氏は、来日するとP&Gファー・イースト本社のある神戸市内のごく普通の家庭を訪問するという。近所の家並みや商店の様子を歩いて見て回り、部屋のつくりやトイレの様子をつぶさに観察する。そして、今使っている洗剤やシャンプーをなぜ選んでいるのか、洗剤の計算はどのようにしているのかなどを矢継ぎ早に質問する。
・相当な容量を持つ添付資料が付いたメールが飛び交い、役に立つ情報なのかどうかも重いファイルを開けてみなくては分からない。そうした情報が飛び交っているため、販売会社側はやがてファイルを開けることもしなくなり、逆に重要な情報の共有されないということも起きていた。
・すべての現場が一様に素晴らしいのではない。ましてや聖域などではない。「強い現場」「良い現場」もあれば、「弱い現場」「悪い現場」も存在する。「強い現場」も放っておけば、腐りはじめ、閉鎖的、内向きになってしまう。現場とは企業の「誇り」でもある一方、「恥部」にもなりうるものである。
・真の現場主義とは、現場を妄信するのではなく、経営と現場が一体となって切磋琢磨することに他ならない。「現場のことは現場」という無責任な現場放任主義はもう通用しない。現場を腐らせないのは経営者の責務である。
・国連難民高等弁務官として活躍された緒方貞子氏は、日本人の特質についてこう語っている。「人間は仕事を通して成長していかなければなりません。その鍵となるのは好奇心です。常に問題を求め、積極的に疑問を出していく『心』と『頭』が必要なのです。開かれた頭で、何かを求めていく姿勢がなければなりません。日本人は答えはきっちり出すが、問題を出してこないという欠陥があるように思われます」。
・現状に満足することなく、常に問題点を探し出そうとする自律神経を現場に埋め込むことが何より重要である。
・「汗をかく現場」から「知恵を出す現場」への変身が求められているのである。
・ワタミがめざしているのは、徹底的なクレームの検証を通じて、現場が経験値を上げることである。居酒屋・外食チェーンのサービス品質は現場でしか担保できない。すべての「真実の瞬間」は現場で起きている。
・世界に冠たる石油会社エクソンモービルは、世界中にオペレーションを展開しているが、石油の精製から調達、物流、販売に至るまで、すべての現場を熟知している本社担当役員が世界中を飛び回り、「現場監査」を日常的に行っている。その監査は社内では「コールド・アイ・レビュー」(冷徹な目による監査)と呼ばれ、各国の経営者、現場責任者に恐れられている。
・このレビューは半年に一度、2~3日をかけて実施される。生産性や効率性が世界中の現場と比較され、そして公表される。そこでは、劇的な改善を実現したり、新しい革新的なプロセスを生み出した現場が評価される一方で、改善が見られない現場の責任者は厳しくその責任を問われる。そこには「現場は尊い」などという甘い考えはない。そこにあるのは、「自ら向上し、進化しようとする強い現場だけが生き残る」という本来の現場主義の精神である。
・本来、「戦略」と「実行」は車の両輪みたいなものであり、切り離して考えること自体がナンセンスである。
・そもそも戦略の「実行性」とは「適社性」「納得性」という二つの要素で構成されている。
・「強い現場」をつくるために最も大切なことは、オペレーション力、すなわち現場力に対するしっかりとした「企業哲学」を確立することである。「現場こそが企業経営を支える屋台骨であり、競争力を大きく左右する」ということを、経営トップから現場の従業員に至るまで全員に浸透させなければならない。
・「全員参加」「徹底してやる」―この二つの言葉は現場力の本質を表している。そして、これを実行するためには「現場がエンジン」という考え方・哲学を全員が腹に落として理解しなければならない。
・ノードストロームの規則 その一―どのような状況においても、自分で考え、最善の判断を下すこと。これ以外の規則はありません。
・どの企業でも、独自の「ウェイ」を編み出したり、冊子をつくったりすることはできるだろう。しかし、重要なのは従業員全員がその基本哲学に共感し、一人ひとりが実践することである。
・現場力を信奉するノードストロームにおいて、新入社員に伝えられる次の言葉が、「基本精神を共有する」ことの重要性を物語っている。
・「当社では、社員は最大限、自主性を発揮できます。細かいことまであれこれ指図する人間はいません。制約になるのは、本人の能力だけです。しかし、顧客を幸せにするためにはどんなことでもやるという心構えがないのであれば、当社には合っていないのです。そうであれば、入社しない方がいい。社員であれば、そうなるのが当然なのです」。
・立ち上げたばかりの小さな組織では、創業者であろうが、その肩書きや、階層、機能に関係なく全員が同じ目的に向かって複数の仕事をこなすのが当たり前である。
・社内のコミュニケーションはきわめて蜜であり、情報の滞留もなく、意思決定も早い。会社が今、どんな状態にあるのかが肌感覚で分かり、問題があれば一致団結し、協力することを惜しまない。
・ところが、企業が成長し、関わる従業員が増えてくると、当然のことながら、組織は専門化、分化していく。部門や個人の仕事はより明確に分けられ、他との「境界線」がはっきり規定される。
・拠点も地理的に分散し、コミュニケーションは形式的になり、人間同士の「触れ合い」はどんどん薄くなる。「ひとつの会社」でありながら、一体感は希薄になり、「見えない境界線」が会社の運命を困難にする。これはどの組織も避けては通れない「成長の宿命」なのである。
・「事業部の論理」が「経営の論理」に優先してまかり通ってしまっている企業は決して少なくない。現場とは企業の総合力を働かせるところである。そのためには、放っておくとできてしまうタコツボ意識を常に払拭する努力、すなわち「ツボ割り」が不可欠なのである。
・トヨタや花王では、ものごとが決定されるまでは、喧々諤々議論する。しかし、いったん決まったら、後は一致団結して、粛々と実行し、結果を出す。
・一方、現場力の弱い企業では、ものごとが決まるまでは押し黙っているくせに、決定され実行される段階になると、「俺は反対だった」と言い出す人が出てくる。
・現場力は「健全な意見の対立」があってこそ、鍛えられていく。健全なぶつかり合いをさけてはならない。ギクシャクすることを恐れてはいけない。トヨタという会社の凄いところは、愚直なまでに「意見のぶつかり合い」をすることである。
・17年連続で二桁増益を続けている化粧品世界最大手のロレアルでは、創業以来「誰でも間違える権利がある」を不文律にしている。たとえミスを犯しても、もう一度別のポジションでチャンスを与える。
・ミスを恐れるばかりに社員が事なかれ主義になるよりも、リスクをとって挑戦する気持ちを現場に植え付けることが同社の競争力の源泉となっている。
・2600万枚ものフリースを売り上げ、一躍、カジュアルウェアの代名詞となった「ユニクロ」を展開するファーストリテイリングの創業者・柳井正会長はこう指摘する。「失敗するのは当たり前。誰だって失敗するし、失敗することを恐れていては、新しいものは何も生まれてこない」。
・目先の成功・失敗だけにとらわれず、中長期の観点から現場の力を最大限に引き出すことこそが、まさに経営の役割である。
・PDCAサイクルが定着しているトヨタでは、さらに進化して「PDCAA」という新たなサイクルが展開されている。これは従来のサイクルに「Achievement」(効果検証)」というステップを加えたものである。
・改善、すなわちActionがどのような効果をもたらしたのかをきちっと検証することが重要であることを再認識しようというものである。改善することに満足してしまうことを戒め、常に改善の「質」を問い、「やりっぱなしにしない」という現場の覚悟が表れている。
・世の中には「改革」という言葉に踊らされて、改善を軽視する風潮があるが、トヨタや花王が実践している改善は実に奥が深い。表面的な症状だけで右往左往していたのでは、本質的な問題を解決することはできず、改善すらできない。
・多くの企業がトヨタを真似て、全社的な改善活動を展開している。そして、それなりの改善提案数を集めているケースも少なくない。しかし、その後を辿ってみると、「提案の出しっぱなし、言いっぱなし」になっていることが圧倒的に多く、実際に改善提案が効果を上げている事例は稀である。こうした企業では改善活動が一過的な「イベント」に位置付けられ、日常的な活動にまで高められていないのである。
・現場力を鍛える上で最も重要なのは、問題点をさらけ出し、見えるようにすることである。問題そのものの存在を顕在化させることが解決への第一歩である。問題点が見えることによって、問題に対する組織としての意識が高まり、知恵も出てくるのである。これをトヨタでは、「見える化」「見える仕組み」と呼んでいる。
・現場力を強化する知恵は、実際の体験を通じてしか高めることはできない。机上の空論を何度繰り返しても、問題は解決しない。自らが汗をかき、知恵を絞り、失敗や成功を繰り返すことでしか、現場力を高めることのできるリーダーは育成できないのである。
・トヨタにおいて、次の時代を担う人材を育てる役割を担っている林技監はこう語っている。「生命のDNAは放っておいても継承できるが、企業のDNAはたゆまぬ努力を怠ると薄らいでしまう」
・トヨタと並んで強靭な現場力を誇る花王の後藤社長は、「現状不満足企業たれ」と語っている。現場力に完璧ということはありえない。現状に対して満足してしまっては、その時点ですべての思考は停止してしまう。「不満足」こそが継続するためのエネルギー源なのである。
・トヨタにおいても、「打倒トヨタ運動」という言葉が頻繁に使われる。実際、一兆円以上の利益を上げているトヨタの幹部から、「うちは来年潰れてもおかしくない」という言葉を真顔で度々聞かされる。「日本企業最大の利益を上げる最強の企業」という世の中のレッテルに惑わされることなく、常に「自己否定」しようとする姿勢が強く感じられる。
・その根底に流れるのは、「危機感」であり「緊張感」である。勝ち組と呼ばれる企業ほど、自負・誇りとともに、強烈な危機意識を持っている。しかも、それが経営のトップだけでなく、現場に深く浸透している。
・天才棋士、羽生善治氏はこう断言する。その言葉にこそ、現場力の本質が凝縮されている。「同じ情熱を傾けつづけられることを才能という」。
・強い現場をつくり上げるためには、失敗だけを管理していたのでは不十分である。失敗に目が行きすぎると、どうしても新しいことにチャレンジしない保守的な考え方に染まる傾向が出てくる。「失敗するくらいなら、何も変えない方がいい」「今のままが無難」といった現況肯定的な考えが蔓延してしまっては、現場の活力は生まれてこない。
・その時に重要なのが、「否定学」という考え方である。失敗という「結果」を考察するだけでなく、そもそも「現状を否定する」という思考、習慣を現場に根付かせることが現場の進化を促す。
・オペレーショナル・エクセレンスを誇る企業に共通するのは、現状を常に前向きな視点で「否定」しようとする姿勢である。花王の「現状不満足企業」というスローガンはまさにその精神を表しており、トヨタの「年間改善提案数61万件」もひとつずつの「否定」の集積である。
・自然科学を見ると分かるように、否定は新しいものを生み出すエネルギー源である。コペルニクスは天動説を否定することから、地動説を導いた。アインシュタインはニュートンの絶対時間・絶対空間というそれまでの定説を否定することによって、特殊相対性理論を生み出した。社会科学においても、アダム・スミスは統制と規制の重商主義を否定し、「見えざる手」による自由放任経済という新しい考え方を打ち出した。
・否定は現場をよりよくする、より強くするための手段である。そして否定の対象はあくまでも現場の仕事のやり方や、コミュニケーションのあり方といった業務に直結したものである。
・しかし、否定が下手な会社は、ともすると「業務の否定」と「人の否定」「人格の否定」が混同してしまう。何かを否定されると、それは自分自身を否定されたものと思い込んでしまい、反発をする。それでは現場の進歩は起こりえない。
・トヨタは「業務には厳しいが、人にはやさしい」会社である。業務の品質には徹底的にこだわり、厳しく追及するが、人の育成やケアにも手間隙を惜しまない。
・トヨタにおいて、業務マニュアルはあくまで「その時点での標準的な仕事の手順」として位置付けられており、マニュアルをよりよいものに進化させていくことこそが求められる仕事だと定義されている。
・個々人の業務や業務連鎖を見直す上で、まず最初に問い掛けるべき質問は、「そもそもこの業務は必要なのだろうか」という根本的な否定である。否定ができず、惰性が支配している現場では、過去には重要だったが、現在では付加価値の低い業務が現場の至るところに残されている。
・効率化を考える前に、「その業務をやめることができないか」を問い直すことが肝心である。経営学者のピーター・F・ドラッガーはこう指摘する。「本来やるべきではない業務を効率化しようとすることほど非効率なことはない」。
・「同じ船に乗っている意識」を醸成するためには、なにより組織の大目標、夢を共有しなければならない。同じ夢を追っているという一体感があるからこそ、現場は縦割りの弊害を乗り越えて、泥臭い努力を続けることができる。
・精錬事業の名門、同和鉱業の吉川広和社長は、2002年4月の社長就任以来、社内の壁6枚、オフィスの仕切り50枚を廃棄処分にしたという。当時社内に蔓延していたセクショナリズムや官僚主義を打破するために、秘書室を廃止したり、社内のレイアウトを大胆に変更した。社内の壁を取り払うことによって、「一番変わったのは組織よりも人の壁」だと吉川社長は語っている。
・花王では、部門横断的な会議が飲み会に発展した時には、一次会まで経費で落とすことを認めている。コストには徹底的に厳しい花王だが、社内交流を促すこうしたコストには寛容である。インフォーマルな触れ合いがあるからこそ、「業務連鎖に血が通う」ことを花王は熟知している。
・改善とは「自主的に業務のあり方を考え、課題を発見し、解決を導き出す活動」である。それでは「改革」とは何を指すのだろうか。これも様々な定義があるが、私は改革を「5~10年ごとに行うべきビジネスの仕組みの構造的変革」と定義している。
・ある大手情報機器メーカーでは、全役員に4半期に一度、カスタマー・センターへ出向き、丸一日顧客からの苦情や問い合わせに耳を傾けることを義務付けている。報告用に加工され、まとめられた不具合レポートは「角」がとれ、生々しさが削り取られ、経営判断を誤らせる。「お客様の声」、しかも苦情という「聞きたくない」源流情報に自ら接することによって、今の経営品質、現場の品質があからさまに見えてくる。
・「加工情報」に依存していたのでは、経営者失格である。「加工情報」に頼らず、「源流情報」に近づいていく。これこそ現場主義の基本精神である。
書籍名:なぜ松下は変われたか
著者名:片山修
出版社:祥伝社
紹介:現場での取り組みを通して松下電器再生への軌跡を追います。(04年3月読了)
感想:以下の点に共感しました。
・改革の成功は、明確な目標を掲げることによって成し遂げられる。しかも、その目標は高くなければいけない。
・どんな企業にも、気骨のある社員はいる。だが、気骨ある社員を活かせるかどうかは企業の器量次第だ。
・机や電話、OA機器などのオフィス・インフラは、働くためのギアである。いたがって、ギアの動きをよくすれば、やる気の向上につながるというのが、カナダ松下の牛丸の主張だ。
・「人は、何のために仕事をするのかを考えて欲しい。もちろん、お金のためもあるけどそれだけじゃない。働くことに喜びを感じるから仕事をするんだ。あるいは、自己実現したい、成長したい、勉強したい、エキサイティングなことをしたいから仕事をする。職場が楽しい、同僚が楽しいから、上司がきちんと面倒をみてくれるから働くわけでしょう。だとしたら、働く場は快適でなければいけない。使いやすい電話や心地よい環境は働くためのギアになるんだ。それを整えることが、従業員のやる気を高めるんだ。コンファタブルな職場環境をつくるのが、トップの役割だと思う」という論陣をはった。
・訛りのある英語が、かえって社員の心に響いた。全員が牛丸の肉声を耳にすることで、社内の一体感が高まった。
・「あるとき、中村の紹介で、アメリカの著名なコンサルタントがカナダにやってきて、お前は、なぜ前近代的なボイスメールで情報を伝達するのか、Eメールを使えばすむことじゃないか、というんですね。いや、Eメールで感情が伝わると思うか、訛りのある英語で一生懸命しゃべるからこそ感情が伝わるんじゃないか、と反論すると、彼はいいました。確かに、ジャックウェルチもそのようなことをいっていた。彼は社員にファックスを送るが、その筆圧や書きなぐった筆跡に喜びや怒り、悲しみが出るという。お前がいう通りだ、といっていましたよ」
・「トップが思いを語らなければ、組織は動かない。語りつづけ、部下とコミュニケーションをしなければ、目標達成はできない。それも、自分の言葉で語りかけなければいけない」
・松下はいま、冷蔵庫に限ぎらず、すべての家電製品について、リデュース(廃棄物の発生抑制)、リユース(再使用)、リサイクル(再資源化)の3Rを目指した商品づくりを行っている。
・森田は、あらためて「中村革命」の本質を知る思いだった。「選択するということは、他を捨てることなのだ」と思った。
・松下幸之助はつねに、「自分は何のために事業をしているのか」という思いに悩まされていたという。使命を明確化し、具体的な目標を掲げることが、企業組織の団結を深めると考え、「水道哲学(産業人の使命は、水道の水のごとく、物資を安価無尽蔵たらしめ、楽土を建設すること」を掲げた話はいまも語りつがれる。
・松下電器の商業者の松下幸之助は、人づくりや教育について一家言持つどころか、教育者そのものだ。お得意先にいって、「君のところは何をつくっているのか」と聞かれ、「松下は人をつくっています」と幸之助が語ったエピソードがあるほどだ。(以上)
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…
- 乾燥機付き洗濯機のメリットとは?
- (2024-12-01 22:41:59)
-
-
-

- みんなのレビュー
- 岡谷市のスギムラ精工さん…
- (2024-12-02 17:18:34)
-
© Rakuten Group, Inc.