テーマ: 京都。(6076)
カテゴリ: 京都検定1級受検勉強
伝統工芸#5編の解答です。
京友禅 (下記をクリックしてください。)
https://www.youtube.com/watch?v=K20BwqIHAdE
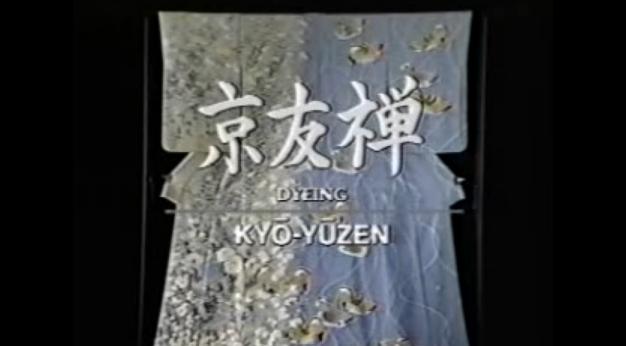
不正解だった場合は▲とし、その後に正解を記入しています。
●西陣織
・西陣織は平安京の朝廷所属の織り手集団である(大舎人座)以来の伝統を誇る。
・上京区の大宮付近には平安時代(織部司)があったところ。
平安時代の中頃からは(私職)も行われ、鎌倉時代から室町時代にかけて、
(先染め)である織物は(大宮絹)の名で知られた。
・応仁の乱で、織り手の匠は(堺)や(奈良)に避難し、乱後に戻り復興。
・中国から(空引機)が流入し、その影響を受けて(金襴)、(緞子)、(間道)
など高級織物が産出された。
・江戸中期の西陣焼けと呼ばれる(享保の大火)で、織機(3000余り)を失い、
幕末の(▲奢侈品禁止令)で大打撃を受けた。
・明治初期(佐倉常七)らがフランスからジャカード機械織機を輸入。
その後(荒木小平)がジャカード機を製作した。
・能装束の(唐織)は絶品
・堀川今出川に(西陣織会館)がある。
昔の建物は現在(京都市考古資料館)になっているが、この建物は(本野精吾)の設計。
●京友禅
・江戸前期の町絵師で、(扇絵)を描いていた(宮崎友禅斎)の考案と伝えられる。
・(型友禅)と(手描き友禅)に大きく分けられる。
・明治以降、型によって友禅模様を染める(写し友禅染め)が考案され、量産化の道が
開かれた。
・手描き友禅は(下絵)を描き、それに沿って(防染糊)((糸目糊)という)を置き、
(▲色挿し)を行う。(▲伏せ糊)を置いて(▲地染め)をし、蒸して染料を定着させ、
水洗いをして不要な糊を落とす。
・(鴨川)や(堀川)では、この水洗いを(友禅流し)と呼び、古都の風物詩であった。
・その他、後染めものでは(A:辻が花染)(B:茶屋染)などが知られる。
Aは桃山時代に流行し、(▲絞り)、(摺箔)、(刺繍)が併用され、織物にはない、自由な
文様が残されている。
Bは創案者が豪商の(茶屋四郎次郎)といわれ、(流水)など爽やかな文様が施された
(藍染)である。
(尾形光琳)の名からとられた(▲光琳雛型)という文様集が出版された。
●京小紋
・友禅型染めの技法と同じだが、小さな文様を、(▲一色)で型染めし、(防染糊)を置いた
あと(▲引染め)するのが特徴
・江戸時代、武家の(裃)が正装となり、(▲上杉謙信)の紋付小紋帷子や(徳川家康)の
小花紋小紋染胴服などは、小紋の技法を駆使して作られている。
・はじめは(単色)だったが、(▲彩色)へと変化した。
・型紙は和紙の(▲型地紙)に、刃物で模様を彫り抜いて作られる。
防染には(米)から作った糊が使われてきた。
・小紋型の小さな文様のものを(鮫小紋)、さらに微細なものを(極鮫)と呼んだ。
__________________________________
「京都検定過去問」カテゴリー一覧表
http://plaza.rakuten.co.jp/saaikuzo/diary/ctgylist/?ctgy=28
「京都検定出題傾向分析」カテゴリー一覧表
http://plaza.rakuten.co.jp/saaikuzo/diary/ctgylist/?ctgy=30
「京都検定勉強」カテゴリー一覧表
http://plaza.rakuten.co.jp/saaikuzo/diary/ctgylist/?ctgy=31

よろしかったらぽちっとお願いします。

にほんブログ村
京友禅 (下記をクリックしてください。)
https://www.youtube.com/watch?v=K20BwqIHAdE
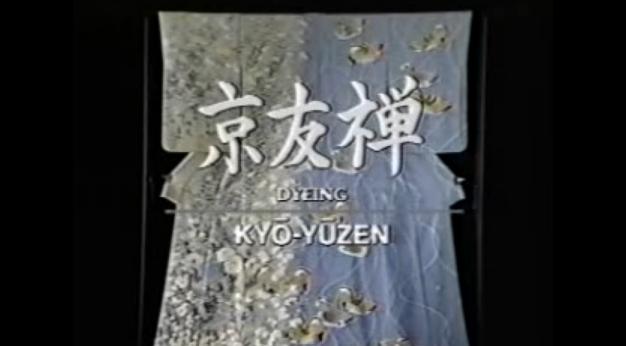
不正解だった場合は▲とし、その後に正解を記入しています。
●西陣織
・西陣織は平安京の朝廷所属の織り手集団である(大舎人座)以来の伝統を誇る。
・上京区の大宮付近には平安時代(織部司)があったところ。
平安時代の中頃からは(私職)も行われ、鎌倉時代から室町時代にかけて、
(先染め)である織物は(大宮絹)の名で知られた。
・応仁の乱で、織り手の匠は(堺)や(奈良)に避難し、乱後に戻り復興。
・中国から(空引機)が流入し、その影響を受けて(金襴)、(緞子)、(間道)
など高級織物が産出された。
・江戸中期の西陣焼けと呼ばれる(享保の大火)で、織機(3000余り)を失い、
幕末の(▲奢侈品禁止令)で大打撃を受けた。
・明治初期(佐倉常七)らがフランスからジャカード機械織機を輸入。
その後(荒木小平)がジャカード機を製作した。
・能装束の(唐織)は絶品
・堀川今出川に(西陣織会館)がある。
昔の建物は現在(京都市考古資料館)になっているが、この建物は(本野精吾)の設計。
●京友禅
・江戸前期の町絵師で、(扇絵)を描いていた(宮崎友禅斎)の考案と伝えられる。
・(型友禅)と(手描き友禅)に大きく分けられる。
・明治以降、型によって友禅模様を染める(写し友禅染め)が考案され、量産化の道が
開かれた。
・手描き友禅は(下絵)を描き、それに沿って(防染糊)((糸目糊)という)を置き、
(▲色挿し)を行う。(▲伏せ糊)を置いて(▲地染め)をし、蒸して染料を定着させ、
水洗いをして不要な糊を落とす。
・(鴨川)や(堀川)では、この水洗いを(友禅流し)と呼び、古都の風物詩であった。
・その他、後染めものでは(A:辻が花染)(B:茶屋染)などが知られる。
Aは桃山時代に流行し、(▲絞り)、(摺箔)、(刺繍)が併用され、織物にはない、自由な
文様が残されている。
Bは創案者が豪商の(茶屋四郎次郎)といわれ、(流水)など爽やかな文様が施された
(藍染)である。
(尾形光琳)の名からとられた(▲光琳雛型)という文様集が出版された。
●京小紋
・友禅型染めの技法と同じだが、小さな文様を、(▲一色)で型染めし、(防染糊)を置いた
あと(▲引染め)するのが特徴
・江戸時代、武家の(裃)が正装となり、(▲上杉謙信)の紋付小紋帷子や(徳川家康)の
小花紋小紋染胴服などは、小紋の技法を駆使して作られている。
・はじめは(単色)だったが、(▲彩色)へと変化した。
・型紙は和紙の(▲型地紙)に、刃物で模様を彫り抜いて作られる。
防染には(米)から作った糊が使われてきた。
・小紋型の小さな文様のものを(鮫小紋)、さらに微細なものを(極鮫)と呼んだ。
__________________________________
「京都検定過去問」カテゴリー一覧表
http://plaza.rakuten.co.jp/saaikuzo/diary/ctgylist/?ctgy=28
「京都検定出題傾向分析」カテゴリー一覧表
http://plaza.rakuten.co.jp/saaikuzo/diary/ctgylist/?ctgy=30
「京都検定勉強」カテゴリー一覧表
http://plaza.rakuten.co.jp/saaikuzo/diary/ctgylist/?ctgy=31

よろしかったらぽちっとお願いします。
にほんブログ村
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[京都検定1級受検勉強] カテゴリの最新記事
-
【京都検定勉強】§8回目の京都検定1級受… 2016/12/11
-
【京都検定解答】#116 京都の観光 解答 2015/12/12
-
【京都検定勉強】#115 京の町並み・京都… 2015/12/12
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
PR
X
キーワードサーチ
▼キーワード検索
カテゴリ
カテゴリ未分類
(6)常駐ガイド
(132)同行ガイド
(13)修学旅行ガイド
(51)修学旅行昼食処
(66)研修会
(9)京都ガイド諸活動
(53)私的ガイド
(4)京都研究
(45)京都市内全寺社巡り
(197)京都歩き
(194)美術・博物館
(50)講演会
(21)国内旅行
(6)旧東海道
(65)京都検定1級受検勉強
(239)京都検定1級過去問
(180)京都検定1級問題分析
(9)京都のニュース
(1888)京都のイベント・お祭り案内
(140)京都本
(27)津軽三味線
(31)日本でのゴルフ
(41)懇親会
(61)就職・退職など手続き
(55)吾唯足知~断捨離と必要最低限の買い物
(19)散歩・草花記
(630)健康管理
(24)この本読みました
(35)映画
(33)観劇・観戦
(9)私の十大ニュース
(99)気になったニュース・CM
(317)お天気・気候の話
(12)今日のこと
(170)仕事のこと
(0)癌闘病記
(485)癌治療振り返り
(87)癌治療情報
(593)ドイツの想い出
(209)スイス横断サイクリング
(31)ゴルフとアメリカ生活
(132)アメリカ出張
(36)ワルディ流日米国情比較
(16)母の備忘録
(0)商品レビュー
(3)ブログ記録
(10)食事処、飲み処
(13)京都案内
(218)若冲と応挙
(55)カレンダー
© Rakuten Group, Inc.












