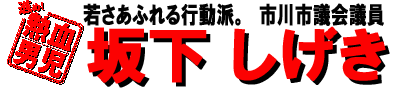一般質問(行政改革全般について)後編
市の政策は、財政健全化計画や、行政改革大綱などによって、方針が決められておりますが、実際には、市民に密着した、民間委託や、扶助費の削減などの政策は、市民から分りにくい、事務事業評価などによって決定されます。市民の方からすると、知らない間に保育園が委託化され、何故、自分の保育園だけが急に委託化されるのか、不信と不安で一杯になります。
そこで、第二点目の1といたしまして、松戸市などでは、事業評価の概要を市のホームページに載せております。市川市では、事業評価の評価基準、審査過程、結果を公表するシステムや、それに対する市民の意見を聞き取るシステムを、得意のITを駆使してでも創れないのかお答え下さい。
また、第二点目の2といたしまして、本市の事務事業評価は、予算作成資料と重なったり、毎年度変化のない事業に対して毎年評価を行ったり、福祉など量計不能な分野でも同じシートで評価していたり、これについては改善はしないのかお答えください。
第三点目の政策責任についてお尋ね致します。
市川市の政策責任は市民から見ると、非常に分りずらいと感じます。6月議会で東京都の石原都知事の例を出しましたが、都知事は議会において扶助費の削減を明言され、都民にもダイレクトに都の政策方針が伝わり、責任の所在も明らかになりました。
市としての削減の方針や責任の所在がはっきりと市民に伝わっていれば、職員も市民に対して、歯に衣を着せた言い方ではなく、はっきりと自信を持って説明でき、そのことが説明責任の達成になって、市民も真実がわかりやすくなり、行政事業に対する評価がしやすくなります。事務も一層効率化されるでしょう。
市川市では、職員の窓口対応の向上を目指して、アンケートをとられたということですが、制度改正などによって、直接利益を害された市民から見れば、勿論窓口での対応は重要な事ですが、どんなに親切に対応されても、詳細な経緯を説明されないまま権利を害されれば、心底から納得はできません。充分な情報公開がないまま、保育園を委託したり、助成金を削減するような時は、職員の窓口対応だけに頼るのではなく、市の責任として、事業自体へのアンケートこそ取るべきであると思います。
委託化は、市民から見れば突然降って沸いたような話しで、不信感で一杯であると思います。市の委託に関する方針は、第一次アクションプランによると、企画部によって基準など検討されていくわけで、市民からすれば、担当部に問い合わせるのか、企画部に問うのか甚だ分りにくい形になっております。
市長は常に説明責任について語られておりますが、今議会においても、ご答弁は無く、委託化をはじめ諸事業についての説明責任を充分に果たされているとは思えません。
市民としては、何も分らぬまま委託化を勧められては、不信しかありませんが、市の財政状況や、委託の事業内容など、市が市民に対して分りやすい情報を提供し、説明責任を果たし、市民との意見を交換し、課題を共有することで、より良いシステムが構築されるのではないでしょうか?
そこで、第三点目の1といたしまして、政策責任の所在・内容が明らかになるように、千葉県でも実施しておりますが、市の政策決定機関でもある庁議や部課長会での決定事項などを、市のホームページ上で公表はしないのかお答え下さい。
第三点目の2といたしまして、審議会についてですが、従来より、審議会について指摘されている事は、審議会は、「行政の隠れみの」的存在で、行政の政策責任逃れの道具になっていると言うことです。市川市では、審議会が、行政の意思決定の道具とならないように、独立性が保たれる工夫をされているのかお答えください。また、行財政改革審議会については、単なる諮問機関であるのか、また、例外的な形態である、参与機関として位置付けられているのかお答えください。
続きまして、第四点目の市民とのパートナーシップについてお尋ね致します。
この財政難の時代を乗り切り、緊縮財政を市民の方々に理解して頂くには、信頼関係・パートナーシップを築くことが重要です。市民の方々と、パートナーシップを築くための、基礎となるのは、行政が市民に多くの情報を公開し、説明責任を果たすことであると考えます。
しかし、これはあくまで、パートナーシップを築くための基礎の部分であって、信頼関係を築くには、情報を公開した上で、更に市民の意見を取り入れる仕組みが必要であると思います。
また、1940年代前後におきた、行政責任論争における、内在的責任論によると、責任ある行政官とは、民衆感情に応えられる行政官であると言います。民衆感情、すなわち、市民感情に応えて、行政が判断し行動する責任であり、行政が市民に接触する独自のチャンネルを確立することを提唱しております。
新行政改革大綱第一次アクションプランでも市民参加制度の創設、及びパブリックコメントの手続き制度の創設があり、所管部は、企画部になっております。
そこで、第四点目の1といたしまして、計画目標年度を平成16年度に早めることはできないのかお答えください。
第四点目の2といたしまして、パブリックコメントの手続き内容について、平成11年3月の閣議決定における手続きと、市川市のパブリックコメントの違いについて、具体的にお答え下さい。
第四点目の3といたしまして、市川市では、政策決定事項に対するパブリックコメントを募集するのかお答え下さい。
閣議決定でのパブリックコメントは、議会の審議事項や、行政サービスに関わるものは対象とはされておりませんが、住民により近い地方公共団体としては、議会が関与しづらい、規則・要綱などに基づく行政サービスについても、パブリックコメントをとる必要があります。先順位者も質問をされておりましたが、市川市は、条例が少なく、規則や、特に要綱が多く、本来要綱で定めるべきでないようなものまで要綱で定められています。このように議会も関与できない制度については、積極的にパブリックコメントをとるべきです。その点も含めてお答え下さい。
財政難の状況下、市民から信頼される行政を目指し、市民とのパートナーシップを築き、市民の理解を得るには、市長が説明責任を果たすことが重要です。保育園の委託化、扶助費の削減など、重要事項について市長が説明責任をこれからどう果たしていくのか、市民とのパートナーシップ・信頼関係が築けるような、ご答弁を期待致します。
© Rakuten Group, Inc.