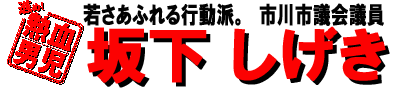一般質問
新政クラブの坂下しげきでございます。
通告に従いまして一般質問致します。
私は、市議会において3年間、市の行財政改革を中心に質疑・質問を行ってまいりました。そしてNPMニューパブリックマネージメントについて、その有用性と問題点についても議論させていただきました。その中で本市は、行財政改革の一環として「市川市アウトソーシング基準」を作り、外部委託を推進しております。先の衆議院総選挙においては、官から民へという行政手法が国民の支持を得ました。
官から民へ移行可能な事業については、行政サービスの質を高めるという目的、効率性、経済性の観点から取り入れていく必要があります。
一方で、すべてのアウトソーシングが市民利益に合致しているわけではありません。私のライフワークとして取り組んでおります災害対策などは、民間ですべて行えるものではなく、また事業によっては、安易なアウトソーシングは、返って市民生活をおびやかす懸念もあります。
従って、アウトソーシングにおいては、どの業務を委託するのか、という判断が重要です。そして、アウトソーシングが可能と判断できた事業については、外部委託に移行し、これによって余剰ができた人材・予算を、市が直営として行わなければならない分野に転化していき、行政全体の効果を高め、市の施策全体の成果を挙げていく必要があります。
そこで今回はまず、アウトソーシングが可能な事業について、ただ経済性を追求し、財政コストの縮減を目的とするのではなく、本市の限られた政策経費予算の中で、アウトソーシングを通じて、雇用政策、福祉政策、環境政策等を実現させる方法の一つ、政策入札の導入・実施について提案・質問させて頂きます。
政策入札とは、外部委託する際の受託者の決定を、一般的な入札である価格の高低だけで決めるものではなく、市の政策に合致している事業者であるかどうかを評価して、決定していく入札制度です。
例えば、入札参加者が「市民を雇用しているか、障害者の雇用率を達成しているか、次世代育成支援対策推進法に定める一般事業主行動計画が適正であるか、環境基準であるゴミの処分を適正に行っているか、公正労働の条件を満たしているか」など、市の政策に沿って入札者を評価し、入札金額の他に、このような点に優れている者を落札者にしていく方法であります。
例示したような各種政策は、罰則が厳しくないことなどから、政策の実現が難しい場合が多々あります。 しかしながら市がこのようなアウトソーシング基準を作り、政策を前向きに実施している事業者を評価する仕組みが整えば、努力している事業者に対して、市の事業を請け負えるというインセンティブを与えることができ、法が目指す社会の形成に資することができます。
政策入札は、社会的責任を果たそうとする事業者等をバックアップするための手段としても有効なものであります。
本市には、市民の雇用問題、又は法の改正に伴う、障害者雇用、高齢者雇用及び次世代育成支援、又はゴミの減量化等の様々な課題があります。
これらの課題に対して、事業費予算だけの対応では限界があり、決定的な打開策を担保できないのも事実であります。
一方で、平成18年度当初予算における本市の委託料、賃借料等は、一般、特別、病院会計合わせて、218億円を上回り、毎年度増加の傾向にあります。
そこで、この溢れる資産である約218億円を有効利用して、新たなアウトソーシング基準を作ることによって、外部委託を定義し、受託者を決定する過程において、このような社会的課題に前向きに取り組んでいる者を評価し、受託者とすることで、地方公共団体が講ずる施策又は事業主が行う雇用環境等の整備を促進し、市民生活の向上、社会の形成に資するものとしたいと考えるものであります。
ご案内のとおり、大阪府では、庁舎等の清掃業務の入札において、価格、技術評価に加え、公共性評価である福祉、環境に視点をおいた政策入札への転換を図り、14人の知的障害者の雇用が決まった案件があります。
また、価格だけの競争による入札は、市にとって経済的メリットが引き出せることは確かですが、このような価格主義は、不当なダンピングや労働賃金の問題そして、入札方法が簡易なため談合を引き起こしやすい側面があります。
従って、昨今は総合評価方式の入札が取り入れられております。この政策入札も総合評価方式の入札といえます。
そして、本市の契約方法は随意契約が多く、総務委員会においても審査を行っております。
ちなみにプロポーザルも入札ではありません。
しかしながら政策入札は、入札ですので、随意契約にはならず、競争性が高められます。
ただ、この政策入札については、メリットとして、市の政策がアウトソーシング事業に引き出せるという面、及び談合防止につながるという面がありますが、一方では、価格以外の要素が落札の基準となることから、落札者の決定が不透明になるというデメリットがあります。
従って市の政策に沿った落札の基準を公平な観点でつくり、採点基準を明らかにしていく必要があることを申し添えます。
そこで、このような自治体の実現すべき政策を入札条件に盛り込む政策入札の導入について、全体的に伺います。
まず、昨今改正された
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律、
障害者の雇用の促進等に関する法律、
次世代育成支援対策推進法、
廃棄物の処理及び清掃に関する法律等に基づいて、事業主等が法に定める責務を果たしていくための インセンティブとして、本市において、政策入札を実施する方向性はあるのかお答え下さい。
次に、それぞれの法に定める雇用、若しくは雇用環境の充実、並びに廃棄物処理の適正化を促進する手段として、平成16年12月3日改正の「市川市アウトソーシング基準」第3項、第4項ないし第6項に定める基準に政策入札に係る事項を盛り込むことはできないのかお答え下さい。
次に、具体的にお尋ね致します。
各法に定める障害者雇用率の達成や次世代育成支援対策推進法の行動計画の提出などを評価する入札基準、また、これらの法に定める義務事業者だけではなく、雇用の促進に努力している事業者も評価していく入札基準によって、落札者を決定するシステムを今後採用することが可能であるのかお答え下さい。
次に、政策入札の考え方を拡大的に解釈致しまして、指名競争入札における準備行為である指名基準において、それぞれの分野、例えば子ども部の入札においては、業者の指名基準として
次世代育成支援対策推進法に沿った事業者であるのか、また環境清掃部であれば事業者が廃棄物に係る義務を適正に行っているかなどの判断によって指名業者を選定する基準等を検討できないのかお答え下さい。
続いて、高年齢者等の雇用の問題についてお伺い致します。
高年齢者等の雇用の問題については、2007年問題がありますが、今後高年齢者等の雇用の安定を政策的に実現させていく必要があると思います。
平成16年11月10日に施行された地方自治法施行令の一部を改正する法律により、随意契約の一つに第167条の2第1項第3号が加わり、シルバー人材センターとの随意契約が市の判断で基準を作ることにより可能になりました。
規則等は改正されていれていないので、検討段階ということと思います。
ここで高年齢者等の雇用について、整理しなくてはならないことは、施行令第167条の2第1項第3号だけを政策的に考えて良いかということです。
シルバー人材センターは、確かに高齢者の社会参加の促進を図るために重要な機能を果たしていることは疑いません。
しかし、シルバー人材センターの設置の根拠は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第41条第1項及び平成12年労働省告示第82号に規定されております。
この法令の規定では、シルバー人材センターは、生計の維持を目的とした本格的な就業ではなく、月に数日の就業、そして特別の知識又は技能を必要とする業務などにおける雇用の機会を確保する機関です。
2007年以降は、生計の維持を目的とした求職者も増え、そしてシルバー人材センターのような特別の知識又は技能を必要とする業務を望む高齢者だけではなくなると思います。
無論生計は各種福祉政策等により補完されるべきものでありますが、現実として生計維持のための高年齢者等の就労の機会の確保が必要になると思います。
従って、本市の政策として、施行令第167条の2第1項第3号つまり、生計維持が主たる目的ではなく、また特別な技能職がメインのシルバー人材センターだけを政策的に考えていくのか、若しくは、広く、生計の維持や一般職を希望する高年齢者等の就労の機会を均等に確保するためのアウトソーシング施策を展開し、規則を制定していくのかお答え下さい。
次に、政策入札における環境側面についてお尋ね致します。
前議会において、私は、事業系一般廃棄物の適正な処理について質問致しました。その際、市内の事業者において、適切な廃棄物の処理がなされていない可能性が伺えました。
一般廃棄物の処理は、処理費用の負担の観点からも適切な処理が行われる必要があります。
つまり、適切な処理をしている者だけが事業系の割高な手数料を支払い、家庭系として違法な処理をしている事業者が手数料を免れるようなことは許されません。
従って本市の条例である「市川市廃棄物の減量、資源化及び適正処理等に関する条例」及び同条例施行規則に定める事業者の義務を果たしている業者、例えば適正処理済みシールの配布を受けている業者を指名若しくは選定・決定する仕組みは作れないのか、また条例の効果を挙げるためにこのような制度をつくることを環境清掃部としてどのように考えているのかお答え下さい。
次に、第二の本市から排出される廃棄物の取扱いについて、余熱利用施設建設用地廃棄物に係る工事、収集運搬及び処分業務を例にあげて質問致します。
平成17年12月議会において、小岩井清議員の議事進行に対するご答弁で、工事により発生する産業廃棄物の収集運搬及び処分については、工事請負業者である大和工商リースではなく、別の許可業者である太平興産と市が別契約をするとのことでした。
しかし、環境省通知によると、工事請負においては、排出事業者は、工事の元請となっております。
つまり、産業廃棄物の排出事業者は、市ではなく元請の大和工商リースになり、大和工商リースが産業廃棄物の収集運搬及び処分契約を別途許可業者と締結し、その費用を工事請負から支弁することが適当といえます。
このことが答弁と異なっていることから、今議会において、新政クラブ第2の代表質疑の補足質疑者である鈴木まもる議員が内容をただしたところであります。
代表質疑において鈴木まもる議員が言われたとおり、当該工事契約は、高額でリスクが高いため、市民利益を損失することがないよう、重ねて一般質問をさせていただきます。
まず、今議会の代表質疑におけるご答弁で、排出事業者は鈴木まもる議員ご指摘のとおり、市ではなく大和工商リースであることを認めました。その上で、三者契約をしたということです。
では、平成17年12月議会では、排出事業者は、市であると誤認していたのか、若しくは排出事業者が大和工商リースと認識しながら、三者契約を行うことを敢えて答弁していなかったのかをまず、お答え下さい。
続いて、通常ならば、鈴木まもる議員のご指摘のとおり、産業廃棄物の収集運搬及び処分料は市が支払う工事請負費に含まれるものであり、これを元に排出事業者である大和工商リースが別途産業廃棄物の契約をするものです。
しかし、なぜ、市が一方的に債務だけを引き受ける三者契約という特殊なそして一見不利な契約を選択する必要があったのかお答え下さい。
また、代表質疑のご答弁で市は債務引受をしたという旨のご答弁がありましたが、三者契約における債務引受は、チョウジョウ的債務引受、免責的債務引受、若しくは履行引受であるのかお答え下さい。
続いてマニフェスト・管理表について、マニュフェストの発行は誰が行っているのかお答え下さい。
続いて工事の施工についてお尋ね致します。
代表質疑において指摘があったように、大和工商リースは土木の実績がここ2年皆無であり、従ってその施工状況を特に管理する責務が市にあるといえます。
また、建設業法の違反行為である一括下請けの懸念があり工事の施工管理は注意を要します。
そこで、下請けは全体の何パーセントに及んでいるのかお答え下さい。
最後に、第三の、「議会での審議事項を行政がフィードバックする仕組み」についてお尋ね致します。
毎議会、本会議及び委員会において様々な審議が行われております。
地方分権の推進により、地方公共団体自身が自ら決定していく事項も増えました。また、以前は通達行政などと言われ、法令が施行されると各省庁から通知が出され、各地方公共団体がこの通達・通知に沿った運用を行っておりました。
中には、法に沿った条例案までご丁寧に中央省庁で作り、画一的管理・運用を行っておりました。
しかし、現在は、地方分権の観点から通知類は最小必要限度のものに留められ、あとは自治体の能力・裁量に委ねられております。
従いまして、指定管理者制度の例もあるように、地方公共団体の持つ能力・裁量によって同じ制度でありながら、そして同じ趣旨でありながら、運用方法が地方公共団体ごとに様々であります。
良くも悪くも地方公共団体の区別化が進んでくると懸念されます。
従って本市においても行政・議会双方が切磋琢磨し、決められた法の中で、最高の運用を行える能力と見識を身に着け、最高のサービスを市民の方に提供できるようにしていかなければなりません。
このような地方公共団体を巡る動きを勘案し、行政の側も議会での審議事項を真摯に受けとめ、検討し、よりよい運用を目指していく必要があります。
従いまして、議会での審議事項をどのように受け止め整理し、政策、制度運用につなげているのかお答え下さい。
以上1回目の質問とさせていただきます。
ご答弁によりまして再質問させて、頂きます。
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- 今日のこと★☆
- 大幅値下げ!3kg込1,980円、豊橋産ハ…
- (2024-06-30 22:00:08)
-
-
-

- ★つ・ぶ・や・き★
- バナナは「太くてまっすぐ」が大当たり…
- (2024-07-01 00:10:13)
-
-
-

- 株式投資日記
- 平均年収サラリーマンが脱サラ目指し…
- (2024-06-30 22:54:31)
-
© Rakuten Group, Inc.