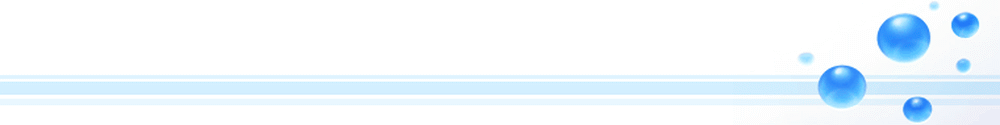るろうに剣心 7
るろうに剣心小説(短編)目次
75000キリ番リクエスト小説。弥彦の成長、そして仲間や家族の物語。左之助が日本を去ったあとのお話。弥彦は平和な時を過ごしていたが……。(弥彦他 仲間・家族もの)
※原作で左之助が日本を去ったのは秋だと思われますが、作品の都合上、縁との闘い後わりとすぐ、という設定になっています。ご了承ください。
ホントはずっと、待っていたんだ――
『夏の終わりに』(るろうに剣心 7)
日雇いの帰りだった。赤べこで汗を流し働いた弥彦は、真夏の日に照りつけられ再び汗を流しながら、神谷道場へ帰る途中だった。この時間なら、夕飯までに二時間位は稽古ができる。そう思いながら歩いていた弥彦は、ハッと立ち止まった。路地裏から、女の叫び声が聞こえたからだ。
「いやぁ! 返してぇ!!」
女の声に、弥彦は急いで路地を曲がる――が、そこで弥彦の足は釘付けになった。
地面に崩れて泣く女の後ろに、駆けていく数人の男。後ろ姿でも一目で分かる。間違いない。関東集英組――弥彦が元いた極道の連中だった。そしてすぐに弥彦は、女が金をスられたことも分かった。
「返してぇ!!!」
その声に、弥彦はビクッとする。号泣する女。薄ら笑いを浮かべているであろう、かつて共に暮らした者たち。弥彦は一瞬とまどったが、男たちの後を追いかける。途中で、路地裏から出てきた誰かにドンとぶつかった。新市だった。
「弥彦くん! いったいどうしたんだい?」
「……」
弥彦は言葉をつまらせたが、新市から目をそらし言う。
「逃げてるヤツら、スリだ。捕まえてくれ……」
「なんだって!?」
新市があわてて男たちの後を追いかけるのを、弥彦はただ見つめていた。悲痛な、女の泣き声を聞きながら……。
新市が男たちを捕縛し、財布は無事女の手に戻った。警察署から弥彦、新市、女の三人が出てきたときは、もう夜だった。
「本当にありがとうございました。ぼうやもありがとうね」
女は、新市と弥彦に丁寧におじぎをした。
「けど弥彦くん。キミならわざわざ僕の手を借りなくても、十分一人で捕まえることが出来たんじゃ……」
不思議そうに顔をのぞきこまれ、弥彦は思わず目をそらす。
「あのお金がなければ、一家はのたれ死にするところだったわ」
安堵の息をもらす女に、弥彦はただうつむいた。
かつて自分はスリをしていたと言ったら、女はどんな目をするのだろうか。
罪の重さを、改めて突きつけられた夜。
その夜、皆が寝静まった後、弥彦は静かに神谷道場を後にした。
「世話になった」と、ただ一筆を残して。
父上母上の誇りを守るために、生きなければならないと思った。
けれど、この手でたくさんの人を傷つけるくらいなら。
いっそのこと、死んだ母のあとを追いかけるべきだったのだろうか。
目が覚めたとき、セミの声が聞こえた。
弥彦のぼんやりとした視界にうつったのは、古びた天井だった。つぎはぎだらけの布団に寝かされている自分に気付く。視線を木戸の外へずらせば、そこにはわらぶき屋根の家がぽつりぽつりと建つ、あとは田畑が広がるだけの、のどかな風景だった。
「俺……は……」
かすれた声でつぶやき、記憶の糸をたぐり寄せようとしたその時――
「気分はどう?」
せまいこの部屋に入ってきた一人の少女。年の頃は十五、六だろうか。一瞬ふいに懐かしさを覚えた弥彦だが、その感情の意味は分からないままだった。
「君、宿場町の入り口で倒れてて、お父さんが連れてきたの。もう丸二日寝てたのよ。見たところ旅の格好だったけど、どっからきたの?」
「……ここ、どこだ?」
質問には答えず、逆に問う弥彦。
「どこって、信州よ」
「信州っ!?」
弥彦は思わず飛び起きた――が、くらりとして、また布団にぼふんと倒れる。少ない食糧で東京を発ち、暑さと空腹でふらふらになりながら、夢遊病のように歩いた。朝が来て夜が来てを繰り返し、何日歩いたか分からない。だがまさか、そんな遠くまで来ているとは思いもしなかった。
「君、名前は?」
「東……いや……、弥彦」
東京府士族明神弥彦。少し前までなら、堂々とそう名乗ることが出来た。
少女は優しい笑みを浮かべ、弥彦の体を支え起こし、かゆをさじですくい弥彦の口へと運ぶ。弥彦はそれを一口すすり、二口すすり……。人は生きたいと願わなくても、食べ物を受け付けることができるのだと、ぼんやり思った。
「私は東谷右喜。お父さんと、弟の央太と、三人で暮らしているの」
そこで右喜は、柱の影に隠れている子供を手招きした。弥彦よりも少し年下の子供――央太は、おずおずと出てくる。子供の目を見て、再び先程の不思議な懐かしさがよみがえった弥彦だが、やはりその訳は分からない。弥彦が央太をじっと見つめると、央太もまたきょとんと弥彦を見つめ返した。
その時、木戸を開ける音がガラガラと響いた。
「あっ、お父さんが帰ってきた!」
部屋へ入ってきた男を見て、弥彦は二日前の記憶を思い出した。
『……左之……助……?』
『あん?』
『……な訳……ねぇか……』
左之助によく似たその男に抱きかかえられながら、弥彦は気を失った。
その男が、どうやらこの一家の主らしい。
「おっ! やっと起きたか。まぁとりあえず食って元気になれや」
男はニシッと笑い、弥彦の頭をぐしゃっとなでると、部屋の奥へと引っ込んでいった。
「やっぱり……似てる……」
「え? 何?」
「……いや」
弥彦はそれきり黙って、かゆをすすった。
感じた懐かしさの原因。それは、男の子供たちもまた、どこか左之助に似ていたからだ。
例えば剣心の「罪」は、とても重いけれど。
その出所は、人々の幸せのためで。
自分の「罪」は、ただ自分が生きていく為に――
「なあに? 外の景色がそんなにめずらしい?」
日の暮れる空と田舎の景色をふとんからながめていた弥彦は、ふいに右喜に声をかけられた。
「なにもねぇところなんだな……」
「君は、大きな街の育ちなんだね」
「……けど、なんか、悪くねぇな」
無表情の中に秘められた、悲しみと安堵。右喜はそれを、なんとなく弥彦から感じ取る。
「じゃあ明日、外を案内してあげる。田舎の景色もいいものよ」
右喜は弥彦に、にっこり笑った。
次の日、まだ本調子ではなかったが何とか歩けるようになった弥彦は、央太と近所を散歩していた。右喜は、急に傘の注文が入ったため、父と共に内職をすることになってしまったのだ。
央太に手を引かれ、弥彦は田舎の風景を目にする。どこまでも続く田畑。わらぶき屋根の家。ひまわり畑。小さな池に咲く蓮の花。連なる山々。とうもろこし畑。木にしがみつくセミやカブト虫。広い空。澄んだ空気。草の匂い。
ごたごたした街もなく、往来を歩くたくさんの人もなく、それは弥彦をほっとさせた。そして東京育ちの弥彦にとって、簡素だが素朴であたたかい景色は、心和ませるものだった。
それにしても……と弥彦は思う。先程から、この央太という子は口を開くことがない。弥彦もいつもよりずっと口数は少なかったが、それにしても央太は話しかける弥彦にただ頷くか首をふるばかりだ。きょとんとした顔をして。
「お前、どこかアイツに似てるのに、中身は全然違うんだな」
央太は首を傾げる。
「前いたところにいた、俺の……その、なんてっか……。なんか、バカで、やたら人のあだ名つけるの上手くて……でもすげぇ強くて、いつか追いつきたいと思うようなそんな背中で……」
気がつくと、央太は真剣に弥彦を見上げていた。
「ん? どした?」
弥彦が不思議そうにたずねると、央太は首をふり、そして笑った。初めて見せた笑顔だった。そのまま央太は、視線を移す。その先は、弥彦が背負う竹刀だった。
弥彦はハッとした。無意識で、背負ってきてしまった。もう、そんな必要などないのに……。
「これ、欲しいのか?」
央太は驚いた表情をしたあと、遠慮がちに首をふる。
「……貸してやる」
竹刀を渡すと、央太はうれしそうに素振りを始めた。無茶苦茶に竹刀を振るう央太を見ながら、弥彦は思う。やるとは、言えなかった。竹刀など、もういらないはずなのに。なぜそんな、中途半端な気持ちなのだろう。
剣筋はめちゃくちゃだが、一生懸命に素振りをする央太はいい目をしている。弥彦はそんな央太をじっと眺めていた。が、央太は均衡をくずして前のめりに転ぶ。
「おい、だいじょうぶか?」
あせってかけよった弥彦だが、央太はけろりと立ち上がった。弥彦は驚いた。ひ弱そうなこの子は、てっきり泣くのかと思ったからだ。
央太はそのまま、弥彦をじっと見つめた。
「なんだ?」
央太は、真剣に弥彦を見つめる。
「もしかして……剣術教えてほしいのか?」
央太は、こくんとうなずいた。
「……分かった。教えてやる」
本当は、もう剣になどかかわりたくなかった。だが、央太の真剣な表情を裏切ることなど、弥彦には出来なかった。
弥彦は、道の横にあるだだっ広い荒れ地へ央太を連れて行くと、竹刀を両手に持たせた。央太の手に自分の手を沿え、竹刀の握り方を教えてやる。
「いいか。左手は、小指を柄尻にひっかけるように……」
言いながら、弥彦の心はズキンと痛む。半年前は、自分も薫にこうして教えてもらった。そばで、剣心が見守ってくれていた。それなのに……。
「強くなりたいか? 央太」
央太は、不思議そうに弥彦を見上げる。
「強くなって、守りたいんだろ? 大好きな父ちゃんや姉ちゃんを」
央太は、目の奥に強い光をたたえ、うなずいた。
「お前は、真っ直ぐで、綺麗な目ぇしてる。手だって、汚れてねぇ。いいか央太」
弥彦は、央太の両肩をつかみ、その顔をのぞきこんだ。
「強くなりたいなら、そして大切な人を守りたいなら……ずっと一緒にいたいなら……今のまま真っ直ぐ生きろ」
そうして弥彦は、央太から目をそらしぼそりと言う。
「俺みたいにはなるな……」
目の前にいる央太が、うらやましくてたまらない。汚れていない。真っ直ぐな未来がある。そんな央太を、弥彦はとてもまぶしく感じる。直視できないほどに……。
そうしてうつむいていたら、弥彦の袖がそっとひっぱられた。央太は、弥彦を心配そうに見上げていた。
「……わりぃ。だいじょうぶ。何でもねぇんだ……」
弥彦は央太の頭を優しくなでると、稽古を再開した。
その日の夕方、東谷家の縁側で独り、弥彦は外の景色を眺めていた。
「よぉ」
右喜たちの父、上下ェ門がぶらりとやってきて、弥彦の隣りに立つ。
「誰か待ってるんかい」
弥彦の肩が、わずかにビクッと反応した。
「……いや」
「フッ、じゃあ帰りたくても帰れない家出小僧ってぇところか」
「そんなんじゃねーって。俺にはもう父上も母上もいねぇし」
夕陽を見つめ続ける弥彦の肩を、上下ェ門はポンとたたいた。
「だが、家族はいるんだろう?」
「家族?」
一瞬弥彦の脳裏をかすめた、剣心と薫。だが、弥彦は伏し目がちになり答える。
「別に……ただ居候だっただけだって……」
「そーいうことか」
上下ェ門はニッと笑った。
「それよりオッさん、左之助の父ちゃんだろ」
ずばり言う弥彦に、上下ェ門は目を見開いた。
「今日央太と宿場町へ買い出しに行ったとき、よそ者の俺にみんなが悪一文字を背負った男……つまり左之助のことを話してきた。アイツ、ここでは英雄なんだな……。そんでもってアイツがやたらこの家に関わってたこととか、アイツとオッさんがやたら似てることとか考えたら、そうだって分かった」
「おめぇさんはアイツを知っているのか? アイツは元気か?」
上下ェ門の口調がわずかに変わったのに、弥彦は敏感に気付く。そこに確かに、家族の絆を感じる。
「左之助は、俺が居候してた家によく飯をたかりにきてた。そんでもって今は、海の向こうへ行っちまった……」
言った後、弥彦はちらりと上下ェ門を見上げる。言うべきではなかっただろうか。
だが、上下ェ門は満足そうに笑った。そして、それを不思議そうに見つめる弥彦に気付く。
「なんでぇ、俺が悲しがるとでも思ったか? アイツはもう一人前の男だ。いい背中見て育って、やっと自分の生き方見つけて、旅立っていったんだろ? 最高じゃねぇか」
上下ェ門の言葉に、弥彦は安堵し、そしてうれしくなった。
「けど、おめぇさんにはまだ、誰かの背中が必要じゃあねぇのかい?」
弥彦は上下ェ門を見つめ、そして再び夕陽に目を移す。思い出すのは二人の男の背中。そのうちの一人、左之助はもう、手の届かないところへ行ってしまった。そして、剣心。心いっぱいの憧れと尊敬と、それだけでない何かを持って、いつも見ていたその背中。だが、その剣心にも、もう会ってはならないのだと思った。
「ところでなぁ、左之助のこと、子供らには秘密にしてやってくんねぇかい。特に、右喜にはな……」
「なんで、右喜には特に、なんだ?」
「右喜は昔よぉ、左之助に置いていかれて、それ以来家族を失うことを恐れるようになっちまった。おめぇさん知ってるか? 出ていった者より置いていかれた方が、よほど辛いことを……」
「……」
自分が出ていったことで、剣心と薫は、少しでも辛いと思ったのだろうか。そう考え、けれどそんなわけはないと思った。あの二人は、きっともうじき結婚し、子供を作り、新しい家庭を築くのだろう。
そうして弥彦は、あの夜聞いた赤ん坊の泣き声を思い出す。
うつむく弥彦を見ながら、上下ェ門は言う。
「まぁ気ぃ済むまでここにいろや」
「……本当か?」
「ああ。ただし、おめぇさんが帰るべきところに帰る日が来るまでだ」
帰る場所なんか、もうないんだ――そう言おうとして、けれど弥彦は何も言わなかった。言ってしまったら、本当になにもかもが終わりになってしまう……そんな気がした。
それから、弥彦は少しずつこの家の生活になじんでいった。畑仕事や内職を手伝い、その合間に央太に稽古をつけた。みんなで大粒のトウモロコシを食べたり、花火を見たり、川遊びをしたりした。
優しい東谷家の人たち。ゆっくりと時が流れる、心穏やかな毎日。弥彦は、そんな生活が心地よかった。
それでも、夕方になると、なぜか縁側で遠くを眺めたくなる。毎日日が沈むまで、東京の方角を見つめる。東京は騒がしく、いつも闘いが絶えず、厳しい稽古と日雇いでせいいっぱいの毎日だった。ここにいれば、そんなことは何一つなく楽になれる。
それなのに、その重かった竹刀を央太に貸したままなのに、荷を下ろしたはずの背中がさみしいのはなぜだろう。
薫が、赤ん坊を抱いていた。
剣心が、そばにいる。
けらけらと笑う赤ん坊。
恐る恐る、弥彦は近づき、赤ん坊に手を差し伸べる。
――パシン――
弥彦の手を振り払った赤ん坊は、火がついたように泣き出した。
恐怖と、嫌悪をにじませた目で――
誰かにゆさぶられ、弥彦は目を覚ました。真夜中だった。央太が隣のふとんからはいでて、弥彦をゆすり起こしたのだ。その心配そうな顔を見て、弥彦は愛おしさを覚える。自分に弟がいたら、こんな感じなのだろうか。
「わりぃ。夢見て、うなされちまってたみたいだな」
央太の頭をなで、布団へ寝かせたが、央太は弥彦をじっと見つめたままである。弥彦はそんな央太をしばらく見ていたが、ふいにこんな言葉がこぼれた。
「あの日、赤ん坊の泣き声を聞いたんだ」
低くぼそりとつぶやく弥彦の言葉を、央太は布団の中でじっと聞く。
「俺が、前いたところを出ていった日」
警察署から神谷道場へと帰る途中だった。どこかの家から、赤ん坊の泣き声が聞こえた。
「それで……思ったんだ……。一緒に暮らしてた二人は、もうすぐ結婚して、子供を生むんだって……。そこに……俺がいたらいけないと思ったんだ……」
央太は、きょとんとする。
「赤ん坊って、きれいだろ。だけど、俺の汚い手でさわったら、きっと汚れちまうから……」
言いながら、弥彦は央太にずれたふとんをかけなおしてやる。
「竹刀だって、きっとどんどん汚れちまう……。そうだ……あれもう、お前にやるよ」
気がつくと、央太が弥彦の袖をつかんでいた。心配そうに、弥彦を見つめながら……。弥彦はハッとする。
「わりぃ。また訳わかんねぇ話しちまったな。俺ももう寝るから、お前も目ぇ閉じろ」
央太は少しの間弥彦を見つめていたが、やがて素直に目を閉じた。弥彦はそんな央太をながめ、微笑し、頬にそっと触れようとして……。けれどその手は、力無くおろされた。そうして、自分も布団に入った。
数日後。上下ェ門は畑仕事に出かけていた。弥彦が山の草刈りを終えて戻ったのは、昼頃だった。
「弥彦くん! 央太を見なかった!?」
帰るなり、右喜は血相を変えて飛び出してきた。
「右喜と一緒に内職してたんじゃねぇのか!?」
弥彦はあわてて聞き返す。
「ちょっと目を離した隙に……いなくなっちゃって……」
右喜はぼろぼろと涙を流し、弥彦にしがみついた。激しく肩をふるわせる右喜。上下ェ門の言葉を思い出す。右喜は家族を失うことをとても恐れているのだ、と。そして――
『おめぇさん知ってるか? 出ていった者より置いていかれた方がよほど辛いことを……』
泣きじゃくる右喜。
「……」
弥彦はほんの数秒、右喜を見つめ何か考える。
「落ち着け右喜。ちょっとそこいらへんに行っただけかも知れねぇし。俺は外を探すから、お前は家で待ってろ。央太が帰ってくるかもしれねぇ」
そう言い残し、弥彦はかけていった。
走って走って、央太の姿を求めた。どこにもいない。宿場町へたどりついたときには、弥彦はかなり息を切らしていた。そこで騒ぎに気付く。人だかりの輪へ入り前へ出ると、そこには田舎ヤクザ数十名が囲む中、そのうち一人の男が央太に暴行をくわえていた。まわりの人々は、恐怖のあまり助けることが出来ずただ騒ぐばかりだ。
「央太っ!」
弥彦はすかさず飛び出したが、がたいの大きなヤクザ男に行く手をはばかられた。
「央太を離せっ!」
「フン。上下ェ門がなにかと俺らの邪魔をするんで、憂さ晴らしに息子のコイツを痛めつけてただけよ」
男は、歪んだ顔でニヤリと笑う。
「バカかてめぇ。そんなことして、上下ェ門が許すと思うのか!?」
「なぁに。俺らこれでもうこの町とはおさらばだ。逃げるが勝ちと言うしな」
弥彦はドキンとした。逃げる……。逃げる……。逃げてきた……。逃げてきたんだ……。東京から……。剣から……。罪から……。自分は――
人々の悲鳴に、弥彦はハッと我に返る。央太が男に襟首をつるし上げられ、殴られたところだった。
「央太ぁ!」
弥彦は央太を捕らえている男に突っ込み、央太を抱きかかえ向こうの地面へと着地した。群衆から感嘆の声があがった。央太を取られた男は驚いていたが、やがてニヤリと笑い弥彦の背後へ近づく。
「央太! だいじょうぶかっ!?」
央太は、体を何ヶ所か殴られたようで、ぐったりとしている。だが、意識はあるし、重傷とまではいかなかった。けれど、腕の中の央太に安堵する弥彦に後ろから降りかかった声は、あまりに残酷だった。
「お前、スリだろう」
凍り付く弥彦。男は、さらに弥彦に言葉を浴びせる。
「今その小僧を取り戻した技、間違いなくスリの技だ。それも、かなり手慣れていた」
男はさらに弥彦に近づく。
「何千回……いや、何万回スリをしてきたんだ? ええっ!? てめぇは俺らと同類だ。意見出来る立場じゃねぇだろうがよ」
「……」
見物人たちが騒ぐ。弥彦は、苦痛な表情を浮かべる。くやしそうに、ぎゅっと目をつぶり……そうして弱々しく開けたその目を央太へ向けた。
「央太、ごめんな……。お前には知られたくなかったんだ……」
央太は、とまどいながら弥彦を見つめる。
「もう、サヨナラだな……」
そうして弥彦は、央太をぎゅっと抱きしめる。
「だけど、今はお前のこと死んでも守ってやるから……!」
そうして弥彦はさらに央太を包み込むようにして、地面にうずくまった。
「けっ! 何かっこつけてやがんだ!」
男は弥彦の体を蹴りつけた。何度も何度も蹴られたが、弥彦はうめき声をもらさず耐える。いつもなら、すぐに竹刀で応戦した。この程度の敵なら、簡単にやっつけることが出来る。だが――
男は、弥彦の腕をねじり上げる。激痛が走る。うっと、弥彦は小さなうめき声をもらす。
「小さくてかわいい手だなぁ。だがよぉ、この手で、たくさんの人を泣かせてきたんだろう? 大勢のヤツらを不幸にしてきたんだろーがよ! それが何か? 今更正義面しようってのか? 笑わせんじゃねぇぜ!!」
男は弥彦の腹に重い蹴りを入れる。弥彦はげほげほとむせながら、震える手で再び央太をかばう。
東京で、自分が元いた極道連中を見たとき。あの時から、分かっていた。あの時、正義のために剣を振るうことが出来なかった。罪が邪魔をして。かつて自分は同じことをしていたのに、どの面下げてスリをやめろと制することが出来たのだろう。
あの時から、分かっていた。自分には、何も出来ないのだと。してはならないのだと。剣を振るうことも。大切な人たちのそばにいることも。もしかしたら、生きることさえ――
央太を抱いたまま、弥彦の体から力が抜ける。
央太を守って、このまま死んでしまおうか。
「おい! おめぇらもやれ! コイツにはもっと痛い目みせねぇといけねぇや」
男の合図で、まわりにいた数十名のヤクザが、いっせいに弥彦に暴行を加える。弥彦は、央太を抱きながら、痛みで気が遠くなる。思い出す。東京。小さな家に住んでいた。母上。橋の上。剣心と薫と出会った。神谷道場。赤べこ。左之助とじゃれあい。燕に恋をして。懐かしいたくさんの人たち。河原。賑やかな街。桜並木。みんなで歩いた。何度もくぐった道場の門。庭の真ん中にある井戸。いっぱいに干された洗濯物。ちゃぶ台。床の冷たい道場。そんな中で。喜んで。悲しんで。怒って。どきどきしたり。憧れたり。張り切ったり。落ち込んだり。うれしかったり。そんな、さまざまな、気持ち……。
竹刀を握る感触――
弥彦はハッとした。この感触は夢ではない。央太が、弥彦の手に竹刀を握らせていた。央太は、弥彦の手を見つめ言う。
「きれい……だから……」
「央太……?」
「僕は……弥彦お兄ちゃんが好き」
弥彦の、体中の血がどくんと騒いだ。竹刀を持つ手が熱い。
この目に映る弱い人たちや泣いている人たちを守りたい
その思いは、自分の中で決して消えることなどなかったのだ。それどころか、抑えつけていた分、爆発しそうで。
例えそれが許されなくても。目の前にいる大切な者が、それを許してくれるのなら。汚れている自分をきれいだと言ってくれるのなら――
「うわああああぁぁー!!!」
弥彦は腹の底から気合いを込めて叫ぶと、目の前の男に思い切り竹刀を打ち込んだ。あっという間に男は気絶する。弥彦は次々と鮮やかな一本を決めていく。
「なっ、なんだこのガキ!」
「化けもんか!」
「つっ、強いなんてもんじゃねぇぜ! 逃げろぉ!」
ヤクザはあっという間に逃げ去り、残ったものはすでに弥彦にこてんぱんにのされていた。
群衆に歓声があがる。わっと寄ってくる人々の群れに押しつぶされそうになったとき、ふいに自分と央太を抱えて助けたものがあった。それは、懐かしい左之助と同じ匂いで。同じ体温で。
「左之助……。俺、お前に語った夢……、人を守る剣を振るう夢……捨てられそうもねぇ……」
そうつぶやき、剣を捨てることが出来なかった自分がそれでもうれしくて、そしてほっとした。
上下ェ門に抱えられ家に戻った二人を、右喜は泣きながら抱きしめた。まず央太、そして弥彦。ぼろぼろ、ぼろぼろ涙を流して……。
夕方、弥彦がいつものように縁側から夕陽をながめていると、となりにそっと右喜が立った。
「きれいね、夕陽」
陽に赤く染められた右喜を、弥彦はそっと見上げる。右喜は、泣きはらした目をしている。
「そんなに、怖いか? 家族を失うことって……」
ぼそりと、弥彦はたずねる。
「……小さい頃ね、お兄ちゃんがいたの。だけど、急に家を出ていっちゃったの。大切な人がいなくなってしまうって……置いていかれてしまうことって……本当に辛いことよ……」
「……ああ」
弥彦は、外に目をやり、東京の方角を見つめた。
それから、また平穏な毎日が過ぎていった。
上下ェ門は央太が弥彦に剣を習うことを大層うれしがり、竹刀を買って央太に与えた。弥彦はあのヤクザ事件以来、再び竹刀を背負うようになっていた。
「よし! 今日の稽古はここまでだ。上達したな、央太」
弥彦は央太の頭をなで、手を引き、東谷家へと続くあぜ道を歩いた。辺り一面、真っ赤な夕陽に染まる。赤とんぼが飛んでいる。
「もうすぐ秋なんだな……」
弥彦はつぶやいた。時の流れを感じる。このまま自分は、二度と東京には戻らないのだろうか。いや、もう戻ることなどできない。
「なぁ央太。お前、この町に現れた悪一文字の英雄の背中追ってんだろ」
驚いて目を見開く央太。
「お前を見てれば分かるって」
央太は、こくんとうなずいた。いつもより、少し力強く。
「俺には別の追いかける背中があるけど……俺もその英雄の背中、追いつきたいと思うぜ」
央太は、にっこり笑う。
「その人は、お父さんの背中とそっくりだよ」
めずらしく口を開いた央太に驚いたが、弥彦は微笑してうなずいた。
「お兄ちゃんのその人は……どこにいるの?」
「……遠いところだ」
央太は、弥彦の手をぎゅっとにぎった。
二人は、どこまでも続くさみしい道を、長い影を引きずり歩いた。
稲穂が揺れる。空が高い。風鈴の音がさみしく鳴る。すぐそこに秋がきている。夏ももうすぐ終わる。
今日も弥彦は、独り縁側で夕陽をみおくる。ここは、とてもあたたかい。優しい家族に包まれ、穏やかな自然が心癒してくれる。上下ェ門も、右喜も央太も、とても自分を大切にしてくれる。それなのに、さみしいのは何故だろう。薫とは、喧嘩ばかりだった。剣心は、なんでも自分に話してくれるわけではなかった。けれど――
「待っているのか?」
上下ェ門が、弥彦の横に立ちたずねる。
「……」
「なぁに。もうすぐ迎えに来るさ」
弥彦は、思わず上下ェ門を見上げた。
「なぁに。いなくなって探して見つけて、東京からこっちくるにはそれくらいかかるってぇことだ」
「俺、家出した訳じゃねぇんだぜ。ちゃんと一筆書いて出ていったんだ」
弥彦の言葉に、上下ェ門は豪快に笑い出した。
「そんなことしたら、心配で、必死になって探すだろうさ」
弥彦は、笑う上下ェ門をながめる。
「それより問題は、おめぇに帰る準備が出来てるかってぇことだ」
「……」
「おっと。おめぇを追い出そうってぇ訳じゃねぇぜ。ただ、本当の家族があるなら、そこへ帰るのが一番だって言ってるだけだ」
弥彦は、上下ェ門を少し見つめた後、目をそらし夕陽に目をやる。
「オッさん、こないだの騒ぎで知ったんだろ。俺が、スリの常習犯だったって」
「それがどうしてぇ」
あっさり言い返す上下ェ門に、弥彦は驚いて目を見開いた。
「人を守る剣を振るう夢……。いいじゃねぇか。堂々と夢を叶えりゃあいいさ」
その言葉と言い方が、とても左之助に似ている気がして。弥彦は、剣心や薫に言えないことをいつも左之助に話したその時のように、上下ェ門に口を開く。
「剣心と薫には、そう遠くない未来、子供が生まれる。その時俺がそばにいたら……その子がスリをしてたヤツと一緒に暮らしてるなんて言われたら……。それに剣心や薫だってそれは同じで……」
「おめぇ……」
「俺はたくさんの人の幸せを踏みにじったから……。だからきっと、幸せになったりしたらいけねぇんだ……」
無表情で淡々と語る弥彦。けれど、その拳が固く握りしめられていることを、必死で何かに耐えている心を、上下ェ門は見逃さなかった。
上下ェ門は、弥彦を縁側に座らせると、自分も隣りに座った。
「おめぇは並の大人以上に立派だが、やっぱりまだ子供だなぁ」
子供、という言葉に弥彦はわずかに反応する。普段の弥彦なら、すかさず言い返していたところだろう。
「おめぇ、好んでスリをしたのか?」
「そんなわけねぇだろ!」
弥彦は思わず口調を強めた。が、伏し目がちに目をそらす。
「だがスリをしたのは事実……。そう言いてぇんだなおめぇは……」
うつむく弥彦。
「おめぇみてぇに小さな子供が生きるためには、スリをするしかなかったんだろう?」
「……スリをするくらいなら、母上が死んだあの時、俺も死ねばよかったんだ」
「馬鹿なことを言うな」
上下ェ門は静かにうなる。
「けど……俺はその間ずっと……父上母上の誇りが守れなくて……たくさんの人を傷つけて……」
「だから死んだほうがよかったってか? おめぇの父ちゃん母ちゃんはそう思ってるってぇか?」
弥彦は、いぶかしげに上下ェ門を見上げる。
「そんなこと、思ってねぇさ」
上下ェ門の目が優しくゆるむ。
「いいか。親ってぇのはなぁ、子供にはまず生きていてほしいんだ」
「……」
「たとえスリをしようが……喧嘩屋してようが……とにかくまず、生きていてほしいんだ……」
「……オッさんは、左之助が喧嘩屋してても、会えて嬉しかったか?」
「当たりめぇだ」
そうして、上下ェ門は弥彦の両肩に手を置いた。
「おめぇがスリをしてでも生きてきた理由はなんだ?」
「父上と母上の代わりに、俺が生きないといけないと思ったから」
「それでいい。それでいいんだ……」
上下ェ門は、弥彦の頭をなで続けた。
何もかも許してもらえる子供の自分に。それでよいのかと問いかけながら。甘えてはいけないと、いっぱいいっぱい我慢しながら。それでも心を楽にさせてくれた上下ェ門に、少しの間そのまま頭をなで続けてもらった弥彦。
上下ェ門の提案で、その夜は東谷家でささやかな宴会をひらいた。
「お父さんってばたまに突然やろうって言い出すのよねぇ」
右喜は家計とにらめっこしながら、それでもあり合わせの材料でせいいっぱい工夫をこらし、たくさんの料理を作った。上下ェ門は豪快に酒を呑み、弥彦は呑もうとした酒を右喜に取り上げられた。央太は、右喜に世話を焼かれながらもくもくと食べている。
「お父さん! ちょっと呑みすぎよ!」
「まぁいいじゃねぇか」
「央太はお父さんみたいになっちゃダメよ!」
騒がしくも平和な一家を、弥彦はながめる。
「ほら弥彦くんも! 食べ終わったら口のまわりふかないと!」
自分にも同様にかけられる声。けれどさみしい。なぜだろう。
「そんな顔すんなぃ、弥彦」
ふいに上下ェ門の声が降ってくる。
「明日にゃあ本当の家族の元へ帰れるんだからよ」
その言葉に驚いたのは、弥彦だけではなかった。右喜も、そして央太も父を凝視する。
「実はなぁ、おめぇの家族、今日宿場町にきたんでぇ」
「……なん……だって……?」
「おめぇに帰る準備させるために、今日は宿場に泊まってもらったがな」
弥彦は上下ェ門を見つめる。なんだか定まらぬ目で。
「家族って……剣心と薫のことか……?」
「ああそうだ。家族なんだろ?」
「……」
弥彦はもう、何も考えられなかった。右喜が、弥彦を抱きしめる。
「右喜……」
「良かったね……」
右喜は、涙をぽろぽろこぼす。
「俺、まだ帰るってきめたわけじゃ……」
「でも、家族の人はずっと待ってるよ。私が……左之助お兄ちゃんをずっと待っているように……。だから、帰らなくっちゃ……だめだよ……」
そうして右喜は、弥彦をぎゅっとする。
「私が……こんなにさみしいんだから……。家族の人たちは……きっともっとさみしいよ……。言ったでしょ……。置いていかれる人は……さみしいんだって……」
弥彦は、右喜の腕の中でじっとしていたが、やがてうなずいた。
「右喜。泣くなって。お前には、オッさんと央太がいるだろ。それに……きっと『左之助お兄ちゃん』だって、遠いところで元気に生きてらぁ」
「……うん!」
右喜は涙をぬぐい、弥彦ににっこり笑った。
「まぁまぁ。一杯呑めや弥彦」
「お父さん! あっ弥彦くん何呑もうとしてんの!」
その夜、東谷家は夜遅くまで賑わった。
真夜中、床についていた弥彦は、小さな気配に目を覚ます。
隣で寝ているはずの央太が、ふとんに座り、弥彦をじっと見ていた。
「どうした? 眠れねぇのか?」
央太は、浮かない顔で弥彦を見つめたまま。
「……散歩、いくか?」
央太は、こくんとうなずいた。
月夜のあぜ道を、弥彦は央太の手を引き歩く。鈴虫の鳴き声がする。涼しい風が、優しく草を揺らす。
「もう夏も終わりだな……」
弥彦は、ぼそりとつぶやいた。
「俺、まだ実感わかねぇんだ。アイツらが迎えにきたってこと。そーだとしても、俺、本当はまだどーしていいか、わかんねぇんだ……」
央太は、きょとんと弥彦を見上げる。
「けど、ずっとここにいるわけにもいかねぇからな。央太とも、明日でさよならだな……」
立ち止まり。弥彦は央太の髪をなでる。生まれてからずっと、大人たちの世界に生きてきた。極道で暮らし、剣心や薫と暮らし……。いつも、自分が一番年下だった。けれど今目の前にいる、初めて出来た弟のような存在――央太は、守ってやりたくて、可愛がってやりたくて――ずっとそうしてたくて、離れるのはさみしい。けれど……。
「明日からは、またお前が姉ちゃんを守っていくんだぞ」
さみしさを隠し、弥彦は央太に笑う。
「稽古も、独りで出来るな。教えただろ? 素振りのやり方」
「……」
央太は、また浮かない顔でうつむく。
「そんな顔すんなって。大丈夫だ。お前ならきっとやれ――」
央太は、弥彦にしがみついていた。
「行かないで……お兄ちゃん……」
「央太……」
「置いて……いかないで……」
必死で弥彦にしがみつき、肩をふるわせる央太。
「央太……」
弥彦は、央太をぎゅっと抱きしめると、そっと央太をはなし涙を手でぬぐってやる。
「だいじょうぶだ。俺は、少なくとも異国に行っちまうなんてことはねぇ。だから、生きてさえいりゃあ、またいつか会える」
「生きてて……くれるの……?」
弥彦は、ハッとして央太を見つめた。生きる意志を失いかけていたことに、央太も気づいていたというのだろうか――
弥彦は、央太の両肩に手を置き、うなずいた。
「お前があの時俺に言ってくれなかったら……生きてなかったかもしれねぇな……」
『きれい……だから……』
『僕は……弥彦お兄ちゃんが好き』
「ありがとな央太。俺、忘れねぇ」
もう一度央太を抱きしめ、再びはなしたとき、央太はにっこり笑っていた。
「あの……」
「なんだ?」
「弥彦お兄ちゃんの、とっておきの技を見せて」
弥彦はうなずく。
「痛いけど、我慢できるか?」
「うん」
「じゃあ俺に打ち込んでこい。思い切りだ」
弥彦は近くに落ちていた太い枝を、央太に渡し、自分は背中から竹刀を抜く。央太は、助走をつけて弥彦に正面から打ち込む。弥彦はそれを刃止めで受ける。
「神谷活心流・刃渡り!!」
技は見事に決まり、央太は後ろへふっとんだ。地面に叩きつけられる。しまった、加減を間違えてしまったかと、弥彦はあわてて央太にかけより抱き起こす。抱いた腕の中で、央太の目は涙できらきらしていた。
「わりぃ央太」
央太は、首をふって笑った。
「僕、また、お兄ちゃんに会えるかもしれない」
「えっ?」
「かみやかっしんりゅうの道場は、僕がいつか行くところだから。あの人に、そう言われたから」
央太は、弥彦ににっこり笑った。
「左之……いや、悪一文字の英雄さんにか?」
央太は、うれしそうにうなずいた。
「僕にも、その技出来るかなぁ」
「もちろんだ。今度会ったら教えてやる」
「うん!」
弥彦は央太に笑い、夜空を見上げた。こぼれ落ちるような満天の星空。もしも東京へ戻ったならば、もうこんな星空を見ることはできないだろう。
弥彦と央太は手をつなぎ、しばらくの間星を見つめていた。
「世話んなったな」
次の日の朝、右喜と央太に短く別れのあいさつをすませ、弥彦は背を向ける。そのまま、弥彦は続ける。
「俺のちゃんとした名前は、明神弥彦。東京府士族明神弥彦だ」
それだけ言い、弥彦は上下ェ門とともに去っていく。央太は弥彦をじっと見つめ、右喜はその手をそっとにぎった。
「帰る決心はついたか?」
「そーだなぁ。だいたい、ホントにこんなところまで剣心たちがきてんのかよ。オッさん、もしかして俺をこのまま無理矢理東京に連れもどそうってんじゃ――」
「ホレ。そこに来てんぞ」
「え……?」
弥彦はしばらく固まったあと、あわてて辺りを見渡そうとしたが、見渡すまでもなく。すぐそこの木の下に、剣心と薫が立っていた。
「……」
剣心と、薫と、目が合う。この気持ちはなんだろう。この一ヶ月間、東谷家と家族のように過ごしてきたのに。こんなにもほっとして、安心出来て、あたたかいこの気持ちはなんだろう。
「ほれ、行って来い」
上下ェ門に背中を押され、弥彦は一歩、二歩とゆっくり剣心たちにむかう。薫が走ってくる。
「ばかっ」
怒った顔で、目に涙ためて、そうしてそれは泣き顔に変わり、弥彦をぎゅっと抱きしめる。
「弥彦のばかぁっ……」
薫があまりにも激しく泣いて抱き付くので、弥彦は困り果て、薫から離れる。
「泣くな……ブス……」
押し殺した声で、弥彦はうつむく。
「だって……」
「弥彦」
剣心に呼ばれて振り向いたとたん、ぱあんと平手打ちをくらった。弥彦の頬が、みるみる赤くなる。それはぶたれたせいでなく。高揚して、両頬が真っ赤になる。
「剣心!」
薫があわてて剣心に声をかける。
「薫殿。ここから先は男同士の話をする故、しばらく上下ェ門殿と散歩でもしてきてはくれぬか」
「……うん」
薫は、上下ェ門とともに歩いていってしまった。
「何故ぶたれたか、分かるか?」
「……薫を、泣かせたから」
「半分は正解でござるよ」
弥彦は、黙って剣心を見上げる。
「もう半分は、拙者を心配させたからでござる」
弥彦はうなずき、そのままうつむく。
「上下ェ門殿から、だいたいの話は聞いたでござるよ」
剣心は、弥彦の両肩に手を置き、弥彦の顔をのぞきこむ。
「過去の罪に、苦しんでいたそうでござるな」
「ああ。けどもう平気だ。央太と約束したからな。生きるって」
そうして弥彦は、剣心を真っ直ぐに見つめる。
「そのために、罪を背負っていく覚悟だって出来てるんだ。例えば、昔スリをしたことで責められたら、どんなにきついこと言われても、それは本当だから黙って受け入れることとか。例えば……剣心と薫の子供に、そのことを責められたとしても……。黙って、受け入れて……。それでも人を守るためなら、ののしられながら剣をふるう覚悟は出来てるんだ。オッさんは、俺が子供だからそんなもの背負わなくていいって言ってくれたけど、俺は子供だからって、自分を甘やかすのはいやなんだ」
「……そうか」
そのまま、少しの間沈黙が流れる。やがて、弥彦が重い口を開く。
「俺、心配かけたのは悪かったと思ってる。だけど、俺は……、剣心や薫や……生まれてくる子供に……その……」
「それでもいいでござるよ」
弥彦は、目を見開いた。
「スリの子だとののしられたら、拙者がその者に必ず真実を伝えるでござる。弥彦は今、せいいっぱい人を守る剣を振るっているのだと。そうして拙者が弥彦を守るから、だから弥彦は、神谷道場に堂々といればいいでござるよ」
剣心は、弥彦を抱きしめる。
「だから、一緒に帰るでござるよ。弥彦」
「……」
「弥彦?」
黙ってしまった弥彦に、剣心は不思議そうにたずねる。
「右喜が言ってた。置いていかれた人は、辛いんだって」
「……ああ。拙者と薫殿も、辛かったでござるよ」
「だから俺のこと怒ったんだろ。……悪かったとは思うけど、けど、それってなんか、ちょっとだけど納得いかねー」
弥彦は、剣心に抱かれたまま、その背中に手をまわしあらあらしく着物をつかむ。
「去っていくほうだって辛いんだ!」
追いつめられて、爆発しそうで。
「それに、ホントはずっと、待っていたんだ……! 心のどっかで……」
けれどそれを、必死で耐えて。
「縁側で毎日毎日夕陽見ながら、ずっと剣心たちの姿探して――」
剣心の着物をぎゅっとつかんで。
「それに俺だって置いていかれたことがある……!」
「えっ?」
「一度目は母上が死んだとき。けど病気だから仕方ねぇ。二度目はお前が京都へいっちまった時。三度目は縁との闘いの後――」
そこまで言って、弥彦は我に返る。あの時の事情、みんなの気持ち。全部分かってたから。だから絶対に言わないと決めていたことを、今言いかけてしまった――
またしばらく、沈黙が続く。今度口を開いたのは、剣心だった。
「弥彦。続き、言ってはくれぬでござるか?」
弥彦は、思いきり首をふる。
「……今まで我慢ばかりさせて、済まなかったでござる。ちゃんと聞くから、言ってほしいでござるよ」
「……」
「弥彦」
剣心は、弥彦を抱く手に少し力をこめる。
「縁との闘いの後、みんな……俺を置いていなくなった……! 薫も……左之助も……。剣心も……」
ひくっと、弥彦の肩が震える。
「誰もいなくなって……。道場へ帰る途中、剣心たちと初めて会った橋の上通って……。俺、さみしくて苦しくて……どうしようもなくて……」
弥彦は、剣心にぎゅっとしがみつく。
「も……あんな……思いするのは……っ、うっ……いや…だ……」
ずっとずっと我慢してきたものがあふれて。
「ひとりに……なるの…は……いやだ……っ。母上が……しっ…死んだ………、とき、みたいに……。うっ……うっく……、神谷……どーじょぉから……みんな……いなくなっ……あのとき……みた…に……っ」
激しく泣きじゃくる弥彦。それでもなお、泣くのをこらえながら泣いている弥彦。
「済まぬ弥彦……。もうどこにも行かないでござるから」
弥彦の背中を、優しくさする。何度も、何度も。その度弥彦の泣き声は激しくなる。この一ヶ月、いや、今までずっと、ずっとずっと、我慢してきた涙があふれる。
「弥彦は強い子で、それは当たり前だと思っていたでござる。けれど、弥彦は、どんなに辛いときでも、耐えて耐えて、我慢して我慢して、絶対に弱音など吐かずに、頑張って……だから強い子だったのでござるな」
剣心は、弥彦の背中をなで続ける。
「けれど、泣いてもいいのでござるよ。弥彦」
弥彦の体が、かすかに反応する。
「泣いたからって、弥彦は弱くなったりしないでござる。それに……」
剣心は、もう一度弥彦を抱きしめる。
「大事な家族が、辛い気持ちを我慢してるのは、嫌でござるから」
弥彦の体の力がするりと抜けて。ずっと重かった心がゆるんで。今までこの少年は、どれだけ張りつめていたのだろう。
剣心の胸から崩れるように膝をつき、意識を失うように眠ってしまった。
目が覚めたら夕方で。辺りは真っ赤に染まり。剣心が隣りにいてくれた。ずっと、そばにいてくれた。仰向けで見る空はどこまでも広く、赤とんぼがたくさん飛んでいて。
剣心が笑ってくれる。笑い返そうとして、涙があふれた。泣き疲れて眠るほど、たくさんの涙を流したというのに。
「帰ろう弥彦。薫殿が待っているでござるよ」
少し離れた道ばたで、薫はかがんで花を愛でている。弥彦は体を起こす。
「……ああ!」
涙をぬぐい、そうしてようやく、弥彦は笑った。
少し先を歩く、剣心の背中と。
花を愛でる、薫の優しい手に。
これからも守られて生きていく。
それが少しだけくやしく。
そして最高に幸せだと思った。
「あれ? オッさんは?」
「別れのあいさつは苦手なんですって」
「オッさん……」
「またいつか会いに来ような。弥彦」
「ああ」
夏の終わりに。空は高く。赤とんぼが飛び。鈴虫が鳴き。涼しい風が吹き。剣心と薫。家族とともに過ごした。それは例えば、夕立がやんだ後の虹のように。ほんの短い一時で。けれど、剣心がいて、薫がいて。ほっとするたび胸がいっぱいになった、十歳の、夏の終わり――
☆あとがき☆
トッポ様より75000キリ番リクエストです。今回「るろうに剣心明神弥彦生誕祝い企画」中のリクエストでしたので、企画の一つとさせて頂き、通常より長い作品となりました。
頂いたリクエストは「弥彦。仲間もの。弥彦が赤べこの日雇い帰りに自分がいたヤクザ集団を見かけて……」です。
リクエスト者様から当サイト小説『きみの未来』の感想を頂いた際「時に昔を思い出す弥彦」がよかったとのうれしい感想を頂きまして(ありがとうございます^^) その内容、小説内で思い当たったのが、お祭りのときのお話なんです。弥彦が、去年まで祭の日はスリをしていたのにって、過去に触れ辛くなる場面があるんです。そんなところから、この作品を作っていきました。弥彦の罪とつぐない、そして成長。
他に「仲間もの」との指定がありましたので、弥彦と東谷一家の仲間もの、弥彦と剣心・薫の家族ものを要素にいれました。
この作品、自分の妄想に似つつも少し違い、かといって原作弥彦ともまた違い、今まで書いていそうで書いていなかった作品になりました。
弥彦の十歳の夏。少しでも心に響くところがあれば幸いです。
75000キリ番リクエストありがとうございました。
この物語を、トッポ様へ捧げます。
ご感想、日記のコメント欄か 掲示板 に書き込みしていただきますと、とても励みになります。
るろうに剣心小説(短編)目次
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- この秋読んだイチオシ本・漫画
- 【中古】奪う者 奪われる者 <1−10…
- (2024-11-27 13:54:27)
-
-
-

- ジャンプの感想
- 週刊少年ジャンプ 2024年第52号
- (2024-11-28 11:10:37)
-
-
-

- 連載小説を書いてみようv
- 白い沈黙
- (2024-11-27 21:00:10)
-
© Rakuten Group, Inc.