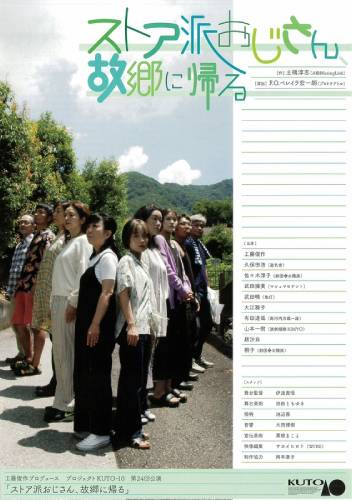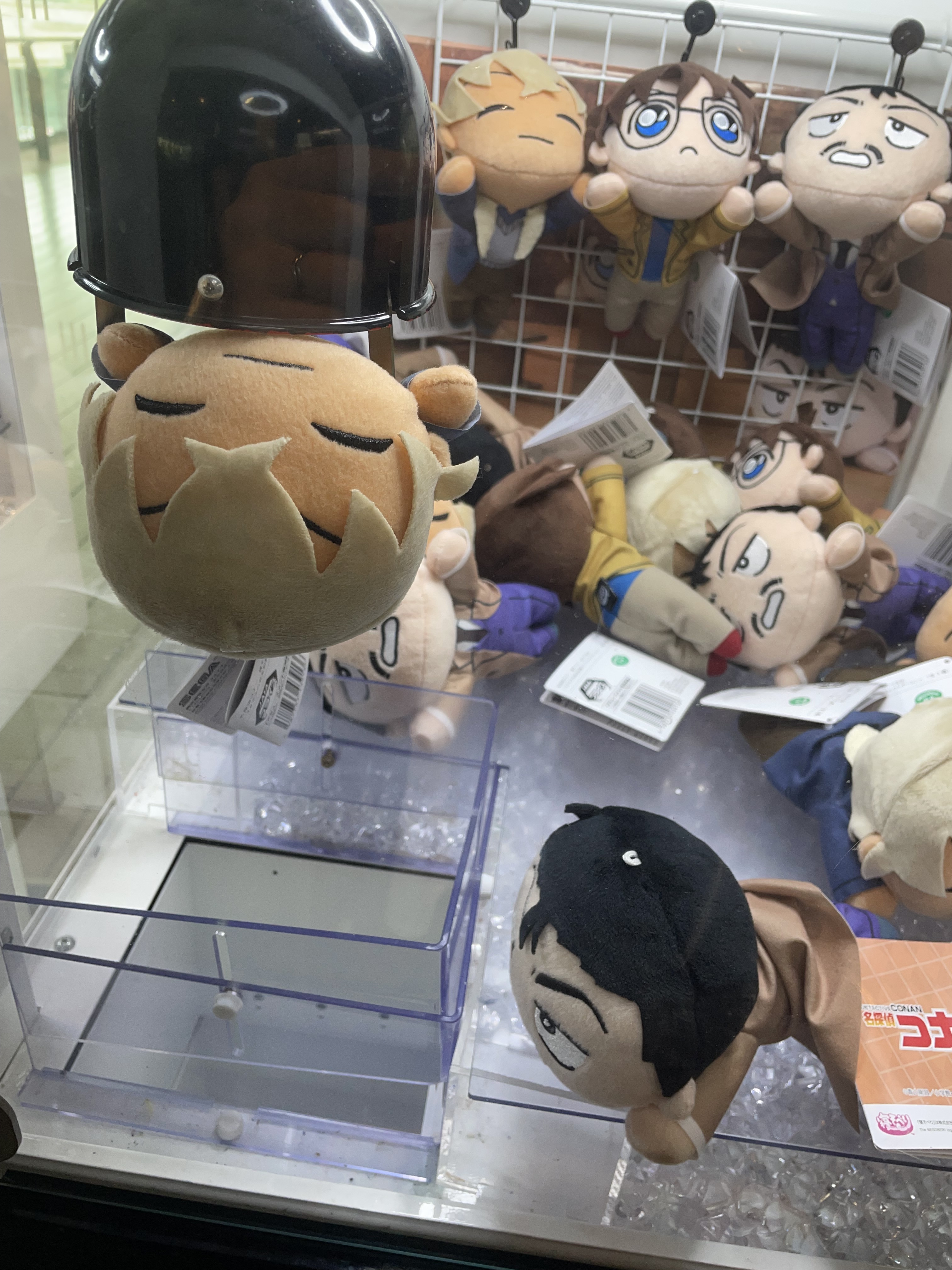「文楽初春公演」
国立文楽劇場で、文楽人形による三番叟の舞いを見た。初春文楽劇場の公演番組は
「壽式三番叟」
「お染久松 染模様妹背門松」
生玉の段、質店の段、蔵前の段
「壇浦兜軍記」
阿古屋琴責の段
以上の豪華なメニュー。
特に「三番叟」と「阿古屋」が見たくてチケットを買った。
国立文楽劇場の正面入り口には、新春らしく門松が置かれ、華やいだ雰囲気。

中に入ると、着物姿の女性も多く、舞台上部には「にらみ鯛と凧」も飾ってあり、お正月気分が戻ってきた。

「三番叟」の舞台は、能楽と同じしつらえ。
正面には松羽目があり、舞台の下手には橋懸りや三本の松がある。
人形も揚幕から登場する。(ちなみに人形がはいている足袋の色も、狂言と同じ黄色だった)
義太夫が天照大神の岩戸神話を語りはじめる。
アメノウズメノミコの舞が、全ての芸能の発祥となったという故事による語り。
映画「陰陽師Ⅱ」を思い出してしまった。
萬斎さんの女舞いは、三番叟に繋がっていたんだ・・・と思う。
翁の舞いでは、文楽人形にも面をつけて舞っているのを見て、感心する。
その舞の後、2人の三番叟が連れ舞い「揉の段」を始めた。
狂言の「三番叟」に比べ、文楽人形の衣装は艶やかである。
袴の柄は松、肩衣(文楽ではどういうのだろう?)の柄は鶴。
舞は狂言と同様、足で床を踏み鳴らす動きが多く、人形の足が何度も床をける。(実際には人形遣いが踏んでいるのだが)
「鈴の段」では、千歳から受け取った鈴を振りながら、賑やかな舞が始まる。
あまりにもテンポが速くなるので、途中三番叟の1人(人形頭が又平の方)が倒れこむ動作をし、扇であおぎながら汗を拭く。
その動きがこっけいで、観客の笑いを誘う。
狂言の「三番叟」に比べて、神事的な要素より、エンターテイメント性が高くなっていると感じた。
「三番叟」が終わると、新春恒例(らしい)手ぬぐい投げがあった。
三方にのせた手ぬぐいを、3人の技芸員が観客に向かって投げる。
たまたま1本の手ぬぐいが、私に向かって飛び込んできた。ラッキー!

「阿古屋琴責の段」
歌舞伎の演目でも、同じものがある。
阿古屋を演じる女形は、琴、三味線、ニ胡の演奏が出来なければならない。
阿古屋は、それぞれの楽器の名手なので、演じる女形もそれなりの演奏をしなければならないのだ。
歌舞伎界では、坂東玉三郎さんがよく阿古屋を演じている。
以前「たけしの誰でもピカソ」というTV番組で、阿古屋を演じるためにそれぞれの楽器を習っているということを、玉三郎さんは話していた。
さて、文楽人形の阿古屋の場合はどうなのだろう?
それが阿古屋を見る楽しみの一つでもあった。
結果は、当然と言えばそうなのだが、囃し方の一人が人形にあわせて琴、三味線、ニ胡を弾いていた。
阿古屋の人形遣いは、重要無形文化財保持者の吉田蓑助さん。
人形を見、演奏を見、音に聞き惚れ、なかなか忙しい番組だったが、楽しめた。
2004年1月12日 国立文楽劇場
© Rakuten Group, Inc.