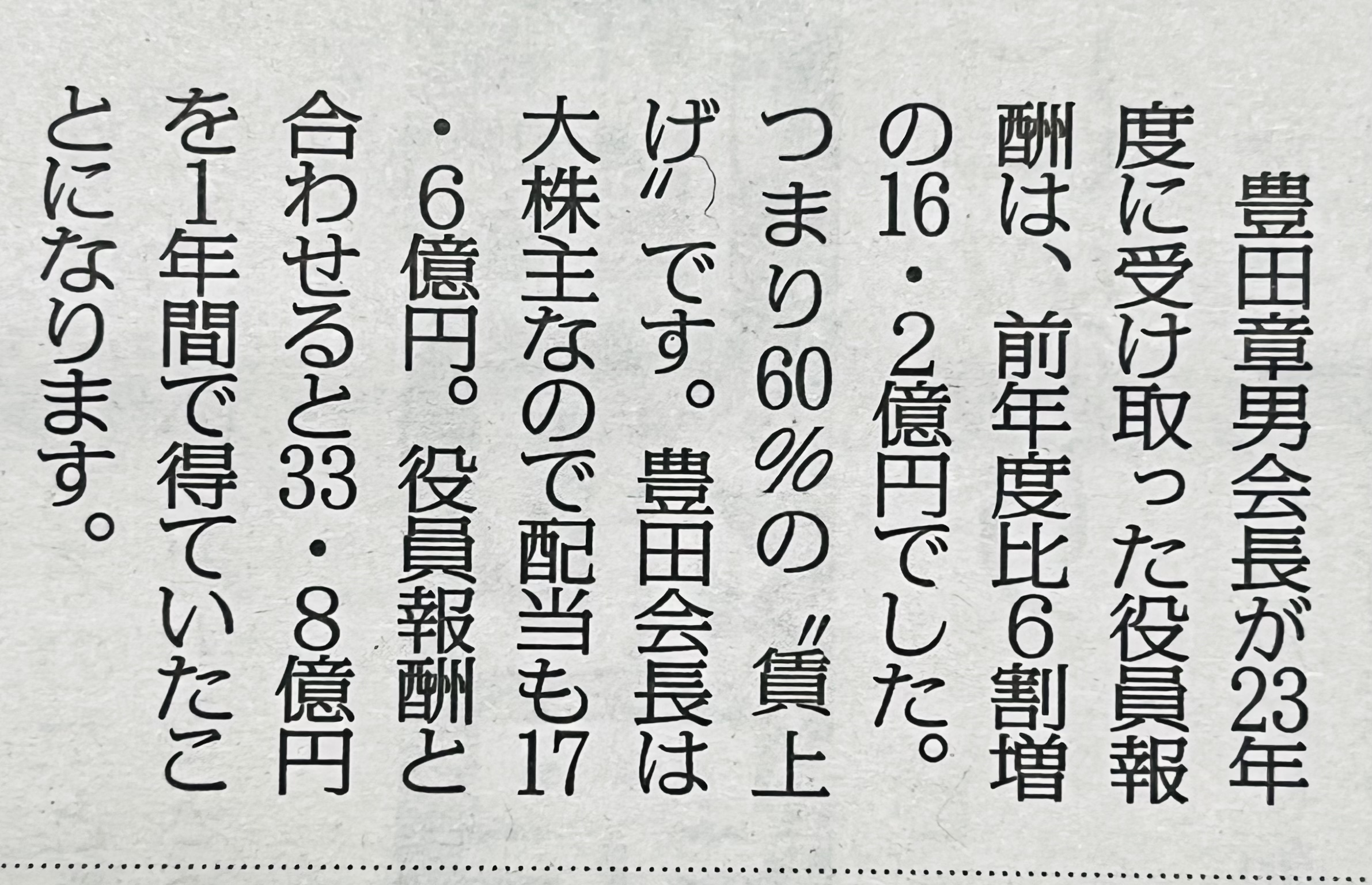砂漠の果て(第12部「告別」)

4月になってからずっと、ムカールは、自分でも不思議なほど体が軽く、死の恐怖に慄いたことなどまるで嘘のように感じていた。だが彼自身、これはほんの一時のことに過ぎず、自分の命は既に、危うい綱渡りのような儚いものに過ぎないのだということは忘れはしなかった。それでも生来、自由で陽気な性格の彼は、「今を楽しめ」という心情になっている間は、あまり先々のことを考えたりはしなかった。
午前中はいつものようにザキリスの病院に翻訳の仕事にでかけ、調子の良い時は、近くのスーク(市場)で軽い買い物をして帰った。彼は、アルブラートの19歳の誕生日にラジオを贈ったが、アルブラートとアイシャの演奏がラジオで流れるようになると、自分でもラジオが欲しくなった。
仕事の時間の都合や、体調の悪さのために、なかなかアルブラートのレストランでの本物の演奏を聴けないのを、ムカールは残念がっていた。だがラジオで彼らの演奏が流れるようになると、夕食の後、アルブラートに頼んで、自宅にラジオを持って来てもらい、聴くようになった。
最初はそれで満足していたが、驚いたことに、むずがる時はどんなにあやしても泣き止まなかったアザゼルが、ラジオの演奏を聴いた途端に泣き止むのだった。ムカールは、アザゼルのために、いつもラジオでアルブラートの演奏を聴かせ、それをテープに録音できないかと考えた。
ある日、昼頃立ち寄ったムカールに誘われて、アイシャと共に、アルブラートは3階の彼の自宅を訪れた。奥の居間に行くと、小テーブルほどの黒い大きな機械が置かれてあった。ムカールは、これはイギリス製のステレオだと説明した。当時はステレオは非常に珍しい物だった。
「ステレオ……?これで何をするんだい」
「これはラジオも聴けて、その音楽もテープで録音して聴けるんだ。レコードもここにかければいつでも聴ける。いいだろう。割と安かったんだ。2000ポンド」
2000ポンドは、ムカールの病院での2ヶ月分の給与がほとんど無くなる額だった。アルブラートがその値段に驚いていると、ムカールは愉快そうに笑った。
「お前、こう思ってるんだろう―やっぱり俺が金遣いが荒い奴だなってさ」
「そんなことないよ―これで、俺たちの演奏がいつでも聴けるし、アザゼルも喜ぶんだろ。ちっとも無駄遣いじゃないよ―アデルにもちょうどいい気晴らしになるじゃないか。でもこれ立派でいいな。2000ポンドは高くないよ」
ムカールはアルブラートにテープを見せ、最近録音したアルブラートの演奏とアイシャの歌をステレオにかけてみせた。途端に、心の溶けるような美しいカーヌーンの音色と、遥か天の高みから響き渡るような張りのある、煌びやかなアイシャの歌声が流れてきた。
ムカールはソファーに座りながら、じっとその調べに聴き入っていた。アザゼルは目がぱっちりと見開かれ、甘えるような声を出すようになった頃だった。昔はアルブラートの演奏を「楽な仕事だ」と羨んだアデルも、子供を産んでからは穏やかな性格になり、彼の演奏とアイシャの歌声に感嘆していた。
彼女はもう21歳で、モロッコ人の父親譲りの褐色の肌がしっとりと輝き、濃い長い睫毛が黒目がちの瞳に神秘的な翳りを与えていた。以前よりもよく微笑むようになったアデルを、ムカールは「砂漠の女性の中で一番美しい」と言っては、彼女を深く愛し、このうえなく大切にしていた。
ムカールは演奏を聴き終わると、向かいに腰掛けていたアルブラートに話しかけた。
「本当にお前の才能には頭が下がるよ。もう超一流だな。その証拠に、カイロのラジオ局がお前たちの演奏を流すようになったんだから。あんなホテルで終わらなくて良かったな―おまけにアイシャも、一流のオペラ歌手顔負けの声をしてるんだもんな。アルラートはこれからもますます伸びていくんだ―ほらほら、パリでの成功が見えてきたぞ―アルラートのヨーロッパでの成功が手に取るように見えてきたぞ」
ムカールはこう言うと、すっかり満足したようにふふふと笑ってみせた。
アルブラートはなぜ彼がまたパリの話をするのかが分からず、不思議そうに黙っていた。ムカールは深みのある温かな低い声で、真面目な顔で繰り返した。
「お前、俺の言うことを信じてないな。俺は本当のことしか言わないんだ。パリでの成功は必ず起こる。パリで成功することは、ヨーロッパを制覇することだ。お前ならきっとやり遂げる―お前はパリ音楽院で正式に勉強して、プロとなって、アラブ音楽をヨーロッパに広める使命を担っているんだ」
その時、アザゼルが不満げに母親の腕の中でぐずり出した。
「お乳の時間なのよ。アジー、いい子ね」
アデルは娘をあやしながら、赤子の小さく柔らかい唇に乳をふくませた。アザゼルは喜んで飲み始めたが、途中で止めると、子猫のような声で泣き始めた。ムカールがもう一度、演奏のテープをステレオにかけると、アザゼルは安心したように、再び乳を吸い出した。
アイシャはアザゼルを覗き込んでは、金髪がかった小さな頭をなで、可愛くてたまらないと言って、赤ん坊を時々抱かせてもらった。アルブラートは、顔立ちがだんだんはっきりしてきたアザゼルを見て、この子はまったくムカールによく似ていると思った。年頃の娘盛りになれば、さぞかし美しくなるだろうと思われた。
「アルラートは舞台での挨拶は全部英語だな。お前の英語は本当に達者だな。確かアイシャの父さんに昔習ったんだろ。立派なイギリス英語じゃないか。俺は英語は独学だから、お前に比べるとまったく話にならないよ」
アイシャは自分の父親の話に、少し顔を赤らめた。アイシャは目が見えるようになってからこの2ヶ月ほど、少しずつ読み書きができるようにと、アラビア語と英語の練習を続けていた。
「アイシャの父さんは、学生の時に3年間ロンドンに留学していたんだ―俺は7歳から14歳まで、アイシャの父さんに英語を教わったよ。とても優しい立派な人だったんだ」
「お前―舞台では絶対にアラビア語を使わないようにしているんだな」
アルブラートは組み合わせた両手を膝の上に置いたまま、じっと考えていた。
「お客にはイギリス人も多いし......カイロの言葉は本当に正統な発音だから―俺の訛りはきついから、すぐにパレスチナ人だって分かってしまう。身元を人前に曝したくないんだ。ゲリラと誤解されそうで......」
「そうだな―お前のパレスチナ方言ははっきりしてるからな。お前も苦労が絶えないな。でも身元とか素性なんて、変なものだな。あんなのは、他人と関わると何かと問題になるんだ。お前は身元ははっきりしているのに、それを人前では隠したい―俺は身元が謎に包まれているから、人から信用されない。俺たちは似た者同士だよ、まったく」
ムカールは子供が生まれた以上は、アザゼルのためにも国籍を何とかしてやらないといけないと思った。彼は、近々対面せねばならないオルガ大公妃のことを忘れてはいなかった。だがその前に、以前アルブラートが提案したように、アデルと正式に挙式を済ましておかねばならないと考えていた。
「アルラート。あさっての晩に、この家で挙式をしたいと思うんだ。アデルは西洋風のドレスを着たいって言うから、先週貸衣装屋から借りてきたんだ―8時から1時間ぐらいで済ませるから、来てくれよ。写真は、ドクターにお願いしているんだ」
アルブラートは喜んで出席すると答えた。彼は、その日から早速、ムカールへの贈り物を用意し始めた。それは、自作の詩と、ムカールの挙式のために買っておいた、金色の懐中時計だった。
1961年4月20日のことだった。アルブラートはレストランの主人に事情を話し、早めに仕事を済ませると、舞台衣装のまま、8時前にムカールのアパートをアイシャと訪れた。アイシャもまた、レースの白地にオリーブ色の刺繍をあしらった舞台衣装を身につけていた。彼女は花束を抱え、アルブラートはかねて用意していたプレゼントを手にしていた。
3階の部屋に入ると、ムカールはタキシード姿で二人を迎えた。彼の様子はほがらかで、いつも以上に生き生きとした表情をしていた。アルブラートは彼の黒い宝石のような瞳がこんなにも輝いているのを見たことがないように思った。
純白の花嫁衣装に身を包んだアデルは、2メートルほどの透き通ったベールを床に垂らし、奥の部屋から姿を現わした。彼女はザキリスに手を取られて、ムカールのそばに歩み寄った。
ザキリスが、誓いの言葉をラテン語と英語で読み上げた。
「いつ何時とも、何人も、この二人を裂くことのないように―死が二人を分かつまで永遠に生を共にするように―神よ、この祈りを聞き届け給え」
二人は指輪を交換し、接吻を交わした。アイシャは手を叩いて、花嫁に花束を渡した。アルブラートもホッとしたように笑みを浮かべると、ムカールに贈り物を渡した。こうして挙式は無事済んだ。アザゼルは、ベビーベッドの中で、大人しく寝ていた。
ザキリスは、先ほどの誓いの言葉を読み上げた自分は無責任すぎると感じていた。
「死が二人を分かつまで」だって......?もうすぐこの青年には「死」が訪れるのではないか......この挙式はほんの一時の慰めなのだ―アデルはあと何十年でも彼と一生を共にしようと思っているというのに......
式を終えると、皆はダイニング・テーブルについた。この日のために、医師は、アルブラートの勤めるレストランから特別料理を注文し、アパートに運ばせていた。
「アデルはモロッコのベルベル人なんだ。でも育ったのはアルジェだからフランス風の結婚式に憧れてたんだよ。今はアルジェは5年前から独立戦争をしているのにさ―フランス人は嫌いなんだろう、アデル」
「そうね。私の子供時代は、フランス人が街の官吏で、母の勤める絨毯工場も、フランス人が取り仕切っていたわ―今だって、独立戦争を、フランス人は 『野蛮人と文明人の戦争』 だなんて言ってるほどよ。でもそれとは別なの―不思議ね。西洋に憧れるなんて」
アデルの『野蛮人と文明人の戦争』 という言葉に、アルブラートはわずか4年前の、捕虜収容所での出来事をふと思い出し、嫌悪感が体を突き抜けた。
あの男は―アラブ人のことを「野蛮」と貶した...... そして自分のことを「文明人」などと言っては俺たちを差別した......
この世界は結局は欧米人が優れていると―そういう見方が支配している―
そんな世界観は誰が―いつの間に作り上げたんだ......?
ムカールは、食事の手を止め、アルブラートからの贈り物の包みを開けながら、アデルにこう言った。
「アデル。アルジェの戦いは、きっと来年の3月頃には終わるさ―アルジェはフランスからの独立を勝ち取るんだ。そうしたら、お前とアルジェに行ってみたいな」
「あなたって―何でも予言をするのが好きね。でもそれが不思議と当たるんだから。女の子が産まれるって言っていたのも、本当だったもの。じゃ、独立戦争の話もきっと当たるわね」
ムカールは微笑みながらうなずくと、アルブラートのプレゼントに目をやった。途端に彼はハッとしたように、贈られた物に目を凝らした。青い包み紙の中には、金の懐中時計と、そのそばには、フランス語で書かれた短い詩が添えられてあった。
君は僕の最高の友
君の手は僕の手をとり未知の世界へといざなう
僕の知らなかった街へ 港へ 海へ 異国へ
君は僕の永遠の友
君の目は僕に何かを語りかける
真実を 希望を 友情を 夢を
その黄金の輝きは僕の生を彩る
君の存在が 君の生が僕のすべて
君の心は僕の心と響きあい
その黄金の命が永久(とわ)に息づき
僕の心を大きく包み
僕の魂を永久に救う

ムカールはその詩を読んで、自分がアルブラートの魂をもはや救えないという絶望感が心臓を貫くのを感じた。アルブラートの心は、自分が生きて存在することで支えられていることを、改めて悟ったからだった。だが彼は、動揺する心を強いて見せまいとした。
彼は、テーブルの斜め右に座っているアルブラートに、詩と金時計のお礼を言うと、ワイングラスを手に取り、バルコニーに出ないかと誘った。バルコニーの手前には、ムカールがスークで手に入れたレバノン製の艶やかな木製の机が置かれてあった。彼はグラスを机の上に置くと、一番上の引き出しから何か書かれた紙を取り出し、アルブラートに渡した。
バルコニーに出ると、夜のひっそりとしたしめやかな香りの中を、コーランを読み上げる夕べの祈りの声がどこからか響いてきた。二人はベンチに腰掛け、しばらく街の夜景の煌きと、遥か遠くに光るナイル川を眺めた。
アルブラートが青年から渡された紙には、エリュアールの詩『リベルテ』が立派な筆跡で書かれてあった。ムカールはワインを飲むと、それは自分が詩集から写し取ったのだと言った。
「アルラートには、あのフランス詩集をあげたけれど、俺はその詩が昔から好きだったんだ。何回も読んだから頭に入っている。それをそのまま書いたんだ」
彼は、アルブラートをじっと見つめた。彼の真っ直ぐな額からは、流れるようなウェーヴのかかった艶のある黒髪が、夜風に吹かれてやや乱れたような形でこぼれかかっていた。アルブラートには、その髪が、宝玉のような彼の黒い目が放つ微妙な光と共に、滝のように連なっているように見えた。
「お前はアラブの中のアラブ―才たけて容姿麗しく、詩を愛し楽神でもある―俺にはお前は、まるでベツレヘムのアドニス* のような存在だよ......あの詩をありがとう。嬉しかったよ......お前は詩を書くのが本当にうまいんだな」
アルブラートは、あの詩は急いで書いたから、あまり出来栄えは良くないと断った。だがやはり率直に詩を誉められると、嬉しかった。ムカールはにっこり笑ったアルブラートを、まじまじと見入っていたが、ふいに右手を彼の褐色の頬に静かに当てた。
本当にこの子は......なんて純粋な美しさなんだろう......磨き上げたような透明なマホガニーのような肌をして―すっきりとした理知的な顔立ちをして―手足がすらりと伸びて......どんな人にも愛される深い情のこもった若い鹿のような愛らしい瞳をして......この子は俺には二度と与えられない最高の神の贈り物だな......
アルブラートは、頬にムカールの手の温かみを感じ、これは彼の友情の証なのだとふっと思ったが、何か照れくさい気持ちがして、不思議そうに微笑んだ。
「何だよ―俺の頬に触ったりして」
「いや......ただお前が本当の弟みたいに思えてさ―アルラートの笑顔をいつまでも見ていたいって思ったんだよ」
ムカールは手を下ろすと、少し黙っていたが、何気ない調子でこう言った。
「そのエリュアールの詩と、お前がさっき贈ってくれた詩は、俺の机の一番上の引き出しに入れておくよ。それで......お願いがあるんだ―もし俺に何か万が一のことがあったら、その2つの詩を俺と一緒に埋葬してくれないかな」
この言葉に、アルブラートの微笑みは途端に消え失せた。彼は表情を曇らせ、先月ザキリスが話した「ムカールの命はもう数ヶ月もない」という宣告を急に思い出した。普段から、その宣告は彼の心の中で揉み消されていた。先月味わった刺すような恐怖が、今また甦り、彼の頭は混乱と戦慄でいっぱいになった。
「埋葬......?万が一のことって......なんでこんなおめでたい日にそんなことを考えるんだ......そんなの―ずっと先のことだろう」
「うん.....先の話だよ。年をとってからのことだよな......今から約束しておきたかっただけさ。ごめんな―こんな祝いの最中に話したりして」
ムカールはまだ何か言い足りない様子だったが、それ以上何も言わず、室内に戻りかけた。
アルブラートはエリュアールの詩篇を彼に返すと、妙な胸騒ぎを覚えながら、席に戻った。彼は、悪夢に悩まされる時のような心臓の高鳴りを感じていた。アイシャは彼の表情を一目見て、また何か心配ごとが起きたのだとすぐに察した。
アデルは、そばに来たムカールに話しかけた。
「明日、アルブラートとアイシャが私たちとドクターをレストランの演奏会に招待してくれるそうよ。今、そのことを話していたの。挙式のお祝いですって」
ムカールはそれを聞いて喜んだ。
「それじゃ、今度は本当にアルラートの生演奏が立派なステージでゆっくり聴けるな。俺からもアルラートとアイシャにプレゼントがあるんだ。明日、演奏のあとに渡してもいいかな」
アルブラートは、バルコニーでの会話のことを考えこんでいたが、はっとして青年の方に顔を向けた。彼は、祝いの席で心配そうな様子を見せるべきではないと思い、さりげない風を装った。
「ああ―いいよ。楽屋裏にいて待っているから。演奏っていっても、いつもやっているようなものだけど―これがいい機会だと思って。6時から始まるから。アザゼルも喜んでくれたらいいな」
* アドニス(アリー・アフマッド・サイード):1930年シリア生まれの詩人。1956年、政治的理由からシリアを離れ、レバノンのベイルートに移住し、詩誌『詩』を創刊。

翌日、夕方になると、ムカールはネクタイをしめて正装し、ザキリスと出かけた。アザゼルはやや風邪気味になったために、アデルは外出できないのを残念がっていた。レストランへの道すがら、ムカールは昨夜のアルブラートとの会話を思い起こしていた。
あんな話を昨日するんじゃなかった......
どうせならドクターに頼めば良かったんだ―
俺は本当に馬鹿な奴だな......
アルラートが人一倍感じやすいのは分かっていた筈なのに......
彼の笑顔が消えて欲しくないと思っていたのは俺自身なのに......
アルブラートの勤める高級レストランまでは、ムカールの足では15分ほどだったが、彼は医師とゆっくり歩いて行った。ザキリスは、考えこんでいる青年に、いつもの落ち着いた口調で話しかけた。
「あなたはアデルとの挙式も済まされたし......お子さんが生まれてもう1ヶ月ですね。前お話したアルメニア大公妃は、実はもう1週間前からアテネからいらして、この街のホテルに滞在なさっておられるんです―そろそろアデルに大公妃のことをお話していただけますか」
ムカールは、大公妃の話をすることで、アデルの微笑みまでもかき消され、彼女に大きな悩みを与えるだろうと思うと、気が進まなかった。だが医師との約束には忠実でありたかった。彼は歩きながら、少し考えをめぐらしていたが、やっとザキリスを見ると、決意したように言った。
「......それでは、明日、彼女に話してみます。でも大公妃とお会いしても、何をお話したらいいのか―まったく見当がつきませんが―その方とお会いするのは早い方がいいんでしょう」
ザキリスは、ムカールの現在の小康状態が維持されている、この数日以内が一番良く、手遅れにならないうちに二人を対面させたいと常々願っていた。だが「手遅れにならない今が絶好の機会だ」と考えていることを悟られないように、平静な態度で相槌を打った。
「あなたのご意向をあまり考慮に入れずに、私はあの方のご希望を叶えて差し上げたいばかりに―あなたには本当に申し訳なく思っています。でもご子息を探し当てたいというのは、あの方の20年来の悲願なのです。急なお話でしたが、あなたにもお母様と思われる方に引き会わせて差し上げたいと......私はこう思いましたのでね」
ムカールはそう話す医師をじっと見つめていたが、また少し考えた後、戸惑ったように言葉を返した。
「......それは先生の私に対するご好意であると理解しています......でもその方と私とでは身分があまりにも違いすぎて―本当にお会いするべきなんでしょうか」
「何もご心配はいりませんよ。あの方は身分や体面を重んじた上で、ご子息を探してこられたのではありません。ただ、ひとりの母親として、大事な息子に出逢いたいと―そればかりを念じてこられたんです。あなたが何もお気遣いにならなくても、自然と会話は生まれますからね」
目的のレストランは、建物全体をライトアップし、3階建ての豪華な造りだった。入り口から客席や階段に至るまで、赤い重厚な絨毯が敷き詰めてあった。ザキリスが接客係に名刺を見せると、係の者は、医師をいつもの席に案内しようとしたが、連れの客を一目見た途端、ハッとし、恭しい物腰で、2階の席に二人を案内した。
そこはレストラン全体と、ステージをよく見渡せる一等の貴賓席だった。ムカールは驚いて、ボックスの天上の高さや、手擦りやテーブルや椅子の立派な作りに目を見張った。天上からは、金糸の刺繍の施されたベルベットのカーテンが、ベッドの天蓋からのようにかかっていた。
青年の様子に、ザキリスは微笑んで、こう言った。
「多分案内係は、あなたをどこかの貴公子がお忍びで訪れたのだと思ったのかもしれませんね」
その言葉に、医師の自分の容貌に対する賛辞をムカールは感じ取ったが、外見を誉められるのを嫌う彼は、黙って返事をしなかった。
やがて6時となり、食事が運ばれて来たが、それとほぼ同時に舞台の幕が開き、アルブラートとアイシャが現われた。アルブラートは全体に黒のベルベットの衣装だったが、上着は左右に金の細かな刺繍が織り込まれていた。その黒い衣装は、彼の細い体を更にすらりと美しく見せていた。
アイシャは、目の淵に化粧をし、真紅の生地に白い蔓草模様をあしらった長いドレスを身につけていた。
二人が登場すると、馴染みの大勢の客が割れるような拍手を贈った。周囲が静まると、ひと呼吸置いて、アイシャがいきなり高らかに歌いだした。
お金も宝石も私はいらない
宝物はいつも私の心
私は砂漠で生まれて
砂漠で死んでいく
オアシスで倒れた
白い駱駝のように......
私は砂漠の白い鳥となって
天女のように絹の衣をまとい
高い空を自由に舞うの
ただひとつの緑豊かなオアシスを求めて
ああ あの駱駝はどこに行ったの
神よ 私をあの駱駝に乗せて
神よ 私のブルカ* をどうぞ見つけて
どうぞ愛の泉に私を連れて行って......
* ブルカ:伝統的にイスラム世界の都市で用いられた女性のヴェール(ヘジャブ)の一種。

アイシャの歌声に添うように、続けてアルブラートがウードをゆっくりと奏で始めた。その旋律は2回繰り返された後、やや高い音階となり、速度も上がっていった。その音色から、広大な砂漠の寂寞な景色が浮かび上がった。ムカールは、絵や写真でしか見たことのない砂漠やオアシスが今、目の前に現われているように感じた。
ウードの演奏が終わると、すぐに再びアイシャが歌いだした。
泉のほとりに誰かがいるの
それは私の探し求めた人 私の愛する人 私を愛してくれる人 泉のほとりで彼が私を呼ぶの
優しく 美しく ひそやかな声で
泉に湧き出る黄金のしずく
私は裸足で走っていくの
太陽の光と砂漠の風を受けて
あの人の微笑と泉が乾いた喉を潤してくれるように
そう祈りながら
でも愛する人の姿は蜃気楼となって
いつも消えてしまう
わたしの目の前で
私はオアシスで倒れた白い駱駝のように
泉のほとりで倒れ
愛の夢も幻のように消えていく......
アルブラートは今度は、先ほどの旋律をカーヌーンで、徐々にテンポを上げながらかき鳴らした。伝統的なアラブ音楽の手法の中に、彼独自の斬新な感覚が光っていた。ムカールには、その光が細い絹糸となって、ほの暗いレストランの天上から舞い降り、きらきらと輝きながら、神秘な紋様を空間で織り上げていくような想いにとらわれた。
演奏が終わると、場内は喝采で湧き返った。アルブラートは落ち着いた調子でマイクに向かい、今の曲を説明した。
「この歌と曲をここでご紹介するのは今日が初めてです。この歌は彼女が8歳の頃に歌っていたものに、更に歌詞を付け加えたものです。アイシャは2ヶ月前に手術を受け、目が見えるようになってから、読み書きを練習し、1ヶ月かかって、作詞を完成させました」
彼はそう言うと、次にカーヌーンの独奏を始めた。ムカールはそれを聴いて、身を乗り出した。その曲は、昨年の3月、サイダの海の城の上で、アルブラートが地中海を見ながら彼に弾いて聴かせた曲だった。彼は、自分が16年間を過ごしたレバノンを懐かしく思い出した。
サイダには怖ろしいことや嫌なことが色々あった......でも楽しい思い出もあったんだ......アルラートがサイダに来てくれてからは―レバノンも楽しい思い出に変わったんだ―あの海の城に行った時はまさかエジプトに亡命するなんて思わなかったな......
6時に開演した演奏は、こうして30分経った。舞台に幕が一時的に下り、15分の休憩になった。ザキリスは食事をとりながら、こう言った。
「今の曲目は2曲とも、初めて聴くものでしたよ。本当にあの二人は素晴らしい才能の持ち主です。見事な芸術を完成させて―あの若さでね」
「若いからこそでしょう」
ムカールは、相手の言葉を短く引き取った。医師は微笑んだ。
「あなたもまだまだお若いじゃありませんか」
この言葉を聞いて、ムカールは、何か鋭い物が胸の奥深くに突き刺さったかのように心の底が激しく疼いた。自分は若くしてこの世を去らねばならない―この想いが頭をよぎったからだった。彼は食事の手を止めると、相手をじっと見つめた。ある決意が彼の心に生まれた。
ザキリスは、青年の真剣な表情に、いつもと違う何かを感じたが、穏やかな口調で話を続けた。
「数多いアラブ人の中でも、パレスチナ・アラブは傑出した才能を持つ人が多い。そのパレスチナ人と、また秀でた能力の持ち主であるユダヤ人とが争うとは悲劇です。しかし、そのユダヤ人にも優るのはアルメニア人です。『3人のユダヤ人が集まっても、一人のアルメニア人には叶わない』と言われているほどですからね」
ムカールは、暗に自分が誉められていることを察し、それを打ち消すような調子で応えた。
「......私はアルブラートに比べると、何の才能もない、つまらない人間です。先生のおっしゃることに従えば、アルブラートこそ真に優れた傑出した人物です。彼にはアルメニア人の血とジプシーの踊り子だった母親―それにベツレヘム音楽院を優等で卒業した父親バシール・アル・ハシムの血が流れているんですから」
「アルブラートは......あのバシール・アル・ハシムの息子なんですか。バシールの演奏は確か―20数年前に、よく私もアテネでラジオで聴きました。ベツレヘム出身の名演奏家でした。でも終戦直前にぱたりと噂を聞かなくなりましたね」
「アルブラートの両親は、まだ2歳ほどの彼を連れて死海近くのエイン・ゲディに逃れ、難民となったんです。父親は難民キャンプに移る前に、泥で造った掘っ立て小屋で病死したそうです―アルブラートはそれから、父親のウードとカーヌーンと共に生きてきたんです......彼はまさにあの音楽の才能で生き延びることができたんです」
ムカールの声は緊張感を帯び、表情は深刻さを増していた。ザキリスはこんなムカールを見るのは、昨年の夏、亡命の相談に彼がホテルの部屋を訪れてきたあの時以来だと思った。
「先生―今からお話することは、私だけが知っていることでした。私はこのことを他の誰にも話すまいと、この1年間固く口を閉ざしていました......でも、もう先生にこの話を託すしかないのです......先生はアイザック・アルバシェフという男を知っていらっしゃいますか」
「......アルバシェフ?よく知っていますよ。戦前、ポーランドで活躍したピアニストでしょう。私は彼のレコードを何枚か持っています。ですが戦時中にアウシュビッツに捕らえられたと聞きましたが―」
「アルブラートは15歳の夏に、ヨルダンのアルジュブラ難民キャンプで暮らしていたところを、イスラエル軍に占領され、ベト・シェアン捕虜収容所に送られました。そこで、彼を囚人として捉えていたのが、そのアルバシェフだった......しかし、アルブラートの話によると、その男は既に狂人と成り果てていたそうです......アルブラートはアルバシェフの前で、毎日ウードを弾くことを強要されました―看守にピストルを突きつけられながら―そうしないと即座に銃殺されるからです......」
ムカールは話しながら、声を低め、自分の身に起こったことを話すように、肩を震わせていた。
「......彼が16歳の誕生日を迎えた数日後、強制労働が始まりました―ほとんど食事らしいものも与えられず、痩せ細った彼の手首に看守は手錠をかけ、雪の中をトラックでナザレに連れて行きました......アルブラートはそこで穴を掘り、無数のパレスチナ人の遺体を投げ込んで埋めたそうです―収容所に戻ると、アルバシェフの狂った目で睨まれながら、ウードを弾くことを強制されました......そんな生活が続く中で、アルブラートの神経や感覚も麻痺していったんです―」
ザキリスは露ほども知らされなかったアルブラートの過去の話に、返す言葉が見つからなかった。
「―1月のある日、アルブラートは生き別れになっていた母親と収容所で再会しました。ですがその直後、アルバシェフの命令で、彼は母親を―猟銃で......猟銃で―射殺してしまったのです......その後、アラブ・シリア連盟の解放軍に救出されましたが、彼の心は罪の意識に囚われたままです―私がそれは罪ではないと、どんなに言っても......彼の魂はいつも苦悩の重い鎖に繋がれている―結局―私はもう彼を救うことができないんです、先生」

ムカールの告白に、ザキリスは言葉を失った。深い沈黙が果てしない闇のように二人を覆った。しばらくして、やっと医師は呻くように言葉を押し出した。
「......そんな残酷な目に遭って......よくあんな見事な演奏を......」
肩を落とし、額に片手を押し当て、目を閉じたままのザキリスを見つめながら、ムカールは尚も低い声で乞い願った。
「今......私がお話したことは、どうか他言なさらないで下さい―アルブラートにも、私が先生に彼の過去を打ち明けたことはおっしゃらないようにお願いします......でも―もし私がいなくなったら―どうか先生が彼を支えて下さいませんか―私の一生のお願いです」
「あなたが......いなくなったら......?それは―どういう意味です?」
ザキリスは心臓が凍りつくような冷気を覚えながら、怖ろしい秘密を聞くかのように声を震わせた。ムカールはちょっと口をつぐんだが、相手に真っ直ぐに視線を向けた。
「......私はいつまでもこの街にいないかも知れない―アデルとアルジェに行くかもしれない......それに人はいつ死ぬか分からない......そういう意味です」
二人の会話はそれきり途切れてしまった。アルブラートの演奏はやや遅れて、7時近くなって再び始まった。その日のコンサートは、8時近くに終わった。その間、ザキリスはムカールの告白や、謎めいた言葉が胸の奥深く沈潜し、悲痛な心情が続いていた。
あの話を聞いた後では、楽屋裏で二人を待っているアルブラートの顔をとてもまともに見れない気がした。だが冷静な態度を保ちながら、ムカールと共に、楽屋裏へと案内してもらうよう、接客係の者を呼んだ。
アルブラートはいつもより疲れた様子で、椅子に座っていたが、二人を見ると明るい笑顔を見せた。医師は、彼のそんな表情に、かえっていたたまれない、痛ましい気持ちが募った。ムカールはいつもの調子で彼に話しかけた。
「どうしたんだ、足を押さえて―膝が痛むのか」
「―前は立って1時間でも演奏して平気だったのに......30分が限度になってしまって......ずっと立っていると右膝が痛くてたまらないよ」
医師は、アルブラートが捕虜収容所でひどい栄養失調に罹ったことが影響しているのだろうと思った。
まだ成長期の10代の少年が飢餓状態に陥ると、いったんは体調を回復しても―膝を撃たれるなどひどい外傷を受けると、手術に耐えられる免疫力は通常のおよそ半分ほどだ......多分軟骨が徐々に擦り減っているんだろう......
彼は、何かを尋ねたい様子のアルブラートにこう言った。
「あなたの足はあの大怪我で―無理は禁物なんです。後で痛み止めの薬を出しますから、私の病院に来て下さい」
ムカールは持って来た荷物をアルブラートに渡しながら、微笑んだ。
「お前たちの演奏は本当に感動したよ―やっぱり本物の舞台は違うな。サイダのホテルでやっていた時より音がよく響いてさ。ほら、約束通りプレゼント」
アルブラートが包みを開けると、それはパレスチナの伝統的な結婚衣装一式だった。細かな金糸と銀糸の刺繍がふんだんに織り込まれた黒いベルベットのジャケットと、裾に幾何学模様のある長衣に彼は目を見張った。アイシャのためには、金貨が幾重にも連なった赤いブルク*と、白地に藍をほのかに染めたドレスが折り畳まれてあった。
「これは、スークの奥の目立たない一角で見つけたんだ。ヨルダンから戦前にカイロに移り住んだパレスチナ人の女性が店をやっているんだ。お前はベツレヘム出身だから、そう言ったらこの衣装を勧めてくれたんだ」
アルブラートは、幼い時、キャンプでよく見かけた婚礼の儀式を思い出し、懐かしさに胸がいっぱいになった。
「パレスチナ人の衣装は格別だな。俺は昔から立派な芸術品だと思っていたんだ―アルラート。お前は何があってもパレスチナ人だということを忘れるなよ。俺はお前に、パレスチナの伝統を誇りをもって受け継いでいって
ほしいんだ」
感謝の気持ちを目に浮かべながら、アルブラートは青年をじっと見上げた。彼は、赤いブルクをそっと手に取り、そばにいたアイシャの頭を飾った。アイシャは、9歳の頃、父からつけてもらった頭飾りの金貨の感触を額に感じ、思わず微笑んだが、次第に目に涙が浮かんできた。
ムカールはアイシャのその姿を見て、にっこりすると、本当によく似合って美しいと褒め称えた。彼は、アルブラートにも、ジャケットを着てくれと頼んだ。ムカールは花婿衣装を身につけたアルブラートを惚れ惚れと見つめ、安心したように静かに言った。
「これを見ておきたかったんだ―お前たちはこの衣装は人前で着ることができないだろう。でも6月の婚礼には、この衣装を着てほしいんだ」
* ブルク:パレスチナ地方の花嫁が身につける頭飾。刺繍を縫いこんだ赤いフェルトの下に数多くの金貨を糸で結びつける。デザインで女性の出身地が見分けられる。

ムカールの挙式から2日後のことだった。アデルは朝から雨が降る中を、まだ風邪の治らないアザゼルを抱いて、ザキリスの病院に出かけた。ムカールは彼女の留守に、不意にアルブラート宛に手紙を書いておこうと思い立った。
彼は机に向かうと、引き出しから便箋を取り出した。紙がずれないように、養父であったモハメダウィの時計を重石代わりに便箋の左上に乗せた。ムカールはその時計の中から、優しかったモハメダウィの声が聞こえてくる気がした。
モハメド......父さん......きっともうすぐ俺はモハメドのそばに行くよ......俺のために力を尽くしてくれたのに―やっぱり不様な最期になっちまうかも知れない......ごめんよ......ヨシュアともうまく会えたらいいな......
彼はインク壺に万年筆を浸すと、手紙を書き始めた。
親愛なる友アルブラート
この手紙を君が読むのは、きっと私が死んだ後でしょう。私は婚礼の日に君が書いた詩と、エリュアールの詩を、私と共に埋葬してほしいと頼みました。君の苦悩に満ちた過去は、私が生存していることで救われることもあったかもしれません。ですが私が死んだら、君の心はどうなるのでしょうか。私はそのことを考え、あのようなことを君に頼んだのです。
私がただの冷たい亡骸になっても、どうか悲しまないで下さい。あの2つの詩を埋葬してくれれば、私の魂は永遠に君のそばに留まることができます。死は単なる消滅ではありません。私はどこか遠くの世界に旅立つだけなのです。
私は君のような素晴らしい人と出逢うことができて、とても幸福でした。どうぞ私のことをいつも思い出して下さい。そうすれば、私はいつでも君に会いにやって来ることができます。私たちの心は永遠に友情の絆で結ばれていることを忘れないで下さい。
偉大なる才能に恵まれた君に神の大いなるご加護が与えられますように。さようなら。
1961年4月22日 ムハバイール・アル・モハメダウィ
ムカールは、手紙を書き終えると、安堵感を覚えたが、なぜ自分はこんなことを書かねばならないのかと自問自答した。すると何か落ち着かない、苦しい気持ちが湧き起こった。それは断崖の淵から必死に這い上がりたい恐怖に似ていた。彼はその恐怖を振り払うように、急いで手紙を折り畳むと、一番上の引き出しにしまいこんだ。
彼は娘のアザゼルのことを考えた。娘は生まれてまだ1ヶ月と10日だった。
可愛い小さなアザゼル......俺はあの子が1歳の誕生日を迎える時を見られるかな......あの娘は俺の命なんだ......
アザゼルはこのままカイロで大きくなって―俺のことは写真でしか分からないだろうな......愛しい愛しい宝物のアジー......
昼過ぎにアデルは帰って来た。ムカールは娘の小さな顔を覗きこむと、雨に少し濡れた柔らかな金髪をかき上げてやり、額に優しく接吻した。アデルは、赤ん坊をベッドに寝かせると、この子は風邪薬を嫌がらないで飲むから助かると言って、ヴェールを脱いだ。
「あなたは具合はどうなの?明日は仕事に来てくれってドクターが言ってたわ。昨日の外出がそんなに疲れるなんて......」
「たいしたことないんだ―でも寝坊するなんて、やっぱり何だか疲れたのかな......それよりちょっと話があるんだ、アデル」
アデルは微笑んで、テーブルにお茶を用意し、彼の右側に腰掛けた。ムカールは彼女の手を握り、肩を抱き寄せると、頬にそっと口づけした。
「アデル......俺はずっと孤児で、生まれた所も知らずにあの街で大きくなったんだ―そんな俺をお前は愛してくれたんだな......」
アデルはいつになく元気のない彼を心配そうに見やると、口ごもるように答えた。
「なぜ......そんなことを急に言うの......?人を愛するのに......相手が孤児だからって......そんなこと関係ないわ......私だって同じよ―父さんは出稼ぎだと言って―サイダの駅に私を置き去りにして、行方不明になって......母さんはマルセイユにメイドの仕事をしに行った後、病気で死んでしまったもの......私はサイダの駅であなたに出会って、本当に幸せよ......あなたのような素晴らしい人―夢の中でしか出会えない人と巡り逢って......」
ムカールは言い辛い様子で、ちょっと黙っていたが、やがて決心したように話し出した。
「俺も別に......親の顔なんぞ知らなくてもいいと思っていたんだ―でもこんな俺に......本当の親らしい人がいることが分かったんだ」
「......本当の親......?どうして分かったの―?」
「その人はドクターの古くからの知人なんだ......今のギリシャ王の兄との間にアレクサンドルという男の子を産んだ人なんだ......先のギリシャ王はもう14年前に亡くなって―今その人はアルメニア大公に嫁いでいる......ドクターから先月、その人の写真を見せてもらった......俺はその人によく似ているんだ......ドクターは、俺がそのアレクサンドルじゃないかと言っている......その人も、今カイロに滞在中で、俺に会いたがっているんだ」
アデルは彼の腕に抱かれたまま、黙って話を聞いていたが、急に顔をあげると、じっとムカールを見つめた。彼女は涙を浮かべると、静かに彼から体を離した。
「......そう......分かったわ......あなたのお父様はギリシャ王で―お母様はアルメニア大公妃なのね......あなたはきっとそんな生まれじゃないかと以前から思っていたわ......あなたは―あまりにも類い稀な気品と威厳を備えた人だもの......でも―私はただの平凡な女よ―あまりにも身分違いだわ......もう......もうだめね......あなたのお母様はきっと―あなたとあの子をアルメニアに連れて帰るでしょう......だから―」
アデルは泣き声になり、顔を覆ってしまった。ムカールは何と言ったらよいのか途方に暮れたが、再び彼女をぐっと抱き寄せた。
「そんな馬鹿な......!確固とした証拠は何もないんだ......!小さな子供じゃあるまいし―その人が俺をアルメニアに連れて帰りたいと言っても、黙って言う通りにするわけがないだろう......?俺はずっとお前とアザゼルとカイロに住むよ......アルジェに住んでもいいんだ......何も心配はいらない......!心配は何もないんだ......!」

アルブラートは膝の痛みが取れず、2日後再び病院で診察を受けた。医師はレントゲンを撮ると、やはり軟骨が潰れかかっていると言った。
「痛み止めの注射をしておきましょう。それに毎日、カルシウム製剤を服用して下さい。それと、立ち仕事は避けて、座って演奏することです......そうしないと、20歳を過ぎると、徐々に関節が固まってしまい、義足か杖を使わないと歩けなくなりますから」
治療が済むと、ザキリスは改めてアルブラートをしげしげと眺めた。
この子はすらりと長身だが、華奢で、どことなく闊達な活力が欠けている......今でもムカールの話が信じられない.....本当にこんな子がまだ16で母親を銃殺したのだろうか......
そう思っても、医師は穏やかな口調で話をしようと努めた。
「あなたは今日はお仕事はお休みでしょう。実は午後の2時に、私の家のリビングに、例のアルメニア大公妃が訪ねて来られます。ムカールとアデルと対面して頂くためです。あなたとアイシャも、同席してくれませんか」
「そんな......プライベートな場に僕がいていいんですか」
「あなたにも、オルガ様が、いかにムカールに似ているかを実際に確かめて頂きたいのです。それに、あなたが彼にとって大切な友人であることを、オルガ様に知って頂きたいと思いますので―」
アルブラートは、ムカールが自分の母マルカートによく似ていることから、青年に瓜二つの大公妃に実際に会えは、彼女が母にそっくりなのではないかと思った。彼は複雑な思いで病院を後にした。
モハメダウィの日記帳で、大公妃の若い頃の写真を見たが、これから会う彼女はもう40代になっているはずだった。もし大公妃が母にそっくりであったなら―そう思うと、期待感に胸が膨らむ一方、その女性を見ることに大きな畏怖を感じた。
2時10分前に、彼はアイシャと連れ立って、アパートから10分の所にあるザキリスの自宅に出かけた。医師の家は、病院のすぐ隣にある3階建ての立派な邸宅だった。玄関のベルを鳴らすと、夫人のザカートが迎え入れた。リビングに通されると、既にムカールと娘を抱いたアデルが緊張した面持ちで、ソファーに腰掛けていた。
ムカールはちらりとアルブラート達に目をやったが、溜息をつくと、絨毯に視線を落とした。彼は白い長袖の開襟シャツに、黒いズボンを身につけていた。
やがて時間通りに、オルガ大公妃が一人で部屋を訪ねてきた。彼女は豊かな黒髪を結い上げ、質素な黒いドレスに、真珠のネックレスといったいでたちだった。
その人を見た途端、アルブラートは我が目を疑った。
こんなに......こんなにムカールに瓜二つの人がいるだろうか......!顔立ちだけでなく―雰囲気や誇り高い気品まで―何もかもそっくりじゃないか......この二人が親子なのはもう疑いない......!
アルブラートは部屋の入り口付近に腰掛けていたが、おずおずと立ち上がり、大公妃に黙礼した。彼は、写真で見た時よりも、ずっと彼女がムカールの眼差しや、人を見る時の癖まで酷似していることに驚いた。大公妃は彼に気づくと、黙ってそちらに目をやった。
ザキリスがフランス語で、彼女にアルブラートを紹介した。
「奥様―こちらはアルブラート・アル・ハシムでございます。音楽家で、例の青年の親友です」
「あなたのことはドクターから伺っております。この街でも、私はラジオであなたの素晴らしい演奏を聴いておりました」
彼女の声は透き通るように美しく、発音は鮮明だった。その物腰や歩き方は洗練され、都会的でもあり、なお且つ典雅なものだった。アルブラートはジプシーとして、またパレスチナ・アラブとして生きた母は、ずっと野生的だったと感じた。だが大公妃の顔立ちは、やはり母マルカートを思わせた。
彼は、この女性を見ることが、急に辛くてたまらなくなった。
医師は、居間の中央に座るムカールを見ながら、彼女に話しかけた。
「奥様、あのソファーに座っている青年がムカールでございますよ。隣は妻のアデルと娘のアザゼルです」
大公妃は、ムカールにゆっくりと歩み寄った。ムカールはなぜか眩暈がしたが、静かに立ち上がり、彼女を無言で見つめた。彼は彼女の差し伸べた白い手を取ると、礼儀正しく跪き、軽く接吻した。彼はこの女性が自分の母であるという実感は何もなかった。ただ不思議なまでに自分に似ている彼女を黙って見上げていた。
●Back to the Top of Part 12
© Rakuten Group, Inc.