砂漠の果て(第19部「希求」)
「アザゼル・エレーナ・グロズヌイ」

アルブラートの脈は急に速くなり、顔は紙のように蒼ざめ、額は汗でじっとりと濡れた。そばにいたザキリスは、彼の右腕に安定剤を注射すると、細くしなやかな褐色の手首を優しく握った。
だが、アルブラートは医師の顔を見ることもできず、苦しげな短い呼吸をしばらく繰り返した後、相手の手を振り払った。ザキリスは、こうして度々起こる、アルブラートのトラウマの発作の激しさに心を痛めた。
うかつだったな......アレクサンドリアへの避難があまりにも急だったから、収集していたレコードもすべてそのまま持って来てしまった―アルバシェフのレコードなど、この子を養子とした時から、すぐに捨ててしまえば良かった......彼はようやく、ピアノへの嫌な思い出を忘れて、ピアノ曲を自ら聴きたいと望むほどになっていたのに......
医師は、アルブラートの潜在意識に喰い込んでいる罪の意識や、収容所での恐怖などから来るストレスが、彼の右膝の痛みをも悪化させているのだと考えた。
ザキリスは、彼をソファーに寝かせたまま、1時間ほど様子を見守っていた。薬の効いてきたアルブラートは、静かに目を閉じ、うとうとし始めた。医師は、つと立ち上がり、書棚の横のカレンダーの前に立った。
今日は―1月25日か......アイシャが亡くなってちょうど1ヶ月......こんな日に、アルブラートがあの男のレコードを発見して、発作に襲われるとは......何と皮肉な......
アルブラートは、31日に、ザキリスと共にパリに出発する予定だった。ザキリスは、それまでの間に、アルブラートの今後の体調について、本人と相談しておかなければならないと思った。
その日の夕食後、医師はアルブラートを自分の部屋に呼んだ。
「アルブラート。あと6日でパリに発つだろう。君はその後、ずっとヨーロッパで暮らすわけなんだ―君の学費や生活費は、私が毎月送金するし、アザゼルの養育費は、子爵夫人が払って下さるから心配いらないんだ」
アルブラートは、まだ悪夢から覚め切らない表情で、力なく医師を見つめ、小さくうなずいた。
「......でも―僕が音楽院を卒業して、また働くようになれば―生活費の分までご心配おかけするわけにいきません......貯金もありますし......」
「そうか―でも君は、小さな子供たちを2人も育てていかなければならないんだよ。その子たちが、せめて学校に行くようになるまでは―君も、なるべく家にいた方がいいだろう。それに......」
医師は、ここで言い淀み、難しい表情になった。
「......私が本当はずっとそばにいてやりたいんだが......
君は―君の心の問題でね......その―君には―過去の苦しい経験が心の奥に残り、時折―ひどい発作に襲われる......だから、私の代わりに、君のその問題を受け止め、治療に当たってくれる心理カウンセラーが必要だと思うんだ」
「......心理カウンセラー......?」
「そうだよ―君の過去を理解し、発作を最低限に抑える処方箋も出してくれる専門の医師がいなければ......」
アルブラートは、途端に不安になった。自分の怖ろしい過去を、再び誰かに打ち明けることなど、到底できない相談だった。彼は、心の奥底に、再び深く黒い、大きな穴が無理やりギリギリと音を立てて開いていくのを感じ、寒気に襲われた。
「......嫌です!そんな所に―行きたくありません......!」
いきなり叫ぶと、アルブラートは目をつぶり、耳を塞いだ。
「もう―もう発作なんて起きません......!僕は―あんなことを―もう誰にも......誰にも話したくありません!」
ザキリスは、大人しいアルブラートの、突然の激しい拒絶に驚いたが、しばらく無言で、考え込んでいた。
「......そうか......そうだろうな......いや、急にこんなことを切り出して―私が悪かった......それでは、こうしよう......万が一の時のために、私が君に安定剤を航空便で送るから―それでどうかね」
アルブラートは、医師の声が遠くから聞こえ、頭の中で誰かが叫んでいるような声に眩暈を覚えた。医師は、ソファーを立ち、彼の前に跪くと、その細い肩を両腕で掴んだ。アルブラートは、まだ目を閉じ、片手で顔を覆っていた。だが、養父の腕の温かみを感ずると、急に涙が溢れてきた。
「......僕を―僕をどうか......どうか助けて下さい......
先生......!」
その小さな女の子の肌は、透けるように白く、流れるように波打つ、濃いブラウンにところどころ金髪が混ざった髪が肩の辺りまで伸びていた。まだ2歳にもならないのに、物怖じもせず、初めて会う人を真っ向からじっと見つめていた。その瞳は黒く美しく、黒曜石のように微妙な輝きをはなっていた。
「この娘はアザゼル・エレーナ・グロズヌイと申します。私はカザリン・アエリア・グロズヌイでございます」
アルブラートがパリのデュラック氏の邸宅に着いて、まだ2日目だった。1963年2月2日のことだった。デュラックは、アルブラートからの手紙で、4年前にダマスカスで別れてからの出来事を既に知っていた。氏は、4年ぶりに会うかつての教え子の背が伸び、すっかり大人びて、更に、小さな息子を連れてきたことを喜んだ。ただ、4年前よりも瞳の表情の翳りが濃くなったことや、右足が不自由になったことを憂えた。
アルブラートは、アラブ世界から、いきなり別世界の異境に飛び込んだ斬新だが奇妙な印象がまだ拭えなかった。街並みも、行き交う人々も、アレクサンドリアやカイロにいた頃とは当然ながら、全く異なっていた。デュラックは、旅の疲れも取れていないのに申し訳ないと言いながら、彼に、アザゼルを連れた子爵夫人を引き合わせたのだった。
「私は、2日後には夫と息子と共に、北米に亡命しなければなりません。大公妃様から、お預かりしていた貴方のお写真を拝見し、お話を伺って、私は、貴方ならこの子をお任せできると思ったのです」
子爵夫人はまだ若く、25歳ほどに見えた。個性的な黒い瞳に、魅惑的な口元をした、小柄な女性だった。アルメニア語訛りがあるのか、癖のあるフランス語で、何かに怯えるように、小声で話した。アルブラートは、何とはなしに、この女性が少しアイシャに似ている、とふと感じた。だがアイシャは背がすらりとし、表情もいつも生き生きとした、活発な明るい性格だった。
ああ......駄目だな......若い女性を見ると―どうしてもアイシャを思い出してしまう―アイシャのことを忘れたい―忘れたくて、ヨーロッパまで―アレクサンドリアから何マイルも離れた所まで来たのに......
「お疲れのところを申し訳ございません。でも、私の家に、数日前、『闇の狼』から脅迫状らしきものが投げ込まれたのです」
アルブラートが受け取った、質の荒いごわついた厚紙には、赤いインクで、次のような内容が書かれてあった。どこかギリシャ文字の癖が残るフランス語だった。
―我々はギリシャ王家の血筋を引く者を匿っていた すべての貴族階級の者をも抹殺する それが我々の神聖なる使命である―
「......もう私たちはここにはいられません。北米に亡命しても、暗殺集団から狙われる恐れがあります......ですから、せめてこの娘だけでも貴方にと......それが大公妃様のご意思ですので―」
アルブラートは、オルガ・エレーナと対面し、直接言葉を交わした2年前の5月を思い出した。アザゼルの現在の名前は、祖母であるオルガの名からとったのだと思った。
「......そうですか......あの方は―今どうしておられるのでしょうか」
「それが―オルガ様は、今まで住んでおられた別荘から出るよう命ぜられ、バシリエフスキー大公の城内の個室に強制的に住まわせられておいでです......大公の侍従が、別荘にいたアザゼルを庭で見つけてしまい、大公は『アフリカ人との混血児など捨てて来い』とお怒りになって......オルガ様のご子息のお墓も跡形もなく取り壊されてしまいました」
アルブラートは、あまりのことに一瞬言葉を失った。
「墓碑を破壊するなど......それは―死者への冒涜ではありませんか―あの方のご子息は、私の最愛の友でした―それに、あの方は、誘拐されたご子息を20年間も捜し求めて―やっとカイロで再会できたのです......
その甲斐もなく、ご子息は亡くなられて、傷心のまま、アルメニアにお帰りになられたというのに......なぜ大公は、あの方にそんなひどい仕打ちをなさるのでしょうか」
「バシリエフスキーという方は、もともとはロシア人の地主で、土地成金ですから......その財力だけで、ソビエト政府から貴族の称号を賜ったに過ぎません。現在、アルメニアはソビエト連邦の一部ですし、大公はアルメニアの名門であるグルジャーノフ家の娘のオルガ様と結婚されることで、地位を確立してしまったのです......大公は、ご子息を捜し求める旅に始終出ておられるオルガ様を初めから愛しておられませんでした―ついにはオルガ様を憎むようになり、宮殿の一室に閉じ込めておしまいになったのです......」
あの天に届く教会の尖塔のようなオルガ・エレーナの崇高な美が、囚人のような生活に封じ込められたことや、彼女に瓜二つだったムカールの墓が破壊されたことは、アルブラートにとって、何か大理石の眩い宝玉が粉々に砕かれたような虚しさだった。
彼は、彼ら親子に、無意識に己の母のイメージを託していた。そのイメージが、心苦しくも、潜在的な心の支えでもあった。この虚無感が、その支柱が完全に瓦解したことによるものだとは、自分でも気がつかなかった。
「......あの方のおかげで、私は内密に別荘からパリに逃亡させて頂くことができました。最後の日の晩、あの方は『私のこれからの生活は、籠の中の鳥よりも窮屈なものになるのよ―本当に不幸な結婚を後悔しているわ』と嘆いておいででした―今、あの方に許された唯一の自由は、知人の方々にお手紙を書くこと、小さなお庭を散歩することだけです......それも常に監視人付きで」
子爵夫人は、このパリでアザゼルを養育してもらうのに、今の名前のままでは危険過ぎる、と言った。
「勝手なことを申し上げまして、真に申し訳ありませんが......
この娘のお父様にあたる、オルガ様のご子息が、モハメダウィと名乗っておられたことは、多分、暗殺集団の者には既に分かっているのではと思うのです―ですので、貴方のご養父にあたるザキリス様のお名前が一番良いと、オルガ様はおっしゃっておいででした」
この時になって、やっと初めて、アルブラートは、自らも名前を変えねばならないと決心がついた。
可哀想なアザゼル......こんな小さな頃から命を狙われて―お前のお祖母様も、お父様も、不幸な人生を歩んでしまった......せめて、お前だけでも幸せにならなくては......
彼は、必死になって、アザゼルの別の名を考えた。それは、自分の養女としての名前―ギリシャ系フランス人としての名前でなくてはならなかった。彼は、数分間、アザゼルを見つめながら考え込んだ。同時に、ムカールが愛情込めて愛娘につけた名を、自分が変えてしまうことにためらいを覚えた。だが躊躇している暇は無かった。
「......それでは―『アデール・アニエス・ザキリス』ではいかがでしょうか」
子爵夫人は、愛らしくて美しい名前だと感心し、彼に丁重にお礼を述べると、アザゼルを抱きしめて、涙ぐんだ。
「さようなら......私の小さな天使―あなたの名前は今日からアデールよ......きっとこの立派な方が、あなたのお父様の代わりになって、あなたを幸せにして下さるわ......」
彼女は、アザゼルの頬に最後のキスをすると、アルブラートに娘を抱かせた。アザゼル―アデールは、少し不安そうに子爵夫人を振り返った。夫人は、身分を隠すために、わざと質素なワンピースを着ており、余計な宝飾品などはいっさい身につけていなかった。彼女は、デュラックにもピアノ教授のお礼を言うと、外に待たせてあったタクシーに乗り込んだ。
アルブラートはアデールを抱いたまま、玄関先に立ち尽くし、タクシーの消え去った方向をしばらく眺めていた。アデールは、彼にぎゅっとしがみつき、やや恥ずかしそうに彼を見つめ、にっこり微笑んだ。そして、何か片言を喋ったが、それはアルメニア語らしく、彼には全く理解できなかった。
「さあ、もう中に入りなさい―足が痛むだろう。それに、アリが君を呼んでぐずっているよ」
デュラックが優しく促した。実際、アデールの重みでアルブラートは右膝がひどく痛み出した。幼女を氏に預けると、彼は足を引きずりながらリビングへと戻った。
リビングには、大きなグランドピアノが置かれてあった。そのそばで、メイドのマリーがアリをあやしていた。アリは、知らない人々の中にいるのを怖がり、泣きべそをかきながら、父親に抱かれたがっていた。アルブラートは、ソファに腰掛けると、アリを連れてきてもらい、小さな頭や背を愛しそうに撫ぜて、息子を安心させようとした。
「小さな子たちがいるのに、足が痛むというのは大変だな―手術をしても、そうなのかね」
「ええ......僕は―成長期にひどい栄養失調に罹ったので―それで、軟骨が磨り減り易いんだそうです―ザキリス先生から、カルシウムを頂いていましたが、それでも20歳を過ぎると、義足にするか、杖に頼るかになってしまうと―そう言われました」
「何とかならないものかな―ここの市立病院で、一度診てもらったらどうかな―ところで、明日あたりからピアノの練習に入ろうか。渡しておいた楽譜は一応暗譜したかね?」
アルブラートは、ショパンとバッハの曲を暗譜していたが、バッハの作品を弾くのは気が重かった。だが、先ほど、子爵夫人があのグランドピアノでショパンを弾いた時の感動がまだ深く残っていた。彼は、すぐにでもピアノに触れ、曲を演奏したかったが、まだ旅の疲れがとれておらず、荷物の整理もまだだった。
「子供たちの世話は、マリーがしてくれるから心配ない。彼女はよく気が利く人でね。まだ来て半年なんだが......しかし不思議だな―君は、アザゼルをアデールと改名しただろう。マリーの前に、1年間ほどメイドとして働いてくれた女性も、アデルという名前だった。偶然だね」
アルブラートは驚いた。彼がアザゼルを「アデール」と名付けたのは、行方不明になったアデルのことを考えてつけたからだった。
「その人は......どんな女性だったんですか」
「モロッコ出身のベルベル人でね。まだ若くて、22歳ほどだった。アルジェのレストランで働いていたそうだが、叔母がマルセイユにいるからと、フランスにやってきたとか......だがその叔母はもう亡くなっていて、それでパリに来たんだそうだ。以前、レバノンのホテルでメイドをしていたらしくてね。仕事も相当手馴れていたよ。アザゼルが子爵夫人と私の所に訪れる日は、随分とあの娘を可愛がっていたな......まるで本当の自分の子のようにね」
「......カイロに住んでいたとは―言っていませんでしたか」
「いや、それは聞いてないな―結局、去年の8月頃に辞めてしまった。『貴族の方のお世話は、やはり気を遣うし、私には向いていません』と言ってね」
アルブラートは、焦燥感に駆られて、思わず必死でデュラックに早口で問いかけていた。
「......彼女の行く先は、ご存知ありませんか」
「さあ―『またマルセイユに戻って、ホテルのメイドをするかも知れない』と言っていたことはあったがね......」
「......そのアデルという女性は―アザゼルの本当の母親です、先生......!2年前の6月にカイロから行方をくらましたアデルに違いありません......!アザゼルがアルメニア大公妃に引き取られることになって―しかも、アルメニア大公が、彼女を『野蛮なアフリカ人』と侮蔑したために......
アルメニアに行くことが恐ろしくなって、仕方なくアザゼルを僕たちの元に残したまま、どこかに行ってしまったんです......!」

デュラックはあまりの偶然に呆然としていた。アルブラートは、こんなことになるのだったら、なぜパリ行きを昨年の夏にでも決めなかったのだろうと悔やんだ。
それでも、アリが産まれたのは、昨年の7月であったし、彼はアイシャとずっとカイロで暮らすつもりだったのだ―それを思うと、実際、アデルに会いにパリに行くことなど考えもつかなかったのだと考え直した。
「......アデルは、先生のお宅で、偶然自分の産んだ娘と再会したんです―でも、アザゼルは、その時点では事実上、アルメニア大公妃の孫であり、グロズヌイ子爵夫人が養女としていた―だから、とても、自分が母親だと告白することは現実に叶わないと諦めたのでしょう......僕は、彼女の性質を良く知っているから、その気持ちは分かります......でも......」
「......でも、何だと言うんだね?まさか―彼女をフランス中探し回るとでも―そう考えているのかね?......君はコンセルヴァトワールに入学するために私の元に来た―入学試験のレッスンを投げ出し、右足を更に痛めてまで彼女を探す......そんなことは不可能だ」
アルブラートは、恩師にそう言われると、もはや返す言葉が見つからなかった。氏の言うとおり、自分のこの足で、広いフランスの南部、マルセイユにまで行って、彼女を探し回ることは不可能だった。それに、パリ音楽院への入学試験をふいにしてしまっては、デュラック氏に申し訳が立たなかった。
ああ......なぜこんな行き違いが起こるんだ......
アザゼルは、本当の親の元で大きくなるのが一番なんだ......ムカールだって、そう願っていたに違いないのに......!
アルブラートは悄然として、アリを抱きしめたまま、何か得策はないかと思い詰めた。アリは、父親の項垂れた様子に敏感に反応し、落ち着かなげに泣きべそをかき出した。彼は、慌てて幼い息子を愛撫すると、ぽつんと思いついたように、デュラック氏に申し出た。
「......あの......『尋ね人』として、新聞広告を出して見てはどうでしょうか―もちろん、僕の名は頭文字で―何か......何か反応があるかも知れません」
デュラックはすぐにそれに賛成した。翌日、彼らはパリのあらゆる新聞社に広告を電話で依頼した。広告内容は、次のように短いものだった―
「アデル 子供は僕が引き取ることになった 今パリ音楽院の近くにいる A.A.H」
「A.A.H」という様に、アルブラートの名の頭文字を明記することで、彼には、ギリシャの暗殺集団の的から逃れようとする意図があった。
だが、数ヶ月経っても、アデルからの連絡は何もなかった。彼は、徐々にアデルのことを諦めつつあった。また、同時に、音楽院入学へのレッスンに余念が無かったためでもあった。
その年の2月末、アルブラートは、デュラック氏の強い勧めで、アザゼルの名を改名した上は、彼自身とアリの名をもギリシャ系フランス人として変え無ければ、アザゼルが怪しまれる恐れがあると判断し、ついに改名に踏み切った。
彼は、まず自分の名をどうしようと考えた。デュラック氏に相談すると、「アルブラート」は「アルベール」に、セカンドネームは、ギリシャの美神である「アドニス」が良いと言われ、「アルベール・アドニス・ザキリス」とした。
また、「アリ」と言う名はいかにもアラブ的であるため、いろいろ考えた末、デュラック氏の亡き息子である「アンリ」に変えた。そこで、アリは、「アンリ・イドリース・ザキリス」で通すことになったのだった。
デュラックは、アルブラートの書簡から、彼がアラブを捨てるためにパリに来たことは十分承知しており、そのことには触れないよう配慮していたが、彼が名を変えたことにやや落ち着きを失っている様子を見抜き、考え込む彼に、ためらいがちに語りかけた。
「名前を変えたと言っても、表面的なものと思えばいい。身の安全のためにしたことだから......君の意思に反して悪いが、私は―君の本来の名を愛しているよ」
アルブラートは、アリと自分の名を改名したことを、カイロの医師に書簡で伝えたが、同時に、ザキリスと空港で別れた時を思い出しては、夜も眠れないほど悔やまれた。
ザキリス先生と今度会う時は、すべてフランス語で会話をする―それに俺は二度とカイロには行かない―先生にパリまで来てもらうんだ......それを頼んだのは俺なんだ―なんて俺は我儘なんだ......あんなに大恩のあるあの先生に対して......先生は、別れる時、涙ぐんで俺を強く強く抱きしめてくれたじゃないか......!俺のこれからの人生の基盤を造ってくれた人に―なんて俺は恩知らずな人間なんだ......!
また彼は、様々な思いが錯綜し、自分が何のためにパリにまで来たのかが混乱してしまう時があった。
ほら、やっぱりまだアラビア語でものを考えているじゃないか......あの青い男が言ったじゃないか―「ヨーロッパに行くのなら、すべてその国の言葉でものを考えろ」と―あのル・ラフの言うとおりだ......
きれいさっぱりと覚悟を決めて、別の自分にならないと、自分自身を見失う―
でも俺は、アラビア語を忘れきることがまだできない......
ザキリス先生との縁を切ることは絶対に許されない......
でも、先生と会って―「アルベール」としてフランス語で話を交わしたところで―アラブ社会のことを忘れ去るどころか、逆にレバノンやカイロでの出来事を思い出してしまう......!
おまけに―おまけに......アザゼルを「アデール」として俺の養女にすることを承諾したからには......どうしてもムカールのことを考えてしまう―彼とのアラブ社会での様々な思い出を......あんなにムカールにそっくりなアザゼルなんだ......彼が幻となって現れて、俺に言ったとおりだ......俺は―ムカールのことはやっぱり忘れることなんてできない......それに、気がついたらアデルの行方を考えたりしているんじゃないか......
アルブラートは、ムカールの十字架が取り壊された話を時折思い出しては、心がかき乱されそうになった。そんな時は、ニコシアの墓碑をムカールのために建てたことを慰めにしようとしたが、また逆に、アイシャとの思い出がまざまざと甦り、過去の幸福が心に食い込み、煩悶するのだった。
俺はパリに行く前日、ザキリス先生に言ったっけ......「アラブ社会を忘れるために―ムカールのことを忘れるために―アイシャを忘れるために―アザゼルに会いにいくために―パリに行く」と......
でも......パリに来たために、かえってアラブのことが懐かしく思えてならない―結局いつも―いつも俺はそうだな......俺の居場所は―どこにも見出せないんだ......
彼は、新たな自己が確立できぬまま、無理やり自分を「ギリシャ系フランス人」の枠にはめ込もうとしていた。パリに来て恩師のデュラック氏と再会し、フランス語での生活そのものは、ほんの数日で馴染んでしまった。ただ、アルブラートは自己を見失った状態で暮らすことに、焦燥感と息苦しさを感じていた。
それにもかかわらず、楽器に向かうと、アルブラートは別人のようだった。
弦楽器を長い間やっていたためか、ヴァイオリンをマスターするのに、1ヶ月もかからなかった。午前中にヴァイオリンを、午後はずっとピアノのレッスンを受けたが、ピアノに関しても、その上達の速さにデュラックは舌を巻いた。
最初はおぼつかなかったが、一度コツを呑み込んでしまうと、暗譜していた曲は、初心者とは思えないほどのテクニックで完璧に仕上げてしまった。デュラックは、アルブラートのウードとカーヌーンのレコードがカイロでヒットしたことを思い出し、満足そうに微笑んだ。
「まったく、君は語学だけでなく、音楽の才能にかけても抜きん出た才能の持ち主だね。君の弾いた曲は、初心者なら4ヶ月はかかるというのに、それを君は1ヶ月半でプロのレベルにまで到達したんだ。この調子なら、音楽院の入学は何の心配もない。君なら首席で合格できる」
アルブラートは、その後も新しい曲を、ヴァイオリンなら2日で、ピアノなら3日で次々とマスターしていった。彼はどんな曲でも、1時間もあれば暗譜してしまった。デュラックが最初に手本を演奏すると、1回聴いただけで、曲の流れすべてを覚えこんでしまい、確実なタッチで滑らかに演奏できた。
彼は、バッハの曲を弾くのが好きではなかったが、氏から、改めてバッハの作品について説明を受けると、その思想を忠実にピアノに再現しようと努めた。それは、「神の声と天上の至福の表現」だった。
また、他の作曲家の作品に関しても、彼は西洋音楽が、見事に人間的感情を歌い上げていると感嘆した。あるものは理性的であり、またあるものは叙情性を深く帯びていた。ただ、それらに共通しているのは、ちょうど整ったパリの街並みのように、整然とした統一性だった。
以前演奏していたウードやカーヌーンのことは、敢えて考えまいとしていたが、時折、ピアノやヴァイオリンを弾きながら、比較してしまうことがあった。
彼が幼い頃から慣れ親しんできたあれらの楽器による演奏には、西洋音楽のような合理性はなかった、と感じた。彼は、「無秩序による秩序の美と情操」を奏でていたのだ―そして、それらにより、やはり人間的な感情を表現してきたのだ―こう結論付けようとした。
あの楽器を通じて―今でははっきりと聞こえてくる―あれは、虐げられ、踏みにじられ、祖国を失った人間の哀しみと孤独と叫びだと......それを俺はずっと奏でていたんだと......
アルブラートは、レッスンを続けるうちに、好きな作曲家というものが徐々に出てきた。それは、ラヴェル、ドヴュッシー、ショパン、そしてチャイコフスキーだった。彼は、ピアノでもヴァイオリンでも、ラヴェルの曲を特に愛好した。ラヴェルの「ツィガーヌ*」を、ある日彼が弾き終わると、デュラックが惚れ惚れとしたように、演奏を褒め称えた。
「アルベール、君のその弾き方はもう完成度を極めている。何とも艶やかな繊細な音色に仕上がっているね―ハンガリーの民族音楽の特徴が巧く表現されているし、ロマニーの放浪の哀愁も見事に描かれている。その『ツィガーヌ』は、君の十八番の一つになってしまったようだな―君の音色を聴いていると、アルベルト・ローランの演奏を思い出すよ。ローランも、やはり『ツィガーヌ』が十八番だった」
* 「ツィガーヌ」(Tzigane):「ロマ(ロマニー、ジプシー)」の仏語訳。
「アルベルト・ローラン」といきなり言われ、アルブラートははっとした。
「先生は、アルベルト・ローランを知っていらっしゃるんですか」
「2度ほど直接会ったことがある―最初は、終戦の3年ほど前だった。あの人は、まだ42歳だったな......立派なストラディヴァリウスを所有していて、若い頃からヨーロッパ各地で演奏活動を行っていた有名なヴァイオリニストでね。私はその頃、まだ音楽院の学生だった。彼はコンセルヴァトワールの教授になるよう、音楽院から薦められたが、束縛されるのが嫌だと言って、断ってしまった。私には憧れの人だったから、たまたま音楽院にローランが来ている時、会って話をしたんだ......ローランは、娘に男の子が生まれたと言って喜んでいたね」
終戦の3年前......1942年......
俺が生まれた年じゃないか......お祖父さんは、赤ん坊の俺を抱いてくれたんだろうか......
「彼は、アルメニア人のジェノサイドを逃れたアダム・カーレィンという人と、ロマニーとの混血でね。父親のアダムも、ヴァイオリンを弾いていたらしい。まあ、ロマニーとして育った人だから、一ヶ所に定住するのは性に合わないと笑っていたよ。二度目に会ったのは、10年くらい前かな......
パリでコンサートを開いていたので、また私は会いに行ったんだ。私が『お孫さんはお元気ですか』と尋ねたら、悲しそうに『娘も孫も、もうどこにいるか分からない―死んでしまったに違いない』と言っていた―あの人の娘さんは、パレスチナ人の演奏家と結婚したから......それで悲観していた様子だった」
デュラックは、「パレスチナ」という言葉を思わず発したことに、気まずい様子で口をつぐんだ。アルブラートは、祖父が自分たち親子の行方を心配していたことを聞き、ますます祖父に会いに行きたいとの想いが募った。だが、デュラックには、自分がそのローランの孫であることは、まだ言い出しにくかった。
「......それで―そのローランという演奏家は、今どこにいるのでしょうか」
「......さあ―あの人はロマニーの血を受け継いでいるから、かなりその後ヨーロッパ各地を転々としていたらしいが......そうだ、昨年の暮れの新聞で、カタルーニャ地方で演奏活動をしていると報道されたことがあったよ。多分、バルセロナ辺りに今は住んでいるかも知れない。またパリで演奏会を開きに来ることもあるだろう。アルベール、君もその機会があれば、ローランに君の演奏を聴いてもらったらいい。きっと、あの人は自分の奏法や音色がそっくりな若手演奏家に遇えて、驚くんじゃないかな」
アルブラートは、夜の9時にはピアノのレッスンを終えると、昼間デュラックと話したアルベルト・ローランのことが自然と思い浮かび、ヴァイオリンを再び手にし、「ツィガーヌ」を弾こうとした。だが、居間でマリーに絵本を読んでもらっていたアザゼルが、アリの手を引いてそばにやって来たため、弾くのは止めた。
「アデール、アンリ......もう寝る時間だったね」
やっとつかまり立ちをし、つたい歩きを始めたアリは、父親に甘えてもたれかかってきた。昼間は、マリーと過ごすことの多いアリもアザゼルも、少しずつフランス語の片言を覚え、口にするようになっていた。もうすぐ生後9ヶ月のアリは、アラビア語を完全に忘れ、父親をおぼつかない愛らしい発音で、「モン・ペール、モン・ペール(パパ)」と呼んだ。
やっと2歳を過ぎたばかりのアザゼルも、アルメニア語ではなくフランス語でいくつかの言葉を話すようになった。彼女は、アルブラートのヴァイオリンを指差して、「弾いて、お父さま、弾いて」とねだった。彼は、仕方なくソファに腰掛け、「ツィガーヌ」を静かに奏で始めた。その情緒豊かな美しい音色は、子供たちには子守唄だった。いつの間にか、ソファで寝入ってしまった二人を、マリーが愛おしそうに抱き上げ、アルブラートに会釈して寝室に連れて行った。
彼は、「ツィガーヌ」を弾きながら、物思いにふけった。デュラックの「ロマニーの放浪の哀愁も見事に描かれている」との賞賛がふと頭をよぎった。彼は、途中で演奏を止めてしまった。
ツィガーヌ......ジプシーか......
お祖父さんも、母さんもジプシーだった......放浪の旅を続けて―俺のこの人生も、結局は永遠の放浪だ......母さんは、お祖父さんのヴァイオリンに合わせて、きっと踊っていたんだろうな......俺はアルベルト・ローランに会いたい―そして演奏を聴いてもらいたい......いや、そんなことよりも―アリ以外の唯一の俺の肉親である人に会いたいんだ......
アルブラートは、こう考えたが、祖父に会うということに、以前から抱いていた一種の恐怖がちらりと頭をもたげた。その恐怖は、アレクサンドリアに避難する直前、ムカールの歴史書で「アルベルト・ローランはアルブラートの祖父に違いない」とのムカールの走り書きを偶然、目にした時から燻っていたものだった。
ローランに会うのが、本当は俺は怖いんだ......
お祖父さんは、孫の俺が生きていたことを、喜ぶだろう―でも―きっと......「お前の母さんはどうしているんだ」と訊くに違いない......
そんなこと、分かりきったことじゃないか......!「私の娘は元気なのか」と......
そう尋ねられたら―「母さんは死にました」と言わなきゃいけない―お祖父さんは「なぜ死んだんだ」と訊いてくるさ......
とても本当のことなんか―言えっこない......!だからって―「病死した」と嘘をつくのも......ああ、苦しい―苦しくてたまらない......!
アルブラートは、母のあの事件、あの恐ろしい場面が、生々しく頭の中で再び甦るのを感じ、息苦しさと吐き気を覚えた。彼は手が震え、汗が瞬く間に全身から噴き出した。
彼は、数分間、ソファにうつ伏せになり、顔を両手で覆っていた。眩暈と頭痛を感じながらも、こんな姿をデュラックに見せたくないと思い、気分が悪いのを我慢しながら立ち上がった。彼は、居間を抜け、台所に行くと、コップに水を汲み、いつもズボンのポケットに入れてあった安定剤をやっとの思いで飲んだ。
デュラック先生は「あのこと」を知らないんだから......先生には絶対、「あのこと」を知られたくない......!
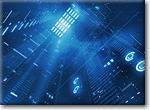
いつかのように、薬を服用しても、再び喉がつかえるような胸苦しさに襲われ、アルブラートはふらつきながら、ソファに座り込むと、喉元を押さえながら横になった。
この薬は......眠くなったかと思うと......
幻覚のような悪夢や奇妙な夢を見るんだ......副作用なんだ―副作用なんだから仕方がない......こんな恐ろしい発作を鎮めるためには......
彼は、しばらくすると、うとうととまどろみ始めたが、その中で、誰かが自分の額の汗を拭い、手首の脈をとっているのを感じていた。アルブラートは、夢の中で、床に仰向けになっていた。その上に、黒いグランドピアノが、いつもの倍以上の大きさになってのしかかるように覆いかぶさり、彼の両手を押さえつけていた。
ピアノの重みはどんどん増し、アルブラートは手首や指が潰れるのではないかと気を揉んだ。
指が痛い......痛い!骨が折れてしまう......!このピアノの下から抜け出せない―どうしよう......コンセルヴァトワールの入学試験はあと4ヶ月後なのに......?
「せっかくパリにまで来たが、やはり音楽院など高嶺の花なんだよ」
彼は、誰かがこう言うのをそばで聞いた。その人物は、ピアノの下にいとも簡単にもぐりこんで来ると、彼を軽蔑するように鼻先で笑った。
「パリ音楽院は、ひどい偏見に満ちた世界だ―白人でないと入れない。白人であっても、フランス人以外は入れない―ましてやお前はアラブ人ではないかね。諦めて、カイロに帰るんだ」
「俺はもうアラブじゃない―ギリシャ系フランス人だ。ピアノだって十分に弾きこなせる―フランス語だって不自由はしない―そう言うお前は誰なんだ」
「私か......私は、アルベルト・ローランだ。お前の祖父だ。お前はお前の母親を殺しただろう。そんな人間に、音楽院入学が許されると思っているのか?お前は私に会いたいんだろうが、私は殺人を犯した者を孫とは認めない」
その祖父の顔は、薄暗いピアノの下では、はっきりと見えなかった。アルブラートはせめて指の痛みから解放されたいともがき苦しんだ。その時、彼は悪夢から眼が覚めた。
気がつくと、彼の傍らにはメイドのマリーが心配そうに跪き、様子を伺っていた。アルブラートは、なぜマリーがここにいるのかよく分からず、しばらく無言で、彼女を見つめていた。彼は、いつのまにか毛布にくるまっており、手を力いっぱい握り締めていた。指の痛みはこのせいだったのだ、と彼はようやく気がついた。
「大丈夫ですか......アルベール様」
マリーは、透き通った碧色の目で、彼に優しく問いかけた。
「4月でも、こんな広間に横になっておられると、寒いですから......
ご気分がよろしければ、寝室にお戻りになっては......」
「......僕は......いつからここに寝ていたんですか......」
「9時過ぎに、坊ちゃまとお嬢様を私が寝室に連れて行ってさしあげて―2階から、アルベール様のヴァイオリンが聞こえていました......
その音が途切れて......私はきっとお勉強をなさっておられるのだと思ってました......10時少し前に、台所に用事がありましたから、こちらに降りて来ましたら、貴方様がソファーに横になっておられて......とても汗をかかれて、苦しそうでしたから、私びっくりして......」
「手を握っていてくれたのは......あなただったんですか」
「......ええ―脈が速くて......何かご病気かしらと心配して......」
「......あの......先生は......?」
「あら、先生でしたら、今日の夕食後に、夜行でブリュッセルにお出かけになられたじゃありませんか。あちらで3日間、演奏会があるって―」
ああ―そうだった......こんな発作の時に先生がいなくて助かった......だがマリーは―何か感づいたかな......何かうわ言でも聞いたんじゃないのか......?
「......僕は......寝ている間、何か言ってませんでしたか......」
「いいえ、特に......ただ、『痛い』とは2,3度おっしゃってました」
「ああ......何か怖い夢を見たので―心配をかけてすみません......きっと、練習のし過ぎで疲れたんだと思います―それに―あの......音楽院入学がうまく行くか、いつも心配しているので......そのプレッシャーか何かで―頭痛がして......」
「まあ、アルベール様のように上達の早い方は珍しいって、いつも先生はおっしゃってるじゃありませんか―私は音楽なんて演奏できませんけれど、聴くのは大好きですし......今まで来られた生徒さんなどより、遥かに優れた素晴らしい演奏をなさるじゃありませんか......!きっと成功なさいますよ」
「......それならいいんですが―あの―僕が今夜、ソファーで倒れていたことは......先生には言わないでくれますか......先生に心配をかけたくないので......」
マリーは、何も言わないと約束し、台所からワインを持って来てくれた。悪夢の後、ワインを飲むと、アルブラートはまるでサイダのホテルにいるような気分になった。よくムカールが、「気分が落ち着くから飲め」とワインを勧めてくれたことを思い出した。
ムカール......ムカールに夢の中でもいいからもう一度、会いたい......アルベルト・ローランに「人殺し」と呼ばれる夢を見るくらいなら......ムカールに会って―彼を慰めてやりたい―墓地も荒らされて、母親は宮殿に閉じ込められて......ムカールの魂はもうアルメニアでは安らかに眠れないだろう―レバノンやカイロの思い出が甦ってもいいんだ―ピアノに押し潰される夢なんかより、彼の夢を見たい......
アルブラートは2階の寝室に入ると、窓際の椅子に座り、パリの街の夜景を眺めた。家の斜め前に、近代的なデザインのコンセルヴァトワールがライトアップされているのが見えた。遥か遠くのエッフェル塔が美しく輝いていた。彼は、パリに来て2ヶ月、ほとんど外出せず、ヴァイオリンとピアノのレッスンを続けていた。たまにはパリ市内を見物してはどうかとデュラックから薦められたが、なかなかその気になれなかった。
なぜかな......先生の自家用車でいつでも連れて行ってもらえるのに―何だかこの街は馴染めない......
あまりに整いすぎていて......それに―自分が好奇心の目で人から見られそうで―でも自意識過剰なんだな......パリには世界各地からいろんな人が集まっている―当然......アラブ人だって街を歩いているんだろうに......
ふとベッドサイドの時計を見ると、もう午前1時をとっくに過ぎていた。彼は、慌ててベッドにもぐりこんだが、なかなか寝つかれなかった。
さっきの夢で、「コンセルヴァトワールは白人しか認めない」とお祖父さんは言っていた......本当なんだろうか―
先ほどの悪夢が頭から離れなかった。そんな時、部屋の明かりが一旦灯ったかと思うと消え、それが2,3回続いた後、薄暗がりの部屋のドア付近がぼうと明るくなり、ムカールの姿が現れた。
アルブラートは唾を飲み込み、その姿をじっと見守った。ムカールは生前と変わらぬ白い開襟シャツに、グレーのズボンを見につけていた。親友の幻は、やがて彼のベッドの傍らに近寄り、寝ている彼を見下ろした。
「アルラート......俺が怖いか」
アルブラートは首を振り、ベッドから体を起こした。
「お前はさっき、俺に会いたいと願っていただろう。俺が生前の手紙に書いたとおり、お前が俺を想ってくれれば、いつでも俺はお前のそばに来ることができるんだ」
アルブラートは彼に触れようとしたが、ムカールの手は氷のように冷たく、体もほぼ半分以上透き通って見えた。彼は一瞬ぞくっとし、手を離したが、愛する友人の幻に語りかけたくてたまらなくなった。
「ムカール......俺は、アルメニア大公のムカールの葬儀や墓地の破壊の話を聞いて......もうムカールはアルメニアに静かに眠っていられないと思ったんだ......」
アルブラートの呟くような沈んだ口調に、ムカールは微笑むと、アザゼルにそっくりな煌く黒い瞳を若い友人に向けた。
「あのアルメニア大公って奴は、貴族の名どころか人間の名に値しない卑劣漢だ。身分が高いのをいいことに、その権限で、俺の棺を掘り返し、俺の遺体を棺ごと焼いてしまった。でも誰もあの男を咎めないし、このことは国内外には秘密にされてある。
はっきり言って、あの男は墓荒らしを犯した犯罪者だ。だが誰もあいつを裁けない―だから、俺は以前、お前に言っただろう。身分の高さなんて、人間には邪魔で窮屈で、場合によっては犯罪を隠す手段にも成り得る―母も、宮殿に閉じ込められて、毎日泣き暮らしている......そんな所に俺はもう居たくない。だから、お前やアザゼルのいるパリに来たんだ」
「ムカール......死んだら―本当に苦痛は何もないのか......
苦しむことも、悩むこともないのか」
「そうだ。ただ浮遊している魂があるだけで、好き勝手にどこにでも行ける。強いて言えば、まだ生きているお前やアザゼル、それにアリへの愛情だけが俺の魂の核を成しているんだ―お前が演奏している曲はいつも聴いているし、アジーやアリの成長を見ることができるのが嬉しいんだ。
アザゼルは、昔、俺をさらった連中に命を狙われているが、お前がザキリス先生の養子になり、名を変えたことまではまだ気づかれていない。お前があの娘の養父となって、育てていることで、何とか敵の目をごまかせるだろう―それに、何よりも、お前がアジーを娘としてくれたことに、俺は感謝しているんだ」
「俺も―ムカールのそばにいつも居ることができたらと思う......
こうやってパリに来たにせよ、やはり悪夢に悩まされてしまうんだ......
祖父のローランが夢の中で、俺のことを殺人犯と罵るんだ―それに、パリ音楽院は白人しか入れないなどと......」
「それはお前の見た夢であって、現実じゃない。お前の漠然とした不安が、ローランの姿を借りて、悪夢となって現れただけだ―アルラート......お前は本当にアルベルト・ローランの孫なんだ。ローランにお前はいつかは会いに行くだろう。その時に、ローランはお前を罵ったりはしない。むしろ、お前が何も言わずとも、お前の身に何が起こったのか気遣って、何も詮索したりしない......
それに、コンセルヴァトワールは確かに偏見に偏っていることで昔から有名なんだ―でも、お前の演奏は、どんな仏人にも白人にも負けない。最初は人種的偏見で、教授たちはお前の入学を拒むかも知れない―
でも今お前が師事している先生が、お前の腕を既に一流だと認めている。きっと、あの先生がお前の味方になってくれる―そして、お前は音楽院での3年間、首席で通すことができる。何も心配するな。また不安が頭をもたげたら、俺を呼ぶんだ―あまり深く考えずに、今は西洋音楽をマスターすることだけを考えるんだ......」
ムカールはここまで言うと、ふっと姿を消した。部屋は元のように真っ暗闇になった。だがアルブラートは、ムカールの幻影を少しも怖ろしいとは思わなかった。こうして心の中で強く念ずれば、最愛の友人に会えるという事実が嬉しかった。
明日はレッスンを少し休もうとも思ったが、楽器の演奏は1日でも休むと、すぐに手がなまってしまうことは、長年楽器に触れ、演奏を続けて来た彼自身がよく知っていた。入学試験に最低必要とされる曲目はラヴェル、リスト、チャイコフスキー、そしてショパンだった。
先生がブリュッセルに行っている間だけでも、リストとチャイコフスキーをもっと完璧に仕上げないと......
先生は褒めてくれるけれども、本当はまだ―曲に深みがない......
感情がこもっていない箇所がいくつもある―もっと研究しないと......
でもムカールは、俺が音楽院の3年間はずっと首席だと言ってたな......
アルブラートは、ムカールの幻と再会できたことを懐かしく、また嬉しく思っている自分に矛盾を感じてもいた。パリに来て、アラブ社会のことを思い出すまいと思っているのに、なぜこんなにムカールのことをいつまでも恋しく思うのだろうと訝った。そして、あることに急に気がついた。
そう言えば......さっき、ムカールは俺にフランス語で話しかけていた......俺がアラビア語を使うまいとしているからか......レバノンで、彼は街でもホテルでもフランス語を使っていた―でも、俺とはフランス語で話をしたことはなかった―それでも、俺はさっき、自然と彼とフランス語で話をしているのに違和感がなかったっけ......
また、彼は、寝室に戻る前、マリーが「うわ言で『痛い』と何度かおっしゃっていた」と言ったことを思い出した。
俺は今はやっぱりアラビア語であれこれ考えているが......マリーの言うことが本当なら、フランス語で寝言を言うようになったということなのか―
アルブラートは、青い男ル・ラフの言ったように、「その国の言葉で生活をする」ことが、自然に身についてきたのだと思い、やや安堵した。
だが、こうして異国で暮らすことで、違う自分になっていくにつれ、何かを失いつつある空虚さに踏みにじられる己をも見出した。それは、この世に生れ落ちた時から潜在的に己の魂の母体となっているアラブというものが失われることに大きな危惧と怖れを抱き、震え慄く自分の姿だった。
●Back to the Top of Part 19
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- これまでに読んだ漫画コミック
- 陽だまりの月 2巻 読了
- (2024-11-25 21:41:16)
-
-
-

- マンガ・イラストかきさん
- ちょっと気味の悪い話をしますが最近…
- (2024-11-25 12:21:24)
-
-
-

- 読書
- Wedge 2024年10月号 読了
- (2024-11-27 22:33:15)
-
© Rakuten Group, Inc.



