砂漠の果て(第21部「嫉妬」)

アルブラートはいつの間にか自分を取り囲んでいる街の人々に、多少戸惑っていた。今自分が弾いたのは、いつも通りの出来具合であって、大したものではない、と感じていた。だが、聴衆は、爽やかな陽射しの、広々とした眺めの良い庭園で、思いがけず素晴らしい演奏を聴く事ができたことに歓喜の声を上げざるを得なかった。
熱狂的な拍手喝采の中で、困惑している彼に、ある若者が近寄って握手を求めた。人見知りをするアルブラートが躊躇っていると、その青年はぜひと言って、彼の手を握り締めた。そして、そばにいるデュラックに一礼し、話しかけた。
「ロベール教授、こんな所で偶然にお会いできて光栄です。私は何となく気晴らしに、この公園に散歩に来たんですが、先生はこんな見事な宝石箱をお持ちになられたんですね」
「そう、宝石箱―まさに君の言うとおりだ、ジャン。このアルベールを、君ならきっとそう言うに違いないと思っていた。今の『タイス』は最高の美しさだっただろう」
デュラックは、その青年をアルブラートに紹介した。
「アルベール、彼はジャン・ニコラと言って、音楽院の3年生でね。定期公演のコンサートマスターだ。ヴァイオリン科の先輩だよ。ジャン、アルベールは今秋、入学試験を受けるのに、必修曲目のリハーサルを管弦楽団とする必要があるが、彼のスケジュールはまだ組めるかね」
「ええ。もう45名のリハーサルをしました。1日に5名までですが、そのうち30名は第一次予選で不合格です。現在、残っているのは15名です。今年の入学志願者は150名で、競争率は5倍ですね。4月中に、予備選考の演奏で、105人が落ちました。後、今月中旬から7月にかけて、一人3回までなら、第一次予選のリハーサルが可能です。ヴァイオリン科の定員は、30名ですから―」
ジャンは、そう言いながら、アルブラートを微笑んで見つめた。「でも先生、彼なら第一次予選だけで合格ですね。今の『タイス』だけで、そう確信できました」
アルブラートは、この色白の青年が、自分に何の偏見もなく、自分の才能を褒め称えてくれるのが嬉しかった。デュラックの言ったとおり、音楽院にはギュスターヴのような差別観に凝り固まった人間ばかりではないのだと、すっかり安心した。
彼は、ジャンや周囲の聴衆のアンコールに応えて、今度は『ツィガーヌ』を演奏した。本来、オーケストラの伴奏が入る部分を、彼は独自に編曲し、ヴァイオリンの独奏曲として弾いた。その落ち着いた洗練された音色は、まだレッスンを始めて3ヶ月半の者とは思えなかった。彼は、一点の狂いもなく、非常に難解とされる部分を鮮やかに再現し、緩急の微妙な旋律を、艶やかな伸びやかな音色で弾きこなした。
その演奏にこめられた深い哀愁と、生き生きとした感情に、ジャンは驚嘆の表情を隠せなかった。それは、誰もがこれまでに聴いたことのない、極上の音色だった。ジャンは、演奏を終えたアルブラートに、例え億万長者になったとしても、この演奏を聴かない限りは幸福とは言えないだろうと絶賛した。
周囲は以前にも増して、大勢の群集でいっぱいになり、皆夢中で「ブラヴォ」と叫び、拍手が鳴り止まなかった。
だが、急に集まった大勢の人々の騒ぎに、アザゼルとアリはおびえ、マリーに抱きついて泣き出した。アルブラートは周囲の人々に目礼すると、困惑したように、子供たちをなだめようとした。
ジャンは、まだ若いこの演奏家の卵に、小さな可愛らしい子供が2人もいることに目を見張ったが、微笑ましげに子供たちの姿を眺め、管弦楽団とのリハーサルの予定をまた改めてお知らせすることを、優しい口調でアルブラートに告げた。それからジャンは、連れの青年を振り返り、声をかけた。
「フランソワ。やっぱりロベール先生が白羽の矢を当てただけあって、今のこの受験生の演奏は見事だったろう。このアルベールはきっとピアノも優れた腕前だろうよ。君もいつまでも首席の座にいられるとは限らないね、よっぽど精進しないと」
「ああ、フランソワ、君も来ていたのか。アルベール、彼はフランソワ・ギレと言って、ピアノ科の首席奏者だ。今度、2年生になるんだ。彼の演奏は実に見事でね―去年のクリスマス・コンサートも素晴らしかった」
フランソワは、憮然とした態度で、黙って肩をそびやかすと、アルブラートをちらりと見やっただけで、その場を去ろうとした。アルブラートは、その青年の表情に、憎悪と嫉妬の入り混じったものを見出し、再び急に音楽院受験が不安になった。
ジャンは、フランソワを促すと、デュラックに一礼し、見物客の輪から離れて行った。アルブラートが遠ざかって行く二人の様子を見ていると、二人は何か言い争っているように見えた。
「君は何か、あの風変わりな受験生の肩を持つようだが、僕は腑に落ちないね。ヴァイオリンがうまいからって、ピアノまでうまいとは限らないだろう。
親友の君が、あんな異人種を担ぎ上げて、僕をこき下ろすとは思わなかったよ」
「別に、君を貶したわけじゃない。毎年、優れた人材の学生が入学するだろう。だから、君も常に腕を磨かないと、トップの座も保てないと忠告しただけだ。それに、あの学生が異人種だなんて―どんな根拠があって、君はそんなことを言うんだ」
「あの褐色の肌の煤けた色や、顔立ちを見てみろよ。あんなのがフランス人であるわけがない。どうせギリシャあたりの混血さ。最悪の場合は、アラブ人そのものかも知れない。薄汚いアラブ人が、音楽を解する頭があるとは傑作だね」
ジャンは友人の思いがけない偏見に満ちた言葉に驚愕した。
「なぜアラブ人が『最悪の場合』とか『薄汚い』などと言うんだ―君は白人史上主義だったのか。まるでアメリカのクー・クルックス・クラン* か―それともナチスのような思想じゃないか。僕は、お生憎とユダヤ人でね、君の言うような純潔な白人とは違うんだ。それでも、君は僕を友人と見なすことができるのか―僕の両親は、僕が7歳の時に、アウシュビッツで殺された―
僕は、ソ連軍に救出されて、しばらくモスクワで看護を受けた後、米国に亡命していたカンヌの叔母の元に引き取られたんだ......それに、歴史を調べてみると、ユダヤ人もアラブ人も、元は同じ人種だ。たまたま、ユダヤ人は世界各地に離散したために、白人との混血が進んで、外見上は白人と変わらないだけだ。そんな人は世界中に大勢いる。それでも、君はアラブ人を軽蔑するのか。アラブ人を軽蔑することは、僕をも軽蔑することになる―そうなると、君とはもう、友人ではいられない。それでもいいのか」
フランソワは、しばらく黙っていたが、フンと鼻を鳴らし、彼を見下したような眼差しになった。
「僕がアラブ人を嫌うのは、特にパレスチナ人さ。あの連中は、今ではイスラエルに敵対しようと、微力ながらも馬鹿げた軍事力でもって、世界中をテロで脅かしつつあるじゃないか。君がユダヤ人であるのは一向に構わない。むしろ、君こそ、パレスチナ・アラブを敵視すべきじゃないか。
君の同胞が、イスラエルで大勢殺害されているんだ。もし、あのアルベールとかいう学生が、パレスチナ人だったら―それでも、君は、彼をかばって、その実力を真に認めるつもりかい。君の博愛主義には呆れるね。多分、デュラック教授の影響なんだろうが」
アルブラートは、先程のフランソワという青年の態度を気にしながらも、公園ではもう演奏せずに、子供たちとマリーの軽食を取ることにした。集まった人々からは、毎週、この公園に来て、何か演奏をしてくれと熱烈に頼まれていた。彼は、それを快く引き受けたが、何か心に引っ掛かりができてしまったように、落ち着かなかった。
彼は、聴衆が散り散りになった後、落ち着きを取り戻した子供たちを見て、何か二人に楽器を与えたら喜ぶのではないかと考えた。アザゼルは、ピアノが好きであることから、幼児向けのピアノを買ってやっては、とデュラックに申し出た。
「それはいいことだね。幼い子が、興味を持っていることを、思う存分やらせることで、思いがけない才能が芽生え、大輪の花を咲かせることもあるんだからね」
彼らは、公園でしばらく休息した後、車で楽器店に立ち寄り、アザゼルのために、小さなベビーピアノを買い求めた。アルブラートは、幼い娘に、これは「アデール」のピアノだ、と言い聞かせた。彼女は、嬉しがって彼に抱きつき、早く弾きたがる様子を見せた。
アルブラートは、ふと、彼女のそんな様子を見て、もしかしたら、ムカールの魂がこの幼い娘に宿り、ピアノを弾きたがっているのではないか、と考えた。
家に戻ると、彼は早速、梱包を解き、アザゼルにピアノを弾けるように準備してやった。彼女は歓喜し、夢中で小さな手で鍵盤をでたらめに叩いて、満足していた。アルブラートは、アザゼルの笑顔を見ていると、フランソワの憤慨に満ちた表情を忘れることができた。彼は、アザゼルに、右手で、基本の音階を美しく弾けるように、手ほどきしてやった。すると、彼女はすぐに覚え、楽しそうに何回も繰り返し弾き始めた。
7月には、アリの満1歳の誕生日が待っていた。アルブラートは、息子のために、やはりベビーピアノを買ってやろうかと考えた。だが、アリは、幼い姉の弾くピアノには興味を示そうとしなかった。もうすぐ11カ月のアリは、父親がソファーに置いたままのヴァイオリンをじっと見つめていた。
やがて、アリは、ソファーによじ登り、そのヴァイオリンを手に取ろうとした。アルブラートは不思議に思い、幼い息子のそばに近寄り、その様子を見守った。アリは、ヴァイオリンの弦をしばらく眺めた後、白く人形のように愛らしい指で、弦をポロンポロンと弾いた。
その時、アルブラートは、この子がまだ5ヶ月になった頃、自分がウードやカーヌーンを弾いて聴かせてやっていたこと、また、今年の1月、アレクサンドリアに避難していた頃、アリがそれらの弦楽器を弾こうとして泣いたことを急に思い出した。
彼は、自分が幼い時から、やはり父親の持っていた弦楽器に興味を示し、いつしかそれらを弾いていたことに想いを馳せた。アリを思わず抱きしめながら、彼は目をつぶった。
アリ......お前は、本当に父さんと同じなんだ......あのウードとカーヌーンが忘れられないんだね......でも父さんはお前にもうウードを弾いてやれない......ごめんよ......代わりに、ヴァイオリンを教えてやるから......
* 「クー・クルックス・クラン」(Ku Klux Klan):アメリカの白人至上主義団体。KKKと略される。
部屋に戻り、しばらくすると、マリーが彼宛の書簡を渡しに来た。それはカイロからの手紙だった。アルブラートは、義父の折り目正しい、細かな文字のフランス語の文章をじっと眺めた。ザキリスとは、パリに来て以来、一度も再会していなかった。彼は、あの医師の哲学者のような理知的な面立ちを心に浮かべ、深い敬愛の情が湧いて来るのを感じた。
―懐かしいアルベール
先日はアンリとアデールの可愛い写真を送ってくれてありがとう。君はもうパリでの生活に慣れましたか。一度、入学試験の前に君に会いにそちらに行きたいところですが、ザカートのお産も7月の中旬で、常に注意を要する状態ですし、目が離せません。胎児は元気ですが、早産の恐れもあります。
私たちは、二人とも、君がいなくなって、しばらくは寂しくて仕方ありませんでした。しかし、今では産まれて来る子供たちのことを楽しみにして暮らしています。ザカートは、「アンドリュー」と「ニコラス」と先に男の子の名前を決めています。彼女は、君に再会する日のために、フランス語を熱心に勉強しています。
君の8月20日と21日の入学試験のコンサートには、私一人でもぜひ聴きに行きたいと考えています。2ヶ月前から、助手の医師が二人勤務するようになりましたので、私も従来の忙しさから少し抜け出せそうです。
それでは体に気をつけて。デュラック教授に宜しくお伝え下さい。
1963年5月18日 ウィリアム・A・ザキリス
アルブラートは、ザキリスに会える嬉しさから、入学試験前の妙な不安が薄らぐ気がした。彼は、手紙に書かれた「ニコラス」という名から、今日出会ったばかりのジャン・ニコラを思い出した。あの青年がまた公園に来てくれるのなら、来週の日曜日は再び楽しく過ごせるかも知れないと思った。
きっと、あのフランソワとかいう男はもう来ないだろう......あの嫌な表情―俺を心底嫌悪していた......
でも音楽院のピアノ科に入学したら、嫌でも彼と顔を合わせるのか......
翌日曜日、アルブラートは楽器を携えて、先週と同じ場所に出かけた。そこには100人ほどの人々がもう集まっていた。群衆は彼の姿が目に入るやいなや、熱狂的な拍手で若い演奏家を迎え入れた。子供たちは、もうこの場の雰囲気に慣れてしまった。アザゼルは、アリの小さな両手を後ろから握ると、パチパチと拍手させた。
アルブラートは、前回と同じように『タイスの瞑想曲』を弾いた後、次に『ロンド・カプリチオーソ』を演奏した。彼の演奏には不思議なまでに深い哀しみと、洗練された繊細な感情、そして心の奥に染み通る大きな愛情が込められていた。それらが、泉のように湧き出でて止まぬ、豊かで磨き上げられた技巧と共に、ひとつの曲を絶品の域にまで到達させていた。
彼には、この公園での演奏によって、音楽院入学以前に、大勢の熱狂的なファンができてしまった。彼は、このことは嬉しくないわけではないが、音楽院に多数構えているに違いない、教授たちや先輩連のことを思うと、あまり好ましくないことと感じていた。だが、彼のこの心配も、群集の中から現れたジャンによって一掃された。
「アルベール、音楽院に入学もしないうちから、こんなに多くの人々から演奏を絶賛される人に、僕は初めて出会ったよ。これだけ大勢の人が君の演奏を愛しているんだ―君の才能は本物だということだ」
アルブラートは、このジャンの人柄の良さに心から感謝していたが、「予備選考」のことが気がかりだった。「あの......第一次予選のリハーサルの前に、他の受験生は予備選考を受けています。僕は、それを受けていません。それは、いつになりますか」
「君は、本当は予備選考など必要ないぐらいの腕前なんだ。でも、気になるのなら、そうだね―明後日の午後に音楽院の2階の第3練習室に来てくれたらいい。僕と、デュトワ教授が演奏を聴くことになっているから。そこで、今日の『カプリチオーソ』を演奏したらどうかな。いいですよね、ロベール先生」
デュラックは笑って、アルブラートにこう言った。
「うちの学校には、こんな学生のリーダーがいるからね。ジャンの意見に間違いは何もない。ジャン、君が決めることは常に正確だ。もちろん君に任すよ」
5月22日の午後2時に、アルブラートは一人で音楽院に出かけた。2週間ほど前、デュラックと出かけた時の嫌な気分がちらりと頭をかすめたが、1階には人影は見当たらなかった。彼はほっとして、ジャンの待つ2階の練習室に行った。そこには、30歳ほどの若い教授が教壇に腰掛けていた。ジャンは、学生の座る先頭の席に座り、入ってくる演奏者を見つめていた。
デュトワ教授は穏やかな口調で、アルブラートに優しい眼差しを向けた。
「私はミシェル・デュトワと言います。話は、ジャン・ニコラから聞いています。君の志願書類も見せてもらいました。何も緊張せずに、これは試験とは思わずに、普段通りに、まずは演奏して下さい」
アルブラートはジャンをちらりと見た。彼はジャンの微笑みに緊張感がほぐれ、まったく自室で一人でヴァイオリンを構えているような心地になった。彼は、『ロンド・カプリチオーソ』を、一昨日の公園での演奏以上に、伸び伸びと弾きこなすことができた。彼の音色の輝きは、一種の不可思議な呪文のように、低音から果てしのない高音へと自在に光を放ち、聴く者の心を荘厳な響きで満たした。

デュトワ教授はジャンとしばらく顔を見合わせていた。ジャンは満足そうににっこり笑うと、大きな拍手を演奏者に贈った。教授も拍手しながら、何回も頷き、満面に笑みをたたえ、アルブラートを賞賛した。
「素晴らしい!素晴らしい!いや、言葉に言い尽くせない―こんな凄い演奏を聴いたのは生まれて初めてですよ!ジャン・ニコラの演奏を最初に聴いた時、こんな立派な腕前は稀有なものだと思ったものだが―いや、君の今の演奏は―実に見事だった!ジャン・ニコラが天使なら、君は神だね!」
教授は感動の興奮が冷めやらない表情だった。彼は、アルブラートに「合格以上の出来栄えだ」と言いながら、提出されていた入学願書を眺めた。
「『アルベール・アドニス・ザキリス』か―ギリシャ系なんだね。君にぴったりの美しい名前じゃないか。もう覚えてしまった。いや、一生忘れられない名になってしまったね。君はアテネの生まれなの?小さい時からヴァイオリンをやっていたのかね?」
アルブラートは、自己の名や出生を、人前で偽らねばならない苦しさに、突然言葉が詰まった。「......いえ......その―父はアテネ生まれで......それで、その―僕は、弦楽器は......5歳頃から......始めました」
「ギリシャの弦楽器と言うと、ブズーキが有名だね。ヴァイオリンも5歳の頃から?」
「いえ......あの......ヴァイオリンは―その......今年の......今年の2月から......」
「じゃあ、まだ弾き始めて3ヶ月半なのか!これは驚きだね!聞いたかい、ジャン!彼はたった3ヵ月半で、芸術の域にまで達してしまった!8歳から17年間弾いてきた君が、やっと天使のレベルなのに!」
「ええ、だから申し上げた通りでしょう、アルベールは天才であって、神なんですって。先生、今日は素晴らしい日になりましたね。アルベールは少し疲れたようですから、ちょっと失礼していいでしょうか」
ジャンは、教授の質問にまごついていたアルブラートを気遣い、一緒に食堂でコーヒーでも飲もうと誘った。アルブラートは、構内を歩いていると、また自分の姿が人目につかないかと気が引けた。だが今日は何の講義もないらしく、辺りは閑散としていた。白く明るいテラス風のカフェに入ると、ジャンは陽射しに照らされた席に相手を招待した。
「ごめん。ちょっと強引だったかな―君が何となく、教授の前で履歴を言い淀んでいたみたいだったから......でも―ちょっと尋ねていいかな―君は本当にギリシャ系なの?話したくなければ別にいいんだ。でも、君の腕前があまりに優れているから、出身のことを知りたくってね」
アルブラートは、自分の故郷のことなどは、誰にも言うまい、そういう覚悟でパリに来たのだと思って来た。だが、落ち着いた、優しい性格のジャン・ニコラの真っ直ぐな視線を感じると、この人には何も包み隠すべきではないと思い始めた。
嘘をついて逃げてばかりいる自分が苦しくてたまらなかった。彼は、誰かに秘密を持ちたくないという、この焦燥感は、ちょうどムカールと対峙している時とまったく同じだと気がついた。
「......僕の今の父は、英国系エジプト人とギリシャ人との混血です―でも本当の父ではありません―父は、カイロの外科医で僕を養子にした人です。僕の真の父は......ベツレヘム出身の―パレスチナ人で......
ウードとカーヌーンの演奏家でした......でも僕が5歳の時に病死しました」
ジャンは、彼が多分そうではないかと、最初に公園で見かけた時から感じていたが、相手がパレスチナ人と聞いても、特に驚いた様子ではなかった。
運ばれてきたコーヒーも飲まずに、アルブラートは声を震わせながら話し続けた。ついに自分がアラブ人であることを、この音楽院で人に告げてしまった苦しさでいっぱいだった。
「......母も―もう......いませんが......母には複雑な......複雑な血が流れていました......母方の祖母は、やはりベツレヘムのパレスチナ人で―でも、祖父は―アルメニア人とロシアから流れてきたジプシーの混血です......僕は―レバノンやカイロで、3年半ほど、ウードやカーヌーンの演奏をして働いていましたが、ある時、母方の祖父がヴァイオリニストであり、まだヨーロッパで健在であることを知って......それで―パリに来たんです」
ジャンは、辛そうに話す彼に申し訳ないことをしたと思い、思わず彼の右手を握り締めた。
「......もういい。話さなくてもいいよ―ごめん、聞いたりして―君は話すのが苦しかったんだろう。でも、これで分かったよ―君の音楽の才能は、やっぱり遺伝と環境だったんだと―アルメニアやジプシー出身の人々の中には、優れたヴァイオリニストが多いし、お父さんやお祖父さんが演奏家だったのなら尚更だ。アルメニアで思い出したけれど、かのアルベルト・ローランもそうだね。ジプシー出身で素晴らしいヴァイオリニストだし......」
アルブラートは再び祖父の名を人から聞いて、噂を尋ねたくなったが、やはり訊きにくく感じ、口を閉ざしていた。ジャンは、しばらく黙っていたが、急にまた話し始めた。
「アルベール、君には僕がどう見える?僕は、君にはただのフランス人に見えるかい?」
アルブラートは、相手の言っている意味がよく分からなかった。彼は首を振り、ジャンを見つめ、考え込んだ。ジャンは、意を決したように、いきなり切り出した。「僕の故郷はパリじゃない。君と同じベツレヘムなんだ―僕は、フランス人じゃない。ユダヤ人なんだ」
その言葉を聞いた途端、アルブラートの体を戦慄が貫いた。彼は、ジャンの手を乱暴に振りほどくと、相手をきっと見据えたが、耐え切れなくなり、目を固くつぶると、頭を抱え込んでしまった。
この人が......この親切な人がユダヤ人......!嘘だろう......嘘に決まっている......嫌だ......!信じたくない......!
彼は、サイダのホテルで出会ったヨシュアも、ユダヤ人だったことを思い出し、「ユダヤ人にも親切な人はいっぱいいる」と言った、ムカールの言葉をも思い起こした。だが、ヨシュアやムカールとの思い出は、もう遠い過去になってしまい、彼の中では「ユダヤ人」は「パレスチナ人を苦しめ続けるイスラエル人」でしかなくなっていた。
ジャンは、アルブラートが当然激しい拒否反応を示すことを予測していたが、あまりの深刻な雰囲気に、どう言葉を繋いでいいのか躊躇っていた。
「―僕は、長い間、考えていたんだ......きっと、友人がパレスチナ人であっても、互いの憎しみなどなく、信頼関係を築くことができる―そんな人が必ずいると......僕はユダヤ人であっても、『イスラエル人』ではない。僕は―イスラエルという国が嫌いなんだ―僕の両親は、ベツレヘムで僕が生まれた後、パリで音楽を学びたいと、フランスに来たんだ......
でもその為にナチスに捉えられて―生き延びた多くのユダヤ人は、イスラエルを戦後、建国した。でも、彼らは己の幸福を、数え切れないほどのパレスチナ人の流血と引き換えに手に入れている―僕は、そんな国に住みたくない。このまま、フランス人として暮らしていたいんだ」
彼は、尚も項垂れているアルブラートに語りかけた。
「君は......君が憎悪しているのは『イスラエル』全体なんだろう―でも、この僕はどうなんだ―君にとって、僕は、やはり『イスラエル』でしかない―そうなのか」
アルブラートは唇を噛み締め、相手を見つめた。ジャンは、彼の大きな黒い瞳から、炎が放たれ、辺りは闇となり、ただその炎だけが激しく燃え盛っているように思えた。ジャンは、アルブラートの額が汗でぐっしょりと濡れ、こみ上げて来る涙と共に、顔全体が水に浸かった後のようにびしょ濡れになっているのを見た。
「......あなたが―あなたが『ユダヤ人』であると......
そう僕に打ち明けなかったら......こんなに苦しまないんです―あなたが―『イスラエル人』である事実はない.....そうです―最初のままで良かったんです―僕があなたを普通のフランス人だと―そう考えた.....
ほんの10日ほど前に知り合ったばかりのままであったなら.....
でも僕は―あなたの口から―あなたが『ユダヤ人』であると聞いてしまった―この事実は永久に変わらない.....それが―それが苦しいんです......」
「でも君は―僕が憎いのか。僕は君を憎んでなんかいない―君は天才であり、豊かな才能に恵まれた音楽家であり、僕は君を尊敬している。僕の腕なぞ遥かに超えている、その冴え渡った演奏に敬服している。それに、僕は君の繊細で謙虚で愛情深い人柄が好きだ―音楽を愛する者同士として、友人でありたい。でもそれは......僕が『ユダヤ人』であり、君が『パレスチナ人』である以上は不可能なことなのか」
アルブラートは、ジャンの友情と愛情を熱烈に欲している自分に気づいていた。彼は、フランス人のマリーに「自分を一人の独立した個人と見て欲しい」と頼んだことを思い出した。今、ジャンが自分に求める心は、その時の自分の心と全く同一のものなのだ―そう考えた。
彼は、ジャンの「ユダヤ人」という言葉に取り乱した自分が急に恥ずかしくなった。
常に俺は考えていたじゃないか......
「アラブ人」というだけで、なぜ人が自分を卑しめたり、皮肉ったり苦しめたりするのだと......なぜ同じ人間を「人種」で差別するのかと......
ジャンも同じことを言っているんじゃないか―同じ人間として、音楽を愛する者として、理解し合いたいと......
アルブラートは、ジャンが「ユダヤ人」だと、敢えて自分にその出生を明かしたのは、単なる概念に過ぎない民族的呼称の壁を崩し去りたい、その一念のためなのだと理解した。彼は、涙と汗で濡れた顔を手で拭い、相手を見ずに、しばらくテーブルに目を落としていた。先程の苦しみが徐々に嘘のように鎮まっていった。
やがて彼は静かな表情でジャンを真っ直ぐに見つめた。ジャンは、アルブラートの目に、深い感謝の気持ちが込められているのを見て、ほっとした。同時に、彼の目の美しさに改めて驚き、その深みに吸い込まれそうになった。
「あなたのおっしゃることが、よく理解できました―あなたのような人に、僕は初めて出会いました。僕は、あなたの勇気に敬服しています―僕のような者と、友人になりたいとおっしゃって下さって......深く感謝しています。僕の演奏も高く評価して下さって―それだけでも幸せだったのに......
失礼な態度を取って......許して下さい」
「じゃあ、僕とずっと友人でいてくれるんだね?」
「もちろんです.....ジャン、あなたは僕の、パリでの初めての大事な友人です―僕は、パリに来て、音楽院に憧れながらも、音楽院に入ることが不安でした......今月の初めに、入学願書を取りにこの学校に来た時―受付係と、事務長、そしてある教授から、酷い差別的言葉を投げつけられたから―でも、ジャンとデュトワ教授、それにロベール先生がこの学校にいて下さったら―そう思うと安心できます」
「その教授は誰だか、まあ推測できるよ。こんな『音楽院』という狭い世界の中だけなんだ、偏見や差別が起こるのは。一度リュクサンブールのような広い空間に出てごらん。君も経験したように、100人以上の人が君の演奏を絶賛しただろう。あの喝采は、君の演奏だけに贈られたのではない。君という一人の立派な人間への賞賛なんだ」
この時以来、二人は、すっかり気持ちが打ち解け、互いに大切な友となった。だがフランソワ・ギレが、食堂の影で、この二人の会話をずっと聞いていたことには、彼らは全く気づかなかった。
それから4日後の土曜日の午後、ジャン・ニコラはデュラック邸を訪れ、アルブラートに、第一次予選のリハーサルが6月6日に決まったことを告げた。
「リハーサルは、第一次予選から第三次予選まで行われて、それぞれを無事通過できたら、8月20日の入学試験の公開コンサートを受験できるんだ。でも君なら、第一次予選だけで、もう本選のコンサートを受けられる。それでも、君の性質からして、それは無理なんだろう?君は純粋で真面目だものね」
アルブラートは気恥ずかしそうに微笑み、頷いた。彼は、必修曲のリストを練習していたが、ジャンにコーヒーを入れようと立ち上がった。だがジャンは遠慮して、それよりアルブラートのピアノを聴きたいと言った。
「突然お邪魔して申し訳ありません、先生。でもぜひ彼のピアノも聴いてみたくて―構いませんか。僕は、大人しく聴いていますから」
「訊くまでもないよ。ヴァイオリン科首席の君が我が家に来てくれることこそ、光栄なことだ。それに、君が大人しいのは、もう充分分かっているよ」
デュラックはそう言って笑うと、教え子に演奏を促した。アルブラートは楽譜もまったく見ずに、1曲すべてを通して弾いた。ヴァイオリンと並行して、毎日毎日練習してきた彼には、今ではリストのソナタは楽なものだった。彼の指は自在に滑らかに動き、細かな複雑な旋律も、何のミスもなく、目にも止まらぬ速さでダイナミックに演奏した。
ジャンには、アルブラートの指が100本あるかのように思えた。30分の長い演奏の間、彼はただただ感嘆して、アルブラートの天才にますます魅了されていった。
演奏が終わると、彼は手を叩いて、すっかり感心したように首を振った。
「これはもう、リストの技術をも超えてます―リストはピアノの魔術師でしたが、アルベールはピアノの神ですね」
「私も、彼がここまで弾けるとは思わなかったよ。これならピアノ科の試験も合格間違いなしだね。ジャン、今度は君が何か弾いてごらん」
だがジャンはいつものように微笑んで、とんでもないと断った。
「僕のピアノなど、こんな素晴らしい演奏の後ではとても駄目ですよ。恥ずかしいほどお粗末で」
それでも彼は、デュラックに勧められて、ショパンのマズルカを演奏し始めた。彼の弾き方は正確且つ繊細であり、音色の美しさが最大限に際立つものだった。アルブラートは、ジャンの見事な金髪や、深みのある青い瞳から、細かな光のかけらが煌きながら散りばめられ、宝玉の音を奏でていると感じていた。
ジャンの演奏が終わると、アルブラートは感服し切ったように、拍手した。
「僕の演奏はどうも地味でね。10歳の時から始めたんだけど、15年経ってもまだこのレベルさ。君は本当に凄いよ。ピアノも、やり始めて、まだ3ヶ月半なんだろう?」
その時、彼らの背後で、小さな拍手が聞こえた。ジャンが振り向くと、アザゼルとアリが愛らしい手で一生懸命手を叩いていた。
「おててパチパチのお兄さまよ。公園のお兄さまよ」アザゼルは弟にそう言い聞かせた。アリは舌足らずの発音で、手を叩きながら、「パーパの。パーパの」と言ってきゃっきゃっとはしゃぎ、嬉しそうに笑った。
ジャンは子供たちのそばにしゃがみ込んで、アリの頭を撫ぜ、アザゼルの額にキスをした。
「本当に可愛らしいね―ねえ、僕はジャンって言うんだよ。お譲ちゃんは何て名前なの?今いくつ?」
「アデール。二つなの。アデール、ピアノのお姫様よ」
「ふうん、すごいな。お姫様なのか。ねえ、アデール、君のお父さまはすごく上手だね。ピアノもヴァイオリンも、ね」
「お父さま、音楽の王様よ。アンリはヴァイオリンの王子様なの」
アルブラートとジャンは、マリーの用意したお茶を飲むと、2階のアルブラートの部屋に行った。
「アデールは君によく似ているね。目がきれいで―まだ若いのに、君は結婚が早かったんだね。まだ19歳ぐらいなのに」
「僕はいつも実際の年齢より若く見られて―今は、21歳なんです。それに僕の本当の子は、赤ん坊のアンリだけで......アデールは、カイロで亡くなった友人の娘です。あの子はアルメニア人で―」
「じゃあ、その亡くなったという人が、君にそっくりだったんだね。君もアルメニアの血を引いているもの。アデールに母親はいないの?」
「それが、友人が亡くなった後、複雑な事情で―ちょうど2年前の今頃、行方をくらましてしまったんです。とても娘を愛していた女性だったのに......でも偶然、去年の夏までの1年間、この家でメイドをしていたと、デュラック先生のお話で分かったんです。ある男爵夫人が先生の所にピアノを習いに来ておられて......アデールはその家の養女になっていました。それでも昨年の夏、彼女はこの家を辞めて、マルセイユに行ったそうです」
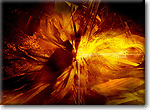
「そのアデールを君が今度は引き取ったのか......人にはいろいろな込み入った事情があるものだね」
「ジャン、あなたにもきっと複雑な事情があるんでしょう。あなたは明るくてほがらかだから、僕はあまりそんなことを考えたりしませんが......」
ジャン・ニコラは彼を見ずに、やや沈んだ表情で、何かをじっと考えていた。アルブラートは、きっと幼年時代のアウシュビッツの恐ろしい記憶が彼を苦しめ、悩ませているに違いないと察し、悪いことを訊いてしまったと悔いた。
アウシュビッツでは、人間は「人間」として扱われず、家畜以下のものにされたと聞いた......収容された人々は、生きながら燃やされたり―懐妊した女性の腹を猛犬に襲わせて食い千切り、その胎児を犬が食べたり......生きたまま髪や皮膚を引き剥がされて、人体実験の道具にされたり......そんな残忍非道な目に、彼の両親は彼が幼い時、遭って―そして殺されたのかも知れない―ジャンはそんな地獄から救われても、今尚幼時の恐怖が癒えていないのだろう.......俺と同じように......
「......いや、僕の事情なんて、取るに足らないことさ。きっと―君に比べたら......それより、君の素敵な奥さんに会って見たいな」
ジャンは、顔を上げて、何事もなかったようににっこりした。だが今度は、アルブラートが黙り込む番だった。彼は、喉の奥に固く重い岩が詰め込まれたように、しばらく言葉が出なかった。
「.....僕の妻は、半年前に―12月のカイロのテロに巻き込まれて......17歳で亡くなりました」
やっとこれだけ言うと、彼は再び周囲が夜のような闇に包まれる、異様な違和感を覚え、くらくらと眩暈がした。
二人は窓際に立っていたが、アルブラートが気を失ったように体をぐらりと斜め前に傾けたので、ジャンは慌てて彼を椅子に座らせた。
ジャンは、相手の気分が落ち着くのを待って、ようやくそっと尋ねた。
「昨年のテロと言うと―あの......シナゴーグの事件......?」
「......あれは―パレスチナ人の過激派が主犯で......シナゴーグの祈祷に集まっていた200人あまりのユダヤ人が殺されたんです―僕の妻は、スークへの近道をしようと、シナゴーグの前を通りかかったために......命を落として―」
この時、ジャンとアルブラートの間に妙に張り詰めた緊張感が走った。ジャンは、「パレスチナ人が罪のないユダヤ人を、報復のために多数殺した」ということが耐え難かった。
僕はどうかしている―パレスチナ人が戦後、イスラエルから受けてきた、想像を絶する苦悩に共感していたはずなのに―アルベールがパレスチナ人でも、テロを起こしたのは彼ではない、分かりきっている......その彼自身が、愛する妻を、彼の同胞に殺されたのに―どうしたんだろう―アルベールが憎い......パレスチナ人であることが恐ろしい......!
ジャンは、アルブラートへの憎悪をなかなか打ち消すことができなかった。これはアルブラートへの憎悪ではない、パレスチナ人過激派への憎悪なのだと自分に言い聞かせたが、自ら求めた友人の顔を、今は見ることができなかった。
ジャン・ニコラは、毎週末や祝祭日には必ずシナゴーグに通う敬虔なユダヤ教徒だった。このパリにもパレスチナ・アラブは多く、ユダヤ人人口が世界2位のこのフランスにおいても、いつまたシナゴーグ襲撃が起こるだろうかとの不安が、彼の中で強まった。
彼は、シナゴーグ爆破の話により、普段は気にかけていない、ユダヤ教徒としての洗礼名「ジャン・イシューヴ・イツハク・ニコラ」の名が思い起こされた。熱心にシナゴーグで祈りを捧げる傍ら、この洗礼名を彼は嫌悪していた。洗礼名を考えると、嫌でも幼少時の恐怖に満ちた記憶が甦るからだった。
ジャンは、カイロで多数のユダヤ人が殺害されたあの事件と、昔7歳の幼い頃目の当たりにした、両親の惨殺の光景とが重なり合い、耳を塞いで長椅子に座り込んでしまった。それは、父が母を「アンナ!アンナ!」と叫び、母が父を「ヨゼフ」と呻いて倒れた、決して忘れられない悲痛な悲鳴だった。
父は、首に鎖を繋がれて、ドイツ兵に引きずり回されて息絶えた......母は、喉から腹まで真っ直ぐにナイフで切り裂かれて死んだ......僕の―目の前で......!
彼は言いようのない苦しみに悶々とした。だが長椅子の前のテーブルに、アルブラートのヴァイオリンが置かれてあるのが、ふと目に入った。
ジャンは、ヴァイオリンを見ると、光に満ちたリュクサンブール公園での友人の最高の演奏を思い出し、はっと我に返った。
彼は、部屋の中をゆっくり見渡すと、自分は何を思い煩っていたのかと訝った。ブラウンの木目調の壁に、小ぶりな書棚と長椅子、応接台、そして詩集や歴史書、辞書のきちんと並べられた明るいベージュ色のビューロー、丁寧に整えられたベッド―その部屋には、自分が天才だと感嘆した大切な友人がおり、見事な演奏を奏でる彼のヴァイオリンがあった。
ジャンは、アルブラートの艶やかに光る褐色の肌と、賢明そうなすっきりと整った、まだ少年のような純朴な顔立ちを黙って見つめた。
これは「血」なのかもしれないな―こんな風に、罪のないパレスチナ人に対して、根拠のない憎しみを抱いたりするというのは......昔から各地を放浪し、追放され、差別され、虐殺の憂き目に遭ったユダヤ人としての、生まれつき備わる他者への敵愾心か―馬鹿げた「血」だ―今は、若い妻を失ったアルベールを慰めるべきなのに......
アルブラートは、ジャンが耳を塞いで長椅子に座り込んだ時から、異様な雰囲気を彼に感じ、不安な気持ちで、差し向かいの小椅子に腰掛け、じっと彼の様子を見守った。アルブラートは、今、ジャンの心の中で、初めてパレスチナ人に対する恐怖心が生まれたのだと敏感に悟った。
誰でも、自分の同胞を殺されたら、加害者の属する民族が憎くなる......俺が、「ユダヤ人」と聞いただけで、ジャンを恐れたように―ジャンは、俺が「パレスチナ人」であることが耐え難くなったのかも知れない......結局、ユダヤ人と友であり続けることは不可能なのか―
「......ジャン、あなたは僕を恐ろしいと―そう感じたのではありませんか......?でも、それも当然だと思います―僕は、カイロでの事件によって、自分自身がパレスチナ人であることを嫌悪し、恐ろしく思うようになりました―
パレスチナ人は、アラブ社会でも『テロリスト』として憎まれ、敵視されているほどです―レバノンでは、パレスチナ人というだけで、治安部隊から右足を撃たれ―カイロに来て、今度は同胞により妻を失う......僕は、こんなアラブ社会から逃げ出したかった―だから、遠いパリに来たんです」
ジャンは、まだ顔色が悪かったが、静かな落ち着いた口調で答えた。
「......いや、僕は君を憎んだりしない。どんなことがあっても―僕は、友達を民族的な固定観念でとらえたくない。そんなのは歪んだ、荒んだ偏狭な差別心に過ぎない―ただ、相手を祝福されて生を享けた、一人の人間として純粋に愛し、同じ人間同士として、共感を分かち合いたい―それが僕の理想なんだ。その理想を実現させてくれるのは、君しかいないんだ」
アルブラートはジャンの、深海の青さにも似た優しさ溢れる目に、正義感と真の誠実さの光を見た。彼は深い溜息をつくと、「完全な人はいない」と、少しでもジャンのことを考えた自分を恥じた。
「明日も、リュクサンブール公園に演奏に行きます。来てくれますか?何でもリクエストして下さい。ただ、30分以上の長い曲は駄目なんです。立っていると、右膝が痛むので―」
「ああ、君はそう言えば、歩くのを辛そうにしていたね―気がつかなくてごめん。レバノンで撃たれた後遺症か―もちろん、公園には毎週行くよ」
アルブラートは、彼に晴れやかな笑顔を見せた。ジャンは、彼の笑顔の素晴らしさに心打たれた。
世界中どこを探しても、こんなに魅力的な笑顔の人はいないな......何て芳しい香気を放つ笑顔なんだろう......さんざん苦労して、辛い目に遭いながら育ったんだろうに―
アルブラートは、リュクサンブール公園での演奏を毎週日曜日の昼前、ほぼいつも決まった時刻に1時間ほど行った。その「定期公演」の後は、常にジャン・ニコラと野外でのランチをとりながら、歓談した。子供たちはすっかり懐いて、「ジャン、ジャン」とまとわりついた。
6月6日の第一次予選リハーサルは無事に済み、次の第二次予選は7月1日だった。リハーサルの指揮者はデュロワ教授だった。彼は第二次予選の後、教授からジャンの話を聞いた。
「ジャン・ニコラは市内の公立音楽院生だったが、15歳の時、ロン・ティボー国際コンクールバイオリン部門で1位、18歳の時、ショパン国際コンクールピアノ部門で1位、20歳の時、チャイコフスキー国際コンクールバイオリン部門でグラン・プリを獲得してね。それで22歳の時、このコンセルヴァトワールにピアノ科とバイオリン科に首席で合格したんだ。今度は君がジャンに継ぐ稀な逸材となるのは、もう決定的だよ」
「ジャンは、それほど優れた腕前なのに、なぜ今ではピアノは首席ではないんでしょうか」
「毎年、学年末にピアノ科の学生たちの合同試験があるんだが、ジャンは2年生の終わりに、ほんの少しの差で、フランソワ・ギレという1年生に首位を奪われてしまったんだ。本当にわずかな差なんだがね」
「そのわずかな差とは......どんな点がジャンに欠けていたのですか」
「ジャン・ニコラの演奏は、彼の性格をそのまま鏡のように映し出している。誠実で、真摯で、正確で、且つ繊細、そして情緒豊かだ。課題曲はショパンの『革命のエチュード』だった。この中でショパンが、祖国がロシアに敗れた怒りを表現する部分がある。そこを、ジャンは襲いかかる津波のように力強く弾いた。だがフランソワは、同じ部分を、斬新なスピードでスリリングに演奏した。
私はジャンの演奏は、この曲想を非常に正確に表現している、と高く評価した。だが他の教授たちは、フランソワの新鮮で、モチーフからはみ出るほどの躍動感が勝っているとした。まあ、ピアニストの技量の差は些細なことだ―どちらも優れた学生だし、いつまた逆転が起こるか分からないね」
アルブラートは、ジャンの国際コンクールでの数々の輝かしい成功や、コンサートマスターとしての、この音楽院に於ける真の実力に憧れた。そんな人と自分とが肩を並べることはできないと思い、自分の力不足を恥じた。だが、7月10日の第三次予選での指揮者はジャンであり、彼は友人に「真の芸術家がついに現れた」と、皆の前で賞賛されたのだった。
息子のアリは、7月5日で満1歳を迎えていた。その時、ジャンはプレゼントにおもちゃのベビー用ヴァイオリンと、2歳児用の本物のヴァイオリンをアリに贈った。ジャンは、「子供がピアノより弦楽器に興味があるなら、2歳から学べば立派な演奏家になれる」と言った。
アルブラートは、昨年、アリが産まれた時の、アイシャの幸せそうな様子が頭に浮かんで離れなかったが、ジャンが来てくれたことで、その辛さを忘れることが出来た。アリは、夢中になって、毎日のようにおもちゃのヴァイオリンで、父を見ながら弾く真似をした。
2歳3ヶ月のアザゼルは、もう両手で『愛の挨拶』* をすらすらと弾けるようになった。彼女は、本物のピアノで弾きたがった。アルブラートがグランドピアノの前に座らせると、アザゼルは小さな白い手で、器用に弾いた。
子供たちの健やかな成長を見守りながら、アルブラートは入学試験のレッスンに余念が無かった。デュラックは、もうすべての曲は完成していると評価したが、彼は完成度を更に高めたいとの想いに駆られていた。
7月28日の暑い盛りだった。カイロより、無事に双子の男児が生まれたとの知らせが届いた。4日後の8月1日には、新生児を抱く嬉しそうなザカートとザキリスの写真と共に、短い手紙が送られてきた。
―親愛なるアルベール ご覧の通り、乳児たちも母親も元気です。20日と21日には、パリに行きます。試験が成功するよう、祈っています。1962年7月30日 W.A.ザキリス―
コンセルヴァトワールの入学試験はコンサート形式をとっていたため、既にフランス中の熱心な音楽愛好者たちがその日を待ち受けていた。そうして、ついに8月20日の前日となった。ザキリスは、直接デュラック邸に訪れた。アルブラートは、半年ぶりに再会した義父と抱き合い、懐かしさに涙がこぼれそうになった。
翌日20日のヴァイオリン・コンサートは、アルブラート自身が驚くほどの最高の出来栄えとなった。演奏がすべて終わると、会場に集まった聴衆たちの間からは感極まったように、いきなり大喝采が沸き起こり、「ブラーヴォ!ブラーヴォ!」の歓声が響き渡った。
彼は、ジャン・ニコラから祝福され、デュラックから「首席合格」の通知をその晩受けた。翌21日のピアノ・コンサートでも、満場一致で歓声を浴び、拍手が鳴り止まなかった。だが、彼が音楽院からその晩受けた通知は「不合格」だった。ショックを隠せず、悄然と肩を落とす教え子を、デュラックは励まし、必ず音楽院入学を勝ち取らせると約束した。
22日、デュラックは教授会に出席し、憤懣やるかたない様子で、アルブラートの演奏の完成度の高さを強調した。それを見たギュスターヴは軽蔑したように相手をなじった。
「あの学生は、噂ではパレスチナ人らしいじゃないか。そんな危険分子は入学は許可されない。それとも―ロベール、君はあの汚らわしい学生と同じアラブ人なのかね」
デュラックは身を乗り出し、握り締めた拳を震わせていたが、ついに堰を切ったように言い放った。「彼はギリシャ系フランス人です―しかし、私はアラブだ!母はアルジェリア人です......!それではいけませんか!」
* 『愛の挨拶』サリュ・ダムール(Salut d'amour)エルガー(英)作曲。
●Back to the Top of Part 21
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- ★ おすすめのビジネス書は何ですか!…
- 勝言/アスリート勝言研究会
- (2024-11-23 22:32:50)
-
-
-

- 今日どんな本をよみましたか?
- マクベス
- (2024-11-24 07:30:09)
-
-
-

- ジャンプの感想
- 週刊少年ジャンプ 2024年第51号
- (2024-11-24 09:52:54)
-
© Rakuten Group, Inc.



