砂漠の果て(第22部「名声」)

デュラックの唐突な発言に、会議室に集まった一同は、一瞬静まり返った。だが、その沈黙も、ギュスターヴの不愉快な嘲笑によって打ち破られた。
「ハッ!ハッ!この学院髄一の秀逸な芸術家である理由がそれか!アルジェの貴婦人の私生児とはね!売春宿で育つと、こうも立派な音楽家が誕生するわけか!」
「止めたまえ、ルイ・ギュスターヴ。君は優秀なピアニストだが、どうも人品に欠けるね。ここは会議の場であって、人を嘲笑する場ではない。口を慎みなさい」
学長はギュスターヴをたしなめた。そして、デュラックにおもむろに問いかけた。
「我々は今、君の母上がアルジェリア人であると知った。失礼だが―君の父上も、アルジェリア人なのかね」
デュラックは、ギュスターヴにより受けた侮蔑に心乱れていたが、努めて冷静に答えた。
「いいえ―私の父は、フランス人官僚です。しかし、私を実子と認めませんでした。母は、元はアルジェの豪族でしたが、勢力争いで没落しました。当時、没落した一族の娘は、スルタンの後宮に上がるのが慣習でした。ですが母は、その後宮に入るには、身分がやや低いとされました。
後宮に入れなかった女性たちは、アルジェの街の一角で、自活しながら共同生活を始めたのです。その後、第一次大戦が始まり、フランス人官僚たちが、そうした女性たちの棲家を『ハーレム』と勝手に名づけ、人身売買の享楽の場としてしまった―父は、そうした官僚の一人でした......」
意外な話を聞かされた学長は、落ち着かなげに、椅子を何回か座り直し、人差し指で、机の表面をコツンコツンと叩いていたが、やがて静かにデュラックに話しかけた。
「......人は、誰しも、親や、生まれて来る場所を選ぶことは不可能だ。人間がその生を享けるのは、すべて、神のご意思によるものなのだ―だが、私が今、君に対して抱く感情は、奇妙なことに、全く相反するものだよ。それは、この上ない驚嘆と、この上ない遺憾の念だ」
学長は、席を立ち、窓際に立つと、デュラックを真っ直ぐ見ながら語った。
「君の才能や業績は、間違いなく、この音楽院の歴史に残る。君は、不遇な生い立ちにも負けず、その天賦の才を遺憾無く発揮し、我が校の名誉となり、数々の優れた人材を育て上げた、立派な芸術家だ。これに私は、実に驚嘆している。だが、君の故郷は、我がフランスの長年の植民地であり、そして過去8年にも渡って、アルジェの民衆は独立闘争を続け、ついに昨年、勝利を手にした。
これは支配者側の敗北であることは事実だ―我々は、政治家はなく、芸術家だ。そんな政治的側面に関与すべきでないことは分かっている。だが、国民的感情というものがある―帝国支配の時代は既に終わりを告げつつあるし、ある国を軍事力で支配下に置くことは大いなる誤りだ。それなのに、私にはフランス人がアルジェリア人に敗北した悔しさがある―自分でも、認めたくないことなのだが―」
彼は、デュラックからやや視線を反らした。
「非常に申し訳ないが、これが、君に対する遺憾の念の最たる理由だ―君が長年フランスに抵抗を続けたアルジェリア人との混血である、この点が残念でならない―君の絶賛する、アルベールという学生の成績は、この2日間の演奏と口頭試問で、既に『両専攻首席合格』の太鼓判を押してある。あれだけの優れた完璧且つ才能豊かな学生は、ここ数年出現しなかった―そうだったね、ミシェル・デュトワ、アンジェ・ジュール」
「もちろんですとも。あの入学試験コンサートに集った聴衆は、単なる物見遊山の烏合の衆ではありません。皆、クラシックに対する洗練された趣味を持つ、耳の肥えた人々ばかりです。その聴衆が最も拍手喝采し、熱烈なる絶賛の声を上げたのは、32名いる受験生の中でも、唯一、アルベール・ザキリスの演奏に対してのみでした」
ジュールが冷静な口調で学長にこう告げると、デュトワが熱心な口ぶりで言葉を継いだ。
「アルベールの演奏は、全曲、何のミスもないばかりか、完成度の極地を極めていましたし、また洗練された音色と情操の見事なまでの豊かさ、そして高度なテクニックの正確さを駆使して、実に新鮮な深い感動をもたらしたという点で、稀なる芸術性を備えた、大変優れたものでした。口頭試問でも、発音の美しさは言うまでもなく、独自の音楽理論を既に確立させていた点でも、他の学生を抜きん出ており、トップの評価を与えましたよ」
「そう、アルベールという学生には気の毒なことをした。初日の試験では、彼はヴァイオリン科首席合格というのは確実だった。2日目のピアノ科の試験でも、私は首席合格の通知を用意していた。だが、その通知をデュラック、君に渡す前に、私は、あの学生がパレスチナ人であるとの話を聞いたのでね」
「学長、それは......根も葉も無い噂です。一体、誰がそんなことを学長に申し上げたのですか」
「ルイ・ギュスターヴだ。彼が、ある学生からその話を聞いたとのことだ。だから、私はアルベール・ザキリスを一旦、不合格とした。しかし、それは決定的なものではない。デュラック、君自身から、彼がパレスチナ人か否かをじかに聞きたかった。彼の身元は、一体どういうものなのかね」
「あの若者は―私の従兄弟なのです。私は、10歳の時、パリに出て来て、実の父を探し当てました。しかし、父は私を、父の弟、つまり私の叔父に預けました―叔父は純粋なフランス人でしたが、叔母はアテネ生まれのギリシャ人でした。叔父夫婦の5人の子供たちの末っ子がアルベールです。私とは23歳も違いますが」
デュラックは、アルブラートがパレスチナ人であることを、決して公言すべきでないと、かねてから用意していた作り話をした。だが、可愛い教え子を弁護するうちに、この事実の織り交ざった虚構が、不思議と真実であるかのように思えて来た。
「叔父には5人もの子供を育てる経済力がありませんでした。そこで、叔母の兄の、ザキリス医師がアルベールを養子としたのです。医師は熱烈な音楽愛好家で、アルベールの才能を伸ばしたいと、親戚の私の所に下宿させたのです」
「なるほど―あの若者の才能は、君との血縁と影響によるものか―まあ、これで納得がいったよ。君の言うことに間違いはないだろう。それでは、アルベール・ザキリスを、我が音楽院の栄えある首席合格者と、正式に認めよう。さあ、デュラック、これがアルベールの両専攻首席合格通知と、入学許可証だ。彼は今は失意のどん底にいるだろうが、今日は彼にとって、人生最高の喜びの日になるだろうね」
デュラックは、それらの書類を有難く受け取った。だが、学長は言い難い調子で、渋るように、彼に人事の件を告げた。
「それで、デュラック、君には大変申し訳ないのだが、新学期からは、このコンセルヴァトワールには君の仕事はもう無いのだよ。君の、我が音楽院における、長年に渡る貢献と業績は、非常に高く評価している。だが、私は―アルジェリア人との混血である君が、今後もこの伝統ある音楽院の教授であることに耐えられないのだ―君は、人種差別と受け取るだろうが、そうではなく、長い間、植民地支配下に置かれてきたアルジェリアが、支配者であるフランスを敗北させた―そのことに関する国民的感情ゆえのことなのだ」
デュラックは、学長から、このように辞職を勧められるだろうことは予想していた。彼は、平静な態度で、この話を聞いていた。だが、内心、学長の言う「国民的感情」というのは単なる言い訳に過ぎないと感じていた。
学長は、アルブラートを入学させる条件として、アラブとの混血である私を、この学校から追放したいのだろう......つまり、学長の意識の底には、「アルベール・ザキリス」という学生に対する、パレスチナ・アラブではないかという疑念が燻っている―だが非常に優れた才能の学生を入学させたいという願望も強い―その矛盾した心理のバランスをとるために、アラブ人の血を音楽院から排除したい―つまり私を辞職させたい―そういうことなんだろうな......
「承知致しました。幸い、私はブリュッセル音楽院の教授のポストを、度々勧められておりましたので―9月からはベルギーで仕事をすることになるでしょう。なかなか決心がつきませんでしたが、これを機に、コンセルヴァトワールを辞職致します」
アルブラートは家で、師の帰宅を待っていた。彼は、ジャンやザキリスから懸命に励まされたが、内心、もう入学は駄目だろうという諦めが強かった。
「アルベール、あんなに立派に演奏が出来たのは、ヴァイオリン科とピアノ科の受験生の中で君一人だけだったんだ。何かの間違いに決まっている。必ず、ロベール先生が朗報を持って来て下さるから」
「いえ、両方とも専攻しようだなんて、いきなり欲張り過ぎました―ヴァイオリン科だけで良かったんです......来年、ヴァイオリン科だけを再受験しますから―」
......とは言っても、俺が「入学拒否」されたのは―やはり「差別」によるものかも知れない......書類で「ギリシャ系フランス人」だと主張しても、この外見がすべてを語っている―もう音楽院は諦めて、どこかのレストランで、また演奏して働くか......ヴァイオリンとピアノの演奏で―
「君が私の元を離れて、デュラック先生のご指導を受けて、たった半年で、あれほどの聴衆の拍手喝采を受けるほどにまで、ヴァイオリンとピアノが上達したことには、本当に驚いたよ。子供時代からクラシックの大ファンの私が聴いた中で、極上の演奏だった―きっと、ジャン・ニコラの言う通りになる」
医師は、溜息をついているアルブラートの肩を叩いて、再度励ました。マリーは、子供たちを遊ばせながら、彼を気の毒に思った。
「お父さま、かっこ良かった。ねえ、マリー。すごい拍手、ねえ」
アザゼルは、ピアノを弾きながら、無邪気にマリーと話していた。その時、ドアの呼び鈴が鳴った。マリーが慌ててドアを開けると、デュラックが急いで室内に入り、嬉しそうに叫んだ。
「合格だ!両専攻首席合格だ!正式に入学が決定したよ!」
ジャンは、一瞬、信じられないという表情をしたが、すぐにアルブラートの方を振り返ると、満面に笑みを湛え、彼の両手をしっかりと、優しく握り締めた。
「おめでとう―本当におめでとう。君の半年間の努力がついに実ったね」
それから、ジャンはデュラックに駆け寄り、合格通知と入学許可証を目にすると、まるで自分のことのように喜んだ。
「すごいな―ロベール先生、魔法でも使ったんですか?もしそうなら、先生は魔法使いだ!僕、絶対そうじゃないかって思ってましたよ!」
「まるで子供みたいなはしゃぎぶりだね、ジャン!でも君の言う通りだよ!私は魔法を使ったんだ―言葉の魔法をね!さあ、アルベール、君への最高の贈り物だよ」
デュラックは、音楽院の書類を、アルブラートにそっと手渡した。アルブラートは、夢を見ているような心地で、恩師を見つめながら、合格通知を静かに受け取った。確かにそこには、自分の名と、「コンセルヴァトワール」という文字と、「ヴァイオリン科・ピアノ科両専攻首席合格」との言葉が書かれてあった。
彼は、改めて師の顔を見た。デュラックの黒い瞳や顔立ちは、不思議と遥か遠い自分の故郷の地への憧憬を思い起こさせた。その憧憬に、5年前のガリラヤ湖の風景が重なった。
デュラック先生と知り合ったのは、俺がベイルート音楽院に入学したいと希望したのがきっかけだったんだ......先生は、そのために俺に根気良くフランス語を教えてくれた......お金と、外出着と、靴と腕時計を生まれて初めて受け取ったのも、先生から―そのデュラック先生が、今度は俺に西洋音楽を教えてくれて、パリ音楽院に合格させてくれた―この先生との縁はなんて深いんだろう......
アルブラートは、感謝の言葉がなかなか出て来なかった。だが、デュラックは、彼の憂いに満ちた瞳に、深い感謝の表情をはっきりと読み取り、大きく頷くと、教え子の肩を抱き寄せた。その肩は5年前と同じように、細く華奢でしなやかだった。
「アルブラート」と、彼は心の中で、愛する教え子の本来の名を呼んだ。
アルブラート......君はなんと立派な能力に恵まれているのだろう......アルブラート......私はこんな素晴らしい子に出会えて、世界一の幸せ者だ......
「さあアルベール、笑ってごらん。君の最高に魅力的な笑顔が見たくって、飛んで帰ったんだから」
アルブラートは、やっといつものように明るく微笑んだ。ジャンは溜息をついて、惚れ惚れとしたように、その笑顔を眺めた。
「本当に良かった!僕は絶対に信じていたんだ、君が首席で入学できるって!今日は最高に嬉しい日だ!1日悲しんだ分を取り戻さなきゃね!」
マリーのそばで遊んでいたアリは、ジャンから貰ったおもちゃのバイオリンを手に取ると、アルブラートの傍によちよちと歩いてきた。アリは、懸命にバイオリンを弾く真似をして見せた。そのおもちゃは、弦を弓で触れただけで、いろんなメロディーが鳴り出すものだった。
アリは、先月1歳の誕生日を迎えた3日後辺りから、一人歩きができるようになった。歩き出した赤ん坊は、目が更に生き生きと輝き、生まれて初めて自由を手に入れた喜びを、全身で表していた。アリは、父親や周囲の嬉しそうな雰囲気につられて、バイオリンを得意気に鳴らし、しきりに同じ言葉を繰り返しては、きゃっきゃっと喜んだ。
「パーパ、パーパの。これ、これパーパ。パーパのね」
ジャンは子供好きらしく、アリを抱き上げて、頬ずりした。
「可愛いなあ―本当に愛らしいねえ。ねえ、アンリ、パパが笑うと君も嬉しいんだね。ね、僕の名前も言えるかな、『ジャン』って」
アリはきょとんとして、アルブラートの方をジャンの肩越しに見た。
「ジュ、ジュ。ジュ......ジュ......ジャ......」
人差し指を口にくわえながら、懸命に正しく発音しようとしているアリを、アルブラートは微笑んで、褒めてやった。「そう、上手だね。ジャンが好きなんだね」
父親に褒められた嬉しさから、今度はアリははっきりと「ジャン」と言うことが出来た。すっかり得意になったアリは、ジャンに抱きついて、「ジャン、ジャン」と繰り返しては可愛い声で笑った。
その晩はアルブラートを囲み、皆で祝杯を挙げた。彼は、皆にお礼を言い、ワインを飲みながら、ふと碧水晶のことを思い出した。
ああ、そう言えば......そうだ、あの碧水晶がやっぱり蒼く光って、半年後の未来を見せたじゃないか―サハラに行って、あの水晶をもらったのは1月10日だったから、ちょうど半年後を気をつけなけりゃと思っていたんだ―7月10日は、ジャンの指揮でチャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲の第三次予選を受けたっけ......
その日の晩、本当にあれから半年後、夜中の12時少し前から、水晶が輝き出して......音楽院のコンサートで俺がピアノを弾いている姿とか、デュトワ教授の個人レッスンを学校で受けている姿が見えたんだ―それで、「きっと合格するんだ」と安心していたのに―昨日の不合格通知で、そのことをすっかり忘れていたな......
だが彼の満ち足りた幸福感は、デュラックとザキリスの会話を耳にした途端、色褪せてしまった。
「今度のアルベールの首席合格は、3年前のジャンに次ぐものでしたよ。私の指導が良かったわけでは決してなく、すべて彼の才能と真摯な努力によるものでね―これで私も安心して、ブリュッセル音楽院に行くことができます」
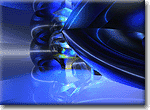
デュラックの隣に座っていたジャンは、食事の手を止め、驚いて師に問い返した。
「ロベール先生、なぜブリュッセルに行かれるんですか?コンセルヴァトワールでも先生の右に出る教授はおられないのに―」
「いや、私は、度々ブリュッセル音楽院から、教授のポストを薦められていたんだ―去年の秋頃からね。最初はあまり乗り気ではなかった。ここの音楽院で20年も教えて来たから―でもブリュッセル音楽院の方が、正直言って報酬はずっといい。だから、アルベールの合格を見届けた後は、ベルギーに行こうと思うようになったんだ」
彼は、向かいに腰掛けているアルブラートを見て、励ますように言った。
「ずっと黙っていて悪かったね―でもパリからブリュッセルまでは特急で2時間半だし、私は週末や休暇にはこの家に戻るから、全くこれで『アデュー』* と言う訳じゃない。私と君の間に永遠の別れなんてないんだ」
「そうですか―でも、僕は、コンセルヴァトワールでも先生に教えて頂けると思っていたので......やっぱり、残念です」
感じやすいアルブラートは、自分の合格は、もしかしたら、自分を弁護したデュラックの音楽院からの追放という代償の上に得られたものではないか、と確信した。彼のその疑惑は、ほぼ直感的且つ決定的なものだった。
「アルベール、入学した後の心配は何もいらない。私がいなくても、1年生のピアノ科はアンジェ・ジュール教授、ヴァイオリン科は、君もよく知っているデュトワ教授が指導して下さる。どちらも人格者で、学生の眠れる才能を呼び覚ます、優れた指導で評判なんだ。それに、ジャンは卒業後は、研究科に進学して、教授の助手になるそうだ―そうだね、ジャン・ニコラ」
「ええ―先日の卒業試験で、幸い首席でしたので......」
「モスクワの国際コンクールは、今年は出場しないのかね」
「僕は、もっと研鑽を積まないと―自信が今の自分にはないんです。コンクールは、正直言って、今の僕には敷居が高くて......ただの名声目当ての音楽家になってしまうのが嫌で―もっと、音楽と自分との関係をよく考えて、自分の音楽を深めなければ、コンクールに出場してもあまり意味がないと思うんです」
ジャンは深刻な口調で、静かに語っていたが、アルブラートの方に顔を上げると、いつものように優しく笑みを浮かべた。
「それに、僕は国外で演奏活動をするより、音楽院で後輩の指導に当たる方が向いていると思って―僕なんかがアルベールに何かを教えるなんて、全く逆な気がしますが」
アルブラートは、ジャンが卒業後も学院に残ってくれることに大きな安堵感を感じ、ややほっとした。デュラックは、ジャンの謙遜ぶりにすっかり感心していた。
「本当に、首席卒業でありながら、ここまで自分を戒められるとは、大いなる美徳だね!大抵の首席卒業者は、自分に酔ってしまい、浮ついた気分でコンクールに参加して、結局は薄っぺらなスターとなってしまう。要するに、地に足がついてない、自分を見失っていることに気がつかない者が大半なんだ。アルベール、君はこんなに人徳ある友人に恵まれてラッキーだよ!ああ、そうだ、ジャン」
デュラックは、ジャンに、下宿先は卒業後はどうするのかと尋ねた。
「今まで、君は、奨学金を受けて、リュクサンブールの学生寮に下宿してただろう。でも研究科に進むとなると、奨学金は出ないし、その学生寮は出ないといけない。今後はどうするんだね」
ジャンは肩をすくめて、笑って見せた。
「なんとかしますよ。助手の給料もご立派な額だし、亡くなった叔母の遺族年金も、僅かですがありますし―この街には、国立出の音楽家にはありがたいほど、ボロい下宿屋がうんざりするほどありますからね。貧乏学生も、楽しいものですよ、先生」
デュラックは、ジャンの屈託のない明るさに改めて惚れ込んだ様子だった。
「君もなかなかエスプリ* の利いた皮肉がうまいもんだ―ジャン、君みたいな面白い人は、いっそのこと、うちに下宿したらどうだね?私がいない家は、アルベールには寂しいだろうし、私は週末には帰って来て、賑やかに過ごせるし―どう、名案じゃないか!ただし、下宿代は世界一高くつくから、覚悟しておいで」
ジャンは、思いがけない提案にすっかり有頂天になってしまった。
「アルベール!今の聞いた?君と同じ家で暮らせるなんて!ありがとうございます、先生!もちろん、世界一高い下宿代は、即金でお支払しますよ!」
アルブラートはすっかり嬉しくなり、傍にいた子供たちに浮き浮きした調子で話しかけた。
「ねえ、アデール、アンリ!9月から、ジャンがこの家で一緒に暮らしてくれるんだって!良かったね、嬉しいだろ?」
アザゼルは一瞬、意味が分からなかったらしく、首を傾げたが、すぐに目を輝かせて、アルブラートに飛びついた。「ジャン、来るの?ジャン、一緒なの?それなら、一緒ね、アデールとピアノ、ピアノとジャン―嬉しいな、嬉しいな」
アリはキュッキュッとくすぐったそうな笑い声を上げて、小さな両腕を上げると、「万歳」の仕草をして見せた。「ジャン、ジャン、パーパと。パーパ、ジャンとなの」アリは懸命にこう言うと、万歳をしたまま、パチパチと拍手した。
* 「アデュー」Adieu : 「さようなら(もうお会いできないでしょう)」長い告別の場合に用いられる。(=farewell forever)
* 「エスプリ」esprit : 機知・才知 (=wit)
「随分と熱心だね。いつもこんな時間まで勉強を?」
もう晩の11時近かった。机の上には楽譜や西洋音楽史事典、フランス語の辞書やノートが広げられ、乱雑に積み重なっていた。ワイングラスを片手に入って来たザキリスは、応接台の長椅子に腰掛け、テーブルの上の合格通知を改めて眺めた。
ザキリスは、いつも整理整頓が行き届いているアルブラートの机が乱れているのを珍しく思った。アルブラートは、医師にワインを注ぎながら、笑って溜息をついた。
「僕は昨夜は眠れなかったんです―不合格のショックで、ワインを飲みながら、手当たり次第に読むものを引っ張り出して、そのまま今日の午後までほったらかしにしてたんです」
「それでも、毎晩ピアノとヴァイオリンのレッスンを続けて、夜は夜で口述試験や筆記試験の勉強をしていたのか......私は、君なら合格するとは思っていたよ。しかし両専攻ともに首席とはね―本当にパリに来た甲斐があったじゃないか」
アルブラートは、義父の精悍な、彫りの深い、古代ギリシャの哲学者にも似た面立ちをじっと見つめていた。野性味を感じさせる男らしさと、鋭利な知性と荘重な雰囲気の漂うギリシャ人特有の魅力的な風貌は、彼に地中海の風とカイロの香りを強烈に感じさせた。
彼は、ザキリスに、思わず、以前のように、アラビア語で話しかけようとした。彼は、どうしても母国語と自分を完全に切り離すことができないもどかしさを、今ここで改めて痛感した。
「せっかく合格したのに、そう嬉しそうでもないね―何か心配事でもあるのかね―パリに来て......体の調子は大丈夫だったかな―2週間分、以前よりも少し弱い安定剤を持って来たんだよ。前のは副作用がきつかっただろう」
「体調は―3度ほど―吐き気や頭痛に襲われました。最初は、先生のお薬で治まりました―後は、薬なしでも不思議と治まったんです......
その―子供たちを見ることや、ピアノを弾くことで......」
「それならいいが、どうしてもまた―苦しさが起きたら、この薬を飲んでみてもいいし―しかし、発作がピアノで救われるのなら......君はいろいろと辛い問題を抱えながらも、たった半年で、ヨーロッパでも一流の音楽院に首席で合格したんだ―私は君の強靭な精神力に脱帽せざるを得ないな」
「いいえ、僕の精神力は驚くほど虚弱です......僕は、先生にお会いして、あれほど決意したのに―アラビア語で語り合いたい衝動に駆られてしまう―僕は、フランス語で生活していれば、フランス人に成り得ると考えていました......そしてアラブ世界のことを全て忘れられるのだと―
でも、僕の中には別の僕がいる......『アルベール』なんて名前の人間はお前自身じゃないとささやく僕がいる―そんな名前でピアノやヴァイオリンを弾いても、それは虚像だと叫ぶ僕がいる......だから、この合格通知も、嬉しいと感じる僕と、『自分をごまかしてフランス人の振りをして、それで通るか』となじる僕がいる―僕には、どちらが本当の自分なのかが分からないんです―」
アルブラートは、自分でもワインを飲みつつ、半分酔ったように頭がぼんやりとし、普段とは打って変わって饒舌になっていた。ザキリスは、彼の美しい発音のフランス語に感心しながらも、アルブラートがパリ音楽院に合格したことで、新たな悩みが彼の魂を蝕んでいる様子が哀れでならなかった。
「アルベール......いや、アルブラート。フランス名を名乗り、フランス人足り得ようとする君の意識的な努力を、プラスの方向に変えなさい。君が母国語を捨てて、異国の人間として生きようとする心に、『母国語を捨てても、完全にフランス人になれるわけがない』というマイナスの力が働きかけているからこそ、君は自分自身を掌握できないでいるんだ」
アルブラートは、再び振り出しに戻り、サハラ砂漠の中を彷徨っている時の、あの寄る辺無い虚しさを覚えた。彼は、ワインにすっかり酔っていたが、半分酔いが醒め、いつもの真面目な口調で応じた。
「......先生のおっしゃる通りです―僕は、自分が分裂したままなんです―その二人を一人に合致させて、しっかり掌握しない限り、デュラック先生がご自身を犠牲にしてまで勝ち取って下さった合格通知は、ただの紙切れになってしまう......僕は、首席である必要なんかないんです―僕には名声なんて無縁なんです―ただ、西洋音楽が過去の苦しみを忘れさせてくれる―それで充分なんです......でも、自分を見失ったままでは、首席どころか、この学院から転落していくだけなんだ.....」
ザキリスは、アルブラートの「デュラック先生がご自身を犠牲にした」という言葉に驚いた。
「ロベール先生が犠牲に......?なぜそう思うんだね―先生のベルギーへの転任は、前から決まっていたことだと、君も聞いたじゃないか」
「いいえ、ベルギーへの転任は、僕の不合格を弁護したために決定がおりたんです―デュラック先生は、普段から、先の予定をきちんとお話下さる方です―あれは、僕を安心させようと......それに―先生は―多分、アルジェリア人との混血です.....そのせいもあって、学院から追放されたんです」
ザキリスは、これは奇妙な憶測に過ぎず、その憶測は、アルブラートの自己を責める傾向の強い性格から来ているのだ、と感じた。
「君の今、考えていることには、何の根拠もないだろう。デュラック先生の赴任は、先生ご自身が決定されたことかも知れないし、ブリュッセル音楽院からの赴任の依頼も、事実あったことなんだろう―パリ音楽院が勝手に、あの先生にひどい仕打ちをしたと判断するのは早計だし、的はずれなことかも知れないんだ。何でもそう悲観的に解釈すべきではないよ」
「......このパリ音楽院は、東洋系人種を毛嫌いする傾向があります―僕の2回目の発作も―5月、音楽院に入学願書を受け取りに行った時に起こりました―僕の外見から、『野蛮なアラブ人がピアノに触れると学院が穢れる』と―そうなじられたんです」
「そいつはひどいな―誰が一体そんなことを......?」
「ピアノ科の教授が、デュラック先生に面と向かって、そう言ったんです―その時、先生は僕を『ギリシャ系フランス人だ』とかばって、激しく憤っていました......僕は、先生がそんなに憤るのは、教え子を擁護するためだと思いました―でも、僕が侮蔑を受けたショックで、ピアノのレッスンに失敗を重ねている時、先生は僕に、『君と私には同じ血が流れている』と励まして下さいました......僕は、その『同じ血』という意味がすぐに理解できませんでした―でも、その翌日、思い当たることがあったんです......」
彼は、デュラックの書棚から、1925年に撮影されたアルジェリア人親子の写真を見つけたことや、一緒に写っていた7歳ほどの「サイード・アル・ガサン」という名の少年が、デュラックに似ていることを話した。
「それでは、そのサイードという少年が、デュラック先生だと―そう思っているのかね」
「......僕は、先生にはどこか、フランス人らしくない雰囲気があるといつも感じていたんです―先生の言われた『同じ血』というのは、きっとアラブの血ではないかと、その写真を見て気がついたんです―先生が僕を必死に弁護して下さるのは、きっと、同胞の者をかばいたい一心からじゃないかと......だから、僕を入学させるために、仕方なく、自分の素性を明かす必要性に迫られて―ついに辞職させられたのではないかと......そう思うと申し訳なくて―」
ザキリスは、デュラックと最初に出会った22年前の大戦中を思い起こした。自分自身にも流れるアラブの血の直感から、彼は、当時から、デュラックのことを、純粋なフランス人ではないと見ていた。
「ロベール先生は、まだパリ音楽院生でね、ドイツ軍の車にはねられて、肩を骨折されたんだ―私は医学部の研修生で、偶然先生を手術することになった―初めての外科手術の患者だったから、それで互いに知り合いになってね―先生は、ドイツ軍のパリ占領を、フランスのアルジェリア支配に準えて、アルジェリアの独立を熱っぽい口調で私に語ってくれた―だから、私は、何となく、先生を、その時以来、アルジェリア人との混血なのではと感じていたんだ」
医師は、アルブラートにそう語り、無言で頷いて見せた。
「でも、今私と君が感じていることも、単なる憶測に過ぎない、何の根拠もないことなんだよ。もし、あの先生が、音楽院で、自ら自分の出生を明かしたとしても、それは、先生には苦しい経験だったかも知れない。だから、アルベール―先生がはっきりと君に打ち明けないことを、君は先生に質問しないことだ......分かるね」
アルブラートはまだ話し足りない様子だったが、ザキリスは時計を見て、もう午前1時を回っているのに気がついて、話を打ち切ろうとした。
「明日はゆっくりパリ見物でも久しぶりにしたかったがね、生憎午前11時半の便でカイロに帰るんだ。息子たちもまだ生後1ヶ月にも満たないし―ザカート一人じゃ双子の世話は大変でね、看護婦を一人世話係につけてあるんだが......10月の後半にはアンディーとニコを連れて来るよ」
ザキリスは新生児の息子たちが、一卵性なので、父親の自分でも二人の区別がつかないこと、仕方なくアンドリューには「A」、ニコラスには「N」の文字を書いた腕輪を付けているのだと笑った。
「とにかく、君の9月10日の入学式にはまた来るよ。君は首席合格者だから、確か新入生代表として、あのコンサートホールでまた演奏をするんだろう?それに、あの青年―ジャン・ニコラも研究生代表でピアノを演奏するらしいね。アルベール、君はジャンがいれば―きっと、フランス人として自信を持って学校生活が送れるんじゃないかな。彼は本当にいい人だよ。君も、ジャンがいる時は、実に楽しそうにしていたじゃないか」
アルブラートは、ジャンのことを考えると、義父の言う通りだと思い直した。だが、彼は、ザキリスがそばにまたいなくなることに、妙な不安を覚えた。彼は、ノートを開くと、アラビア語で何か簡単なメッセージを書いてくれと医師に頼んだ。
ザキリスは、彼の心が落ち着くならと思い、少し考えた後、短いメッセージを書き付けた。
あらゆることに挑み自らの音楽を磨く
そうすれば君は芸術の高みを果てしなく極めていくだろう
君をもし陰で謗る者がいるならば
その者こそ真にこの世界から転落していくだろう

ノートを返すと、ザキリスはお休みと言って部屋を出ようとしたが、急に振り返って、アルブラートを強く抱きしめ、アラビア語でしっかりと言い聞かせた。
「忘れては駄目だ......自分のルーツを決して、決して忘れては駄目なんだ......!君が自己を見失いかけているのは、君自身のルーツを否定しているからなんだ―アルブラート、君は、アラブという根本的民族性が意識の底に根付いているのに、それを無理に曇った硝子で覆い隠そうとしている―これからは、自分が何者か把握出来なくなった時、その都度、苦しくとも、そのルーツに立ち戻らなければならないんだ......
その時は、苦しい過去を意識から取り除いて、アラブ人であること自体を誇りに思わなければ意味が無い―まず自分の根源的存在を認めた上で、フランス人というヴェールを身にまとうことだ―そうしないと......君は君自身を、アラブ人ともフランス人とも決めかねて、ついには本当の自己を喪失し、精神が破壊され、音楽の修行どころではなくなってしまう―これを心に留めておいておくれ......君は、私の大事な息子なんだ」
義父のこの言葉は、アルブラートに、新たな認識をもたらした。ザキリスの考え方は、自分のものとは全く異なっていた。彼は、義父がカイロに帰った後も、毎日のようにこの言葉を何度も心の中で繰り返した。
ウィリアム先生が言ったことは、俺のヨーロッパにまで来た決意を百パーセント覆すものじゃないか......俺は、アラブであることを強いて忘れ去ろうと努力して来たんだ―そうすることで、別の人間に成り切ろうと―でも、先生は俺の努力が座礁に乗り上げていることを見抜いて、あのアドバイスをしてくれた―結局は......そうなんだ、結局は、先生の言うとおりにしないと、俺は自分というものが無くなってしまう......
彼は、ザキリスが言った、「フランス名を名乗り、フランス人足り得ようとする君の意識的な努力を、プラスの方向に変えなさい」との言葉を、「アラブという根源的ルーツを誇りを持って再認識する」との考えに重ね合わせた。彼は、医師の言う「プラスの方向」とは、その「アラブであることを常に忘却の底に埋めてしまわない」ということなのだ、と理解した。
青い男ル・ラフの言ったことも、別に誤りではない―彼は、俺が「アラブ」という民族性を捨てることを知った上で、「フランス人であろうとするなら、アラブ人である意識が残らないように、すべてフランス語を使え」と言った―ル・ラフは賢明で、筋の通ったアドバイスをした―俺みたいに、フランス人であろうとしながら、アラブを懐かしんだりしないな......もし、ル・ラフが俺だとしたら......
アルブラートは、合格通知を受け取った8月22日以降、入学式に首席合格者としてホールで演奏するラロの『スペイン交響曲』を練習しながらも、レッスンの合間にはこれらのことを考えた。彼の心には、少しずつ、自分のルーツを大事にしようという意識が芽生え始めていた。
夜には、自室の窓を開け、晩夏の芳しい空気を吸い込みながら、煌くパリという大都会の豪奢な輝きの遥か西南へと目を凝らした。そして、漠然と見たことのない生まれ故郷のことを考えた。
いつかはきっと、俺はベツレヘムに帰る......20年後か30年後に......この頃にはベツレヘムはパレスチナ人の故郷になっているに違いない......
一人で部屋にいる時は、部屋履きを脱ぎ、裸足になり、絨毯の上に寝転んだりした。その時甦ってきたのは、ヨルダン北部で過ごした難民キャンプの思い出であり、貧しくとも大自然の中で暮らす、自由な幸福感だった。絨毯はたちまち色褪せたイェリコ製の幾何学紋様に変化した。
彼の目の前を、パレスチナの衣装を身につけた若い女性たちが、井戸から汲み上げた水を、形の崩れたブリキのバケツにたっぷりと貯めて、頭の上に乗せながら、通り過ぎていった。小さな子供たちが、着古したイギリス製のシャツやズボンを着て、裸足で楽しそうに走って行った。年配の男性たちは、伝統的なクフィーヤで頭を覆い、パレスチナに古くから伝わる民謡を口ずさんでは談笑していた。
アルブラートのこの難民キャンプの幻影には、母も、タウフィークも、アイシャも存在していなかった。彼は、彼らの思い出をすべて消しゴムのように記憶から消し去り、そして、ただ、パレスチナ人であることの誇りのみを、それら幻影の中に見出そうとしていた。
その時、彼は、ムカールが死の1週間前に、彼らに婚礼衣装を贈りながら、「パレスチナ人には素晴らしい文化がある。それを継承し、パレスチナ人であることの誇りを忘れないで欲しい」と言った言葉を思い出していた。
ある日の夕方、自室でレッスンの後、やはり裸足になって、絨毯に寝転び、オレンジをかじっていると、急にアリが部屋に入ってきた。アリは、絨毯に寝転ぶ父親を面白いと感じたのか、愛らしい声でキャッキャッと笑い、仰向けの彼の体に抱きついてきた。
アルブラートは、アリの真っ直ぐな額や理知的な顔立ちが、驚くほどアイシャに似てきたことに、はっとした。彼は、幼い息子を見るのが急に辛くなり、アリの顔を自分の胸に抱き寄せながら、難民キャンプの懐かしい夢のまどろみから醒めようと、体を起こした。だが、そこは応接台の下で、彼は額をテーブルに思い切りぶつけてしまった。
「パーパ、パーパ。ここ、パーパ、ゴッツン」
アリはそう言うと、思いがけないハプニングに有頂天になり、自分でも父親の真似をして、絨毯に寝転び、テーブルに頭をぶつける真似をし出した。アルブラートは慌てて、赤ん坊を止めようとしたが、アリにはそれは新しく発見した遊びだった。彼のかじっていたオレンジは床に落ち、開け放したドアから廊下へと転がっていった。
「何をやっているんだい、アンリは」
通りかかったデュラックが、オレンジを拾い上げた。デュラックは、アルブラートの合格後、4日間ほどベルギーに出掛けていた。アリは、「ムッチュ、ムッチュ(ムッシュー)」と言いながら、今度はデュラックの方に気を取られ、そちらにヨチヨチ歩いて行った。
デュラックは、アリを抱き上げると、、アルブラートにヴァイオリンを持って自分の部屋に来るように言った。アリは、デュラックの前では、たいてい大人しくしていた。
「もう入学式まで2週間だからね。ラロはだいぶマスターしただろう。一度弾いてみてごらん」
アルブラートは第一楽章を演奏して見せた。音色の艶に一段と磨きがかかり、重厚で深みのある響きが部屋中を満たした。デュラックは、最初の出だしを、もう少し重々しく弾く方がいいと言ったが、満足のいく出来栄えだと喜んだ。
「ブリュッセル音楽院での赴任手続きや、滞在する家のことで手間がかかったが、知り合いの教授の家に居候させてもらうことになってね―ところでアンリは、さっきなぜ絨毯に寝転んだりしてたんだい」
「その―僕が―絨毯に寝転んでいたので、その真似なんです」
「君が絨毯に?絨毯は寝転ぶ場所じゃないだろう。マリーが毎日クリーナーをかけてくれているが、すぐ汚れてしまうじゃないか」
アルブラートは、義父のザキリスから言われたことを説明した。
「父は、フランス人のヴェールを纏いながら、パレスチナ人であることを忘れてはならないと、そう教えてくれたんです―僕には、パレスチナ人であることを一番思い出させてくれるのは、15の夏まで育った難民キャンプでした。キャンプでは、砂漠やオアシスの遺跡の中に絨毯を敷いて、そこで寝起きをしていました......辛く、貧しく、恐怖に満ちた生活でしたが、自分を偽らないで済むという幸福感もありました―それで、あの時の感覚を思い出そうと、敢えて絨毯に寝転んでみたんです」
デュラックは、両手を組んで彼の話を聞いていたが、少し安心したように言った。「そうか―それじゃ、君は自分がアラブであることを肯定しながら、パリで生活しようと、そう考えが変わったんだね。いいことだ。誰しも、自分が何者であるかを忘れて生きることは不可能なんだから」
彼は、書棚に近づくと、ある本を指差した。
「ほら、ここに『ヨーロッパ後期ロマン派音楽大全:M.j.ユベール著』というのがあるだろう。でも、君は音楽理論の参考書として、オジェの『ヨーロッパ19世紀ロマン派音楽理論』を選んだ。何故こちらを?」
「特に理由は―単純なことです。音楽理論を学ぶなら、タイトルにそう書かれた本が最適だと思ったからです」
「なるほどね。それで、たまたまこちらの本を引き抜いて、この写真を見たんだろう―君は、もう感づいているんじゃないのか。この写真が、私の幼少時代だと」
アルブラートは、急に例のアルジェリアの写真の話を持ち出されて、躊躇っていたが、しばらく考えた後、黙って頷いた。
「私は、君が『アラブの血を捨てる』とまで言っていたから、自分からこのことは打ち明けなかったんだ。でも、今なら言える。私たちは、同胞だと―私は、君を教授会で弁護する際、君のことは『ギリシャ系フランス人だ』と言った。でも、あの学院の東洋人に対する偏見を打ち破りたい―そう思って、私の出生を教授たちの前で打ち明けた。
アルジェリア人をフランス人は長い間植民地支配して来たし、アラブを『野蛮人』と軽蔑している。私は、彼らが軽蔑する人種でも、立派に演奏家として独立できる―それを証明したんだ。だから、これは二重の勝利だよ。植民地支配への勝利、そして東洋人差別への勝利というわけだ」
アルブラートは、デュラックの言葉には、何かを覆い隠そうとしている印象を受けた。今まで、20年間も音楽院で教えながら、他人には明かさなかったであろうアルジェリア・アラブの生まれを、何故今になって公にしたのかと訝ったが、やはりザキリスに否定された自分の憶測は正しかったのではないか、と考えた。
俺の不合格を弁護する教授会で、わざわざ言わなければ分からない出生を、何の理由もなしに話してしまうわけがない―きっと、先生は、俺の身元を周囲から訊かれて、「ギリシャ系フランス人だ」と強調したんだ......それでも疑念を残さないように、教授達の注意を自分に向けようと、アルジェ出身だと話したんだろう......
彼は、デュラックにブリュッセル音楽院教授の仕事があることは、事実なのだと認めたが、普段から「君をパリ音楽院で直接教える日が待ち遠しい」と言っていたことを思うと、恩師が結局、アラブとの混血だということで辞職を促されたのだと思い至り、申し訳ない気持ちになった。
だがザキリスの言った通り、相手が話さないことを詮索しない方がいいのだと考え、何も尋ねはしなかった。
「先生は......勇気があるんですね―僕は、自分ではアラブであることを認めても、このパリで、他人にそのことは打ち明けられません―」
「いや、勇気ではないよ。ベルギーに行く前に、東洋人を差別する者たちに、アラブとの混血であっても、多くの業績を残すことができる、その証を一度は立てることが、同胞への義務だと強く感じただけだ―君は安心して音楽院で勉強しなさい。ただ、君はアラブだとの自覚を失わなくても、音楽院ではギリシャ系フランス人なのだからね。そう振舞っていればいい」
アルブラートは、勿論だと言い、子供たちの前でもフランス人として振舞うのだと答えた。「絨毯に寝転んで、感傷に浸るのは今だけです―アリやアザゼルが2歳、3歳になったら、物心もついてくるし......僕はあの子たちには、自分がパレスチナ人であることは、絶対に言いません」
だが、パレスチナ人としての誇りを自己が維持していても、自分の子供には自己の出生を誤魔化していては、己の文化を伝える者もいなくなる―そう彼は思った。それでも、アルブラートには、決して真実を明かすことはできない理由があった。それは、難民であったために捕虜となり、そして、自ら母を殺害してしまったことだった。それらすべてを、もしあの碧水晶でアリが知ったなら―
彼は、身震いし、改めて、あの碧水晶の力を恐ろしく感じた。
「君が自分の出生を、子供たちに言うかどうかは君の自由だ。私は、最初は息子のアンリに、アルジェ出身であることを隠していた。だが、あの子はリセに入ると、縮れた黒い髪や黒い目をからかわれ、アラブ人だといじめられた。だから、あの子が10歳の時、私は初めてあの子にすべてを話したよ」
アルブラートは黙って、師の方を見つめた。そして、息子のアリを見た。
先生はそれでいい......だって何も後ろめたい、恐ろしい過去などないんだから―でも、俺はアリに「あのこと」を絶対に知られたくない......話すことさえ―それを考えただけで―苦しいんだから......!
数日後、ジャン・ニコラが荷物をまとめて、デュラックの家に引っ越して来た。ジャンの部屋は、アルブラートとは向かいの、白い壁紙に囲まれたすっきりと広々とした部屋で、ベッド脇の階段を昇ると、天井裏の小部屋に続いていた。そこの小窓からは、パリ市街が一望できた。
その小部屋の天井近くに、扉付きの棚を見つけたアルブラートは、ここが碧水晶の隠し場所にもってこいだとひらめいた。
引越しの初日、ジャンは、アルブラートに、ラロの『スペイン交響曲』の音合わせを音楽院のコンサートホールでやっておきたいと語った。
「まあ、リハーサルは明日と、9月1日だけでいいと思うよ。しかし、本当にこの家に来れてラッキーだったな。僕のいた寮にはグランド・ピアノもなくてね、自分の部屋にアップライトを購入して入れたら、床が抜けちゃってさ、まったくあれは悲惨だったよ」
「......床が......抜けたって?本当に?嘘だろ?」
「ホントさ!音楽院の寮は築60年で、あっちこっち補修が必要なほどオンボロなんだ。あのオンボロさは、やっぱりコンセルヴァトワールならではだね!ほら、すぐにご立派な伝統に固執するじゃないか」
こうして笑うジャンを見て、アルブラートもおかしくてたまらず、涙が出るほど笑った。そして、自分がこんなに笑ったことは生まれて初めてではないかと気がついた。ジャンは、友人の笑顔を見て、にっこりした。
「君って、普段はおとなしいけど、そうして笑うと素晴らしくチャーミングだよ。まあ、僕はそういう君が好きなんだけどね」
アルブラートは、そういえば、自分と友人になる人は、自分と異なり、話し好きで、陽気な人ばかりだと思い、あのムカールもそうだった、と亡き友人を想い浮かべた。すると、その心を読み取ったように、ジャンはこう言った。
「君が大人しくて、慎み深いところに、周囲の人は魅了されるんだと思う。僕が君と友人でいたい理由も、きっとそうさ。君みたいな素敵な人が音楽院に入学するなんて、もったいないぐらいだよ。9月からは、きっと何もかも素晴らしい日々になるだろうね」
だが、入学してからの生活が、自分の想像とは全く違った、苦難の日々となり、恐ろしい運命が待ち受けているとは、アルブラートには予想もできないことだった。
●Back to the Top of Part 22
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- 最近、読んだ本を教えて!
- 魔導師の娘 ミシェル・ペイヴァ―
- (2024-11-27 14:03:46)
-
-
-

- NARUTOが好きな人、投稿はここだって…
- duta89 link daftar terbaik dengan …
- (2024-09-11 01:49:11)
-
-
-

- この秋読んだイチオシ本・漫画
- 【中古】奪う者 奪われる者 <1−10…
- (2024-11-27 13:54:27)
-
© Rakuten Group, Inc.



