砂漠の果て(第23部「孤立」)
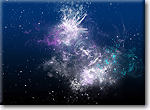
ジャン・ニコラが新しい部屋で荷解きをするのを、アルブラートは手伝った。彼は、ジャンのヴァイオリンがストラディヴァリウスであるのを見て、目を見張った。ジャンは、リュクサンヴール公園によく散歩に来ていたアルベルト・ローランから譲ってもらったのだと説明した。「アルベルト・ローランが......このパリに......?」
「そうだよ。8月初旬から来ていたんだ。10月末まで滞在して、それからスペインに帰るらしい。あの人は今はバルセローナを中心に活躍しているけれど、一箇所にじっとしていられない性分らしいんだ。どう、来週の水曜に音楽院のコンサート・ホールでローランの演奏会があるんだけれど、行かないかい」
来週の水曜というと、もう5日後だった。いきなり、5日後に祖父を生まれて初めて見ることができると聞かされて、アルブラートの胸は高鳴った。
「もちろん行くよ―それで、その......ローランと少し話とかできるのかな」
「うん、興味を持った人物とは話をする人のようだから。きっと君はローランに気に入られるに決まってるさ」
アルブラートは、それでも、会って何を話すつもりなのか、自分でも全く考えてなかった。ただ、自分の顔を見て、祖父は何かを感じるだろうかとかすかな期待を寄せていた。彼は、祖父と話は今は特にできなくても良い、ただどんな人なのかを一度確かめたいだけなのだ、と自分に言い聞かせた。彼は、ジャンの譲り受けたというストラディヴァリウスをじっと眺めていた。
「そういえば、あなたのヴァイオリンの演奏を聴いたことがなかった。ちょっとでいいから、聴いてみたいな」
ジャンは笑って、少し考えていたが、こんなものでいいならと、シベリウスのヴァイオリン協奏曲の出だしを10分ほど弾いて見せた。彼の音色は慎ましく、正確で、磨き上げられた麗しい宝玉を想わせた。アルブラートの脳裏に、半年毎に妖しげな蒼い光を放つ、例の碧水晶が輝いた。彼は、その水晶を握りしめながら、ジャンの演奏に聴き入った。
「.....僕は、あなたのようには、やっぱり弾けないな―あなたの音色は珊瑚礁のように穢れなく、絹の銀糸のように限りなく繊細だから―僕はまだまだ未熟なんだな」
「そんなことはないよ。君の実力はパリ中の人々が感嘆するほどのものだ。僕なんかより、君の演奏の方が、ずっと技巧に優れて力強く、感動的じゃないか」
ジャンはそう言いながら、ふとアルブラートが手にしている水晶玉を見やった。彼は、息を呑んでそのガラス玉を見つめた。「それ......どうした?一体どこで手に入れたんだ?」
アルブラートは、ジャンの様子の変化に感づき、驚きながらも説明した。
「ああ......これは、今年の1月に、サハラ砂漠を旅した時に、トゥアレグ族のシェリフからプレゼントされたんだ―透明だし、ちょっときれいだから、手元に置いているけれど、アリが触って落として割れたら大変だから、ジャンの屋根裏部屋に置かせてもらおうと思って―」
ジャン・ニコラの眼は深刻そうに曇り、恐ろしいものを見るかのようにすぐにその水晶から視線を反らした。彼の声は重大な警告を発するかのような響きに変わった。それは、いつもの明るいジャンの声ではなかった。
「アルベール、君―これは―ただのガラス玉じゃない。これは、過去や未来を予言する水晶だよ。僕には、今―君の過去や、半年後の未来が見えたんだ......」
それを聞いて、アルブラートはぎくりとした。
「僕の......過去―だって......?なぜ―他人のあなたにそれが......」
「この水晶の所有者は、自分の半年後の未来しか見えない。でも、15歳以下の子供がいると、本人の過去が洗いざらい見えてしまう―だが、僕が見た君の過去は、ほんの一部だ。君が、絶対に他人に知られたくないと強く思っている過去は、僕には見えない―普通は、他人が見ても、これはただのガラス玉に過ぎない―でも、僕には君のことが分かってしまうんだ」
「なぜ......ジャン、あなたが僕のことを......?」
「......これは、過去において、身近に死が迫るという恐怖を味わった者にしか、その所有者の未来と過去を見ることができないものなんだ―」
そう言うと、ジャンは、沈鬱な表情になり、まだ開けていない段ボールの上に座り込み、何かを言おうとしつつ、首を振っていたが、やがて静かな声で呟くように自分の幼年時代を語り出した。
「僕はまだ5歳の頃―両親と共に、パリでゲシュタポに捕まって、ビルケナウ第二強制収容所に送られた。最初の頃は、すぐに―ガス室なんかで抹殺されずに、家族棟に入ることができた。そのバラックで、同じ年頃の子供たちと出会った中で、5歳年上の、イェシヴァルという少年が、その水晶玉を持っていたんだ」
彼の声は次第にか細くなり、時折かすれ、咳き込んだ。
「収容者たちは、所持品なんか許されない。でも、そのイェシヴァル―僕らはシーヴァと呼んだけれど―シーヴァは、不思議な子で、看守が見回りに来ない夜の9時以降は、手の中から、魔法のようにその水晶を取り出して、僕らに見せた。万が一、看守が入って来た時は、その水晶はシーヴァの手の中で消えてしまった―それで、僕は、彼から、自分の未来を2度ほど見せてもらったんだよ」
ジャンは、アルブラートの水晶を見ないように、床に視線を落としつつ、沈んだ声で話し続けた。
「シーヴァには、父親しかいなかった。その父親も、収容されて、1ヶ月後に、別の収容所に移されてしまった。彼の未来も、僕らはその水晶で見ることができた。彼は、1年以内に、ビルケナウ第一収容所......アウシュヴィッツに移されて、そこで伝染病に罹り、ガス室に送られる運命だった。僕らはそれを見て、きっと自分もそうなるだろうと、怖ろしくてたまらなかった―
それから、シーヴァの水晶には、まず僕の父と妹の未来が映った。父は、3ヶ月後に第一収容所に強制労働に駆り出され、妹のローザは、10日後にその第二収容所のガス室に送られて殺される―そして、水晶の予言は現実となった。それから、僕はシーヴァのことが厭になって、しばらく口をきかなくなったよ」
アルブラートは、ジャンの幼少時代の記憶の恐怖に耳を傾けているうちに、不思議なことに、彼の恐怖がある種の快感となって、自分の意識の中に根付くのを感じた。今、アルブラートの中には、もう一人の自分がいた。
そうだ......俺たちパレスチナ人を殺戮してまで、自分の国を築いたユダヤ人だからさ―苦しんで、肉親を失うぐらいの過酷な過去があって当然なんだ......ユダヤ人は、皆、過去の恐怖に一生苦しめばいい―
「...僕もアウシュビッツに送られて―シーヴァと同じ日に貨物列車に閉じ込められて運搬された.....シーヴァは僕に、水晶玉のことを謝って来た。『もう二度と君にはあんなもの、見せないから―僕はガス室で殺されるけれど、君はソ連軍に助けられて、将来は立派な音楽家になれるから。これ、本当だよ』と言って来たんだ―
彼は、収容所について間もなく、伝染病に罹り、病棟に隔離された。病棟と言っても、不潔な馬小屋以下のような所さ......僕は、彼に会いたくて、看守の目を盗んで、隣の敷地の網目に穴を開けて、夜、病棟に行った。そこで見た彼は、板に寝かされていて、骨だらけだったよ―シーヴァは、『僕は明日、ガス室で抹殺された後、焼却されるけど―10年後に生まれ変わる。パリで君ときっと再会できるから、悲しまないで』―これが最期の言葉だったな......
その頃には、収容所のあちこちで、餓死した人や、焼却された人々の遺体が山のように積まれてあった―人間っていうのは、幸いなことに、そんな恐ろしい光景にも、感覚が麻痺して、何とも感じなくなるんだ」
これを聞いた時、アルブラートは、自分自身、16歳の時に、そのような感覚が自分にも備わって、人の死が平気になったことを思い出した。
そうだった......俺もそうだった......ああやって、人間の遺体が平気になったから―母さんを......ジャンは何も悪いことをしていない―でも、この俺は、自らこの手を血に染めて―平然としていられたじゃないか......!
こう思った瞬間、彼は、自分の中にいたユダヤ人を呪う悪魔のような心が瓦解し、また、通常の自分もが崩れ去り、とても平静な心でいられなくなった。
彼は水晶玉を段ボールの上に置くと、ジャンの白いピアノのそばに座り込んだ。いつもの異様な寒気と震えが起こりそうだったが、その発作を、楽器に触れることで抑えようとした。
ジャンは、気分が悪そうな友人を見て、自分が先程水晶に見た、アルブラートの過去を思い起こした。ほんの5秒ずつ、3つの場面が見えた。まだ12歳ほどのアルブラートと、とても美しい女性とが二人で狭いテントの中にいる様子、どこかのホテルのサロンで、彼がカーヌーンを弾いている姿、そして、立派な古代神殿の跡に佇む黒いヴェールを被った、まだうら若いきれいな娘と彼が笑いながら話をしている姿だった。
あの最初の美しい女性は、アルベールによく似ていた―彼の母親なのかも知れない......そしてあの神殿前の娘は、テロで亡くなった彼の妻なのかも知れない......遺体の話なんかして、苦しく嫌な記憶を呼び覚ましてしまったのか―悪いことをしてしまったな......
ジャンは、友人が難民であったことをつい忘れて、無神経なことを言ったと深く反省した。難民であったがゆえに、イスラエル軍の捕虜になったことをも考慮に入れればよかったのだ、そう思った。
「ごめん―君に辛い思いをさせてしまって......でも僕はソ連軍の救出後、音楽との出会いで、心が洗われるような心地がして―」
「いいんだ......あなたの話で気分が悪くなったんじゃない―それで―そのシーヴァとは再会できたのかい」
ジャンは、話を続けるのを躊躇っていたが、過去の糸を手繰り寄せるように考えながら、慎重に話を始めた。
「......僕は17歳の時、まだパリの公立音楽院に通っていたんだ。もう8年も前に―学校帰りに、5歳ほど年上の青年がカフェで急に声をかけてきた。その人は、『僕を覚えているだろう。イェシヴァル・キルマーだよ。昔、水晶を見せたシーヴァだ。僕は、昔、収容所で一旦死んだ。でも、生まれ変わりではなく、僕そのものが蘇ったんだ』―そう言って、もう二度と暗い未来は映らないと、例の水晶玉を僕にまた譲ったんだ―
シーヴァと名乗る青年は、確かに12歳の頃のシーヴァの面影があった。僕は、一旦命を絶たれた人間が蘇るなど、とても信じられなくてね......だから薄気味悪かったよ。でも結局、その頃はコンセルヴァトワールに入ることを夢見ていたから、『もう二度と暗い未来は見えない。音楽家として成功する姿だけが見える』―そう言う相手の言葉に魅せられて、その水晶玉を受け取ったんだ。でも、もし所有者の未来に災厄が起これば、水晶玉は青く光る前に、まず黒く濁り始めるとも聞いた。それで―結局、一旦譲り受けたものの、そんな魔力を持った物を持つのは嫌で......パリの雑貨屋に売ってしまった」
ここまで話すと、ジャン・ニコラは、アルブラートが段ボールに置いたその水晶玉にちらりと目をやった。
「シーヴァは、自分の住所のメモを僕に渡して、別れた。でも僕が、そのアパルトマンを数日後、訪ねた時には、『イェシヴァル・キルマー』なんて名の人間は、最初から住んでいないことが分かったんだ......あの時出会った青年は、一体何者だったんだろうか―今でも、それを思うと、ぞっとしないね」
アルブラートは、何とはなしに、死後もムカールやアイシャの幻影に会い、話をしたことを思い、そんなことも有り得るのではないかと考えたが、そのことは話さなかった。
「その―僕がパリの雑貨屋に売った水晶玉は、世界でただ一つしかない、イェシヴァル・キルマーの水晶玉なんだ。それを、トルコの商人が土産物として仕入れ、砂漠の部族がそれを買い、そして君の手に渡ったんだ―不思議な因縁だね―それで、アルベール、君は半年後は、音楽院のトップとして活躍することは、僕はもう確認したから―安心して持っていても、きっと大丈夫さ」
「きっと......?」
「まあ、人の未来なんて、誰でも分からないものだろう、普通はね。だから、その水晶玉は、必要ないと言えば、それまでなんだ―でも、一旦、数か月所有してしまった者は、その不思議な力いかんにかかわらず、その水晶玉を手放したくなくなるそうなんだ―アルベール、そうなんだろう?」
アルブラートはしばらく黙っていたが、ジャンの言う通り、一見、ただの平凡なガラス玉にしか見えないのに、この水晶を身近に置いておきたい気持ちになっている自分を訝った。「それは、あなたの言う通りだ―でも、ジャンが嫌っているものを、あなたの屋根裏部屋に置くことは止めるよ。僕の自室のクローゼットの奥に、アンリに分からないように、隠しておく―それでいいかな」
ジャンはしばらく何か考えにふけっている様子だった。ジャンの見事な青い目と、アザゼルよりも鮮やかな輝く金髪を眺めながら、アルブラートは、なぜこの人にはこうまで物静かな清潔な美しさが備わっているのだろうと感じ入った。ジャン・ニコラは、「半年後は君は音楽院でトップで活躍している」とだけアルブラートに告げたことを後悔していた。
僕が見たのは―彼が常にトップであるがために起こる苦しみだった......そして―「あのこと」......それは必ず1年以内に起きてしまう......なぜ僕に彼の1年後が見えたのか分からない―でも、「あのこと」は止めることは出来ないんだ......けれども、必ず彼は救われる―そう信じていないと、とても彼とは暮らせないじゃないか―
ジャンは、段ボールに座り込んだままだったが、友人を見上げると、微笑んで、うなずいた。「ああ......うん、そうだね―クローゼットの奥なら、アンリには分からないさ。そうだ、君、さっき、アンリのことを『アリ』と言っただろう。『アリ』があの子の本名なんだね。僕たち、知り合って、まだ4ヵ月にも満たないけれど、僕は君の本名を知らなかった。教えてくれるかい?」
アルブラートは、フランスに来て、デュラック以外の人に自分の本名を教えるのは初めてだった。彼は、しばらく躊躇したが、「アラブ人である本来の自己を忘れてはならない」とのザキリスの言葉を思い返し、思い切って、ジャンに告げた。
「......『アルブラート』と言うんだ。ここだけの話だけれど...」
ジャンは頷いた。「良かったら、姓も教えてくれる?」
アルブラートは、一瞬、ベト・シェアン収容所での看守との会話を思い出し、嫌な気分になったが、それを振り払い、静かな口調で答えた。
「.....『アル・ハシム』―というんだ」
「そう、『アル・ハシム』か.....君、もしかして王族の末裔?」
アルブラートは、ジャンの屈託のない応答にやや緊張した気持ちがほぐれた。彼は少し笑いながら、説明した。「いや、まさか.....父のバシールは、カーヌーンとウードの演奏家で......先祖代々、サウジアラビアのハシム家という王族の、名もないお抱え楽師だったらしいんだ―たまたま、その王家から、『ハシム』という名を授かったらしい。本当かどうか怪しいけれどね」
「でも素敵なエピソードじゃないか。『アルブラート』って綺麗な響きの名前だね。君って、お父さん譲りなんじゃないかな。さっき、水晶で、君がどこかのサロンでカーヌーンを弾いている姿を見たんだけれど―いつか、その楽器を弾いて聴かせてくれるかい?」
アルブラートは、ジャンの言葉に、以前はサロンのアラブ楽器の演奏をしていたことを思い出した。そして、そのわずか4年から昨年までの経験が、随分遠い昔になってしまったように感じた。
「その......このパリには、西洋音楽を勉強しに来たものだから......
申し訳ないけれど―当分―アラブ音楽から離れたくて......
だから、あなたには聴いてもらいたいけれど―ごめん。駄目なんだ―」
ジャンは拍子抜けしたように残念がったが、分かったと言って、謝った。そして、思い出したように、こう付け加えた。
「......さっきのシーヴァの水晶のことだけれど―彼とパリで再会した8年前、はばからず彼が断言したことがあったんだ。『今、ユダヤ人は、パレスチナの地にイスラエルを建国し、パレスチナ・アラブを苦しめ、生き地獄に突き落とし続けている―昔、ナチスがユダヤ人にしたことと同じことを、今度は罪のないパレスチナ人に繰り返している―とても許せない行為だ。世界中が、両者が平和に共存することを望んでいるが、なかなか実現しない。
でも、僕はイスラエルが折れて、パレスチナ人に幸福をもたらす日が70年後には訪れることは分かっているんだ―それは、イスラエルを支えてきた米国経済が力を失う時なんだ』―こう、シーヴァを名乗る青年は語ったんだ。それが本当なら―彼は、真の預言者ではないかと、僕は信じているんだよ。21世紀半ばを過ぎる前に、何らかの形で、再びあの地に平和がもたらされると―」
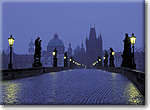
この時のジャン・ニコラの言葉は、アルブラートにとって、後半生を決定づけるほどの影響を与えたのだった。
もしシーヴァやジャンの言うことが現実に起こるのなら......俺はアリとアザゼルを連れて、ベツレヘムに帰ることができる......
70年後に90代の老人になっていても、必ず......必ず......
「もしそうなれば、僕はベツレヘムに帰って暮らしたい。イェシヴァルの預言が真実なら―今は米国は世界強大の繁栄を誇る経済大国でも、それもいつかは衰退する―そういう栄枯盛衰は昔からあることだからね。きっと、70年もしないうちに、かの地の和平は実現するさ」
アルブラートは、ジャンが自分と同じことを望んでいることを知り、深い共感を抱いた。ジャンの白いピアノは、部屋全体の白い色調と溶け込んでいたが、その白さは、彼の潔白な人柄を表現しているように感じられた。
「そのピアノだよ。そのピアノで、寮の床が抜けたのさ。黒いピアノもいいけれど、白いのがなぜか欲しかったんだ。奨学金とピアノの家庭教師で、奮発して3000フランで買ったんだ」
アルブラートは、彼が「ソ連軍に救出された後、音楽と出会って心が救われた」と先程、語ったことを思い出し、そのことを尋ねてみた。ジャンは、幼い頃に想いを馳せるような、懐かしげな表情を瞳に浮かべ、彼を見た。その眼差しは柔らかく、温かかった。ムカールの眼差しは、やはり優しかったが、人を真っ直ぐに見つめる癖には、何の遠慮もなくこちらに切り込んでくるような鋭さと高貴な気品があった。彼は、亡くなった友人を、敬愛の念で未だに深く愛していたが、ジャンの明るいが慎ましい人間性には、ムカールとは、全く異なる温もりがあると思った。
「―そうだね......あれは、僕が8歳になった頃だった。まだモスクワの療養施設にいた時、小児病棟を回って、遊び相手になってくれるセラピストの人たちが、サロンにみんなを集めて、ピアノでショパンの『ノクターン第2番』を弾いてくれたんだ。それを聴いた時は、何か明るい光に照らされたような心地になって、全身に血がさっと巡って、涙が出た......そんな経験は初めてだったんだ。僕はそれまで、人生に楽しいことなんてないと思ってたんだ。絵本を見ても、散歩をしても嬉しくない。でも、そのピアノ演奏を聴いたことで、人生が素晴らしいものに感じ始めたんだ―
その後、同じ病室で仲良しだったゼルダという少女が肺炎で急死して、施設の先生たちは悲しんで、その子のためにお葬式をした。これも、僕には初めての経験だったんだ―なぜ、たった一人の人間の死のために、お葬式なんて営むのかと驚いたよ......収容所では、多くの人々が亡くなるのは当たり前だったから―でも、僕はモスクワでの経験で、本当に人間らしい感情が戻ったんだね―これも、すべて、音楽との出会いのおかげだと思う。それから、僕は音楽家になりたいと、勉強を始めたんだ」
「お葬式」か......俺の立ち会った葬儀は―タウフィーク―アイシャの父さんと......アイシャ......ムカール......いや、ムカールのはニコシアの丘に墓碑を立てただけか......それと、俺の父さん......父さんは雪の中に埋葬した......それは誰とだったか―葬儀はそれぐらいだったっけ......?
アルブラートは、ジャンの白いピアノで、いきなりショパンの『革命』を奏で始めた。彼のタッチは鋭く、独特の冴え渡った煌きと情熱的な静寂があった。ジャンは、彼の音色が天の光となり、夜空を細かに彩る星座の輝きとなるようだと感じた。アルブラートは、最終節を何度も激しく、素早く弾きながら、何かの大きな喪失感に徐々に喉を締めつけられる感覚に苦しみ出した。
俺の立ち会った葬儀は......まだひとつあった......いや、あれは葬儀じゃなかった―何の棺も花束もなく......祈りの言葉もなかった......あれは誰の葬儀のつもりだったんだろう......?とにかく、棺の蓋をしなければ......蓋を、早く、一刻も早く......!
彼は、腕が痛むのではないかと思われるほど、最終節をいつまでも激しく弾き続けた。ジャンは、何か彼に異様さを感じ、その腕をとり、ようやく止めさせた。アルブラートは、息を切らしながら、相手を黙って見た。まるで悪夢から無理やり目覚めさせられた者のような表情だった。
「どうしたんだ......なぜそんなにピアノを弾き続けて―疲れているみたいじゃないか。引越しの片付けは、また明日僕がやるよ。少し休んだら?」
「......そう......少し休みたいんだ......ごめん。晩の食事には顔を出すから......」
アルブラートは弱々しく呟くと、ふらふらと自分の部屋に戻ったが、急に吐き気を催し、慌てて隣の客間に駆け込み、そこのバス・ルームで吐いてしまった。嘔吐物を水で流しながら、まだ残る嫌な臭いに、寒気を覚えた。客間のバス・ルームは入り口のすぐ右手に、ビニール製のカーテンで仕切ってあった。彼は、洗面台のコップに水を注ぎ、シャツの胸ポケットにあった安定剤を一気に飲み込んだが、その手の震えは止まらなかった。
いつもの発作だと思いながら、鏡に顔を映した。その顔は蒼ざめて、紙のように白かった。彼は、色白ではない自分の肌を嫌っていたが、こんなに病的な白さでは、皆が心配するだろうと思いながら、その部屋のベッドに横になった。ザキリスの言ったとおり、副作用はきつくはなかったが、妙に腹が疼いた。
ああ......!どんなに蓋をしようとしたって、もともと棺なんてなかったんだ......だって、俺は母さんの命を無理やり奪ったんだから......!まだ若くて、生きていたかった母さんの息の根を止めたんだ―俺が、この手で......!そんな俺が、母さんを弔うなんて一生できやしない!一生、一生......!
アルブラートは、こうして自らを責め苛んだ。腹痛に腹を押さえ、額に汗を滲ませつつ、苦痛に顔を歪めた。だがその時、≪自分を責めるな≫と、懐かしい声が耳元に響いた。彼が目を開けると、ベッドのすぐそばに、ムカールが静かに立ち、彼を見下ろしていた。
―アルラート、自分を責めるんじゃない。俺はまだ生きている時から、お前に「自分を責めるな」と何度も言っただろう。お前には何の罪もないんだ......それでも、お前が、お前の母さんに何とかして償いをしたいと思っているのなら、それは十分果たされている。お前はこうしてパリに来て、一流の音楽院で最優秀の成績を修めているじゃないか―お前の母さんはそれをとても喜んでいる。だから、償いはもう終わっているんだ。
「ムカール......母さんに会ったのか」
ムカールは頷くと、そばの椅子に腰掛け、足を組んだ。彼は右手で頬肘をつくと、にっこり微笑んだ。白い長袖のシャツに、黒のサスペンダーで吊るしたズボン、紺色の靴下に煤けたロシア製の古靴―4年前、サイダで初めて出会った時と同じ格好だった。
―ああ、会ったよ。立派な黒いドレスを着て、本当にきれいな人なんだな。今は、お前の父さんのバシールと暮らせて幸せだと言っていた。ただ、お前がいつまでも良心の呵責に苦しむのが可哀想でならない、と泣いていた。お前は、母さんがここに来たら、会って話ができるか。
「母さんが......ここに来る?」
―そうだ。この指輪を俺は預かっている。この指輪に、お前が詩でも手紙でもいい、何か彼女へのメッセージを書いたものを、折り畳んで結びつけ、このベッドサイドにいつでもいいから、寝る前に置いておけよ。そしたら、彼女は時々お前に会いに来れるようになる。俺の遺書にお前は自分の詩を結びつけて、納棺しただろう―だから、俺はお前にこうして会いに来れるんだ。
「ムカール......!でも、俺は母さんと会うのが怖いんだ......
それ以前に―それ以前に―自分のしたことが永遠に許せない―どんなに音楽で成功したって、母さんの生の喜びを断ち切った事実は消えない......
俺も、同じように......流血の苦しみにもがかないと駄目なんだ......ムカール......」
だがムカールは、それは無理だというかのように、首を振り、そうして姿をすっと消した。アルブラートは、安定剤が効き出したのか、うとうととまどろみ始めた。そんな彼の姿を、客間のドアの隙間から、アザゼルとアリが覗いていた。二人は、この珍しい光景を、ジャンに伝えようと、走り出した。
アザゼルは、ビッグ・ニュースを手にしたかのように、ピアノのそばで荷物を整理していたジャンに飛びついた。「ジャン!ジャン!今日からいっしょ!うれしい!」
ジャンは、友人のことを心配していたが、アザゼルが小さな白いバラのように愛らしく、思わず彼女を抱きしめ、微笑んだ。
「そう、今日から一緒だよ、ちっちゃなお姫様、王子様。ねえ、お父様はどうしているの?」アザゼルは、にこにこしながら、ジャンの手を握り締め、首をかしげた。
「ええとね、お客様なの。ムカール、ムカールって」
「お客様?今、お部屋にその人がいるの?」
「そう。でもね、すうって消えちゃった」
「......消えちゃった?お客様が?」
ジャンは不思議に思い、向かいの客間をそっと覗いた。部屋にはアルブラートが一人、ベッドで休んでいた。彼は、子供の見たことは、何らかの真実に違いないと思い、たまたま通りかかったマリーに尋ねた。
「あの、今日はどなたかお客様がおられるのですか?」
「いいえ、どなたも。ニコラ様以外、今日は......なぜですの?」
「いや、アルベールが一人で客間に寝ているんですが、子供たちが―今、客間に人がいたと言うので―ムカールという人がいたけれども......その......『消えちゃった』と言うものですから」
マリーは、それを聞いて蒼ざめた。彼女は、洗濯物を抱えていたが、子供たちのいるジャンの部屋に入り、後ろ手でドアをそっと閉めた。マリーは、言ってはならないことを恐る恐る口にするように、声を潜めた。「その―『ムカール』という方は......アデール様の本当のお父様なのです。でも、その方は―2年前にカイロで亡くなられたそうです」
それを聞いて、ジャンは、「アデールは亡くなったアルメニア人の友人の娘だ」とのアルブラートの言葉を思い出した。その友人の魂が、たまたまアルブラートに会いに来たのだ―しかし、自分もシーヴァの幻らしき人物と出会ったのだから、そう不思議なことでもないかもしれない―そう思った。だが、マリーにはそのような話はとてつもなく恐ろしいことのように感ぜられるようだった。マリーは声を震わせながら、怖気ついた子供のように、今にも泣き出しそうだった。
「.....アルベール様は、時折、あのような.....苦しげな発作を起こします......あの方は、過去の苦しみが今もなお続いておられるようで.....よくは存じませんが―とても繊細な方ですから.....でも、申し訳ございません、私.....私は.....あの、こういう話は苦手で―夜は怖くて眠れなくなってしまいますから.....」
ジャンは、慌てて丁寧に詫びた。「いいえ、僕が悪いんです。子供の空想だったのかもしれないのに、真に受けて奇妙な話をあなたにしたりして、本当に無神経というか―子供っぽいというか―これからいろいろとお世話になるという時に、申し訳ないのは僕の方です。僕はこんなだから、すぐに女性にふられてしまうんですね」
マリーは意外そうな表情になり、ジャンをまじまじと見つめた後、少し顔を赤らめたが、夕食の支度をすると言って、階下に降りて行った。
アルブラートは、目が覚めると、しばらくぼんやりとしていたが、慌てて体を起こし、ベッドサイドを見た。果たしてそこには、ムカールが置いていった、母の指輪があった。それは、彼が幼い時から見慣れていた、母の結婚指輪だった。古びた銀色の輪に、細かなバラの紋様が刻み込まれていた。彼は、とても母に手紙を書く気になれず、この遺品をどうしたものかと懊悩した。しばらく悩んだ末に、とりあえず、カイロの義父に預かってもらうことに決めたのだった。
午後の7時に、彼が居間に降りて行くと、ジャンがドヴォルザークを弾きながら、ピアノのそばにいる子供たちの相手をしていた。彼は、先ほどの「不思議な客」の話は避けようと、明日の予定のことをアルブラートに話そうとした。彼が口を開くと同時に、アルブラートも話を切り出した。「明日のリハーサルは―」
二人同時に同じ言葉を発し、思わずアルブラートは笑い出した。ジャンは、友人が笑ってくれたことに安心した。彼は、いつものように明るい口調で説明した。「『ヴァイオリン協奏曲』だろ、ラロの。いつものコンサートホールでね、午後の3時から。指揮は、明日はデュトワ教授だけれど、9月5日の最終リハーサルは僕が指揮だから。それで大丈夫?体調はいい?」
アルブラートはにっこりしながら頷き、食卓につくとアリを膝に抱いた。その日は、デュラックはベルギーにおり、留守だったが、ジャンの転居祝いを二人で行った。翌日、リハーサルは無事に終わった。ジャンは、アルブラートの鮮やかな演奏に改めて感心し、昨日の具合の悪さが嘘のようだと感じた。
リハーサル会場には、学内関係者数名と、一般市民が10名ほど観客席にいた。その客の中に、黒いシルクハットに、黒いサングラス、黒いコートといった格好のかなり年配の男性がいた。デュトワ教授は、その客に目礼したが、その男はやや頷くと、会場を立ち去った。
教授は、訝しげにその客を見守っていたアルブラートに、苦笑いしながら説明した。「あの人は、君の最終リハーサルを行う9月5日に、このホールで演奏をするヴァイオリニストでね。かの有名なアルベルト・ローラン氏だ。曲目は―」
「『シベリウス ヴァイオリン協奏曲』ですよ、先生」
ジャンがそばから助太刀した。教授は思い出したように話を続けた。「そう、君のリハーサルは5日の午前11時、あの人の演奏会は、午後の2時からだっけな。君は、ローラン氏を知っている?」
アルブラートはすぐ目の前に祖父がいたことに、戸惑いを隠せなかったが、やっとのことで答えた。「え.....ええ。少しは―」
「ちょっと偏屈者という印象だったかな。それで、『ノートルダムの怪物』なんてあだ名がついているんだ。だが打ち解けてみれば、実に素晴らしい人でね、真の芸術家というのはああいう人をいうのだね」
「なぜ『ノートルダムの怪物』なんですか?」
ジャンが教授と入れ替わるように説明した。「あの人はパリに来ると、必ずノートルダム寺院に行って、祈りを捧げる。その後、鐘楼までの階段を上がり、見晴台で気晴らしに数曲、お気に入りの曲を弾くんだ。そこからの響きは美しくてね、パリ中の人が聴き入ってしまう。ただ、あの寺院の鐘楼には、有名なシメールと呼ばれる幻獣の彫刻がずらりと並んでいるんでね。それと、あの人の演奏の鬼才ぶりとが混合して、そんなあだ名がついたんだ。でもローランは、そのあだ名を随分好んでいるようだよ」
シメール......怪獣か―空想上の神秘な存在―そのイリュージョン―幻の如きイマージュが、ローランの演奏と合致するのか―でもこの俺はローランの孫であっても、怪獣ならぬ本当の怪物だな......
親の心の臓に弾丸を撃ち込み、血しぶきを浴びて喜ぶ鬼......!
アルブラートの腕は震え、膝は痛み、眩暈がしそうだった。だが彼は、ジャンの朗らかな声に、我に返った。「デュトワ先生、アルベールはローランと、コンサートの日に話ができたらと希望していたんですが。ねえ、そうだったろう、アルベール?」
「ああ、アルベール、あの人と話したいのかい。それなら、私からローラン氏に直接電話を滞在先のホテルにしておくよ。大丈夫、そういう申し出はローランに対して滅多にないことなんだ。何しろ高名な音楽家だが、どこか神秘的というか、現実離れしたような風の人だから―おいそれと話をしたくても、申し出をする人はほとんどいなくってね」
その日の晩9時頃、デュトワ教授からアルブラートに電話があった。「アルベール、ローラン氏は5日の午後7時半に、グラン・ロワイヤルホテルの5012室で君を待つとの返事だ。ジャン・ニコラも同伴してほしいとのことだった。何か君に訊きたいことがあるらしい」
その伝言は、アルブラートに不安と恐れをもたらした。
何だろう―訊きたいことだって......?もし―母さんのことだったら―いや、それ以外にないじゃないか......?じゃあ、ローランの方でも、俺の演奏を聴きながら俺を見て―何か分かったのか......?
彼は、電話の後、自室に戻ると、まだカイロに送っていなかった母の唯一の遺品である、薔薇の文様が彫り刻まれた指輪を、机の横のキャビネットの引き出しから取り出した。それはムカールが彼の母から預かっていたという指輪だった。銀色に光り、ところどころ蒼く錆びて剥げかかった指輪が、今この現世にあることが信じ難く、また恐ろしかった。アルブラートは、この指輪を、ローランに会う時、母の話題になった時、見せようと思った。
この指輪を見せれば、自然と「母は病死した」という話の流れができるだろう、と考えたのだった。彼は、そんなことをしてまで、祖父である人に嘘をつく自分が嫌だった。だが、真実を言う羽目になったら、自分は破滅だ―そう感じた。
他にも、「もしローランが難民キャンプのことを尋ねたら」とか「もし自分のヨーロッパに来る以前のことを訊かれたら」など、さまざまな不安が頭をよぎったが、それ以上のことを考えるのが苦しかった。アルブラートは、その指輪を、5日に着用するコンサート用の上着のポケットに、無理やり押し込んでしまった。

5日の朝は、アルブラートにとって落ち着かなかった。入学式コンサートの最終リハーサルに、母の指輪などを服のポケットに入れて、果たして演奏などできるだろうか、と心配でたまらなかった。何度も何度も、指輪をキャビネットに戻そうと考えた。だが結果として、「祖父と会うのなら、真実は告げまい。母の死の理由も言うまい、ただこの指輪が遺品である―そのことをローランに示そう。自分がローランの孫だという証を示すために、これは必要なのだ」と思い至った。
午前11時定刻に、彼のリハーサルは始まった。アルブラートは、演奏しながら、ジャンの指揮がいつもと違い、躍動感とスピードに溢れていると感じた。彼の指揮のもとで演奏することは、アルブラートにとって、自然な波のうねりに身を任せるような快感だった。演奏が終わると、場内に割れんばかりの拍手が響いた。ちらりと客席に目をやると、最後列に、ローランの姿があった。
アルブラートはジャンに少し驚きながらささやいた。「今日の指揮はいつもの君の指揮とは違うね―随分と活気に満ちて―でも僕には、とても合っているというか、演奏しやすかった」
「それは、君の演奏法のおかげさ。この間、デュトワ教授の指揮で演奏した時の、君のスピード感を僕は学んだんだ。君の音色を最大限に生かす指揮をしなければ、と思ってね」
デュトワ教授は、にこにこしながら、ジャン・ニコラの肩を叩いた。
「ジャン、入学式のアルブラートの指揮は君に任すよ。君の指揮法はかなり大胆でダイナミックに変貌したものだね。ローラン氏も、私の指揮より、ジャンの指揮が良いとおっしゃっているほどだからね」
アルブラートは、ハッとして客席を見たが、そこにはもうローランの姿はなかった。彼は、祖父が自分のすべてを考え、注意深く観察し、見抜いているのだと感じ、何かしら嬉しいような、怖いような気がした。
午後2時からは、ローランのヴァイオリンで『シベリウス ヴァイオリン協奏曲』が始まった。そこでアルブラートは、初めて祖父の顔を見た。祖父の眼は深い緑色で、鼻は鷲鼻であり、強くうねる黒々とした髪が肩まで伸び、そしてたっぷりとした黒い口髭をたくわえていた。意志の強そうな太い眉の下の、窪んだ大きな眼は、時折、険しさと厳しさと不思議な哀しさを見せた。全体に背が高く、孤独な印象があった。だが若々しく、とても63歳には見えなかった。
あの意志の強そうな、それでいて哀しそうな表情は......母さんの表情だな―やっぱりあの人は―母さんの父親なんだ......
アルブラートは、ローランの顔を見るのが辛く、目をつぶった。ローランの演奏は、険しそうな表情とは裏腹に、繊細で、煌く細い絹糸のようであり、且つ上質なベルベットの布触りを想わせる、しなやかで力強い音色であった。その音色の中には、アルブラートには到底、到達しえない遙かな高みと計算され尽くした完璧さがあり、それらが有無を言わせぬ圧倒さで彼に迫ってくるのだった。
彼は、こんな立派な人が、たとえ己の祖父だといっても、とても話などできない、力量や経験の面からして、自分を小さな恥ずべき存在だと感じ、なぜ今夜会う約束などしたのかと戸惑った。ジャン・ニコラは、今夜二人してローランに会えることにわくわくしていた。そんな友人を見ると、逆にアルブラートの心配は募った。
「ジャン―僕は間違っていたかもしれない......あんなすごい人と会うだなんて、僕にはそんな度胸がないよ」
ジャン・ニコラは面食らったような顔をして彼をじっと見た。「何言っているんだい?君ほど彼に会うのに相応しい人は滅多にいないのにさ」
アルブラートはコンサートが終わると家に戻った。デュラックはまだ数日、ベルギーに滞在する予定で、留守だった。彼は、午後6時にマリーの用意してくれた夕食も、あまり喉を通らず、食後、演奏時と同じ礼服にしぶしぶ着替えた。この服のポケットに、例の指輪があることも、彼には重荷だった。ジャンは、彼の沈んだ様子を不思議に思ったが、7時になると、タクシーを呼んだ。
タクシーは、一路「ロテル・ド・グラン・ロワイヤル」を目指して走った。7時15分には、二人は既に目的のホテルのロビーを歩いていた。ジャンが、フロントに「5012号室で、7時半にローラン氏にお会いする約束がある」と告げた。二人は赤い金縁の椅子が置かれた待合室で10分ほど待ったが、間もなくボーイが来て、彼らを5012号室に案内した。
「待っていたよ、ジャン・ニコラ、アルベール・ザキリス」
アルブラートの目の前には、黒ズボンに黒いタートルネックを着たローランが、白いソファーに座って待っていた。掻き揚げられた漆黒の髪の下の、真っ直ぐな額には、深い皺が刻まれていた。コンサート会場では濃く見えた緑色の瞳が、今はやや透明に澄んでいた。その瞳は、明らかに関心は「アルベール」にあることを語っていた。
アルブラートは、おどおどしながら、挨拶をしたが、なぜか舌がうまく回らず、アラブ訛りが出てしまっていた。だが自分でもそれに気がつかなかった。
「あの......今夜は―お...お目にかかれて―その...光栄に思います」
ローランは、その挨拶に苦笑した。「まあ、そんな堅苦しい挨拶は抜きにして、と―君が私に会いたい、話をしたいという目的は別にあるんだろう?」
アルブラートが押し黙ってうつむいていると、ローランは優しげに話しかけた。
「私はね、あまり人と話す機会がこのパリではない。私はどこか奇妙な風采をしている―そう、魔術師のようなイメージだ。実際、そう新聞に書かれたことがある。私は、ロマ(ジプシー)とアルメニア人の混血だ。このヨーロッパでは、ある意味、異端者のような印象が人々の中にあるんだ。
だが、私は一介のヴァイオリニストだ。君も、そう思って私を見てくれないかね。私は、この夏から、リュクサンブール公園や、あの音楽院のリハーサルやコンサートで、ずっと君を見てきた。君のことは、デュトワ教授に訊いたが、何でもギリシャ系で、西洋音楽をほんの数か月でマスターし、入学試験も首席合格だそうだね。だが私は、君の別の顔を知っているんだ」
ジャンは意外な表情で、ローランに問い返した。「アルベールの別の顔―それは何ですか」
ローランは、ジャンを見ずに、硬直したように無言の若者に見入った。「私は、BBC 発売のアラブ音楽のレコードを3枚持っている。その演奏者の名は、『アルブラート・アル・ハシム』で、紹介された写真はすべて、アルベール、君の顔なんだ」
事情を知るジャンは、合点がいったように、アルブラートに視線を向けたが、当の本人は、どう答えたら良いのか分からず、相変わらず口をつぐんでいた。
「それで、私の中で君に対する3つの感情が生まれた。この謎に対する疑問、そして君の出身に対する期待、またこの私に対する救い、この3つだ。まずは、謎解きをお願いしても良いかね」
アルブラートは、ローランと対峙する際の真の不安がついに具現化したことに、思わず身震いした。彼は、しばらく目を閉じていたが、真っ直ぐにローランを見つめると、答えた。「何も疑問に思わなくても結構です―そのジャケットの写真と名前は......この僕なんですから」
ローランは答えは分かっていたかのように、満足そうに微笑みを浮かべた。
「それでは、レコード・ジャケットに掲載された名前が君の本名だと、そう解釈して良いのかね?君はそうなると、紛れもなくアラブ人であるということになるが、そうなんだね?」
アルブラートは、戸惑いながらも、大人しそうに頷いた。ローランは、ジャン・ニコラを今度は見つめながら、落ち着いた、深みのある声で話を続けた。
「デュトワ教授の話では、君は今年度、ヴァイオリン科とピアノ科を首席で卒業したそうだね。こちらのアルブラートは首席入学、そして二人はデュラック氏の家に共に下宿し、仲が良い。また二人はユダヤ人とアラブ人である―こういう事実は、あの音楽院そして世間では、却って二人を孤立させてしまうだろう」
ジャンは驚いてローランに問いかけた。「僕たちが孤立?なぜです」
「音楽の世界では、スポーツや芸能界と同じで、実力のある者たちを妬んだり謗ったり、何らかの罠に陥れる人間がいる。それにイスラエルは今、アラブ人たち、特にパレスチナ人を苦しめ、難民化させている。私から見れば、君たちほど理想的な若き音楽家たちはいないのだが、世の中は偏見と中傷に満ちているものだからね」
ジャンは青い目をしばたかせ、しばらく考え込んでいたが、問題を整理しながら、こう答えた。
「要するに、あなたのおっしゃることに従えば、二つの難点があるわけですね。僕たち二人が、音楽院で共に首席であるということ、そして敵対すべきユダヤ人とアラブ人が仲が良いということ、そうでしょう?でも、首席であることに関して、何らかの中傷や妨害があったとしても、それは気にしなければ良いことです。僕が年輩である以上、もしアルベールを謗る者がいても、僕は彼を守ってやれます」
「それはそうだ、ジャン・ニコラ。そして、アルベールが、BBCレコード・ジャケットの『アルブラート』であるという事実も、それを指摘する者がいても、君が彼を守って、事実ではないと言えば、それまでの話だ。彼がアラブ人であることが分かると、パリのシオニストたちが、『ユダヤ人の敵であるアラブが共に音楽界の花であることは許しがたい』と騒いで、君の大事な親友をパリから追放しかねない―分かるだろうね」
アルブラートは、このパリまで来て、自分がアラブ人であるというだけで、世間から抹殺されるのかという冷酷な現実に慄いた。彼は、それでも、ジャンだけを頼りにし、素性を一切世間に明かさなければいいのだ、と自分に言い聞かせた。ホテルの一室に集まった3人は、数分間、無言だった。だが、ようやく、アルブラートの方から疑問を投げかけた。
「ムッシュー・ローラン。なぜ、僕の出身への期待が―あなたに対する救いになるのか......教えていただけませんか」
ローランは、改めて、アルブラートの顔を食い込むようにじっと見入ったかと思うと、深いため息をついた。
「私は、君がアラブであると、最初、リュクサンブール公園で見た時から気がついていた。だが、アラブといっても、多種多様だ。イエメン人は、エジプト人とは違う。アルジェ出身の者は、シリア人とは違う。私は、馬車であらゆる所を放浪したから、アラブ同士でも、微妙な顔立ちの違いや風俗の違いを知り尽くしている。アルブラート、君は―パレスチナ人そのものだ―そうだね?」
アルブラートは、いきなり、ローランとの対話に対する潜在的な不安に矢を射られて、一瞬、息が詰まった。「......僕は―違います......僕のどこがパレスチナ人だと......?」
「パレスチナは、古代から様々な人種が行き交う土地だった。特に古代ローマ、ギリシャ、ユダヤ、そしてアラブ人が混血している。君の顔立ちには、アラブでありながら、古代ローマ彫刻を思わせる高貴さがある。これは、パレスチナ人独特の雰囲気だ。それに、私の妻はベツレヘムのパレスチナ人だったし、娘は、やはりベツレヘムのパレスチナ人音楽家バシールと結婚した―だから、私は、パレスチナ人は、すぐ見分けがつくんだよ」
今こそが、祖父であるローランに、自分の素姓を明かし、ローランに救いをもたらすべきではないか、とアルブラートは自覚しつつも、逡巡せざるを得なかった。ローランに対し、孤独である人生に、既に死んだと思っていた肉親がいることを証明し、彼の祈りを喜びに変えるべきだ、そう理解しつつも、なかなか次の言葉が出てこなかった。
「私の娘は、21年前に『アルブラート』という名の可愛い男の子を産んだ。だが―それ以来、娘夫婦と孫の行方は分からないままなんだ」
●Back to the Top of Part 23
© Rakuten Group, Inc.






