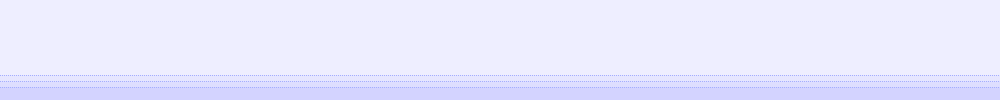未完成
……なんて意気込んでいた朝が懐かしい。現在五時間目数学、残念ながら未だ彼女に声すらかけれていない僕がいた。朝の勢いはどこへやら、絶好の機会であるお昼休みも先ほど過ぎて、この五時間目が終われば下校となってしまう。放課後と言うのもベストな状況だが、僕にはそんな気力はもう残っていなかった。そういうのを意識すると、話しかけることさえ出来なくなってしまう。
全然駄目な男、それが僕だ。大体恋なんてし慣れていないのに、いきなり朝岡さんと言うのが無謀なんだ。告白もしたことないし、もちろんされたこともない。だから付き合うなんてこともしらないし、当然彼女が何を考えているかも全然分からない。
四方八方謎だらけ。もうお手上げだった。
僕は別段格好良くない。自分で言ってて悲しいから、一応悪くもないくらいだと思っておく。中の中でど真ん中とか、それぐらいの器量だ。
それなのに相手はまるで作り話の中に出てくるような超絶美少女。こうなるともうアリVSゾウみたいなものだった。僕の負けです。勝ち目なし。
しかし、どんなにそれが無謀で身の程知らずな想いであっても僕はもう、完全に彼女に魅入られてしまっていた。勉強も無視して恋なんか知ったことかと、お気楽学生ライフを送っていたあの頃にはもう戻れない。
この好きな気持ちから逃れるのは、もう不可能なんだ。
と言うわけで、僕は気持ちを伝えるために色々チャンスを探っていた。しかしそれは探るだけで、決して体が実行に移行しないのが悩みどころだった。
もう自分、馬鹿。どうせ駄目なんだから潔くって誓ったじゃないか、ちょぅど近くに居た野良猫に。なんでそんなに意気地無しなんだよ……。
なんて頭を抱えてわしゃわしゃと髪を乱す。はたから見たら異様な熱意で数学に取り組んでいる学生に見えるだろう。なんせうんうん唸りながら頭を抱え苛立ち気に思案を繰り返しているんだから、狂気に取り憑かれた数学者のように見えるはずだ。
僕はふと意味もなくノートを睨みつけるのを止めて、その視線を隣に少しだけ移す。窓から入ってきた風に、彼女の肩まで伸びた黒髪が静かに揺れる。なめらかな白い肌に、少し端がつり上がった大きな瞳。真剣な顔で、彼女はノートに目を落としていて、細い指でシャーペンを操っていた。
この世のものとは思えない美しさ、なんて言うと大げさに言いすぎかもしれないけど、でも僕にとって彼女は人生で一番綺麗な人だった。個人的な好みもばっちりど真ん中なのかもしれない。自分の好みなんか考えた事が無いから、よく分からないが。
と、ぼぉーと夢心地で彼女の眺めていたら、突然声が降ってきた。
「おい、飛来。さっきから猛然と問題に取り組んでいるようだが解けたか?」
「え? あ、はい。……え?」
先生が黒板の隣で微笑んでいた。もちろん黒板に書かれていた問題なんて、一問たりとも分からない。よく考えれば分かるが、咄嗟となると無理だ。突然夢のような世界から引き戻されて混乱しているし。
「えーと……」
僕が言いよどんでいると、僅かに左の袖が引かれた。僕が目をやると、なんと朝岡さんがノートにでかでかと「2だよ!」と書いていた。
「えーと、2ですか?」
「おう、正解だ」
先生が解説を始めて、僕は息をついた。授業中にぼぉっとするのはほどほどにしておこう。
「危なかったね」
隣から鈴の音のような朝岡の声がした。小声で、そう言って微笑んだ。僕は眩暈を感じ、あやうく遠のきかけた意識を必死で捕まえる。
「あ、ありがとう。助かった」
「いいよ、別に。なんかぼぉーとしてたの?」
小首を傾げて、可愛すぎる笑顔で問いかけてくる朝岡。何もかも自白したくなってしまうが、もちろん見とれてたなんて言うことはできないので、僕は笑って誤魔化した。
そうすると朝岡も優しげに微笑んで、
「うとうとでもしてたの? でもこの天気じゃ仕方ないよねぇ」
そう言って窓の外に目をやる。青空と白い雲と太陽。綺麗な晴天がそこにあり、それを見つめて気持ち良さそうに朝岡が微笑む。
朝岡は、たくさん笑顔を持っている。嬉しい時、楽しい時、綺麗なものを見たとき。その時々でいつも微妙に違う笑顔を見せてくれる。こうして席が隣になるまえは綺麗な子だなぁ、くらいにしか思っていなかったけど、初めて席が隣になって朝岡の本当の魅力はこの笑顔だと気付いた。そのどれもが可愛すぎて、初めてその魅力に触れたとき、僕はもう完全に魅了されて虜と化していた。
「眠くなるような暖かさだもんねぇ。きっと今日は猫の皆、お昼寝し放題だろうな……」
朝岡は羨ましそうに呟いた。頬杖をついて目を細めて、ぼぉーと空を見ていた。なんかこのまま寝ちゃいそうな勢いだ。
「猫、か……。たしかに道路とかに一杯寝転がってそうだね」
僕の言葉に眠りかけてた朝岡はなんとか睡魔から逃れ、恥ずかしそうに顔を赤らめた。
「ごめん、言ってる傍から寝ちゃいそうになっちゃった。うん、こんな日に道路で眠るのは本当に気持ちいいから、きっと猫たちもごろごろしてるよ。私も……」
最後の方は声が小さくなって聞き取れなかった。て言うか呑気に猫談義してる場合じゃない。僕よ、これはチャンスだ。チャンスでしかない。ここで放課後どこかに呼んで、思いを告げるんだ。神がお与えくださったチャンスなんだ。
よ、よーし……。言うよ、言っちゃうよ。そうだどこに呼び出そう。公園? 体育館裏? 一緒に帰ろうとか? いやそれはないな。じゃなくて、とにかく誘わないと――。
脱線しがちな思考回路に活をいれて、気合で意識をはっきり保ち、震える体を抑えながら、
「あ、あの朝岡さん――」
と、授業終了のチャイムが鳴り響いた。途端騒がしくなる教室内、教師が大声で宿題のページ数を皆に伝えている。
やられた――。最悪のタイミングで訪れた授業の終わり。僕の中に芽生えたひ弱な決意は簡単に殺されて、
「ん? 何?」
反応してくれた朝岡に、
「いや……なんでもない」
としか言えなかった。
ああ――、もう。
◇
白い猫がいた。学校の近くに建っている小さな神社。その賽銭箱の隣でずんぐりと腰を下ろしていた。時折大きな欠伸を漏らし、あとはうとうと気持ち良さそうに目を細めていた。
「デブ猫だなぁー、お前」
その猫の横で、僕は体育座りをしながらそっと白猫を撫でていた。白い餅みたいになっている猫は、すごく気持ち良さそうにしているので、なんとなく嬉しい。
「なぁ聞いてくれよ……。僕は駄目な奴なんだ。あんなに絶好の機会があったりしてるのに、肝心な事は何一つ言えないんだ」
なんて愚痴ったりした。白猫に言っても仕方ないが、時にはこうして言葉の通じないものに悩みを打ち明けたくなってしまう。最近じゃこの神社の常連として、ほぼ毎日白猫を撫でている。そしてそのたびに愚痴を聞いてもらうのだ。
まぁこの猫半分寝てるから、言葉が通じる通じない以前に聞いてないけどさ。
「ほんっと可愛いんだよー、もう意識簡単にぶっ飛ぶくらい。麻薬的な? いや麻薬みたいな危険性はないな。中毒性はばっちりあるけどなぁ」
ゆっくり一日が過ぎていく。神社は広くて日当たりがよくて、心地いい。学生がこんなところで好きな子の事を猫相手に話してるなんて、精神的に相当やばいって見えるかもしれない。でも僕はここが好きだから毎日通ってしまうし、意外と猫相手に話すのも悪くないんだ。
と突然白い猫が立ち上がった。遅い足取りで神社の賽銭箱の後ろに周り、突然障子を前足でかりかりと引っかきだした。
「なんだよ。中に入りたいのか?」
僕が話してる最中なのに、失礼な猫だ。いつもは陽だまりの中から動かないって言うのに、もしかして僕の話に飽きたのだろうか。なんて思いながら少しだけ障子を開けてやった。
鍵も何もかかっておらず、それは開いた。中は一室だけで、古そうな畳が六畳くらい床に敷き詰められていて、奥に猫の像が見えた。今まで神社だと思っていたがこの規模の小ささを見ると、なんだか怪しくなってきた。
白い猫は、その中へとするりと入っていった。強い
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- 妖怪ウォッチのグッズいろいろ
- 今日もよろしくお願いします。
- (2023-08-09 06:50:06)
-
-
-

- 戦闘機の写真を撮るのが好き!
- ブルーインパルス
- (2024-12-04 06:30:10)
-
-
-

- 美術館・展覧会・ギャラリー
- エミール・ガレ展-美しきガラスの世…
- (2024-12-04 20:23:11)
-
© Rakuten Group, Inc.