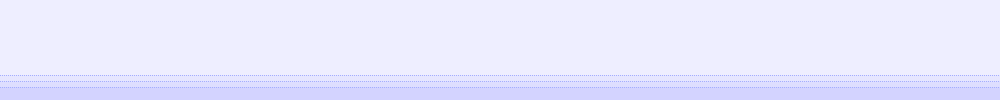図書館
――遠く及ばない世界にて。
――雨が降ると、少女は少年の家へは来なかった。
少年が本が嫌いだった。
少年の父親は大変な読書家で、彼の家には父親が集めた本が所狭しと転がっていた。
片付けてもすぐに父親が昔の本を引っ張り出してきて読み出すし、本の数が膨大なため整理が追いつかない。そもそも冊数が多すぎて本棚に収まりきらないのも理由として挙げられるが、とにかく少年の家はどの部屋も例外なく本で埋まっていた。
少年はもともと本を読むのが得意ではなかったから、よって本が好きではなかった。得意じゃない事は好きじゃない。当然だった。
それに、本の虫である父親は幼い自分に構ってくれない事が多かったこともあって、ますます本と言うものを毛嫌いするようになっていた。
本で埋め尽くされた家を飛び出して、日が暮れるまで遊び続ける。冒険をし、秘密基地を作り、時折悪戯もし、喧嘩もする。
家に帰ったらご飯を全力で食べて、疲れ果てた身体にへばりついた泥と疲労を風呂で洗い流したら、本なんかには目もくれずにベットに身を投げる。
彼はそういう子供だった。
少女は本が好きだった。
少年の家から徒歩十分、噴水広場の教会。そこが彼女の家だった。彼女は捨て子だったため、教会の人々に世話になりながら生きていた。
彼女はとにかく本が好きだった。
と言うのもシスター達は毎日忙しいからあまり少女に構ってくれないし、自分と同い年の子たちには自分に居ない、両親という存在がいる。彼女には遊び相手も、甘える相手も少なかった。
そのうち彼女は変な遠慮を覚えるようになった。お世話になっている身なのに、さらに遊んでくれなどと迷惑をかけるわけにはいかない。彼女は頭が良かったために、とても子供らしからぬ思考へとたどり着いてしまった。
変に自分の欲求を抑え続ける日々が続く。が、ある時一人のシスターが彼女に絵本を渡してくれたのだった。
絵本の中に広がる現実じゃない架空の世界は、彼女にとって魅力的なものだった。やがて彼女は物語に没頭するようになった。
いつも夜になると、教会の誰かしらが絵本を読んでくれた。ただ教会の人たちが忙しい日にはそれは叶わなかったし、彼女は遠慮を覚えていたので素直にその幸せを受け入れなかった。
まるで毎夜読んでもらうのを望むことを罪であるかのように、そのうちに彼女は自力で文字を覚え、一人で本を読めるようになった。同じ年頃の誰よりもそれは早かった。
そうなると一日の大抵を本を読んで過ごすこととなり、最初は絵本から、徐々に小説類へ。図書館に通いつめては様々な本に手を伸ばす。
もともと外で遊ぶのは好きじゃないし、友達と遊んでいるとその子は必ず『両親』が迎えにきてしまう。ならば架空の世界に没頭していたほうがずっと傷つかずにいれらるではないか。
小さい彼女は、どこまでも賢くて、悲しかった。
◇
彼が彼女に興味をもったのは、十五の夏頃のことだった。
学校で一番の美少女である彼女は、それだけで興味を惹かれる存在だった。それに加えていつも一人で居ることや、本を盾に人を寄せ付けない空気を纏っていることが、さらに彼の好奇心を膨らませることになった。
ただ彼自身は、あんな無愛想な女より明るい子のほうが可愛い。なんて思ったりしていて、自分の内心には気付いていなかったのである。
彼女が彼の家の蔵書に興味をもったのは、十五の秋頃のことだった。
たまたま学校の行事関係で話す機会があり、向こうが割とよく話しかけてきたので、少女は黙って相槌を打っていたのだが、
「お前ってよく本読んでるよな。うちにも腐るほどあるんだがな、なにが面白いんだ?」
少女があまりに無口なので話題に困っての一言だったのだろうが、この一言に少女は興味を持った。
腐るほど、と言うのはどれくらいなのだろうか。自分がまだ読んだ事のない、図書館にもない本があるだろうか。
本の何が面白いと問う男の子の言うことだから大したものじゃないかもしれない。十冊くらいしかなかったとしても、口ではなんとでも表現できる。
「……どれくらい、あるの」
「え、何が?」
しばらく考えて、聞いてみるのが一番早いと少女は判断した。少年は少女が初めてちゃんと喋ったことに目を丸くして驚いていた。そのせいで質問の回答まで気が回らず、思わず間の抜けた声で聞き返してしまった。
「本。一杯あるんでしょう」
「あ、ああ。本ね。うん、腐るほどあるさ。どこ見ても本だらけ」
少女は無表情のまま、思案した。本当だろうか。本当だとして、なぜこの人の家にそんなに本があるのだろう。本に興味は無さそうなのに。
「親が馬鹿みたいに本が好きで、どこかに出かけては山のように買い集めてくるんだ。しかもいつか読み返すかもとか言って、全然捨てさせてくれないから、溜まりたい放題なんだぜ」
少女は思わず謎が解けて、そして少年の家に蓄えられている本に対する興味も大きくなっていた。長年かけて様々に買い集めた本。しかも少しも処分されずに、家いっぱいに。
少女はワクワクした。鼓動がほんの少しだけ大きくなったのを感じた。
「行ってみてもいいかしら」
「え?」
「貴方の家の本を、読んで見たいのだけど」
「……ほんとに本が好きなんだな」
こうして少女は図書館と学校以外に、少年の家にも通いつめるようになった。
毎日学校が終わったあと、少女は少年の後ろに引っ付いていく。少年の家に着くと、すぐさま本棚の物色を初め、そのあとはただ黙々と本を読み続ける。日が暮れた頃にようやく本の世界から帰還すると、いそいそと帰り支度を始めるのだが、その時決まったように何冊か本を借りていいかと少年に訊ね、少年が好きにしろと言うと手当たり次第に何冊か鞄につめて帰っていく。本は次の日に少年に返却される。
こうして毎日帰りの少年の鞄には、教科書以外に本が何冊も詰められることになった。これが結構な重さで、どうせ家までついて来るんだからそれまで持っていて家についたら返してくれればいいのにと少年は何度か思ったが、なんだかひ弱な情けないことを言ってるような気がして言わなかった。
「なぁ。そんなに本読むの楽しいわけ?」
ベットに横になり本を読んでいた少年だったが、そのうちに疲れてため息を吐くと背伸びをした。それから横を向いて、体育座りで黙々と本を読んでいる少女に話しかけた。
一応この少女は自分が連れ込んだ客なのだから、放って遊びに行くわけにもいかない。少女にとってはそれでも構わないだろうし、少年もそれでも大丈夫なんだろうなと思ってはいたが、そうはしなかった。
だから少年の外出は減った。だが彼女に付き合って部屋にいてもすることがなく、話しかけても返事をしてくれないので会話もできず、ついには一緒に本を読むことすら始めた。
「楽しいわ。貴方は楽しくないの?」
だから少年は返事など諦めていたので、ビックリした。
「今日は返事するんだな」
「……」
少女は本から目を離し少年を見つめ、それからもう一度本に視線を戻すと、しおりを挟んで本を閉じた。それから伸びをした。
「ちょっと疲れたから、休憩」
「お前でも読書すると疲れるんだな」
「当たり前でしょう」
この珍しい変化に少年はちょっとだけワクワクした。少女が家に通い始めた頃のワクワクよりは全然小さな感情だったし、変な期待はしないほうがいいという最近学んだ教訓が生かされてる複雑な心境だったが、それでも確かにワクワクしていた。
「貴方は本を読んでいて、楽しくないの?」
少女は先ほどの質問を繰り返した。少年はしばらく考えてから、
「楽しくないね」
そう応えた。少女に対して、媚びた返答など必要が無さそうだ。そう判断したのだった。
「何故?」
単調な質問が返って来て、少年はうーんと唸った。それから、
「やっぱり文字を見てても詰まらない。なんか変に難しいことばかり書いてあるし、そもそもなんで面白いのか分からないね」
しばらくの沈黙。少女は黙りこくっていたが、
「現実じゃない世界は楽しくない? 小説の中でなら、絶対起こりえないことがおこるじゃない。冒険だって、恋愛だって、幸せだったある。それは楽しくない?」
ゆっくりとした、小さな呟きのような喋り方で聞き取りにくかったが、それでも綺麗な声だと少年は思った。
「いや、でも結局は文字だけしかないじゃないか。それだったら外に行って遊んだり、ダチと馬鹿な話して笑ってたほうがいい。それに、」
少しだけ言いよどみながら、
「恋愛だって、現実でしたほうが楽しいに決まってるだろう」
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- 模型やってる人、おいで!
- ドイツ1号戦車B型 (ズベズダ) …
- (2024-12-05 05:57:10)
-
-
-

- GUNの世界
- 昭和回想1988年3月号のGUN広告
- (2024-12-04 13:58:41)
-
-
-

- 超合金
- ONE PIECE アニメ25周年 Memorial ed…
- (2024-07-07 18:08:47)
-
© Rakuten Group, Inc.