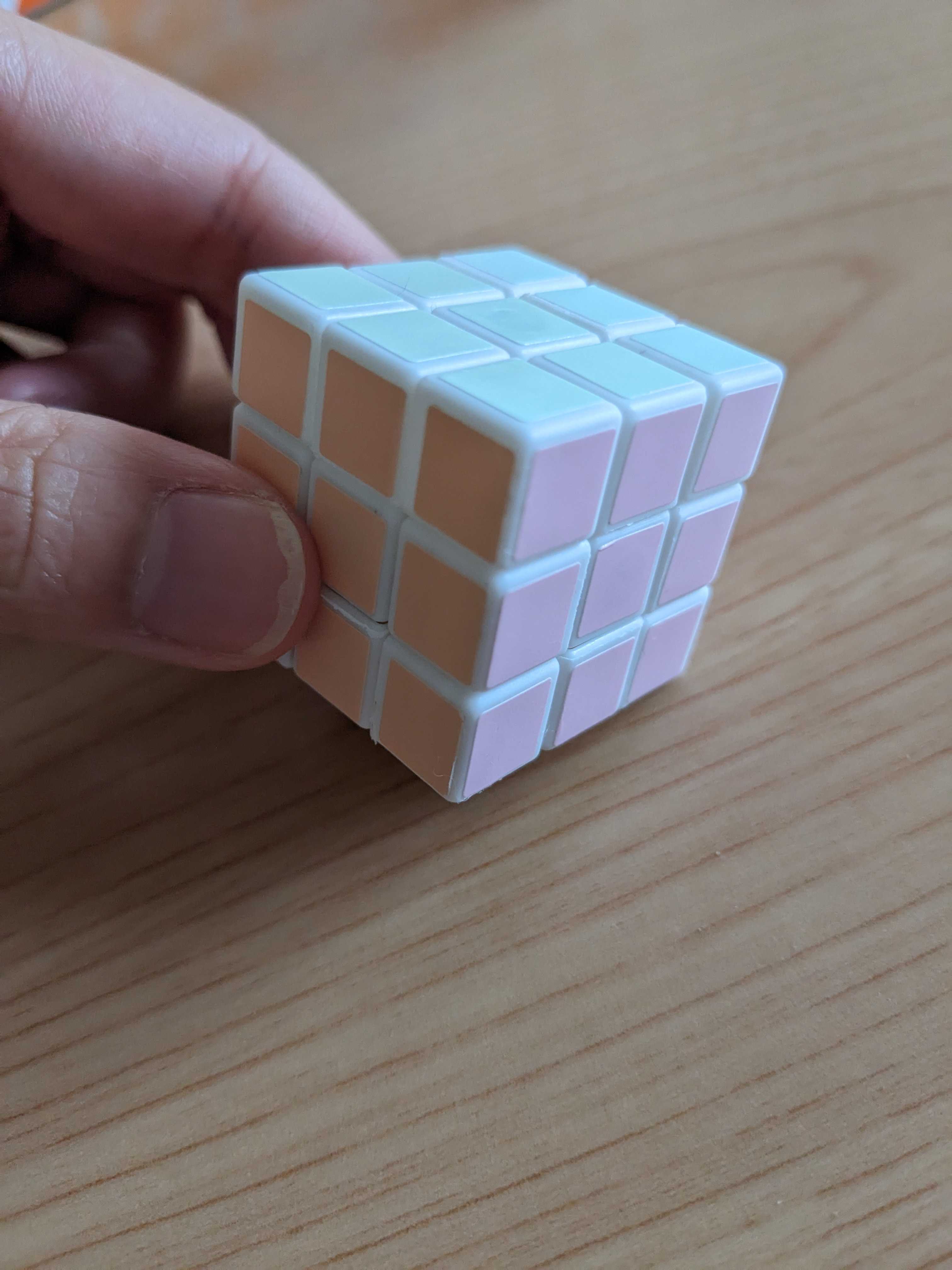自給自足と農業
僕もどちらかというと暮らしのイメージが先だったので、その気持ちは非常によくわかります。
米も味噌も野菜も卵も今作っているものはすべて、もともと家族のために、自給用に作り始めたものです。それを多めに作って、仲間に買ってもらえばそれで生活していけるのではないか。というのが、
最初のビジネスプランでした。(笑)
実際、15年位前までは、それでいけたんじゃないかと思いまし、当時の有機農業の一般的なスタイルだったんじゃないかと思います。
農業についてはこの日記のリンク先でもあるスーパー投資家さんが、非常にいい記事を書いておられます。メルマガもだされてますので、新規に農業をはじめようとされる方は是非購読してみてください。僕も読ませてもらってます。
ですので、僕は、どちらかというと、経営としての農業というより、暮らしにウエートを置かれている方向けに思いついたことを書いていこうかと思います。
実を言うと僕は30歳直前で田舎に飛び込んだとき、農業で食べていこうとは全く思ってませんでした。以前、農業関係の出版社に勤めていたことがあるので、事業としての農業がいかに大変かくらいのことは知っていたからです。
同じくリンクしてもらってる塩見さんの半農半X、たかはしじむしょさんの半農半SOHOではありませんが、自給的な農業をしながら、半分は何か他の事をしようと思っていました。陶芸、絵画、小説、塾、木工、何かそのうち見つかるだろうくらいの呑気な感覚でした。
でも案外、僕の日記を読んでくれてる人は、こちらのタイプの人が多いかもしれませんね。
僕の経験で、失敗したと思うこと、よかったと思うこと等、参考になりそうなことを少しづつでも書いていきます。
今回伝えたいのは一つだけ。
自給自足の延長を農業経営につなげるのは新規就農者にとっては神業に等しいということ。
先ほどの15年前の作戦は今、ちょっと難しいと思います。
まずは何か一つ自分の得意分野を固めた方がよいと思います。
米で百万、野菜で百万、卵で百万を目標にするのではなく、例えば卵だけで3百万を目標にする。
半農半○でいこうと思うなら、この○の部分だけでまずは生活できるようにするべきです。そこは足りないけど半農の部分があるからなんて思ってると多分、どちらもアウトになります。
僕が塾の講師をしていたとき、気分的には半農半○でしたが、かけた労力、時間は、農が9、○が1。収入はその逆でした。
まずは一つの柱を作る事。という今回はお話でした。
さて、昨日の続きです。
僕が自給自足的なものの中から一つメインにしようと思ったのはお米でした。
口和町で、だいぶ鍛えていただいてましたし、好きだったからです。
今でもそれほど間違った選択ではないと思っています。
ただし、田んぼが充分あればの話です。
田んぼが有り余っているというのは僕の経験上では、誤った情報です。条件の悪いところに限り、という但し書きをきちんとつけるべきでしょう。
条件の良い所はむしろ取り合うくらいで、とても新規のよそ者には回ってこないと思ったほうがいいです。
まして、無農薬なんていおうものなら。。(笑)
収量を追う訳ではないので、条件が悪くても。。なんて思わないほうがいいです。
労力は、収量をおわなくても、普通の田んぼ以上にかかりますから。
2ha以上、条件の良い田んぼを借りる事ができて、ほぼすべてにお米の作付けができて、自分で販売できれば、田んぼ中心の農業経営にも可能性がでて来ると思ってます。
ただし、どちらにしても他人のふんどしとなるのは避けられないでしょう。
大豆小麦なども米に準じます。これらは畑に作ればいいようなものですが、かなりの大面積をやらないと非常にコストが高くつきます。
買った方が安い。(笑)
僕のところでは集団転作で、7ヘクタールほどを機械の共同利用でやってますが、それでも大豆代金より高い国の補助金をあわせても赤字気味です。
ちなみにうちの集落は国のモデル事業に指定さていて、県内でも先進地といえます。それでも、継続は厳しいと思っています。
新規ではいる場合、畑や、米を作らないという条件での転作用の田んぼは借り易いとは思います。
でも、面積で勝負するような作目は避けたほうがよいと思います。
まあ、なんにしても農地の買取は無理だなと判断した僕は、唯一買うことのできた山林で何とかしようと考えました。
いまでこそ、さらっと書いてますが、田んぼ中心と思っていたプランを変えざるをえないとわかったときはかなり悔しかったです。(笑)
「無い物を、無い無いと嘆く前に、有る物を数えてみい」という、開拓者魂に、このときも救われました。
「ワシには山がある!」です。(笑)
但しこの山、今でも十分には活かしきれていません。
味噌の加工所兼ケビン、少々の鶏小屋、少々の椎茸。。
力不足、猛反省です。
まずは一本の柱。これを決めるときに、僕の頭には常に子供の姿がありました。
少しでも一緒に作業ができるなら、それだけで大きな意味を持つと思ったからです。
僕が無農薬にこだわったのも、まずは自分の子どものことを考えたからです。マスクつけて農薬まく作業を子どもと一緒にやるところなんて、想像したくもないでしょう。
まずは鶏を飼いました。えさやり、卵とリ、子どもと一緒にできます。解体もつきあわせました。
最初は大失敗です。なぜ、この鶏を殺すのかという、当時保育園児の長男に、他の鶏をいじめているから。と答えてしまいました。
当時は僕もそんなもんだったんですね。
採卵しているときに僕の頭に鶏がとまった事がありました。間抜けな姿ではあります。でも、長男にはとてもうらやましかったらしく僕の頭にもとまって、なんて鶏にお願いしてたのを懐かしく思い出しました。(笑)
このとき、百羽からスタートしました。売り先見つけるまでが大変でした。1日60から、70個の卵ですから、1日わずか6か7パックです。でも、夫婦揃って営業ができない。(笑)
決死の覚悟で、自然食品店に営業に行き、何も言えないで、ただコンニャクを買って帰ったのもこのときです。(笑)
情けない。なんて言いながら女房は全く動こうとしません。毎日たまっていく卵の山をみて、真剣に卵の漬物が作れないか、なんて考えてました。(笑)
幸い二つの店で扱ってもらえる事になって、漬物の研究はしなくてすみました。でもねえ、夫婦のうちどちらかが営業好きでないとしんどいですよ。僕の回りでも、うまくいってるところは大抵、奥さんが、営業担当。
愚痴になりそうなので先に進みます。(笑)
今は50羽程度。結論から言うとひらがい養鶏(地面の上で飼う)の場合、最低400羽以上は飼わないと採算は取れないような気がしています。このくらいなら労力的には殆ど問題はないです。売りさばく営業力の問題です。
勿論これで食べていけるということではなくて、これ以下だと赤字になるという意味です。
僕の今の50羽というのは完全に赤字です。ただその赤字も小さすぎて、あまり気にならないというだけのこと。子供達が殆ど鳥小屋にも行かなくなった今、自給用に10羽程度にするつもりでした。ところが。。。
ここはまだ、微妙なところなので僕のことは書きませんが、少しでも収入の一つとして考えようとするなら、最低500羽程度から考えて見られたら良いと思います。
まあ、でも鶏の鳴き声が聞こえる日常というのはいいものですよ。
© Rakuten Group, Inc.