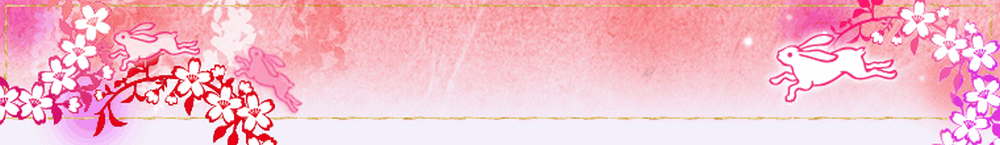俳人山頭火
種田山頭火 は1882年12月3日、山口県佐波郡防府の宮市に生まれる。父竹次郎と母ふさの間に4人の兄弟姉妹の長男としてなに不足ない幼少の
日を送った。
この少年は11歳の時、最大の悲しみに逢着する。
竹次郎は酒を飲まなかった。女の愛情には盲目であった。
政友会の顔役になってから、竹次郎の女狂いはいよいよ激しいものになった。
このことは巷談に屡々のぼるようになったが、かえって竹次郎の人物の大きさ
偉さとして宣伝された。
それにしても三人もの妾をかかえて、政治にかこつけては家をあける夫に対して、山頭火の母ふさは、「かぜにやなぎのごとく」、夫に対するには、慇懃にへり下って従順でいなくてはならなかった。
「舅姑、苦我を愛せずして誹り悪むことありとも、怒り恨むることなく、
誠を尽くして、其の心に協はんことを務べし。」と、教わられていても、
それには、やはり人間としての限度があったのも当然のことと言わなければならない。
日を逐って竹次郎の女狂いはいよいよ激しく、それは、すべて妻であるふさの責任なのだ、と竹次郎を庇う舅姑との争いは、ますます深く抜き難いものになった。
ふさは、母屋と土蔵の中ほどにあった古井戸に投身自殺をしてしまった。
なに不足なく日日を送っていた山頭火の幸せは、ただ、母の慈愛によってのみ、
その調和を保っていた。
けれど、突如としてその天秤のバランスは崩れ去った。
その孤独の中には父や母へ投げかけた限りなき懐疑と絶望があった。
そして、その懐疑や絶望は、ブーメランのようにある円周を描くと、また、山頭火の
ところへ還って来て、この少年の前途を暗いベールで覆っていった。
後に山頭火が大学中退で学業をたち、遂に出家に至る人生行路は、この時に、
既に出発されていたと言うことができるであろう。
そして50歳の時には乞食同然となり、落ちている物はなんでも拾ってくる
癖がついてしまった。ある日、平たい化粧用クリームの空瓶を拾って来た。
ところが、洗っても洗っても女の匂いが落ちない。
乞食坊主となって旅から旅をつづけているこの50男は、白粉焼けのした
人吉町の淫売や、呼子町の女郎衆や、平戸町の酌婦などから一度に
挑まれているような思いをするのであった。
1932年2月28日の日記に、
「生きるとは味わうことだ、酒は酒を味わうことによって鮭も生き人も生きる。
しみじみ飯を味わうことが飯をたべることだ。
彼女を抱きしめて女が分かるというものだ。」
この乞食坊主はこんなふうに書いている。
白い小さな一個の空き瓶は、どんなに歯を食いしばって洗っても、どこからか
甘い女の匂いを立ちのぼらせた。
俳人山頭火
潮文社新書 上田都史著より
© Rakuten Group, Inc.