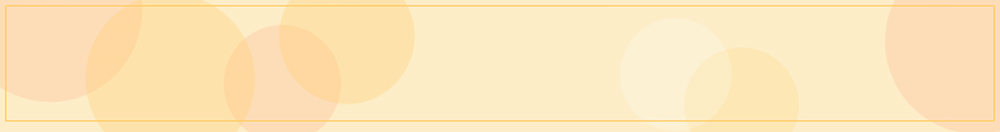映画「ロード・オブ・ザ・リング」「ホビット」
映画「ロード・オブ・ザ・リング」原作マニアの立場からの独善的感想→HPにジャンプします
第一部「旅の仲間」
第二部「二つの塔」
第三部「王の帰還」
若々しくて悲壮なイライジャ・フロド
PJ監督はゴンドールよりローハンがお好き?
映画「ホビット」
「思いがけない冒険」
「竜に奪われた王国」
「竜に奪われた王国」エクステンデッド・エディション
「決戦のゆくえ」
「決戦のゆくえ」エクステンデッド・エディション+α
>

若々しくて悲壮なイライジャ・フロド
(2005.6)
映画「ロード・オブ・ザ・リング」について少しだけ。
まず、これほど原作に敬意を払った映画だとは、思いませんでした。なおかつ、映画独自の味も出していて、原作をただなぞっただけでないあたり、ピーター・ジャクソンさんの映画作りの姿勢に感動です。
もちろん、原作溺愛歴20年以上の私には、原作との違いが気になる点があちこちあります。「王の帰還」なら、フロド・ゴーラム・サムの関係だとか、オリファントにひょいひょい登っちゃうレゴラスとか…、でもほとんどが許容できる範囲内の“違い”でした。
で、やっぱり三部作を通して何が一番気になるかというと、原作と比べて若すぎるフロドでしょう。
原作フロドが、その年齢や風貌、雰囲気から、原作者トールキンをほうふつとさせるところがあるのに対し、映画のフロドは、イライジャの熱演によって、まったくオリジナルな、若くて悲壮な自己犠牲的主人公となってます。
見目麗しく、前途有望なホビットの若き貴公子イライジャ・フロドが、指輪を託されたばかりに、故郷を捨て重責を担った逃避行を続け、そりゃ得難い出会いや体験もいっぱいしますけど、要は人生何十年分の労苦と辛酸を一気になめつくして、任務をまっとうするのですけど、その試練は彼の人生を奪ってしまってますよね。
英雄とたたえられ無事生還した喜びもつかの間、彼は若々しいまま、エルフの重鎮たち(彼らはいいんです、もう十分トシですから)とともに、ミドルアースをあとに船出していく。
ああ、もったいない、イライジャ・フロドの若き生命。なんて悲壮。燃えるような恋をする、なんてこともないままに。
それは、人生の折り返しを過ぎた中年のおじさんフロド(原作)の旅とは違います。おじさんフロドは、そのままただ年取っていくかわりに、ビルボの後に続くんだ! と自分なりに前向きに出立していき、指輪の始末に残りの人生(残り、です!)を惜しげもなく捧げたけれど、自分が守った故郷に帰ることができ、安堵して跡を継ぐ者たちにそこを託して西へ去る…たしかに痛みはともなうけれど、充実した人生だったといえるのではないでしょうか。
それゆえ、私は映画を見ると、痛々しいイライジャ・フロドが心配でかわいそうでなりませんでした。このへん、純粋ファンタジーからはちょっと外れた、悲劇?ぽい味がする…と思います。
どちらが好きかと言われると、うーん、やっぱり私は古典的ファンタジストなので、原作、と答えてしまうのですが。
でも、原作フロドより、イライジャ・フロドの方が、存在感(訴えかけるもの)があるのは、否めません。
映画「ロード・オブ・ザ・リング」について少しだけ。
まず、これほど原作に敬意を払った映画だとは、思いませんでした。なおかつ、映画独自の味も出していて、原作をただなぞっただけでないあたり、ピーター・ジャクソンさんの映画作りの姿勢に感動です。
もちろん、原作溺愛歴20年以上の私には、原作との違いが気になる点があちこちあります。「王の帰還」なら、フロド・ゴーラム・サムの関係だとか、オリファントにひょいひょい登っちゃうレゴラスとか…、でもほとんどが許容できる範囲内の“違い”でした。
で、やっぱり三部作を通して何が一番気になるかというと、原作と比べて若すぎるフロドでしょう。
原作フロドが、その年齢や風貌、雰囲気から、原作者トールキンをほうふつとさせるところがあるのに対し、映画のフロドは、イライジャの熱演によって、まったくオリジナルな、若くて悲壮な自己犠牲的主人公となってます。
見目麗しく、前途有望なホビットの若き貴公子イライジャ・フロドが、指輪を託されたばかりに、故郷を捨て重責を担った逃避行を続け、そりゃ得難い出会いや体験もいっぱいしますけど、要は人生何十年分の労苦と辛酸を一気になめつくして、任務をまっとうするのですけど、その試練は彼の人生を奪ってしまってますよね。
英雄とたたえられ無事生還した喜びもつかの間、彼は若々しいまま、エルフの重鎮たち(彼らはいいんです、もう十分トシですから)とともに、ミドルアースをあとに船出していく。
ああ、もったいない、イライジャ・フロドの若き生命。なんて悲壮。燃えるような恋をする、なんてこともないままに。
それは、人生の折り返しを過ぎた中年のおじさんフロド(原作)の旅とは違います。おじさんフロドは、そのままただ年取っていくかわりに、ビルボの後に続くんだ! と自分なりに前向きに出立していき、指輪の始末に残りの人生(残り、です!)を惜しげもなく捧げたけれど、自分が守った故郷に帰ることができ、安堵して跡を継ぐ者たちにそこを託して西へ去る…たしかに痛みはともなうけれど、充実した人生だったといえるのではないでしょうか。
それゆえ、私は映画を見ると、痛々しいイライジャ・フロドが心配でかわいそうでなりませんでした。このへん、純粋ファンタジーからはちょっと外れた、悲劇?ぽい味がする…と思います。
どちらが好きかと言われると、うーん、やっぱり私は古典的ファンタジストなので、原作、と答えてしまうのですが。
でも、原作フロドより、イライジャ・フロドの方が、存在感(訴えかけるもの)があるのは、否めません。

PJ監督はゴンドールよりローハンがお好き!?
(2005.8)
ようやく「王の帰還」SEE(4枚組DVD)の本篇を観ました。
映画館で観た時は、いろんな場面をいっぱい詰めこんであって忙しい展開だなあ、と思いましたが、ノーカット版はなるほど落ち着いて観られます。映画のつくり方も楽しみ方も、最近はすいぶん変わってきているなと実感。
サルマンの最期とか、アラゴルンがパランティアに挑む場面とか、補われたところはたくさんありましたが、結局、ゴンドールに関するエピソードはたいして増えていませんでした。
フロドら3人の個人的試練の旅に並行して描かれる、ペレンノールの合戦シーンはどうしてもアクション重視、終局へ向かってまっしぐらに盛り上げていくべきところで、ゴンドールのあれこれを描く余裕はなかったのだとは思いますが、
たとえばイムラヒル大公。名前だけでも、またはちらりとでも居てほしかった。ローハン軍ではグリムボルトなど各族長の名前が挙げられていたのに。ゴンドールにはファラミアの他にまともな大将はいないのか? て感じがしてしまいます。
ついでに言うなら、原作にあったミナス・ティリスに各地の領主・勇士が集まる「叙事詩的カタログ」な場面、あれを映像で観てみたかったのですが・・・
また、あまりにみっともない執権デネソール。セオデン王との対比は結構ですが、デネソールには彼なりの努力と誇りと重責と苦しみがあったのですから、そこをもうちょっと描いてほしかったです。特に、命取りとなったパランティアのことが割愛されたので、彼はただの物わかりの悪い年寄りになってしまって、むしゃむしゃ食べてばっかりで・・・、残念です。
さらに、やっぱりなかった「王の手は癒しの手」。アラゴルンの真価を発揮し、施療院の老女イオレスを始めとするミナス・ティリスの民衆が、ただ悲愴なばかりではなく、未来への希望を持つ力強い人々であることを、描いてほしかったですね。
ローハンでは、原作にはなかった幼い兄妹なども描きこんでいたのに・・・
というようなあれこれから察するに、ピーター・ジャクソン監督、どうもローハンの方がお好みのようですね? ペレンノールの野で突撃するローハン軍のすばらしさとセオデン王の勇姿は、黒門前のアラゴルンよりも立派な感じがしちゃいます。
私もローハンとくにセオデンは大好きなのですが、それに比べて、衰えたりとはいえ、古代ギリシャ・ローマにも匹敵する先進文明大国であるはずのゴンドールの扱いが、どうもちょっと軽い、と感じます。
まあ、あれだけの原作をどう読み、どう映画にするかは、人それぞれいろんな「指輪物語」があって当然ですから、その中で「PJ版指輪物語」はかなり相当、楽しめるのは事実ですよね。
まだあと吹き替え版やコメント付きのがあるし、付録ディスクも2枚もあるし、老後まで楽しめそうなSEEです。
ようやく「王の帰還」SEE(4枚組DVD)の本篇を観ました。
映画館で観た時は、いろんな場面をいっぱい詰めこんであって忙しい展開だなあ、と思いましたが、ノーカット版はなるほど落ち着いて観られます。映画のつくり方も楽しみ方も、最近はすいぶん変わってきているなと実感。
サルマンの最期とか、アラゴルンがパランティアに挑む場面とか、補われたところはたくさんありましたが、結局、ゴンドールに関するエピソードはたいして増えていませんでした。
フロドら3人の個人的試練の旅に並行して描かれる、ペレンノールの合戦シーンはどうしてもアクション重視、終局へ向かってまっしぐらに盛り上げていくべきところで、ゴンドールのあれこれを描く余裕はなかったのだとは思いますが、
たとえばイムラヒル大公。名前だけでも、またはちらりとでも居てほしかった。ローハン軍ではグリムボルトなど各族長の名前が挙げられていたのに。ゴンドールにはファラミアの他にまともな大将はいないのか? て感じがしてしまいます。
ついでに言うなら、原作にあったミナス・ティリスに各地の領主・勇士が集まる「叙事詩的カタログ」な場面、あれを映像で観てみたかったのですが・・・
また、あまりにみっともない執権デネソール。セオデン王との対比は結構ですが、デネソールには彼なりの努力と誇りと重責と苦しみがあったのですから、そこをもうちょっと描いてほしかったです。特に、命取りとなったパランティアのことが割愛されたので、彼はただの物わかりの悪い年寄りになってしまって、むしゃむしゃ食べてばっかりで・・・、残念です。
さらに、やっぱりなかった「王の手は癒しの手」。アラゴルンの真価を発揮し、施療院の老女イオレスを始めとするミナス・ティリスの民衆が、ただ悲愴なばかりではなく、未来への希望を持つ力強い人々であることを、描いてほしかったですね。
ローハンでは、原作にはなかった幼い兄妹なども描きこんでいたのに・・・
というようなあれこれから察するに、ピーター・ジャクソン監督、どうもローハンの方がお好みのようですね? ペレンノールの野で突撃するローハン軍のすばらしさとセオデン王の勇姿は、黒門前のアラゴルンよりも立派な感じがしちゃいます。
私もローハンとくにセオデンは大好きなのですが、それに比べて、衰えたりとはいえ、古代ギリシャ・ローマにも匹敵する先進文明大国であるはずのゴンドールの扱いが、どうもちょっと軽い、と感じます。
まあ、あれだけの原作をどう読み、どう映画にするかは、人それぞれいろんな「指輪物語」があって当然ですから、その中で「PJ版指輪物語」はかなり相当、楽しめるのは事実ですよね。
まだあと吹き替え版やコメント付きのがあるし、付録ディスクも2枚もあるし、老後まで楽しめそうなSEEです。

映画「ホビット 思いがけない冒険」感想
(2013.1)
なかなか映画館に足を運ぶ暇がなく…今日やっと2D字幕版を観てきました。
予告編など予備知識もあまり無いままいきなり観たので、かなりびっくり。映画に行く暇がないかもしれないと、映画版カレンダーだけ去年のうちに購入したのですが、ドワーフたち、誰が誰やら(見た目で分かるボンブール以外は)分かりませんでした。
それで、よもや大トーリン・オーケンシールドがあんな若造(失礼!)になっているとは思わなかったのです。傷つきやすい思春期風イライジャ・フロド以上の、びっくりかも。
最初、りっぱな白ひげの別のドワーフ(実はバーリンだった)をトーリンかと思ってしまったため、混乱しました。寺島龍一(岩波の挿絵)の絵の印象が刷りこまれていたのです。
それで、トロルのあたりからやっと頭を切り換えて、P・ジャクソンのドワーフ群像を新しく鑑賞しなおすつもりになりました。
結論としては、悪くないです。P・Jは原作を変更しながらも、根っこの部分はきちんと踏襲しているので・・・、ドワーフたちの執念深い復讐心や強固な意志、それを強権的でなくうまく方向付けようとするガンダルフの深慮、はたまた読者の共感を呼ぶホビットの良識的で小さな勇気などです。
しかし、高貴で慇懃で、むかしの多血質も年齢によって内にこもった感のある、やや高慢な長老・・・落魄の身を嘆きながらもやれることはやってきたというプライドのある「あの」トーリンが、映画ではまだまだ人生これから働き盛りの「若き」王子という設定になり、彼の立場も言動も悩みも、原作とは異なっています。
したがって、別なトーリンを見なければならず、かなりタイヘンです。何となれば、( 別のところ に 記しましたが)トーリンは、 『指輪物語』 におけるフロドと同等とも言える、物語の中心人物だからです。 『ホビット』 は、忍びの者ビルボの視点から見ていますが、まさにトーリンの王国奪還と自己実現の物語なのです。
若きトーリンは、その若さゆえ、松の木からゴブリンの王アゾグに一騎打ちを挑みに戻ります。原作のトーリンにはないその場面が、映画ではクライマックスとなっています。そして、原作のビルボならすぐにも指輪をはめて加勢に出向くであろうところ、映画のビルボは姿も消さずに捨て身の体当たりに出ました。本人も言っていたように、忍びの者らしいところは少しもありません!
とはいえ、ビルボの方は、全体的に控えめで常識的で落ち着いて、とてもホビットらしかったです。ゴクリとのなぞなぞ問答も期待通りでした。
まだまだ冒険も序の口でこれからいろんなことが深くなっていくのでしょうが、ドワーフの区別をちゃんと頭に入れてもう一度観たい気がします。
最後に、ドワーフの歌が、期待以上に素朴で力強くてよかったです。それから、 「ロードオブザリング」 同様、ニュージーランドの大自然にも圧倒されました。
なかなか映画館に足を運ぶ暇がなく…今日やっと2D字幕版を観てきました。
予告編など予備知識もあまり無いままいきなり観たので、かなりびっくり。映画に行く暇がないかもしれないと、映画版カレンダーだけ去年のうちに購入したのですが、ドワーフたち、誰が誰やら(見た目で分かるボンブール以外は)分かりませんでした。
それで、よもや大トーリン・オーケンシールドがあんな若造(失礼!)になっているとは思わなかったのです。傷つきやすい思春期風イライジャ・フロド以上の、びっくりかも。
最初、りっぱな白ひげの別のドワーフ(実はバーリンだった)をトーリンかと思ってしまったため、混乱しました。寺島龍一(岩波の挿絵)の絵の印象が刷りこまれていたのです。
それで、トロルのあたりからやっと頭を切り換えて、P・ジャクソンのドワーフ群像を新しく鑑賞しなおすつもりになりました。
結論としては、悪くないです。P・Jは原作を変更しながらも、根っこの部分はきちんと踏襲しているので・・・、ドワーフたちの執念深い復讐心や強固な意志、それを強権的でなくうまく方向付けようとするガンダルフの深慮、はたまた読者の共感を呼ぶホビットの良識的で小さな勇気などです。
しかし、高貴で慇懃で、むかしの多血質も年齢によって内にこもった感のある、やや高慢な長老・・・落魄の身を嘆きながらもやれることはやってきたというプライドのある「あの」トーリンが、映画ではまだまだ人生これから働き盛りの「若き」王子という設定になり、彼の立場も言動も悩みも、原作とは異なっています。
したがって、別なトーリンを見なければならず、かなりタイヘンです。何となれば、( 別のところ に 記しましたが)トーリンは、 『指輪物語』 におけるフロドと同等とも言える、物語の中心人物だからです。 『ホビット』 は、忍びの者ビルボの視点から見ていますが、まさにトーリンの王国奪還と自己実現の物語なのです。
若きトーリンは、その若さゆえ、松の木からゴブリンの王アゾグに一騎打ちを挑みに戻ります。原作のトーリンにはないその場面が、映画ではクライマックスとなっています。そして、原作のビルボならすぐにも指輪をはめて加勢に出向くであろうところ、映画のビルボは姿も消さずに捨て身の体当たりに出ました。本人も言っていたように、忍びの者らしいところは少しもありません!
とはいえ、ビルボの方は、全体的に控えめで常識的で落ち着いて、とてもホビットらしかったです。ゴクリとのなぞなぞ問答も期待通りでした。
まだまだ冒険も序の口でこれからいろんなことが深くなっていくのでしょうが、ドワーフの区別をちゃんと頭に入れてもう一度観たい気がします。
最後に、ドワーフの歌が、期待以上に素朴で力強くてよかったです。それから、 「ロードオブザリング」 同様、ニュージーランドの大自然にも圧倒されました。

すべてがカッコイイ!「ホビット 竜に奪われた王国」
(2014.2)
昨年は上映が終わる間際に見た「ホビット」ですが、今年はリキを入れて、初日の朝から観てきました。
とりあえず、2D字幕。いきなり3Dはこわいので・・・
これも昨年とは反対に、予告編とか前評判とか少し情報を仕入れて行ったのですが、気になっていたのはふたつ、新登場の女性エルフ(タウリエル)と、熊人ビヨルンのことでした。
(以下ネタバレ注意)
ビヨルンは、ほとんど割愛されたのではないかとひそかに心配していました。しかしちゃんと登場! 巨大グマの迫力はすばらしく、もっとよく見たいと思いました。人間になった彼は、日本版の挿絵とずいぶん違っていたため(端的に、やせていたため)、少しとまどいましたが、独特のなまりのある話し方や、威厳のある物腰は、好印象。
ハチは飛んでいたのに蜂蜜菓子がきちんと登場しなかったのが残念。そういえば「たらふく」もなかった。DVDで追加されていることを祈ります。
さて、タウリエルですが、前宣伝で非常に目立っています。闇の森が舞台となればレゴラスの登場はまあよいとして、この女エルフは誰よ、レゴラスとベタベタしてたら許さないわよ! などと思っていた一方、とにかく一人も女性の出てこない原作ですから、必ずや女性キャラが必要とされることも予想ていました。
結局、PJ監督のセンスはおおかたの原作マニアの望む方向と一致しているようで、本筋を邪魔せず脇のエピソードを上手にもりあげる、すてきなキャラクターでした。
腕が立って、外好きで、若く?活発なところは、中山星香の『妖精国の騎士』のヒロイン、ローゼリイを思い出させました。そういえばレゴラスも今回、ローゼリイの師匠のエアリアンにちょっと通じるものがあったかも。二人ともエルフらしく、クールで軽快で小気味よかったです。
レゴラスは、「ロード・オブ・ザ・リング」ではどうもギムリとの漫才?がうますぎて、性格的に軽すぎる感じでしたが、今回、高貴な冷たさが出ていて、それなりに良い感じ。ただし私の原作のイメージとはちょっと違うのですが。ノルドール(上のエルフ)ではないにしろ、エルフなんですから、少しは「影」があってよいと思うのです。
そして、これらの不安をすっかり忘れるほど、ほれぼれと見とれてしまったのが、
・邪悪なるスマウグどの! 想像を絶してものすごい。その大きさ、顔、動き、すべてがカッコイイ。竜なんてファンタジーではありきたりな今日この頃、その原点ともいうべき彼を、ここまで創り上げたのは敬意にあたいします。声もすばらしく、物語にあるとおり「魅せられて」しまいます。
・サウロン! ガンダルフによって暴かれたとき、最初「ロード・オブ・ザ・リング」でお馴染みの「目」でした。しかしその中にぼうっと生前のサウロンのシルエットが浮かび上がり、輪郭だけとはいえ、これがすさまじい。私の中で、死人占い師という名前からして、なんかドロドロヨレヨレしたイメージだったのが、かなりポイントアップしました。
今度は3Dでぜひ観たい(特にスマウグ!)HANNAでした。
昨年は上映が終わる間際に見た「ホビット」ですが、今年はリキを入れて、初日の朝から観てきました。
とりあえず、2D字幕。いきなり3Dはこわいので・・・
これも昨年とは反対に、予告編とか前評判とか少し情報を仕入れて行ったのですが、気になっていたのはふたつ、新登場の女性エルフ(タウリエル)と、熊人ビヨルンのことでした。
(以下ネタバレ注意)
ビヨルンは、ほとんど割愛されたのではないかとひそかに心配していました。しかしちゃんと登場! 巨大グマの迫力はすばらしく、もっとよく見たいと思いました。人間になった彼は、日本版の挿絵とずいぶん違っていたため(端的に、やせていたため)、少しとまどいましたが、独特のなまりのある話し方や、威厳のある物腰は、好印象。
ハチは飛んでいたのに蜂蜜菓子がきちんと登場しなかったのが残念。そういえば「たらふく」もなかった。DVDで追加されていることを祈ります。
さて、タウリエルですが、前宣伝で非常に目立っています。闇の森が舞台となればレゴラスの登場はまあよいとして、この女エルフは誰よ、レゴラスとベタベタしてたら許さないわよ! などと思っていた一方、とにかく一人も女性の出てこない原作ですから、必ずや女性キャラが必要とされることも予想ていました。
結局、PJ監督のセンスはおおかたの原作マニアの望む方向と一致しているようで、本筋を邪魔せず脇のエピソードを上手にもりあげる、すてきなキャラクターでした。
腕が立って、外好きで、若く?活発なところは、中山星香の『妖精国の騎士』のヒロイン、ローゼリイを思い出させました。そういえばレゴラスも今回、ローゼリイの師匠のエアリアンにちょっと通じるものがあったかも。二人ともエルフらしく、クールで軽快で小気味よかったです。
レゴラスは、「ロード・オブ・ザ・リング」ではどうもギムリとの漫才?がうますぎて、性格的に軽すぎる感じでしたが、今回、高貴な冷たさが出ていて、それなりに良い感じ。ただし私の原作のイメージとはちょっと違うのですが。ノルドール(上のエルフ)ではないにしろ、エルフなんですから、少しは「影」があってよいと思うのです。
そして、これらの不安をすっかり忘れるほど、ほれぼれと見とれてしまったのが、
・邪悪なるスマウグどの! 想像を絶してものすごい。その大きさ、顔、動き、すべてがカッコイイ。竜なんてファンタジーではありきたりな今日この頃、その原点ともいうべき彼を、ここまで創り上げたのは敬意にあたいします。声もすばらしく、物語にあるとおり「魅せられて」しまいます。
・サウロン! ガンダルフによって暴かれたとき、最初「ロード・オブ・ザ・リング」でお馴染みの「目」でした。しかしその中にぼうっと生前のサウロンのシルエットが浮かび上がり、輪郭だけとはいえ、これがすさまじい。私の中で、死人占い師という名前からして、なんかドロドロヨレヨレしたイメージだったのが、かなりポイントアップしました。
今度は3Dでぜひ観たい(特にスマウグ!)HANNAでした。
「ホビット 竜に奪われた王国」エクステンデッド・エディション
(2014.11)
夏頃から予約していて発売すぐに家に届きましたが、あんまり長いので、暇を見つけて少しずつ観ました。
「ロード・オブ・ザ・リング」でもそうでしたが、シアター版が新しいファン獲得用とすると、エクステンデッド・エディションは原作マニア向け。映画館で「無くて残念」と思ったシーンや『指輪物語 追補編』のエピソードが付け加えられています。以下ネタバレあり。
たとえばビヨルンを訪ねるとき、ドワーフたちがわざと2人ずつ出てきて挨拶をする場面。原作通りとはいきませんが、まったくカットされたかと思いきや、原作の風味を伝えるぐらいには再現されておりました。
あるいは闇の森の魔の川、白い鹿、眠りこむボンブール。ドワーフたちが彼をかついで進むいくつかのカットは、映画館用のシーンにうまくはめこんであって、これが単なる付け足しではなく、最初からエクステンデッド・エディションを十分意識して作られているのが分かります。
それから、気の毒なスライン2世もドル・グルドゥアの場面に登場し、指輪が取り上げられ、欠けた指をしているところをガンダルフに発見されます。「ロード・オブ・ザ・リング」のフロドの欠けた指を彷彿とさせるあたり、心憎い演出でした。
もちろん、それでもまだ「無くて残念」な部分はあって、その多くは牧歌的な場面・・・ビヨルンの蜂蜜菓子、湖の町の「たらふく」。「糸くりテンテン」を始め樽の川下り、湖の町の予言など各場面で唄われる歌・・・
ところで映画を観たときから気になる点が。「エルフはお酒に強いのか?」という疑問です。映画「二つの塔」に確か、ギムリと飲み比べをしてもほとんど酔わないレゴラスという、原作にはないエピソードがありますが、今回の「ホビット」では、原作通りエルフの番人は上等のワインに酔って寝こんでしまっています。・・・矛盾しませんか? それともレゴラスだけが酒豪なのでしょうか。
もしかしたら、私のまだ観ていないオーディオ・コメンタリには、このようなトリビアへの答えがあるのかもしれません。オーディオ・コメンタリはとても興味深いのですが、本編映像と一緒に聞くとどうも集中できないので、あまり観る気になれません。文字に書いた物があれば読みたいのですが・・・
夏頃から予約していて発売すぐに家に届きましたが、あんまり長いので、暇を見つけて少しずつ観ました。
「ロード・オブ・ザ・リング」でもそうでしたが、シアター版が新しいファン獲得用とすると、エクステンデッド・エディションは原作マニア向け。映画館で「無くて残念」と思ったシーンや『指輪物語 追補編』のエピソードが付け加えられています。以下ネタバレあり。
たとえばビヨルンを訪ねるとき、ドワーフたちがわざと2人ずつ出てきて挨拶をする場面。原作通りとはいきませんが、まったくカットされたかと思いきや、原作の風味を伝えるぐらいには再現されておりました。
あるいは闇の森の魔の川、白い鹿、眠りこむボンブール。ドワーフたちが彼をかついで進むいくつかのカットは、映画館用のシーンにうまくはめこんであって、これが単なる付け足しではなく、最初からエクステンデッド・エディションを十分意識して作られているのが分かります。
それから、気の毒なスライン2世もドル・グルドゥアの場面に登場し、指輪が取り上げられ、欠けた指をしているところをガンダルフに発見されます。「ロード・オブ・ザ・リング」のフロドの欠けた指を彷彿とさせるあたり、心憎い演出でした。
もちろん、それでもまだ「無くて残念」な部分はあって、その多くは牧歌的な場面・・・ビヨルンの蜂蜜菓子、湖の町の「たらふく」。「糸くりテンテン」を始め樽の川下り、湖の町の予言など各場面で唄われる歌・・・
ところで映画を観たときから気になる点が。「エルフはお酒に強いのか?」という疑問です。映画「二つの塔」に確か、ギムリと飲み比べをしてもほとんど酔わないレゴラスという、原作にはないエピソードがありますが、今回の「ホビット」では、原作通りエルフの番人は上等のワインに酔って寝こんでしまっています。・・・矛盾しませんか? それともレゴラスだけが酒豪なのでしょうか。
もしかしたら、私のまだ観ていないオーディオ・コメンタリには、このようなトリビアへの答えがあるのかもしれません。オーディオ・コメンタリはとても興味深いのですが、本編映像と一緒に聞くとどうも集中できないので、あまり観る気になれません。文字に書いた物があれば読みたいのですが・・・
最後はしょりすぎ?「ホビット 決戦のゆくえ」
(2014.12)
大晦日のわたくし的恒例、朝から映画に行ってきました。
じつは封切り直後に2D字幕版を観てあるので、2回目の 「ホビット 決戦のゆくえ」 、今度は娘と一緒に3D吹き替え版です。
最初はドキドキ(いろんな意味で)、2度目は楽しんで観るのがいいかな、と。
前回、エクステンデッド・バージョンの感想でも書きましたが、どうもPJ監督、劇場版は新たなファン獲得のために公的に作り、原作ファンと監督自身のマニア心を満たすためにはエクステンデッド・バージョンがある、と割り切っているようですね。
以下、ネタバレ注意。
「ロード・オブ・ザ・リング」への橋渡しとなるようなオリジナル場面をいくつも挿入している割には、最後に、肝心のトーリンのお葬式がなかったのが、びっくりでした。「アーケン石を胸に」(←ここが大事)エレボールの奥底に葬られたはずなんですけど・・・やはりエクステンデッド・バージョンを待つしかないのでしょうか。
そのアーケン石。なんか、ちゃちでした。白く輝く大宝石でなくちゃいけないのですが、ぼんやりした卵形だし、透明な中にピンクや空色の淡い光が散っているところなんか、水入り水晶というか、巨大なレジンというか、夜店のおもちゃみたいでした。あれじゃあトーリンが偽物と疑うのも無理はないかな。
しかし、全体としては映画版ならではのコンパクトさ(2時間半で終わってくれてほっとしました。3時間以上になると、やはり目が疲れます)の割に、戦争場面のスペクタクルのすばらしさは想像以上で、十分楽しむことができました。
ガラドリエル様の本領発揮(さすがノルドールの王族、こわかった!)、くろがね山のダインがファニーなトンカチ(原作ではつるはしmattockなんですけど)を振るい頭突きしまくる勇姿、トーリンが黄金と竜の呪いにさいなまれ葛藤するさま、あるいはなかなか外見もイケてる(娘談)アゾグの冷静な逆襲など、2度目でも飽きない場面がいっぱいです。
「化けミミズ」は中山星香の 『妖精国の騎士』 にそっくりの怪物がちらと出ていたのを思い出したりしました。
原作に忠実な場面や台詞がたくさんあってうれしかったほかに、原作にはないけれど原作の精神に忠実で、それゆえ私が最も感動したエピソードについて、最後に一言。
それは、ビルボのドングリです。ビヨルンの庭で拾い、帰郷したら冒険の思い出に庭に植えようと思う、とビルボはトーリンにドングリを見せて語ります。その言葉は、スマウグの呪いで硬化してしまったトーリンの心をいっとき和らげ、彼は最期にそのことに触れて息をひきとります。
黄金や宝石に心をかたむけるトーリンとの対照がみごとで、しかもこのドングリは!! のちに本当に大樹に育って、 『指輪物語』 冒頭および最後で描かれる「ビルボの誕生祝いの木」になるのですね。あとで植えられたマローン樹がサムの木であるように、この木はバギンズ家の象徴として重要だと私は思うのです( 拙稿「“一つの指輪”の象徴性」2D †bおよび 3B 参照)。
ともあれ、これでPJの創るトールキン世界が終わってしまうのがちょっと寂しい気がするほどでした。
大晦日のわたくし的恒例、朝から映画に行ってきました。
じつは封切り直後に2D字幕版を観てあるので、2回目の 「ホビット 決戦のゆくえ」 、今度は娘と一緒に3D吹き替え版です。
最初はドキドキ(いろんな意味で)、2度目は楽しんで観るのがいいかな、と。
前回、エクステンデッド・バージョンの感想でも書きましたが、どうもPJ監督、劇場版は新たなファン獲得のために公的に作り、原作ファンと監督自身のマニア心を満たすためにはエクステンデッド・バージョンがある、と割り切っているようですね。
以下、ネタバレ注意。
「ロード・オブ・ザ・リング」への橋渡しとなるようなオリジナル場面をいくつも挿入している割には、最後に、肝心のトーリンのお葬式がなかったのが、びっくりでした。「アーケン石を胸に」(←ここが大事)エレボールの奥底に葬られたはずなんですけど・・・やはりエクステンデッド・バージョンを待つしかないのでしょうか。
そのアーケン石。なんか、ちゃちでした。白く輝く大宝石でなくちゃいけないのですが、ぼんやりした卵形だし、透明な中にピンクや空色の淡い光が散っているところなんか、水入り水晶というか、巨大なレジンというか、夜店のおもちゃみたいでした。あれじゃあトーリンが偽物と疑うのも無理はないかな。
しかし、全体としては映画版ならではのコンパクトさ(2時間半で終わってくれてほっとしました。3時間以上になると、やはり目が疲れます)の割に、戦争場面のスペクタクルのすばらしさは想像以上で、十分楽しむことができました。
ガラドリエル様の本領発揮(さすがノルドールの王族、こわかった!)、くろがね山のダインがファニーなトンカチ(原作ではつるはしmattockなんですけど)を振るい頭突きしまくる勇姿、トーリンが黄金と竜の呪いにさいなまれ葛藤するさま、あるいはなかなか外見もイケてる(娘談)アゾグの冷静な逆襲など、2度目でも飽きない場面がいっぱいです。
「化けミミズ」は中山星香の 『妖精国の騎士』 にそっくりの怪物がちらと出ていたのを思い出したりしました。
原作に忠実な場面や台詞がたくさんあってうれしかったほかに、原作にはないけれど原作の精神に忠実で、それゆえ私が最も感動したエピソードについて、最後に一言。
それは、ビルボのドングリです。ビヨルンの庭で拾い、帰郷したら冒険の思い出に庭に植えようと思う、とビルボはトーリンにドングリを見せて語ります。その言葉は、スマウグの呪いで硬化してしまったトーリンの心をいっとき和らげ、彼は最期にそのことに触れて息をひきとります。
黄金や宝石に心をかたむけるトーリンとの対照がみごとで、しかもこのドングリは!! のちに本当に大樹に育って、 『指輪物語』 冒頭および最後で描かれる「ビルボの誕生祝いの木」になるのですね。あとで植えられたマローン樹がサムの木であるように、この木はバギンズ家の象徴として重要だと私は思うのです( 拙稿「“一つの指輪”の象徴性」2D †bおよび 3B 参照)。
ともあれ、これでPJの創るトールキン世界が終わってしまうのがちょっと寂しい気がするほどでした。
「ホビット 決戦のゆくえ」エクステンデッド・エディション+α
(2015.12)
映画館で観て以来、「アーケン石を胸に、故郷に葬られるトーリン」を観たいと、心待ちにしていた エクステンデッド・エディション 。11月に入手して、ようやく荘厳なお葬式シーンを鑑賞することができました。
ただお葬式自体はあっという間で、アーケン石もやっぱりちゃちな感じでしたけど・・・
ドワーフたちの戦車での戦いが長々と追加されたのは、楽しかったです。PJ監督がコメントで「昔観たイタリア映画のシーンにヒントを得た」と語っていた、刃つき車輪の戦車ですけど、あれはケルトの戦車ですね。ついこの間観た 、「第九軍団のワシ」 のケルト部族との戦いシーンで、似たような刃つき戦車が出ていましたもの。
それにしても、今年は(も?)世界でいろいろ物騒なことが相次いだせいか、 「ホビット」 を観ていて思うのは、普通の市民の、当たり前の一般常識や冷静さというものが、世界の平和には大事だなあ、ということ。
黄金に目がくらみ一族の結束やドゥリン王家への忠誠にしばられたドワーフや、宝石に目がくらみ排他的な森のエルフ、お金に目がくらむ湖の町の頭領やアルフリド、などなどが、自分たちの論理だけを追求し破壊的な方向へと突き進む。
これを引きとめようとするガンダルフの、大局的な賢者の知恵さえ裏目に出たり、聞き入れられなかったりするとき、負のベクトルにあらがい、戦争をとめうるのは、ごくふつうの近代市民意識を持つビルボやバルドの言動だけなのです。
トールキンもPJ監督も決して寓意的な作品を意図したわけではないけれど、ドワーフやオークやエルフの論理を観ていると、現実の世界を騒がすあんな大国、こんな国、あんな集団、こんな政治家のことがつい脳裏をかすめます。
我々もビルボやバルドのような一市民的常識で、偏った考え方に世の中がぶれていくのを阻止せねばならないような、そんな気がします。
ところで、今日は話題の 「スター・ウォーズ フォースの覚醒」 を観てきたのですが、なつかしい登場人物や3D映像の迫力に感動したほかに、たとえば敵方の一兵卒だったフィンの、「正しいことをしたいんだ」という単純明快なセリフが心に残りました。
世界を動かすのは偉大なるだれそれだけではなく、一市民、一兵卒、一ホビットなのかもしれません。
映画館で観て以来、「アーケン石を胸に、故郷に葬られるトーリン」を観たいと、心待ちにしていた エクステンデッド・エディション 。11月に入手して、ようやく荘厳なお葬式シーンを鑑賞することができました。
ただお葬式自体はあっという間で、アーケン石もやっぱりちゃちな感じでしたけど・・・
ドワーフたちの戦車での戦いが長々と追加されたのは、楽しかったです。PJ監督がコメントで「昔観たイタリア映画のシーンにヒントを得た」と語っていた、刃つき車輪の戦車ですけど、あれはケルトの戦車ですね。ついこの間観た 、「第九軍団のワシ」 のケルト部族との戦いシーンで、似たような刃つき戦車が出ていましたもの。
それにしても、今年は(も?)世界でいろいろ物騒なことが相次いだせいか、 「ホビット」 を観ていて思うのは、普通の市民の、当たり前の一般常識や冷静さというものが、世界の平和には大事だなあ、ということ。
黄金に目がくらみ一族の結束やドゥリン王家への忠誠にしばられたドワーフや、宝石に目がくらみ排他的な森のエルフ、お金に目がくらむ湖の町の頭領やアルフリド、などなどが、自分たちの論理だけを追求し破壊的な方向へと突き進む。
これを引きとめようとするガンダルフの、大局的な賢者の知恵さえ裏目に出たり、聞き入れられなかったりするとき、負のベクトルにあらがい、戦争をとめうるのは、ごくふつうの近代市民意識を持つビルボやバルドの言動だけなのです。
トールキンもPJ監督も決して寓意的な作品を意図したわけではないけれど、ドワーフやオークやエルフの論理を観ていると、現実の世界を騒がすあんな大国、こんな国、あんな集団、こんな政治家のことがつい脳裏をかすめます。
我々もビルボやバルドのような一市民的常識で、偏った考え方に世の中がぶれていくのを阻止せねばならないような、そんな気がします。
ところで、今日は話題の 「スター・ウォーズ フォースの覚醒」 を観てきたのですが、なつかしい登場人物や3D映像の迫力に感動したほかに、たとえば敵方の一兵卒だったフィンの、「正しいことをしたいんだ」という単純明快なセリフが心に残りました。
世界を動かすのは偉大なるだれそれだけではなく、一市民、一兵卒、一ホビットなのかもしれません。
このページの素材は、 アンの小箱 さまです。
© Rakuten Group, Inc.