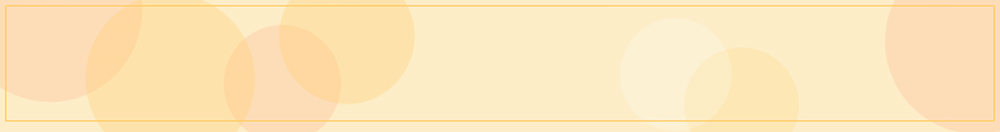リンドグレーン「ピッピ」
リンドグレーン「ピッピ」シリーズ他『長くつ下のピッピ』 シリーズ考
「ピッピ」シリーズのラスト・シーン――幼年時代の永遠化
『長くつ下のピッピ』
シリーズ考
(2005.6)
小学生の息子に読む“寝る前のお話”、ここ数日は 『長くつ下のピッピ』 でした。
言わずと知れたリンドグレーンのロングセラーですけど、2巻 『ピッピ船に乗る』 3巻 『ピッピ南の島へ』 になると、物語の内容が少し変わっていくのに、最近気づきました。
1巻では「世界一つよい女の子」ピッピの破天荒ぶりを描くエピソードが続きます。いじめっ子をやっつけたり、火事から子どもを助けたりもするけど本人は無自覚。「なんておもしろい火事でしょう!」なんて言ったりして。
ピッピは常識破りの破天荒で周囲をびっくりさせ、今までの価値観をひっくり返す“トリックスター”。
2巻になるとちょっと変化が。
ピッピは、弱者を助けるいわゆるヒーロー(女の子だけど)的要素が強くなってきます。乱暴者をこらしめるエピソードが多い。
そのうえ、ピッピ自身子どもでありながら、“子どもの守護神”的ふるまいをします。遠足についてきて皆を楽しませたり、お菓子を買いまくって子どもに配ったり。難破ごっこをした時など、トミーとアンニカにスリルを味わわせながらも、彼らの両親へ「子どもしんだとか ゆくえふめとか おもわないでね。…すぐかえる。ほんとよ。」という手紙を出しておくことを忘れません。
ただの破天荒なお騒がせ者から、守護神的ヒーローへ、進化です。だからこそピッピが去ろうとしたとき、子どもたちはあんなにも悲しく、トミーはピッピを連れ去る船に憎しみさえいだくのでしょう。
3巻でもピッピの人助けは続きます。
1巻ではイヤがられあきれられた彼女のウソ八百のおしゃべりも、3巻ではラウラおばさんをはげます妙薬となります。南の島へ行ったピッピは、ここでも子どもの守護神ぶりを発揮し、彼女がいるだけで皆は底抜けに楽しく遊ぶし、真珠泥棒をやっつける本物の冒険もできます。
最終章のおとなになりたくないピッピを読むと、ピッピは、子どもの姿をとって子どもたちの中に顕現した、“永遠の子どもの神さま”なんじゃないかな、と思います。
ピッピの本を楽しむとき、大人の読者も子どもになって、彼女をあがめ、いっしょに無邪気な理想郷で永遠に遊び続ける…その遊びと楽しみは、無限!
小学生の息子に読む“寝る前のお話”、ここ数日は 『長くつ下のピッピ』 でした。
言わずと知れたリンドグレーンのロングセラーですけど、2巻 『ピッピ船に乗る』 3巻 『ピッピ南の島へ』 になると、物語の内容が少し変わっていくのに、最近気づきました。
1巻では「世界一つよい女の子」ピッピの破天荒ぶりを描くエピソードが続きます。いじめっ子をやっつけたり、火事から子どもを助けたりもするけど本人は無自覚。「なんておもしろい火事でしょう!」なんて言ったりして。
ピッピは常識破りの破天荒で周囲をびっくりさせ、今までの価値観をひっくり返す“トリックスター”。
2巻になるとちょっと変化が。
ピッピは、弱者を助けるいわゆるヒーロー(女の子だけど)的要素が強くなってきます。乱暴者をこらしめるエピソードが多い。
そのうえ、ピッピ自身子どもでありながら、“子どもの守護神”的ふるまいをします。遠足についてきて皆を楽しませたり、お菓子を買いまくって子どもに配ったり。難破ごっこをした時など、トミーとアンニカにスリルを味わわせながらも、彼らの両親へ「子どもしんだとか ゆくえふめとか おもわないでね。…すぐかえる。ほんとよ。」という手紙を出しておくことを忘れません。
ただの破天荒なお騒がせ者から、守護神的ヒーローへ、進化です。だからこそピッピが去ろうとしたとき、子どもたちはあんなにも悲しく、トミーはピッピを連れ去る船に憎しみさえいだくのでしょう。
3巻でもピッピの人助けは続きます。
1巻ではイヤがられあきれられた彼女のウソ八百のおしゃべりも、3巻ではラウラおばさんをはげます妙薬となります。南の島へ行ったピッピは、ここでも子どもの守護神ぶりを発揮し、彼女がいるだけで皆は底抜けに楽しく遊ぶし、真珠泥棒をやっつける本物の冒険もできます。
最終章のおとなになりたくないピッピを読むと、ピッピは、子どもの姿をとって子どもたちの中に顕現した、“永遠の子どもの神さま”なんじゃないかな、と思います。
ピッピの本を楽しむとき、大人の読者も子どもになって、彼女をあがめ、いっしょに無邪気な理想郷で永遠に遊び続ける…その遊びと楽しみは、無限!
「ピッピ」シリーズのラスト・シーン――幼年時代の永遠化
(2005.6)
「ピッピ」シリーズ最終巻 『ピッピ南の島へ』 の最終章のラスト・シーンについて、心理学者の河合隼雄が、ろうそくを吹き消したピッピが消えてしまうと思った、と書いています( 『子どもの本を読む』 、先日、図書館で拾い読みしました)。
私は子どものころピッピが大好きで、何度もくり返して読みましたが、ピッピが消えてしまって明日からはいなくなるだろうとは、一度も思いませんでした。
なぜって、その日ピッピたちは“大人にならない、生命の丸薬”を飲んだのです。そして作者は、彼らがいつまでも子どものまま、毎日楽しく遊び暮らすでしょう、と書いているのです。だから、ピッピは消えっこないはずです。
ところが、ピッピは永遠に今のままだ、とくどいほどくり返されているにもかかわらず、一抹の不安、寂しさ、何かが確実に終わったような喪失感が、このラスト・シーンには確かに漂っています。
それは、幼かった私にも感じられ、なぜわざわざこんなさびしい終わり方をするんだろう、大人ってわからないな、と思ったものでした。
つまり、その夜、トミーとアンニカが子ども部屋の窓から見ると、ピッピの家の台所で、彼女がろうそくの火をながめながらすわっているのが見え、
「ピッピは、なんだかさびしそうにみえるわね。」 ――リンドグレーン『ピッピ南の島へ』大塚勇三訳
そして、
「もしピッピがこっちをむいたら、ぼくたち、手をふろうよ。」…でも、ピッピは、夢みるような目つきで、じっとまえをみつめているばかりでした。
それから、ピッピは、ふっと、火をけしました。 ――『ピッピ南の島へ』
河合隼雄の本を読んで、やっと大人の私にはわけがわかったように思います。
どんなにしがみつこうとしても、楽しい幼年時代には確実に終わりが来るということ。それが本能的にわかっているからこそ、ピッピと仲間たちは“生命の丸薬”を飲むのですが、できることはただ、幼年時代の黄金の思い出を心の中で永遠化していつまでも持ち続けること、それだけなのです。
トミーとアンニカの幼年時代は終わろうとしているのでしょう。けれどピッピと遊んだすばらしい思い出は、“生命の丸薬”として結晶され、彼らの心の中では永遠に生き続けるのでしょう。
同じような永遠化が、A・A・ミルン「プー横丁にたった家」の最終章でも語られています。クリストファー・ロビンは幼年時代の終わりに、仲良しのプーを連れて“魔法の丘”に出かけます。
「ふたりは、いまもそこにおります」
あの森の魔法の場所には、ひとりの少年とその子のクマが、いつもあそんでいることでしょう。 ――A・A・ミルン 『くまのプーさん・プー横丁にたった家』 石井桃子訳
このラスト・シーンも、子どものころ私には理解不能でした。今では、わかるような気がします。私の幼年時代も、同じように永遠化されて、私の心の中にしまわれているからです。
幼年時代の永遠化。大人になってから初めて味わえる、幼年童話の醍醐味なのです。
「ピッピ」シリーズ最終巻 『ピッピ南の島へ』 の最終章のラスト・シーンについて、心理学者の河合隼雄が、ろうそくを吹き消したピッピが消えてしまうと思った、と書いています( 『子どもの本を読む』 、先日、図書館で拾い読みしました)。
私は子どものころピッピが大好きで、何度もくり返して読みましたが、ピッピが消えてしまって明日からはいなくなるだろうとは、一度も思いませんでした。
なぜって、その日ピッピたちは“大人にならない、生命の丸薬”を飲んだのです。そして作者は、彼らがいつまでも子どものまま、毎日楽しく遊び暮らすでしょう、と書いているのです。だから、ピッピは消えっこないはずです。
ところが、ピッピは永遠に今のままだ、とくどいほどくり返されているにもかかわらず、一抹の不安、寂しさ、何かが確実に終わったような喪失感が、このラスト・シーンには確かに漂っています。
それは、幼かった私にも感じられ、なぜわざわざこんなさびしい終わり方をするんだろう、大人ってわからないな、と思ったものでした。
つまり、その夜、トミーとアンニカが子ども部屋の窓から見ると、ピッピの家の台所で、彼女がろうそくの火をながめながらすわっているのが見え、
「ピッピは、なんだかさびしそうにみえるわね。」 ――リンドグレーン『ピッピ南の島へ』大塚勇三訳
そして、
「もしピッピがこっちをむいたら、ぼくたち、手をふろうよ。」…でも、ピッピは、夢みるような目つきで、じっとまえをみつめているばかりでした。
それから、ピッピは、ふっと、火をけしました。 ――『ピッピ南の島へ』
河合隼雄の本を読んで、やっと大人の私にはわけがわかったように思います。
どんなにしがみつこうとしても、楽しい幼年時代には確実に終わりが来るということ。それが本能的にわかっているからこそ、ピッピと仲間たちは“生命の丸薬”を飲むのですが、できることはただ、幼年時代の黄金の思い出を心の中で永遠化していつまでも持ち続けること、それだけなのです。
トミーとアンニカの幼年時代は終わろうとしているのでしょう。けれどピッピと遊んだすばらしい思い出は、“生命の丸薬”として結晶され、彼らの心の中では永遠に生き続けるのでしょう。
同じような永遠化が、A・A・ミルン「プー横丁にたった家」の最終章でも語られています。クリストファー・ロビンは幼年時代の終わりに、仲良しのプーを連れて“魔法の丘”に出かけます。
「ふたりは、いまもそこにおります」
あの森の魔法の場所には、ひとりの少年とその子のクマが、いつもあそんでいることでしょう。 ――A・A・ミルン 『くまのプーさん・プー横丁にたった家』 石井桃子訳
このラスト・シーンも、子どものころ私には理解不能でした。今では、わかるような気がします。私の幼年時代も、同じように永遠化されて、私の心の中にしまわれているからです。
幼年時代の永遠化。大人になってから初めて味わえる、幼年童話の醍醐味なのです。
このページの素材は、 アンの小箱 さまです。
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- お気に入りの漫画は??
- 「NARUTO-ナルト-」25周年記念の熱狂…
- (2024-09-21 15:03:09)
-
-
-

- 私の好きな声優さん
- 声優の篠原恵美さん、病気療養中に死…
- (2024-09-12 00:00:14)
-
-
-

- 連載小説を書いてみようv
- 麗しき皇太子妃 第1話:新生活―前編―
- (2024-09-27 17:24:29)
-
© Rakuten Group, Inc.