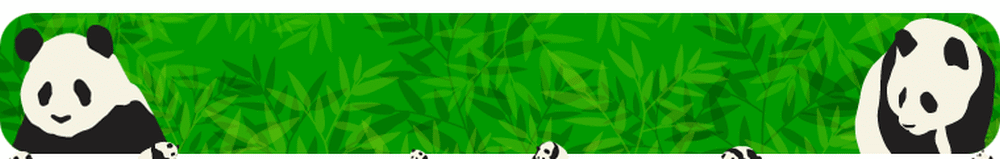べるぜバブ小説『嫉妬』
べるぜバブ『嫉妬』
「幸せそうな奴って、なんかムカつく。」
夏目は3階の教室の窓から幸せそうに笑う古市を見ていた。
古市は校庭のベンチに座っていた。隣には当然のように
男鹿がいた。男鹿に頭を撫でられて、古市は照れたように
笑っていた。
「あいつら、またイチャついてやがる。」
神崎が夏目の横の窓から顔を出すと、外を見て言った。
「リア充、死ね。俺はリアルに充実してる奴が大嫌いだ。」
もてない男ほど他人を羨んで呪詛を吐く。夏目はニヤリと笑って、
こう言った。
「そうだ。いいこと思いついた。前に男鹿の弱点はないかって
神崎、言ってたよね?古市、あいつを痛めつけたら、男鹿に
復讐できるんじゃないかな?」
「おっ、それ、いいねぇ。夏目、ナイスアイディア。じゃ、早速、
城山に命令出しとくか。お~い。城山、いるか?」
神崎が教室を見渡して、城山を呼ぶと、城山が飛んで来た。
「はい。何ですか?神崎さん。」
「おまえ男鹿に見つからないように、古市、拉致ってこいや~」
「えっ?!あっ、はい。了解しました。」
城山は驚いた顔をしたが、神崎の言う事には逆らわなかった。
「なんか面白くなりそうだね。」
夏目は神崎の顔を見て、ニヤッと笑った。
この男は心底腐っているから面白い。他人の幸せを羨んで
破壊する行為は卑劣だと思う。でも、自分の不幸を嘆くより
他人をいたぶるほうが数倍楽しい。総ての者をひれ伏させる
実力がありながら、石矢魔の頂点に立つことを考えず、
己の道を生きる男鹿もムカつくけど、顔が良いだけで、
実力もないくせに男鹿にくっついて、誰の配下にも加わらない
古市はもっとムカつく。天真爛漫に笑う綺麗な顔を滅茶苦茶に
引き裂いて泣かせてやりたいと夏目は思った。何の悩みもなく
幸せそうにしてる奴を地獄の底に突き落とすのは実に楽しい。
卑怯者と悔しそうに罵る顔が見えたら、最高だ。
くだらない人生のくだらない日常の中で、ちょうどいい
暇つぶしを見つけたと夏目は思った。
何も知らない古市は恋人との楽しい時間に幸せを感じて
笑っている。キラキラと輝く初夏の陽ざしは眩しくて、
青空には飛行機雲が浮かんでいた。
真夜中の教室に響く卑劣な笑い声。両手両足を縛られて、
猿轡を咬まされた古市は生贄の儀式に使われる子羊のように
震えていた。夜、一人でこっそりと家から抜け出して、男鹿に
会いに行く途中、古市は城山に殴られて気を失い、拉致されて
しまったのだった。目が覚めると、古市はナースのコスプレに
着替えさせられていた。右手首と右足首、左手首と左足首を
それぞれ包帯で縛られて、床に座らされ、目の前に並べられた
おぞましい道具に恐怖して怯えて震えていたのである。
「ナースの格好が良く似合うよ。男鹿だけじゃなくて、たまには
俺達とも遊んでよ。お医者さんごっこは好きか?」
夏目は古市のスカートの裾をまくり上げると、ナイフで
パンティストッキングを引き裂いた。そして、あらわになった
古市の下半身を摘み上げるようにして、包帯をきつく巻いて
袋まで縛ると、媚薬入りローションをスポイドで瓶から吸い上げ、
スポイドの先を古市に差し込み、注入した。本来吐き出す
場所から媚薬を体内に注入され、古市は呻いた。だが、
夏目は嘲笑うかのように親指と人差し指で尿道を広げ、
導尿カテーテルをゆっくりと差し込んだ。声をあげることも
許されず、猿轡を噛みしめて苦痛に耐える古市に神崎たちは
欲情した。夏目は冷静にカテーテルを膀胱まで入れると、
携帯を取り出して、写真を撮った。
「放尿したら、それも撮って男鹿に送りつけてやる。」
その言葉に古市は目を見開いて、一瞬、逃げようと動いたが、
縛られているので、逃げられるはずもなく、逆に腰を浮かせた
拍子にカテーテルがズレて尿道に激痛が走ったのか、
呻き声をあげたかと思うと、放尿した。
「ハハハ・・・おしっこ漏らしてやがる。」
神崎が腹を抱えて笑った。古市は動揺して泣き出したが、
排尿を止める事はできなかった。
全部、尿を出し切った後、泣きじゃくる古市に夏目はこう言った。
「よく撮れたよ。古市は素質があるのかな。今すぐ男鹿の携帯に
送りたいところだけど、まだ診察が終わってないからね。
3人でまわした後に送信してやるよ。」
夏目は古市から導尿カテーテルを抜き取ると、後ろを向かせた。
そして、夏目は
「注射は好きかな?」
と言って、媚薬入りローションの入った注射器を古市の尻に
差し込んだ。元々浣腸用の注射器なので、否応なく古市の
身体にはローションが入っていく。たっぷりと媚薬を注入した後、
夏目は玩具の聴診器で古市の下半身を診察した。古市は
媚薬のせいで包帯の上から刺激されただけで感じてしまった。
しかし、大きくなると同時に再び屈辱的な痛みが古市を襲った。
まだ大きくなっていない内に縛られたせいで、包帯がめり込んで
くい込むのだった。
「痛いかい?こんなに大きくして、悪い子だ。」
夏目はピシッとお尻を叩くと、古市の蕾に聴診器を当てた。
ひんやりとする金属の感触が媚薬で火照った身体に心地良い。
古市が無意識に尻を突き出すと、夏目はこともあろうに聴診器を
蕾に沈めようとした。玩具とはいえ、500円玉くらいの大きさの
聴診器を入れられて、古市は顔を真っ赤にして困惑した。
不思議と痛みはなかったが、聴診器の金属の部分を全部
入れられて、体内の音を聞かれていると思うと、恥ずかしさに
震えてしまった。
「感じるのか?」
夏目はそう言うと、聴診器を指で更に奥へと押し込み、管の
部分を掴んでグルグルっと掻き回した。内壁に聴診器の管が
当たる度に卑猥な音を立てて蕾からローションが零れ落ちる。
「コラコラ。こぼすなよ。」
と言って、聴診器の管が垂れ下がった尻を夏目は叩いた。
「聴診器でよがる奴って初めて見たぜ。」
見物していた神崎達はゲラゲラと笑っていた。
古市は拘束された痛みと羞恥プレイによる快感とに苛まれ、
何度もイキそうになった。だが、そのたびに根元からきつく
縛られた包帯が古市を苦しめる。古市は呻きながら無意識に
腰を揺らしていた。
「もう、入れて欲しくなったのか?」
夏目が聴診器をズルズルっと引き抜いて言った。
「欲しくてたまらないなら、入れてやるよ。」
夏目は古市の尻を両手で押し広げて挿入した。
「ウーッウーッウーッ」
と、古市が呻くと、夏目は
「なんだか猿轡してると、色気のない声で呻くな。猿轡外して
やるから、いい声で啼けよ。」
と言って、挿入したまま古市の両肩を掴んで身体を起こし、
後座位の格好で深く貫きながら猿轡を外した。すると、
古市は苦しそうに息をして、こう言った。
「あっ。包帯も外してくれよ。あ~」
「注文が多いな。逃げないって約束するなら包帯を外してやる。」
「分かった。約束するから。あ~。早く外して。」
夏目は床に転がっているナイフを片手で拾って、両手両足を
縛っていた包帯を切って外した。だが、古市の身体の中心を
縛っている包帯は外してはくれなかった。
「あっ、全部とってくれよ。」
「もう少し待ちな。男鹿が来たら解いてやるから。あ、そうそう。
写メまだ送ってなかったっけ?神崎、代わりに送っといてくれ。」
「了解。」
神崎は男鹿の携帯に送信した。
「男鹿のやつ、絶対、怒って飛んでくるぜ。でも、あいつ
バカだからな。場所が学校の教室だって分かるかな。
意外と翌朝まで来ねぇかもな。」
古市は絶望の中で夏目に犯された。
「あ~、ああっ、イク。ほどいて。あっ、もうダメ。ああ~」
腰を振り乱して喘ぐ古市に夏目は
「そんなにイキたい?じゃあ、解いてやるよ。」
と言った。夏目が包帯を解くと、
「あっ。ああっ。あああ~」
古市は声を上げてあっけなく果てた。夏目は呆れたように
笑うと、古市にキスをした。ねっとりと舌を絡ませて、
イッたばかりの敏感な身体の中に欲望を放出した。
古市の身体は果ててもまだ快楽を求めているかのように
萎えることなく、酔いしれたように濡れていた。古市は長い
ディープキスの後、ガラガラッと音がした方向に視線をやった。
教室の入口に息を切らして駆けつけた男鹿が立っていた。
「意外と早かったね。ひょっとして、送信する前から探してた?」
夏目が顔面蒼白になった古市を膝の上から退かして、
男鹿に聞いた。
「当たり前だ。古市を返せ。」
鋭い目つきで睨む男鹿に夏目は
「そう簡単に返すわけにはいかないな。」
と言って、ナイフを古市の顔に押し当てた。
「この可愛い顔に傷をつけたくないなら、言う事を聞きな。」
すると、ナイフに怯えた古市は泣き出して、
「男鹿、助けてくれ。」
と、懇願した。自分のいやらしい姿を男鹿に見られて、古市は
軽いパニックを起こしたのだろう。男の膝の上で腰を振る淫らな
自分はなかったことにしたいと思ったのか突然殺されかけた
被害者のように助けを求めて泣き出したのだった。
「分かった。言う事をきくから、古市を放せ。」
「随分と物分りが良いようだな。男鹿。」
夏目はニヤッと笑って、こう言った。
「お前が古市の代わりになるなら、古市を放してやる。
お前は愛する者の為に自分を犠牲にすることができるか?
もちろん、たった一回だけで許してやるよ。お前が大人しく
抱かれたら、二度と古市には手を出さないって約束する。
どうだ?この条件が呑めるか?できないなら、かかって来いよ。
その代わり、お前が俺を殴る前に古市の顔はナイフで
切らせてもらう。どちらにするかはお前が今、決めろ。」
決めかねて俯いてしまった男鹿を見て、夏目は満足そうに笑った。
「アハハ・・・やっぱり、その程度か。おまえらなんて、所詮、
恋愛ごっこなんだよ。自分を犠牲にしてまでこいつを守る
価値はないって知ってるんだな。おまえ、もう帰れ。古市は
俺がもらう。一生、俺のペットにして可愛がってやるよ。」
夏目は古市の頭を掴んで顔をペロッと舐めた。古市は
怯えたままじっとして、すがるような目で男鹿を見上げていた。
「こいつは中坊の頃から男を知っている淫乱だ。中一の時に
先輩達にまわされたショックでグレたって噂だぜ。そんな奴、
助けたって今更だろ?お前がバカじゃなかったって分かって
安心したよ。お前はとっとと家に帰って赤ん坊の子守でもしてな。」
「クソッ!俺のことはいい。でも、古市のことはバカにするな!」
男鹿は拳を握りしめて、夏目に殴りかかった。
「おっと!これ以上近づいたら、顔を切るぞ!」
と、夏目は古市の頬にナイフを押し付けた。男鹿は慌てて、
拳をピタッと止めた。
「よし。それでいい。あとはこのまま教室から立ち去るか服を
脱ぐかのどちらかにしろ。それとも脱がせて欲しいのか?」
夏目は男鹿をからかうようにニヤニヤと笑いながら言った。
「わかった。脱げばいいんだろ。」
男鹿は覚悟を決めて、服を脱ぎ捨てた。男鹿の鍛え抜かれた
身体に神崎がヒューっと口笛を吹いた。
「パンツも脱げよ。」
夏目は容赦なく目を輝かせて命令した。だが、男鹿は躊躇い
があるのか下着を脱ごうとしなかった。すると、
「なんだぁ?脱がせてほしいのかぁ?」
神崎が寄って来て男鹿の腰に手をまわした。
神崎は下着の中に手を入れて、いきなりぎゅっと握りしめた。
「うっ、うう・・・や、やめろ!」
男鹿は思わず手を振り払った。
「おいっ。古市を助けたくないのか?大人しく言う事を聞けよ。」
神崎が男鹿を押し倒し、抗う男鹿の下着を無理やり引き剥がす
ように脱がせた。まだ幼さの残るほんのりピンク色のそれを
神崎は掴んで皮を引っ張り頭を出すと、口に含んで舐め始めた。
「あっ。」
思わず声を出してしまった男鹿に神崎は
「感じるのか?」
と聞いた。男鹿は
「ち、違う。」
と否定はしたものの、男鹿のそれは立ち上がりかけていた。
「もっと気持ちよくしてやる。」
と言うと、神崎はローションの小瓶の先を男鹿に突っ込んだ。
「うっ。ううっ。あっ。」
冷たいローションが尻に入ってくると、何故か身体が熱くなった。
「随分と美味そうに飲み込むな。媚薬入りのローションは
美味しいか?男鹿も古市と同じビッチだな。ハハハ・・・」
神崎は笑いながら、男鹿の尻を掴んで左右に押し広げると、
まだ慣らしていない蕾を一気に貫いた。
「うぁあああああ~」
男鹿が物凄い悲鳴を上げた。痛がる男鹿に神崎は
「なんだ。処女だったのか?ゴメン。ゴメン。血が出ちゃったなぁ。
へっへ・・・痛いか?」
と嬉しそうに聞いた。固く閉ざしたままの男鹿の蕾は無惨にも
引き裂かれ、鮮血が溢れ出ている。神崎が動く度に鋭い痛みが
男鹿を襲う。激痛に苦しむ男鹿に夏目はこう言った。
「大袈裟に騒ぐなぁ。ローション使ってやってんだから、内臓の
ほうは大丈夫なはずだ。入口が少し切れただけだろ?フッ。
意外と男鹿って痛みには弱いんだ。喧嘩強い奴ほど痛みにも
強いから、調教次第では立派な犬になると思ったのにな。
残念だよ。それに比べて、古市はいい犬っぷりだったよ。
快楽に弱いせいか腰振って喜んでた。男鹿も見ただろう。
気持ち良さそうに俺に抱かれてキスしている古市を!
アハハ・・・誰にでも犯らせる奴の為に処女を差し出すなんて、
とてつもない馬鹿だな。」
嘲笑う夏目の横で古市は泣いていた。男鹿は教室の床に
両手をついて、後ろを犯されている自分を惨めだと思ったが、
後悔はしなかった。子供の頃から頭が悪いとからかわれて
喧嘩ばかりしていた自分に初めて出来た親友が古市だった。
古市は怖がらずに初めて優しく接してくれた友達だった。
キスをして、身体を重ねたのも古市が望んだからで、自分から
童貞を捨てたいとか思ったわけではなかった。男でも女でも
関係ない。ただ自分の傍にいてくれる人が欲しかった。
喜びも悲しみも分かち合える大切な人を自分を犠牲にしてでも
助けなくてはならないと男鹿は考えた。暴力で解決できるなら
とっくにそうしている。だが、こういう奴らはやられたらやり返すで
キリが無い。自分の身体を差し出す事でもう古市に手を出さない
というのなら、それでもいいと男鹿は思った。血を流しながら
男鹿は神崎が果てるのをじっと待った。神崎は男鹿を征服した
喜びに夢中になって腰を激しく打ち付けて、10分で果てた。
ドクドクと男鹿の体内に欲望を吐き出した神崎に
「なんだ。もう終わりか?早いな。」
と、夏目が呆れたように言った。
「うるせぇ。こいつすっげぇいいからよぉ。こいつの中、狭くて
食い千切られそうだったんだぜ。夏目、お前もやるか?」
「遠慮しとくよ。男鹿は趣味じゃない。俺より城山にやらせろよ。」
「そっか。じゃあ、俺、今度は古市とやるから、古市貸せよ。」
神崎はそう言うと、古市に近寄り、腕を掴んで引っ張り、
古市を引き寄せた。
「おいっ!何やってんだぁ?!古市には二度と手を出さない
って約束だろ?古市を放せ!」
男鹿は尻から血を流しながら、ゆらりと立ち上がって言った。
「何だよ!約束したのは夏目で俺じゃねぇぞ。俺は一言も約束
してねぇからな。へっ!さっきまでひいひい啼いてたくせに!
いきがるなよ!おいっ!城山さっさとやれよ!」
城山は男鹿を取り押さえようとしたが、男鹿は一撃の裏拳で
城山の顔面を叩き潰した。鼻をへし折られた城山はそのまま
気を失って倒れてしまった。男鹿は城山なんか眼中にないと
いったかのように神崎のほうへ歩いて行った。
「く、来るな!これ以上近づいたら、古市の顔を切るぞ!
な、夏目!ナイフ貸せ!」
神崎は焦って、夏目が持っているナイフをひったくるように
奪い取ると、古市の顔にナイフをあてようとした。しかし、
どういうわけかナイフを持った手が上に上がらない。神崎は
自分の手元を見て、ぎょっとした。男鹿がナイフの刃を掴んで
握りしめていたのだった。男鹿の手から溢れる血がナイフを
伝って床に滴り落ちていた。男鹿は力任せに血だらけの手で
神崎からナイフを奪い取った。
「ひいっ。」
恐怖に慄いた声をあげた神崎に男鹿は
「ひいひい言ってんのはてめぇのほうじゃねぇのか?」
と、凄みのある低い声で睨みつけて言った。そして、古市を
神崎から引き離し、自分の後ろにやると、思いっきり力を込めて
神崎を殴った。男鹿に殴られた神埼は窓ガラスをぶち破って
校舎の外に飛んでいった。
夏目はしばらく何もしないで黙って見ていたが、やがて
こう言った。
「俺のことは殴んないの?」
「ああ。」
男鹿は少し考えてから返事をして、血のついたナイフを
夏目に手渡した。
「返すよ。顔を切るなら俺の顔を切れ。その代わり、
古市には手を出すな。」
「ハッ!バッカじゃねぇの?!」
男鹿の予想外な言動に夏目は眉をつり上げた。だが、男鹿は
「ああ。馬鹿だよ。俺は。でも、そんな俺でも古市だけは
守りたいんだ。」
と言った。すると、夏目は呆れたようにこう言った。
「お前ってホント、バカだな。神崎にそんなこと言ったら、顔
切り刻まれるぜ。」
「だろうな。でも、俺はあんたに言ってるんだ。」
「もし、俺が古市をまた襲ったら、どうする?襲わないって
保証はどこにもないぜ。」
「その時は夏目を殺す。」
男鹿は真剣な眼差しで言った。
「本気なんだな。もう、いい。消えろ。お前ら見てると、
イライラする。もう二度と二人とも俺の前に顔出すな。」
「分かった。」
男鹿は古市を連れて教室を出た。
二人を黙って見送った夏目は独り取り残された気分になった。
夏目はけっして男鹿に臆したわけではなかった。退屈な人生に
ピリオドを打つのも悪くはないが、そこまでする必要がないと
思ったのだ。何があっても二人の仲は引き裂けないという事が
痛いほど身に沁みて分かったから、古市を諦める事にしたの
だった。完敗だと夏目は思った。自分には到底真似できない。
男鹿の古市に対する無償の愛に成す術も無く打ちのめされた。
夏目は今まで生きてきて、欲しいと思うものが特になかった。
でも、古市だけは欲しかった。毎日、教室の窓から古市を見て
いたのを男鹿は知っていたのかもしれない。古市を抱いたら、
手に入ると思ったのに、結局、何も変わらなかった。永遠に
手に入らない相手を愛し続けるほど馬鹿じゃない。諦めて
正解だと夏目は思った。初夏の夜風は涼しくて、夜空には
綺麗な星が浮かんでいる。もし、流れ星を見つけたら、
二人が別れるようにお願いでもしてみるかと夏目は思った。
これは恋なんかじゃない。ただの醜い嫉妬だ。いつまでも
気が晴れない心を持て余しながら、夏目は何度も自分に
言い聞かせた。片想いにも至らない夏目の淡い失恋を
夜空に輝く星たちは静かに笑っていた。
(完)

© Rakuten Group, Inc.