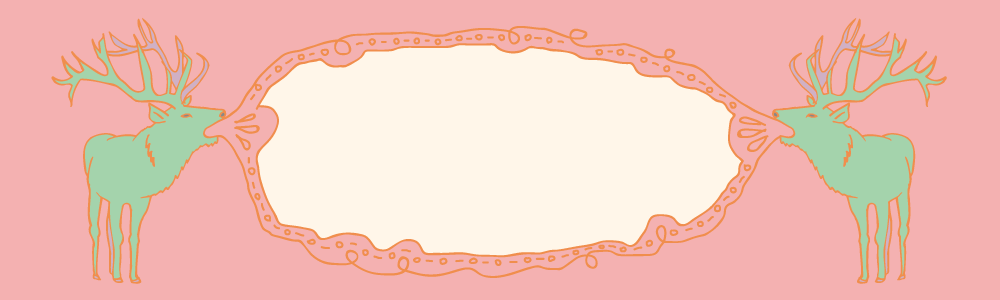幸子
五人姉妹の末娘幸子は、近所に嫁いだ長女の里実とはひとまわり以上年齢が違う。すぐ上の姉の四女涼子でさえ、幸子の七つ上だ。年の離れた姉達とは話すこともなく、幸子は、家に居場所を見つけられないでいた。母の危篤を知り、深夜の病室に駆けつけた時もそうだ。既に息をひきとった母のベッドを、父と姉達が囲んでいた。不釣合いに煌々と明るい蛍光灯の下で、自分以外が一様に、同じ重さで沈んでいた。三女の美春に腕を引かれ、母の枕元まで近づいたが、調和のとれた空間の真中に侵入した居心地の悪さに、涙も出なかった。
幸子が玄関でのろのろとブーツを脱ぎ終わった頃、勇子はもう暖房のきいた台所で、美春が用意した昼食をほおばっていた。
「今年は母さん、お花見できなかったわね」
美春が、コンロにやかんを乗せてつぶやいた。母里子は、コンロの上の窓から見える桜が満開になると、桜餅を食卓に並べて家族を呼んだ。物心ついた頃からのことで、幸子も、この時ばかりは、四人の姉と並んで桜を眺めた。話題はいつも、桜の開花が早いとか遅いとかそんなことで、子どもにはさして面白くもない。それでも幸子は、桜が芽吹く季節になると、毎日桜を見上げては、満開の日を待ったものだった。
「あんたが家を出てからも、母さん毎年桜餅を七つ買ってたのよ」
勇子にポンと背中を叩かれた幸子は、ふんと鼻を鳴らして言った。
「うそばっかり」
「本当だ」寡黙な父勇造が、ぽつりと言った。
「桜が満開になったから、帰ってくるんじゃないかってね」
里実がそう言いながら、バッグから包みを取り出した。桜餅だった。
「幸子が来るっていうから、季節はずれだけど作ってみたの」
「いいわねえ。お供えしてくる」
美春が立ち上がり、いつもクールで幸子に無関心に見える涼子が、うわずった声で
「二階でちょっと仕事してくる」
と言いおいて、俯いたまま台所を出ていった。
食卓の六つの桜餅を見つめる幸子が、小声で繰り返した。
「うそばっかり…」
それに答える風でもなく、勇造は続けた。
「四十を超えて赤ちゃんを授かるなんて、我が家に幸せを運んできてくれた子だって、母さん大喜びだった。それで、『幸子』」
幸子は言葉を失くした。平凡で、期待も思い入れもない名だと思っていた。静寂が流れ、やかんがシュンシュン湯気をあげた。
コートを着た美春が、廊下でコホンと咳払いをした。婚約者の林を、駅まで向かえに行くらしい。美春が結婚して家を出れば、勇造は仕事一筋の涼子と二人ぐらしになる。涼子にしても、いつ良い結婚相手がみつかってもおかしくない年齢だ。長女の里実は、勇造の暮らしが心配でならない。
「大丈夫だ」
と勇造が言い終わらないうちに、
「あたしがいるじゃん」
幸子が小さく手を挙げ立ち上がった。食卓に背を向けてやかんの湯を急須に注ぐ。閉めきった窓のすりガラスを、風にしなる桜の枝が、コツンと叩くのをきっかけにして、幸子は言った。
「ねえ、春にはもっとおいしい桜餅食べようよ」
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- 風水について
- クローゼットで運気アップ♪
- (2024-11-11 18:00:07)
-
-
-

- handmadeのある暮らし。
- バーゲン本 SALE50%OFF カットクロス…
- (2024-11-09 12:39:06)
-
-
-

- 今日のお出かけ ~
- 小川町観光案内所(埼玉県小川町)
- (2024-11-15 23:09:06)
-
© Rakuten Group, Inc.