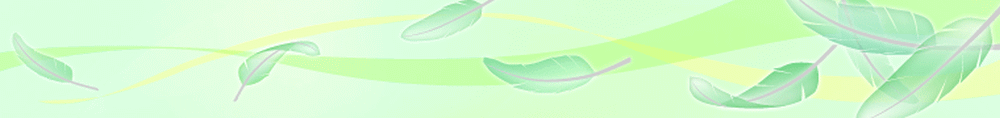*母が遺した言葉
短歌(合同歌集「槙」より)
昭和52(1977)年8月15日発行

白き曙
柊花 作
うつつとも夢ともまがふ虚しさの覚めたるあとの白き曙
枕上のスタンドの灯を消さむとてのべしかひなに春の冷えよる
ほしいまま舞ふ春雪の庭隅に万年青の残り実赤くするどし
水仙のあまた生ふれど蕾まだほぐれむともせず寒たちかへる
鉢の薔薇匂ふ厨辺病む夫に少しばかりの粥を炊き居り
晴るるかと思いし空の翳りきてにぶき光のものの芽に満つ
まだ解けぬ山ひだの雪ふかくして穂高を流るる雲は夏めく
つゆ冷えのいたみに堪えで散りしきる薔薇垣の花の白き裏町
冷却南下の兆しならむか七月の半ばを過ぎて寒き雨降る
姫娑羅の花見に来よと招かれし君が菩提寺山鳩の啼く
天上の白きは娑羅の花なりと君が指さす夏の夕暮れ
睡蓮の水底流るる雲遠く背を吹く風の夕冷えとなる
人居らぬ公園の広場風生れて銀杏落葉の黄なるさざなみ
永らへて黄を尽したる秋の蝶風立ちくればよろめく如し
渓流に石を抛りて白き水をどるを見つつ澄みし身辺
忘却や掛け居る眼鏡を更にまた探さむとする老いたるは憂し
夜光時計の青き文字盤見つめつつ真夜を覚め居てまた眠りつぐ
送り来しカラー写真の色冴えて病みにし母とは思はれなくに
たまきはる命は所詮灰なりと詠ひし人の今は世に亡し
一杯の酒あれば病むを忘るといふ夫の酒は止むべくもなし
いたはり合う齢となりぬ薬飲む夫に白湯つぐまだ寒き朝
老いぐせに眠れぬ夜半風鈴の音絶え絶えに運ぶ風あり
里馴れの鳥来て遊ぶ葉かげより啄む木の実ほろほろと散る
屋上より望む家並み平らけく棟寄せ合へる灯はあたたかし
はるかなる電線工夫の黒き影なにあやつるや宇宙人めく
吹き晴れし空の蒼さのきはまりて骨組みあらく裸木そびゆ
枯れ急ぐこのあたり戦場が原車の速度ゆるめてめぐる
北風のゆさぶり上げる陸橋を肩尖らせて急ぐ人人
印幡沼の山なみ低くたたずみて風すき透る寒は来りぬ
冬沼は変貌もなく夕暮れて平たき黒き光となりぬ
布団干す蒼き空欲し残業のある日と告げて出で行きし子に
取り合ひし手のぬくもりの幼き日吾子は二十五歳となりぬ
滋賀の湖ふり返りふりかえり別れ来て吾子住む街の見えずなりゆく
帰省了へ戻りゆきたる子の部屋の窓は灯らず寒の月射す
テレビ画面華麗に消えて永平寺の雪より除夜の鐘わたりくる
断らざればかくまで心いたまぬを真夜覚めて聴く窓の笹鳴り
父の職継がずと言ひ切り音量をあげて「運命」くり返し聴く
五千屯救援米積むアリゾナ丸ビアフラ指してわたつみわたる
病む身には未来図なしといふ夫の命守りてひたすらに生く
同じ愚をくり返しつつ過ぎ来しよこの老いざまにかなしき師走
捨て水の落合ふところ光りいて寒き夕べの裏町に入る
繁華街のマーチに思はず歩が合ひて通り過ぐれば空しさの湧く
枸杞の実の赤く熟るる日が愛し秋されば恋ふふるさとの庭
別るる日君より賜びし鉢の伽羅ぬくき日をみて庭に移さむ
見上ぐれば風渡るのみ頼政公自刃の庭に春逝かむとす
豊頬にさしのべしかひな柔かく弥勒菩薩の思惟の半眼
1915(T4).6.9 生
1996(H8).6.9 没
(Y.N)
佐々木信綱は「歌は第一に心、第二に言葉、そして第三に調べである。歌のよしあしは、心と言葉と、調べとの全ての調和で決する。どれ一つも切りはなすことはできない」ということをいっている。この道を極め、求めて行くことはなかなかむつかしい。
短歌が西洋にも東洋にもない文化で、まったく日本独自の短歌型として、二千年の久しきにわたって、わたし達の祖先が生きて来た喜びと悲しみの歴史を歌が告げて来ている文字を、私もまた、生きてゆく日に、いつの「時」か、身震いする感動の歌を作って見たい念じている。しかしその一瞬に心をふるわす感動であったとしても、時とともに、ふわっと溶けてしまって、あとに残らない短歌であってはならないと思われる。
それぞれが個性と環境に即して「瞬時」の感動と美を求め、詠いこまれた人人が綴られた、合同歌集の発刊を心から喜ぶ。
(S.K)
歌作に苦渋を感じることのみ多かった私にとって八千代市短歌会から愉しい短歌を味わうことができたのは望外である。それは結社閥もなく、歌壇のスポットライトを浴びようという野心もなく、短歌が安息であり、自分を充足し新しくしてゆくかけがいのない場であるという市民の純粋な願いが歌会全体に漲っていたからであろう。そういう人達の素朴な言葉のあいだにかげのように生まれるかすかな「心のゆらぎ」が数々の佳作となった。それは、初め趣味性を帯びたものから次第に文学性をもつものに変わり、わずか月一人一首というささやかな営為が、四年を経て、こんなに充実した合同歌集を生んだのである。
労働の協同作業を契機として生まれた日本の詩歌がやがて万葉集というアンソロジーに結実した過程は日本文化の原点といわれているが、われらのこの一冊の「集団詩」も八千代市の文化の原点になるだろうことを自負して良いのではなかろうか。そして短歌が数少ない天才のためのものではなく庶民みんなのものであることの喜びをいま秘かに噛みしめている私なのである。
合同歌集『槙』より
平成元年
わが家継ぐ鎖のひとつ呱々の声あげてうれしき平成元年
新生児のみとりを終へて発つといふ君が空路に障りあらすな
耳澄ます幼に問へば花の声聞きたしと言へりひたむきの顔
庭土を踏みしめ花に手触れつつアパート住ひの幼よろこぶ
祖母なるに久に逢はねば見詰めいて終に泣きだす絆は知らず
春雪は溶けやすくして忽ちにショパンの「雨だれ」の曲を奏づる
水鉢におりきし野鳥何に怯ゆ右顧左眄しては水を飲む
絢欄の薔薇の花芯に陰生れて梅雨に入りゆく気配ただよふ
傾ける齢はさびし咲き終へし都忘れの花を剪りつつ
魚の目に似たる昂を仰ぎ来て橋を降りれば陥穽のごと
人の流れに伍して歩めずはばからず立ち止りては呼吸整ふる
欄干に置きしわが掌に重ねたる君が掌愛し今は病みつつ
掌に並めて幾許薬をかぞへいる夫の指も細く老いたり
病む故の苛立ちならむ看護婦にあらがふ夫を止むるすべなし
安住を決めしこの地に次々とビル建ち並び星空せばむ
地上げ屋に渡りしならむかがなべて家崩さるる物音つづく
減船を強いられし人の顔暗しテレビは日ソの谷間を映す
襟裳岬の昆布干す海女に問ひかくるアナウンサーに海の色照る
漸くに水は温みて洗濯の渦ふくらみぬ春の潮とも
一つ灯につれて次々点りゆく団地はいづこも灯の連鎖
なす事の多きを思ふ薬飲むことも日課のひとつとなりて
はらから亡く友の友の減りしを嘆く夫にそれは長寿の証と励ます
さなきだに眠れぬ老に暑き夜のつづけば睡眠薬ためらひて飲む
明日香保存のニュースに吾も諾ひぬ古きを秘めし青き国原
ターナーの絵の恍惚は消ゆるなく迷へる如く街に出でゆく
今宵また恐しき夢見ん心地して重き夜具一枚はぎて寝るなり
金沢より出でて千葉に果てむ身の夫は累代の墓のこと言ふ
あとがき
(S.K)
合同歌集『槙』の第三集が発行の運びとなったことを会員の皆様と共に心から祝福したい。
歌は心の潤いであり、また心の糧であることを、この数年八千代市短歌会に出席される皆様の表情を通じて痛いほど感じてきた。この営為は、上手下手の問題を超えて作者の魂を歌という形式にぶっつけ、生きるきっかけにすがりつこうとするものなのだという再認識もした。作家道とはそういうもので、決して遊びではないのであろう。例えば叙景歌での写生は、つきつめれば物を正確に直截に見るということで、他人の借りものではなしに自分の魂で現実を凝視するということなのである。
千の歌は、一見すれば朝夕駅頭で見かける千の顔立ちに似ており、同じ目鼻立ちの、奇もない類型の集合にすぎないかも知れない。しかし仔細に見れば、その類型にもそれぞれに生活の陰影が収まり生きてきた人生が刻まれている。逆説的にいえば人間の顔は、みなおなじフォルムであるゆえに、かえって個々の微妙な差異が目立つのだともいえよう。花と石を比べることはむつかしい。しかし、千のさつき、千の椿の品評が、種を同じくするものの同意の上に成立するものであってみれば、精神と情意の座である人間の顔に個性のうつらぬ道理があろうか。同様、私たちが短歌に期待するものも、不用意な人の眼には千遍一律に五七五七七のフォルムのくり返しと見える詩型の中に、まぎれず現れるその人に個有の、同感を呼び目を開けさせてくれ、心を洗ってくれるような生の認識のかたちである。
八千代市短歌会、短歌サークル・泉の作品、および私が選をしている広報「八千代」八千代歌壇への投稿歌を見てきて、そういう作品に出会うことが次第に多くなっていることも実感してきた。今、ここに集大成された作品を見て、更めてその成果を噛みしめ、喜びにひたっている私なのである。
(H.S)
私達の合同歌集「槙・3」がようやく刊行されようとしている。有難いことである。「槙」は私達が五年毎に出す詞華集(アンソロジー)、いつの間にか第三集を出す年を迎えていた。そして、それはたまたま平成元年という年にあたった。何だか期待のもてそうな年である。
「槙」には際立ったテーマなどありはしない。ただそこで生活している人々の、それぞれの平凡な思いが、顔があるだけである。丁度、五百羅漢が並んで黙って立っているように。私はそれでよいのだと思う。森鴎外も「歌日記」の中で、
情は刹那を命にて
消えて跡なきものなれど
記念(かたみ)に歌を残すなる
とうたっている。
合同歌集『槙』より
五十年の旅
共に来し五十年の旅終へて黄泉をゆく夫うつし世の旅
死は恐れずされど淋しと常言ひしその言の葉も今はなき夫
居眠ればもうお休みと言ひくれし夫は逝きたりやさしかりしよ
位牌の位置ただして捧ぐる灯にゆらぐ夫の面影逝きてひととせ
夫の供華に咲かで萎へたる花あれば今日ねもごろに選りてあがなふ
今年また都忘れの花咲きぬ植えたる亡夫の心模様に
市より長寿を祝ぎくれし座布団に座ることなく終に夫は逝きたり
晩年の心血そそぎて亡夫編みし安田保善社史書架に輝く
豊饒の世なるもG戦犯の義兄逝きて十余年今日終戦の日
空襲下命からがら吾と逃げし息の世にはゆめ戦ひあらすな
戦ひの真只中に生れし息と歩む平和のこの世はうれし
常日頃無口なる息が念入りに花活け呉れぬ病み臥す部屋に
二時間を通勤する息は肩すぼめ風にあらがひ今朝も出でゆく
余剰人員と言ふ語はかなし自らを殺めし幾人の命思へば
常夜灯の更けし光にぬれながら遠ざかる人企業戦士か
朝顔の弁ゆるやかにほぐれいる今朝まぎれなき秋の彩見る
ありなしの風にさゆらぐ睡蓮の花々白しモネのまぼろし
咲き終へし躑躅の花殻つみゆく春の名残の淡き陽ゆらぐ
溢れ咲くシクラメンに君を待つロビーに真昼の光白くゆれつつ
没りつ陽の淡きに染みて頂は風におもねる合歓の花房
はつはつの彩り見せて春を待つ木瓜の蕾の交叉あかるし
永住を決めしこの庭バラ、朝顔、木犀、山茶花四季を咲きつぐ
歌劇のロマン声を限りに唄ふ女のテレビ画面が華やぎゆらぐ
白内の疲れし眼やすめむとしばしを閉ぢて名曲に浸る
牧水の恋せし岬さらさらに雲は流離の蒼き夏の日
去年の今日入院せるに術後なほ健かに過ぎ喜寿を迎へぬ
平均寿命はせめて超へたししかすがに寝たきりとなるを我は望まず
酒壷を愛でつつ百万石藩下なる御用商人酒造所わが家
あとがき
(S.K)
『槙』第四集の編集を終えて感慨一入のものがある。この五年間は平成としての新たな年代の発進の時期であった。その間にバブル経済の崩壊もあった。国際的にはソ連のペレストロイカ、東西ドイツの統一、湾岸戦争の発端と終結、とめまぐるしい変動も経てきた。そんな背景の中で吾々の作家活動は永永とつづき数々の佳作を生んできた。この営為は、激動の世を懸命に生きようとする市民の尊い生きがいの一つでもあった。この合同歌集はそれらの作品の集大成であり、とりもなおさず参加者夫々の人生の軌跡でもある。
今回の登録者は五十二名で過去三集に比べ最も多い。しかし、この五年間に六名もの歌友の訃報に接したことは痛惜の極みである。その中には前会長H.S氏も含まれている。さいわいS氏をはじめ四名の故人については遺族のご配慮で遺作を登載することができた。既に幽明界を異にした人達ではあるが詠い残された作品を読むとき、いきいきと故人を思い出すことができる。殊にS氏の写実を踏まえ素朴で、しかし読み返しているうちにしみじみあたたかく味わいのある作風は人柄そのもので、忘れがたい。この歌集を六名の物故者の仏前に供え謹んでご冥福をお祈りする次第である。
残された吾々は、今をいかに生きるか、という永遠の課題をふまえそれを詠いつつ、ますます旺盛に余生を享受してゆきたいと念願する。それが故H.S氏の遺志であろう。
この出版を機として歌友諸士の健詠を祈りながらあとがきとしたい。
平成5(1993)年6月
鼈宮谷
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- フィギュア好き集まれ~
- 【最大1000円クーポン★27日まで】【…
- (2024-11-22 15:18:55)
-
-
-

- フォトライフ
- 源氏物語〔12帖 須磨 6〕
- (2024-11-26 10:20:13)
-
-
-

- 機動戦士ガンダム
- HG 1/144 デスティニーガンダムSpecI…
- (2024-11-23 16:12:08)
-
© Rakuten Group, Inc.