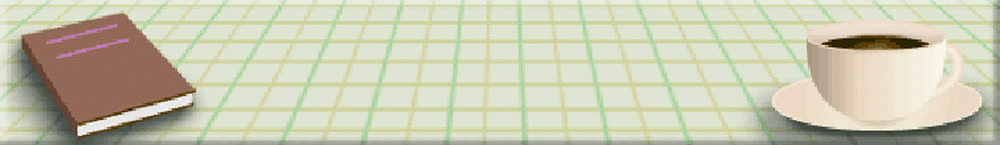短編集 「宝くじに当たった」男の悲劇
「宝くじに当たっている」。男はその場に倒れこんだ。「あは、は、息が苦しい」。男は、うれしいやら、涙が止まらない。このうれしさを誰に。男は携帯を取り出して、あの女に連絡しようとした。でもしばらく考えて止めた。「あいつに伝えたら、誰に告げ口されるかわからない」。男はその日から、人を避けるようになった。仕事場でも、そしてプライベートでも。ある日、家の前に一台の黒塗りの車が止まった。中から、出てきたのは、上品そうな女の人、そうこの男の母が心配して訪ねてきたのだ。この男は、40にもなるが、未だに独身、そして一人暮らし。アパートはけっしてきれいとは言えない2LDKのアパート。「トントン、ねえ、ター坊」、「いないの」。男は、迷った。開けるべきか、居留守を使うか。迷ったあげく、ドアを開けた。この男の母は、この男、息子の姿をみて、こう尋ねた。「どうしたの、何かあったの」。男は、がまんできず、全てを母に話して、ついでに母に当たった宝くじを預けた。母は息子の姿に驚いたそして息子の話とこの当たった宝くじに驚いた。そして預けられた宝くじを持って、帰っていった。男は、その日から、元気になり、仕事にもこれまで以上に励むことができた。それもこれも母のおかげである。それから、暫らくして宝くじの引き換えもできるくらいの時間が過ぎた頃、母に電話をした。電話をしても母は出ない。次の日もその次の日も。この男は一人で母が住んでいた実家を訪ねた。そこは父親の持ち家で既にその父親も他界していた。古い家の開いている窓から、どうにか、中に入った。男の目に留まったのは、テーブルの上に置かれたノートだった。そして男はおそるおそるノートを開き、最初のページに書かれている文字を読んだ。そこにはこう書かれていた。「ター坊、ごめんね。こんな母を許しておくれ、母は生い先短い、このぐらいの贅沢は許してくれるよね。本当ありがとう。ター坊、お前はいい息子だよ。がんばって仕事してね。いいお嫁さんも見つけるんだよ。母のことは捜さなくていいから」。男は、読んだあと泣いた。泣けるだけ泣いた。淋しくもあった。そして男は、この古びた家を出た。何もなかったように。自分のアパートへ戻っていった。
この男は、帰るとき、このノートに何かを書いた。泣きながら。それは次の通りだ。「かあちゃん、いいんだ。この当たった宝くじの金で贅沢してくれていい。好きなことして。ただ、この家に帰ってきてこのノートをみたら、また昔のように暮らしてくれ。かあちゃんに逢いたい」。以上
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- まち楽ブログ
- 榛名湖イルミネーションと花火✨【冬…
- (2024-11-29 11:46:13)
-
-
-

- ニュース関連 (Journal)
- 中国、「ICBM (大陸間弾道ミサイル…
- (2024-12-02 05:44:38)
-
-
-

- 気になるニュース&話題(Infoseekニ…
- 横山由依&純烈・後上結婚 仲間が感…
- (2024-12-02 19:00:08)
-
© Rakuten Group, Inc.