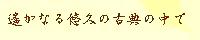おちくぼのあかね姫 3
「ああ、姫、なんとも苦労をさせるね。本妻腹の姫達に思わぬ時間をとられて、あなたのことまで気が回らなかった。北の方に世話するよう頼んであるが、あれも、自分の子どもに手を取られるのでね。もし、良いような話があれば、自分で計らって結婚でもなんでもするがよい。あなたにまかせるよ。」
と言い置いて、自分の部屋へ戻ると、北の方に、
「なあ、おまえ、おちくぼの姫のことだがなあ、あれはちょっとひどくないか? こちらへつれてきたというのも、死なせて罪を作るためではないのだから、あんなことをして死なれでもしたら……」
「あら、殿、おちくぼの君の着物のことをおっしゃっておいでなのですか? 私、気をつけて着せておりますのに、何がお気に召さないのか、全部人にやっておしまいになりますの。私が差し上げたものをお召しになるくらいなら、ぼろでふるえていらっしゃる方がお好きなんですわ。」
「そんなに気持ちがねじけた姫だとは思わなかったがねえ……」
「私のことを、なくなったお方からないことないこと聞いておいでなのかもわかりませんわ。わかりました。何か適当に見繕って差し上げてきますわ。」
北の方が、あかねの部屋に縫い物を持ってきた。
「中納言の殿が、おまえのぼろを気にされてねえ。さあ、これは、蔵人の少将のお召し物だよ。あの方は、良い物はいい、悪い物は悪いとはっきり口にされるから、上手に縫えたとおっしゃったら、おまえに着る物をあげますよ。」
あかねはにっこりと受け取った。
「藤姫!」
「ええ、神子様、聞こえましたわ。」
「私、ひどい姿をしているわ。こんな姿で友雅さんに逢いたくない……」
「わかりますわ。北の方は、お口に出されたことはそのとおりになさる方ですから、きっと、着る物をくださるでしょう。鷹通殿に伝えますわ。今度、お召し物をいただかれたら、褒めちぎってくださいませって。」
ちょうどそのとき、
「あこき、三の君に手を洗う水を」
とお呼びがかかったので、藤姫は三の君の部屋へ参上することにした。
藤姫が三の君の化粧を手伝っている間に、あかねは縫い物を仕上げ、北の方が取りに行った。
鷹通の蔵人の少将が、三の君を訪れてきた。
藤姫はそっと鷹通の側へ行った。
「神子殿はそんな暮らしを……。よし、それくらいのことで神子殿が少しでも楽になられるなら、いくらでもほめて差し上げましょう。それにしても、神子殿はいつのまに裁縫上手になられたのかな、異世界のお方だし、こちらへいらしてからも、裁縫などなさるお暇はなかったろうに……。」
(……泰明殿の術のおかげだとは言わないでおきましょう。)
と、藤姫は思って、にっこり笑うと、三の君の側に戻っていった。
北の方がご機嫌伺いに来た。
「少将様には今宵もご機嫌麗しゅう……本日はこの衣をお召しなされてくださいませ。」
「おお、かたじけない。早速着替えよう。」
鷹通は衣に手を通した。あかねの心が伝わってくる気がした。
(……助けて……ここから出たい……!)
(神子殿、お助け申す。今まで以上に心を込めてほめよう。)
「本当に、いついただいてもこちらの衣は体にすうっっとそって、軽くあたたかく気持ちがよいですね。内裏でも、よい仕立ての物を着ていると評判なのですよ。よい縫い手をお持ちのようですね。」
「まあ、お褒めいただいて、うれしゅうございますわ。」
「このように大事にしていただけるとは、実にうれしい。どのようにお答えして良いのかわかりませんが……」
「いえいえ、三の姫を大事にしてくださればそれでうれしゅうございますよ。ほんとにすばらしい婿君様にお通いいただいて、姫も果報者でございます。」
すっかり喜んだ北の方は、約束通り、あかねに着物をくれた。
自分の着古した、あちこちから綿のはみ出したような上着……
「こんな物でもいただかないよりはまし。寒くてたまらなかったもの。でも、友雅さんには会えないわ……」
あかねの心はいっそう暗くなるのだった。
「お返事はどうだった、頼久。」
「それが……」
友雅はどうやらどこにも出かけずに待っていたようだった。声に張りがあり、いつもの眠たげな様子は見られない。
「私の姫君に、文を見ていただけたか?」
「私の姫君……ですか?」
どうやら、友雅は、あかねに本気になっているようだ。
「今まで、何も、心からほしいと思ったものはなかった。ところが、神子姫のお返事だけは、なんとしてもほしいのだよ。どうしたというのだろう、物語の魔力だろうか。」
頼久は、できるならそうであってほしいと思った。
「文は見ていただけたようですが、お返事はいただけませんでした。」
「ふん……。藤姫がとめられたか?」
「『友雅殿とでは神子姫が不幸になるのでは』と、たいそうご心配のご様子でした。」
「おや、なぜだろうね。私には実がないというのだろうか。私はこんなに心から思っているのに……。そうだ、また、文を差し上げよう。きっとわかっていただけよう。」
それから、何度も、友雅の少将から文が届いた。
あかねはなかなか返事が書けなかった。
北の方が持ち込む縫い物の量が日に日に増え、複雑な物が増えて時間がかかることも理由だったが、
(こんな姿を友雅さんに見られるなんて……お返事したら、きっとお迎えにおいでになるわ。)
あかねは、ぼろを着ている自分を何があっても友雅には見られたくなかったのである。
あかねが着物のことで悩んでいることは、友雅にはもちろん、頼久にも伝わっていなかった。藤姫にはとても言えなかったのである。たとえ言ったとして、着物を助けてもらっても、例の北の方がめざとく見つけるし、そうしたときの言い訳を思いつくことができなかった。
「こんなにお返事がないのは、神子姫になにかあるのではないか。病気をしておられるとか……」
「藤姫様には何も仰せではありませんでしたが……」
「なんとか、中納言殿の屋敷に忍び込む方法はないか。あそこの屋敷は人が多くて、なかなか入りにくそうだ。」
「何とかしてみましょう。」
機会は、割合早く訪れた。
北の方が、石山寺詣でを思いついたのである。
あかねのおちくぼ姫をのぞく、中納言の殿をはじめ、姫君若君全部のお出かけとあって、お仕えする人々は我も我もとお供を願い出た。
あこきの藤姫も、三の君の願いでお供にくわえられていた。
(……神子様を一人にしてはおけないわ)
あこきは、北の方に、お供からはずしてもらうよう願い出た。
「おかしいことだねえ、足腰立たないような婆の君までがお供を願い出るのに、おまえは反対なのだねえ。まさか、あのおちくぼの君と一緒にいたいための願いではなかろうねえ。今のおまえの主人は三の君なのだよ。」
藤姫は必死だった。何とかして屋敷に残っていなくてはならない。あかねを一人にしたら、何が起こるかわからない。ここは、鬼の一族の陰体の中なのである。
「北の方さま、私がなぜお供に行きたくないはずがありましょう。おっしゃるとおり、婆の君までお供をしたい物もうででございますのに。ところが、私には、その日にどうしても忌まねばならないことができまして、不浄の身で仏様に詣でて罰が当たったらいかが致しましょう。恐ろしゅうございます……」
「本当かえ? あやしいものだねえ、信じられないね。でも、本当だったら、それは大変だ。じゃあ、今回は、仕方ない。別の女童を連れて行くことにするよ。」
お供からはずされた藤姫は、急いで頼久に文を書いた。
「お屋敷中、石山寺詣でにお出かけです。詩紋殿もお出かけ、鷹通殿のお渡りもありませんので神子様が心配です。お守りに来てください。」
藤姫は、文を「露」と呼ばれる少女に託して、頼久のもとに届けさせた。
次へ
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- 何か手作りしてますか?
- ペンギンの革人形を作る その220
- (2024-12-03 19:37:42)
-
-
-

- GUNの世界
- 昭和回想1988年3月号のGUN広告
- (2024-12-04 13:58:41)
-
-
-

- 機動戦士ガンダム
- HG 1/144 デスティニーガンダムSpecI…
- (2024-11-23 16:12:08)
-
© Rakuten Group, Inc.