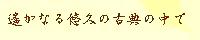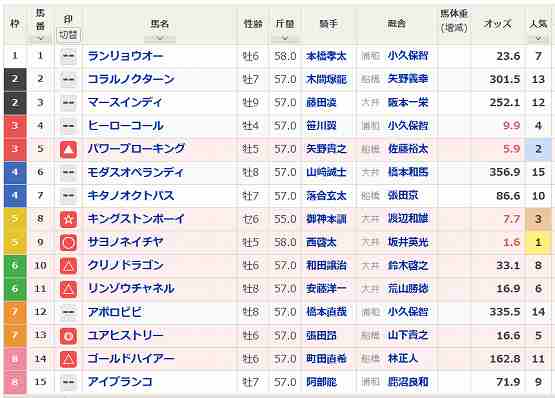おちくぼのあかね姫 7
友雅はあかねの部屋から出ることができなくなった。未だ時は熟していないから暗いうちに屋敷を出るつもりだったのだが、つい、寝過ごしてしまったのだ。
あかねは気が気でなかった。北の方が戻ってきたら、真っ先にここへ、点検にくるだろう。変わったことはないか、自分の言いつけに背いていないか……。藤姫が几帳を用意してくれたことがありがたかった。少なくとも、友雅を隠すことはできる。
「おちくぼ!!」
北の方が現れた。障子をがらっと開けた。
見慣れない几帳が目立った。どこから持ってきたのだろう? どこからか、薫香の香りもする。いったい、自分の留守中に何をしていたのか……。
「おちくぼ、どこにいる!」
あかねは、友雅が見えてしまわないように慎重に几帳からいざり出た。
北の方はあかねの服装が変わっているのを見逃さなかった。明らかに自分より上等の衣を着ている。絶対なにかがあったのに違いない。
「まああ、北の方さま、お帰りなさいませ! お帰りに気づかずゆっくりしておりまして本当に申し訳なく……」
藤姫があわててやってきて北の方に声をかけ、視線を逸らさせた。
「留守番のものが出迎えにも来ずに何をしていたんだえ? おおかた、部屋で寝坊でもしていたのだろう。まったく、いさせてやっているのに、大した度胸だよ! ところで、ここへきたのはね、旅先でいい鏡を手に入れたのだけれど、ちょうどいい箱がなくてね。こちらの箱がちょうど良さそうだと思ったものだから、ちょっと貸してもらおうと思ってね。」
あかねは早く北の方にでていってもらいたくて、大急ぎで箱を持ってきた。北の方は持っていた鏡を早速入れてみた。
「まあああ、あつらえたようにすっぽり入るよ。しかも、この塗りの美しいこと。やはり、昔のものは違うねえ。じゃあ、貸してもらうよ。」
北の方は、にこにこ顔で部屋を出ていった。藤姫がふうっと大きなため息をついた。
「この部屋のきれいなものがまた一つ減ってしまいましたわ。あちらにはそんなものいくらでもあって、何一つご不自由なさっておいででないのに、何が憎くてこちらの姫をこんなにいじめるのでしょう。」
「……鏡の箱くらい、あちらの世界に戻ったらいくらでも用意させるよ、藤姫。」
「そういう意味ではございません!」
藤姫は、北の方のあかねへの仕打ちを事細かに語った。着物・食べ物は粗末なものしかもらえないこと。夜も寝られないほど縫い物を持ってくること。今回の石山寺詣でも、旅先で縫い物があるわけないという理由でおいて行かれたこと……。
「今まで無かった御几帳やお召し物を見て行かれましたから、きっと、もっとひどい目に遭わせなさいますわ。神子様がお幸せなご様子なのが何しろ気に入らない様子なのです。」
友雅が朗らかに笑った。
「なら、きっと、北の方は鬼の一族なのであろう。さっき顔を見たら、なんだか、アクラムの眷属に似ていたよ。シリンとか言った……」
「……そうかも。」
あかねも、うなずいていた。
「アクラムが私をほしがるから、シリンは嫉妬しているのよ。この陰体って、ひょっとして……」
「何をしてくるか、わからないね。十分気をつけよう。今日は一日、私はここを出られないから安心おし。」
「……友雅さん♪」
友雅はあかねを抱き寄せると、几帳の奥に入っていった。藤姫はため息一つのこし、頼久の待つ自分の部屋へ戻った。
北の方は、あかねの様子が変わっていたのが気になって仕方がなかった。
どういうことなのか確かめたくて、もう一度、あかねの部屋に、足音を忍ばせて戻ってきた。
しきりの障子を音を潜めてそっとあけてのぞいた。
几帳の奥で人声がする。密やかなため息、小さくあらがう声、優しく懇願する……男の声!
(おちくぼに男が……! 一体誰だろう……?!)
目を凝らしてじっと見ると、几帳に男ものの衣がひっかけてあるのがわかった。上等そうな絹……かなり身分の高そうな男。
(いったい誰が手引を……あこきか? あこきのところに、蔵人の少将の帯刀が通っているとうわさになっていた。帯刀は右近の少将の乳母子だそうな。まさか、あの好色者とうわさの少将が、おちくぼの話を帯刀から聞いて?)
北の方の心の中で、残忍なものが声を上げた。あかねのおちくぼを絶対に不幸にしてやる……!
友雅はその夜も泊まって、明くる朝早く、屋敷に戻っていった。
翌日は出仕の日、となっていたので、右近衛府に出かけた。そのまま宿直、となったので、あかねに文を書いた。
頼久が文を持っていった。
「お返事があれば、私、もって参りましょう。」
あかねは返事を書き、頼久は懐に文を入れて屋敷を出ようとした。
そこへ、鷹通の蔵人の少将が、三の君の許へやってきた。
鷹通から頼久へ、顔を出していくように声がかけられた。
「ああ、頼久、ちょっと、私の髪をなおしてくれないか。風に吹かれて乱れてしまったのだよ。」
鷹通は女房達をさらせ、頼久と二人だけになった。
「神子殿はいかがおすごしか。私のために縫い物をさせられていると聞いているが。」
頼久はどう答えていいかわからなかった。
「……お健やかにお過ごしです。」
ぼそっと言った。手早く鷹通の髪を直し、去ろうと急いていた。整髪道具を片づけようとうつむいたとき、懐からあかねの文がこぼれ落ちたが、急いでいる頼久は少しも気づかなかった。
鷹通は、そっと文を拾い上げた。小さく「友」という字が見えた。あかねの筆跡だった。
(神子殿の……。「友」とはまさか「友雅」か……?)
妙に急いだ雰囲気の頼久が去った後、鷹通は文をそっとほどいて読んでみた。
心が、ざわっと音を立てた。
「神子殿は、では、友雅殿と……!?」
何かがぼろぼろと崩れていく気分がした。呆然と文を眺める鷹通をめざとく見つけて、三の君が近づいてきた。
「……どなたのお文かしら……?」
鷹通は文を隠そうとしたが遅かった。文は三の君に取られてしまった。
「あらあ、これ、おちくぼの君の手跡ね。殿が?」
「いや……帯刀の落とし物だ……」
やきもちやきの三の君の攻撃から逃れようと、鷹通はつい、本当のことを言ってしまった。
「恋文だわ、帯刀がおちくぼの君にもらったのかしら? たちはきはあこきのところの通っているのだと思っていたけど……。」
騒ぎを耳ざとく聞きつけて、北の方が現れた。三の君は、北の方にあかねの文を見せた。
「まあああ! この間から、部屋の様子は変わっているし、着物も変だし、ナンだろうと思っていたんですよ。こともあろうに、帯刀を通わせていたんですね! なんてふしだらな、お仕置きをしなければ!」
北の方は、中納言の殿のところへ文を見せに行った。
頼久は、懐に手をいれて、文が無いことに気づいた。
「しまった!!」
落としたとすれば、鷹通のところしかない。頼久は大急ぎで鷹通のところへ戻った。
「……神子殿の文は、北の方に取られてしまったよ。」
鷹通は、頼久の目をのぞき込んで言った。
「神子殿と友雅殿はどういうことなんだ。頼久はどこまで知っている?」
「それは……!」
鷹通の目から苦悩の色を読みとり、頼久は、鷹通も自分と同じ苦しみを感じていることを知った。
「……昨夜が三日夜でした……」
「では、友雅殿も本気なのか。一生神子殿を守ると? 神子殿も……」
「昨夜、それがしと藤姫様の前で……」
鷹通の表情が、あきらめに変わった。あかねの心の目がいつも友雅を追っていたことはよく知っていた。友雅があかねに対して未だかつてない温度の感情を持っていることも知っていた。それが、物語の力で成就されてしまったのだ。これはもうとめられないのだろう。おそらく、京に戻っても……。
「……わかった。私も二人を祝福しよう。龍神もお許しになったことなのだろう。もう、何も言うまい。私は私のつとめを果たすだけだ……。
ところで、頼久が神子殿の相手だと思われているよ。ふしだらな、と、北の方はお怒りだった。」
頼久はどきっとして、顔を赤らめ、急いで藤姫の部屋へ行った。
あかねの部屋は大騒ぎになっていた。
「几帳なんか立てて、ナンのつもり! 留守の間に男を通わせていたろう! 居候の身の上でふしだらな! 出てお行き! のたれ死にでもなんでもするがいい!」
北の方が大声であかねをののしっていた。藤姫が必死でとりなそうとしていた。
「男君を通わせるなどとんでもない。几帳もお召し物も、あんまり姫君がお寒そうだったので、私の知り人から拝借しているのですわ。けっしてやましい心からではありませんとも、信じてくださいまし。」
「何を言う、こちらには証拠があるんだからね!」
北の方は文を取り出した。藤姫とあかねは心臓が止まるかとおもった。
(……神子様のお文!)
(頼久さんに預けたはずのお手紙がどうしてここに!?)
北の方は、目を大きく見開いたまま黙り込んでしまった二人に、高らかに言い放った。
「あこき! おまえはもう暇を出すから、どこへでも勝手にお行き! おちくぼには縫い物があるからいさせるが、ひどいところに押し込めてしまうよ! こちらへおいで!」
北の方はあかねの手をつかむと、ずるずると引きずっていった。台盤所にちかい、普段食料庫にしている物置にあかねを押し込むと、がちゃりと鍵をかけてしまった。
「もうこれで出られないよ! 通ってきた男ももう来なくなるよ! いい気味だ。もっと不幸せになるといい。」
北の方は大声で笑いながら自分の部屋へ戻っていった。
暇を出されてこの屋敷から出されてはたまらない。藤姫は、三の君に泣きつくことにした。
「私、恋人にうらぎられたのでございますよ、三の君様。それだけでも不幸でございますのに、お暇まで下されまして、こんな不幸はございません。一緒にお留守番で夜など人がいなくて寂しくて怖くて、それでおちくぼの君にちょっとだけ親切にしたくなっただけですわ。どうぞ、北の方さまにおとりなしくださいまし。あこきに二心はございません。」
「……三の君、助けておやりなさい。」
鷹通も横から口を出した。
「あなたのお家の事情だから私が口を出すことではないかもしれないが、この女童、なかなかおもしろい。ここで助けてやれば、私たちも楽しめるし、来世に功徳を積むことにもなりますよ。」
「……あなたがそうおっしゃるなら、助けてやりますわ。」
三の君が北の方に取りなしに行っている隙に、鷹通は、藤姫にあかねの消息を聞いた。
「わかった。橘少将殿にはこちらの内裏でもあえるから。神子殿を助け出すよい機会なのかもしれない。なんとかしてみるよ。」
鷹通は何食わぬ顔でその宵をすごし、明け方、屋敷を後にした。
頼久は、真っ青だった。
藤姫があかねの消息を知らせてきた。自分の失敗で、神子殿がいっそうひどい目に遭ってしまった! 神子を守ることが自分の最重要な使命であったのに、逆により不自由な目にあわせるなど……。友雅にもなんと伝えたものか。重い足取りで、でも大急ぎで、頼久は友雅の元へ参上した。
友雅も愕然とした。あかねが閉じこめられてしまったとは……。これは、時が熟したのか、それとも、深刻になったのか……。
そこへ、鷹通が訪ねてきた。
「時が熟したのですよ。今度、私は賀茂の臨時の祭りの使者に立つのです。三の君に是非見に来るように誘いますから、そうすれば、この間の石山寺の時のように屋敷はカラになるでしょう。そのすきに、神子殿をお助けできます。」
「錠前は、この頼久が。」
「では、私は姫に今一度文を書こう。必ず救いに行くと、賀茂の臨時の祭りを待てと、誰か届けてくれようか。」
「詩紋殿がいますよ。あの子にがんばってもらいましょう。」
友雅の文を、今度は鷹通が預かった。
次へ
© Rakuten Group, Inc.