・7章
火花を散らしながらクロスポイントを通過する。
線路を引いたのは自分で。
分かれ道を通ったのも自分。
車掌が問う。
“さぁ、どちらにいたしますか――?”
幾千の刃が風となって襲い掛かる。
「―っっ・・・!」
――まだ、死にたくは無い。
そう、当たり前のことだ。
しかし、喧嘩を売ったのは私であり。
“死”という終着駅へのクロスポイントを選んだのも私。
(まぁ、必然・・・か。)
仕方が無い。
割り切ってしまえばどうということは無い、人間死ぬときは死ぬ。
道を歩いていた瞬間に、交通機関につっこまれたらその時点でアウトだ。
世界という理不尽なゲームから、除外される。
(まぁ、変な死に方するよりは、マシ・・・かな。)
というよりも、そう考えないとやってられない。
キィィィ・・・ン!
まるで、雲を突き抜けるような軽快な音を、確実な死を告げる重苦しい音を発しながら、風が迫る。
(元より壊れやすいもの、生きるべからず・・・か。)
手を大きく広げ、せめて天国に行けるように願った刹那。
風が、
私の体を、
切り裂いて――・・・
・・・意識が、消えた。
†the point of view change, Fina→Alwen(視点変更)†
「んが~・・・っ!」
窓から入り込む、白く、明るい朝の日差しで、俺は目が覚めた。
天気晴朗として雲少なし。申し分無しのいいお天気である。
「あれだねぇ、素敵な朝ってのはこういうことだねぇ・・・。」
大きく伸びをして、一人呟いた・・・
「・・・あ、目が覚めたの。」
と。突然のベッド脇からの声に、俺は振り向いた。
「な、ななな・・・?」
驚き余ってまともに声すら出せない。
「おはよう。いい天気だね・・・」
そんな俺を愉しむかの様に、彼女はクスッと笑った。
「・・・ええっと、どちら様で?」
「むーっ・・・何よ、昨日あれだけボコボコにしてくれて、もう忘れたっていうの?」
「へ?え?は?」
状況が理解できない。
というより、ええっと・・・
「あーあーあー・・・、昨日の果たし状の!」
思い出せたは思い出せたが・・・ボコられてたのは俺だった気がするんだが・・・
「は、果たし状・・・ねぇ。まぁ、そうともいうかな?で。本当に覚えてないわけ?」
「あぁ。むしろボコボコにされてた記憶があるぞ、うむ。」
そこで彼女は、小首をかしげ、なにやらブツブツ呟いていた。
「・・・・・・」
「・・・・・・」
窓枠に座っている彼女は、背中に朝の光を受け、とてもかわいく見えた。
開け放した窓から入ってくる風で、純白のカーテンが軽くはためいている。
・・・ん?純白のカーテン?部屋のは青だった気が・・・
さっきまで混乱していたからよく分からなかったが、落ち着いて周囲を見渡してみる。
白を基調とした部屋。
隣に置いてある大きな薬棚。
部屋の隅に置いてある様々な機械類。
そして、置いてあるものは、俺の寝ているベッドと、彼女の座っている窓のみ。
・・・んでもってそれが意味するもの。
「ここって・・・保健室の個室じゃないか。」
そう、この学園には、諸事情により医療病棟なるものがあったりする。
何かと授業での怪我が多い上に、校内での武器所持が認められていたりするあたり、お察しといったところだ。
名目上は保健室だが、入院施設付きの総合病院と呼んだほうがいいだろう。
ちなみに、軍医を目指すやつらは、ここで実習をすることになっている。
「ええ。まったく、感謝してよね。運ぶの大変だったんだから。」
「へっ?運ぶ?」
「んーっと、とりあえずそれはおいといて。昨日の夜は、どこまで思い出せる?」
「ん?むむぅ・・・」
目を閉じ、記憶を引き出す。
「・・・むー・・・ぅ。君に斬られる直前までしか記憶が無い・・・な。」
「え~、ほんとにぃ~?」
そういって、俺の顔を覗き込んでくる彼女。
・・・夜とはキャラが違うんだな・・・
「―っつ、近い近いっ!嘘ついてないから離れてくれっ!」
気づけば吐息の交じり合うような場所まで近づいていた彼女を、必死になって離す。
「ふ~ん・・・ねぇ。おぼろげでも思い出せない?」
「む・・・むう。」
さらに記憶の深層部を探る。
引き出しを開けていくような感じだ。
「・・・・・・ぁ、あ―ダメだ、引き出しに鍵がかかっているような感じで、そこだけ開けない。」
「引き出し?面白い覚え方をしているのね。」
「あぁ。気づいたらそういう風に覚えるようになっててな。一応これでも物覚えはいい方なんだが・・・」
「へぇ・・・ま、覚えてないなら仕方ないわね。」
そういって、彼女はトンッ、と軽く音をたて、窓枠から飛び降りた。
「名乗るのが遅くなったけど・・・私はフィーナ。フィーナ=アラテスシア、よ。」
よろしく、といって手を差し出してくる彼女は。
光を受け、とても穏やかに、輝いて見えた。
「あ、あぁ・・・俺はアルウェン=アームシュライト。何をしたか分からないが・・・とにかくすまんな。」
「え?ああ、いいのいいの。そんなに気にしてないし、生きてるだけ奇跡だと思うわ。ありがとう、アル。」
なんとも微妙な・・・だが心地よい沈黙。
気まずくは無いが、なんというか。
どうしても顔が赤くなってしまう雰囲気。
・・・心なしか、彼女の顔も赤いように見えた。
(いい感じ、ってのはこんなことを言うのかな・・・)
などと、ほんわかと思った瞬間。
「だだだ、大丈夫か?生きてるんか、アル!?」
「あのねぇ、生きてたら保健室にいないでしょう。」
「ああ。・・・で、容態はどうだ?大事には至っていないとは聞いたが。」
「うぅ~・・・、心配だよぅ。」
・・・決定的にマズい予感がする。
迫ってくる4つの声は、間違いなくあいつらだ。
で、俺のほうはというと、個室で美少女と2人っきり。
なんていうかこれは、いろいろとダメな展開じゃないのか?
「あわ、あわわ・・・どどど、どうするよ?」
「どうする・・・って。逃げようがないじゃない?」
むしろ逃げる必要があるの?と目で問うてくるフィーナ。
大ありです。いや・・・なんていうか、この状況をアレな方向に誤解されたら・・・
「ふぅん、そういうことかぁ・・・」
なぜか勝手に納得して、ニヤニヤし始めたフィーナ。
「え、ええっと、フィーナ・・・?」
「よいしょ・・・っと。」
よくよく見れば彼女は寝巻きの上に上着を羽織っただけという服装。
で、今まさに彼女はその上着を脱ぎ・・・
「お邪魔しま~す。」
「のわーっ!や、まてまてまてっ!」
寝巻きの状態で俺のベッドに入ってきた。
いろいろとアレな煩悩を振り払い、つとめて平静を装う・・・が。
「・・・そこっ!くっつくなって!」
「あはは~・・・面白そうだしさ!」
「あ~う~・・・」
コツコツコツ・・・
コツコツコツ・・・
近づいてくる足音。
・・・ドアの前に面会謝絶の札が貼ってある、もしくは全員が何かの急用を思い出してくれることを強く願いつつ、破滅への足音を聞く俺。
隣ではフィーナが、クスクス笑いながら俺のほうを見ている。
・・・ちくしょう、可愛いじゃねぇか・・・じゃなくてっ!
「あー・・・フィーナ様?ベッドからお出になる予定は?」
「目下、ございません。」
「マジか・・・」
・・・しかし。
考えれば考えるほどマズいシチュエーションだぞコレ。
ヘルプ、神様・・・!
「アル、入るぞ~」
そんな俺の願いも虚しく、個室のドアが開く。
病人の俺を気遣ってか、ドアは少しずつ開き・・・
「「「「・・・・・・は!?」」」」
半開きになったドアから覗いた4つの顔が、凍りついた。
・・・素晴らしい一日になるという俺の予想は、早々にして裏切られたようだった。
「さて・・・どういうことかな?アル?」
俺たちは同志だっただろう!?と、怒りを顕著にするダン。
何もお前と、”モテない男の為の熱い友情を推奨する会”を作った覚えは無いぞ・・・
「へぇ・・・一晩中帰ってこないと思ったら、個室で女の子と、ねぇ・・・!」
・・・あわわ、あらぬ妄想を膨らませてるよウェンリィ。
「・・・・・・ほぅ?」
アランはアランで興味深げだなオイ。
目が怖い、目が怖い。絶対トークネタに使うつもりだなコイツ・・・
「・・・・・・」
クレアは未だにポカンとしているな・・・そんなに信じられないことだろうか。
しかし、体中から怒りのオーラが出てるな、うわぁ・・・
・・・あーあーあー・・・とりあえず。
「よ、よく見舞いに来てくれたな、うむ。俺は嬉しいぞっ!」
・・・反応無し。
むしろ、こういうときに素直に笑っていられません、俺は。
引きつった笑顔のまま、言葉を続ける。
「さて、俺はこの通り元気だが・・・みんなはどうだ、元気か!?」
・・・無理矢理に言葉をつなぐ。
マズい。
非常にマズい。
「まぁこれにはいろいろと事情があってだな・・・な?フィー・・・」
・・・フィーナ姫はご就寝のようで。
唯一の頼みの綱と思って声を掛けた彼女は、スースーと寝息を立てていた。
穏やかな横顔・・・寝るの早いなオイ。
思わずその横顔を見てほんわかしていると。
スッ――
俺に四つの影が降りた。
絶 対 絶 命 !
思わず、ドでかいドラゴン4体に囲まれてアワアワ言ってる、RPGの主人公を思い浮かべてしまった俺。
次の瞬間、ドラゴン4匹の必殺の打ち下ろしが俺を襲った。
まさに一撃必殺。
俺の頭には、
「GAME OVER」
の文字が点灯し・・・そして、意識は暗い深淵へと落ちていった。
・・・白い白い静寂のセカイ。
「また、ここか・・・」
一人、呟く。
「そう、また、ここだ・・・。」
背後からする声に振り返ると。
そこには、鏡に映った自分がいた。
「こんにちは――いや、初めまして、か。」
「あんたは・・・?」
「俺か?俺は俺で、おまえだ。チガイは・・・表と裏、か。」
「あんたが、俺だって・・・?」
「当たり前だ。この顔、見覚えないのか?」
見覚えがあるも無いも、その顔、その姿は、毎朝洗面台で見ている自分そのものであった。
「この前の意識の反転によって、俺とお前の境界線があいまいになったんだろうな。」
「意識の反転・・・?境界線?」
「そうだ。俺はお前の反転したモノ。簡単にいっちまえば裏人格だな。んでもって、その俺、裏人格と、お前、これまで生きていたアルウェンを分ける境界線があいまいになって、意識が混同してるんだ。」
「あいまいに・・・?」
「なんだ、物分りの悪いヤツだな。それでも俺か?」
そんなことを言われても、理解できないものは理解できない。
「・・・お前さんは、”反転する意識”っていう特異体質をもってるんだ。」
「特異体質、ねぇ・・・」
「そう。それを発動することにより、お前さんは、俺になる。」
「で?どんなチガイが発生するんだ?あんたと俺のチガイなんて、口調ぐらいじゃないのか?」
――フッ、と、裏人格だと名乗る俺が笑った。
「そうか?これを見てもか?」
直後。
俺の頭に猛烈な情報が流れ込んできた。
時間としては短時間だが、人間としての処理能力では猛烈な量である。
そもそも、1秒の情報を1秒で処理しているからこそ対処できるのであり・・・
それでもなんとか、情報を保存した俺は、それを再生する。
「・・・これが、俺の、か?」
高速で流れる視界。
肉体に送る指令。
理解の範疇を超える思考ルーティン。
どう考えても不可能な行動入力。
なにより――
攻撃することへの異常とも言える快感。
「理解したか?それが、裏人格のお前、要するに俺だ。チガイは歴然だろう。」
「・・・・・・俺の記憶には、こんなものは・・・」
「ハッ、なくて当然だ。第一、お前が好き好んで反転したんじゃないのか?」
「何を・・・?俺はそんな能力さえ知らなかったが。」
「・・・まぁいい。これで分かっただろう。俺とお前が、同人物であり、別人物であることは。」
「ああ・・・ようやく、な。」
「どうやら無意識のうちの反転だったようだが・・・一つ警告しておこう。」
「あ?なんだよ?」
「・・・境界線があいまいになっているといったが、その原因は明らかに意識の反転だ。その発動をお前は無意識に行っていた。ということは、お前は・・・」
「発動とやらを、制御できていない、のか・・・」
愕然とする。
そんな能力自体知らなかったというのに、さらにデメリットまでついてきてくれた。
「境界線がなくなると、どうなっちまうんだ・・・?」
「恐らく、お前ではなくなる。植物人間になるか、もしくは情緒不安定な危険人物になるかだな。」
無意識のうちの発動による弊害が、そんなデカいものなのか。
割に合わない・・・
「防ぐ方法は、あるのか?」
「知るかそんなもの。自身で気づくしか他ならないだろう。」
やはりか。
制御方法を見つける・・・それが最優先の課題のようだ。
だが、本当に見つかるのだろうか?
自身の事を一番理解できるのは自分だろう。
その自分でも理解できない、無意識下の行為を、果たして他人が制御法を知っているのであろうか?
「・・・チッ、まったく、俺のツラでそんな情けない顔すんな!」
あげくの果てには、裏人格にまで怒られる始末だ。
――もう、笑うしかねぇ。
「仕方ない、か。開き直るしかない。善処するぜ・・・」
「それでいい・・・じゃあな。お前の意識が覚醒するみたいだぜ。」
気づけば、白い空間は少しずつ、存在を小さくしているようだった。
厄介なことになったもんだ――
そうして、少し自虐気味に、俺は苦笑した・・・。
目を開ければ夕刻。
授業も一通り終わったことであろう。
あのドでかいドラゴン四体は、俺をぶん殴った後出て行ったようだ。
夕焼けの橙に染まるベッドの中、俺の隣には彼女が眠っていた。
まるで絵になるような情景。
そんな中、俺は彼女に声を掛ける。
「フィーナ・・・起きろ。」
「ん、んん・・・」
にゃーっ、とか微妙な声を発しながら、彼女は大きく伸びをした。
「・・・ん?あれ?あれれ?どうしてこんなとこに・・・のわぁ!」
自分の状況を良く理解していないような彼女は、隣に寝ている俺を見て、さらに驚いた。
「どどど、どうして隣にっ!?」
顔が赤いのは、なにも夕焼けのせいだけではないはずだ。
見ていて微笑ましくなるほどの慌てようが、それを表している。
「どうして、じゃないだろ。自分でもぐりこんできたんだろうが。」
「へ?え?・・・・・・あ。」
ようやく思い出したようだ。
しかし、状況を把握するどころか、さらに赤くなっていくのは気のせいだろうか。
ってかむしろ、地球の大気の光屈折率が超絶な勢いで変化していない限り、フィーナが照れているのは確実だろう。
「うぅー・・・なんであんなことしたんだろ・・・」
赤くなってモジモジしている彼女は、例えようもなく可憐だった。
「まぁ、俺は困ってないぞ。むしろ嬉しかったしな。」
俺は、彼女が、俺に迷惑をかけたんじゃないかと思って悩んでいるのだと思い、気休めになるようこう言ったのだが・・・
「ふぇっ?う、嬉しい?」
・・・超絶的に逆効果だったようだ。
俺は人の気持ちを読むのが例えようも無くヘタなようで、彼女は俺の言葉を聞いた瞬間、さらに赤くなってしまった。
「そ、それってどういう・・・」
あー・・・どうやらトンデモな誤解をされているようだ。
このままではただのヘンタイだと思われることだろう。
それはマズい。
こんなカワイイコに嫌われるのは、かなりショックだ。
「い、いや、深い意味は無いぞ!ただ、俺は迷惑じゃなかったって意味で・・・!」
「・・・え?迷惑じゃない・・・?」
とたん、彼女の顔色が普通になった。
なったはいいが、今度は少々しょぼくれているように見える。
・・・ううむ。
乙女心というものは理解しがたいものだ・・・。
とりあえず、弁解というかなんというか。
ああもう、言おうとした台詞を考えると、どうしても赤くなってしまうっ!
「あー、その、なんだ。嬉しいというのは、フィーナみたいなカワイイコと一緒にだな・・・」
と、必死に説明しようとする俺を、彼女は笑いながら制止した。
「アハハ、もういいって!良く分かった、アル。」
そして彼女はニコっと笑って、
「私としても、嬉しいかな・・・」
なんて、こっちも猛烈に赤くなるようなことを言ってくれた。
まぁ、フォローだってのは分かってるんだけどさ。
「さて・・・と。そろそろ行こ?」
「あぁ。体ももう大丈夫だしな。」
というより、朝から体調は全くもって平気だ。
多少の筋肉痛が残っている程度であろうか。
「まぁ、仕方がないよな・・・」
「ん?どしたの?」
「いや、あれだけ肉体を酷使したんだから、筋肉痛になるのは当たり前だ、ってね。」
おっと、そういえば。
「・・・そうそう、記憶を思い出したんだ。」
「へぇ・・・あの時の?」
彼女の眼が少し鋭くなったように思えたのは気のせいか。
「ああ。悪かったな、あんな風にして。ただ・・・」
「何?」
言い訳がましいとは思うが、これだけは言っておきたい。
「アレは俺じゃあない。・・・今の俺は、フィーナに手を上げることすらできないさ。」
・・・まぁ、するような状況になってもしないけどな。
その、俺の心を見透かしたようにフィーナは、
「分かってる。あなたは優しくて、素敵な人よ。」
と言って、とても綺麗に笑った。
・・・うーむ。
ま、恐らく気休めだろうが・・・
とりあえず、言われて嬉しくないことはない。
「サンキュ。そういってもらえると、お世辞でも嬉しい。」
フフ、と彼女は笑った。
そして、夕日に染まった白い部屋から、俺たちは各自の部屋へ戻っていった。
・・・ああ、部屋に帰った時の、仲間の反応が恐ろしい・・・
己は己。
意識は二つ。
・・・己はヤツで。
・・・ヤツは己で。
白く静寂のセカイ、濁った灰色の街並で己に問う。
―――さて。私は誰でしょう・・・?
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-
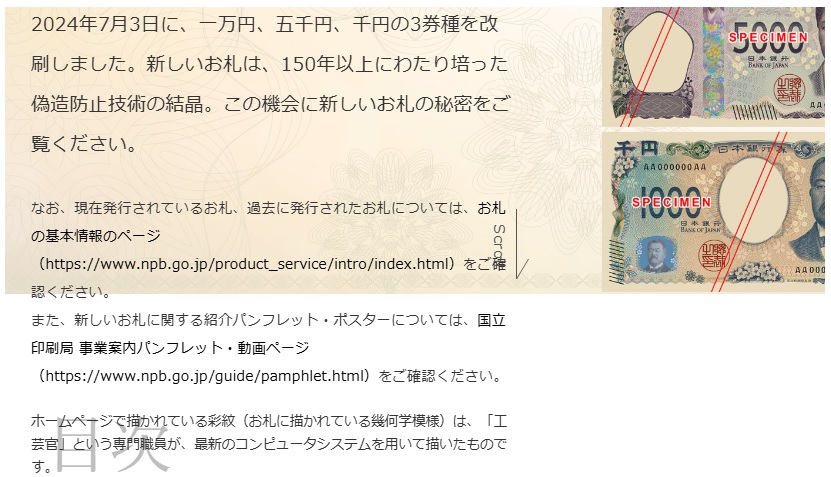
- 模型やってる人、おいで!
- 東京口の211系(その43) サン…
- (2024-11-15 19:15:30)
-
-
-

- 機動戦士ガンダム
- マイティーストライクフリーダムガン…
- (2024-11-14 20:16:36)
-
-
-

- 競馬全般
- 11/3 エスタンシア~京都 待望のデ…
- (2024-11-16 00:55:07)
-
© Rakuten Group, Inc.



