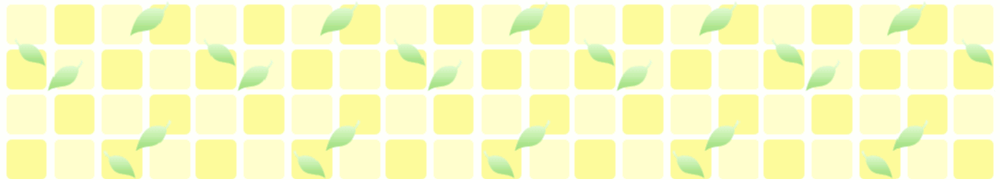リレー企画 170
Land back at home オりーさん病院からの帰り道、外で食事をすませた僕らは夕方ソウルの街へ戻ってきた
「店にちょっと顔を出そうか」
彼が僕に言った
「そうだね。みんなの顔が見たいな」
「今なら開店前のちょうどいい時間だ」
彼は店の方へ向かってハンドルを切った
店の駐車場に着いた
そんなに長い事留守にしたわけではないのに
車から降りたとたん懐かしさがこみ上げてくるのを感じた
彼はそんな僕の左手を取って首をふると店の方へ誘った
建物に入ると厨房に向かうmayoさんとちょうど行きあった
「ちょっとご無沙汰したね」
彼がmayoさんに挨拶した
振り返ったmayoさんがおっという顔をしたけど
すぐ真顔に戻っておかえりなさいと言った
それから彼にすいっと近づくと耳元で何か囁いた
彼は、相変わらずすばやいねと言って笑った
mayoさんは照れたように下を向いたけど、その目は当然だと雄弁に主張していた
それから僕を振り返り、怪我はどう?と聞いた
僕が何とか大丈夫です、と答えるとそそっと近寄って僕の耳元で囁いた
「これを機会に少しこき使うといいよ、あの人」
それからにっと笑ってまた厨房へ消えた
僕もちょっとにやついてしまった
「どうした?何にやついてる?」
「何でもないよ。そっちこそ何がすばやいの?」
僕は彼に聞いた
「ソヌさんとミンギ君が新人を拉致してきたそうだ」
「拉致?」
「留守の間に新人が3人入った」
「また増えたの」
「そうだ、これでメンバーは24人になった」
「そんなにいた?!」
「mayo情報によるとそうなる」
「数えたんだ・・」
彼は楽しそうにくくっと笑った
僕と彼が戸口でそんな話をしていると中からテプンさんが大きな声を出して近づいてきた
「見慣れない奴が来てるじゃねえかよ」
そして僕の左手を掴むとずりずりとみんなの方へ引っ張っていった
「おおいみんな、怪我人が帰ってきたぞ」
テプンさんは僕の左肩をばんばんと叩きながら叫んだ
彼が後ろから傷にさわるから叩くのをやめろと言い
だから左側を叩いてるんだろ、とテプンさんがすかさず言い返した
彼とテプンさんのいつものやりとりを聞いて、その場の空気が和んだ
僕はちょっと照れながら、ただいま帰りましたとみんなに頭を下げた
みんなが僕に近づいてきて、口々におかえりと言ってくれた
ドンジュンさんは少し離れた所から僕にウインクしてくれた
テプンさんは、お前のせいで俺たちはまだ土産をもらえないんだぞ、と大声を出した
それで僕はドンジュンさんの心遣いを知った
「どっちにしろ、テプンさんとこの土産はテジ君にしかないからね」
ドンジュンさんが畳みかけるようにそう叫んだので
テプンさんがまじで暴れそうになって、シチュンさんとチョンマンさんに両側から取り押さえられた
ソヌさんがすっと近づいてきて、刺し傷はないの?と聞いた
僕が首を横に振ると、そうか、と言ってまた離れて行った
隅の方で、先輩何アホな事聞いてるんですか、とミンギ君に突っ込まれていた
監督がのそのそと近づいてきて、ねえどんな様子だったの、撃たれた時ってどんな感じ?
後でじっくり教えてね、ネタになるかもしれないから、と言って僕の肩をじっと見つめた
「どの程度?」
ソクさんが僕の右肩を顎でしゃくりながら低い声で聞いた
「貫通してます。けど口径が小さかったので」
「そうか、じゃ怪我のうちに入らないな」
「ソクさんっ、怪我人に向かってそういう事言わないのっ!」
「あんっ、スヒョクっ、ごめんっ!だってさあ、僕もっとすごいの知ってるもん」
「そういう問題じゃないでしょっ。ちょっとこっち来てっ」
ここは問題なしかな
ウシクさんはなぜか一回り大きくなったような感じだ
隣のイヌ先生の影が心なしか薄い
「よかったね、無事帰ってこれて」
「ほんとよかった。僕は大変なんだ、今ウシクに・・・モゴモゴ・・ひゃっ、ウシクやめっ・・」
「先生何言い出すんだよっ!こんなとこでっ!」
「何も言わないよ・・モゴモゴ・・口押さえるのやめっ・・モゴモゴ・・」
「ちょっとっ先生っ!」
「モゴモゴ・・攻められるのが・・モゴモゴ・・怖い・・」
「こっち来て!」
攻める?責める?どっちだろう・・
でもきっと大したことはないだろう
兄さんとラブ君は遠くから手を振ってる
そう言えばあの二人、タルト食べたかな・・・
「僕より重傷みたいだね」
テジンさんがそろりと近づいてきた
「あ、マグカップ買って来ましたから」
「大変だったのに、悪かったね」
「テジンさんこそ怪我したんですって?」
「そうなんだ。たいしたことないけど」
「テジンさん、その事は・・」
「ああ、スハ、そうだったね。一応秘密になってるんだ、みんなにはちょっと・・」
「わかりました」
超重要極秘機密事項・・了解
でもきっと大したことはないだろう
「俺も撃たれたことあるんだ。兄貴をかばってよ」
鼻の下をさすりながらホンピョさんが言った
「俺はよ、まあその、自力で乗り切ったけどな」
「大変でしたね」
ドンヒさんが割り込んできた
「刑事さんが来てくれなかったら危なかったんだろ」
「そ、そうだったかな・・」
「最後は兄さんが守ってくれたって言ってたじゃないか」
「あれ、そうだっけ?おかしいなあ、俺が悪い奴をメッタメタのボッコボコに・・」
「もういい。こっち来い!」
意見が食い違ってるみたいだ
でもきっと大したことはないだろう
ジュンホさんは涙目になっていた
「ぼくはなぐられたことしかないのでよくわからないけど、いたそうですね」
「大丈夫です、ちゃんと治療してもらいてましたから」
「チーフにしっかりかんびょうしてもらってください。あまりやくにたたないとおもうけど」
「はい」
ジュンホさんは無駄口をきかずにいつも真っ直ぐに核心をつく
さすがボクサーだ
「ちょっと痩せた?」
そう言って近づいてきたのはテソンさん
「精悍な感じになったよ」
「そうですか?熱が出たせいかなあ」
「違うな、隣にいる人と比べるからだ」
「え・・」
「「ぷっ!」」
僕とテソンさんと同時に吹き出した
テソンさんは意外にユーモアがある
アラレちゃんのような眼鏡をかけた新人のビョンウ君が
僕は医大生ですけど経験不足なので怪我のことは何もわかりませんと言った
スーツの上になぜか作業着を着ている新人のソグさんが
この傷は労災が適用されるの?とまるで管理職のような質問をした
やっぱり眼鏡をかけていて少し落ち着きがない新人のジョンドゥさんが
まじで撃たれたの?君は撃ったの?どうなのよっ!と詰め寄ってきた
僕は答えるかわりに3人に自己紹介してよろしくお願いしますと言った
いつの間にか僕の隣に来ていた彼も自己紹介をして新人と握手した
「元チーフのミンチョルです。何かあったらスヒョンか僕に言って」
だめだよ、当分僕の面倒見るんだから、店のことはスヒョンさんにまかせなさい
それから僕はみんなと少し話をして
彼はスヒョンさんと何やら仕事の打ち合わせをした
そして店が開く時間が近づいたので僕たちは帰ることにした
彼は明日から店に出るとスヒョンさんに伝え
僕は当分自宅療養しなさいとスヒョンさんに言われた
帰りしなに彼はドンジュンさんをつかまえて話しかけた
「車の仕事はどうなってる?」
「順調だよ。年明けにプレゼンあるからそれに向けて準備中」
「ミンがちょっとよくなったら、一緒にボイストレーニングの時間も取ってくれ」
「何?」
「基礎の発声練習から始めないと」
「何それ?」
「ミンの傷が目立たなくなったらホームページの作成にも入るから」
「だから何それ?」
「デビューの準備だ」
「デビュー?」
「ミューズの初仕事だ。張り切ってくれ」
「ちょ、ちょっと待ってよ、聞いてないよっそんな話っ」
「言ってなかったか。なら今聞いてくれ。そういうことだ」
「ギョンビンっ、何それ?」
「あ、ああ・・」
僕は頭にある情景がひらめいた
いつか彼がパソごしに僕をじっと見つめていた目つきと
彼のオフィスに行った時、僕の顔をチロチロ見ていた彼とそのアシスタントの顔
あの事とこの事とが瞬時に結びついて突然に答が出た
「ギョンビンっ、知ってた?」
「いえ、あっと、うん、いや・・」
「どっちよっ!」
「詳しい事はまた後で」
彼はわめいているドンジュンさんの肩をたたくと、僕を目で呼んで出て行った
僕とドンジュンさんは一瞬目を合わせた
『これってどうよっ!』
『どうよって言われてもどうよっ!』
僕はドンジュンさんに、後で連絡するからと唇を動かし合図を送って彼を追った
後ろでスヒョンさんがドンジュンさんに話しかけるのが聞こえた
「ドンジュンが歌手デビュー・・いやあ、びっくりしたなあ・・」
楽しんでいる声色で、とてもびっくりしているようには聞こえなかった
僕は彼の後を追いながら、ドンジュンさんの膨れる顔を思い浮かべた
戸口を出たところmayoさんがまた立っていて、僕がお辞儀をして通りすぎるとくふっと笑った
「ジタバタしてもだめだよ」
「え?」
僕はmayoさんの方を振り返った
「もうすっかりその気になってるからね、あの人」
そう言いながら彼女は彼の後姿に視線を移した
そしてあっけに取られている僕を残して手をひらひらさせながら厨房へ消えて行った
mayoさんまでグルなの?!
僕は久しぶりに体中の血液がふつふつするのを感じ、なんだか傷口が開きそうな錯覚に襲われた
いとこの恋3 足バンさん
嫉妬してる?
テジュンに?
僕が?
何で?
僕は胸ぐらを掴んだイナに自分でも驚くほどの静かな声で聞いた
聞いてなかったの?
僕はあのふたりがうまくいってる時からずっと見守ってきたんだよ
あのふたりがうまくいくように支えてきたんだよ
言ったでしょう?僕の意思で生きてきたんだって
僕は本当に彼女が幸せなら…
「今の…ことだよ」
「何?」
「その人が亡くなってからのこと」
「あれから…何年経ってると思ってるんだ」
「年数なんて関係ない」
「だから何で僕が嫉妬するんだ」
「テジュンが羨ましいんじゃないの」
「はっ…君にイカレてるとでも言いたい?」
「さっき言ってたじゃない…彼女に…待ってていいかと聞いたままだって」
「…」
「今でも彼女の想いがテジュンに向いてるって思ってるんじゃないの?」
「そんなこと…」
「そんなこと意味ないのに…そう感じてるように見える」
「イ…」
「ずっと想い続けてるのは…自尊心なんじゃないの」
「…」
「今の自分を続けている限りはテジュンに負けないって…思ってない?」
後頭部から背中に電気が走った
一瞬頭の中がからっぽになり
身体中が寒気を感じてから一気に熱くなった
「君は…泣きながらひとを侮辱するの?」
僕は腕と身体に体重をかけてイナをテーブルの端に押しつけた
ゆっくりとゆっくりと掴んだ胸元を圧迫し
テーブルについたイナの腕が自分を支え切れなくなって
ついに倒れ込むまで押し続けた
僕は椅子に片足をかけ覆い被さって襟元を締め上げる
僕の影に身を沈める男は抵抗しない
彼の周りの色とりどりのチップは
子供の描いた絵のように無邪気に散乱している
おまえに何がわかるんだと
このままテジュンのように殴ってほしいかと言ってやろうと思った
わかりやすい怒りをぶつけるのが
この苦しい空間から出られる早道のような気がした
考えなしの脚本家のドラマのように
でもそうできなかった
ねじ伏せたイナは少しも恐怖を感じていない
涙でくすんだのその目は憐れみすらも映していない
あの時のテジュンと同じ
無性に哀しい気持ちがこみ上げた
ずっと長い間堪えてきたものが波のように押し寄せ
両目から涙が堰を切って溢れ出す
「何で…君なんだ…」
「…」
「何で…彼女じゃなくて君なんだ…あいつを動かしたのが…」
「ヨンナムさん…」
「彼女になくて君にあるものは何なんだ…え?…何なんだ…」
「…」
「あいつにあって…僕にないものは…何なんだ…イナ…何なの?」
イナのシャツの皺に僕の涙が次々と吸い込まれていく
イナの目が深い慈悲の色を帯びる
どこかで見た慈しみの目
「あなたはすごいひとだよ…ヨンナムさん…」
あの時の彼女の目だ
こんなにあのひとを愛しているのにと僕の胸で泣いたあの時
もうテジュンの元へは戻らないという決心を聞いた日
長い間抱きしめつづけた僕に
彼女はありがとうと言って唇を寄せてきた
震えて…躊躇して…
どうしても受けることができなかった僕に
彼女が言ったんだ
「あなたは素晴らしいひとよ…」
僕はイナにかぶっていた自分の影を少しずらす
白熱球の光が目にはいり眩しそうにするイナ
そんなことでしか僕は自分の気持ちを隠すことができない
眩んでしばらく閉じていた目をゆっくりと開けると
その視線ははっきりと僕を捕らえる
「すごいと思うよ…あなたも…」
「…」
「あなたがいたからでしょ…」
「あなたがいたから…そのひとはテジュンを思いきり愛せたんじゃないの?」
僕の
僕の心の壁に突然でかい風穴が開いた
ほとんど空気の通っていなかった空間に
いきなり大量の風がごおと音を立てて入ってきた
羽根虫はその風に吹き飛ばされた
僕は
僕は左手をテーブルにつき
利き手でゆっくりとイナの頬の涙の跡に触れてみる
あの時彼女にしてやりたかったこと
あの疲れ切った涙を拭ってやりたかった
目を閉じるとそこに彼女がいる
僕とあいつが愛した女性
ずっとずっと閉じ込めてきた涙がこぼれつづける
どうかしている…
そこにいるのは彼女なんかじゃない
まるで別人だ
でも…僕はそこに彼女を感じて目の奥が熱くなる
こみ上げる涙がまだ止まらない
あの時と同じように僕の頬に優しい指が触れる
目を閉じたまま顔を近づけ
震える唇で彼女の唇にかすかに触れてみる
触れたくて触れたくて仕方がなかったその唇に
彼女はそっと応えてくれた
暖かく柔らかく僕を受け止めてくれた
そして僕は今までの想いをこめて深くくちづける
僕の腰におかれているのはあの白い手で
伝わってくるぬくもりはあの柔らかい身体で
かすかな吐息はあの…
時間が僕の足元をさらい
麻痺した頭の奥の奥が安らぎのため息をつく
小さな電子音
目を開けるとそこには
優しく僕を見つめる知らない顔がある
僕はそのまま片手で電子音の元をさぐり耳にイヤホンを付ける
得意先の業務連絡を受けながら
頭の中の日常は胸ポケットの受信機に何ごともないように答える
目はすぐそこに組み敷いている男を幻のように見ながら
「はい…大丈夫です手配済みです」
僕は震える中指でその少し開いた唇にそっと触れてみる
「では後ほど…毎度ありがとうございます…」
耳の奥でツーツーという小さな音が響いている
灯の中で透き通る目をして僕を見ている幻
そしてその幻が言う
「どうして来てくれなかったの病院に」
「…」
「もし来てくれら…あなた…何て言ってくれたの?」
「…」
「ね、何て言ってくれた?」
「…頑張ったねって…」
涙が再び溢れ出る
「もう…大丈夫だよって…」
「そう…ありがとう…ヨンナム…」
僕は再びそのひとに唇を重ねる
その頭を抱きかかえ僕の中の細く長い隙間を埋めるように
深く深くくちづけをした
また耳のツーツーという音が意識に入り我に返るまで
唇を離すとそこにはイナがいた
僕はゆっくりと彼から離れまた白熱灯の輪の外に出る
何かを言おうとして飲み込んだ
もう逃げ出したいような気分は霧のように消えていたが
ただ今は何も言いたくなかった
ゆっくり歩きドアに手を掛けようとした時
イナが聞き取りにくい声で何か言った
僕には「これからも空と話しながら生きていくの?」と聞こえた
振り向くと男はテーブルに仰向けになったまま
灯りの下にその身をさらしている
僕は何も聞こえなかったふりをして部屋を出た
No Way オりーさん
「どうだって?」
「何だかその気らしい」
「その気らしいってどうすんのよっ」
店が引けた頃を見計らってドンジュンさんに電話した
例の話はどうやら本気らしい
祭りの時や、家のカラオケでデュエットしてたのを見て思いついたらしい
二人はきっといいデュオになる、彼はそう言って僕の頬をするっと撫でた
でも僕らは素人だし、ドンジュンさんも車の事で忙しいし、
大体僕は目立つ事あんまり好きじゃないし、などと反論してみたけど
彼はただにっこり笑うだけだった
ドンジュンさんは電話の向こうでめっちゃ興奮してる
「どうって・・」
「しかも突然でさあ・・何がボイトレよっ」
「そう言えばね、近頃何となくへんな目つきで僕を見てたんだよね」
「変な目つき?」
「何かこう品定めっていうか、商品を見るっていうか、そんな感じ・・」
「お前ら、何やってんの?」
「え?」
「キスしながら品定めされちゃってるわけ?」
「けほっ、そんなんじゃなくてね、時々ちらちらって」
「まあそりゃ冗談だけどさ、とにかく僕たち素人じゃん」
「うん」
「素人が歌手デビューって無謀じゃん」
「うん」
「そりゃ確かに僕らはね、素人にしてはルックスはいいしぃ、歌も歌わせれば人並み以上だしぃ、
ほら祭りの時とかさ、でもって踊りだってカンはいいしぃ・・」
「うん」
「下手なプロよりいいかもしれないよ」
「うん」
「だけどさあ、だからって何でデビューよ!?僕プレゼンの準備で忙しいのよ」
「だよね」
「やりたい事やりたいわけよ、わかる?」
「うん・・」
「ギョンビンだってやりたい事やりたいっしょ?」
「うん・・あ、でもやりたい事なんだ」
「ギョンビン、歌手やりたいの?」
「違うよ、彼がやりたい事がこれなの」
「ぶーーっ!それとこれとは話が別でしょっ。何が敏腕プロデューサーよっ。
身内に手をつけるなんてさあ、きっちり言ってやんなよ」
「うん・・」
「僕もドンジュンさんも無理ですって」
「うん・・」
「大体お前、今療養中なんだからね。わかった?」
「うん・・」
「んじゃ、バシッと言うんだよ、バシッと!」
「わかった」
「じゃまたな」
「うん」
「あっとしっかり休めよ」
「ありがと」
「じゃ」
ドンジュンさんはずっと興奮したまんまだった
僕はため息をついた
確かに僕だって歌手なんて言われても困る
何とか彼に思いとどまってもらわないと
「どうした?」
窓際に立っている僕の後ろから声がした
「疲れただろ。もうベッドに入った方がいいよ」
「ドンジュンさんに電話してたんだ」
「ドンジュンがどうかした?」
「やっぱ歌手は無理だって」
「無理?」
「僕も気がすすまないよ。素人だし」
「それは心配ない。しっかりトレーニングするから」
「でもドンジュンさん、車の事もあるし」
「かち合わないようにする」
「でも・・」
彼は僕の目の前に立って僕の頬を両手で挟んだ
「ミンも嫌なの?」
「気がすすまない」
「どうして?」
彼はそう言うと僕の唇にさっとキスした
「できないよ」
「そんなことない」
「だって・・」
「無理だと思うの?」
彼は僕の目を覗き込んでからまたキスした
さっきよりちょっと濃い目の
「歌手なんて柄じゃないよ」
「だからいいんだよ」
彼は今度は僕の唇を見つめながらまたキスした
さっきよりもっと濃い目の
僕は少しづつ彼の唇に魅かれていく自分を感じていた
「どうしよう・・」
「何が?」
「ドンジュンさんは困るって」
「車の事はちゃんと考えてるって言っただろう」
「でも・・」
彼は僕の唇が動きを止めるのを確かめてからまたキスした
最初は優しく丁寧に、そしてだんだん激しくとても深く
僕はくらくらして思わず彼の首筋を掴んだ
「大丈夫だから、僕にまかせて」
彼はそう囁きながら僕に深いキスを続けた
彼の唇が彼の舌が僕をどんどん引き込んで離さない
僕はこの人を見くびっていた
こんなキスをする人に逆らうなんてできない
ドンジュンさんをどうやって説得しようかとちらっと思ったけど
すぐまた彼の唇に思考を遮られた
彼の唇が僕を翻弄し、彼の舌が僕を溶かす
僕の腰に巻きついた彼の腕が動いて、僕の頭をそっと抱いた
彼の深いキスはずっと続いている
僕は夢中で彼の髪の毛を掴んで彼のキスに応えた
彼はそんな僕を焦らすように一瞬唇を離した
そして優しく囁いた
「ミンならきっとできるよ」
「うん」
僕は思わずうなづいていた
でもどんな無理でも聞いてあげなくちゃ
だって彼だもの
こんなキスだもの
ああ・・彼のキスはまだ終わらない
「あれがぐいーんでっか?」
「ちゃうちゃう」
「あれも十分エロいキスでっせ」
「あれは単品だわな」
「ぐいーんは単品ではないんでっか?」
「色々まざった複合品だわな」
「こらえらいこっちゃ。はよ見たいわあ」
「ぐいーんは寝て待て」
「そうでんな、また楽しみが増えましたわ」
残像 ぴかろん
明るい光が俺の目を射る
眩しくて目を開けていられないはずなのに
俺の瞳はその光源の先の先を見つめている
目が潰れてしまいそうだ
俺は誰?
そこにいるのは誰?
俺は何?
あんたは何?
夜なのか昼なのかさえも解らない
灰色の石ころの上で
俺は体を投げ出している
動けずにいる
俺が
俺の根っこが切り離されて
その光源に向かって凄まじいスピードで飛んでいくような
とてつもなく怖ろしい感覚に襲われる
ここから
離れなくては…
誰か
手を貸して誰か…
ズボンのポケットの電話が着信のダンスを踊っている
俺の手はそのダンスに導かれて電話を拾い上げる
声がいざなわれ、耳が起きる
『ヨボセヨ、イナ、寒いよぉ』
懐かしい声がした
でも今は…
「テジュン…」
『何してる?』
「ん…『オールイン』に…いるよ…」
『今日はそっちなの?』
「いや…ちょっと顔出しただけ…。てじゅ…仕事はどうなの?」
『いやぁ忙しくてさぁ、トイレぐらい行かせてくれって怒鳴ってきたんだ今』
「…トイレ行った?…ちゃんと手、洗った?」
何を馬鹿な事を俺は…
『洗ったさ!お前に電話するんだもの。…イナ…、ヨンナムんちに行ってないだろうな!』
「行ってないよ」
本当だ
『絶対会うなよ!BHCに水の配達に来ても逃げろよ』
「解ってる」
嘘だ
『あああ心配だっ!そうだ!ソクにも気をつけろよ!あいつスヒョク君とうまくいってるけど、余裕ができたらまたお前にちょっかいかけるかもしれないから』
「…んふ。大丈夫だよ。スヒョクのガードは鉄壁だ」
『ああもう早く会いたい!』
会えるんじゃん、会おうと思えば今夜だって…
「そうだな…」
『3日も我慢できなぁいぃ』
嘘つき
「しょうがないじゃん…」
『なんだよっ冷静だなっつまんねぇの!しゃびしいっちってくれよぉ』
「…寂しくないもん…」
『むぅ…。あ…はいっはいっ今はいっ…ごめんイナ、行かなくちゃ』
「てじゅ…無理して電話しなくていいぞ。仕事しっかりやってくれ」
『…うん…』
「俺も頑張るからさ…」
『あああっはいっ今行きますっ…イナ…愛してるよ』
「…ん…」
パタン
フリップを閉じる
ふーっと息を吐き、耳に当てていた腕を横に伸ばす
その腕がまた小刻みに震えた
「ヨボセヨ」
『イナっ!お返しは?!』
「ん?」
『僕、愛してるっちったろ?』
「…あ…ああ…」
『お前はっ?!』
「…言わなかった?」
『言ってない!』
「…ごめんごめん…。愛してるよ…」
『よしっじゃ』
パタン
ぱたん…
ふーっ
灰色の、石ころだらけの川原にまた寝そべる
こんなところに寝ていてはいけないというテジュンの声がする
俺はその声に助けられてようやく身を起こす
チャラチャラチャラと軽い石が俺の背中から川原に落ちる
現実に目を向けても、強い光の残像が、俺をそこから遠ざけている
チャラチャラチャラ
ゆっくりと身を捻って石ころを見る
残像がだんだんと薄れて、石ころがチップに変わる
「バラバラだ」
「壊しちゃった」
「きれい」
俺が言ったの?
誰が言ったの?
俺は立ち上がって見事な抽象画が描かれたそのテーブルに向かう
さっきまでしていたようにチップを集める
その色ごとに手早く纏め、一つの山を作る
もう一山…もう一山…
三つ作ったところで俺はその山を崩した
できない
しちゃいけない
俺がする事じゃない…
チャラチャラ…
チップを撫でて、俺は裏の戸口に向かう
「なんだ、イナ、今日はこっちか?」
「ヒョン…悪いけどあれ…頼む」
「あれって…おおお…お前ぇぇっなんでこんなばっらばら…」
「…ごめん…」
「ごめんっておま…おいっ!イナ!」
怒鳴るチョングをそのままにして俺は戸口を開けた
外に出ると体が凍てつく
吐く息が白い…
タバコが吸いたくなって近くの販売機で一箱買った
適当に押して出てきた箱は、テジュンの部屋にあったのと同じだった
BHCの控え室に行ってそこにいる仲間に火を貸してくれと頼んだ
誰かが俺のタバコに火をつけてくれた
俺と同じ顔をしたその誰かに礼を言って、俺はまた外に出た
こんな寒い外で
煙を肺に入れると
昇り立つ紫煙と一緒に
暗闇に吸い込まれそうに思う
俺の根っこはぎりぎり繋がっている
ふーっ
俺の心には根を張った人がいる
ふーっ
俺の幹を守ってくれる仲間がいる
ふーっ
チップを崩したのは俺だ
積みなおすの…任せていいかな…
ああそんなにキレイにしないで…
それじゃ元通りじゃない…
いいんだよ
貴方のチップは色とりどりの山にすれば…
混ぜて
その色もその色もその色も全部混ぜて
混ぜて積みなおして
そうしてよ
貴方が…
貴方が貴方の手で
お願いだから
俺は
俺には
手出しできない事だから
「いいよな…ほっといて…」
吸い込んだ煙にむせる俺
煙が滲みて涙が出る
「いいよな…ほっといても…」
『ヨンナムに近づくな』
「だって…来たんだもの…」
『ヨンナムに近づくな』
「だって…お前の事いうんだもの…」
『ヨンナムに近づくな』
「…もう…」
遅い…
吸いきったタバコを道に落とす
靴でその火を消す
拾わないと後で誰かに叱られるな…
幹を守ってくれてる誰かに…
ハハ…
笑った唇に指をあてる
冷たい指
冷たかった唇
誰に接吻したの?
『どうして行かなかったの病院に』
『もし行ったら…何て言いたかった?』
『ね、何て言いたかった?』
聞きたかったのは誰?
『…頑張ったねって…。もう…大丈夫だよって…』
満足した?
血が
通いだしたよ…
胸が締め付けられて嗚咽と涙が溢れ出す
誰のための涙なんだよ
あの人じゃない
あの人なんかじゃない
「ちょっと…怖かっただけだよ…てじゅ…」
冷たい壁に凭れてそのまま凍ってしまいたかった
俺は誰?
俺の根っこはどこ?
あの人の根っこは?
どこ?
One Way 足バンさん
ドンジュンの機嫌が悪い
ギョンビンと電話で話してますますふくれている
「だってそうでしょっあの天然!敏腕が聞いて呆れる!ただの自分勝手じゃん」
「そう怒るなって…せっかくこんないいムードの店に来たのに」
「スヒョン…知ってたんでしょ」
「んーどうだったかな」
「ふんっ何考えてんだかジジイたちは」
「声小さめにね、響くから」
閉店後、僕は確信犯的にふくれたさんをこのバーに連れて来た
以前はふらりと寄ったが、ひとと来たことはない
考えてみればドンジュンと飲みに出るのは初めてだ
カウンターに並んで座る僕たちは仕事帰りの先輩後輩というところかな
黒と紅の薄暗い店内に響くキース・ジャレットのピアノがしっとりと心地いい
「ああ…このひとの曲使いたいって言ってたなシン監督…」
「話はぐらかさないでよ」
「おまえ、そんなに嫌なの?」
「当たり前じゃない」
「そうかぁ…ふうん」
「…」
「それは残念だなぁ」
「ちょっと」
「そうか…嫌なのか」
「ちょっとスヒョン何言ってんの」
いぶかるドンジュンにわざと素っ気なく言ってみる
「ミンチョルね…映画の音楽やるかも」
「何?」
「映画の音楽のプロデュース」
「え?」
「ぼ、く、の、え、い、が、の」
「…」
「わかる?ぼ、く、の、え、い、が」
「わかったってば!…それってマジ?」
「明日監督に会って初アプローチする」
「ね、スヒョン…」
「絶対取るって張り切ってたなぁミンチョル」
「何で…」
「ぼ、く、の、え、い」
「わかったっつうの!…ね、それって僕の歌と関係あるの?」
「どうかなぁ…でもそうだった気もするなぁ…まだ企画段階だけど…たしか…」
「ね、あの…」
「ま、ドンジュンたちが嫌なら仕方ないな」
「ね、それってまたふたりで仕事するってこと?」
僕はたっぷり時間をかけてグラスを傾け、美しい氷の塊をからからと揺らす
小さなため息などもついてみる
心配そうに僕を見るかわいい顔がカウンター向こうの硝子に映っている
「直接は関係ないだろうけどね…いろいろ接点はできるね」
「…」
「悔しいから少しはやってみようって気になった?」
「ふんっまさか!そんな単純じゃありません」
「そっか」
「甘く見ないでよね」
「そうだな、そんな甘い仕事じゃないもんな」
「そうだよ」
「祭で余興やるのとはワケ違うし、相手はプロだからね…余程覚悟しないと」
「…」
「ミンチョルの人を見る目もわかったもんじゃないしなぁ…ね?」
「ん…」
「うん、やめた方がいいな、おまえとギョンビンが恥かくの見たくないしな」
「…」
「ね?」
「ちっとトイレ行ってくる…」
ずいぶん長く戻って来ないドンジュンの様子を見に行くと
ふくれたままレストルームの入口の壁に寄りかかっている
僕はゆっくりと近づいて壁に手をかけ顔をかしげて覗き込む
「連れのひとはどうしたの?」
「何さ」
「君、寂しそうに見えてたから…さっきから」
「何言ってんのよ」
「店…出ない?」
「ばかスヒョン」
「できればゆっくり過ごさない?」
はっとしたドンジュンの顔がいきなり弾けて僕の胸をばしんと叩く
「んぎゃーっわかった!それちょっと!あのシーンでしょ!台本の!コマシの!」
「あ…バレちゃった?」
「ぶぁっかスヒョン!何やってんのさ!」
「いてっ…リハーサルだって」
「もうもうもうどこまで僕をからかえば気がすむのさ!」
とは最後まで言わせずに身体をぎゅうと壁に押しつけて
ついでに唇も押しつけて濃い目のをひとつ
「んぐっ!ちょっと!何やってんのもう!ひとが来るってば」
「やってみたらどう?ギョンビンと一緒に」
「ちょっと!離せって!」
「あのお話憶えてるでしょ?」
「当たり前でしょ」
「泣いてくれたじゃない」
「だからって」
「僕が彼になるんだよ?」
「わかってるよ…」
「僕が彼を語って…おまえが歌うの…」
「…」
「そんな風にひとつになるのって…よくない?」
「でも…」
耳の下にそっと唇を当てて小さな音を立ててみる
「僕はやってみたい…おまえの声に包まれて愛を演じるの」
「ぅ…」
「いや?」
「…でも…実現するか…わからないんでしょ」
「ミンチョルに必ず取らせる」
「ちょっと…ひとが来るって…」
ドンジュンの心配通り一瞬背後にひとの気配がしたけれど
慌てて「あひっすみません」と言ってぱたぱたと行ってしまった
「ねぇってばっ…ひと迷惑だって…」
「おまえがうんって言わないと今日の客はみんな膀胱炎になるよ」
念のためにもう一回スペシャルバージョンのキスをして
目の潤んだふくれたさんにレベル”MAX”の微笑みを投げかける
「おまえの仕事に支障はなくしてもらうから」
「ぅ…」
「僕も協力するからね」
「…」
「やってみるね?」
「…」
「ね?」
「ん…」
「ふふ…いい子だね…じゃご褒美」
ふぐ担当、任務完了
Camera Test 足バンさん
スタジオは既に動き始めていた
カメラテスト用の機材が整えられライトのチェックが行われ
スタッフが右へ左へ動き回っている
少し早めに到着した僕は隅で邪魔にならないよう立って
シン監督たちが来るまでおとなしくしているつもりだった
もちろん見知らぬ僕に注意をはらう者などいない
…はずだった
「あなた、スヒョンさんですね?」
いきなり横から声を掛けたのは僕と同年代くらいの女性
小柄でショートカット、ジーンズ+セーター姿のおとなしそうな彼女は
「すぐにわかりましたわオーラ出てますもの!シン監督の言う通り!」と
快活に笑って真っすぐに握手を求めてきた
その場で彼女が監督と組んでいるムービーのカメラマンであることがわかり
話に聞いていたパワフルなイメージと全く違った印象に驚いたが
僕よりも6つも年上だと知り呆気にとられたのはもっと後のことだった
その日はシン監督、チョプロデューサー、カメラマン、音楽監督はもちろん
照明、衣装、美粧など大方のスタッフの顔合わせを兼ねる大掛かりなものになっていた
スポンサーの広報スタッフまで来ている
音楽監督の話からすると具体的なことはまだ決まっていない様子だ
彼はいわばまとめ役で実際の決定権は監督やPにある
テストの後にアポが入っているミンチョルに
彼ら全員の前で何とか一発かましてほしいところだ
スタッフと僕の顔合わせ後、監督から今回の経緯などについて話があり
すぐにカメラテストに入った
あの女性カメラマンの目がいきなり強い光を帯び僕を見据える
監督の言っていた「すごいひとだよ」という意味がわかるような気がした
ライトを浴び立ったり座ったりさせられながら、大勢の人間の目に吟味される
モニターを覗く監督たちの満足そうな表情からすると
特に問題はなさそうで、それなりにほっとする
しばらくして何人かが新たに入ってきた
その中の3人の男たちには見覚えがある
相手のヒョンジュ役の俳優さんたちだ
マネージャーらしき人たちは監督たちに異常なくらい丁寧に挨拶をし
僕にまで何やら笑顔をふりまいて自分のところの俳優を宣伝していた
緊張し真っすぐ前を見ている役者たちの目を見ていると
ものも言わずパソに向かって仕事をしているドンジュンの目と重なる
みんなその世界のチャンスをモノにしようと必死なんだろう
せめて今日のテストでは僕自身も全力で当たらなくてはと気を引き締めた
テストの内容は「ソファに並んで座り会話をする」
ただそれだけだった
ひとり目は比較的背の高い男で
モデルをやっていたというだけあって端正な顔立ち
自己紹介から初めて自分の趣味などをつらつらと話す横顔は優しい
カメラを十分に意識していて表情は硬いが
伏せた睫毛にライトが当たる様は美しくモニター映りは良さそうだ
監督たちも絵を見て満足そうに頷く
「ちょっとスヒョンさん、彼を抱き寄せてくれる?」
いきなりの監督の注文に僕がそうしようとすると
睫毛の彼は明らかに緊張してやっとのことで僕の腕におさまった
あんまりガチンガチンになってるのが可哀相で
僕が耳元で「力を抜いて」と囁くとますます硬くなって脂汗をかいている
初々しさでいくならいいのかもしれないが
ヒョンジュという男の影の部分は感じられないかもしれない
監督のOKが出るまで彼のリラックスのための努力は続いた
ふたり目は舞台出身の役者さんで
睫毛の彼よりはかなり場慣れしている様子だった
やはり端正で美しいが強い目のひかりの方が印象深い
彼は役の感じを出そうとしているようだった
重い心の病とあまりに純粋な心をあわせ持つ美しい男ヒョンジュ
きっと何度も読んできたのだろう
同じく監督の「抱き寄せて」という言葉にも自然に対応し
僕の肩に甘えるようにしなだれかかる
抱いた彼の身体から役を得ることへの強い情熱が感じられる
そのままじゃ芸がないかなと思い「キスでもしてみる?」と囁くと
彼はちょっと微笑んでいきなりキスをしてきた
さすが業界のスタッフたちはそんなことくらいでは動揺しない
ここぞとばかりモニターを覗き込んで監督たちが何やら話し込んでいる
ヒョンジュのイメージよりはかなり強いかなと感じつつ
僕は海辺でのシーンを思い描き
たっぷりとその子とのキスを堪能してOKの声を聞いた
3人目は新人の俳優でこの中では一番若い
チョさんが気に入っているが見た目の若さが気になると言っていた男だ
やはり美しい瞳はとても魅力的で
若いわりにはチョさんが求めている色気もあり
二番目の彼ほどの強さがない分どこかに寂しさを漂わせている
肩を抱き寄せた感じは一番しっくりときた
「君もちょっとキスしてみてよ」
監督の声に彼はちょっと戸惑っていたが
向こうに見えるマネージャーの「やれっ」というジェスチャーに
控え目に顔を近づけてきた
その様子がなかなかよくて僕は頬を支えて優しくキスしてやった
監督たちもその生な反応にウケている様子だったが
やはり若い印象が気になるのだろう
腕組みをしたままの顔は決して楽観したものではない
僕もヒョンジュという男はもう少し落ち着いたイメージだと感じていた
しかし僕とのムードに合わせてホンをいじることもあり得ると言っていたので
その辺はあまり気にしなくていいのかもしれない
候補の3人と付き添いがスタジオを出たあと
監督たちの声はいきなりくだけた感じになりボリュームが上がった
「スヒョンさんバッチリバッチリ!」
「いいわぁあなたいいわぁ、お祭りの映像よりずっとシャープ!」
「おおカメラマン女史の”あなたいいわぁ”が出たらこっちのもんですよ」
「相手によって絵もこれだけ違いますね」
「ね、スヒョンさんは正直言ってどう?」
モニターの前に呼ばれて先ほどの映像を見せられる
絵的には1番の彼が何ともいい感じだったが
しっくりとくるムードから言えば3番だろうか
見知らぬ人たちとキスする自分の映像を客観的に見ていたが
いきなりドンジュンのことを思い出して苦笑した
今朝、相手役とのカメラテストがあると聞いてぷりぷりしていたあいつは
初日から手出しちゃだめだよ!
監督さんに”ひとりずつ味見してから決めます”なんて言わないように!
などとまくしたててとっとと自分の打合せに出て行った
さっきのキスは味見に入るかな?
ずいぶん話し合った後、ほぼ3番目の彼に決まった
僕が感じたしっくり感をかなり考慮してくれたようだった
正直言ってほっとした
というのも役者が決まらず不安定なムードのまま音楽の打合せになだれ込むのは
ミンチョルといえどもマイナスになるんじゃないかと思っていたから
ミンチョルに何としてもこの仕事をとらせてやりたい
半ばで成し得なかった仕事にもう一度トライさせてやりたい
しかし
こののち僕は数え切れないため息を吐くこととなる
Bitter & Sweet ぴかろん
イナが変だ
タバコを指に挟んで控え室に火を借りに来た時すぐに解った
僕はライターの火を灯して、焦点の合わない目をしたイナのタバコに差し出した
イナは虚ろにありがとうと言って外へ出て行った
「妬くなよ」
「え?何が?」
「妬かないでくれよ、ラブ」
「…」
「イナが…変だ」
「…」
「何かあったみたい…」
ラブは少しだけ唇を尖がらせた
「だから妬くなって」
「すぐに解るんだ…イナさんの事は…」
「ラブ」
「…。俺も変だとは思ったけどさ…確かに…」
「…。もし…イナがキスしてくれって言ってきたら…するかもしれないけどいい?」
ラブはギロリと僕を睨み、それから妖艶な微笑みを浮かべて人差し指を僕の唇の隙間に差し込んだ…あん…
そして下唇だけを親指と人差し指で摘む
そのまま指を巻き込んで、
「いってぇぇぇぇっ!」
僕の下唇に爪を立ててぐいっと引っ張った…
「ひたひれしゅ…らふしゃま…」
「調子に乗るんじゃないよ!」
「ほへんなしゃい…」
「…心配しなくてもアンタにキス求めてなんかこないよ!」
「れも」
「俺がケアするから」
「あにっ?!」
「…確かに変だし…イナさん…。どうしたのかな…」
「くん…あろ…しょろしょろゆひをはらしてくらしゃい」
「ああ…。…。やだっ!唾ついちゃった!きったないっ」
ラブは指先を僕のゼニアのスーツにねじくった
酷い…
「妬くなよ」
「え?何が?」
「妬かないでくれよ、スヒョク」
「…」
「イナが…変だ」
「…」
「何かあったみたい…」
スヒョクは少しだけ唇を尖がらせた
「だから妬くなって」
「すぐに解るんだ…イナさんの事は…」
「スヒョク」
「…。俺も変だとは思ったけどさ…確かに…」
「…。もし…イナがキスしてくれって言ってきたら…するかもしれないけどいい?」
「あり得ません!」
「…あり得ないって…解んないじゃん!」
「馬鹿な事言わないでください!」
「…スヒョクぅ…」
「絶対許さないもん!」
「…でも…」
「ソクさんがそんな事するくらいなら俺がイナさんにします!」
「だめっ!それはだめ」
「…どうしたのかな…イナさん…テジュンさんいなくて寂しいのかな…」
「…違うと思う…」
「俺も違うと思う…」
「…」
もっと吸いたかった
火がなかった
俺は裏口からBHCの中に入り、厨房に行った
「mayoさん、使い捨てライター持ってない?」
奥のmayoさんが何か言う前に、テソンが俺の前に立ちはだかった
「なんでmayoに聞くの?」
「…あ…。mayoさんなら色々その…」
「控え室にメンバーいっぱいいるだろ?なんでmayoんとこに来るの?!」
「テソン!…イナシ、これ…どうぞ。珍しいね、ここんとこタバコ吸ってなかったのに」
「…。ごめん…。いくら?」
「いいよ、あげるから。それとこれも…」
mayoさんは携帯灰皿も一緒に渡してくれた
俺を睨んでいるテソンをちらっと見て、mayoさんに礼を言ってもう一度外に出た
立て続けに何本か吸った
気持ち悪くなるぐらい吸った
寒さのせいか体が緊張しているからなのか、えづきそうになって俺は吸っていたその1本をねじ消して中に入った
「イナさん、どこにいたの!指名入ったよ」
「…あ…」
ウシクに声をかけられた
仕事…仕事しなきゃ…
「悪い…。5分待ってって言ってくんない?」
「もう5分待たせてる」
「…顔洗ってくるから…誰かいない?」
「解った。早くね」
「悪いな…」
俺はもう一度厨房に入った
テソンがまた睨んだ
「ごめん…お客様にチョコの盛り合わせ出したいんだけどさ…」
「…」
「俺につけといて…。待たせちゃってるから…。俺ちょっと顔洗ってくるから…」
「歯も磨けよ。タバコ臭い」
「…ああ…。ごめんテソン…頼む」
「ラジャ」
テソンは不機嫌な顔で頷いた
俺は言われたとおり歯を磨いた
何度もえづいた
涙が溢れた顔が鏡の中にあった…
顔を洗った
もう一度鏡を覗き込んだ
仕事…
俺も頑張るから…
お前は仕事をしっかりやって…
俺、頑張るから…
この仕事が好きだから…
本当に?
…
本当に…
頭をふるふると振って頬を軽く叩く
気合を入れて顔を拭き、控え室に戻ってシャツを着替える
何人かいたメンバーが俺を見つめているような気がしたが
これ以上お客様を待たせるわけにはいかないので
俺は黙々と着替えを済ませて厨房に行った
チョコが用意されていた
「ありがとう…。いつものと違う?」
「…特別だ。高級なの。イナさんにつけときゃいいんでしょ?」
「…ん…」
***************
「テソン、ちょっとイナさんにきつかったよ」
「だってなんでmayoに頼るのさっ!」
「私なら使い捨てライター持ってると思ったんでしょ?」
「たかられてるのにmayoったら!」
「ちゃんとお金払うつもりでいたよ、イナさん…」
「…そうだけど…」
「ちょっと変だね…」
「…うん…」
「チョコ、用意しなきゃ…」
「…ん…」
「いつものでいい?」
「僕がやる…」
****************
「テソン…それ…」
「…」
「あたしにもちびっとしかくれないやつじゃんっ!」
「ふふ。はい…一個だけね…」
「…これ…出すの?」
「…。イナさん変だから…」
「…テソン…」
「それにイナさんにつけときゃいいんだから、水増し請求しとく!ライターと携帯灰皿の分、上乗せ」
「ふふ…」
「…どうしたんだろ…。いつもの『しゃびしい』じゃないみたいだ…」
「…あの子も大人になったのかしらねぇ…」
「ばぁか…」
「くふ…」
***************
「イナさん、ちょっと待って」
「ん?」
テソンは皿の上の一個を取って俺に差し出した
「これは…イナさんのために…」
「…え…」
「元気が出るよ」
「…テソン…」
揺れそうになった
チョコの包みを剥こうとするテソンを制し、仕事済ませてから貰うと言った
テソンは少し目を丸くして、それから微笑んだ
「解った…じゃ、欲しくなったら寄ってよ。必ず」
「…。さんきゅ…」
俺はその特別なチョコを持って客席に行った
客席には新人三人が並んで固まっていた
お客様からの質問攻めに合い、しどろもどろで答えていた
俺は詫びを入れ、チョコを差し出した
それからリクエストを受け、いつものようにパフォーマンスしたり、いつものように楽しい会話をした
俺、頑張るから…
この仕事が好きだから…
俺…プロだから…テジュン…
その後も指名が入り、俺はいつものように仕事をした
閉店間際に俺はまた厨房に行き、テソンとmayoさんに礼を言った
高級なチョコレートにお客様は大満足だった
「一息ついた?」
「ああ」
「じゃあこれ…」
「…え…でも…」
遠慮する俺をよそに、テソンはチョコの包みを剥き、俺の口元に差し出した
「あーん」
「…あーん…」
口を開けるとテソンはチョコを放り込んだ
口の中でじっくりと溶けていくその固体を、チョコレートだと認識するのに時間がかかった
美味しいのに、ほろ苦くて甘いチョコレートなのに…
今日の俺の感覚は、何かがブロックされていて、すぐに反応できないでいるみたいだ…
「どう?」
「…あ…うん…。美味しい…」
「…それだけぇ?」
「…ごめん…」
表面のチョコと中のチョコの味が違う?
最初、俺の舌は、苦さしか感じてなかった…
溶け出したそれはやっぱりチョコレートだ…
何かに似ている…
今日の俺の感じた何かに…
なぜかまた涙が出そうになった
それに気付きたくなくて俺は慌てて礼を言い、控え室に行こうとした
テソンが近づいてきて、俺をそっと抱きしめてくれた
温かかった
涙を堪えて控え室に戻り、荷物をまとめた
早く一人になりたい
でも一人になるのが怖い
「「イナ」」
ギョンジンとソクに同時に声をかけられた
顔を上げると二人が睨み合っている
その後ろでラブとスヒョクがギョンジンとソクを睨み付けている
「なにこの四人は!」
「…お前…どうしたの?」
「え?」
「なんか様子…変」
「…。ちょっと…寂しいだけだよ…てじゅがいないから…」
嘘つき
『嘘つき』『嘘つき』『嘘つき』『嘘つき』
「気にしてくれてたの?ありがと」
「…僕のキスが必要ならばいつでもぐえっ☆」
「慰めてほしけりゃ僕がいてぇぇぇっ」
俺にそんな言葉をかけてくれたジジイの二人は、それぞれの若い恋人達にきっちりシメられていた
ふっと笑って大丈夫だからと言い残し、俺はRRHに戻った
ミンチョル達にただいまとだけ告げて、俺は部屋に閉じこもった
シャワーを浴びてすぐにベッドに潜り込む
想いが…
次から次へと寄せてきて
俺は眠ることができなかった…
© Rakuten Group, Inc.