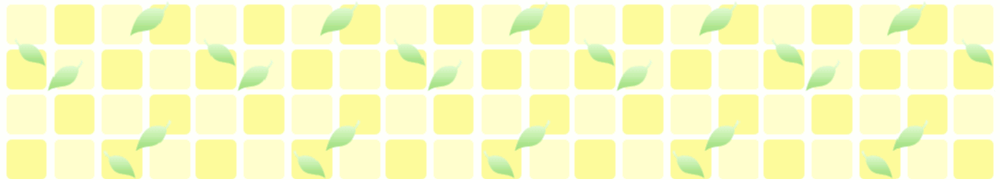リレー企画 265
ゆく処 あしばんさん携帯にスヒョンの伝言が入ってた
ー撮影、終わったよ、少し飲んで帰る
どきん…
スヒョンはめったに留守録なんかしないから
そこからあの声が響いてきただけでも緊張したんだけど
終わった
終わったんだ
そう思ったらなぜか急に心臓が跳ね返り始めて
僕はロッカーに寄りかかって、暫く目をぎゅっとつぶっていた
終わったんだ…終わった…どうしよう
いや、全然、全く、どうもしなくていいんだけど
とにかくその時の僕はひたすら「どうしよう」って考えてた
ロッカールームに入って来たソヌっちが「おや?」という顔で
向こうに行き過ぎようとしていた足を止めた
僕は質問される前に背筋を伸ばし「何でもない」と言って首を強く振った
ソヌっちは二ヤリと意味深に笑って奥に行ってしまった
はぁ…どうしよう
おとといは何気ない話でスヒョンの様子を伺って焦れた
昨日はズバリ核心に触れかけて結局辛かった
今日は…今日はどうしよう
やっぱスヒョンちに行くのはよそうか
でも今朝ちゃんと送り出さなかったし
行かないと…へそ曲げてるみたいかな
でも…でも…そうじゃないって思わせるにはクールにしてなくちゃいけない
僕は、そのクールってやつが一番苦手だ
考えあぐねて床を睨んでると足音が近づいてきて
顔を上げれば、ソヌっちが手に収まる程度の箱の包みを差し出した
「これね、レモンティ、ひと箱あげる」
「へ?」
「ティーバッグだけど、けっこういい香り」
「うん…でも…」
「知り合いからたまに貰うの、僕はまた貰うから」
「あり…ありがと…」
部屋にジョンドゥたちがドヤドヤと入ってきて
ソヌっちは手をヒラヒラさせてまた奥に引っ込んでしまった
そういえば彼がミューズのHP作成に参加してくれてるらしくて
一度話を聞きたいと思ってたのに、また聞き損ねた
まぁ…ミューズの話になれば僕らの主題歌の話にもなるから
それはそれで気が重いんだけど…
帰る先を決め切れず
でかいテントを張った屋台でおでんを食った
会社帰りの沢山の男たちが、仲間と笑ったりブツクサ言ったりしてるのを肴に
その日店では我慢してたため息を吐き、少しだけ焼酎も飲んだ
スヒョンもあのバー辺りでひとりで飲んでるんだろうか
だって、あのひとはもうRRHに帰ってるらしいってギョンビンが言ってた
ある意味ギョンビンが羨ましい
帰るべき場所に、いるべきひとがいる
僕は…
こんな日が一番不便だ
会いに行く理由も会わない理由もあり過ぎて
でも
一緒に住むなんて…今更だし…
鳥肌が立つかと思うほど驚いたのは
ずいぶん長居した屋台を出て、ぼんやりと光の溢れる大通りを歩いてた時
でかい交差点の向こうの巨大なスクリーンに
いきなり見覚えのある目が映って
僕は赤信号で立ち止まる人の群の中で、たぶんただひとり息を止めた
本をゆっくりとめくる指…憂いの瞳
キッチンの流しに落ちる1滴の水
蒼いセーターを着た男の背中
デスクの上の古い封筒
本の文字をそっとなぞる指
黒いソファの肘掛けに腰掛ける男
目を閉じる横顔
窓の外を横切る白い鳩、羽根の音
目を開ける男
水の入ったグラス
唇に触れようとする指
漂う視線
壁の古い写真
窓の外の柔らかい光
ほんの僅かに微笑んだかのような瞳
I Feel You
髪をかきあげる男
Jin Blue
側に立ってた女の子3人組がその映像を見て嬉しそうにしてる
聞こえる小さな嬌声の中に「ジン」という言葉があった
突然、目の中心が熱くなって潤んだ
あれは…僕のスヒョンだ…ジンなんて男じゃない
あの目は溶けるほど僕を見つめるし
あの指は僕の指と絡み合うし
あの唇は僕の身体の隅々までキスしてくれるし
あの綺麗な髪は僕の手でくしゃくしゃになることだってあるし
次の腕時計のCMの途中で信号が「行け」(僕にはそう感じた)に変わり
流れ出した人たちを縫って僕は走り出した
スヒョンんちに辿り着いたのはもうかなり遅い時間だったと思う
玄関の硝子に薄く灯りが映ってて
もう帰ってるんだってことはわかったんだけど
薄暗い部屋は静まり返ってたから、一瞬思い違いなのかと思った
窓に向いた白いソファを覗いて
そこで眠ってるスヒョンを見つけた時はホントにドキリとした
庭の灯の陰影に浮かび上がる青白い顎の線が作り物みたいだったから
薄青に見えるシャツ、軽く交差させた黒いスラックスの足
いつもの癖で片腕を瞼に乗せて寝てるから
ほんの少し開いた唇だけが薄紫色に濡れて見える
その…そのはだけた胸に合わさったあのひとの肌を思えば
仄暗い動悸が頭に響く
僕は、ただ奥歯を噛み締めることだけを自分に許してその場に突っ立っていた
気配を感じてスヒョンが腕を額にずらしゆっくり目を開けて
ああ、何か言わなくちゃと思って
その時、唇がすごく乾いてたことに気づいた
「ごっごめん…起こしちゃった?」
「お帰り」
「留守電聞いた、お疲れさま」
「夕飯は?」
「あ…うん…適当に済ませた」
すごく普通の会話
「店は大丈夫だった?」
「へ?」
「お店」
「ああ…んと、今日厨房にちぇみのおっちゃんが来てくれた、そんでテソンさんが店に出て
テス君も手伝ってくれて…あ、あのピーちゃんもまた何かと華やかにしてくれて
そう、チェリムさんとメイさんが助っ人に来てくれた」
「そうか、イナとギョンジンは?」
「セーフセーフ、先生ったら泣くほどホッとしてたみたい
うん、こっちの話はそんなとこなんだけど」
う…墓穴
「こっちの」って…「そっちの」ことを聞きたいみたいじゃない
ゆっくりとスヒョンがソファに起き上がるのを見て
なぜか少し慌てた僕の口から出た言葉は
「こっ、紅茶飲むっっ?」
「ん?」
「ソヌっちに貰った!ティーバッグだけどレモンだって、レモン!」
ティーバッグとレモンは何の関係もないんだけど
きっと僕の顔には何かよくわかることが書かれていたんだろう
スヒョンはツッコむこともなく「頂こうかな、ちょっと飲み過ぎたし」と言って静かに笑った
それからディーノ(ポットの愛称だ)で湯を沸かすまで
僕たちはずっと黙ってた
ソファの背に腕をかけて僕を見てるスヒョンも
ディーノの前で湯の温度が上がる小さな音を聞いてる僕も
その沈黙の間、僕の思考は強い風に舞う道端の桜みたいに散り散りになる
その日の撮影でどんなことがあったかは…
まぁ完成品を見れば瞭然だけど
スヒョンとあのひとだけに流れた時間についてはわからない
ずっとどこか深いところに注がれてるスヒョンの気持ちが
どくどくと音を立てて僕の前を流れ過ぎていくようで…
その辿り着く先を覗いてみるのが怖くて
僕はいつまでも目の前の流れだけを見てる
それが…それがね
ただの嫉妬だったらもっと楽かもしんない
でも流れながらスヒョンも傷ついてるんじゃないかって、この頭はつい考えて
それは、僕がこのひとを本気で好きになってからこっちの悪癖
相手のことを大事に考えてるなんて、そんな殊勝なものじゃない
苦しいのは自分だけじゃないって言い聞かせて
自分を丸め込もうとしてるだけなんだ
それが…どんなに捻れた自慰行為かってこともわかってて
マグにたっぷりの紅茶をいれて
ソファで足を組んでるスヒョンに渡す
僕はその横に…少し離れて膝を抱えるように座った
その離れ具合が不自然かなと思い、ちょっとだけスヒョンに寄った
でも微妙に離れてるのもおかしいと思い、もうちょっ寄った
尻をちょびちょびとずらしてるうちに
結局、最後はスヒョンの身体にぴたりとくっついた
ホントはそうしたかった
思春期のガキみたいだけど
そのロンネフェルトっていう紅茶はとてもうまかった
レモンの香りがくすぐったいくらいよくて
両手で持ってるマグが暖かくて
段々それが食道から胸の辺りにじんわり広がって
くっついてるスヒョンの身体もあったかい
ほんの微かに香るのは石鹸だろうか
僕の知らない石鹸の匂い
僕は黙って紅茶を飲んでるスヒョンの横顔を盗み見た
そう…これはスヒョンだ
この目は溶けるほど僕を見つめるし
この指は僕の指と絡み合うし
この唇は僕の身体の隅々までキスしてくれるし
この綺麗な髪は僕の手でくしゃくしゃになることだってある
でも…それが何だって言うんだろ…
この横顔が向こうを向いたままだったら
僕はどうするんだろうか
一度も、二度も諦めかけた恋だった
でも
僕は、きっとどんな形でも好きでいるんだろう
この身勝手な海みたいな男を
失望しても、怒りにはち切れても、僕はこのままの調子で
全然違うところで全然違う生活を始めても
やっぱり好きなんだってどこかで自覚させられるんだ
ずるいよあなた…
どうせなら
もっとめちゃくちゃに嫌なとこ見せてくれればいいのに
僕に見えるものといったら
自分で抱え切れないほどの情愛を持て余してる男の艶と
他人には決して見せない針みたいな孤独
痛いほど惹かれるんだ
それが絶望や喪失と隣り合わせであってさえ
少し前から僕の目を見てるスヒョンの顔が突然ぼやけたのは
堪えてた涙がぶわっと溢れてきたかららしいけど
僕は急いでマグに顔を突っ込んで紅茶をすすった
もう絶対に泣かないって決めたし
スヒョンにそれを見られるのもすごく嫌だったから
勿論、目ざとい男がそれを見逃したとは思えず…
スヒョンは片方の腕を上げて僕の頭を抱き寄せた
今日二度目の長い沈黙の後、スヒョンの静かな声
「ドンジュン」
「…ん」
「今夜来てくれてよかった」
「…そ…なの?」
「うん」
「…そか…」
僕は、その時まで入れていた首の力を抜いて
スヒョンの肩にすっかり頭を預けた
「スヒョン…」
「ん?」
「明日の朝は、フレンチトーストがいい」
「わかった」
僕の髪に軽いキスが落とされた
本当に
哀しいくらい
いい香りなんだ
紅茶も、それから…
プラスマイナス…? 1 ぴかろん
ぼんやりとステージを見ながら、イナは思った
店に入ってから何度驚いただろう…
*****
勢いよく裏口からBHCに入り、イナはトイレに向かった
用を足していると、誰かが洗面台の鏡を覗き込んでいるような気配がした
手を洗おうとイナも洗面台に向かい、初めてその人物をしっかり確認した
「…チェリ…ム…さ…」
「よっ。イナちゃん」
いなちゃん?
「…。な…にして…」
「ヘルプだよ」
「…。テプンの?」
「人手不足だって聞いたからさぁ」
口調がオトコだ…
そう言えば以前チェリムはスヒョンのおふざけでヘルプとして店に出たことがあった
それにしても…
「とっ…といれは女子用を…店の方にちゃんとあるし…」
「あっち使うとお客様にとっ捕まるからめんどくさいじゃん」
「…れも…」
「ね、口紅の色、濃いかなぁ」
「へ?」
「抑え目の色にしたんだけど、どう?」
「…」
スヨンより赤くないという事は解るが、どう?と聞かれてもなんと答えてよいのかイナには解らなかった
「ちょっとチェリムぅ、何やってんのよ!」
「だってさぁ、口紅の色、アンタと被るじゃん」
「いいじゃないのよ、誰も気にしないわよ」
「…め…い…さん?」
「あら、イナさん。こんばんわぁ」
メイはチェリムと同じようなスーツを着込んでいる。しかし胸元が少し苦しそうに見える
「苦しいわぁ、ちょっと開けようっと」
「あっアンタ!見せつける気ね?!」
「だって苦しいんだもん」
プツプツと三つほどボタンが外されたシャツから、メイの豊かな胸元が覗いている
イナは驚き、慌てて手を洗ってその場から逃れた
あたふたしながら厨房に顔を出したイナは、「ひっ」と声を上げた
来たか、持ってけ!と豪快な『男のサラダ』を持たされ、チェミに背中を押されて厨房から追い出されるイナ
チェミさんなんでここに…というイナの呟きは、闇夜の「人手不足」という低い声に掻き消された
「あ、イナさ~ん、こっちこっちぃ」
ニコニコと手招きするテスに小さく驚きながらもサラダを運んだイナは、くるりと振り返ったBHC顔の持ち主が誰なのかが解るまで、きっちり10秒かかった
「てそ…」
「ふぃ、あんがと。ささ、みなさぁん、チェミの『男サラダ』らよっ」
「…てそん…が…接客?」
「くふん…イナシぃぃくふふん」
「酔ってるの?んでテスは、もしかしてヘルプ?」
「うん。イナさん、済州島どうだった?チョンエ元気だった?ってじっくり話聞きたいけど、後でね」
「あ…おん…」
ニコニコ顔のテスは、放っておくと誰にでもヘラヘラと擦り寄って行くテソンを見張りながら、イナを追い払うようにバイバイと手を振った
チェリムにメイにテスにテソン…厨房にはチェミ…、人手、十分じゃねぇのか?
そんな事を思いながら、イナはイヌを探した
「☆ sorry、おー、ごさいじぃ」
「…」
「おかえりぃ」ハグッ
「げ…。ぴー」
「んふっ可愛いなぁ、キスしようか」
「なんでピーちゃんが…」
「だってぇ、イヌ先生がヘルプ~っていうんだものぉけひひん」
「…」
「ちなみに昨日もヘルプしたから俺」
「…。そ」
金髪ゴリラまで投入したとは…イヌ先生、見境なさすぎじゃないのか?
店内をうろつきながら、イナは思った
ようやくイヌを見つけ、先生只今帰りましたと言うと、涙ぐんだイヌが、よく無事に帰って来てくれたね、イイコイイコと抱きしめてくれた
隣のボックス席に殺気を感じたので、イナはすぐに先生から離れた
「…イナさん…おかえり…」
ウシクがウシクらしからぬ低い声を響かせた。イヌはゴクリと唾を呑み込んだ
「俺、どこに入ればいい?」
「…そ…そうだな…。ラブ君のところへ…彼らもうすぐ舞台に上がるし」
「はい」
返事をしたものの、『彼ら』とは誰のことだろう…
ラブ一人ではないのか?ポールも?だとしたらそれも驚きだ
イナはイヌに言われたとおり、ラブたちの席に入って接客をした
今日は随分客が多いと驚き、ラブとポールのコンビネーションのよさに驚き、テソンの愛想のよさに驚き、メイとチェリムの『危ないパフォーマンス』に絶句し、チェミの料理に驚き、チョンマンの元気のなさに驚き…
そして今は舞台の上で『ゴム芸』を披露しているジホに驚いている。随分ハイテンションだけど何かあったのかなぁ、と考えていると、ラブとポールが「いってくるね」と立ち上がった
皆で「いってらっしゃい」と見送った後、イナの近くにいたマダムが、昨日のツアーではラブちゃんとポール君の濃厚なキスシーンがとってもよかった…と言い出した
「もしかして『ふゆそなつあー』のお客様ですか?動画を撮った?」
「そーよぉぉ。ラブちゃんがあんまり可愛くってぇ(^o^)だから今夜のお店、『ソナタ』から『BHC』に店を変更したのよぉ」
「そうそう!今回のツアーは、景色は素敵だったけど、もしラブちゃんたちがいなかったらホントにつまんなかったと思うわぁ」
「ねっ。次回のツアーは『彼らだけのつあー』にしようって言ってるの!」
「でも『彼らだけのつあー』だと…」
「「「「「きゃーっ(>▽<)やっだぁ~奥様ったらぁ(>▽<)」」」」」
「…」
何がどう『やっだぁ~』なのかは解らないが、イナはとりあえず唇を尖らせながら笑顔を作った
「きええええ!」
イナのいるボックス席近くまで、ジホはこめかみに青筋を立てながら、ゴムを引っ張ってやってきた
「見て見て!すっごいでしょ?きひっ☆あーーーー」どすぅぅぅん☆
頑張っていたジホは、ゴムの反発力で舞台にすっ飛んでいった
大変な勢いに心配になったが、すっくと立ち上がって愛想を振りまいているジホを見て、イナは、さすがはM大王だと思った
スポットライトが舞台中央のジホから袖に移る
いかつい体格の男の背中がライトに浮かび上がる
よく見ると、首筋に巻きついた腕が見える
BGMはムードたっぷりのジャズだ
「きゃ。始まったわ!」
「「「「「ラブ&ピーよぉぉっ (>▽<)」」」」」
ラブ&ピー?
首筋に巻きついていた腕が、男の背中を這いまわっている
男がくるりと振り返ると、男の唇にがっつり齧り付きながらぶら下がっているラブが現れる
ラブ!何をやってるんだっ人前でっ!(@_@;)
イナはまた驚いた
「「「「「きゃーっ(>▽<)すてきぃぃぃ~」」」」」
「(@_@;)すてき?!」
がっつり濃厚なキスを舞台でぶちかましているラブとポールを見ながら、とりあえずギョンジンがいなくてよかったとイナは思った
ぱさん…
イナのボックス席に誰かがヘルプに来たようだ
ふと見るとそれは…
「ぎょんじんっ(@_@;)」
「…や、イナ…」
「お…おま…(@_@;)」
「ラブ…。元気そうでよかった…」
舞台を眩しそうに見つめながらギョンジンが呟いた
プラスマイナス…? 2 ぴかろん
目の前で柔らかく微笑んでいるギョンジンを見て、イナは思った
よかった?ラブは金髪ゴリラと舞台でチューをかましてるんだぞ?!
なんで『よかった』なんだ!
いやそれよりも、お前、今日帰って来るなら帰って来るって言えよ!お前まで抜けたら大変だと思って俺はテジュン孝行もしてやれずに慌てふためいて帰ってきたんだぞ!
ギョンジンに向かって文句を言おうと準備していたイナに、ほやっとした顔つきのギョンジンが声をかけた
「イナ、済州島どうだった?」
「え」
「テジュンさんと愛し合えた?」
「(@_@;)」
「愛って…大切だね、イナ」
「…。お前…どうしたの?」
「え?どうもしないけど」
イナはギョンジンを見つめた。ギョンジンは慈愛に満ちた瞳でイナに微笑みかけた
「…ギョンジン、お前…どっか悪いのか?」
「え?」
「調子悪いのか?」
「いや(@_@;)大丈夫だ!」
「…」
ラブとポールは『濃厚接吻ショー』を終えて客席に向かって微笑んだ
割れんばかりの拍手と嬌声が店内に溢れかえる。皆に愛想を振りまいていたラブだったが、突然瞳を見開いて動かなくなった
その瞳に涙が溜まり、唇がふるふると震えだす。ラブは舞台を駆け下りて、イナの傍にいるギョンジンのところへ走ってきた
「ラブ…」
「ひっく」
「ただいま…」
「ぶぁがっ!」ばっちぃぃん☆
涙目のラブがギョンジンの頬をひっぱたく
「(☆▽☆)ひ…ひいん…」
「ぶぁがっ!ぶぁがっ!」
ラブは泣きながらギョンジンの胸をドンドン叩く
「あは(^^;;)痛いよラブ…、痛いってば…あはは(^^;;)」
「なんで助けにこないのさ!俺、舞台でゴリラに襲われてたんだよっ!」
…襲われたはないだろう…あんなにうっとりキスしてたくせに…
イナはポールに同情した
ラブは罵りながらも甘えた目つきでギョンジンを見上げ、ギョンジンは嬉しそうにラブを見つめている
舞台に取り残されたポールは照れくさそうに頭を掻きながらパッと耳に携帯を当てると、舞台を一周して袖に引っ込んだ
それと同時に緞帳が下ろされ、ショータイムが終わった
*****
「「「「「きゃーっ(>▽<)噂の『ラブちゃんの奴隷』だわぁぁ~すてきぃぃ」」」」」
マダムたちはバチバチと2人の写真を撮っている。ギョンジンはすかさず『襟巻き』になった。ラブは甘えた顔をしてギョンジンの肩に体を預けている
イナは苦笑してそっと席を立った
裏に回って舞台の入り口に行くと、ポールが溜息をついて階段に座っていた
「お疲れ様」
「お、ジミー」
「お疲れのうえにお気の毒様」
「ふ。ラブちゃんはミン・ギョンジンにぞっこんなんだなぁ」
「そうだね」
にっこり微笑むと可愛くなると、イナはポールを見て思った
「ちょっとぉ、そこの人ぉ、手伝ってよぉ~」
声の方を振り返ると、舞台の幕の後ろでゴムに絡まっているジホがいた
「ジミー、あの人何してるの?」
「しらない。ほっといてもいいよ」
知らぬ顔を決めようとした二人に、哀しげな声が襲い掛かる
「ちょっとぉぉぉ…おねがぁぁい…たすけてよぉ…手伝ってよぉぉ」
「「…」」
イナとポールは顔を見合わせてジホに近づき、ゴムを解く手伝いをした
「絡まったまま明日までここにいれば?」
「そぉはいかないよぉ、僕はいろいろ忙しい身の上だものぉ」
「じゃ、ショータイムやんなきゃよかったじゃない、ジホさんったら俺より後に来たくせにいきなり舞台に立ってるし…」
「だって出遅れたから目立たなきゃ。それにギョンジン君よりは早かったでしょ?」
「…あいつ…来ると思わなかったなぁ…」
「よっぽどラブちゃんに会いたかったのかな」
ポールは鼻をこすってイナを見た。その仕種も結構可愛いとイナは思った
「しっかし、こんなに硬く誰が結んだの?」
「ソヌっち」
「…そ…」
その名前を聞いてポールは条件反射のように身を縮める
「じゃあソヌさんに解いてもらえばいいじゃない」
「ダメよ。あの人すぐにイラついて手首切り落とすとか言い出すから」
「…」
ポールの喉がゴクリと鳴ったのを聞きつけ、ジホはニヤリと笑う。イナはゴムと格闘しながら冷ややかに言葉を発する
「切ってもらえば?」
「あぉ…ごさいじったら残酷ぅ」
「残酷?ジホさんに言われたくない」
「なぁんでぇ?僕はいっつも優しいよぉ」
「ぴーちゃん、切っちゃおう!」
「え…」
「やめてよぉ、ごさいじぃ」
「嬉しそうに『やめて』って言わないでください。ぴーちゃん、このゴム、切っちゃおう」
「やめてっ!ゴム切っちゃだめっ!」
血相を変えて叫ぶジホを見て、手首は平気でもゴムはダメなのかとポールは思った
「ソヌさん呼んできた方が早いよ」
「不器用だなぁごさいじは」
「む。解かないぞ!」
「あぅ…ごさいじぃ」
「怖がってないで手伝ってよぴーちゃん!」
「あ…うん」
三つほどあるゴムの結び目と格闘しているイナに近づいたポールは、突然短い悲鳴を上げた
「どしたのぴーちゃん!」
ポールの目の前に、暗幕から突き出された人差し指があった。それはまさしく目の玉の真ん前にあり、少しでも動けば、ポールの眼球を貫きそうだった
暗幕を引き摺りながら姿を現したソヌは口角を上げて笑顔のようなものを作り、ポールの目の前で人差し指をクイクイと曲げ伸ばしした
「な…んですか…キム・ソヌシ…」
ポン、と肩を叩き、来い、とでも言うように強く指で合図する。ポールが動かないでいると、またツイっと目の玉の前に人差し指を突き立てる
「ひ…。わかりました…いきます…」
顔を引きつらせながらポールが動くと、満足そうな微笑を浮かべてソヌも動く。二人は舞台袖から離れて行った
「…ぴーちゃんってソヌさん苦手?」
「あぁんごさいじだってソヌっちは苦手でしょぉ?」
「…」
確かにソヌは苦手というかとっつきにくいというか…どう絡んでよいのかわからない人物ではあるが、今ここでゴムに絡まっている妖怪じみたジホも、イナにとっては十分『苦手』の部類に入る人間…いや…
「モンスターら」
「うふ♪ソヌっち、カッコイイけどモンスターよねぇ。謎だわぁ」
この場合、絶対に皆、「あんたのが謎だらけのモンスターだよ!」と即答するだろう…と、イナは思った
「あぁん痛いから早く解いてよぉ」
「…。今日はミンチョルとスヒョン、休みなんだろ?」
「うふん」
「ジホさんは何で休まなかったんだ?時間かかる撮影だったんじゃないの?」
「わりとスムースに終わったのよぉ。それに僕は疲れてないからねぇ」
「…」
「彼らはとっても疲れたと思うわぁ」
「…。ふぅん」
「あら。どんなシーン撮ったか、気にならない?」
「…」
「聞きたいのに聞かないのね?」
「…。うわぁ、ソヌさんよっぽどジホさんに恨みでもあるんだね。すっごい結び方だ。わけわかんない」
「捩れまくってるからねぇ、彼」
あんたのが捩れまくりだよ!と心の中でツッコミを入れたイナは、撮影現場で自分を叱ったジホと今ここにいるジホが同一人物であると認識できずにいる
もしかすると自分はまだ地下鉄に乗っていて、夢でも見ているんじゃなかろうかとも思う。玉水の駅周辺は、自分の知らない街並みだったし、あのタクシーの運転手だって随分都合がよすぎるのではないか?そしてギョンジンだ。ラブと濃厚なキスをしていたポールを罵りもしなかったし、あいつが今日帰って来るなんて知らなかったしそれに…
「美しくて切ないベッドシーンだった…」
「え…」
「2人の想いが溢れ出てた…」
「…」
「十分伝わっているのに一つになれないんだよ。辛いねぇ」
2人の想いとは、スヒョンとミンチョルなのかそれともジンとヒョンジュなのか…、イナは問い質すことを躊躇った
聞いてどうなる。それを知ってあの若い2人に同情を寄せたところで何の足しにもなりはしない。むしろドンジュンとギョンビンが自分の瞳の中に憐憫の色を見つけたら、余計に気を遣わせることにならないかとイナは考えた
「なんで聞かない?」
「…別に…今知っても仕方がない」
「仕方ない?」
「…。とにかく…あいつらの撮影がハードなんだってことは解った」
「そ。ハードだと思うよ、肉体的にも精神的にも」
「…」
「そういうところ理解してあげてほしいな~。店に出てきたら、彼ら自身が意識してる部分を皆で解きほぐしてほしいなぁと僕は思うのよ」
「…。ふぅん…」
「そういう役目をいつもは僕の弟子がしてくれるんだけどねぇ、今日は役立たずなんだよ、ダメねぇ」
「チョンマン?…見てたの?今日も…」
「あの子は向上心があるから」
「…。二人の…ベッドシーン?」
「そう」
「…。ジホさん、それをチョンマンに、いつものようにみんなの前で面白おかしく報告してほしいって思ってるわけ?」
「そうよぉ。でなきゃ雰囲気悪くなるじゃん」
「…ジホさんにはできても、チョンマンにはできないって事もあるだろ…」
「あの子はやればできる子なのよぉ」
「…」
結び目がようやく緩んだ。するすると解けていくゴムの下で、ジホの手首は赤くうっ血している。イナはそこにそっと触れてみた
「あら。解けた?うふん、感覚が鈍ってるわぁ」
「…。オネエ言葉、似合いすぎてヤバいよ、ジホさん…」
「うきっ。じわじわ感覚が戻ってきたわぁくふん。全くソヌっちったらきつい性格なんだから!あの人、『Do-eme』ってメニュー、バンフに載せてるけど、やることはいっつも『Do-esu』よねぇ!ああん、酷い。すっごい跡がついてる!…あ…、『跡』って言えば撮影のあとのあの二人の肌にうっすらと紅い花びらが…」
「やめてください!」
舞台への階段を駆け上ってきたチョンマンが声を立てずに叫んだ。彼の頬には涙の筋があり、イナはこの男がどれほど正直な人間なのかよく解ると思った。そしてこの男に今日、あの2人の撮影報告をさせることがどれほど酷な事なのかもよく解った
プラスマイナス…? 3 ぴかろん
「やぁチョンマン、なんで泣いてるの?」
「監督は平気なんですか?!今日の撮影の事、あの2人に知れたら…」
「いずれわかるじゃない、どうせ見ることになるんだから」
「でもっ、作品としてなら冷静に見れてもっ、現場の生々しい報告なんてっ」
「あはん。生々しかったよね。イイモノ見せてもらっちゃったぁ♪」
「ふざけないでくださいっ!」
「あら、だってアンタ感動したでしょ?」
「…しました…」
「ジンとヒョンジュに感動したんでしょ?」
「…でも…。でも演じてたのはスヒョンさんとミンチョルさんで…」
「そう。彼らは『演じて』たのよ」
「…」
「美しかった。切なくて泣けた。ジンのヒョンジュへの狂おしい愛を感じた。そして、ヒョンジュもまたジンを愛しているとよくわかるシーンだった。彼らは素晴らしい『役者』だと思った…。アンタ、あの直後に僕ンとこに来て泣きながらそう感想述べたじゃない」
「…そうだけど…そうだけど…」
「彼らは『役者』で、あれは『映画のワンシーン』でしょ?」
「…でもっ…でも…スヒョンさんとミンチョルさんが…ジンとヒョンジュに見えちゃって…」
「素晴らしいことじゃない。それだけ彼らが役柄に没頭してるって…」
「ジンとヒョンジュじゃなくて、スヒョンとミンチョルじゃねぇのか?」
済州島にいたときから感じていたことを、イナはつい口に出してしまった。ハッとしたようにチョンマンがイナを見つめる。ジホはゆっくりと振り向いてイナに微笑みかける。そしてイナの瞳を覗き込んでヒュウと口笛を吹いた。チョンマンは視線をジホに移した
色が変わる。こと映画となると彼の周りに薄く纏わりついている空気が、何もかもを逃すまいと粘り気を帯び始める。ジホは本心を見せない。時折、幾重にも張り巡らされた網の隙間から、用心深い彼の本質のようなものを見た気になるのだが、それが本当にジホの本体なのかどうかは解らない
読み取りたいが複雑すぎるし、近づいたかと思うとはぐらかされる。そこがジホの大いなる魅力ではある
ともあれイナの率直な心と言葉は確実にジホを刺激している、とチョンマンは思った
「そうだろ?あれはスヒョンとミンチョルの物語だ。たとえヒョンジュ役がミンチョルでなかったとしても、あの話の『ヒョンジュ』はスヒョンにとっての『ミンチョル』なんだ」
「ふぅん、ごさいじはそう解釈するのね?」
「スヒョンの想いがそのまま溢れ出してるんだ…」
「言っとくけど、あれは『映画』なんだよ、ごさいじ」
「それでもあれは『スヒョンとミンチョル』なんだ」
「…。だとしたら?何が言いたいの?ごさいじとしては」
「だから…だから…」
「監督、やめてください…もういいよ」
「よくないよチョンマン。ごさいじのご意見を伺いたいね。で?ごさいじとしては何?あの映画がスヒョン君とミンチョル君の話だって言うの?」
ジホはイナの言葉を遮った。傍目には熱く語り始めたイナの暴走を抑えるように見えるだろう。だがチョンマンにはなんとなく解る気がした
嬉しいのだ…イナがあの映画を真剣に考えることをジホは喜んでいるのだ。イナがどう感じているかを聞きたくて仕方がないのだと
そして自分もジホと同じ思いを持つことに気づき、チョンマンはどきりとした
「少なくとも2人のシーンは…そうなんじゃないかなと思う…」
「ふぅん、現場、一度しか見てないのにそんな風に思うの?」
「…今日のは…あの時以上だったんだろ?」
「演技だよ」
「演技でも。あいつらの気持ちは近づいたよ…触れ合うことで…」
「それで?」
ジホはイナの次の言葉を促した。イナは唇を噛みしめているチョンマンに目をやって呟いた
「…そうなると辛いよな…ドンジュン達は…」
「うん…」
「でもな…よかったんだと思う、俺…」
「…。オモ…」
口元に手をあてて驚くジホの瞳がほんの一瞬、嬉々と瞬いたのをチョンマンは知らない
「…ずっと誤魔化し続けてるよりよかったんだと…俺、思うよ、チョンマン…」
「イナさん…」
「抑えても抑えても消えないなら噴き出させたほうがいい…でなきゃ余計ドンジュンとギョンビンが辛い思いする…」
「ふぅん、ごさいじったら随分成長しちゃって…。済州島で何があったのかしらぁ、興味深々だわぁ」
まるでお楽しみを先延ばしにしたいとでも言うように、ジホはイナを茶化した。チョンマンの心は大いに乱れていた。茶化すジホの気持ちが解る。茶化すジホに腹が立つ。涙もろいイナが涙腺を緩ませることなく話す事が嫌だと思う。なのにイナの言うとおりだと思う自分がいる
「…イナさん…ぼく…」
「チョンマンの様子見てりゃ、どんなだったかなんて解っちゃうよ…」
「…え…」
「お前、今日、変だもの。毎日のように撮影覗きに行って皆に報告してるお前が何も言わずに沈んでるんだから。ドンジュンもギョンビンもあいつらが今日どんな撮影するかなんて、お前よりよく知ってるだろ?そういう事考えりゃさ…もう…伝わってるんだよ、チョンマン」
「ごさいじ。今日の精神年齢、35歳ぐらいじゃないのぉ?」
「だからこいつに無理強いすることないよ、ジホさん…」
不思議な気がした。今日の現場で感じ取ったこと、それを報告出来ないこと、イナの話に揺さぶられること…それらに自分は関わっている。今から話そうとしているのは間違いなく自分の本心である。泣きそうな気持ちを抱えている。なのに…
なのにチョンマンはカメラを覗いているように感じる
ジホの傍にいると、まるでセルフ撮影の映画の出演者になったみたいだと思う。ありったけの感情を表現する自分とそれを客観視する自分とが同時に存在しているような…
自分は醒めているのだろうか…よく解らない…
曖昧に「ふぅん」と呟いて口元に手をやったジホの赤い手首を見つめながら、チョンマンは静かに話した
「ぼく…ドンジュンと同期でしょ?…あいつ初めガチガチのカタブツだったのに、スヒョンさんの手ほどき受けて段々色っぽくなっていくの見てきた…。あいつが笑うとスヒョンさんも嬉しそうに笑ったし、あいつが困ってるとスヒョンさんは遠くから優しい眼差しで励ますように見つめてたのも知ってる…。スヒョンさんはドンジュンの事とても大切にしてるのに…とても愛してるはずなのに…なのにスヒョンさんは『ヒョンジュ』に心を奪われてる…
ぼく…混乱してる…架空と現実がごっちゃになっちゃって…ぼく…」
スヒョンとミンチョル、ドンジュンとギョンビンのことだけでなく、今の自分も架空と現実の中で混乱している…チョンマンはそう思った
「チョンマン、イナちゃん、僕、何度も言ってるけど、あれは『映画』なんだよ。どんなに『愛し合ってる』ように見えても、『映画の中の話』なの。あれは『夢』なのよ」
「…全部、夢?」
イナがそう呟いた時、チョンマンはジホを見た
「だよ。だって機材が一杯あって、カラダの一部分に装置つけられての触れ合いだよ。何人ものスタッフがいる中で自分自身の本能の赴くままにそんな行為ができるとしたら、僕は彼らを『違うジャンルのムービー』に売りつけるよ」
また茶化してジホは言った。それでもイナとチョンマンの心は、気掛かりな一点から離れなかった
「『夢』の中の想いは『うそっぱち』か?」
「『夢』は『夢』だよ」
「『嘘』ではないだろ?」
「…。『現実の真実』だっていうの?…『ジンとヒョンジュの想い』が?」
「…ジホさん解ってるんだろ?『スヒョンとミンチョルの想いが』…だよ」
「だったら?」
「…」
「彼らの想いが真実であろうとなかろうと、あれは『映画』なんだよ、イナちゃん」
「…」
「ま、確かに…今後の『きっかけ』にはなるかもしれないけどね…」
「監督、もしそんな事になったらドンジュンは…ギョンビンはどうなるのさ…」
「…それ、今考えてどうすんのよチョンマン」
「…どうって…」
「苦しむさ」
あっさりとイナが答えた
「…。そうね、ごさいじ。苦しいね、きっと…」
「でもチョンマン、俺、それでいいと思う。…どっちにしろ…苦しむよ、あいつら」
「…どっちにしろ?」
「あら、わかんないの?チョンマン。ここで露呈させなきゃあのジジイ2人は『想い』を後生大事に抱えたまんま、青少年達と向き合っていくことになるんだよ。しかも青少年達は、ジジイ達の『想い』をいやと言うほど解ってる…お互いが爆弾抱え込んで、触れないように気を遣いながら生きていくみたいなモンだよ。でしょ?ごさいじ」
イナは軽く頭を動かした
Distance 6 ~ひとひらの紅~ オリーさん
儚なげなふりをして
人の心の奥襞にまで忍び込む
桜の花びらのようだった
彼の喉元の奥深く
胸の浅い谷間のはざ間につけられた
ひとひらの紅・・
そろりと紅に指を伸ばす
指先がそこに触れる直前
その紅はひらりと生を受け
見る間に桜吹雪に変化(へんげ)する
あたりは漆黒の闇
その闇を切り裂き舞い上がる
無数の紅たち
それは僕を威嚇し遠ざける
吹雪の中
切り取られた視線を
繋ぎ合わせようとするけれど
絡め取られた手を
伸ばそうとするけれど
どうすることもできない
彼の姿は消え
ひとひらの紅たちが
狂おしく舞い踊る
触れないで
抱きしめないで
愛さないで
どうか僕の彼を・・
「おかえり」
僕を出迎えた彼は、すでにバスローブを羽織って
ワイングラスを手にしていた
彼が一人で飲むことは珍しい
するりと冷たい風に頬を撫でられた気がした
僕は何でもないふりをして言ってみる
「もう飲んでるの?」
彼はそれには答えずうっすらと微笑んで
無造作に赤ワインを注いで差し出した
「一杯どうだ?」
僕がグラスを受け取るのを確かめて
彼はそのままソファに沈みこんだ
そして残ったワインを一気に喉の奥に流し込んだ
僕はグラスを握り直し彼の隣に腰をおろした
彼は空のグラスを見つめながら静かに言った
「今日、思いがけない事があった」
「思いがけない事?」
問い返した僕の胸の奥がざらざらと音を立てた
空のグラスを見つめたまま答えない彼に
こらえきれず、もう一度訪ねた
「何かあったの?」
彼はボトルに手を伸ばし
グラスに赤い液体を注ぎこんだ
そして
ワインをゆっくりと飲み込んでから口を開いた
「オーディションに落ちた青年がやってきた」
「え?」
「ヒョンジュの候補だった青年が楽屋におしかけてきたんだ」
「おしかけた?」
「決まりかけた役を僕に横取りされたと思ったようだ」
「脅されたの?」
「いや、スヒョンが間に入ってくれて大した事にはならなかった」
「そう・・スヒョンさんが」
「思ってもみなかった。知らない間に他人を蹴落としていたとは・・」
僕はしみじみと
目を伏せている彼の横顔を見つめた
この人は何という人だろう
今日ドンジュンさんに言った言葉を思い出した
よくも悪くもイノセンス・・
僕は握りしめたグラスを持ち上げ一口飲んだ
極上の赤ワインは僕の喉元をするりと通り
ざわついた臓腑に落ちていった
それを確認して僕はおもむろに口を開いた
「何言ってるの?」
彼がゆっくりと僕の方を振り返った
「誰かが浮けば、誰かが沈む。元々そんな世界にいたんでしょ?
というか、自分が浮かせたり沈めたりしてきたくせに」
彼の瞳孔がわずかに開いた
「今更そんな事言うなんて、らしくない」
「ミンの言うとおりだ」
彼は素直に頷いた
「僕はたくさんの歌手を選んでは浮かせ、沈めてきた」
「神の手は血まみれってわけだ」
「ひどい言いようだな」
「そう?」
僕はもう一口ワインを飲んだ
「でもそんな役回りも必要だし、ビジネスはビジネスなんだから」
「それも・・確かだ」
「似たような事はどこにでもころがってる。
いちいち気にしてたらキリがない。」
「今日はどうした?」
「え?」
「何だかいつものミンらしくない」
「そうかな、僕は当たり前のことを言っただけだよ」
「・・・」
「ただ、痛みを知っているかいないかで違いがあると思う。
切り捨てられた側の痛み。経験済みでしょ?
だから他人の人生でゲームをしているような手合いとは違う」
「経験済みか・・そのつもりだったが・・
オーディションを受けた人間がいたことすら忘れてた」
「それは・・まあ、いきなりの展開だったから仕方ない・・」
「情けない話だな・・」
彼は小さくため息をついた
「押しかけられたのがそんなにショックだった?」
「正直言うと・・そう・・ショックだった。
役を取るために体を売ったんじゃないかと言われた時は・・」
「え?」
「僕に決まったのはその手の裏があるんじゃないか、と」
「そんな事言われたの?」
「ああ」
「あり得ない」
「そういう見方をされる事もあるんだと、
覚悟しておくべきだったかもしれない」
「冗談じゃないよ。そんな事してたら、僕が許してません」
「ミン?」
「そう言ってやればよかったのに」
彼はその時初めて顔を和らげた
そして僕の首筋を掴んで僕を引き寄せた
「思いつかなかった、いい台詞だ」
そうなのだ
この人は、
限りなく我儘で底知れなく無邪気
そして僕は
そのどちらにも憑りつかれている
どうしようもなく・・
「今日は店はどうだった?」
「人手不足で大変だったよ」
「そうだった、すまない」
「でもイナさんも駆けつけてくれたし、兄さんも出てきた」
「お兄さんは戻ったのか?」
「うん。最後の方に滑り込み」
「それは大変だったな・・」
「でも応援部隊もすごかったから」
「応援部隊?」
「ロジャースさんはまた来たし、テソンさんも店に出た」
「テソンが?」
「厨房は強面さんの応援があってね」
「チェミさん?」
「テス君も手伝ってくれたし、チェリムさんやメイさんもね」
「そんなに?」
「何しろ抜けた穴が大きいからね」
「すまない・・明日は出るよ」
「うん」
僕は彼とたわいのない話を楽しもうとした
彼と飲みながら話すのは久しぶりだったから
今日の撮影はどうだった?
この簡単な一言を何度か飲み込んだ
それを言いたいのか
言えないのか
言いたくないのか
どうなんだろう
心が迷子になったよう
僕がグラスを空けるのを見届けた彼が
微笑みながらボトルに手を伸ばした
そして僕のグラスにワインを注いだ
流れるようなその動きを追っていた僕の視線に
いきなり艶かしい現実が飛び込んできた
腕の動きにつられ
彼のローブの衿元がわずかにはだけた瞬間
その刻印が僕の心臓を握りしめた
彼の胸につけられた・・・あの人の印
あの人はどんな風にそれをつけたの
彼はどんな風にそれを受けたの
モニターに大写しになったあの人の横顔
二人で睦まじく歩く海岸
あの人の指からこぼれ落ちる煙草
店でやけに静かだったチョンマンさん
テンションが高かったジホ監督
僕に慈悲深い笑顔を向けるイナさん
頭の中でさまざまな場面が入り乱れる
僕は注がれたワインを一気に飲み干すと
シャワーを浴びると言ってと立ち上がった
彼はソファの背に片手をかけて
先に休んでいるかもしれない、と言った
はだけた胸元の印をさらしながら
シャワーを浴びて部屋に戻ると
彼はすでにベッドに入っていた
僕はバスタオルを抱えながら
しばらくの間、その背中を見つめていた
その印がついていることをわかっている?
気づいている?
それとも
知っていて
気づいていて
僕の所へ帰ってきた?
僕はベッドに近づいた
彼がゆっくりと振り向いた
「どうした?」
「いや、別に・・」
僕はバスタオルを落としてベッドの方へ歩き出した
彼はベッドに滑り込もうとした僕の方を見上げた
「兄さんの土産は何だった?」
「何?」
「あの水色の箱、ティファニーだろ?」
「あれはボールペン。でも兄さんからじゃない」
「・・・」
「先生からもらった」
彼は一瞬デスクの上の水色の小箱を振り返った
「先生から?」
「そう」
「なぜ?」
「なぜって?」
「ボストンまで何しに行ったか知らないが、忙しい旅だったはずだ。
よく時間があったな」
「宿はコプリープレイスの近くだよ、店をのぞく時間くらいあったろう」
「そんな事を言ってるんじゃない」
「じゃあ何?」
「あの人はミンに好意を持ってる」
「・・・」
「気づいてないのか?」
「それは・・わかってるつもりだよ」
「なら不用意に物をもらうな」
「不用意・・」
「誤解の元だ」
彼の視線が上目遣いに僕を捉えた
その瞬間、僕の中で何かがはじけた
「誤解してもらってもかまわない。僕もあの人が好きだ」
「何だって?」
「聞こえなかった?僕もあの人が好きだ」
静かな時間が僕たちの間に流れた
まるで時が止まったような白い氷の時間
彼の瞳から表情が消え、無言で僕に背を向けると
ブランケットを引き上げた
あの人がいつもあなたを見ているように
先生は僕を支えてくれる
先生は痛みを知っているから
その痛みを与えたのは
僕なのに・・
言葉をつなごうとした僕は
彼の背中にごうと鳴る桜吹雪を感じ
その言葉を飲み込んだ
それきり僕らは、その夜言葉を交わすことはなかった
僕は同じように彼に背をむけた
目を閉じるとその奥で
漆黒の闇にそそり立つ大きな桜の木から
花びらがたえまなく降り注いでいた
桜は人を狂わせる
こんな風に・・
触れないで
抱きしめないで
愛さないで
どうか僕の彼を・・
替え歌 「風の姿」 ロージーさん
どうして今更悲しがるの、と
鏡の中の僕が微笑ってる
とうに何度も描いた景色
少しは慣れてもいい筈なのに
嵐が近い 嵐が近い
折れた心が僕を揺らしているの
だから
風の姿を誰か教えて
愛の姿を誰か教えて
かぞえきれない数の定義じゃなくて
たった一人の愛の言葉で
僕をつなぎとめて
平気なふりして病んでた季節
身体の奥が本当は痛かった
外すことさえ出来ない何か
捨ててあなたに甘えたかった
嵐が近い 嵐が近い
思いがけない僕かもしれないの
だから
風の姿を誰か教えて
愛の姿を誰か教えて
かぞえきれない数の定義じゃなくて
たった一人の愛の言葉で
僕をつなぎとめて
だから
風の姿を誰か教えて
愛の姿を誰か教えて
かぞえきれない数の定義じゃなくて
たった一人の愛の言葉で
僕をつなぎとめて
(中島みゆき『 風の姿 』)
© Rakuten Group, Inc.