桜のうた(3)
後鳥羽院
1) 桜咲く遠山鳥のしだり尾のながながし日もあかぬ色かな
藤原俊成
2) 幾年の春に心をつくし来ぬあはれと思へみ吉野の花
式子内親王
3) はかなくて過ぎにしかたをかぞふれば花にもの思ふ春ぞ経にける
の三首に始まり、あいだに二首を置いて、八首にわたる古歌がつづきます。これらはいずれも新古今の時代よりはるか往昔の作で、その古雅な味いに捨てがたいものがあります。世々の歌びとの声を聴く意味でも、この八首を取りあげてみましょう。
(02春下0104)
山辺赤人
ももしきの大宮人はいとまあれや桜かざして今日も暮しつ
宮廷に仕える人々はいとまがあるのだろうか。今日も桜をかざしにしてひと日を優雅に送っているが。(かざしは花の枝などを手折って髪や冠に挿す風俗。)
赤人は万葉の歌びと。この歌は万葉集では「梅をかざしてここにつどへる」となっており、平安時代の古今六帖、和漢朗詠集といった書物に採られたときに下の句が変化したようですが、歌としてはこちらのほうがはるかに優れています。まず、「つどへる」という言葉には動きがありませんが、これを「今日も暮しつ」とすることで言葉のなかに動的なひろがりが生れました。今日もという言葉のひびき、移りあいも美しく、「今日」で代表される時を描写の対象とすることで、その背後にある時間の大きな流れが歌のなかに描きこまれ、「暮しつ」の動的なひろがりがいっそう深められた面があります。
そして、梅を桜と改めた点。これがなによりこの歌に晴々とした趣を与えています。大宮人は宮廷に仕える人々のこと。「ももしきの」は宮にかかる枕詞です。もし彼らが愛でるものが梅であれば、この歌は、海外の事情に詳しい宮廷の知識人たちが観梅の宴をひらいているというただそれだけのことにすぎません。梅を見るという風習が中国から伝えられたものであることを考えても、それはいかにも「つどへる」という言葉に代表される動きのなさ、とざされた印象を与えます。古い時代の日本で、梅を見るという風習と美意識を持っていたのは、ごく先進的な(それは海外知識が豊富であり、日常から遊離した知的な態度である、ということと同義です)人々に限られていました。
ところが、これが桜であれば様相は一変します。桜を見るということは、日本に古くからある野遊びと田の神祭りの風俗(桜の語源は、おそらくサ・クラでしょうが、クラは神のいますところ、そしてサは早乙女、早苗のサで稲作に関係する接頭辞です)が中国ふうの花を観賞する審美的な風習と融合して生れたものであり、本質的に一部の知識人、宮廷人にかぎられたものではなく、ほとんどすべてのひとにとって共感を持って受けいれられるものなのです。それゆえ、梅が桜へと改められた時点において、この歌は「自分たちとは関係のない、遠いところにいる人々の様子をながめた歌」ではなく、「自分たちの代表として春を楽しんでいる人々の様子をながめた歌」へとその性格を変質させたのです。そこに、このうたの魅力であるひろやかで晴々とした春の気分が生まれた。この歌は大宮人を難じたものでも、我々と彼らは違うといった歌でもありません。ああ、あの人たちもやってるなやってるな、というやわらかな春の親和力を詠んだ歌なのです。
(02春下0105)
在原業平
花にあかぬ嘆きはいつもせしかども今日の今宵に似る時はなし
桜の花に逢うたびに、いくら心をつくしても、もうこれでいい、もうたくさんだ、という気持を味う暇もないうちに散ってしまう嘆きを感じてきたが、それでもなお今日のこの夜のように惜しい心がまさったことはない。
業平はご存じのとおり色男の根本、六歌仙の一。古今集成立よりも前に活躍した、平安時代前期の歌人です。言うところは深く、言葉が直截であることは、この歌を見てもわかるとおり。感じ方の繊細さと、それを暴力的に言いきる言葉のつよさがこの歌人の魅力です。永遠の未完といった趣の、しかしふるえるような至純さを持つ歌。
飽く、とは、以前にも書きましたが、もうこれ以上いらない、もう充分だ、ということです。満ちたりることを言う。しかし花を相手にするとき、私の心にはそういう平安が訪れることは決してないのです、というのが業平の述懐なのです。風雅の人の業の深さというべきでしょうか。美しいものは罪深い。人が満足ということを知りうるのはその対象が不完全であるからなのかもしれません。完璧な美を前にしたとき、人間は永遠にその美を求めようとする業を背負わされている……。業平が言いたいのはあるいはそういうことなのでしょうか。「いつ」はどこと定められない場所や時間を指す語です。時も所も選ばずに、私は花を想い、しかしその恋がついに成就しない嘆きを負っている、それがこの歌の深いところにある声です。時も所も選ばずに、どこと定められず、いつと決められず、とは逆に言えば限定できないほどのひろがりそのものを指すものです。永遠。久遠。そういってもいい。嘆きは永遠へとつづいている。
その永遠が、しかし寸毫の時間のなかに集約され、その圧縮によって燃え立つときに、詩が成り、歌が成るのです。それを業平は「今日の今宵」と言った。これはどこにもない言葉です。今日(けふ。「ふ」は「ひ=日」の変化)の「けke」と今宵の「こko」は子音kを共有する同根の接頭辞で、手近にあるもの、直面するものを指ししめす「この」の「こ」とおなじものです。つまり「今日の今宵」は「この日のこの夜」というトートロジーなのです。こういう言葉遣いはおかしい。間違っている。――しかし詩人は(あるいは業平は)、その奇妙なトートロジーを使ってしか言えないなにかを我々に伝えようとしている。「この、この」と繰りかえす言葉のむこうに見えるのは、永遠につづく長い時間が一瞬のなかに畳みこまれ、燃えあがる、美しさとはかなさです。業平は嘆きという。嘆きは花の美しさによって起きるものです。その嘆きが、花の美しさが、一瞬のうちに凝縮する瞬間、それが今日の今宵なのです。美と哀しみとが頂点に達し、耐えられないほどの想いがわきあがるとき、しかし歌びとは、その「想い」から目をそむけることができないという宿命を背負った人間です。彼は美しすぎて哀しいと感じる自分の内側を見る。そこにあるのは、永遠に飽くことなく美を欲しつづけるみずからの業であり、その業を挑発するかのように永遠に続いてゆく美の回廊です。むろん人は永遠を生きることはできない。しかし一瞬を通して、その内側にある永遠――この美しさは永遠に繰りかえされ、それを求めるみずからの心もまた永遠であるという――に手を触れることはできるのです。いや、それはむしろ、一瞬であるから、燃えあがるように凝縮した美の一瞬であるからこそ、可能であることなのかもしれない。頂点を極めた美は、やがて瞬く間に消えうせるでしょう。しかし、その内側において人が永遠という存在に手を触れたという事実だけは消えない。だから、詩人はその記念に「今日の今宵」を詠むのです。
(02春下0106)
凡河内躬恒
いもやすく寝られざりけり春の夜は花の散るのみ夢に見えつつ
春の夜は心やすらかに寝ることもできない。夢の中でも花が散るさまばかりが見えてしまう。
作者の名は、おほしかうちのみつね(オオシコウチノミツネ)と読みます。高校の古典の時間に習ったかもしれませんが、古今集の撰者の一人で、紀貫之の影響を大きく受けている歌人です。なお「いもやすく寝られざり」というのは「いも……寝られざりけり」のあいだに「やすく」という副詞が入ったもので、「い」はもともと睡眠を指す上代語です。ちなみに寝(ネ)は元来体を横たえるという意味、眠り(ネムリ、ネブリ)はうたた寝、居眠りの意で、それぞれ別なものですが、ある時期からイが廃れてきて、「イを寝る」という定型句的な用法で「寝る」という意味に用いられることが多くなってきました。この歌はまさしくその用法です。
この八首の歌は、ふたつの高峰を持った連峰であるということができます。第一の峰は上の業平の歌、そして第二は末尾八首目の貫之の作がこれにあたります。この二首の傑作をいかにうまくつなぐかが編者の腕の見せどころです。古歌八首のうち、赤人のそれは単純に花を愛でる人々を外から見、軽い共感を持って描写したものでした。業平の作はその花を愛でる人の内面に深く踏みこんだものです。しかし三首目に、業平とおなじ方向性を持った歌を配置することで内面描写をより深くしてゆくのは得策ではありません。高い峰だけが連続すると、それは山ではなく土の塊になってしまいます。ステーキ、豚カツ、ビーフシチューの繰りかえしではその美味も半減してしまう。業平の歌は内面描写の面ではもはや極限といっていい部分まで踏みこんでいます。必要なのはその熱を抜き、方向転換をうながしてやる、ひろがりがあって淡彩な歌なのです。そろそろメニューはししゃもでお茶漬けであるべきなのです。
躬恒の歌は、とりたててこれがどうのという作ではありません。あえて言えば「花の散るのみ」のノミという助詞のつよさ(ほかの夢を見ることはないのです、ただただ花の散る夢だけを、という切実さ)に作者の意図があるのでしょうが、そのほかはどうということはありません。ただ風情が豊かで、内容は深くないけれども、業平の歌の世界に逆らうことなく、それをよりひろやかに展開するちからを持っている、という部分に美点があるのです。夢に花を見る、という美しさは、たしかに業平の焼くような切実さからは遠い。しかし同時に、まったく別のものであるわけではないのです。夢のなかに散る花は、業平の心を焦がしたものとおそらく同じ花でしょう。あるいは同じ花である、と読ませるために、撰者はこの歌を三首目に配している。その心を読む必要があります。
夢に訪れがあるのは、相手が自分を想っているからだという考え方が平安時代にはありました。そこはかとなく官能の匂いのする伝承です。花が作者の夢にあらわれるのは、歌びとの心と花の心がひびきあっているからなのでしょう。業平は花に心をつくして嘆きの想いを抱きました。一方的で、つよく、切実な、苦しい気持です。その苦しさが、この歌にいたってやわらかく受けとめられている。受けとめたのはなにものか? いうまでもなく、業平が焦がれた花です。花という美しさであり、官能であり、そこにこめられた抒情です。――この歌の魅力もまたそこにあると言っていいでしょう。焦燥をやさしく受けとめる花の姿は、躬恒によって淡彩の一筆がきで描きあらわされています。しかし「花の散るのみ夢に見えつつ」という下の句には、淡彩のひと言ではすまされない官能の匂いがそこはかとなくただようのもまた事実です。この歌は古今ぶりではありますが、例えば貫之や業平のようなかわいた知的な要素がいくらか後退して、代りに抒情の風情が濃い部分があります。おそらく上の句と下の句の倒置がこうした印象をつよめているのでしょうが、その抒情がときにやさしさとも感じられ、官能とも感じられる、あいまいな美しさをこの歌は持っている。夢のなかにものを見ることは、新古今歌人が多用した手法でもありました。もちろん新古今ぶりの「夢」の手法からすれば、この歌はあまりに単純で、淡彩ではありますが、しかし、その単純さ、淡彩さが、決して艶めかしい色気と無縁であることにはならないのです。
十七、八の娘ざかりが見せる、たくまざる清潔な色気――官能へも、清さへも転じうる――、そういうものを思わせる歌です。
(02春下0107)
伊勢
山桜散りてみ雪にまがひなばいづれか花と春に問はなん
山桜が散って、木の下にとけのこる雪とまぎれてしまったら、どれが花であるかと春に問うてほしい。
伊勢は古今の女流歌人の一人。だいたい貫之ら撰者と同世代かと思われます。――歌は言挙げするほどのものでもないでしょう。風情で見せている一首です。ことに桜の花が散るさきに残雪がとけのこっている、という美しさがその風情を支えています。「春に問はなん」という一句を作者の機知とすることもできますが、そこにあまりに才気ばかりを見ようとするのは歌をおもしろくなくします。それよりもむしろ、こうした歌を詠む作者の心を思ってみるべきなのではないでしょうか。桜が散ったら、雪と混じったら、どれが雪でどれが花びらかわからなくなったら……、というさまざまの仮定でできている歌ですが、これだけたくさんの仮定をしなければおさまらないのは、それほどまでに花に心を奪われているからなのです。だから春に問はなんという奇抜な発想がすっと出てくるのでしょう。すべては空想であり、仮定であり、その空想や仮定はただただ花を想うという心から出ている。それゆえに、花の行方を散った後にも見定めたいという気持が生れて、春に問うという表現が出てくるのでしょう。あるいは、出てきても木に竹を接いだような奇抜さに見えないのでしょう。四首目のこの歌も、躬恒の「花の散るのみ夢に見えつつ」という桜に心浮かれた人間の、すこし滑稽で、でも花を想わずにはいられないという風雅の心を受けついでいるのです。
(02春下0108)
紀貫之
わが宿のものなりながら桜花散るをばえこそとどめざりけれ
わが家に咲くものでありながら、桜の散りゆくのはとどめられないものであることよ。
ただの機知の歌として読むべきではないでしょう。特に注意するべきは「わが宿」という部分です。「わが」とは、ソトに対して、ウチを示す言葉です。ウチ/ソトとは単に場所のことではありません。それはむしろ心理的な存在なのです。ウチは自分に近いもの、親しいものを指します。「うちの犬は……」「うちの会社は……」というときの「うち」、あるいは上方の女児の一人称「うち」、みずからの住まいを言うときの「うち」、みな同源のことばです。例えばウチとナカは似た意味の言葉ですが、ナカにはこうした心理的なひろがりがありません。「なかの会社」とは言わない。会社と自分を一体視してみせる親和力を言うための機能がナカにはないからです。ウチは自分を中心とした一定の範囲を、外側からではなく、内側から言うための語であり、その核にあるのは「自分」を中心とした親しさ、近しさなのです。
この歌の底にあるのは、貫之が桜に対して抱いている親しい気持なのです。だからこそ、彼は桜を擬人化し、散らないでおくれと語りかける。むろんそこにあかるく、かわいた、微笑みの抒情があることは見逃せません。しかし一首を単純に機知による笑いの歌と解してしまってはよろしくない。彼が心のあるはずもない桜の木に冗談を言いかけるのは、その前提として「桜花」を親しい友人であると考えているからなのです。そこにこの歌の抒情がある。そして、だからこそ単純な笑いではなく、しみいるような抒情味を持った微笑みが生れてくるのです。
(02春下0109)
読人しらず
霞立つ春の山べに桜花あかず散るとや鶯の鳴く
霞の立つ春の山に、まだ見飽きるということもないのに桜の花が散るといってか、それを惜しんで鶯がしきりに鳴くことよ。
読人しらずですが、寛平御時后宮歌合という古今集成立以前に行われた歌合にある歌。童話のようなのんびりとした世界を思わせる作で、春の野山の若草の匂いまでが感じられるようです。決して繊細な描写などないのですが、あたたかい日ざしに桜の花、鳥の声までそこにあるようで、稚拙で大ぶりであるからこそ、かえって歌の世界がどこまでもひろがってゆくような印象を与えます。
二首、桜の散るのを惜しんで無心のものに語りかける体の歌がつづきましたので、その風情を承けて、しかしここでやや趣向を転じます。花を惜しむのは人には限らない、という心の歌です。それと同時に、作者の主観や心理を遠ざけ、なるべく目にうつるところを素直に詠もうとする写生ふうの歌でもあります。注意をひくのは「あかず散るとや」の句ですが、あかず、は「鶯が桜に飽かぬ」ということでしょう。もちろん鶯の想いには作者の心が投影されているわけですが、それを表立ったかたちでは言いあらわさないのがこの歌の持味です。「や」はこの歌の前半と後半を結ぶための橋掛りです。鶯の鳴く(鳥が鳴くということを、平安びとは、ただ単に啼く――声をあげる――ということではなく、泣くことであると考えました)その心事を推しはかって、こうではないか、と想像した結果がヤという助詞の選び方にあらわれているのです。ヤは本来感動を示す助詞もしくは間投詞でしたが、かなりはやい時期に疑問の助詞となり、さらに平安期に入って同じく疑問の助詞であるカと明確な使いわけの基準を持つようになります。平安時代の、特に和文におけるヤは、単に上に承ける内容を疑問に思って相手に聞きかえす(「こうこうですか?」)ための助詞ではなく、「こうこうではないのですか?」と自分の判断を示してそれへの同意を求めるニュアンスを持ったやわらかい疑問の助詞として使われています。この歌の場合、ヤには、鶯が桜を惜しんでいるのではないか、という作者の推量がこめられ、そうではないかと思うのですが……という疑問ふうの提示が読者に対して行われているのです。
この歌の妙味はそこにあります。桜と鶯の関係が繋がるようで繋がらない、ふわふわとした、ゆったりとした、まるで童話のようなあどけなさを持っている関係であればこそ、この歌には古雅なこせつかない魅力があるのです。「霞立つ春の山べ」などという大ざっぱすぎる描写が、それにもかかわらず歌のなかで魅力的でいられるのは、歌全体にのどかな春の日のようなおだやかな空気が漂っているからであり、それが例えば「とや」の部分に象徴的にあらわれているからなのです。もしこれが「あかず散るとテ」という断定的な推量であるならば、そのきびしすぎる言いまわしが歌のなかに論理的な整合性を求めすぎ、こののんびりとした味いが失われてしまいます。鶯の心事など推しはかりうるはずもないし、そもそもそんなものがあるかどうか疑わしい。鶯が花を惜しむなどということがありえるのか。そういう疑問はたとえ平安びとであったとしても持っていたことでしょう。歌はそれを乗りこえて成りたつものなのです。たとえどれほどふしぎで奇妙なことであとうとも、そこに陶然として古雅な春の日ざしさえ存在すれば、こまかなこととは関係なしに童話のような物語が真実味を持つようになるのです。その童話の真実味を可能にするものこそが、「……ではないかと思うのですが」というヤの助詞の控えめなナラティブなのです。ナラティブとは物語の語り口の謂。どんな荒唐無稽な物語であっても、それを真実だと思わせることはできるのです。それが語りというものの魔力であり、具体的には言葉というものの技術なのです。ハンカチから鳩が出るわけがない。しかし出たように見える、もっと言えば出たように見えたという奇跡を信じさせる説得力を持っていること。それが歌というものの魔力であり、芸なのです。
この歌は、たしかに写生ふうの歌ですが、写生そのものではありません。写生といい、写実というには描写があまりに大まかすぎる。たしかに歌の世界は作者の主観から自由になっています。しかしそれは近代的な写実や写生のために自由になったのではなく、むしろ主観を殺すことによって、個というものを持たなかった古い古い時代の描写を装おうとしているからなのです。てらわれた単調さ、無技巧、そして没我。そこから立ちのぼってくるのは童話のようなのんびりとした、ひろやかな、春の日の光景です。しかしそのために作者は細心の技巧を払っている。あるいは、巧まずして細心の技巧を払う結果になってしまったから、この歌の味いがきわどく成立している。それが例えばヤという助詞なのです。
(02春下0110)
山辺赤人
春雨はいたくな降りそ桜花まだ見ぬ人に散らまくも惜し
春雨はひどく降ってくれるな。桜花が散ってしまうのが、まだ見ていない人のためにも惜しいから。
万葉集に下の句「いまだ見なくに散たまく惜しも」とあるのを改めています。作者と桜という直接的な関係に、「見ぬ人」という要素が加わった分、花を惜しむ心の幽遠が添うています。作者の心が、桜と、見ぬ人と双方に掛かっていて、見ぬ人の存在が読者のなかで大きくなる仕掛けになっています。恋のこころを見るにはあまりに淡すぎますが、ひとりで桜を惜しみながらふと思われる相手が特別な存在であることはたしかでしょう。そのあるかなきかの色気に染められた眼ざしがいっそうに桜を美しく、叙情的に見せています。
「な……そ」は「……するな」の意。「まく」は動詞の未然形について名詞化する接尾辞で、この場合は「散ることも惜しい」というほどのことでしょう。さほど意味のある言葉遣いとは見えませんが、「まく」の古雅な響きが赤人にふさわしいと考えられたのではないでしょうか。以下心理描写を表に立てない散花がつづく配列になってゆきますので、ここでひとまず惜花の情を打ちきり、次の一群へと繋ぐ意味で雨の花の歌を置いたものだと思います。
(02春下0111)
紀貫之
花の香に衣は深くなりにけり木の下陰の風のまにまに
桜の花のおかげで私の衣はいっそう香りが深くなった。木の下陰に花の香を吹きおくる風につれて。
なんらむつかしいところはありません。素直な歌です。素直ですが余情の深い歌です。桜の花の移り香のむこうには、おそらく恋しい人の面影があるのでしょう。身に吹きかわす風は惜春の想いにではなく、恋心の官能に彩られています。花は想う人なのです。散るのが惜しいのではなくて、その香りに抱かれることを素直に作者は喜んでいる。「深くなりにけり」の一句に込められた感慨、「風のまにまに」にひびく余韻にそれがあらわれています。
この歌に至って花は花ではなくなります。すでに目に見え手に触れる花ではなくなっている。香気というかたちのないものが歌の対象になっているのです。それは単に花の香りというだけではなく、花を象徴するなにものかなのです。恋のようにほのかな色、艶、響き、そういったものであると言ってもいいでしょう。これは花そのものではなく、花の美しさ、かぐわしさ、人の心を狂わせるもの、そういった本質が、具体的なモノやかたちに拠らず、ただ純粋に本質として存在している、そういう手ざわりなのです。それが象徴なのです。あの桜の花に香りなどというものがあるでしょうか。貫之はそんなことは百も承知でこの歌を詠んでいるのです。香りなどあってもなくても構わない。それは形而上的な「花」においてはなんの意味も持たないことなのです。匂うとすれば、この花は読手の、あるいは作者の意識のなかで香っているのです。形而下的に花の香が存在するかしないかはどうでもよいことであって、ただ花の香に感じる気持がこの歌に触れる人間のうちにあればいい。それらの人間の心の奥に、この歌の「花の香」という言葉がひびけばいい。そのとき意識の裡に起こる心のざわめき。それが官能なのです。「花の香」は実在しなくても、この歌のなかで虚構化され、実際に花の香りをかいだのと同じ心のざわめきを人に起こさせる。それだけで充分なのです。いや、むしろ、そうした虚構化された、実体のない香りだからこそ意味があるといえるのかも知れません。
むろん実体のない記号として存在することを目的とするならば、言葉であれば「花の色」でも「花のかたち」でもいいのです。しかし香りというもっとも実体性のうすいものを選びとったところに貫之の老獪さがある。ここでは、言葉というものの実在感のなさが、「花の香」というさらに実在感のないイメージによって倍加されているのです。その結果として、「花の香」は言葉としても、イメージとしても実在感の希薄な、純粋な記号として存在している。だからこそこの「花の香」という記号は自由なのです。それは桜の花という限定を離れ、ただ単に「官能」を指ししめす記号として人の心に働きかけることができるのです。「官能」という名の記号。それはこの場合、もちろん第一義的には、花というものの香りが与える官能として機能するでしょう。しかしそれは絶対的な第一義ではなく、相対的なものに過ぎないのです。かたちを持たぬ記号は、ただ官能を人の心に与えることだけを目的としています。記号は媒介項です。記号(f)は、aであり、bであり、cでありうる。何故なら、a、b、cそれぞれに存在する抽象的な共通項を仮に実体化するために記号は作られているからです。しかしそこに詐術が生まれる。a≠b≠cであるにも関わらず、(f)=a、(f)=b、(f)=cという事実が、(f)=a=b=cという虚構を成立させる。(f)は自由にa、b、cのあいだを行き来する。「花の香」は花の香りによる官能の謂であって、花の美しさの官能や、恋の官能ではない。しかし、「花の香」が官能の記号として用いられるとき、その記号からは、自由に美という官能、恋という官能が引きだしうるのです。だからこそ、ここで歌われる「花」は恋とひびきあうのです。かたちにさえぎられることなく、その美しさ、かぐわしさが、花から人へ、人から花へととどまることなく刻々と読手の意識のなかで変転してゆくのです。そのあいまいさ、ほのめかしさ、におやかな手ざわり。そういったものだけが、人に「花」という名の官能を信じさせるのです。
業平の歌は、一瞬の時という極度に個別的な世界のむこう側に永遠という普遍性、美という普遍性を見ようとする歌でした。これはそれとは逆に、どこまでもひらかれ、個別的なかたちを失うことで、美という世界へと大きくつながってゆく、そういう歌なのです。八首を締めくくるにこれほどふさわしいものがあるでしょうか。
以上の八首を受けて、
藤原俊成女
4) 風通ふ寝覚めの袖の花の香にかをる枕の春の夜の夢
一首おいて
藤原俊成
5) またや見ん交野のみ野の桜狩花の雪散る春のあけぼの
が続きます。すぎてゆく春のかたわらに歌だけがとりのこされてゆく……。
【引用歌註】
1)二之巻「桜のうた(1)」の項参照。
2)二之巻「桜のうた(2)」の項参照。
3)わくわくわか「はかなくて」の項参照。
4)わくわくわか「風通ふ」の項参照。
5)わくわくわか「またや見ん」の項参照。
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- 懸賞フリーク♪
- ラカント フローラビオ
- (2025-02-25 14:57:34)
-
-
-
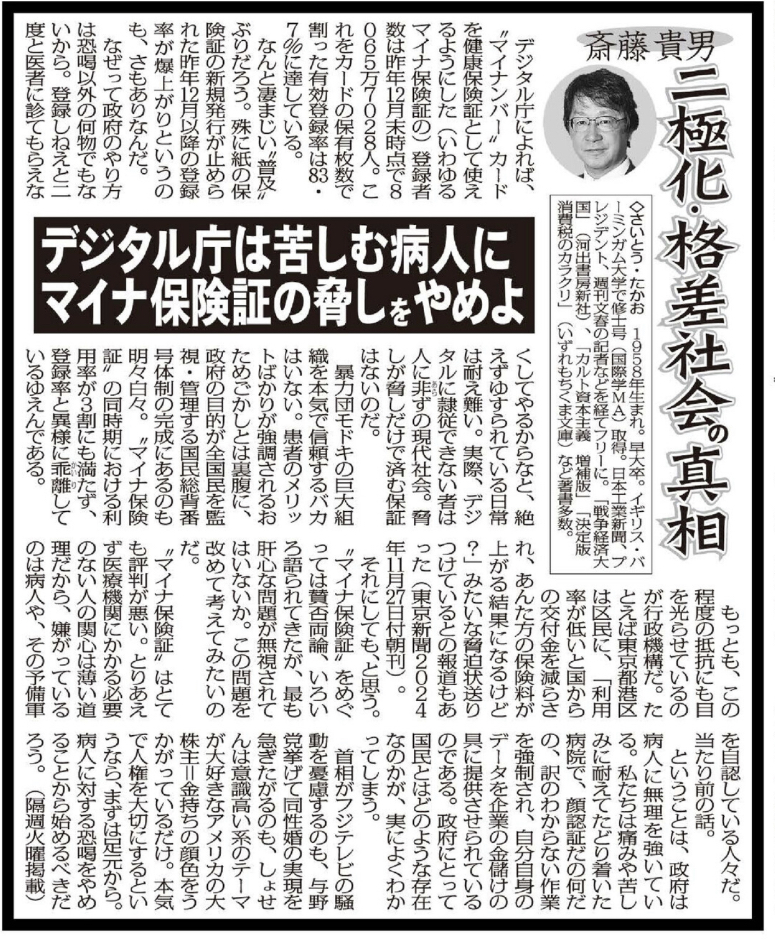
- 政治について
- 国民、自治体に対しても脅迫する反社…
- (2025-02-25 17:28:23)
-
-
-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…
- 【購入品】つけっぱなしでもOK! …
- (2025-02-25 12:17:39)
-
© Rakuten Group, Inc.


