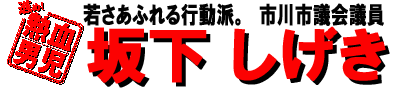一般質問
通告
1、市民満足度を高める行政経営について
ア、特別保育園の整備について(駅前保育・24時間保育・休日保育・病児病後児・保育障害児保育)
イ、犯罪から子供を守る防犯の取り組みについて
2、行政改革について(公平、公正で科学的な説明責任を果たせる行政)
ア、人事・給与制度改革
・人事の庁内分権の問題などについて
科学的な行政分析システムと人員配置
部内の職員移動の仕組み
スタッフ制について
プロジェクトチームと事業チームについて
特別昇給候補者の推薦について
イ、行政経営
・科学的な分析手法(ABC分析・事務事業評価などの分析について)
・外部委託(指定管理者制度・PFI・委託などについて)
科学的分析手法を使いこなせているのか
事務コスト
目的
外部委託の方針とコスト分析(人件費を委託費に付け替えただけ)
ウ、電子自治体の推進
・市民サービス(保健・福祉など)に直結する業務の電子化の内容と進捗状況について
・電子決裁の問題点及び財務会計システムの進捗状況について
福祉などの電子化の推進状況
電子決裁の問題点(添付文書の扱い、財務規則及び事務決裁規程等の見直し)と改善点について
財務会計システムの進捗状況・累積予算・今後の運用方針
市川市財政と財務会計システムなどの電子の活用、人事の活用及び行政経営分析手法についての関連と今後の展開について
市友会の坂下しげきでございます。
それでは、通告に従い一般質問をさせていただきます。
まず、第一の市民満足度を高める行政経営の特別保育園の整備についてお尋ね致します。
本市の2月1日現在の待機児童数は、628名に上っております。限られた財源の中で、待機児童の解消を図る為には、弾力化、規制緩和を有効に活用する必要があり、市川市の行政手腕が問われます。
他市に遅れを取りましたが今議会で、指定管理者制度の条例案が可決されました。様々な行政ニーズに応えて行く為には、これらの制度の適切な運用が鍵になります。今回本市で提出された条例案は、問題点が多くあったので反対を致しましたが、この指定管理者制度が待機児童解消の大きな役割を担うことは否めません。
例えば、複雑多様化した現代社会では、育児に携わる世代の方々が、必ずしも朝9時から夕方5時までの勤務をされているとは限りません。そして、このような勤務形態の違いや、病気の時の保育や、障害を持たれている方の保育も、市民として平等に受けられるサービスなのです。
しかしながら、市の施設では、大部分がお昼間と言われる時間帯に健康時の保育しか行われておりません。これでは、平等な市民サービスとは、いえないのではないでしょうか。
そして、児童福祉法が定めたラインが『「最低」基準』であることを決して忘れてはなりません。市は長期的な展望をもち、予算を確保し、子どもの育つ環境を整備することが必要であります。子育てと家庭を支援する為には、お金をかけずに事業化することはできません。しかし、市川市の得意分野である行政分析を行い、無駄をなくし、工夫を惜しまず、また、国で法改正が進み、市の独自判断により、新たな行政手法であるPPPを有効活用できる環境が整っておりますので、既存の直営施設をアウトソーシングするという短絡的な手法によるのではなく、新たな行政課題を解決する手段として法改正を有効に取り入れるべきであります。国の構造改革・地方主権を受け、市は今こそ、将来に投資する英断を行うべきトキであります。
そこで、指定管理者制度は、今まで市川市が直営で行うことが出来なかったサービスを可能にする制度であります。しかし、本市の採った政策は、単に既存の保育園を指定管理に移行したものであり、新たな政策的な工夫と住民意見の取入れを怠っていると思われます。
そこで、行政分析を進めることにより、特別保育と言われる、駅前保育・24時間保育・休日保育・病児病後児保育・障害児保育などの保育園を作ることはできないものかお答え下さい。
次にイの犯罪から子供を守る防犯の取り組みにつきましては、12月議会でも取り上げさせていただきました、防犯灯の整備があり、16年度では中国分・北国分がモデル地区となりました。明るい町は、犯罪から子供を守るひとつの手段であると思います。そして、他の自治体では、防犯ブザーの配布や、緊急連絡網に携帯のメールを使うなど、あらゆる方法で犯罪から子供守る取り組みが行われております。また、先の議会において質問させて頂きました子どもの緊急システムについても、16年度予算で計上されました。そして、先順位者から同種の質問がありましたので、子供を犯罪から守る政策については、今後もご尽力いただけるよう強く要望し、質問に変えさせて頂きます。
第二の行政改革の(1)人事給与制度改革についてお尋ね致します。
給与の削減は財政負担を減らす為の最も安易な手法であるので、これまでに行われた給与制度改革については、主に財政の負担を減らす為の手段であるように感じられ、サービスの質についての配慮が感じられませんでした。従いまして今後の人事給与制度改革が、目的を持ったもので、市民の妥協が得られるものとなるように、今後の改革に絞ってお尋ね致します。
(1)の1点目と致しまして、市川市の行政改革の売りであります、科学的な行政分析システムを用いての人事制度改革についてお尋ね致します。
まず、平成16年度から導入されるバランス・スコア・カードのスタンダードで言えば、人事制度は「学習と成長の視点」になりますが、この視点の達成は、庁内分権の下、各所管部局に任されるのか、人事担当部門が主導的に行っていくのかお答え下さい。
また、ABC分析に基づく職員配置分析や、アウトソーシングへの展開は人事制度改革の枠組みではどのように扱われてきたのかお答え下さい。
(1)の2点目と致しまして、プロジェクトチームの設置についてお尋ね致します。
私はプロジェクトチームについては6月議会と9月議会で質問をさせて頂き、やっとその内容が実現化するのかなと思っております。組織を横断して、専門化・複雑化した行政需要に迅速に対処するものとして、事業チームとプロジェクトチームがあります。そこで、16年度実施はプロジェクトチームだけということなのかお答え下さい。また、国からの権限委譲に伴うなどの複雑な新規業務を立ち上げる場合などは、各担当部のほかに情報システム部や法規部門等も積極的に関与して、早急なプロジェクトを立ち上げる必要があると考えられます。このような部をまたがるプロジェクトチームの設置については、どのようなお考えがあるのかお答え下さい。そして、プロジェクトチームには予算的裏付けが無いと実行力が伴いません。そこで他市町村では、緊急課題があった場合を想定して、予算権限を持てるような条例を設置しているところがあります。このような制度的なバックアップ体制はどのようになるのかお答え下さい。
(1)の3点目と致しまして、特別昇給候補者の取り組みについてお尋ね致します。
個々の職員の能力に基礎を置いた人事制度はある意味では当然であり、現在の公務員法でもその精神は規定されており、制度の趣旨事態は方向性として意味があると考えますが、個々の職員の能力を測定する仕組みが明快でないことに最大の懸念を覚えます。
まず、人事上の評価と言うのは、人格を評価することではなくて、仕事を評価することであり、つまり業績評価であります。業績評価が無いような制度改革は基礎を欠いたもので、砂上の楼閣であります。
また、評価の主眼が市民サービスの向上に向けられているのか、財政負担の削減に置かれているのか、新たな業務の構築による評価なのか、相対評価なのか、課題が多い点が懸念材料となります。
代表質疑のご答弁を聞く限り、市川市では業績評価事態が確立されていない段階にありますが、そのような状況下で能力評価を行うと、職員が評価を意識するあまり、市民サービスを停滞させたり、新たなコストを生む恐れがあります。極論すれば、ある職員は、市の内部の財政課題に専念し、コストを追求するあまり、市民にとっては望ましくない結果を与えるような業績を残し、またある職員は、市民サービスを追求し、市民にとっては良い結果をもたらしたが、財政的には負担が大きくなった場合、市はどちらの職員を評価するのでしょうか。市のベクトルがどちらに向いているのかが確実に分からなければ、この制度をどのように評価したら良いのか全く分かりません。このような課題の中で個々の職員の能力を正確に把握することが可能なのでしょうか。
つまり、人事評価としての業績評価も、行政評価によって、組織の目標が数値化され、部課長の業務評価が明確になっていなければ、制度の導入はできても皆が納得するものにはならないでしょう。
内閣府では2004年から内閣府職員の能力向上や業務効率に向けて、達成度評価という目標管理システムを導入しております。内閣府に問い合わせたところ、このシステムは、効率的な業務・組織運営を実現させる為の手段であり、給与などの処遇に反映させないとのことでした。また、明確な評価基準を設定するための要綱が策定されております。
しかし、市川市では、職員が特別昇給をする制度なので、昇給の理由が市民に分かりやすく納得のいくものでなくてはなりません。職員が市民に貢献し、成果を挙げるのは当然の職務であります。その当然の職務に対して、昇給をさせると言うのは市民感情としても難しいところであると思います。昇給制度を考える前に、職員全体のスキルアップや、適正な人員配置を行い、市民ニーズに迅速に答えられるシステムを構築するべきであると考えます。
そこで、まず、本市の業績評価システムの現況及び本市には職員の評価システムに関する要綱等の明確な基準となる規則はあるのか、それは公表されているのかお答え下さい。
次に、特別昇給制度と市民感情について本市のお考えをお答え下さい。
また、今後の行政運営は、部長など管理職の行政経営手腕が問われるようになりますが、職員全体のスキルアップについてはどのようにお考えなのかお答え下さい。
次に、(2)の行政経営についてお尋ね致します。
市長は、今年度行われる科学的な分析手法について、ご答弁の中で、行政経営とバランス・スコア・カードについて、航空機のパイロットに例えていらっしゃいましたが、まさにこれは、バランス・スコア・カードの提唱者であるハーバードビジネススクールのカプラン教授の言葉を引用されたもので、今後の市川市では、今まで蓄積したデータを活用、充実させて、バランス・スコア・カードに落とし、行政経営の舵取りをしていくことになります。
しかし、バランス・スコア・カード BSCは、あくまで、市の経営戦略を展開させる為の手段であります。従いまして大枠では市川市の目指す基本方針、小さな枠では個々の事業の到達点が明らかにされなければ大量のデータを収集したBSCも宝の持ち腐れになってしまいます。
市川市では、市の目標点は、総合五ヵ年計画、行政改革大綱などバラバラに定められており、一貫した全ての業務にまたがる行政達成目標が明示されておりません。個別の取り組みは避けて、行政評価システムの導入の中に、新たな総合計画策定を取り組むという姿勢が求められます。そして、国会での法体系も、以前は憲法から法律、命令と言う流れでしたが、現在は憲法そして基本法、法律、命令と言う法体系に変容しており、国が進むべき基本理念を分かりやすく明文化して、行政のなすべき指針を明らかにする傾向が強くなっております。つまり、市も行政運営に当たり、基本理念を明確にし、市民とのパートナーシップを築いていくことが必要です。
科学的手法を用いた分析は複雑であり、その結果、市民の権利を制限し、義務を課すものもあるので、行政改革が目指す目的地点を美辞麗句で飾るのではなく、ハッキリと伝え、その上で分析結果を公表し、市民や議会に了解を求めなければ、いたずらに議論を長引かせ、行政運営を遅滞させる恐れがあると言うことです。市川市では基本方針を全面的に打ち出しているものが少なく、目的が摑みづらい状況にあると思います。
例えば12月議会のご答弁によると、PFIに対しても導入基本方針が策定されるのがこの3月とのことでしたが、既にPFI事業は進行しており、本末転倒です。またABC分析も行っているということで、人員配置や委託化の指針になっているとのことでしたが、委託化の際に重要な要素となる間接取引コストに関わるABC分析がされていないとのことで、今の段階では公表にも至っていないわけであります。 そして事務事業評価も進んでいるようですが、予算資料との重複など手法の改善も課題です。これらの分析は公表されフィードバックすることで、事業の改善がなされるものであります。また、行政評価を始めた時は、財政難が深刻化した入口の時期で、何を削減しようかと言うスクラップ・アンド・ビルドの時代だったので有効でしたが、現在はビルド・アンド・スクラップの時代に入ってきました。
これらの分析は、現在の主流であるNPM的行政手法からは切り離せない分析方法でありますが、分析資料の作成には膨大な事務コストが掛かることも決して忘れてはいけません。
最少で最大の効果を挙げるためには、しっかりした目標方針を決め、共通意識を持ち、重複の無いデータ作成及び分析を行わなければならないのです。
そこで、(2)の1点目と致しまして、BSCは大量のデータ及び分析を積み重ねるものになりますので、BSCを作成する為の事務量が膨大になることが予想されます。この事務量のコストがどれくらいになるとお考えなのかお答え下さい。また、BSCは、評価の視点が多元化されており構成が複雑で、どのような柱を立てて結果を解釈するかと言う点で技巧を要します。職員が時間外勤務などを行うより、外部委託のほうが効率的と考えられますが予算計上されておりませんでしたので、評価の外部委託、第三者機関などについてはどのようにお考えなのかお答え下さい。
(2)の2点目と致しまして、既に行われているABC分析や事務事業評価の公表と今後のBSCとの関係についてお答え下さい。
(2)の3点目と致しまして、BSCを使用する際の市川市の目標地点について、どのように決定するのかお尋ね致します。民間企業の場合、最終目標を財務の視点に置くのに対して、公共機関の場合は、顧客の視点を最後に置くか、顧客の視点と財務の視点を並列にする場合が考えられますが、市川市の最終目標は、いつ、どのセクションがどのように設定するのか、また、適用規模、及び公表方法についてお答え下さい。また、通常BSCには4つの視点が置かれます。先順位者も視点について質問されておりましたが、私は何よりも、市が、公共サービスの提供機関であるという本来の役割を重視して、公共財のように顧客を特定できないサービスの提供を担うという側面を考え、アメリカワシントン州のように「公益と成果」という視点も必要であると考えます。市川市での視点の設定についてはどのようにお考えなのかお答え下さい。
(2)の4点目と致しまして、BSCはデータの積み上げ段階ではボトムアップでありますが最終的に方針が決るとトップダウンによる統制力の強化に陥ることがあります。また評価の策定が予算執行課ではない、つまり経営管理責任を問われない企画部の主導で行われると、権限の無い部署が組織内に指示を出すことになり、成果が期待できないことも考えられます。従って責任と権限を一致させて運用することが望ましいと考えます。そこで、トップダウン形式及び責任と権限の一致についてどのように対策をとるのかお答え下さい。
続いて、代表質疑のご答弁で、PFIにより借金を平準化している、ABC分析の効果として人件費とは違った委託料という形で予算計上している旨のご答弁がありましたが、これらは逆に言うと借金をあと送りにしている、人件費を委託料に置き換えただけであります。
そこで、(2)の5点目と致しまして、ABC分析により職員の人件費を削減し委託に付け替えた場合、委託当初は経費の節減になっても、そのうち委託業者が固定され返って経費がかさみ間接取引コストを含めると経費の節減にはならないことが多くあります。その為には間接取引コストの分析と改善が必要です。従いまして、ABC分析による間接取引コストの分析についてお答え下さい。
(2)の6点目と致しまして、外部委託に関する市川市の基本と言うべきものは平成12年8月3日付けの「市川市業務の民間委託に関する基準」がありますが、外部委託する際の基準が財政面に置かれるのか質に求められるのかという数値的基準がありません。そして、市川市の16年度予算は、節で比較すると、委託料がトップであります。このように本市の外部委託は行政支出のメインになっているのが現状です。しかしながら、この度の指定管理者制度にも条例中に基本理念が謳われておりませんでしたので、市として、委託・PFI・指定管理者制度等の外部資源活用の基本方針を打ち出す必要があると思われます。従いまして、市としての基本方針の策定及び、外部資源の導入について主軸を市民満足度に置くのか経済性に置くのかお答え下さい。
以上のことを明確にし、庁議をホームページ上で公表することは私の要望でもあります。様々な行政評価は説明責任を果たし、フィードバックして次のステップに進むことが重要なのです。このことを踏まえてご答弁頂きたいと思います。
最後に、(3)の電子自治体の推進についてお尋ね致します。
現在は、行政も経営手法に幅が広がり民間委託など様々な方法が選択可能となりましたが、行政本来のサービス部門といえる福祉行政については、民間の参入には問題が多く、コストの観点からは測量不可能な分野でもあります。従いまして、保健・福祉分野について、総合的に負担を減らし市民サービスの質を高める為には、電子化を推進し、事務コストを減らして市民ニーズに迅速に対応できる余裕を作らなければなりません。その電子化の推進は大きく分けて、パソコンなどのハード機器の充実と、システムエンジニア等を確保してシステムをバックアップする仕組みが考えられます。
そこで、アの1点目と致しまして、情報システム費委託料のうち税・保健福祉分野に充てられる予算額と構成比についてお答え下さい。
アの2点目と致しまして、平成15年6月議会と9月議会のご答弁で、本市には、技術者が15名、専門的スタッフが25名おられると言うことでしたが、その内、保健福祉分野の常駐エンジニアの人数と、システム改善依頼を受けた場合の処理状況についてお答え下さい。また、15年6月議会でご答弁頂いてからの情報プラザから事業担当部署への搬送作業についての改善状況をお答え下さい。
次に電子決裁及び財務会計システムついてお尋ね致します。
私は、電子決裁の先進である三重県に対して問い合わせを致しました。三重県の回答によると、全面電子化に踏み切ると、複数の決裁過程や合議などが必要な場合、返って、審査が複雑になり電子決裁以前に比べて紙の使用量や作業時間が増えるとのことでした。そして三重県では、添付書類を伴う決裁については、全面的なペーパレス化を避け、事務管理機能としての能率面の方を重視していると言うことです。しかし、電子決裁がスタートした時の本市の記者発表では、そのような状況説明はありませんでした。
従いまして、アの3点目と致しまして、記者発表の際、コスト削減効果を2億8千万円と計上しておりますが、この計算内訳は全面ペーパレス化の効果としての形状であり、人件費の計算も実際の運用体系に則していると考えにくいのですが、これらの数値的根拠及びシステム開発に関する総経費、パソコン及び周辺機器の購入、賃借、保守などの運用経費を含めた総コストについてお答え下さい。またそれらを含めた節減効果及び、今後の改善予定についてもお答え下さい。
続いて、イの財務会計システムについてお尋ね致します。
財務会計システムは、今後何年にも亘り、市川市の財務管理の要となるシステムで、その構築内容で、今後の市川市の財務会計の効率性が左右されます。予算も大きく投入されますので、その効果が市民利益に繋がる為にはシステムの完成度を最大に高める必要があります。
そこで、イの1点目と致しまして、財務会計システムの進捗状況及び電子決裁システムとの互換性についてお答え下さい。 イの2点目と致しまして、財務会計システム、電子決裁システムの本格稼動に伴い、事務の合理化、効率化を図る為に各種決裁規定の改正はあるのかお答え下さい。
以上、第1回目の質問とさせて頂きます。ご答弁により再質問させて頂きます。
再質問
それぞれ、ご答弁ありがとうございました。
特別保育園については、子どもを育てやすい環境を作ることが何よりもの少子化対策だと思いますので是非、積極的に行って頂きたいと思います。これは、要望とします。
行政評価については、情報公開、説明責任を果たすと言う作業の中でのフィードバックが重要であります。(現在では、プラン・ドゥー・シーという政策形成過程は神話であり、政策過程は評価からはじまると考えられております。つまり、市民は行政過程では欠かせない要素であり、行政は、広く情報を公開して、ガバナンスを入れた経営が行政のあるべき姿と考えます。)
従いまして再質問の第一と致しまして、市川市において、国土交通省でおこなっている「達成度結果報告書」のようなものはお考えなのかお答え下さい。また、庁議のホームページ上での公表及びBSCのタイムスケジュールについてお答え下さい。
再々質問
最後に、各種行政分析が評価のための評価にならないよう、急がずに着実に、次のステップを目指して頂きたいと思いますので、庁議の公表・行政評価システムの結果の公表、評価の外部委託並びに、電子決裁システムの改善を強く要望して、ご答弁をお願いします。
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- あなたのアバター自慢して!♪
- バーチャル渋谷おでかけハロウィン
- (2022-11-01 19:50:06)
-
-
-

- ニュース関連 (Journal)
- 「プラチナバンド」 携帯電話の電波…
- (2024-06-28 08:21:00)
-
-
-

- 楽天市場
- 貰って嬉しかった、ファーストシュー…
- (2024-06-28 13:48:26)
-
© Rakuten Group, Inc.