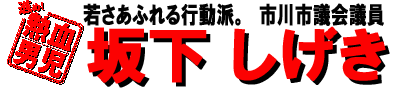一般質問
坂下しげきです。
通告に従って一般質問致します。
今私たちが取り組むべき教育及び学校教育環境は、非常に大きな課題に直面しております。
振り返れば、戦後、教育水準は向上し、生活も豊かになりました。
一方で、都市化や少子高齢化の進展などによって、教育を取り巻く環境が大きく変わりました。
近年では、子どものモラルや学ぶ意欲の低下、家庭や地域の教育力の低下などが指摘されており、若者の雇用問題なども深刻化しています。
このような中で、教育の根本にさかのぼった改革についての議論がなされ、教育基本法の改正が国会に提出され、継続審議となったことはご承知のとおりであります。
今や教育問題は、国家レベルで大きな壁に当たっております。
教育は、国家の基本であります。
故に取り組むべき課題は容易なものではありません。
また教育は、親や家庭だけの問題ではなく、国、地方公共団体、学校、地域社会等すべてが共同して取り組むものであると言えます。
私が個人的におこなった市民の方を対象としたアンケートにおいても、世代を問わず教育への関心がかなり高いことがわかりました。
そして現在は、教育の根本とも言える教育基本法に係る問題以外にも学校施設の問題や学校を取り巻く治安の悪化などハード面における課題も重要かつ緊急課題としてあります。
このような課題が山積している中で、市町村単位で行うことができ、かつ、発達過程における子どもたちにとって重要な要素である「豊かな心」を育む教育・環境教育について今回は質問を致します。
環境教育は、子ども達に豊かな心を育むという教育目的のほかに、子ども達に自然環境問題に対する意識を喚起させるという側面があります。
地球温暖化の防止や廃棄物・リサイクル対策など自然環境の保全について、発達段階に応じて子ども達の理解と関心を深めることは、私たちの子孫に
自然の恵みを引き継ぐための重要な一歩になります。
このような社会状況等を踏まえ、
第一の環境教育・学習の推進についてお尋ね致します。
環境教育については、平成15年7月に
「環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律」が公布され、
平成16年に同法第7条に基づく「基本方針」が
閣議決定され、平成17年2月には、文部科学省及び環境省の連名で同法に係る通知が出されました。
このように、国では、環境教育について、文部科学省と環境省が共同で推進しております。
そして、本市においても環境清掃部では、
環境推進事業として環境学習を行っており、
教育委員会では、市川市教育計画において
「教育の共有化の展開」を謳っております。
このように環境教育については、教育関係機関と環境部門等が事業を連携して行うことが、より有効で効果的な方法と考えます。
従いまして、
(1)自然環境にふれあう教育の推進について、
1点目と致しまして、環境清掃部における
環境推進事業・環境学習と、教育委員会・学校教育との連携についてどのように考えているのかお答え下さい。
2点目と致しまして、今後の方向として連携の強化を図ることができるのかお答え下さい。
次に、イ 豊かな心を育む自然体験活動の実践についてお尋ね致します。
児童生徒の社会性や豊かな人間性を育むためには、成長段階に応じて、自然体験活動をはじめ様々な体験活動を行うことが重要であります。
このことについては、自然体験活動のハード面からの支援として、通告、第二の教育環境の整備と
一体のものとして併せて質問させていただきます。
本市は、都心に近い市街地にありながら、緑や川、海などの美しい自然環境が保全されております。
本市には、江戸川があり、江戸川の水を飲料水として生活をしております。
この江戸川の水がきれいなのか汚いのか?
知っている子どもは案外少ないのではないでしょうか?そして、行徳地域にも海があります。
これら市内の自然環境を生かして、環境問題への意識や豊かな心を育むこと、自然に関する学習などができるように、自然環境を整備していく必要があると考えます。
市川市は、水辺に親しむことのできる環境にありながら、家庭で水辺を利用して水の大切さや自然について学べる環境がないのが現状ではないでしょうか。
国では、子どもたちの川離れが進む中、子どもたちの河川利用を促進し、地域における体験活動の
充実化を図るため、
文部科学省・国土交通省・環境省の3省が連携した事業を進めています。
このことについて、これら自然体験学習を行うに当たって、必要な整備を教育委員会として
建設関係部局へ要望した経緯はあるのか。
また、今後関係部局との連携を図っていくのかお答え下さい。
続いて、第一の(2)社会体験活動の実践について、お尋ね致します。
市川市教育計画では、
「教育の地域活動において指導者やボランティアとの教育の連携が十分ではない」ことを自ら指摘しております。
多様な社会体験活動を通じて地域との連携を強め、子ども達の豊かな心、人間性や社会性を育むことが期待されます。
本市には、高齢者施設があります。施設を利用されている高齢者の方にとりましても子ども達との交流は、悪いこととは思えません。
また、他市では、高齢者クラブや障害者の方との交流などの社会体験活動を行っているところもあります。
このような交流を通じた社会体験活動における今後の計画についてお答えください。
また、統括部もできたことなので、関係部との
連携を図って推進できるものなのかお答え下さい。
次に、第3の地域住環境についてお尋ね致します。
住民の方が住んでいて良かった、住んで良かったと思える始めの一歩が住環境だと思います。
冒頭でも申し上げましたが私が個人的に行ったアンケートでも、地域住環境に高い関心がありました。
地域住環境と言っても、学校、公園、医療機関、道路交通などさまざまですが今回はアンケートで
関心の高かった市内の交通渋滞と道路交通の
安全確保について質問致します。
まず(1)の市内渋滞道路の整備についてお尋ね致します。
市内各所で平日の朝夕など渋滞が慢性的に起こっている箇所がいくつかあります。
この中で、市民の足となっているバスが6路線も通っている渋滞箇所があります。
京成真間駅からJR市川駅に至る間の国道14号線に突き当たるオリンピック前のT字路交差点の渋滞です。この6路線のバスが通るT字路交差点は、市内でも特徴的な、京成線踏切から14号に突き当たるT字路交差点の渋滞です。
八幡駅前も同様の渋滞原因箇所です。
この渋滞の根本的解消は、京成線の立体化や外環道路などの検討に委ねられる部分ですが、このような大きな課題を解決するまでには莫大な時間と予算が必要となります。
しかし、この間放置しておくことは、市内住環境の悪化を促す恐れがあります。従いまして、国、県、警察などと協力して、限られた予算のなかで、迅速に渋滞の緩和や歩行者等の安全を確保していく方法を探る必要があります。
そう考えますと、この交差点は、T字路になっていることから、青信号により、自動車は、必ず右折か左折をし、歩行者は直進するという複雑な動きを起こす交差点になっております。
その上、直進の歩行者及び自転車と、右折左折する自動車の信号が連動しております。
従いまして、直進する歩行者や自転車と、左折若しくは右折する車が交差点内に同時進行するため、交差点内が非常に込み合い危険な状態です。
また車は歩行者の横断を待って進行することになることから、1回の青信号で交差点内に進行できる車の台数が極めて限られ、渋滞の原因となっております。
先ずは、歩行者と車の信号を連動しない形で区別することやスクランブル交差点にすることにより、交差点内の交通整理・歩行者、車のスムーズな流れをつくることが急務と考えます。
このような当該交差点の改良を行い交差点内の
歩行者や自転車の安全確保と渋滞の緩和を行うことはできないのかお答え下さい。
また今後の見通しについてお答え下さい。
次に(2)市内狭隘道路の交通整理についてお尋ね致します。
平成16年度の市川市内の死傷事故件数は、2,376件でした。その内、幹線接続道路の裏通りや居住地内の生活道路での発生件数は、1,425件で全体の約60%に及んでいます。
また、別の調査では、市川市内の生活道路の事故発生率は、1 kmあたり2.0件、そして市川松戸線に並行する市道では14.4件に上り、これは千葉県平均の24倍の事故発生率になります。
更に、市川市内で発生する死傷事故のうち、歩行者や自転車が巻き込まれる割合は県平均より約10%高く、生活道路における割合は、高谷・田尻地区で38%、国分・真間・須和田・菅野・八幡地区で50%、平田・大和田地区では60%を超えております。
もはや看過できない状況です。
このような主要幹線道路に平行して走っている住居内の道路や、生活道路で多発している事故の原因の一つは、道路が交通量に比べて狭く、見通しが効かない点にあると考えます。
このような危険を防ぐ手段として、道路反射鏡・カーブミラーの設置があります。
このカーブミラーについては、市民ニーズが多く、更に計画的に予算措置が行えるものと考えます。
道路反射鏡、カーブミラーの設置については、平成13年2月議会において松葉議員が市民要望を満たされているかなどの質問をされております。
また、本市には、明確な設置要綱等の基準がないため、「住民要望との調整が公平に図られていないのでは」という不信感に繋がる恐れがあります。
他市では、ウェブ上で設置基準を公表している自治体も多く、設置計画が公表されているところもあります。
そこで、カーブミラーの設置要綱の制定についてどのように考えているのかお答え下さい。
次に、第4の公的資金の運用・調達方法について質問致します。
公的資金・公金の運用・調達に関しては過去2回質問させていただきました。
市川市の公金は、平成17年7月31日現在で約286億円あります。
この公金は、日々の支払いや振込みに使用する歳計現金、歳入歳出外現金といったものや、預金性の高い基金など市川市の公金の種類は5種類あり、その目的預金方法、運用方法が異なると考えられます。
公金は、すなわち市民の方々からお預かりしている税金であることから、地方自治法上も、最も確実かつ有効な方法による保管が要求されております。
つまり、預金した銀行等が破綻し、ペイオフが適用されてもリスク回避できる仕組みや、そもそも破綻が懸念される金融機関からの融資や預金を避けるように高度な運用が求められます。
一方で金融の規制緩和等により、同種の預金商品であっても、より利回りの高い金融機関と契約することや、借り入れる場合は、より利回りの低い金融機関から調達する方法が採られるようになりました。
今では、多くの地方公共団体で預金や銀行等引受縁故債の調達には入札を行っております。
市川市でも平成16年6月議会で私が質問を行った際は、銀行等引受縁故債は、全て指定金融機関である千葉銀行による引受けでしたが、その後の平成17年9月議会のご答弁では、13社による公開見積り合わせを行ったということでありました。
このようなことを踏まえ、(1)公金管理運用方針についてお尋ね致します。
市川市には、平成14年制定、翌15年に改定した「公金管理運用方針」があります。
例えば、第4条に公金の管理運用方法について規定があり、その内容として、金融機関への預金や国債、政府保証債又は地方債の購入とありますが、公金の種類は5種類あります。
また預金といっても決済用預金から当座預金 、普通預金、通知預金、別段預金、定期預金、譲渡性預金などがあり、国債でも短期・中期・長期物などがあります。
基本的にどの方法がどの種類の公金に適用されるのか明確な規定がありません。
そこで、1点目と致しまして、今後市民から見ても分かりやすい、明確な運用方針を作成する必要があると考えますが、運用方針の改正又は、
ウェブ上での公表は、行わないのかお答え下さい。
2点目と致しまして、本市の公金管理協議会では、毎年度公金の管理運用計画等が協議されているのかお答え下さい。
他市で行っているように、年度ごとに公金管理運用計画を事前に公表すること、及び議事録の公表はできないのかお答え下さい。
3点目と致しまして、本市には、公金管理アドバイザーがおります。
前回のご答弁では、銀行OB、公認会計士、税理士の3者が当たられているとのことでした。銀行の破綻等の分析については、万全なものと考えますが、積極的な金融商品の運用を行うためには、アドバイザーを増員することや、市の職員だけで行っている公金管理協議会への参加などを考える必要があると思いますが、アドバイザー若しくは協議会制度の積極的な活用を考えられないのかお答え下さい。
次に、(2)公金保護体制につてお尋ね致します。
公金の保護については、預金や借り入れを行っている金融機関の経営状況の調査や、預金、借り入れ条件の取り決めが重要な要素となります。
まず、金融機関の経営状況の把握調査については、公金管理運用方針の第6条に規定がありますが具体的な財務分析や評価指標について、公表されているものはありません。
そこで、まず、1点目と致しまして、
金融機関の経営状況の把握について基準を策定し、金融機関の選択基準等を設けているのかお答え下さい。
次に、前2回の議会のご答弁で、本市の預金若しくは借り入れについては、ペイオフ等に備え、それぞれ相殺ができる契約をしているとのことでした。
このことについて、2点目と致しまして、平成17年度以降は、銀行等引受縁故債については、複数者による見積合せを行っているとのことですが、
見積合せ参加の条件として、金融機関の経営状況の基準、相殺が予約できる条件等を明確にした上で、見積合せを行っているのかお答え下さい。
3点目と致しまして、このような本市の債務引受け可能な金融機関の条件や契約内容を明確化できれば、見積合せではなく、一般競争入札を行うことが可能と考えます。
見積合せは随意契約であることから今後市民利益が最大限確保できるような入札制度を確立できないのかお答え下さい。
以上1回目の質問とさせていただきます。
© Rakuten Group, Inc.