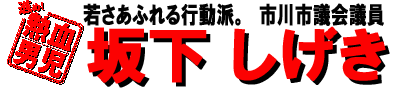議会報告
平成18年12月定例市議会では、4議案、1討論及び一般質問(計210分)の質疑・質問等を行いました。
<一般質問>
○市民(高齢者・障害者)雇用・福祉・環境等の政策の実現について
本市の経常収支比率は、財政健全化計画の目標を達成しておらず、表に出ない実質的な義務的経費のようなものも多々あります。このままでは、少子高齢化社会に向けて、十分な政策的経費が確保できない恐れがあります。このような厳しい財政状況にあっても政策の実現を目指すことができる方法の一つに政策入札というものがあります。
私は平成18年2月議会において、入札における 総合評価落札方式(政策入札)を利用して、福祉・環境政策等の実現を目指す、新たな手法について市に提案を致しました。
この方法は、市が外部発注する委託業務等については、原則価格競争による入札によって、受託する民間業者を決定しますが、政策入札は、入札参加者の提示する価格(見積もり)に加え、入札参加業者における高齢者、障害者雇用の状況や次世代育成支援の状況、環境に関する状況等を評価に取り入れ、これらを総合的に判断して、落札者(受託業者)を決定する方法です。
つまり企業の雇用努力等を入札において評価することにより、雇用者である民間企業にインセンティブを与え、このことによって、社会的な目標を達成していこうとする手法です。
極端な言い方をすると、市民、高齢者、障害者等の雇用・次世代育成支援等の促進を積極的に行っている企業を一定の条件の下に評価し、市の業務を受託させることにより、民間企業等による積極的かつ適正な雇用等を促す方法です。この方法は、談合等の防止にも効果を上げます。
高齢者・障害者の雇用の促進、次世代育成支援の促進は、法律により企業に努力義務が課せられておりますが、達成が難しい状況にあるのは周知のことです。このような社会的な課題への取り組みは、民間の協力と努力が必要となりますが、法律の規定だけでは拘束力が低く、企業メリット引き出すこともできず、政策の実現が難しい状況にあります。
しかし、各地方公共団体が、今ある外部委託等を利用して、民間企業にメリットを与えることができれば、民間企業における経営方針を変化させるきっかけになります。
また、この手法の大きなメリットとしては、財政状況が厳しい市においても特別な予算を措置することなく即実行できる点にあります。本市では、既に平成18年度当初予算の委託料だけで、総額218億円を超える規模があります。これを利用して、政策入札に位置づければ、今行っている外部委託事業で、市民雇用、高齢者雇用、障害者の雇用、次世代育成支援、環境政策の充実が図れるのです。
高齢者、障害者の雇用促進、次世代育成支援、環境政策は、法律上も地方公共団体の責務であることは、明らかであります。
このような課題に対して、今ある予算を利用し、2007年問題に直面する高齢者や障害者の雇用、次世代育成支援、環境政策に取り組むべきではないでしょうか。
そこで、平成18年2月議会の一般質問以降、政策入札について、本市ではどのような取り組みを行ってきたのか、今後の方針について質問いたしました。
○青少年が心豊かに育つ環境づくりについて
学校教育現場における「いじめ」によって、児童・生徒が自らの命を絶つという大変痛ましい事件が全国で起きております。
このいじめに関する問題を含め、現在の子ども達を取り巻く社会環境全体を考えると、子どもたち 一人一人の健やかな成長を社会全体で支援していく仕組みづくりが私たちの喫緊の課題であると思います。そこで、この喫緊の課題である「学校におけるいじめ問題に関する取り組み」について、学校及び教育委員会における体制について以下の事項を中心に質問をいたしました。
・学校及び教育委員会における体制について
・家庭・地域社会・関係機関との連携について
・青少年相談員事業を強化し、いじめ対策に充てることについて
・個人情報の取り扱いについて
○補助金事業のあり方について
本市の経常収支比率は、86.2%であり、第2次財政健全化計画を達成しておりません。今後も義務的経費・扶助費等については、自然増加率の上昇等により財政負担が多くなることが予測されます。しかし、少子高齢化社会における相応の市の負担を財政的に確保し、将来にわたって市民の方が持続的に各種サービスを享受することができるような財政構造を早急に整える必要があります。従いまして、将来に備えて、まずは、見直すべきものを見直し、今ある事業の取捨選択を行わなければなりません。
このような本市の財政状況を見極めつつ、政策的に思い切った改善が図れるのは、補助金ではないかと考えました。補助金は、ある特定の団体に支出される予算です。特定の団体に与えられることから、その補助の決定に際しては、情報を公開し、広く市民のコンセンサスを得る必要があります。また、補助金は一度認められると、ある意味経常的な経費となり財政を圧迫する恐れがあります。
また、社会情勢によって補助金の対象も変化することが考えられ、新たに必要となる部分と不要となる部分が発生しますので、補助金の廃止・変更・新規追加を随時見極める必要があります。
このようなことから、定期的な見直し、外郭団体への重複受給の整理、第三者による評価、情報の公開について質問いたしました。
<答弁>一般質問に関しましては、全体的に検討・見直しを進めるなど前向きな答弁がありました。
一般
<議案質疑>
議案質疑は次のとおりです。
議案第40号
1 改正理由及び改正するまでにおこなった検証について
・制度及び費用対効果の検証についてなど
議案第41号 自転車等駐輪場
・市民ニーズについて
・設備経費及び使用料について
・使用許可について
・施設の管理運営方法についてなど
議案第44号 補正予算
1数年の決算額等と比較し旅費が増加している事由について
2継続費追加分
・広尾防災公園雨水貯留槽等整備事業及び小学校校舎改修事業の工事の着工時期と平成18年度中の進捗率の出し方について
3高齢者支援費 補助金 地域介護・福祉空間整備等補助金の内容及び交付の適正化について
議案第50号 浦安市市川市病院組合規約の一部改正
地方自治法の改正との関係について
<平成17年度決算審議統括(本会議原稿抜粋)>
まず、決算を審議するに当たっての大前提となる事項を述べさせていただきます。
本市の予算は、毎年、シーリング・一律何パーセントカットというように、厳しい予算査定が行われております。
また、経常収支比率も第2次財政健全化計画の目標が達成されておらず、平成17年度決算では86.2%となっており、政策的経費に充てる財源不足が懸念されます。
また、公債及び債務負担行為について、経常収支比率の計算式に変更があれば、本市の経常収支比率の更なる悪化も懸念されます。
このような状況において、引き続き同じ手法を踏襲している本市の財政運営が最善であるかどうかは疑問です。つまり、シーリング・一律何パーセントカットというような手法は、財政が硬直化している一時期においては、緊急避難的に有効な手法といえます。
実際に本市においても、財政的に非常に苦しい局面にあった時に、効果を挙げたと評価しております。
しかし、以前に比べ財政状況が変化している今日においては、ある程度この手法に限度が見えてきている感があります。これからは、決算結果を最大限活用し、トータルコストによる業績評価を行い、次年度予算に活かしていくような方策を立てていくことが主流となります。
従いまして、決算審査は、次年度以降の予算を方向付ける重要な意義を持つものでなくてはなりません。
今まで、国会・地方議会を含めた日本の決算審査は、予算審査よりも軽視されてきたという批判があります。予算偏重主義です。
国会のテレビ中継・新聞でも予算配分に係る審議は華々しく報道されますが、決算審議については、記憶にないことが多いと思います。
一般の会社では、健全な経営のために決算を最も大事にします。どんな素晴らしい予算案があっても、決算が伴わなければ、単なる大風呂敷を広げただけの放漫経営になってしまいます。
ところが日本では、予算偏重主義が必ずしも見直されていません。国家予算において多額の借金を作った一つの大きな原因は決算を軽視してきたことにあるとも考えられています。
日本のこうした行政体質の弱点は、政策評価を行ってこなかった点にあり、これが予算消化の組織風土を生みだしました。しかし、こうした時代は終わり、現在では、計画やプロジェクトの見直し、廃止、予算の減額など聖域なき改革の議論が高まってきております。
決算審査は、次年度以降の財政方針の決定、予算配分そして、未来の健全な財政運営を図る上では、最も重要で、私たちのこれからの生活に係る大切な審査と言えます。
このような視点に基づいて、平成17年度決算につきまして、私なりの視点から評価をし、意見を述べさせていただきます。
○依存財源について
依存財源については、自主財源の大きな伸びが期待できない中で、市民サービスを維持・拡充していくためには、必要な財源となります。しかし、ここで、重要なことは、本市にとって、本当に必要と考えられる交付金は、着実に確保する必要がありますが、逆に、市民ニーズ等が得られないような箱物、将来的に維持することが負担となるものについては、しっかりと見極め、安易に国の交付金等の制度に乗るようなことは避けなければなりません。本市のニーズに合致するものだけを取捨選択し、将来性・計画性のもとに適格に判断していく必要があります。
○市債について
市債については、平成17年度は、広尾防災公園用地の整備などを始め、都市基盤整備が集中しました。従いまして、今後は新たな財政負担が見込まれることから、市債については、事業内容、世代間負担の公平性、後年度負担への配慮を総合的に判断し、計画的な活用に努めて頂きたいと思います。
○歳出全般について
総じては、執行率が前年度並みの96.3%で、概ね適切な執行が行なわれたものと考えております。
しかし、予算計上したものが執行できずに、全額不用額となったものも見受けられます。
これら不用額については、速やかな減額補正を行うなどの措置を引き続き徹底していただきたいと思います。また、不用額を安易に流用できないような財政統制をきちんと行い、予算目的に反するような流用・執行がなされないよう、更に適正な予算執行を図っていただきたいと思います。
更に、平成17年度施策において総じて、その方法・執行が合法的であったのか、経済性、効率性が図られた執行であったのか、予算投入額に見合った有効的な結果が得られたのかについて、厳しく検証を行い、次年度以降の運営につなげていただきたいと思います。
本市の財政状況は、各種の財政指数等から総合的に判断しますと、改善されてきました。
しかし、今後バブル期のような税収の伸びも期待できず、一方で都市基盤の整備や機能維持を始めとして市民ニーズからの行政課題が山積しております。従いまして、今後も財政運営の厳しさは変わらないものと認識しています。
平成17年度は、都市基盤整備が多くありました。本市は、新たに施設を創ることは得意ですが、既に建っている施設の長期修繕計画については、見通しが立っておりません。経常収支比率がまだまだ高い状況にある中で、将来予測される大型修繕の見通しがないというのは、危惧されるべきことです。新規施設の建設計画の際には、当然のことではありますが、必ず修繕・ランニングコストを踏まえ検討していただきたいと思います。
また、冒頭で述べましたが、健全化計画の達成ができない状況において、シーリング・一律カットという手法だけでは、限界があります。他の地方公共団体では、シーリングを撤廃して、トータルコスト予算を導入しているところもあります。
本市においてもゼロベースで事業を抜本的に見直し、本当にどの事業が必要なのかを見極め、必要であれば効率性・有効性について総合的に検証していかなくてはなりません。
そして、効率的な予算積算ができた場合、一律カット方式ではなく、その事業に係る必要経費をしっかり見込んで、着実な市民サービスを提供していかなければなりません。
また、事業の効率化により得られた財源は、少子高齢化対策等の将来に向けた備えとして確保し、市民の方が将来に亘って公平なサービスの提供を受けられるよう、財政的措置を講じていく必要があります。
決算を一過性のものとして捉えるのではなく、将来の市川市のあるべき姿を描き、今現在の決算状況からして、何をやらなければならないのかということをしっかり見極めて、長期的に安定した財政運営を行っていただきたいと思います。
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- ビジネス・起業に関すること。
- 取り越し苦労をするな。
- (2024-06-28 07:00:37)
-
-
-

- あなたのアバター自慢して!♪
- バーチャル渋谷おでかけハロウィン
- (2022-11-01 19:50:06)
-
-
-

- みんなのレビュー
- 届いています 静岡野菜セット C 1…
- (2024-06-28 13:13:27)
-
© Rakuten Group, Inc.