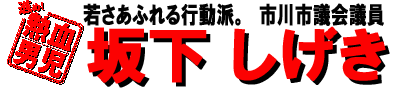議案第52号
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について
坂下しげきでございます。
通告に従いまして質疑致します。
まず、この条例は地方自治法の一部を改正する
法律の施行に伴って所要の改正を行うもので
ありますが、このことに係る本市の認識について、
法律制定の経緯及び趣旨に基づき質疑します。
議案の説明時に当該条例の改正は、助役から副市長に名称を変えるものという説明がありましたが、この地方自治法の一部改正は、助役を副市長という名称に代えるという単純なものではありません。
地方公共団体のトップマネジメント体制の構築と強化、地方公共団体の組織運営面の自主性・規律性の拡大を図ることが地方自治法の改正の目的です。
例を挙げると、改正前の地方自治法では、市町村にあっては助役を一人置くことが原則とされていました。
つまり地方自治法上で助役を一人設置できる根拠があり、地方公共団体が別に条例を制定しなくても助役は一人置けるものでした。
しかし、改正後の地方自治法では、一人置くという規定がはずされ、その定数についても地方公共団体の自主性において、個々に条例で定めることになりました。
このことは、つまり、地方公共団体の自主性により、副市長を何人置くかを条例で決める、言い換えれば市のコンセンサスで副市長を何人置くか、若しくは置かないかを決定できることになったのです。条例により副市長を置かないという選択もできます。
このような地方自治法改正の経緯・趣旨としては、地方公共団体の規模、その所管する行政分野、事務や事業が大幅に拡大し、また、地方分権の推進に
より地方公共団体の役割と責任が拡がっていることにあります。
このようなことから、地方公共団体の
トップマネジメント体制の構築・強化を図るために地方自治法が改正されました。
第28次地方制度調査会の答申において、地方公共団体が自らの判断で適切なトップマネジメント体制を構築できるように、助役制度を見直すことが適当とされたことを受けて、法制化が図られたものであります。
従いまして、今回の条例の改正に当たっては、
今後の市の拡大する事務や事業、市民ニーズ、
そして地方分権に伴う役割と責任の増大等を広く
勘案し、最小の経費で最大のサービスを迅速に行うためのトップマネジメント体制は、どうあるべきかという慎重な議論によって、条例の改正を行う必要があります。
そこで、条例で定める副市長の設置及びその定数の根拠規定となる地方自治法第161条の改正経緯および趣旨をどのように条例改正に活かしたのか、まずお答え下さい。
また、地方自治法の一部改正に係る総務省・総務事務次官通知では、副市町村長の定数は、改正の趣旨、行政改革の観点等を踏まえ、各地方公共団体において適切に定めるべきとあります。条例の制定に当たって副市長の定数をどのように検討したのかお答え下さい。
更に、今後の本市のトップマネジメント体制の構築について、市長の意向をどのように反映して、この条例を制定したのかお答え下さい。
次に、地方自治法第167条との関係についてお伺い致します。
副市長制に係る地方自治法の改正は、長を支えるトップマネジメントの強化の観点から、副市長の職務について、単に内部的な長の補佐にとどまらず、より積極的に長の命を受け政策及び企画について、長に次ぐ立場から関係部局を指揮監督し、
必要な政策判断を行うことを明確化するものであります。
地方自治法第167条の規定により、副市長は、これまで市長が担ってきた市川市としての判断の一定部分について、長の意向・判断の範囲内において、自らの担任事項として処理することが明確にされました。
この条例において、本市では、副市長2名が置かれることになっておりますが、どのような権限を委任する方向で検討が進められているのかお答え下さい。
また、権限の委任に伴うラインの複数化による混乱についてはどのような考えを持ってのぞむのかお答え下さい。
以上1回目の質疑とさせて頂きます。
ご答弁によりまして、再質疑させて頂きます。
© Rakuten Group, Inc.