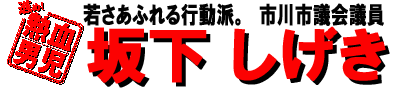一般質問
通告第1の中国分3丁目のマンション建設についてお尋ねをいたします。
市川市は千葉県の西部にあり、江戸川を隔てて東京都に相対し、都心から20キロメートル圏内に位置した文教・住宅都市として発展をしてまいりました。東京までは、交通機関を利用して二、三十分の距離にありながら、緑も多く、学園も多い町であります。そして、本市の北西部に位置する中国分は、緑が多く、住環境及び景観が美しく、住民の方に愛されております。中国分3丁目は私も暮らしているところでありますが、都市計画法第8条第1項第7号に規定する風致地区に指定され、これまで住環境が守られてきました。風致地区は、都市における良好な自然景観を維持するために定められたもので、風致地区内では建築物等の建築や土地の形質の変更などには許可が必要とされ、その風致と著しく調和しないものには許可が与えられないものとなります。中国分3丁目では、周辺一体がこの風致地区並びに第1種低層住宅専用地域に都市計画決定されておりますが、現在のエヌ・イーケムキャット株式会社市川研究所跡地だけが過去の経緯によって風致地区等から除外されています。そして、現在ここに大型マンションが建設されようとしています。
このマンション建設予定地の風致地区等の除外決定について過去の経緯をたどると、もともとマンション建設予定地は風致地区に指定されておりました。しかし、昭和48年12月28日の都市計画決定の前年の昭和47年に、当時この土地を所有していた住友金属及びエンゲルハルト研究所から、用途地域等の決定について陳情が出され、これに伴いこの土地が風致地区から除外されたという経緯があります。
この陳情の趣旨は、風致地区及び第1種低層住宅専用地域に指定されると、研究所等の建物が不適格建築物になり、同研究所の事業に支障が出るというものでありました。つまり、この過去の経緯に従うと、風致地区並びに第1種低層住宅専用地域の除外措置は、当該研究所の持続を前提に決定されたものであり、除外措置の目的である研究所がなくなった場合は風致地区と同様の扱いが求められるものであります。
その証拠に、昭和54年に住友金属がこの土地を大型スーパーに提供するという問題が発生いたしましたが、このとき、当時の高橋國雄市長は議会答弁において、風致地区になっていたものを解除した経緯が昭和47年の陳情等の経緯にあるので、その経緯に基づいて考えてみた場合、少なくとも住居地域になったからといって、その用途地域の関係を逆手にとるようなことは企業モラルに反すると断じております。そして、さらに加えて、住友サイドも法的にはある程度の考えに基づいていると思うが、行政サイドに立った場合は、こういうようなことがまかり通るということは大変大きな問題であるというようなご答弁をされ、少なくとも原点に戻して、白紙になった上で考えるべきであるとされ、結果はご承知のとおり白紙に戻されたわけでございます。
したがいまして、今に至って当該地所に大型マンションを建設することは、昭和48年当時の用途地域決定の経緯を無視したものと言わざるを得ません。本市がこれを認めるようであれば、行政における継続性を失わせるものとなります。また、本市の景観計画に基づく都市計画のあり方にも疑問を抱かざるを得ません。昭和54年当時は、議会と市長のリーダーシップのもと、行政の一貫性が保たれたわけであります。現在も昭和54年当時と状況は変わりなく、地域住民の方も反対をされております。ここは、過去の経緯を考え、行政の継続性、中国分地区の景観の維持という行政本来の目的を達するという立場に立って、市として強いリーダーシップを発揮して臨むべきであると思います。
そこで、このような過去の経緯を踏まえまして、中国分3丁目のマンション建設について、市長はどのような姿勢でリーダーシップを発揮し、どのような解決を目標にして行政の継続性を維持していくのか、お答えをいただきたいと思います。
続きまして、通告第2の北総線北国分駅の利便性についてお尋ねをいたします。
北総線北国分駅は、改札口に至るまでに28段の急な階段を利用しなければなりません。JR市川駅でも階段は11段しかありませんが、エレベーターが設置されております。実際に北総線北国分駅で利用状況を確認してまいりましたが、高齢な方、障害者の方なども多く利用されておりました。北国分駅の階段は、急で段数も多いことから、利便性や安全性を考えると、一日も早い改善が望まれます。市川市では、通称交通バリアフリー法、正式名称では高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律の趣旨に基づいて、平成22年までに市内公共施設等のバリアを排除することを目標に掲げております。しかし、北国分駅は市川市バリアフリー基本構想の中で優先的に整備すべき重点整備地区としての基準を満たしていないことから、重点整備地区から除外された位置づけになっております。このことについて、平成19年2月議会で松葉議員が同様のご質問をされており、これに対するご答弁では、重点整備地区にはなっていないが、鉄道駅は多くの人々が集まる施設であることから、駅の利用者、駅を利用したいと望みながら利用できない方々を考えれば、バリアフリー化を早期に実施すべきと考えているとのご答弁がありました。また、市川市は北総鉄道株式会社の株主であることから、この株主としてのチャンネルを使って設置を申し入れることもできると思います。
したがいまして、北総線北国分駅におけるエレベーター、エスカレーター等の設置について、今後市として設置に係る目標をどのように定めて実行していくのか、お答えください。
続きまして、通告第3の行政境における課題についてお尋ねをいたします。
今日、私たちの日常生活や経済活動はますます広域化し、町並みも広がりつつあります。また、価値観もますます多様化し、地方自治体へのニーズも高度化しており、行政サービスの一層の専門化や高度化が求められているところでございます。このような状況に地方自治体が適切に対応するためには、広域的な視点から連携したり、あるいは調整を行いながら行政を進めていくことが必要になります。このような広域的、すなわち隣接する行政体同士の問題を迅速的、効率的に解決するために、広域行政の取り組みが行われているところでもあります。本市においても、広域行政の推進を行うため広域行政担当が設置されたものであります。地域間、行政境における問題は種々多様であり、このことは常に地域住民の方の生活環境に密着した課題であります。
先ほど質問いたしました中国分3丁目のマンション建設などに見られるように、都市計画の考え方は市によって異なりますが、道路1本隔てた市境で大きく考え方が違う場合は、本市の目的とする理想の都市計画が実現しない可能性があります。例えば、国府台4丁目は松戸市と接しておりますが、ごく小さな道を隔てただけで、都市計画、用途地域が大きく異なるという現実があります。この例では、市川側が第1種低層住居専用地域及び風致地区に指定されており、市川側の容積率80%に対し、松戸側は100%、建ぺい率は市川側が40%に対し松戸側が50%と大きく異なっております。また、私のところには近隣市の船橋市の住民の方から、市川市の排水について苦情が寄せられております。小さな川を隔てた市境にある市川市のマンションから生活雑排水が直接川に流され、悪臭や害虫発生の原因となり、船橋市側の生活環境を脅かしているとのことであります。市境にある問題は、大小を問わず行政に相談してもなかなか決着がつかず、長年解決できずにいることもあります。また、市境の問題は内容がさまざまであり、本市から他市への要望と、他市から本市への要望も交錯しております。
このような実際に起きている諸問題を踏まえまして、市と市の交渉及び住民の方の相談窓口の一元化を目指して新たに組織した広域行政担当において市境の問題を総括し、効率的な解決を図っていくような仕組みづくりができないのか、お答えをください。
続いて、通告第4の環境政策についてお尋ねをいたします。
平成17年12月議会における私の質問を受けて、本市から排出される一般廃棄物については、今年度から適正処理がされることになりました。そして、本市では資源循環型の町市川を目指して3Rを推進しております。そこで、まず本市自身が排出しているプラスチック製容器包装類、紙類、瓶、缶、パソコンについて、どのような処理が行われているのかお答えください。
次に、環境ISO取得に係る効果についてお尋ねをいたします。
本市自身が排出事業者となる廃棄物の種類は、ただいま質問いたしました一般廃棄物、資源ごみがあり、ほかには産業廃棄物があります。本市は、市内最大規模の事業系一般廃棄物、産業廃棄物等の排出事業者であり、同時に市内民間事業所を監督、指導する立場にあります。したがいまして、廃棄物の適正処理について率先垂範すべきであり、その適正さを客観的に判断されるために環境ISOを活用するということが考えられます。紙面上だけの審査では、意味がないと思います。環境ISOの取得において、廃棄物の適正処理及び資源化についての審査はあるのか、そして効果はあったのか、お答えをください。
続いて、通告第5の発達障害に対する取り組みについてお尋ねいたします。
自閉症、アスペルガー障害、ADHD、注意欠陥多動性障害、LD、学習障害といった発達障害を患う子供たちに対する行政のフォロー体制が重要な課題になっております。障害により学校など集団生活においてうまく溶け込めないお子さんに胸を傷めている親御さんたちが多くいらっしゃいます。また、実際には障害がなくても不安を募らせ、過敏に反応してしまう親御さんたちも少なくないようであります。
文部科学省が2002年に約4万人の小中学生を対象に行った調査では、発達障害またはその疑いがある児童生徒は6.3%に上っています。また、専門家によると、早ければ1歳半で障害の兆候に気づく親はいるとのことでありますが、実際に専門機関などを受診して発達障害と診断されるまでに2年以上かかるケースが多く、その結果、子供が孤立したり不登校になるなど、2次障害に発展する例もあります。こうした状況を少しでも改善するためには、子育ての初期の段階で正確な障害の発見を行うこと、そして障害がわかった場合にしっかりとしたケアシステムをつくっていくことが、子育て環境にとって重要なサポートになると思います。したがいまして、発達障害に対する早期発見及び早期療育に係るシステム整備について、順次質問をしてまいります。
市町村が発達障害の早期発見について積極的に関与することができ、また、責任を負っているのが母子保健法第5条第12条及び第13条の規定に基づいて実施する乳幼児健康診査であります。本市では、1歳未満のうちに行われる2回の乳児健診と、1歳6カ月児健康診査及び3歳児健康診査があります。特に、1歳6カ月児健診と3歳児健診においては、精神的、身体的な発達の重要な時期にあり、そのときに正確な健康診査を行い、育児に関する指導、相談等を行っていくことが幼児の健全な発達を図る上で重要になります。したがいまして、発達障害の早期発見の場として期待されるのが、この1歳6カ月児健診になります。
健康診査において早期発見できるかどうかの重要なポイントは、健診方法にあります。早期発見に力を入れている横浜市では、知的障害のない場合も含め、自閉症と診断された子供の約8割が1歳6カ月児健診で指摘されております。これは、健診方法に自閉症であると困難な応答の指さし確認を取り入れていることにあると言われております。
そこで、本市の1歳6カ月児健診における発達障害の早期発見に係る健診方法についてお答えください。また1人当たりに要する健診時間についてもお答えください。
次に、早期発見が行われた場合には、その後の適切な支援が重要となります。支援がない状況で障害を告知することは、親子を不安にさせるだけで、早期発見によるメリットを引き出すことができません。2005年4月に施行された発達障害支援法では、早期発見及び療育が行政の責務とされ、自治体に乳幼児健診の充実、支援体制の拡充を求めています。
そこで、早期発見と早期療育をつなぐシステム整備について、今後どのように取り組んでいくのかお答えください。
以上、1回目の質問とさせていただきまして、ご答弁によりまして再質問させていただきます。
それぞれご答弁をいただきましてありがとうございました。
まず、第1の中国分3丁目のマンション建設予定についての件でございますが、この中国分地区につきましては、質問の冒頭で申し上げましたように、都心にごく近い地域でありながら、緑豊かな良好な住環境が維持されております。これは、この地区に住む方々のご努力であり、昔から継続する用途地域の指定に守られてきたからであります。重要な部分、何点か質問させていただきます。
ご答弁では、それから今までのご答弁を見ますと、一団地の認定に対して認定しない旨の通知をするとのことでありました。ということは、これにより政治姿勢、政治判断を継続して積極的な対応が行われるということでよいのか、お答えをいただきたいと思います。
それから、一団地の認定の申請に対して事前協議は行っているのか、お答えいただきたい。
それから、千葉県に対して風致地区に関する見直しを求めているとのことですが、今後このような問題が再燃しないよう、具体的にどのような働きかけをするのかお答えください。また、景観条例及び条例に基づく市川景観計画から見た今回のマンション建設の適否についてお答えいただきたいと思います。
続きまして、第2の北総線北国分駅の利便性についてであります。今年度、北総鉄道株式会社からバリアフリー化整備について相談を受けたということですが、その内容についてお答えいただきたいと思います。また、北国分駅のバリアフリー化はどのぐらいの予算規模になるのか、お答えいただきたいと思います。
続きまして、第3の行政における課題についてでございます。広域担当の体制はどのようになっているのか。担当職員の人数をお答えいただきたいと思います。また、実際にどのような案件を取り扱ってきたのか、お答えください。
続きまして、第4の環境政策でございます。ご答弁を伺っていますと、本市のISOはペーパードライバーのような気がするわけでございます。審査の段階では、紙の上でそつなくこなしていくというような感じなんですが、一番大切なのはコンプライアンス、法令遵守について、非常に認識が甘いのではないかと思われるわけでございます。ただ、ISOの認証を受けていれば万全だと考えるのはかえって危険で、意味のないことであります。実質面で法と理念にのっとった処理が行えているかどうかを市として監視し、実行していく必要があろうかと思います。コンプライアンスの徹底という立場から再質問をさせていただきます。
資源化しているものについて、資源再生事業者に搬入しているとのことですが、実際にリサイクルされているのか、これを調査、確認したことがあるのか、お答えください。
プラスチック製容器包装類は可燃処理しているとのことなんですが、このうち、例えばペットボトルなどは産業廃棄物に分類されてもいいはずであります。見解も分かれているわけでございますが、本市では事業系一般廃棄物もしくは産業廃棄物のどちらと判断しているのか、お答えをください。
それから、事業系のパソコンについては、リサイクル法の改正により努力義務の範囲ですが、地方公共団体のリサイクル化が義務づけられております。ご答弁では、本市にあるパソコンの多くはリースであって、これは返却するとのことですが、市が所有するパソコンの処分は今までなかったということでよいのか、お答えください。
それからもう1つ、ISOの認証機関では、本市のこのような処理状況をすべて知っているのか、お答えいただきたいと思います。
次に、発達障害についてでございます。問診票に応答の指さし確認を入れているとのことで、健診方法は県内でも進んだ取り組みをされているものと思います。この健診方法を踏まえて、早期発見に係る正確な判断とその後のフォローアップをどのように行うかが次の課題になってくるかと思います。
そこで、質問冒頭で申し上げましたが、早期発見に力を入れている横浜市では、知的障害のない場合も含め自閉症と診断された子供の約8割が1歳6カ月児健診で発見されております。市川市の1歳6カ月児健診における発見割合はどのぐらいか、お答えをください。
また、健診後の見きわめ及びフォローアップにおいて重要な役割を担っているのが保健師であると思います。日本自閉症協会の調べでは、乳幼児健診に携わる保健師の6割以上は子供の自閉症と発達障害を理解していないという結果が出ているわけでございます。市川市での研修体制の内容及び今後の課題は何か、お答えをいただきたいと思います。
以上、再質問とさせていただきます。
それぞれご答弁をいただきましてありがとうございました。順次また再質問させていただきたいと思います。
中国分のマンション建設のほうですが、風致の件、千葉県のほうに申し入れを行ったということだったんですけれども、いつ行ったのでしょうか、お願いをしたいと思います。何よりも、市長の強いリーダーシップのもと、行政の継続性が続いていかなければ、住民の方々は困ってしまうんです。ぜひともその点をお願いしたいと思います。そこを1点お答えいただきたいと思います。
それから北総線、国との協調補助も重要です。それはわかります。だけれども、市川市は株主なんですから、ぜひせっかく投資しているんですから、株主としての役割をきちんと示していただきたいと思います。これは結構です。というのは、どうせ投資するんだったら、市民にとって有意義な投資をしなきゃならないんですよ、税金を使っているんですから、お願いします。
それから、行政境の問題でありますが、この行政境の問題は、いろいろな問題がありまして、大きな行政判断を伴う場合も多く、担当レベルだったりするのは難しいから、こういう広域行政担当があるかと思います。体制をしっかりと整えていただきたいんです。企画部長、よろしくお願いいたします。
それから、環境政策についてです。市のパソコンなんですが、各部署で処理しているということなんですけれども、そうしたら環境清掃部がある意味自体がおかしいですよ。しっかりと、それをどういうふうにしていくかということをやはり示していかないと、おかしいんじゃないですか、と思うんです。ISOをとるということは、私はそういうことなんじゃなかろうかと思うわけですね。ですから、それについて今わかる範囲で結構です、お答えをいただきたいと思います。
そして、発達障害に関しましては、健診をしっかりやっていただいて、早期発見、よろしくお願いいたします。
答弁ありがとうございました。
学校関係で、パソコンを処理されたということでございます。時間がありませんので今ここではできませんが、次回、学校関係でどういった処分をしたのかというところが大事なんです。今後、処分するものもあろうかと思いますので、しっかりとした環境清掃部を中心とした環境行政を行っていただきたいことを要望いたしまして、一般質問とさせていただきます
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- ひとり言・・?
- もうすぐクリスマス アドベントカレ…
- (2024-12-01 23:11:02)
-
-
-

- みんなのレビュー
- レーズン、割れチョコなど お得にた…
- (2024-12-02 09:44:11)
-
-
-

- 今日のこと★☆
- - 02. DECEMBER *Lucy Liu *
- (2024-12-02 10:49:30)
-
© Rakuten Group, Inc.