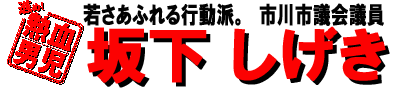一般質問
まず、質問に入る前に、2月議会は24日が最終日となり、この議会が終わりますと、1週間で多くの職員の方々が退職を迎えられます。永年のご尽力に心から謝意を述べると同時に、今後も市川市発展のためにご活躍いただけることを切望いたします。
それでは、通告に従いまして一般質問をさせていただきます。
第1の監査制度についてお尋ねをいたします。
監査は、地方自治法において、市長と対等の立場で監査を実施する独立の機関として位置づけられており、非常に責任の重い機関であります。現在は市民ニーズが多様化し、業務内容も高度な専門性が要求されており、地方分権により事務内容も大幅に変化しつつあります。公正で効率的な行政の確保に対する住民の関心が一段と高まっている中で、その政策の有効性、経済性、効率性などを最終的にチェックし、改善を指摘することができる最後のとりでが監査になります。独立機関として、市民に対して説明責任を負っているのも監査であります。平成3年に地方自治法の監査制度に改正があり、従来の財務監査に加え、地方自治法第199条第2項の規定に基づく、いわゆる行政監査ができるようになりました。この改正を受けて、現時点では、多くの市において経済性、効率性及び有効性の観点から行政監査が行われ、指摘・改善事項等がホームページ上で多数公表されております。一方、本市では、個別テーマを定めた行政監査は現在行われておりません。例えば他市の行政監査で多く行われている事例の1つに、情報関係事業に係る監査があります。今はどこの市でも情報関係予算が膨大化し、経常経費化され、その執行も全庁的に及ぶことから、事業の有効性や効率性、契約方法の適正性、適法性、予定価格の設定を含む経済性について、専門家を含めて行政監査を行っている事例が見られます。補正予算の質疑を行ったときも指摘した事項であります。
また、ある自治体では、市の重点施策について、事業評価の手法による行政監査を行い、アウトプット部門の目的の達成状況や有効性、費用対効果を検証しています。全庁的な随意契約の見直し、予定価格の設定についても、監査委員会みずからが多角的検証を行い、その解消方法について、具体的な検証、提案まで行っております。このような監査委員会における取り組みがなければ、地方公共団体としての市川市の使命である最少の経費で最大の効果を上げていくための実証及び説明責任が果たせないものと思います。市川市は、他市よりも新規事業が多く、情報関連予算も膨大であり、随意契約も過去の本会議や委員会で指摘されているとおりであります。市川市全体として、PDCAサイクルを全うし、市民に対して最大のサービス効果を上げるためには、独立機関である監査の役割は大きいと言えます。
12月議会のご答弁では、本市において、定期監査のときに行政監査の着眼点を含めて実施しているとのことでした。12月議会後、幾つかの自治体を加藤議員、中山議員と視察をしてきましたが、財務監査も行政監査も、かなりの精度、ボリュームが要請されることから、これを一度に行うには限界があるとのことでした。この限界があらわれているかどうかわかりませんが、本市の監査結果の公表は、他市の公表と比べると非常に少ない内容となっております。他の自治体では、監査結果の公表内容として、まずは行政監査の監査目的を明記し、その上で指摘・改善・検討事項を述べ、さらにそれらの要因を多角的に検証し、その解決方法についてまで具体的に言及しております。その結果、他の自治体では、毎年30項目ぐらいが指摘・改善事項で上げられております。本市の場合は、指摘事項等が1つもない年がほとんどであります。このような監査結果の大きな違いは、行政監査の力点、力の入れよう、監査視点や監査目的の違いもあると思います。他の自治体の行政監査では、その事務に関する法令だけではなく、広くコンプライアンスという観点から、本市では監査とは別に実施しているISO的視点、ISMS的な視点からも監査をしております。そして、事業の有効性に関する観点からも厳しく指摘、要望を行っております。
そこで、まず、定期監査のときに行政監査の着眼点を含めて実施しているとのことですが、この行政監査的着眼点、目的で何を監査し、どのような結果が得られたのか。もっと明確化、公表できないのかお答えください。
次に、テーマを持った行政監査の魅力として、全庁的に共通する業務に横串を入れるように一律に見直すことができる点があります。現在の市川市の監査の方法は、毎年監査を実施する組織、部を決めて行っていることから、全庁的な類似業務の見直しを、横串を刺して一掃することができない形となります。全庁的な類似業務の見直しとして、多くの自治体が行政監査のテーマに挙げている事例は情報システムに関すること、個人情報の取り扱いに関すること、土地建物の管理に関すること、随意契約の見直しに関することなどがあります。どれも全庁的に行う必要がある業務で、監査で得られるメリットも大きいと思います。前議会のご答弁では、テーマを定めた行政監査の実施に向けては今後検討するとのことでした。
そこで、全庁的に共通する業務について、テーマを定めた行政監査を実施していくことはできないのかお答えください。
次に、包括外部監査の実施についてお尋ねをいたします。包括外部監査を行っている自治体に視察に行くと、包括外部監査の結果を積極的に活用し、経営の見直しやサービスの改善を行っており、また、その結果を公表することで説明責任を果たしております。また、通告第2の質問とも関連しますが、外郭団体及び補助金交付団体の包括外部監査を行うことによって、市の政策的判断を見きわめることもできます。前回の包括外部監査のご答弁では、経費が1,000万円から2,000万円かかり、他市の例では監査結果も芳しくないなどデメリットが多く述べられていました。しかし、他市の事例は、今、インターネットで公表されているので、だれにでもすぐわかるわけでございます。監査の成果、監査結果の質は千差万別であります。すばらしい監査報告書もあれば、そうでないものもあります。これは包括外部監査制度自体の問題ではなく、監査を実施する外部の監査人の資質、あるいは監査事項による差です。市川市が本気で包括外部監査を実施し、その結果を政策につなげていく意欲があれば、効果を上げる監査ができると思います。監査人の報酬は、平均で600万円から3,000万円と言われておりますが、情報関連や大型事業に適切な監査が入れば1年で回収できる経費であり、その後は事業経費の縮減になり、ほかの有効な事業に予算を回すことができます。
そこで、今後、包括外部監査制度を導入する、しないの判断について、どのような検証を行っていくのかお答えください。
続きまして、第2の外郭団体等の経営改革及び本市のかかわりについてお尋ねをいたします。
外郭団体の経営改革にかかわる指針の改定が平成15年12月12日付で総務省から出されており、第三セクターに関する積極的な運営改善、事業の見直し等、抜本的な対応を求めております。この総務省指針では、現に第三セクターに公の施設の管理を委託している地方公共団体にあっては、地方自治法の改正により指定管理者制度が導入されたことを踏まえ、第三セクター以外の民間事業者の活用について積極的に検討を行うこととされております。これらを受けて、他の自治体でも既に積極的な改革に乗り出しており、市の出資団体に対する指導、監督、支援のあり方について、基本方針を策定し、経営評価システムの導入、監査法人による経営評価の実施を行っております。しかし、本市では外郭団体に関する基本方針の策定、公表はありません。本市では、外郭団体に対して派遣職員の人件費を含む委託料と補助金とが混合して支出されております。このことは、委託料で充てるべき範囲と補助金で充てるべき範囲が整理されておらず、不透明な感があります。また、補助金の見直しは、第1次的には所管課が行う必要がありますが、執行者である所管自身が厳しくチェックすることには限界があります。先ほど行政監査について伺いましたが、これについても最終的には監査がその重要な役割を担うことになると思います。
そこで、外郭団体等に支出する補助金について、最少の経費で最大の効果を上げているか。経済性、効率性及び有効性の観点から行政監査を行っているのかお答えください。
次に、来年度には外郭団体の1つであります財団法人文化振興財団の本丸である文化会館及び市民会館の指定管理者の2度目の選定を行うことになると思います。指定管理者制度の導入までには、地方自治法の改正、経過措置期間等を経て、既に四、五年がたとうとしております。他市でも、地方自治法の改正の趣旨や先ほどの総務省指針、そして何よりも市民サービスの観点から見直しを行っているところであります。大きな政策的観点から、本市が文化会館等の運営を当該財団に任せるというのも市長の政治的判断であります。しかし、管理運営費用は市民の税金であります。市民の視点に立てば、質のよいサービスを低コストで受けるのが当然の権利であると思います。
過去の議会においても、私も市民サービスの向上の観点から議案質疑及び一般質問を行っております。この4年間、市川市がどのような見直しを行ってきたのかが不明確であるため、外郭団体のうち、財団法人文化振興財団の経営改革に関する措置及びこれに関する本市の考え方についてお答えをください。
次に、12月議会において利用料金制の導入が不可欠とのことでありましたが、利用料金制を実施していくという方針でよいのかお答えください。
続きまして、第3の環境政策についてお尋ねをいたします。
まず、資源化ごみについてお尋ねをいたします。ごみの資源化は、将来の地球環境を考え、次世代に与える影響を考えると非常に重要なことであり、地方公共団体としての責務であると思います。しかし、資源化は簡単に行えることではなく、必ず資源化するための莫大な予算がかかることを想定する必要があります。真に政策方針として資源化を行おうとするならば、目先の政策的美辞麗句にとらわれるのではなく、中長期的な視点で計画的に予算を確保し、実行していかなければ、目指すところの資源化はできないと考えております。私は、基本的に民営化が可能な事業は民営化すべきであると考えております。しかし、ごみの適正な処理、資源化は、地方公共団体がみずから行うべき事業であると思っております。
前議会に引き続き、瓶、缶中間処理施設についてお尋ねをいたしますが、この事業は許可という特殊性があることからも公設民営が妥当であると考えます。公設民営であれば、許可というごみ処理施設の特殊性をクリアしつつ、業務の部分で民間の活力が期待できます。市が行おうとしている民設民営はデメリットが大き過ぎます。費用面でも、本市の処理計画においてもメリットがありません。
まず、一般廃棄物処理施設は県知事許可が必要になります。つまり民設民営であれば、初めに許可をとったところが許可業者という独占的な立場になります。一般的に、初めに許可をとった業者では処分し切れないほどのごみの増加がなければ、新たな者に許可は出ません。したがいまして、民設民営にした場合、市がみずから特定の者、つまり初めに契約した業者に独占状態を与えることになり、数年後にはこの独占業者の言い値で市が処理費用を支払う事態になる危険性があります。民設民営における費用対効果はあると言えるのでしょうか。
一方、公設民営にした場合は、施設は市のものでありますから、市がみずからの名で施設の許可をとり、施設で行う業務部分を民間発注することができます。業務部分には許可が必要ないことから適正な競争環境が整い、費用対効果も上がると思います。前議会のご答弁で、民設にしても契約期間満了時に入札ができるとのご答弁でありましたが、その理由として、1回目の契約者が許可を返納しなくても新たな許可が必要ならば許可を出すので1社独占状態にならず、競争できるとのことでありました。しかし、このご答弁を聞いていて、私はかなり驚いたのですが、つまり市は一般廃棄物の処理施設について、幾つでも許可を与えるスタンスにあるということであります。わかりやすく言うと、市は市川市内に幾つもの廃棄物の処分施設をつくることを認めているということになるわけでございます。市は、民設を行うためには市内に新規のごみの処分場が幾つできてもよいと言っていることになるわけでございます。これは市川市の環境政策からして妥当と言えるのでしょうか。そこまでして民設民営にこだわる理由がわかりません。
そこで、前議会のご答弁で、1回目の契約者が許可を返納しなくても、新たな許可が必要ならば許可を出すということの考え方についてお答えください。
次に、現在、市が設置しているストックヤードの千葉県知事への届け出年月日についてお答えください。
続きまして、一般廃棄物処理施設における廃掃法第11条第1項に規定するあわせ産廃の適用についてお尋ねをいたします。前議会のご答弁で、クリーンセンターという一般廃棄物処理施設で産業廃棄物を焼却処分しているとのことでありました。そして、これは廃掃法第11条のあわせ産廃を適用しているものとのことでありました。
そこで、年間どれくらいの産業廃棄物の処理をクリーンセンターで行っているのかお答えください。
次に、許可基準についてお尋ねをいたします。本市では、一般廃棄物処理計画及び条例に基づき許可を行っております。収集運搬の許可業者はここ数年減少しておりますが、新たな許可業者はありません。そこで、許可を与える基準について端的に明確にお答えをいただきたいと思います。
続きまして、第4の市民の生命、財産を守る防犯灯の考え方についての自治会への補助についてお尋ねをいたします。
このことについては、さきの12月議会におきまして質問をさせていただきました。自治会から強い要望のあった防犯灯への補助金アップについてでありますが、これまでは1灯につき年間1,000円の補助金でしたが、12日に20年度予算が成立し、20年度からは1灯につき年間1,500円、昨年度より1灯につき年間500円多い補助金が各自治会へ支給されることとなります。これについては迅速な対応をとっていただいたことに感謝するわけでございます。が、しかしながら、犯罪等が多発している昨今、安心で安全なまちづくりは行政の重要な施策の1つであります。防犯灯の意義を考えると、補助事業ではなく、市が本来行わなければならない委託事業ではないかと考えるわけでございます。
そこで、現在は自治会に対して補助金を交付しておりますが、自治会とも話し合い、今後は委託事業にする必要があるかと思いますので、市のご見解についてお答えをいただきたいと思います。
次に、防犯灯、商店街灯、道路街灯とのすみ分けについてお尋ねをいたします。市川駅北口から真間小学校に向かう途中で、若い女性がひったくりに遭ってしまった事件があるようでございます。そこは商店街灯があるのですが、防犯上、十分とは言えないようであります。このような場所は市内に幾つかあるわけでございますが、4月からは組織改正で経済部の商工振興課が市民経済部に移ることとなるわけでございます。防犯灯の現所管は市民生活部であります。これまで以上に連携を図り、明るいまちづくりをお願いしたいところでもあります。
また、道路街灯はあっても、やはり暗い場所があるわけでございます。市民の生命、財産を守るために明るいまちづくりは必要であると考えます。これまでは担当課が3部にまたがっていましたが、これからは2部になるわけでございます。縦割り行政の弊害が出て、市民が犯罪に巻き込まれないためにも明るい町にする必要があります。これまで以上の連携を図っていただきたいので、現状の防犯灯、商店街灯、道路街灯とのすみ分けについて、どのようになっているのか。また、今後どのような整備を行っていくのかお答えをください。
以上、1回目の質問とさせていただきまして、ご答弁によりまして再質問をさせていただきます。
それぞれご答弁ありがとうございました。防犯灯については、充実をして明るいまちづくり、よろしくお願いしたいと思います。また、委託事業となるよう強く要望したいと思います。
監査制度についてであります。今も適正な監査を行っているのはわかるんですよ。不正な支出があるわけないですから、それをきちんと不正じゃないよと言っているなら、それでいいんです。ですが、監査結果も、市川市を見ると5ページ程度なんですよ。松戸、習志野など、近隣でも40ページぐらい以上にわたって指摘事項とされているんですよね。結果まで公表されている。ですから、やっていらっしゃるんでしょうけれども、それを我々にもわかるように公表していただきたいと思います。
それから、行政監査の前向きな発言がありました。ぜひ行政監査、やっていただきたいと思います。
それから、包括外部監査ですけれども、ABC分析、また事務事業評価、行政評価、そういったものをしっかりと公表していっていただきたいなと思うわけですね。6年間成果を出していないのが現状で、ホームページを見ましたけれども、結果も出てないんですよね。これではわからないじゃないですか。僕、外部監査が絶対必要かといったら、そうでないと思うんですよ。内部は内部でしっかりやって、やはり内部だけでは見切れないところもあるだろうから、包括外部監査を入れたほうがいいんじゃないか。そしたら、個別外部監査という話だったんですけれども、個別外部監査と包括外部監査では意味合いが違いますよね。包括外部監査は、専門的な方が毎年入ってやるわけですから、しっかりとそういった方向でやっていただければありがたいのかなと。というのは、市長の施政方針の中でも出ていたと思いますが、地方政府という言葉が出ているんですよね。そういった中で包括外部監査制度を導入しない、政令市じゃないから入れないんだと言っておきながら政令市を目指している部分もあるわけですから、しっかりそういったところをやっていただきたいなと思うわけです。これも要望しておきます。
それから、外郭団体のところですけれども、文化振興財団、今回2回目の選定を迎えるわけですが、これは原則は公募ですよね。1団体とするなら、言葉ではなく、指標として、その理由を明確にしてもらいたいんですよ。それが今まで一向に出てこない。だから、何していたんですかという質問になるんですよ。あれをやった、これをやったということを伺っているんじゃなくて、そういったものをしっかり出していただきたい。1団体選定ではなく、しっかりと例外なく公募して――だって、民間事業者と競ったって大丈夫なんですよね。大丈夫だったら、1団体選定にすることないじゃないですか。原則公募だとやっているんですから。ぜひ原則公募で民間事業者と競ってくださいよ。今の文化振興財団だったら十分勝てるわけですよね。頑張ってやっていただきたいと思います。
それから、ストックヤードについてですけれども、民設民営、やはりデメリットが多いと思います。公設民営でやっていくべきです。そういったところも、こういう議会から出たものを監査の中で指摘をしていただいたり、取り上げていただきたいと思います。
それから、あわせ産廃のところですけれども、他市は松戸、船橋等、きちんと処理すると、千葉県条例にのっとってやっているんですよ。市川市は条例において産業廃棄物を処理することを規定していない、すなわち産業廃棄物を処理しない、例、市川市、鎌ヶ谷市、印西市、茂原市となっているんですよ。ということは、市川市は県条例の違反をしているんじゃないですか。ということを申し上げまして、一般質問を終わらせていただきます。
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- あなたのアバター自慢して!♪
- バーチャル渋谷おでかけハロウィン
- (2022-11-01 19:50:06)
-
-
-

- ニュース関連 (Journal)
- 「プラチナバンド」 携帯電話の電波…
- (2024-06-28 08:21:00)
-
-
-

- まち楽ブログ
- 都市鉱山から抽出、キラキラ万博リサ…
- (2024-06-28 12:00:26)
-
© Rakuten Group, Inc.