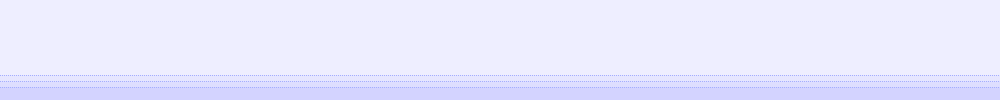またミカンかぁ
街のどこからでも見える時計台。いつでもその張りは性格に時間を示し続けていて、その街の大きなシンボルだった。その地で生まれた者は幼い頃から自分を見ていてくれた彼を愛していたし、初めてこの地を訪れた者も彼が纏う不思議な雰囲気に魅入られた。
彼は建物ながらも、血の通った人間のようだった。親友のような、父親のような、あるいは母親、祖父母。そんな人間らしい暖かさを持った時計台だった。時計台は街の人から愛されていた。
正午を告げる重々しい鐘が鳴った。体の芯に響くような心地よい低音が町中に伝わる。それを合図に、街が少しだけ騒がしく様子を変えた。朝食の用意があちこちで始まり、仕事場には急速時間になったので張り詰めていた空気が消え和やか雰囲気が訪れた。
時計台の鐘は街の雰囲気を管理していた。
「よし。来たぞ」
さっきまで授業を無視し眠り込んでいた男の子が、この鐘の音を耳にして小さく呟いた。するとその呟きに答えるように、教室内が騒がしくなる。
短い黒髪の男の子は、全身をかすかに震わす気持ちの良い鐘の音に、僅かに机から顔をあげた。彼の待ち望んでいた至福の時がきたのだ。その合図が今、鳴り響いている。
女性教師が黒板の前で、教室全体に伝わるように大声で話している。小5の鐘にクラスが騒がしくなったので、少しだけ声の音量があがっていた。肩で切りそろえられている茶色の髪が、楽しげに揺れている。
「では今の問題と、次のページの問題群を宿題とします。期限は明日の数学の時間まで。では、ここまでッ」
教師が教科書を閉じて、午前の授業は終了となった。
そしてその瞬間。机に頭をつけていた男の子は、がはっと立ち上がる。そして机の横にかけられていたカバンを取って、
「昼だなッ! じゃあ先生、行って来ます!」
「ナオ君、お昼の時間には憎らしいほど正確ね。朝も遅刻しないように、それと勉強も頑張ってくれると嬉しいんだけど」
「レーリン先生、それは無理なお願いだよ。じゃ、いってきまーす」
この学校で一番若い女性教師であるレーリンが彼の言葉に何か言おうとしたが、もう彼の姿はそこになく、間に合わなかった。もう、と呆れたように呟いて、そっと窓から街の中央に建っている時計台を見つめた。
「ま……元気な事は良い事……ってことかな」
彼女はそう呟いて、優しく微笑んだ。そしてお弁当の包みをカバンから取り出して、近くの生徒達の輪に入っていった。
髪を二つ縛りにしている女の子の席の隣に座って、その子のお弁当を除いて、
「あ、そのハンバーグ美味しそう」
なんてまるで彼女自身生徒みたいな感じで、無邪気な楽しそうな声を上げた。教師なのは授業中だけのようだった。
「レーリン先生食べる? このハンバーグ。ただし、テスト十点追加と引き換え」
「シクラちゃん。そういう事言ってると……」
「ごめんなさいッ! 冗談だよ。はははははは」
◇
ナオには日課があった。毎日毎日、彼は昼時になるとその日課のために時計台まで走る。
下駄箱で靴を履き替えて、かばんを背負って走り出す。校庭を横切り、小道を抜けて大通りに出る。昼時なので人通りが多いが、ナオはお構いなしに人との間をするすると縫うように走り抜けていく。大通りは真っ直ぐ時計台へと伸びていた。賑やかな街を抜けて、時計台の足元へと急ぐ。
ナオの日課は時計台の最上部でお弁当を食べることだった。高い高い時計台の上から、時には遥か先に見える空や山を。時には眼下に広がる自分の街を見下ろしながら、その絶景にため息をつきつつ弁当を平らげる。彼の最高の楽しみだった。
猿と馬鹿は高いところが好きだ、なんて友人にからかわれたりするが、そんなときは鉄拳制裁。それにナオはこの楽しみが変だと全然思っていなかった。こんな綺麗な景色を見ながら食べるお弁当がすごくおいしいことを知っていたから。
大通りの人ごみを抜けて時計台の足元にたどり着く。見上げていると首が痛くなるような、そんな時計台。
「上からこいつに見下ろされてるだけなんて、ぜんぜん楽しくないのになぁ」
皆はなぜ、この時計台を眺めるだけで、上ろうとしないのか。この上からはなんでも見渡せるのに、なぜ人は時計台を見上げているだけで満足しているのか。
ナオは疑問に思いつつも、決して友達を自分から誘おうとはしなかった。静かなほうが落ち着くし、あの綺麗な景色を自分のものだけにしておくというのも、それはそれでなんとなく気持ちが良かったから。
「よーし、今日も行くかぁ」
彼は時計台の足元で、準備運動を始めた。全身の筋を伸ばし、ストレッチ。終わりに手足をぷるぷると振り、準備完了。
背丈の長い時計台を上るのはそれはそれは体力の使う。階段で上を目指さなければならないので、普通の人間ならすぐへとへとになってしまう代物だ。
「よし、今日も上るか」
彼は一言小さく呟き、気合を入れる。そして時計台の大きな正面扉をくぐった。
「おー。ナオちゃん。今日もかいー?」
腰の曲がった、白髪の多いおじいちゃんが管理人室からナオの姿を見て手を上げた。
「よう、おじいちゃん。時計台の上を借りるぜ」
同じように片手を上げて挨拶を返し、管理人室に入る。壁に掛けられている鍵束をひょいっと取って、老人にもう一度片手を上げる。
「はいはいよー。頑張ってなぁ」
気の抜けた返事を返し、老人は管理人室でのんきに紅茶をすすっていた。ひらひらと皺の多い手を振っている。時計台の管理人である老人は、もうナオの日課には慣れっこだった。
時計台の中は大きな吹き抜けで、その天井は随分上のほうにあった。その片隅に階段がひっそりとある。急めな階段は二十段ほどで折れ曲がり、また二十段ほど上がって、そこでまた逆方向へと折れる。階段の周りには落下防止の鉄格子がついていた。
鍵で入り口の扉をあけて、かばんを背負い直しナオは一歩踏み出した。
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- 戦闘機の写真を撮るのが好き!
- ブルーインパルス
- (2024-12-04 06:30:10)
-
-
-

- アニメ・コミック・ゲームにまつわる…
- ロマサガ2R プレイその9 皇帝退位・…
- (2024-12-04 20:00:13)
-
-
-

- フォトライフ
- 源氏物語〔12帖 須磨 14 完〕
- (2024-12-04 10:20:10)
-
© Rakuten Group, Inc.